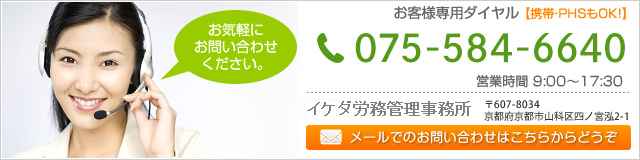労務ニュース スマイル新聞
2019年11月23日 土曜日
令和元年11月23日第494号
2019年10月から消費税率引き上げ分を活用し、年金生活者支援給付金の制度が始まりました。この給付金は、公的年金を含めても所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
1.老齢基礎年金を受給されている場合
支給要件...次の要件をすべて満たしている方が対象です。
1)65歳以上の受給者であること
2)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計金額が879,300円(毎年度の老齢基礎年金の額を勘案して改定)以下であること
給 付 額...月額5,000円を保険料納付済み期間等に応じて算出され、次の1)及び2)の合計額になります。
1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,000円×保険料納付済期間/480月
2)保険料免除期間に基づく額(月額)=10,834円×保険料免除期間/480月
<給付額の例>
被保険者月数480月のうち納付済月数が480月、全額免除月数が0月の場合
1)5,000円×480/480月=5,000円
2)10,834円×0/480月=0円
合計 1)5,000円+2)0円=5,000円(月額)
2.障害基礎年金を受給されている場合
支給要件...障害基礎年金の受給者であり、前年の所得が462.1万円+扶養人数の数×38万円以下の方が対象です。
給 付 額...障害等級が2級の方:5,000円(月額)
障害等級が1級の方:6,250円(月額)
3.遺族年金を受給されている場合
支給要件...遺族基礎年金の受給者であり、前年の所得が462.1万円+扶養人数の数×38万円以下の方が対象です。
給 付 額...5,000円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われることとなります。
給付金の受給には、認定請求を行う必要があります。添付書類は不要、代理人による代筆も可能なので、お気軽にお申し込みください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年11月 8日 金曜日
令和元年11月8日第493号
1.助成金とは
助成金は、融資とは異なり返済不要なお金です。主に、企業が納付する雇用保険料をその財源とし、従業員を新たに雇用したり、能力開発(人材育成)、職場環境を改善する(処遇改善)等を行ったりした場合に、そのご褒美として助成してくれるというものです。
2.助成金を受けるメリット
厚生労働省が取り扱う助成金は使い道が自由です。それに対し、主に経済産業省が所管する補助金は税金を原資にしているために使い道は厳しく限定されます。例えば補助事業実施の際に対象経費から外れた支出をすると補助金は1円も支給されません。
また、助成金の支給申請を行うにあたっては、就業規則の作成・変更・届出、労務管理面でのコンプライアンス遵守が求められます。したがって、助成金を受給したいと考えれば必然的に、就業規則や労務管理をしっかり整備することになります。そして、助成金を受給できれば、「国(厚生労働省)が求めるクリーンな基準を満たす企業である」と認められていることと同義となり、企業の社会的信用が得られます。
人材を確保し長く働ける環境を整備することは、企業を成長させるうえで大変重要なことだと思います。
3.助成金を受けるデメリット
助成金を受給するためには、新たな雇用や賃金アップ、人事制度の導入等が必要になります。助成金受給のために無理をして制度を一度導入すると廃止することは困難が伴い、従業員にとって不利益変更となります。「助成金ありき」で「もらえるものは、もらっておこう」的な考え方は失敗のもとです。
また、助成金は原則後払いです。申請から、お金が入金されるまで時間がかかります。
支給要件を満たしており、なおかつ実際に要求される状態を一定期間継続した後で、はじめて支給されます。申請から入金までは6ヵ月から1年超ほど時間がかかる場合もあるので、その間に発生する必要経費は自前で用意する必要があります。
4.それでも助成金は全額が純利益である。
たとえば百万円の助成金を受給したとすると、本業でそれだけの利益を出すため
に売上をどのくらい上げればよいでしょうか。営業利益率を仮に2%で見積もれば五千万円の売上が必要です。これだけ経営的にインパクトのある助成金を活用しない手はありません。上記メリット・デメリットを良く考えて、メリットの方が大きいとなれば、受給申請を考えてみてはいかがでしょうか。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年10月23日 水曜日
令和元年10月23日第492号
「働き方改革」の一環として、労働基準法が改正され今年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日について、確実に取得させることが義務付けられました。
条件の該当する全ての従業員に対し、年5日の年次有給休暇の確実な取得のため、再度ポイントを確認していきましょう。
1.対象者
年次有給休暇が10日以上付与される全ての労働者が対象です。
法定の年次有給休暇付与日数が年10日以上の労働者に限ります。
対象労働者には、管理監督者や有期雇用労働者、パートタイマー等も含まれます。
2.年5日の時季指定義務
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時期を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
1)時季指定の方法
使用者は、時季指定にあたっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を希望するよう努めなければなりません。
2)時季指定を要しない場合
既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。
3.年次有給休暇管理簿の作成と保存
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
4.就業規則への規定
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
5.罰則
上記2及び4に違反した場合には労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられることがあります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年10月 8日 火曜日
令和元年10月8日第491号
1.パワーハラスメント(パワハラ)とは
厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」の提言によると、パワハラとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」指します。具体的な行為類型は、(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)、(2)精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)、(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)、(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制する等)、(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる・仕事を与えない等)、(6)プライバシーの侵害(私的なことに過度に立ち入る)、の6種類とされています。
2.パワハラ事案における加害行為の違法性の評価
職場におけるパワハラは業務上の指導との線引きが難しく、違法性については、当該言動が正当な教育指導等と評価できるかという観点から検討することになります。
正当な教育指導等と評価できるかは、(1)指導を行う必要性、(2)言動内容(人格非難や侮辱的な内容を含む)、(3)回数(執拗さ)、(4)態様(多数人の面前で行う、閉鎖環境で行う、指導後のフォローの有無等)、(5)日常的な関係性(信頼関係構築の有無)、等に基づき判断されます。注意や叱責の度合いが社会通念に照らして許容されるものであるか、という観点から判断されます。
3.パワハラに対する法的責任
(1)民事上の不法行為責任(民法第715条第1項)...民法上、従業員が「職務の執行につき」第三者に損害を与えた場合、使用者である企業も使用者責任として、加害者の従業員とともに損害賠償責任を負います。
(2)債務不履行責任...企業は労働者に対し、労使間の雇用契約に基づく付随義務として、労働者の労働環境を調整し、快適な環境を提供する義務があります。したがって、パワハラを認知したにもかかわらず放置したような場合は、この義務を怠ったものとして債務不履行責任を負うことがあります。
(3)労災補償責任...企業がパワハラを放置ないし黙認したことで労働者が精神疾患等のメンタル不全を招来した場合、仮に企業に過失がなくとも、労災補償責任を負うことになります(無過失責任)。
企業と職場環境を守るため、パワハラを防止し、万が一起こってしまった場合も適切な事後対応をしましょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年9月23日 月曜日
令和元年9月23日第490号
1.両立支援助成金は環境整備コースと制度活用コースの2種類
治療と仕事の両立支援助成金は、事業者の方が労働者の疾病の特性に応じた治療と仕事の両立支援制度を導入、または適用した場合に事業者が費用の助成を受給できます。
環境整備コースは、事業者が両立支援環境整備計画を作成し、計画に基づき制度の導入を行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した場合に費用を助成します。助成金額は1企業当たり将来にわたり1回を限度とし一律20万円です。
制度活用コースは、事業者が両立支援制度活用計画を作成し、計画に基づき両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定し、実際に適用した場合に費用を助成します。助成金額は環境整備コースと同様に一律20万円です。ただし、対象労働者が有期契約の場合、対象労働者の雇用期間に定めのない場合、将来にわたりそれぞれ1回ずつ助成されます。
2.両立支援はなぜ必要?
社員が病気になってしまった時、無理なく働き続けてもらうためにはどうしたらよいでしょうか?大切な人材に辞められるととても困りますね。
働く世代で病気の人は大変多く、病気を理由に1ヵ月以上休業している労働者がいる企業の割合はメンタルヘルスが38パーセント、がんが21パーセント、脳血管疾患が12パーセントです。仕事を持ちながら、がんの治療で通院している人は、32.5万人もいるのです。
そして、診断技術や治療方法の進歩から、かつては「不治の病」であった病気も生存率が向上し、「長く付き合う病気」に変化しつつあります。
病気になっても働き続けたいとする人は92.5パーセント。生計を維持するためや治療費のためはもちろんですが、自分の仕事に期待してくれる人々がいることは、病気と闘う励みになり、生きがいにもなります。
3.両立支援は事業者・働く人ともにメリット
両立ができると、貴重な人材資源の喪失が防げ、継続的な人材の確保や定着につながります。また、労働者のモチベーションアップから労働生産性が維持・向上され、健康な経営が実現されることでしょう。働く人は治療に関する配慮が受けられ、病気の悪化を防ぎ治療を受けながら仕事が続けられます。何よりも継続して収入が得られ、生活への安心感が生まれます。ひいては仕事による社会貢献や自己実現につながるでしょう。
助成金をうまく活用して、安心できる職場づくりを行いましょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年9月 8日 日曜日
令和元年9月8日第489号
1.高額な損害賠償
自動車やオートバイ等の車両を事業に使用しておられる事業所は多いことでしょう。全ての車両は自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が義務付けられており、交通事故等のいざという時に備えていなければなりません。
ところが「自転車」には、保険への加入義務は現在ありません。ただし2015年に兵庫県の条例で自転車保険の加入が義務付けられて以降は、全国の自治体で自転車保険の加入を義務付ける動きがあります。
2008年、11歳の小学生が自転車で走行中に62歳の女性に衝突、頭を強く打った女性はその後意識が戻らず、2013年には神戸地裁が少年の母親へ9,521万円の損害賠償金の支払を命じています。しかし少年の母親は自己破産を申請し、被害者側は慰謝料等の支払を受けることができませんでした。他にも、高校生が自転車で走行中に同じく自転車で走行していた24歳の男性と衝突、男性に言語機能喪失の障害が残り、9,266万円の損害賠償の判決認容額が出ています。
2.加害者になったら
一般的に自転車保険の補償範囲は、個人賠償責任保険と傷害保険をセットにしたものがほとんどです。個人賠償責任保険は、被保険者が日常生活において偶然な事故で他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、法律上の損害賠償責任を負うことによって被った被害を補償します。支払限度額は保険商品によって異なりますが、1億円や無制限など、上記のような高額の損害賠償に対応できるものも存在します。
3.被害者になったら
自転車同士の事故の被害者となれば、当然に被害者は加害者に損害賠償を請求するわけですが、加害者が適切な保険に加入していない場合、十分な補償を得ることが難しかったり、自分自身の過失分の金銭を受け取ることができなかったりします。
そういった場合は被保険者自身の偶発的外力による死亡や治療を主に補償する障害保険等での対応も考えられます。また自動車保険の人身傷害保険は原則として契約自動車に搭乗中の死傷や後遺障害を補償するものですが、自転車事故が補償範囲に入るオプションもあります。事前に確認しておきましょう。
誰しもが交通事故の加害者にも被害者にもなる可能性があります。従業員や経営者のもしもの時に備えることは、非常に重要です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年8月23日 金曜日
令和元年8月23日第488号
1.日本の労働力の状況
「人手不足」と言われる昨今ですが、「平成30年版厚生労働白書」によると、平成29年、男性の労働力人口(15歳以上の人口のうち、就業者+完全失業者を指す)は3,775万人と前年から2万人増加しています。同様に女性においても、労働力人口は45万人増加し2,936万人となっています。就業者は、男性は3,717万人、女性は2,946万人で、男性が45万人増加、女性は87万人増加となっています。労働への参加は、女性を中心に着実に進んでいるといえます。
非労働力人口のうち、就業希望者(369万人)に多い非就職理由を見ると、男性は「適当な仕事が有りそうにないため」、女性は「出産・育児のため」でした。
正規雇用労働者数も平成27年以降は増加に転じており、平成29年の増加数は、男性が23万人、女性が34万人と大幅です。一方、非正規雇用労働者は男女ともに65歳以上が大きく増加しています。これは定年退職後は継続雇用等により非常勤等の非正規雇用で働き続ける高齢者が増加していることが一因であると思われます。
2.若年層を中心とした完全失業率の低下
平成30年の完全失業者は166万人です。前年度に比べ24万人減少し、9年連続の減少となりました。また完全失業率についても、全体で前年度より0.4ポイント低下し2.4%となりました。こちらも8年連続の低下です。
3.失業率の国際比較について
失業率を国際的に比較してみます。統計では、平成29年度の失業率OECD平均は5.8%ですが、我が国は2.8%と最も低い水準です。リーマンショック等の影響で、各国で失業率は上昇しました。近年は改善傾向にありますが、イタリアとフランスは相対的に改善が遅れています。OECDにおける平均失業率を年代別に見ると、15~24歳は11.9%、25~54歳は5.3%と、若年層の失業率が特に高い状態です。15~24歳の失業率はイタリアで34.8%、フランスでは22.3%ですが、我が国では4.7%と、OECDの中で最も低い水準にあります。
4.数字では読み解けない労働者の現況
日本は正規雇用労働者が年々増加しており、失業率は諸外国と比較して低い水準にあります。しかし労働環境は数字だけで推し量れるものではなく、改善が必要とされる企業や体制も少なくありません。今後も、従業員がより活き活きと働き、長く定着できる環境づくりが求められます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年8月 8日 木曜日
令和元年8月8日第487号
約40年ぶりに相続法が改正されたことに伴い、令和元年7月1日から特別寄与制度が創設されました。相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護を行っていた場合、相続人に対して金銭の請求をすることができるというものです。
1 創設の経緯
相続人でない者は、どんなに被相続人の療養看護に努めたとしても相続人ではないため、被相続人の死亡に際し相続財産の分配にあずかれません。一方、相続人である限りは、被相続人の療養看護を全く行っていなかったとしても相続財産を取得することができます。
以前から問題視されていたこのような不公平を解消するために創設されました。
2 制度のポイント
(1)特別寄与の対象
特別寄与者は、上記の通り相続人ではない親族です。なお民法において親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族を指します。事実婚の場合は、配偶者とはみなされません。
なお特別の寄与とは、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことによって被相続人の財産を維持又は増加させたことをいいます。
(2)特別寄与料の上限額
相続開始時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額が、特別寄与料の上限です。例えば「全財産を特別寄与者以外に譲る」という遺言があれば、特別寄与料の請求権はあったとしても、請求することができません。
(3)請求をすることができる期間
特別寄与料の支払いについて、当事者間で協議が調わないときや、協議ができないときは、相続の開始を知ったときから6ヵ月又は相続開始のときから1年以内に家庭裁判所に請求することができます。
(4)税制における特別寄与の取扱い
相続税の課税対象です。相続人ではない親族が財産を取得するため、「相続税額の加算(いわゆる2割加算)」の対象となります。
遺産を受け取ることのできる人の範囲が広がることは大変喜ばしいことです。しかし、この制度が新たに争いの火種を生むことも想像に難くなく、今後より具体的な整備が必要となる制度ともいえます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年7月23日 火曜日
令和元年7月23日第486号
令和元年5月29日、職場におけるパワハラ防止措置を企業に義務付ける「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。
法制化により、企業が行うべきパワハラ問題への取組みにはどのような影響が出るのでしょうか。
パワハラは従前から社会問題として周知されており、法制化によって新たな概念が生まれるわけではありません。しかし事業主にとっては、これまで講じてきたパワハラ防止措置の見直しと改善を行う必要があります。
現状、厚労省においてパワハラの定義や6類型は示されているものの、パワハラ防止措置に関する労働施策総合推進法においては、具体的に何がパワハラに該当し、事業主がどのような措置を講じるべきかは明確にされていません。
そして今後も、パワハラと業務上の指導の境界線は様々な要因により異なるため、明確な線引きは困難であることが予想されます。
したがって企業には、パワハラか否かをはっきりと線引きすることよりも、「これはパワハラに当たらないだろうか」と「考える癖をつける」ことが求められます。
企業内におけるハラスメント認識を共通化していくことで、パワハラを企業全体で考える問題とし、企業側と従業員の双方が納得のいく認識を持つことが理想です。
法制化に伴い、企業がこれまで以上に注意すべきなのが「パワハラ相談対応」です。セクハラ事案とは異なり、被害者側にも業務上のミスや落ち度、勤務態度の不良等の問題があるケースも想定され、事実確認にはより慎重な対応を要するためです。
また相談後に配置転換等を行う場合は、相談者側が「相談をしたことによる不当な扱いだ」と誤解しないよう意見聴取や転換理由の説明等の丁寧な対応が求められますし、さらに加害者から相談者への報復行為にも注意しなければなりません。
今後はパワハラ相談に対する対応の在り方がより一層重要になります。パワハラ相談があった際の調査や事実確認の方法を明確にルール化しておくことが必要と言えます。
また、そもそも相談に対応するだけではなく、パワハラを未然に防ぐための「パワハラ教育」も非常に大切です。単に実施するだけでは意味がないという意見もありますが、繰り返し実施し、回数を重ねることで、従業員にパワハラ問題に向き合ってもらう機会を作り続けていくことが重要ではないでしょうか。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年7月 8日 月曜日
令和元年7月8日第485号
1.働き方改革関連法の適用開始
この4月から、昨年成立した働き方改革関連法の適用が始まりました。
企業に義務付けられる内容をまとめると、「年次有給休暇5日間の消化」・「労働時間(残業)の削減」・「同一労働同一賃金」などがあります。中小企業はこれらにどう対応していけばよいでしょうか。
現状、ほとんどの中小企業は人手不足です。業績が上がっている会社であればなおのこと人手は足りず、働き方改革にまで手を付ける余裕はあまりないと思われます。
とはいえ、法制化された以上は上記内容を進めなければなりません。
2.残業削減や年休消化だけが目的になっていませんか?
仕事量が今までと変わらないまま、頭ごなしに「残業ダメ」「年次有給休暇をとりなさい」と言っても、社員はタイムカードを切った後に自宅に仕事を持ち帰ってしまうだけです。しかし大多数の企業は「働き方改革」の本来の目的を見失い、その手段であるはずの残業削減や年休取得のみに取り組んでいます。
3.「働き方改革」の本来の目的とは?
「働き方改革」の本来の目的は、人手不足の解消と労働時間の是正を「生産性向上」によって実現することです。働く人の視点に立ち、働きやすい職場・働き甲斐のある職場にするために、まずは社員の生活・健康・やりがいを考えた制度や仕組みをつくることが大切です。最終的には、従業員に「この会社で働けて幸せ」と幸福感を感じてもらうことこそが、「働き方改革」の本来の目的なのです。
4.企業が最初にすべきことは何か?
第一に「社員が離職しないようにすること」です。社員の入れ替わりが激しいと、スキルが向上せず生産性も下がります。逆に辞めずに働き続ける社員は経験値もスキルも上がり、生産性を上げてくれます。そこから業務改善が進み、年休も取得しやすい環境が整い始めます。いきなり「年休を取れ」と言っても、不可能です。
では社員が辞めない職場づくりには、何が必要でしょうか。例えば、社内の課題解決を社員自らが行うことで、職場の環境・雰囲気が向上し、離職率が低下することがあるそうです。結果、生産性が向上し、残業削減や年休消化にもつながります。
形式だけの「働き方改革」を取り入れる前に、まずは自社をよりよくするためには何が必要なのかを考えてみてはいかがでしょうか。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年6月23日 日曜日
令和元年6月23日第484号
社会保険等のe-Gov電子申請がリリースされて、早くも10年以上が経ちます。当初はなかなか普及しませんでしたが、システムが改善されメニューも増えた現在は、以前に比べ随分と使われるようになりました。来年度には、一部で電子申請における義務化も開始されるようです。電子申請が作業効率を向上させることは間違いなく、今後は急激に需要も高まっていくものと思われます。京都府社会保険労務士会に所属する社労士の中でも、すでに半数以上が電子申請を使っています。また、ソフト会社から電子申請に連動した各種商品が販売されるようになり、企業における使い勝手が一段と向上することも、更なる普及率の向上の一因となっているようです。
来年度からの義務化はまだ明確に確定されたものではないようですが、資本金あるいは出資金が1億円以上の企業を対象に、一部の申請手続きからスタートをするようです。この流れはおそらく数年内にほとんどの企業へと浸透するものと思われます。今後、国あるいは自治体への申請手続き等については、社会保険関係に限らず、すべてがネット化へ移管されていくのでしょう。
しかし多くの企業が強い関心を持って電子申請に取り組んでおられる一方、相変わらず電子申請の案内をしても頑なに抵抗をされる企業もあります。その要因は、おおよそ以下の数点に集約できるようです。
・「申請書を作る際、ハローワークや年金事務所へ出向いて、職員に聞きながら作成しているから」
・「うちはハローワークが近いので、電子申請なんて必要ない」
・「全国展開している企業だから、本部の方針があり勝手に当事業所だけで電子申請を行うことはできない」
・「国が推進する電子申請で、費用(電子認証)が発生するのは納得できない」
・「電子認証取得許可を得る社内稟議を作るのが面倒だ!」
「稟議書作成が面倒だ」という理由は別として、確かに各企業それぞれにそれなりの事情があるのでしょう。ただ、現行のやり方を最善として事務作業の改善を試みないのは、大変勿体無い損失であるように思います。従業員の採用が難しくなってきた昨今、こうした簡単な方策でその状況が一部でも改善できるのであれば、企業としては、積極的に取り組むべきだと考えます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年6月 8日 土曜日
令和元年6月8日第483号
女性活躍推進法の施行日(平成28年4月1日)から3年が経つにもかかわらず、後を絶たないセクシャルハラスメントに関わる企業の法的責任についてお伝えします。
1.セクシャルハラスメント(セクハラ)とは
男女雇用機会均等法では、職場におけるセクハラの定義を「(1)職場において行われる(2)性的な言動に対する雇用労働者の対応により(3)労働者がその労働条件につき、不利益を受け、または当該性的な言動により(4)当該労働者の就業環境が害されること」と規定しています。
2. セクハラに当たるかどうかの判断基準
「意に反するものであったか」「就業環境を悪化させるものであったか」が重要な判断基準となります。本人が明示的に反対せず、応じているように思えても、その言動が相手の望まない言動であった場合、セクハラとなることに注意が必要です。また、その判断基準は、客観的に判断しなければなりませんので、「平均的な(男性・女性)労働者が通常どのように感じるか」で判断されることになります。
3. セクハラに対する企業の法的責任
(1)民事上の不法行為責任(民法第715条第1項)
民法上、従業員が「職務の執行につき」第三者に損害を与えた場合に、使用者である企業も使用者責任として、加害者である従業員とともに損害賠償責任を負うことがあります。
(2)債務不履行責任(民法第415条)
企業は、労働者の労働環境を調整し、快適な環境を提供する義務があります。セクハラを認知したにもかかわらず放置したような場合には、この義務を怠ったものとして債務不履行責任を負うことがあります。
(3)男女雇用機会均等法上の責任
何ら対策を講じず、是正指導にも応じない場合には、企業名が公表されます。厚生労働大臣が、事業主に対して報告を求めたにもかかわらず、報告を行わない場合や、虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料に処せられるとされています。
(4)労災補償責任
企業がセクハラを放置ないし黙認したことにより、労働者が精神疾患等のメンタル不全を招来した場合には、仮に企業に過失がなくとも、労災補償責任を負うことになります(無過失責任)。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年5月23日 木曜日
令和元年5月23日第482号
1.新たな在留資格「特定技能」
平成30年12月14日に、在留資格「特定技能」の創設等を目的とした「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が公布され、平成31年4月1日から、特定技能外国人の受入れが開始されることになりました。
これまで就労が認められてきた在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」などの専門的・技術的分野と「技能実習」という非専門的・非技術的分野でした。ただ、専門的・技術的分野では学歴や実務経験が求められており、人材が限られていました。非専門的・非技術的分野の技能実習は本来の目的が日本の技術を移転して発展途上国の経済発展を助けることにあり、労働力の需給を調整するものではありませんでした。
そこで、日本国内で人材不足が顕著な業種を対象に、一定の技能をもった人材を対象としたのが新たに創設された「特定技能」という在留資格です。
2.対象業種
「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、前者は特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいい、介護業や外食業など、人材が顕著に不足している特定産業分野に指定されている14業種が対象となっています。後者は建設業と造船・舶用工業の2業種が対象となっています。今後は特定技能1号の在留資格が増えるものと見込まれます。
特定技能の在留資格を取得するには、特定技能評価試験に合格するか、技能実習2号を修了することが必要となります。特定技能評価試験は、「技能水準」と「日本語能力水準」の試験に合格する必要があります。試験は業種ごとに順次行われる予定です。
3.導入手続
特定技能外国人を受け入れるために雇用する事業者は、支援計画を作成し、申請の際に出入国在留管理庁に提出することになります。これらを自社で行えない場合、一定の基準を満たした登録支援機関に支援を委託することができます。
また特定技能外国人を自ら探せない場合には、職業紹介事業の許可を取得した事業者から紹介を受けることが必要となります。今後は登録支援機関が職業紹介の許可を取得し、または、職業紹介事業者が登録支援機関の申請登録を行い、ワンストップで特定技能外国人のサポートを行うことが考えられ、利便性が向上する可能性があります。
人材不足に悩む事業者には朗報ですが、そこにつけこんだ悪質なブローカーなどが仲介する可能性もあるので、導入する際には注意が必要です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年5月 8日 水曜日
令和元年5月8日第481号
1.高齢者の定義が変わる?
いよいよ、令和の時代が始まりました。昨年、「ライフシフト100年時代の人生戦略」という本がベストセラーになりました。また、日本老年学会・日本老年医学会では、65~74歳を準高齢期、75~89歳を高齢期、90歳以上を超高齢期と定義の見直しを提言している時代です。もちろん、人の価値観は百人百通り、おかれた環境も百人百様。他人は他人、自分は自分かもしれません。しかし、こんな統計があります。「何歳まで収入を伴う仕事をしたいですか?」(平成30年度内閣府調査)に、実に42%の人が「働けるうちはいつまでも」が最も多い回答になっています。前書「ライフシフト」でも、今までは「教育・就職・老後」の3ステージモデルだったが、今後は4ステージ以上になるだろうと想定されています。
2.60歳以上の雇用環境
ご承知の通り、少子高齢化を背景に、昭和22年制定の労働基準法を中心に大きく法律が改正され、平成31年4月から次々と「働き方改革法」が施行されています。なぜ働き方を変えるのでしょうか。前掲内閣府調査で60歳以上の就業状態は、男性60~64歳で約79%、65~69歳で約54%、女性で同約53%、同約34%という数字が出ています。また、改正高年齢者雇用安定法の施行もあり、定年を「65歳以上」とする企業は約18%と、この10年で3倍に増えています。
3.高齢者雇用の課題
ある企業は「定年制なし」として、従業員の方も80歳代で生き生きと働いておられるケースもありますが、現実には勤務体制や賃金設計をどうするのかは企業にとって大きな問題です。改正高年齢者雇用安定法後、企業では、従業員の定年後は責任と権限を限定するというケースが主流であり、雇用管理は調いながら、報酬や評価システムは追い付いていない状態ではないでしょうか。
今後、高齢従業員の戦略化、知識・スキル・ノウハウの伝承等を期待するなら、バリアフリー化、AIの活用、時差出勤、短時間勤務、テレワーク、また、賃金カーブの見直し、リカレント教育の実施、ノウハウや経験の伝承につながる職務開発等細かな配慮と取り組みが必要になります。また、従業員も年金の繰り下げ受給の検討、雇用保険の給付など、利用できる制度を活用してスキルアップや資格取得に取り組み、自身が戦力として期待されるような努力も必要になるでしょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年4月23日 火曜日
平成31年4月23日第480号
1.平成31年4月1日 以降の一括有期事業について
事業主負担を軽減するための取組として労働保険の事務手続きが簡素化されます。
(1)一括有期事業開始届の廃止について
建設事業で一括有期事業を行う事業主は、それぞれの事業を開始したとき、翌月10日までに一括有期事業開始を提出する必要が有りましたが、平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については提出する必要が無くなります。
(2)一括有期事業の地域要件の廃止について
一括される有期事業については、地域要件が定められており、定められた地域の範囲外で行われる事業は一括されず、個別に有期事業として成立させる必要がありましたが、平成31年4月1日以降に開始する有期事業については、この地域要件が廃止され、遠隔地で行われる事業も一括することができるようになりました。
ただし、事務処理上の手続きとしては次の点に留意する必要が有ります。
ア.平成31年3月31日以前に、労災保険関係が成立している有期事業の一括の要件については、同年4月1日以降も引き続き地域要件が適用されます。
イ.一括有期事業に係る地域要件の廃止については、本社及び支店ごとに成立している一括有期事業を本社に一括することではなく、地域要件により、一括されなかった有期事業が、労働保険料の納付事務を行う事務所で一括されることで、労働保険料の納付事務を行っていた事業所を変更することではありません。
有期事業が一括されるには、概算保険料が160万未満、請負金額が1億8千万未満の建築事業であることが必要でこれらの要件に変更は有りません。
2.労働者死傷病報告書の様式改正について
労働者が4日以上労災事故で休業する場合に労働基準監督署へ提出する、労働者死傷病報告書の様式が改正され、外国人である労働者が負傷した場合は労働者死傷病報告書の下段に「国籍・地域」と「在留資格」の記入が必要となりました。ただし、「特別永住者」など、外国人雇用状況の届出制度の対象外となっている方については、記入の必要はありません。
3.65歳以上の雇用保険加入者について
平成29年1月1日以降、65歳以上の高年齢労働者が雇用保険の適用対象とされ、平成31年度まで保険料が免除されていますが、令和2年4月1日以後は雇用保険料の納付が必要となります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年4月 8日 月曜日
平成31年4月8日第479号
尊厳死、尊厳死宣言とは、どのようなものでしょう?安楽死との違いは何でしょう?
1.尊厳死、尊厳死宣言、安楽死との違い
(1)尊厳死とは
「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」。つまり、「自然死を迎えること」とされています。
(2)尊厳死宣言とは
「個人が、意識の正常な間に自ら尊厳死を選択する宣言のこと」とされています。
(3)安楽死とは
耐え難い苦痛から解放するため、「医師などの第三者が、薬物などを使って患者の死期を早めること」とされています。
2.現状と宣言方法
(1)日本公証人連合会が公表した統計によりますと、2018年1月~7月に作成さ
れた尊厳死宣言公正証書の件数が、1000件近くに上ったということです。
(2)尊厳死宣言をする主な方法としては、次のようなものがあるとされています。
ア.公証役場で「尊厳死宣言公正証書」を作成する方法
千葉県の松戸公証役場では文例を紹介しています。
http://www.matsudo-koshonin.jp/songenshi/index.html
イ.一般財団法人日本尊厳死協会のリビング・ウイルで宣言をする方法
同協会では、延命治療を望まないという「終末医療における事前指示書(リビング・ウイル)」を作成することが出来ます。
ウ.エンディングノートで延命治療に関することや尊厳死について触れておく。
3. 問題点など
(1)政府は2007年に厚生労働省が発表した、「終末医療の決定プロセスに関する指針」に基づき、尊厳死を選択する際の最低限のルールと手続の明確化を図っており、人工呼吸器の装着や、胃ろうの造成など生命を維持するためだけになされる延命治療につき、本人が拒否する意思を表明していると認められる場合は、本人の意思が尊重されます。
(2)2016年には尊厳死法案の提出も検討されるようになりました。
(3)障害者団体・難病患者団体などでは安易な法制化に反対する動きもあります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年3月23日 土曜日
平成31年3月23日第478号
2019年4月1日、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により労基法が改正され、使用者は5日の年次有給休暇の時季指定権を1年間に行使しなければならなくなりました。従来から労使協定を作成し、計画年休制度を導入している事業所は、さらなる時季指定が必要なのでしょうか。また、事業所が時季指定したにもかかわらず、社員が出社して就労した場合でも罰則の適用はあるのでしょうか。
1.使用者による時季指定
使用者による年5日の年次有給休暇の時季指定義務が定められます。(新労基法第39条第7項および第8項)これは、年次有給休暇の付与日数が10労働日以上である労働者に係る年次有給休暇の日数のうち、5日については、基準日(継続勤務した期間を同条第2項に規定する6ヵ月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定め、与えなければなりません。(新労基法第39条第1項から第3項)
2.計画年休が付与されている場合
使用者が時季指定し、与えなければならない年次有給休暇は5日ですが、労働者が時季指定した日数と、計画年休で付与された日数は、時季指定義務のある5日から控除することができます。
例えば、労働者による時季指定が2日、計画年休による時季指定が1日の場合には、使用者は2日分の時季指定をすれば足りることになります(新労働法第39条第8項)
3.労働者が年次有給休暇日に出勤した場合
使用者が時季指定した場合でも、業務の繁忙等を理由に労働者自らが出勤してしまうこともありうると思われます。当日については労働者には労務提供義務が免除されているのですから、使用者としては帰宅させることが必要であることはいうまでもありません。しかし、使用者が労働者の労務を受領した場合で、結果的に年5日の年次有給休暇が付与できなかった場合、かつ、当該労働者に計画年休や労働者による時季指定もない場合には、労基法に違反すると考えざるを得ないでしょう。
使用者が新労基法第39条第7項に違反した場合には、罰金(30万円以下)が予定されております。(新労基法第120条第1項第1号)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年3月 8日 金曜日
平成31年3月8日第477号
1.「叱る」上司のもとで部下は成長する
近年「叱らない上司」が増加しています。「叱る」ことによりパワハラと捉えられたり、叱られたことを原因として、部下が簡単に退職する場合もあり、叱れないのでしょう。でも、「叱る」という行動なくしては部下の成長は望めません。
2.「怒る」と「叱る」は別物
「怒る」とは、部下が上司の思い通りに行動しない、結果を出せない等の場合に、冷静さを失い腹を立て、怒りの感情をぶつけることを指します。一方「叱る」とは、相手の間違った行動や望ましくない行動に対して、現状での問題点や改善点を考え、今後の成長のために強めにアドバイスすることです。よって、「怒る」上司は、自分の気持ちが中心となってしまい、冷静に部下を見ることができません。怒ってばかりの上司を持った部下は、決して「この人に認められたい」という気持ちにはならないでしょう。
3.効果的な叱り方
叱る目的は、部下の間違った行動や望ましくない行動を改善して仕事の生産性を上げることです。叱られた側がその内容を素直に受け止め、自ら反省できるような叱り方をする必要があります。
(1)その都度、リアルタイムで叱る
その場で直接叱るのが一番伝わるタイミングです。後になって「あの件だけど」と過ぎたことを蒸し返すのは真意が伝わりにくいです。
(2)主観を入れず、事実の確認をする
まずは起こった事実、行動について共通認識になるまで確認します。
(3)ポイントをきちんと説明する
同じ失敗を繰り返すことのないよう、何がいけなかったのかを明確に部下に伝えて理解してもらう必要があります。
(4)人前ではなく別室で叱る
みんながいる場所で叱ると、相手のプライドを傷つけ、恥をかかせることになり逆効果になります。
4.まとめ
部下や目下の人に対して、褒めて伸ばすことが今主流になっています。「褒める」ことは人を育てるうえで欠かせませんが、「叱る」ことも重要です。できたときは、きちんと「褒める」、ルールや指示を無視したり、やらない部下に対しては真剣に「叱る」というバランスをとれる上司が、本当の意味での良い上司といえるでしょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年2月23日 土曜日
平成31年2月23日第476号
毎月勤労統計調査の不適切な取扱から、労働者の平均賃金額が現実とは異なる金額で集計されていました。これにより、平均賃金額を基準として支給されていた雇用保険、労災保険、船員保険、事業主向け助成金に影響が出ています。
雇用保険関係の給付金は、例えば基本手当(失業給付)であれば、基本手当の日額に給付日数を乗じて算出しますが、この基本手当の日額は上限額・下限額が定められており、その限度額を超える部分についてはカットされます。上限額・下限額は毎年、その時点で適用される上限額・下限額に、毎月勤労統計調査における労働者の平均賃金額の前々年度から前年度への変化率を乗じて算出されるので、この上限額・下限額が事実と異なる金額であれば、支給される金額も変わってくることになります。
毎月勤労統計調査は、事業規模に応じて実態調査を行っています。大企業については、全事業所を調査する決まりになっていたのですが、実際は、その3分の1程度の事業所数しか調査していなかったという不正が発覚しました。賃金の高い大企業の分が少なかったということは、当然、平均賃金も少ない額となります。従って、上記の雇用保険の基本手当の上限額が、実際より低く定められたことになり、受け取る給付額が少なくなる可能性が出てくるのです。
政府は調査をして追加給付を行うとしていますが、それには多くの難関があるようです。現在、該当者と追加給付金額を抽出するべく、コンピュータシステムを改修していますが、時間はかかりそうです。
下記の制度に影響している可能性があります。
1.雇用保険関係(2004年8月以降の受給)
基本手当、高年齢求職者給付、特例一時金、就職促進、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付、教育訓練支援給付、就職促進手当、政府職員失業者退職手当等
2.労災保険関係(2004年7月以降の受給)
傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金、休業(補償)給付等
3.船舶保険関係(2004年8月以降の受給)
職務場災害による障害年金、遺族年金等
4.事業主向け助成金
雇用調整助成金の支給決定の対象となった休業期間の初日が2004年8月から2011年7月の間か、2014年8月以降の受給分
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年2月 8日 金曜日
平成31年2月8日第475号
シンガポールのティラミスを真似た商品を、全く同じ商品名やロゴで売ろうとし、シンガポールの会社と関係のない会社が日本で商標登録したため、シンガポールの会社が困っている、という問題が少し前にありました。
シンガポールの会社は何もすることが出来ないのでしょうか?
1.商標が無効になる場合
問題となっている商標が、商標法第4条第1項が定める「商標登録を受けることができない商標」に当たる場合は無効となります。
具体的には、その商標が、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」(商標法第4条第1項第10号)に当たらないか。
又は「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするもの(第4条第1項第19号)」に当たらないかが、本件では問題となります。
2.本件事例の判断基準
本件で商標が無効になるかどうかは、その商標がどこまで日本国内やシンガポールで需要者の間に広く認識されていたのかがポイントとなります。
本件では、さらに、過去の裁判例に照らし、シンガポールの法人の商標と類似であることを知りながら、無断で出願したなどとして公の秩序又は、善良の風俗を害するおそれがある商標(第4条第1項第7号)ではないのかとの指摘もできそうです。
3.手間ひまを考えると先んじて商標登録を
特許庁に無効審判請求をするなどをし、その商標が「登録を受けることができない商標」に当たるかどうかを立証する手間・労力は多大です。
また、問題の会社が、シンガポールのティラミスヒーローに対し、商標権侵害で商標使用の差止や損害賠償請求をすることもあり得ます。商標は無効であるなどの反論が考えられますが、その対応には手間がかかります。
他者から自分の使っているロゴについて商標権侵害だと言われないようにするためには、他者に先んじて商標登録をしたり、すでに商標登録がされていないかしっかり調べたりしておくことが大切です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年1月23日 水曜日
平成31年1月23日第474号
1.統計不正問題
昨年の年末から今年1月初めにかけて、厚生労働省による毎月勤労統計の不適切調査が明るみになりました。毎月勤労統計では、従業員500人以上の事業所を全て調べると決まっています。ところが、厚生労働省は、東京都で調査対象となる約1400のうち、3分の1しか調べていなかったのです。現段階では調査中であるものの、基幹統計という性質からすでに各方面に大きな影響を与えています。
2.問題の原因
この抽出調査は2004年から行われ、内部の調査手法の手引きに記載され、長年続けられてきたといいます。不正は、昨年の12月に総務省統計委員会と厚生労働省との打ち合わせで発覚しました。その際、厚生労働省の職員が「神奈川、愛知、大阪も抽出調査に変えたい」と説明したとも言われています。さらに、抽出調査の不正発覚後に、全数調査に近づけるための加工をしたというのです。このことから、問題の原因として、厚生労働省の職員が調査手法を理解していなかったこと、全数調査が職員の過度な負担となっていたこと、不正が見つかった場合の対処方法が適切になされていなかったことが推測されます。
昨年、厚生労働省に関連する同様の不祥事として、裁量労働制のデータ問題、障害者雇用者数の水増し問題が話題となり、もっとさかのぼれば「消えた年金問題」にたどり着きます。今回の不適切調査は偶然起こったものではなく、組織全体として体質そのものを改善しなければならない問題でしょう。
3.教 訓
国の行ったことを批判することは簡単ですが、自社で不正が行われないような体制はとられているでしょうか。従業員個人レベルでは、与えられた仕事がどのようなルールに基づいているのかを、理解することが必要です。過去の慣習やマニュアルに従うだけではなく、ゼロベースで考えることも必要です。また、管理職レベルでは、部下の職務内容が質・量・責任において、適切である能力なのかを、見極めることが必要となります。さらに、会社のトップは不正が発覚した場合、どのような対処をすべきかあらかじめ危機管理マニュアルを作成し、迅速に対応できるようにすべきでしょう。この対応を間違えて評価を落とした企業はニュースを見ていても枚挙に暇がありません。他人の不祥事を、自己を振り返る機会にしてみてはいかがでしょうか。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年1月 8日 火曜日
平成31年1月8日第473号
1.労災保険法
戦後いち早く制定された労働基準法(昭和22年)に基き、業務上の負傷、疾病、障害、死亡に対する使用者の補償責任が定められ、(1)療養補償、(2)休業補償、(3)障害補償、(4)遺族補償、(5)葬祭料が義務付けられ、同時に(昭和22年)その補償責任を担保するため労災保険法が制定されました。
我々が日々対応する事業主の方や従業員の方の業務災害、通勤災害に、費用の負担や、労働福祉の面で日常的に大きな役割を果たしている制度ですが、やはり、時代や働き方に沿って幾度もの改正がされているところです。
2.法改正による解決
ところが、労災保険は「業務上」、健康保険は「業務外」に対し保険給付を行うことを要件としたため、労働者が副業として行った請負業務での負傷、学生のインターンシップやシルバー人材センターの業務の場合なども労災保険と健康保険の間に挟まり、保険の保護がおよびませんでした。平成25年健康保険法の改正で対象領域が「業務災害以外」の災害に変更され、労災が否定されると健康保険の給付対象となるよう改正されました。ただし、法人格を持たない5人未満の労働者を雇用している事業所は健康保険の強制適用ではないため、業務外の災害について健康保険の適用から漏れる労働者があり、国民健康保険が適用されるケースもあります。
3.もう一つの問題
もう一つの問題は、本来は労働災害であるのに健康保険で受診してしまった(あるいは受診している)場合です。
この場合、健康保険で受診してしまった(あるいは受診している)事案を労災保険に切替えるわけですが、いったん健康保険で全額を立替えて清算したうえで、労災保険に費用請求するというのが従来の方法でした。
この方法ですと、被災労働者に一時的な経済的負担が生じましたが、新しく、労災保険と健康保険の保険者間で調整し、労災保険給付額を返還額に相当する療養の費用として、健康保険の保険者あて直接振り込むことができるようになりました(「労災認定された傷病に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合における保険者等との調整について」平成29.2.1基補発0201第1号)。
なお、新しい方法によるためには、労災事案であることが必要ですから、調整前に労災認定を受けたものであることが前提です。
後で調査が入り、ちょっとの事故と思っていても、立派な労災事故だった、ということがないよう気をつけたいものです。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年12月23日 日曜日
平成30年12月23日第472号
1.人生100年時代はすぐそこに
現在の平均余命は男性84歳、女性89歳です。人生100年時代は意外に早く訪れ
ます。少子高齢社会において100年の人生を安心に生活するための基本は健康と資産形成でしょう。1億総活躍社会と言われ高齢者の就業が増加しています。働く年限は、厚生年金の加入上限である70歳までと考えられます。それ以後、100歳までの30年間は、年金と資産の取り崩しで生活することになります。
2.夫婦2人の年金と生活費
平均年収700万円程度と専業主婦の組み合わせ世帯の年金は約22万~25万円となり、必要生活費は35万円(生命保険文化センター)と言われています。毎月の不足額を10万円と見積もると30年間で3,600万円の貯蓄が必要になります。
3.投資 お金に働いてもらうとは
3,600万円の貯蓄があれば、貯蓄は充分なので投資の必要ありません。しかし、
貯蓄が不足するなら、お金に働いてもらう必要があります。つまり、投資はお金がある人がする事ではなく、お金が不足する人がする行為といえます。
投資のポイントは、対象の分散、時間の分散、長期投資です。そうすると、危険な投
資の典型は、1つの投資対象に対し、まとまったお金(仮に100万円)を一度に投資することです。
4.非課税制度を利用する
国の制度であるNISA、積立てNISA、小規模企業共済、掛金の全額が所得控除
の対象であるIDECOは、メリットが大きいため多くの利用が有ります。
非課税枠は、ハイリスク・ハイリターンを避けて、確実性の高い商品を中心に選ぶこ
とが大切です。その際、手数料の高低の比較も重要です。
5.E.T.F(上場投資信託)について
ETFとは、日経平均株価や東証株価指数など、特定の指数の動きに連動するように運用される投資信託の種類です。取引所に上場されているので、株式と同様に売買できて指値注文や成り行き注文ができ、一般的な投資信託よりも信託報酬が低いといった特徴があります。
その他の特徴としては、一般的な投資信託は基準価格が有るのに対して、ETFはその時々の取引価格で売買されます。一方、リスクとしては、組み入れられた有価証券の価格変動によりETFの価格が変動します。資産形成は、安全で使い勝手の良い資産を選択することが重要です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年12月 8日 土曜日
平成30年12月8日第471号
所有者が分からない土地を有効に活用することが出来るようにするために「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が本年6月6日に成立しました。
1.所有者不明土地の問題
『所有者不明土地問題研究会』(座長:増田寛也元総務相)の推計によると、所有者不明土地の総面積は九州の面積である約368万ヘクタールを上回る410万ヘクタールとされています。
2.特別措置法の概略
(1)利用権を設定できるのは次のような土地です。
ア.土地上に建築物がない
イ.反対する権利者がいない
(2)公益目的を条件にNPO法人等が直売所や駐車場等を造ることが出来ます。
(3)持ち主が現れた場合は期間終了後に原状回復して返すことになりますが、現れなければ期間を延長することも認められます。
(4)期間は最長で10年とされています。
(5)道路や町づくりの妨げになっている土地について、都道府県の収用委員会の審理を経ずに取得できるような対策も作られました。
3.施行日
この法律は所有者不明土地問題の第1弾とされており、公布日の6月13日から1年を超えない日を定めて施行されます。
4.今後の動き
(1)第2弾としては2020年までに土地所有者の把握を進めると同時に、新たな所有者不明土地を発生しないようにするため、国土調査法や土地基本法の改正を視野に入れた施策を進めるということになっています。
(2)具体的には次の通りです。
ア.所有者不明の土地について登記官に調査権限を与える
イ.自治体が管理する所有者の死亡情報と国の登記情報を結びつける
ウ.相続登記を義務化する
エ.土地所有権を放棄できる制度の創設
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年11月23日 金曜日
平成30年11月23日第470号
従業員が、研修という名目で業務に必要な技能習得、資格の取得をする場合、その費用を会社で負担することも多いと思います。それらの費用は、研修を受講した人への給与となるのでしょうか。
資格取得費用の基本的な考え方は、従業員の資格取得等に要する費用で、会社が負担したものは、従業員に支給された経済的利益に該当し、原則として給与所得として課税されます。ただし、会社が自己の業務上の必要にもとづき、仕事に直接必要な内容であること、そして次の要件すべてを満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与所得として課税しなくてもよいことになっています。
(1)技術や知識を、役員または従業員に習得させるための費用であること
(2)免許や資格を、役員または従業員に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること
(3)関係分野の講義を、役員または従業員に大学などで受けさせるための費用であること
具体例
(1)従業員に対して、業務を遂行するために必要な資格である調理師免許を取得させた場合
・給与所得として課税されない。
(2)新入社員に対して、業務を遂行するために必要な資格である調理師免許を、会社へ入社する前に取得させる。試用期間中に退職した際には、全額を返金させる予定である場合
・給与所得として課税されない。試用期間中に退職した場合も、本人に費用返還を求めるため、給与所得として課税さない。
(3)来年度から入社することが内定している者に対して、ビジネスマナー講座を受講させる。内定者が入社しなかった場合には全額を返金させる予定である場合
・給与所得として課税されるが、内定者が入社しなかった場合は、本人に費用返還を求めるため給与所得として課税されない。
役員、従業員に対して、仕事に直接必要なものであれば、給与所得として課税はされないが、仕事に直接必要のない、自己啓発的な知識習得や、モチベーションアップのための費用を、会社が負担すると給与所得として課税されるということです。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年11月 8日 木曜日
平成30年11月8日第469号
被相続人の死亡により、被相続人の権利義務の一切を相続人が承継することを相続といいます。被相続人の財産は、相続が開始されると相続人全員の共有状態となり、個々の相続分は、遺言を優先し、遺言がない場合は相続人の協議による遺産分割、または法定相続分によります。法定相続とは、配偶者及び一定の血族に対し民法でその順位及び配分率が定められています。
1.配偶者は、法律上の配偶者を指し、常に相続人となります。婚姻届を出していない事実婚の配偶者は含まれません。
2.子(及び子の代襲相続人)は、配偶者を除き第1順位の相続人となります。既に子が死亡している場合は、孫が第1順位の相続人となります(代襲相続)。既に孫が死亡している場合は曾孫が代襲相続します。
3.直系尊属(父母、父母がいないときは祖父母)は、第1順位の血族相続人がいないときに相続します。
4.兄弟姉妹(及びその代襲相続人)は、第1順位および第2順位の血族相続人がいないときに相続人となります。既に兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子までは代襲相続します。兄弟姉妹の孫が代襲相続することはありません。
5.その他、相続開始時に胎児であった者は、実際に生まれた場合には相続権が認められますが、死産の場合は相続権がなかったものとされます。
兄弟姉妹以外の相続人には、法定相続人の遺産継承を確保するため、一定割合の遺産
を確保できる遺留分を認める制度があります。
法定相続分と遺留分の割合は次のとおり決められています。
・第1順位 配偶者と子 法定相続分は1/2、遺留分は1/4
・第2順位 配偶者と直系尊属 配偶者の法定相続分は2/3、遺留分は1/3
直系尊属の法定相続分は1/3、遺留分は1/6
・第3順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者の法定相続分は3/4、遺留分は1/2
兄弟姉妹の法定相続分は1/4、遺留分はなし
・配偶者のみ 配偶者の法定相続分は全部、遺留分は1/2
・子のみ 子のみの場合法定相続分は全部、遺留分は1/2
・直系尊属のみ 配偶者も子もいない場合は、直系尊属が相続人と
なり、法定相続分は全部、遺留分は1/3
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年10月23日 火曜日
平成30年10月23日第468号
労働関係に関する重要な判決「ハマキョウレックス(以下「会社」という)事件」のご紹介です。会社は、運送事業等を目的とする株式会社で、有期労働者である原告は、トラック運転手として配送業務に従事していました。
原告と正社員間のどのような差が「不合理な差別」として、違法となるのでしょうか?
1.無事故手当 →不合理である
無事故手当は、乗務員が1ヵ月間無事故で勤務したときに限り、無事故手当として1万円が支給され、優良ドライバーの育成や、安全な輸送による顧客の信頼の獲得を目的とするものと解されるところ、優良ドライバーの育成や安全な輸送による顧客の信頼の獲得といった目的は、正社員の人材活用の仕組みとは直接の関連性を有するものではなく、むしろ、正社員のドライバーと契約社員のドライバーの両者に対して要請されるべきものである。そうすると、正社員のドライバーに対してのみ、無事故手当月額1万円を支給し、契約社員のドライバーに対しては、同手当を支給しないことは期間の定めがあることを理由とする相違であり、労働契約法第20条にいう「不合理と認められるもの」に当たると認めるのが相当である。
2.作業手当 →不合理である
会社は、作業手当は、元来、乗務員の手積み、手降ろし作業に対応して支給されていたものであるが、現在は、正社員に一律に支給されており、実質的には基本給としての性質を有しているものであるから、その支給不支給の区別が不合理であるということはできない旨主張した。しかし、過去に手で積み降ろしの仕事をしていたドライバーが正社員のみであり、契約社員のドライバーがその仕事に従事したことがないことを認めるに足りる証拠は見当たらないし、作業手当が現在は実質上、基本給の一部をなしている側面があるとしても、本件正社員給与規程において、特殊業務に携わる者に対して支給する旨を明示している以上、作業手当を基本給の一部と同視することはできない。そうすると、正社員のドライバーに対してのみ、作業手当月額1万円を支給し、契約社員のドライバーに対しては同手当を支給しないことは、期間の定めがあることを理由とする相違というほかなく、労働契約法第20条にいう「不合理と認められるもの」に当たると認めるのが相当である。
3.その他の手当差
全てについてご紹介できませんでしたので、また引き続きご紹介したいと思います。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年10月 8日 月曜日
平成30年10月8日第467号
1.特定労働者派遣事業の完全終了
平成30年9月29日をもって届出制の特定労働者派遣事業が完全に終了し、許可制の労働者派遣事業に一本化されました。許可制への切り替えを行っていた旧特定労働者派遣事業者は、許可されるまでは従前の労働者派遣事業を行うことができますが、切り替えを行っていない事業者は、9月30日以降労働者派遣事業を行うことができなくなりました。許可制へ切り替えることで特定労働者派遣では認められていなかった常用雇用以外の労働者派遣や登録制度を採用することができるため、派遣労働者の受け入れ側(派遣先)のニーズにより適した形の派遣が可能になります。
一方派遣先は、以前から旧特定労働者派遣事業者と取引をしている場合、すでに許可を取得しているのか、または上述の切り替え申請をしており、審査中なのか確認する必要があります。許可の取得は「人材サービス総合サイト」で確認することができます。確認をせずに許可申請をしていなかった事業者と取引を行った場合には、労働者派遣法第40条の6の「みなし制度」(派遣先が派遣労働者に労働契約の申込をしたものとみなされる制度)の適用を受ける可能性があるので要注意です。
2.抵触日の到来
改正労働者派遣法が平成27年9月30日に施行され、3年が経過しました。気を付けなければならないことは、派遣事業者については、就業先の同一の組織単位の業務について継続して3年間派遣する見込みがある有期雇用派遣労働者に対して雇用安定措置を講じなければならないことです(派遣法第30条1項各号及び同条2項)。
また、法改正日以降派遣事業者と派遣契約を締結した派遣先は、初めて派遣労働者(一部例外を除く)を受け入れた日から3年を超えてその事業所で受け入れることができません。延長することは可能ですが、抵触日の1ヵ月前までに派遣先事業所での意見聴取手続を終えている必要があります。また、これとは別に就業先の組織単位において同一派遣労働者を、3年を超えて受け入れることはできません(この場合延長の手続はなし)。これに違反すると前述と同様「みなし制度」の対象になりますから、すでに派遣労働者を受け入れていて、これから抵触日が到来する事業者については、適切な意見聴取手続を経て派遣契約を結んでいただきたいと思います。派遣契約に不備があると、派遣元事業者と派遣先事業者双方が労働局による是正指導の対象となりますので、お互いに迷惑をかけないためにも今一度契約内容を確認することが必要です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年9月23日 日曜日
平成30年9月23日第466号
1.残業時間の上限規制は罰則付き
働き方改革関連法が平成30年6月29日に可決・成立しました。この関連法案は労働基準法、じん肺法、労働安全衛生法等8つの法律を一括改正するものとなっています。主な改正内容をご紹介しますと、まず残業時間の上限規制が導入されます。労働基準法に「1日8時間、週40時間」と定められている法定労働時間、これを超えて仕事をさせることができるいわゆる「36協定」において、月45時間、年360時間という基準を明確化し、かつ臨時特別的事情のある場合でも45時間を超えての残業は6ヵ月まで、年間の上限は720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間(休日労働を含む)と定められ、違反には罰則が適用されます。ただし、自動車運転や、建設、医師等に対しては、適用は5年後、新技術・新商品の研究開発には適用されません。施行期日は2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日となります。
2.長期間労働抑制・年次有給休暇の取得促進
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について中小企業への猶予が廃止されます。施行期日は2023年4月1日です。また、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対し、5日について毎年時季を指定して与えなければなりません。この施行期日は2019年4月1日です。
3.高度プロフェッショナル制度の創設
年収1075万円以上の高度なスキルを持つ社員を、労働時間の規制対象から外すもので、一般的には研究職等、年収、専門性の高い職種が該当します。ただし、具体的な額等については省令で規定することとされています。施行期日は2019年4月1日からです。
4.同一労働同一賃金
短時間労働者、有期雇用労働者について正規雇用労働者との待遇格差が不合理か否か、その性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨、が明確化されます。施行期日は2020年4月1日です。(中小企業は2021年4月1日)
5.まとめ
今回の働き方改革は「戦後からの労働関係法による労働行政」の大改革の様相を呈しています。どの企業においても、適切に対処、対策の検討が急がれるところです。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年9月 8日 土曜日
平成30年9月8日第465号
1.老後の生活資金は自助努力が求められる時代
公的年金(国民年金・厚生年金)は現役世代から徴収した保険料を元に老後を迎えた人に給付を行う世代間扶養の方式をとっています。個人年金の様な個人別の口座等の必要がなく合理的に運用することが可能である反面、出生率の低下による高齢化率の加速・平均余命の延長から、年金額の減少や支給開始年齢の引き上げが予想され、公的年金だけでは退職後の生活資金の確保が難しくなってきました。
2.確定拠出年金のテコ入れ策
中小企業や個人への導入を進めるため確定拠出年金法が改正、平成29年1月1日から施行されました。そのポイントは、(1)加入対象者の拡大(2)投資教育の充実(3)企業の選択肢を充実(4)手続きの簡略化です。このうち加入者の拡大については個人型に「iDeCo」と愛称をつけ加入対象者の拡大が図られました。
3.選択制確定拠出年金の導入
選択制確定拠出年金とは、給与の一部を切り離し、企業型確定拠出年金とするか、退職金の前払い(給与)とするかを従業員に選択させる制度です。
(1)導入するメリット
・ 人事評価と給与の一部を切り離して考えることができる。
・ 従業員自身が老後の資産形成を考える機会となる。
・ 社会保険料・労働保険料、所得税・住民税が減額となり、事業主の経費削減と従業員の節税が同時に可能になる。保険料掛け金の拠出額は標準報酬が1等級以上下がるよう設定するのが望ましい。
(2)導入するデメリット(主に従業員側)
・ 掛け金が給与に含まれないことから、雇用保険の賃金日額や社会保険の標準報酬が下がるので、老齢厚生年金の額や、失業した際の基本手当が減額となる。
・ 確定拠出金年金の掛け金は労働基準法上の割増賃金の算定に入らない。
・ 確定拠出年金の掛け金として拠出した部分は60歳まで引き出せない。
・ 退職予定者、出産が近い者、病気休職予定者は健康保険の傷病手当金や雇用保険の基本手当が減額となる。
(3)導入の手続き
企業が単独で年金規約を作成し、厚生労働大臣に承認を得る単独型と既に厚生労働大臣から承認され年金規約を持っている企業を代表事業主とし、当該制度の実施事業主として相乗り参加する統合型が有ります。導入には、労働組合の同意書や、就業規則の変更及び、選択制確定拠出年金規程の作成等が必要となります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年8月23日 木曜日
平成30年8月23日第464号
相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法など関連法が7月6日に成立しました。
1.配偶者居住権の創設(公布日から2年以内の施行)
住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分割し、配偶者は居住権を取得すれば所有権が別の相続人や第三者になっても住み続けることが出来るようになりました。
この権利を公示するため「配偶者居住権」の登記制度を設け、建物の所有者は配偶者に対し登記義務を負うことになりました。
また、相続開始時に無償で居住していた場合、遺産分割協議が終了するまでか相続開始から6ヵ月のいずれか遅い日まで無償で住める「配偶者短期居住権」も設けました。
なお、被相続人が居住建物を配偶者以外の者(夫と長男など)と共有していた場合には配偶者居住権が発生しませんので、注意が必要です。
2.婚姻20年以上の配偶者の優遇策(公布日から1年以内の施行)
婚姻20年以上の夫婦で配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は「遺産とみなさない」という意思表示があったとして遺産分割の対象財産から除外することになります。
3.自筆証書遺言の見直し
(1)財産目録については、パソコンで作成しても良いことになりました。(公布日から6ヵ月以内の施行)
(2)法務局が自筆証書遺言を保管する制度を作りました。この制度を利用した遺言書の検認は不要です。(公布日から2年以内の施行)
4.特別寄与者制度の創設(公布日から1年以内の施行)
相続権のない6親等内の血族と3親等内の配偶者が介護などに尽力した場合に、相続人に金銭を請求することが出来る制度を設けました。(事実婚、内縁等は除く)
5.金融機関における「仮払い制度」の創設(公布日から1年以内の施行)
遺産分割協議が終わる前に生活費や葬儀費用の支払いなどのために被相続人の預貯金を金融機関から引き出すことが出来る「仮払い制度」を創設しました。
仮払いをすることが出来るのは「被相続人の預貯金額×1/3×法定相続分」としますが、別途、法務省令で一行あたりの上限額について定めを設ける予定です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年8月 8日 水曜日
平成30年8月8日第463号
改正刑事訴訟法の「司法取引」制度が、2018年6月1日から施行されました。事件解決に向け重要な供述を得るために活用される司法取引は、欧米諸国で広く採用されていますが、日本で導入される「司法取引」制度とは、どのようなものなのでしょうか。
1.司法取引とは
「司法取引」制度は、特定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪(法第350条の2第2項各号の「特定犯罪」)について、検察官と被疑者・被告人が、弁護人の同意がある場合に、被疑者・被告人が、共犯者等他人の刑事事件の解明に資する供述をし、証拠を提出するなどの協力行為を行い、検察官が、その協力行為の見返りに、被疑者・被告人に有利に考慮し、これを不起訴にしたり、軽い罪で起訴したり、軽い求刑をするなどを内容とする「合意」ができるとし、このような両当事者間の協議・合意を通じて、他人の犯罪行為の訴追・処罰に必要な供述証拠等を獲得しようとするものです(法第350条の2以下)。
2.メリット
・被疑者らから真実を引き出すことができるのであれば真相解明に有効である。
・供述者の協力が得られるから、事件の迅速な処理を図ることができ、費用、時間と労力の節約になる。
・他人の犯罪に関する動機などの証拠が不十分な場合、確実な証拠を持っている者の刑を減免する約束で供述を得ると、他人の犯罪の発見が高められ、より重要な犯罪の捜査に役立つ情報が得られる。
・捜査機関が、被疑者・被告人の刑事処分に手心を加える代わりに、他人の犯罪を聞き出すことが容易になり、組織的犯罪等の解明に威力を発揮することが期待できる。
・密行性の高い組織的犯罪等について、首謀者や背後者などのような真に処罰すべき者を処罰することができる。
3.デメリット
・虚偽供述の可能性による冤罪が危惧される。(司法取引は、冤罪を惹き起こしやすい)
・被疑者・被告人が重罰を避けるため、あるいは自分の罪を軽くするために司法取引を行い、関係のない他人を巻き込んだり、犯罪の役割の軽い者に罪をなすりつけるように偽証したりする可能性がある。
・捜査機関は協力を取り付けようとし、他方、被疑者・被告人は特典の付与を期待するため、利害が一致しやすく、虚偽供述が一層起きやすくなることが懸念される。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年7月23日 月曜日
平成30年7月23日第462号
企業グループ内で主に経理や総務などの各社共通する業務を一つ企業に集約し、経費の削減や業務の効率をはかる経営手法をシェアードサービスといいます。そのために作られた会社をシェアード会社と呼びます。
日本国内では、2000年以降急速にシェアード会社が増え、特に従業員1万人以上、関連企業50社以上の大手製造業での導入比率が高いようです。シェアード化する部門は、経理・人事・総務・IT等の間接部門が大半を占めています。
ここでの注意点は、社会保険や労働保険の代行を業務として行うには、社会保険労務士または社会保険労務士法人の資格が必要だということです。社会保険労務士法第27条に「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じて報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。」とあります。グループ会社内での行為であったとしても業として行う限りは当法律に抵触するものと思われます。
平成29年に厚生労働省主催で規制改革の一環として、グループ企業内でのシェアードサービスにおける「社会保険に関する手続」について各専門委員からヒアリング形式による検討会を開催しております。その時の議事録及び論点に対する回答書が内閣府のホームページに掲載されています。この回答が結論となるわけではありませんが、社労士もしくは社労士法人でないシェアード会社が社会保険等の手続業務の代行を業として行うには否定的な見解のように思われます。ただ、検討会の回数が進むにつれその雰囲気が多少変化しているようにも思われますが、この行為を肯定するには至りません。
社会保険や労働保険は、過去からの変遷を含んだ内容であり手続きであっても煩雑で難しい部分を含んでいます。また、労働者にとって生活に直結する重要なバックボーンとなっています。この制度の運用に過ちがあってはなりません。国がそれを行う者に対し知識の担保を求めることは当然であり必要なことと考えます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年7月 8日 日曜日
平成30年7月8日第461号
平成30年6月13日、民法の成年年齢を、20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする、民法の一部を改正する法律が成立しました。2022年4月1日に施行されますので、あと4年もしないうちに、成年の年齢は18歳ということになります。
これによって、気をつけなければいけない点は何でしょうか?
1.有効な契約をすることができる年齢が18歳
未成年者(18歳、19歳)が、契約といった法律行為をするためには、親権者の同意が必要です(民法第5条1項)。そのため、遠方の大学に進学して、アパートを借りるとか、ローンを組んで車を購入するといった場合には、親の同意が必要です。
そして、未成年者が親権者の同意を得ずに行った法律行為については、未成年者であることだけで取り消すことができました。(民法第5条1項)
しかし、成年年齢が引き下げられることにより、これらのことが学生でも単独で有効に出来るようになります。
消費者被害の拡大が懸念されているところですので、注意が必要でしょう。
2.親権に服することがなくなる年齢が18歳
成年年齢の変更により、18歳以上の子どもについては親権者を定める必要がなくなりますので、18歳以上の子どもについては親権を争う紛争は生じなくなります。
問題となるのは、養育費です。既に、離婚協議書などで養育費の取り決めをしている場合、その終期を「子が成人に達する月まで」という形で決められている場合には、作成時の20歳なのか、改正後の18歳なのかについて疑義が生じる可能性があります。
今後は特に、離婚協議書などで養育費を定める場合には、一義的に明確な終期(〇〇年〇月)を定めておくことが大切でしょう。
3.その他の改正
今回の改正から、女性の婚姻可能な年齢を引き上げ、婚姻開始年齢は男女とも18歳に統一されることになりました。
「成人」の定義が変わることで、学生であっても、責任を持った行動が問われることになります。親としても注意が必要になるでしょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年6月23日 土曜日
平成30年6月23日第460号
1.2つの待遇格差
平成30年6月1日、正社員と非正社員との間の賃金格差が労働契約法第20条の禁
じる不合理な格差に該当するかという問題で、最高裁判所が初めて2つの判決を下しま
した。正社員と契約社員の待遇格差の問題(ハマキョウレックス事件)と定年前の正社
員と定年後再雇用の契約社員との待遇格差の問題(長澤運輸事件)でした。
2.判決の内容
ハマキョウレックス事件の最高裁で争われたのは、住宅手当と皆勤手当でした。とも
に就業規則上正社員には支給され、契約社員には支給されないものとされていましたが、
この点について、最高裁は住宅手当の格差は不合理ではないとし、皆勤手当の格差は不
合理であると判示しました。
その理由として、住宅手当は住宅に要する費用を補助する趣旨で支給されていること
から、転居を伴う配転が予定されている正社員は、就業場所の変更が予定されていない
契約社員に比べて住宅に要する費用が多額になりうることを挙げました。
一方、皆勤手当については、皆勤を奨励する趣旨で支給されていることから、職務内
容が異ならない正社員と契約社員とで差異が生ずるものではないとしました。
長澤運輸事件の最高裁では、能率給及び職務給、精勤手当、住宅手当及び家族手当、
役付手当、超勤手当並びに賞与の格差が問題となりました。精勤手当と超勤手当につい
ての格差はハマキョウレックスと同様の理由で不合理であるとしましたが、それ以外に
ついては不合理でないとしました。
その理由として使用者が賃金格差を縮める努力をしたことや定年後再雇用の契約社
員は老齢厚生年金を受給できることなどが考慮されました。
3.今後の企業対応
今回の最高裁の判断は、支給項目の趣旨から個別具体的な判断をしており、事案によ
って結論は変わりうると思われます。今後法改正が行われ、行政の通達や指針という形
で最高裁判決の趣旨を踏まえた対応を使用者側に求めることが予想されます。企業の対
応としては、社員間の待遇差がある場合に予め理由を説明しておくべきでしょう。また、
手当を見直し、給与体系をシンプルにすることで、無用な労使紛争を起こさないことも
必要になってくると思います。今から検討を始めていきましょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年6月 8日 金曜日
平成30年6月8日第459号
1.時間外労働の上限規制の導入
働き方改革関連法案の1つとして時間外労働時間の上限規制の導入がされる予定です。働き方改革関連法案とは、8つの労働法の改正を行う、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の通称です。平成30年に国会に提出され、衆議院で審議が行われています。
2.現状
法定労働時間を超えて、時間外労働や休日労働をさせる場合、あらかじめ労使間で時間外労働の上限時間等を取り決め、「時間外・休日労働に関する協定届」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第36条)。その際の時間外労働の上限は原則月45時間、年360時間です。
しかし、特別条項を適用させれば、臨時的な特別な理由がある場合に限り、年間6回までの範囲内で、月45時間を超えて時間外労働させても良いことになっています。特別条項を適用させた場合の年6回までの月の上限は青天井であり、実質的に無制限状態です。そのため、今回の法改正で規制されます。
3.変更内容
時間外労働の上限時間数は次のように制限されます。
<原 則>月45時間 年360時間(変更なし)
<特別条項>
次の全ての条件を満たす場合にのみ、特別条項が適用可能となります。
(1)月100時間以下(休日労働時間を含む)
(2)2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内
(3)年720時間以下
(4)月45時間を上回る月数は年6回まで(変更なし)
法律が可決されれば、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から適用されます。人材不足が叫ばれている昨今、時間外労働は簡単に削減できるものではありません。そのため、働き方の見直しや風土改革などが必要な場合は早めの対策をお勧めします。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年5月23日 水曜日
平成30年5月23日第458号
1.年金額の自動改定
年金額は改定率を改定することで毎年度自動的に改定されます。この、改定率の改定には、原則的な改定とマクロ経済スライドによる改定の2種類の方法があります。
(1)原則的な改定は、68歳に達する年度前の受給権者は名目手取り賃金変動率、
68歳に達する年度以後にある受給権者は物価変動率を基準として計算されます。ただし、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合は、全年齢に共通して同じ基準で変化の少ない方の基準で改定されます。
(2)マクロ経済スライドによる改定とは、賃金や物価の変動に加えて、被保険者の減少及び平均余命の伸びという年金財政にとってマイナスの要素を年金額に反映させる(以下「調整率」という)ものです。
マクロ経済スライドは、賃金・物価が上昇した場合に行い、その際、上昇率が調整率を下回るときは年金額は据え置かれます。賃金・物価が下落した場合は、原則的な改定を行い、マクロ経済スライドは適用されません。
2.原則の改定率の算定式
マクロ経済スライドによる年金額の調整期間における改定率の改定
(1)68歳に達する前の年度(以下「基準年度」という)の受給権者:
名目手取り賃金率×調整率(年金被保険者数変動率×平均余命伸率)×前年度からの特別調整率(前年度に調整できなかった繰越部分)
(2)基準年度以後の受給権者: 物価変動率×調整率×前年度からの特別調整率
調整率及び特別調整率を年金額に反映させ、賃金又は物価の上昇率を年金に反映させることにより上昇率を抑制した率が算出率となり、年金額が抑制されます。
3.平成30年度の国民年金額と年金額の新しい改定ルール
賃金が-0.4%、物価は+0.5%であったので、例外規定が適用され、年金額は前年度と同じになります。満額の国民年金は、年額779,300円です。
平成30年度から、年金額で過去に調整できなかった部分が繰り越され、累積されることとなりました。賃金・物価の変化によってマクロ経済スライドが適用された後でも更に下げる余地があるときは、累積部分を積み増しし、さらに年金額を押さえる仕組みが導入されます。つまり、マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない様に維持しつつ、賃金物価上昇の範囲内で前年度の未調整部分の調整を行うこととされました。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年5月 8日 火曜日
平成30年5月8日第457号
市街地では、住所のほとんどは地番ではなく住居表示というものが利用されています。
1.住居表示とは
住所は、元々、地番を利用していましたが、土地を分筆や合筆することで、枝番・欠番・飛び番などが生じて、町がわかりにくくなったり、郵便の配達が遅れたりするなど様々な弊害が生じてきました。
そこで昭和37年に「住居表示に関する法律」を作り、建物に対して番号を付けることになり、この住居表示を住所とすることにしました。
2.住居表示の対象は
市街地を対象にしています。市街地の基準としては「4,000~5,000人/1平方kmの人口密度」とされています。
3.住居表示の方式
街区方式と道路方式の2つがありますが、道路網が整然としている京都市などを除き、ほとんどの市町村が街区方式を用いています。大阪市中央区の一部分でも道路方式を用いているところがあります。
街区方式とは、町の境界を道路・鉄道など恒久的な施設または河川・水路などにより区画し、その中の建物に住居表示のための番号を付けて表示することをいいます。
4.住居表示の方法
住居を表示するには、都道府県、市(区)、町村の名称ならびに町名、街区符号、住居番号を用います。(例:○市○区○丁目「町名」〇番「街区符号」〇号「住居番号」)
5.地番との違い
地番は、一筆ごとの土地に番号を付けたものです。不動産の登記簿謄本「登記事項証明書」を取得する際には、この地番が必要になります。
住居表示が実施されていない地域や、住居表示が実施されている地域でも区画整理事業が実施されたりしている地域では、地番と住所が同じということもあります。
6.住居表示実施基準
住居表示を実施する基準(街区符号を振る基準など)は、各市町村が定めています。
ちなみに、大阪市は「大阪城」、堺市は「宿院」を基準としています。
(大阪城に近いところを起点として街区符号を順序よく付けています。)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年4月23日 月曜日
平成30年4月23日第456号
自宅での労働は労働時間に該当するのか
会社が労働時間短縮を促進するため退社時間を早めたため、帰宅後や休日に自宅で業務を処理する社員がでてきました。その社員に対し、時間外労働、深夜労働、休日労働として取扱い、賃金の支払い対象の労働時間に該当するのかという点が問題となりました。
労働基準法上「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」と定義されています。
そこで、自宅で行った仕事が使用者の指揮命令下のもとになされたか否かを考える必要があります。自宅で「仕事」を行えばどのようなものでも当然に指揮命令下にあると判断されるものではありません。労働者が労務を提供する時間という事ではなく、使用者の指揮命令下で行われることが必要だからです。そうしますと、たとえば、自宅での業務がどのようになされているのかを考えてみます。
(1)テレビやパソコンで動画を観ながら行っている。
(2)いつ仕事を行うか、いつ仕事を終えるのかも本人次第である。
(3)食事をしながら、場合によってはビールを飲みながら作業を行う。
このようなことを踏まえると、自宅での「仕事」は、会社に出社した状態での勤務とは大きく異なることが明らかでしょう。そうすると、原則として、自宅で「仕事」を行ったとしても使用者の指揮命令下におかれたものとは言えないと考えられ、労基法上の労働時間ではないと考えられるため、時間外手当、深夜労働手当及び休日労働手当を支払う義務はないと考えます。
しかし、上司が部下に自宅で仕事を完成させるように指示した場合や、携帯電話や電子メールで上司が自宅にいる部下に対し、作業を指図している等の事実関係があった場合には、指揮命令下にあるものと考えられ、労働時間と判断されることが多くなります。もし、そのような社員がいる場合には、管理職等からどのような経緯で社員が自宅で仕事を行ったのかを確認する必要があります。
また、業務を持ち帰っていることを知りながら、その行為を黙認するような場合は、労働時間と判断される可能性が高くなり、社員が健康を害した場合の労災や損害賠償のリスクも使用者側に生じることがあるので注意しましょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年4月 8日 日曜日
平成30年4月8日第455号
1.現状
平成24年に改正された労働契約法第18条は、有期契約で働いている労働者を反復契約し5年を超えて雇用すると労働者の希望に基づき、無期契約での雇用に転換することが記載されています。平成25年4月以降に締結された有期契約から対象となり、早ければ今年の4月から無期転換が発生します。企業によっては、最近の求人状況等を考慮し有期契約を無期契約へ積極的に切替えることで労働者の囲い込みを進めている会社もでてきています。規模の大きな企業ではこうした積極的な雇用方針の変更を探る会社も見受けられますが、中小企業においては、無期転換への対応策がまだ定まらないでいる会社が多いのではないでしょうか。
正社員は既存の定年制度によって雇用の終了が決められていますが、「無期転換ルール」に基づき、雇用の終着点が無くなった労働者を企業側としてどう対応するかを定めなくてはなりません。自社の雇用状況をよく理解し役割と待遇に不合理性が無く、差異に対してはきちんと説明できる就業規則とする必要があります。第18条では無期契約期間とする旨の記載であり、他の条件の変更を要求しているものでないからと、無期転換者の労働条件を個別の雇用契約で定めたとしても、正社員の就業規則に劣る内容であれば第12条により雇用契約の定めは無効となり就業規則の定めが適用されます。
また、無期契約転換の申入れは口頭でも成立しますが、後々のリスク回避を思えば無期転換権について会社側から労働者へ事前に周知しておくべきです。有期社員用就業規則があればそこに、無ければ有期雇用契約書に無期転換申込の手続きを明記し周知しておくのが良いでしょう。労働者に無期転換申込の権利を放棄させる誓約書等を書かせたとしても、これは法の趣旨に反するものとして無効となる可能性が高いと思われます。
2.対応策
勿論、企業ごとに雇用されている労働者の状況によるところが大きいのでしょうが、一般的には、第二定年制を取入れている企業が多いです。その場合、第二定年を何歳で設ければよいかは、有期契約者の人数や年齢層さらに正社員の定年年齢との比較等をした上で定めることになります。場合によっては、第三・第四の定年制を設けることもあり得るやもしれません。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年3月23日 金曜日
平成30年3月23日第454号
1.保証契約について
民法改正(2020年4月1日施行)によって、保証契約に大きな変更があります。
例えば、不動産賃貸をしている方であれば、借主が家賃を滞納した場合のために保証人
をたててもらうのが通常です。
このとき、多くの場合「根保証契約」をしています。
このような根保証契約の典型は、銀行と事業者との貸金取引など継続的な取引契約が
結ばれる場合です。この根保証契約は、例えば、100万円借りる際に保証人になった
ところ、その後追加で借りた1000万円まで責任を負うことを知ってトラブルになっ
てきたというような経緯があります。
そこで、平成16年の民法改正では、こういった貸金等根保証契約について保証人保
護のための規定が設けられました。
しかし、不動産の賃貸借から生じる賃借人の賃料債務の保証に関する「根保証契約」
については規定がなく、トラブルになる事例もありました。
(雇用契約における身元保証も、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とするので、根保証契約に当たりますが、身元保証については、昭和8年に身元保証に関する法律が制定されています)
それでは、実務への影響が大きいと思われる改正部分について見ていきましょう。
2 個人根保証における極度額の設定義務
改正法により、極度額を書面で定めなければ、その効力を生じないとされます(新法第465条の2以下)。
「極度額」とは、保証人が負う責任の上限額のことです。
個人根保証契約の場合は、この極度額を、書面で定めなければ、契約自体が無効とな
ってしまいます(保証会社のような法人であれば大丈夫です)。
この書面は、公正証書である必要はなく、契約書で足ります。
つまり、改正後は、賃貸借契約において賃借人の親族などの個人に根保証を求める場
合には、契約書の中で極度額を定めておかなければならないということになります。
この極度額は、一定の金額を定めておく方法や、賃料の2か月分といった定めであっ
ても、賃料の額が特定されていて上限額を確定できるのであれば有効です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年3月 8日 木曜日
平成30年3月8日第453号
1.働き方改革
「働き方改革」という言葉を聞かない日がないほどニュースなどで見聞きするようになりました。政府によれば、「働き方改革こそが、労働生産性を改善させるための最良の手段である。」としています(平成29年3月28日付、働き方改革実行計画より)。労働生産性を向上させることによって、企業は収益力を向上させ、労働者はその収益の分配を受けることにより所得の拡大、ワークライフバランスの実現ができ、日本の経済成長が達成される好循環が期待されているのです。
2.労働生産性の国際比較
日本は、国際的に労働生産性が低いと言われますが、では労働生産性とはどのようなものなのでしょうか。
労働生産性は、一般に就業者1人当たり、あるいは就業1時間当たりの成果(GDP)で比較されます。労働生産性=GDP/就業者数(または就業者数×労働時間)
公益財団法人日本生産性本部の発表によると、平成28年の日本の就業者1人当たりの労働生産性はOECD加盟35ヵ国中21位で米国の概ね2/3程度の水準です。詳しくみると、上位の国には法人税を下げることで多国籍企業の本社機能を自国に移転させた結果GDPを押し上げている例もあり、外国の労働者が日本の労働者よりも効率的に働いているとは一概に言えない部分はありますが、このまま何も手を打たなくてもよいとは決して言えないでしょう。
3.今後の課題
労働生産性を向上させるためには、上の式からわかるように分母のGDPを上げるか分子を小さくすることしかありません。日本のGDPは最近20年ほとんど拡大していませんから、まず分子を小さくする方策として政府が労働時間法制の改革に着手しているというのは理解できます。
しかしながら、前述の発表では分母を小さくするための業務効率化はある程度までいくと改善が難しくなると指摘しています。労働力を小さくしながら今までと同様の成果を生み出して生産性を上げ続けようとしても限度があるからです。そうだとすれば、今後は分子拡大のためのイノベーションがやはり必要となってくるでしょう。
これを企業単位でみると、効率的な労働時間制度の導入や無駄を削減するための業務改善は必要ですが、それよりも新しい製品やサービスを生み出しやすい人事制度や企業風土の醸成にもっと注力すべきではないでしょうか。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年2月23日 金曜日
平成30年2月23日第452号
1.特別加入制度創設の背景
昭和22年に労働基準法とともに、制定された労災保険法は労基法第75条以下の災害補償と同一内容・同一水準の補償内容を規定し、労災保険から給付が行われるべき場合、使用者の災害補償責任は原則免責されることから、労基法と労災保険法は、姉妹法であるともいわれていました。しかし、昭和30年代中頃より、労災保険法は数次の改正によって、しだいに労基法から乖離するとともにその独自性を強めるようになり、人的適用範囲の拡大として、昭和40年特別加入制度の創設、昭和51年海外派遣者の特別加入制度が導入されました。
2.特別加入制度とは?
労災保険は「労働者」を一人でも使用している事業には、その業種・規模に関係なく強制適用されます(任意適用事業を除く)が、特別加入制度は、いわゆる労基法で保護の対象としない「労働者以外の者」を保護の対象とする制度で、次のような方が特別加入者となります
(1)中小事業主などの特別加入
金融業、保険業、不動産業、小売業で常時従業員50人以下、卸売業、サービス業で常時従業員100人以下、その他の業種にあっては常時従業員300人以下の事業主が加入できます。また、家族従事者や法人の代表者以外の役員等も包括加入できます。ただし、「労働保険事務組合」に事務を委託していることが条件です。
(2)一人親方などの特別加入
一人親方とは建設業の事業主のイメージですが、他に個人タクシ―業者など職業ドライバー、自営農作業者(加入対象事業場、加入対象作業などの加入要件があります)、労働組合などの一人専従者、家内労働者などが加入できます。ただし、都道府県労働局長の承認を受けた「特別加入団体」を通じて加入ができます。
(3)海外派遣者の特別加入
国内の事業場から、国外の事業場へ「派遣」される労働者が対象となります。
3.まとめ
事業主、法人代表だから、労災は加入できないとお考えの方、特別加入制度に加入すると労働者とほぼ同内容の労災補償が受けられます。ただし、一人親方などには、一部通勤災害が適用されない業種がありますが、一度検討されては如何でしょうか。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年2月 8日 木曜日
平成30年2月8日第451号
教育訓練給付が手厚くなります。政府は労働力の質的向上を図り、一億総活躍社会の実現を掲げています。労働者の中長期的なキャリアアップを、より一層支援するため、教育訓練給付の受講機会の拡大、専門実践教育訓練給付金の拡充及び、教育訓練支援給付金の充実等の改正が行われ、平成30年1月1日から施行されています。
受講延長措置の改正
妊娠、出産、育児等により引き続き30日以上教育訓練を開始できない場合の受講開始期間の延長措置の期間が4年間から最長20年に延長されました。これは、一般被保険者及び、高年齢被保険者でなくなった日から1年(受講開始の延長措置を受ける場合は最長20年)以内にある人又は、教育訓練を開始した日に一般被保険者、高年齢被保険者である人に適用されます。
専門実践教育訓給付金の拡充
(1)支給要件期間の緩和
専門実践教育訓練を受け、終了した場合(終了とみなされる場合を含む)に支給されますが、この支給要件期間が雇用保険の被保険者だった期間が10年以上から、3年以上(初回の2年以上は変更なし。)に緩和されました。
(2)給付水準の引き上げ
受講中の給付率が受講費用(入学料及び受講料)の40%から50%に、上限額が合計96万円から120万円,年間上限額は、32万円から40万円に引き上げられました。
資格取得等をし、受講終了日の翌日から1年以内に一般被保険者又は、高年齢被保険者として雇用された場合は、さらに、追加支給として20%、上限48万円が支給されます。追加支給と合わせると、給付率は70%、上限額は168万円、年間56万円となります。
教育訓練支援給付金の充実
教育訓練給付を受けている人が失業している場合に支給されます。ただし、一般被保険者の資格喪失後1年以内に専門実践教育を開始し、45歳未満でありかつ、初めて教育訓練給付金の支給をうける等の要件をすべて満たすことが必要ですが、支給額が基本手当日額の50%から80%に引き上げられました。
教育訓練給付金は、労働者の能力向上に役立つばかりでなく、事業所にとっても業務拡大に有効です。ただし、受給するには細部要件の確認が必要ですので、専門家に相談してください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年1月23日 火曜日
平成30年1月23日第450号
登記簿謄本で記載されているときがある『買戻特約』とは、どのようなものでしょう?
1.買戻特約とは?
買戻特約とは、売主が売買代金と契約にかかった費用を買主に返して、一旦、売却した不動産を買い戻すことです。買戻権は売買契約と同時に特約の形で行います。
2.買戻しの要件
(1)目的物は不動産に限定されます。
(2)買戻しの特約は売買契約と同時にしなければなりません。
(3)買戻代金は売買代金と契約費用を超えることが出来ません。
(4)買戻しの期間は10年を超えることが出来ません。
(ア)10年を超えるときは10年とします。
(イ)期間を定めたときは、その後にこれを伸長することが出来ません。
(ウ)期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければなりません。
3.買戻しの効力
(1)買戻特約を第三者に対抗するためには、売買による登記と同時にその特約を登記
しなければなりません。
(2)買主から不動産を貸借して登記をした者については、その残存期間中、1年を超
えない期間に限って、売主に対抗することが出来ます。
(3)買戻権の譲渡
(ア)登記された買戻権は、買戻権移転の登記をすれば、買主への通知は不要です。
(イ)登記されていない買戻権は、買主に対抗するには債権譲渡の方法によります。
4.買戻しが利用されるケース
(1)公的機関(市町村や住宅供給公社など)が宅地分譲するときに、一定期間転売を禁止したり、利用目的を限定したりすることがあり、これらを守らなければ買い戻すという特約をつけることがあります。
(2)買戻特約付売買という形で、買戻し期間までに売買代金を返済すれば、不動産を買い戻すことが出来るようにするという手法で、融資の担保として利用されることがありますが、債権者からすれば、売買代金と契約費用だけで買い戻されては、あまりメリットがないので、利用は限られているようです。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年1月 8日 月曜日
平成30年1月8日第449号
昨今、マスコミ等で「大人の発達障害」について
取り上げられることが増えてきました。
全国の発達障害者支援センターに
寄せられる発達障害に関する相談は
平成17年度が
12,826件であったのに対し、
平成28年度は63,172件と
約4.9倍に増加しています。
同センターには児童や生徒の養育等に
関する相談も持ち込まれますが、
着目すべきは就労支援に関する相談が
この間に24.7倍に増えている点であり、
就業や就業継続に困難を感じるいわゆる
「大人の発達障害」が増えている証拠と言えます。
発達障害の代表例の主な特徴
1.自閉症、アスペルガー症候群を
含む広汎性発達障害(自閉症スペクトラム)
・相手の表情や態度などよりも、
文字や図形、物の方に関心が強い。
・見通しの立たない状況では不安が強いが、
見通しが立つ時はきっちりしている。
・大勢の人がいる所や気温の変化などの
感覚刺激への敏感さで苦労しているが、
それが芸術的な才能につながることもある。
2.学習障害(限局性学習障害)
・「話す」「理解」は普通にできるのに、
「読む」「書く」「計算する」ことが、
努力しているのに極端に苦手。
3.注意欠陥多動性障害(注意欠如・多動性障害)
・次々と周囲のものに関心を持ち、
周囲のペースよりもエネルギッシュに
様々なことに取り組むことが多い。
4.その他の発達障害
・体の動かし方の不器用さ、
我慢していても声が出たり
体が動いてしまったりするチック、
一般的に吃音と言われるような話し方なども、
発達障害に含まれる。
発達障害は、職務や作業について
抽象的な指示が理解できなかったり、
一度に複数のことを指示されると
混乱するなど、職務課題はあります。
これらの特徴を把握し、本人が自分の特性に
一定の理解を持つことを促し、
本人を良く知る専門家や家族に
サポートのコツを聞くことなどが、
就労を受け入れる側に不可欠な配慮です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年12月23日 土曜日
平成29年12月23日第448号
医療費が高額になった場合には、
健康保険の高額療養費制度を使うと
自己負担限度額を
超えた分が戻ってきます。
でも一旦は請求の全額を
病院へ支払う必要があります。
これは被保険者にとって負担が
大きく高額になるほど大変です。
保険者から還付されるのも
3~4ヵ月も先になります。
そこで、
「限度額適用認定証」を事前に
取得し病院へ提示することで、
病院窓口での支払いである
療養費が高額になっても
自己負担限度額で
済むことができます。
今回は、
高額療養費制度と
限度額適用認定証について
簡単に説明します。
1.高額療養費制度
高額療養費とは、
同月内に同一病院
(入院と通院は別さらに歯科と歯科以外は別)で
支払った医療費
(差額ベッド代や食事代、保険外負担分を除く)が、
自己負担限度額を超えた場合に
申請することで払い戻しされる制度です。
あるいは、
同一世帯内で上記条件で支払った医療費が、
自己負担限度額を超えていなくても
21,000円以上であれば、
世帯内で合算し自己負担限度額を
超えた差額が申請することで
払い戻しになります。
さらに、
70歳上の方の場合には、
21,000円以上という
制限が無くなります。
自己負担限度額は、
被保険者が70歳未満の場合は
所得状況により5段階に、
70歳以上は3段階に分かれます。
(但し、75歳以上は後期高齢医療制度が適
用されますので当制度は適用されません。)
また、療養を受けた月以前12ヵ月以内に、
同一世帯で高額療養費の支給を
3回以上受けた場合は、
多数該当となり
自己負担限度額がさらに
低くなることがあります。
2.限度額適用認定証
入院・手術等で医療費が
高額となることが事前に分かっていれば、
70歳未満の場合、
申請書を保険者へ提出し
「限度額適用認定証」を発行してもらって
病院へ提示することで、
どんなに高額な療養費となっても、
病院への支払いは自己負担限度額以内となります。
70歳以上の場合は、
「限度額適用認定証」の代わりに
「高齢受給者証」を提示することで
同様の扱いとなります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年12月 8日 金曜日
平成29年12月8日第447号
1. 事業承継5ヵ年計画
中小企業庁では、
今後5年程度を事業承継支援の集中実施期間とし、
支援体制、支援施策を抜本的に強化する、
としています。
その施策は主に5つです。
(1)事業承継プレ支援の
プラットフォームの構築・・・
5年間で25~30万社を対象に
プッシュ型の事業承継診断を実施
(2)早期承継の
インセンティブの強化・・・
後継者による新機軸・業界転換等の
経営革新を支援・事業計画作成支援等
(3)小規模M&Aマーケットの形成・・・
事業引継ぎ支援センターの強化等
(4)サプライチェーン・地域における
事業統合等の支援・・・
中小企業の事業再編・統合・共同化を
促進する制度的枠組みの検討等
(5)経営スキルの高い人材を
事業承継支援へ活用・・・
経営人材の後継者不在企業への
参画を促進するための
人材紹介会社と
事業引継ぎ支援センターとの連携等
2.プラットフォーム構築事業
事業承継ネットワークを
2年かけて全国に展開し、
事業承継診断を
実施しようとしています。
地域の将来に責任を有する都道府県の
リーダーシップのもと、
地域に密着した支援機関
(よろず支援拠点・事業引継ぎ支援センター・
金融機関・商工会議所・商工会・各士業等)を
ネットワーク化し、途切れのない
事業承継支援が出来るように取り組んでいます。
実際に、各都道府県でネットワーク
構築事業が進んできており、
勉強会の開催、地域
の専門家リストの作成がされてきております。
3.この2年は掘り起こしの年
まずは、事業承継の必要性に経営者が
「気づく」ことが大切とされ、
今年、来年の2年間は、
支援機関側から中小企業を訪れて
事業承継診断をしていただき(プッシュ型支援)、
その必要性に気づいて戴くことに力を入れています。
中小企業の経営者に普段接触のある
士業等の支援者の方、また、
中小企業の経営者の方には、
是非意識して戴けたらと思います。
事業承継ガイドライン(平成28年12月公表)では、
60歳を事業承継の着手時期と考えています。
事業承継の促進のため,必要な費用に関する
補助金は来年以降も継続されそうです。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年11月23日 木曜日
平成29年11月23日第446号
1.問 題
契約書の中で、
「〇ヵ月間」という表記で期間を定めるとき、
例えば4月30日から3ヵ月間という場合、
契約の期間満了日はいつになるのでしょうか。
契約書を作成する上で普段あまり
意識していないかもしれませんが、
場合によっては契約違反に
問われかねない非常に重要な問題です。
では、
(1)7月29日
(2)7月30日
(3)7月31日
のどれが正解でしょうか。
2.法律の根拠
以下の条文が法律上の根拠となりますが、
これを使って考えてみましょう。
民法第140条(期間の起算)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、
期間の初日は、算入しない。
ただし、
その期間が午前零時から始まるときは、
この限りでない。
民法第143条(暦による期間の計算)
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、
その期間は暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから
期間を起算しないときは、
その期間は、最後の週、月又は年において
その起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、
月又は年によって
期間を定めた場合において、
最後の月に応当する日がないときは、
その月の末日に満了する。
3.解 答
まず起算日を考えます。
民法第140条の初日不算入の原則から、
5月1日が起算日となりそうですが、
通常契約書は事前に作成されるため、
4月30日の午前零時から
カウントすることが可能で、
同条但書により4月30日が起算日となります。
次に期間満了日です。
その応答(「対応」くらいの意)する日(7月30日)の
前日である7月29日が
3ヵ月の契約期間満了日となり、
正解は(1)です。
しかし、
4月30日に契約を結び、
その日から3ヵ月の契約とした場合、
午前零時から始まらないので、
初日不算入の原則により起算日が5月1日となり、
応答する日(8月1日)の前日である
7月31日が期間満了日となります。
さらに、
2月のように最後の月に応答する日が
ない場合には月末を満了する
(民法第143条2項但書)
ことや
月末が日曜日や国民の祝日等にあたるときで
取引をしない商慣習がある場合には
その翌日に満了する(民法第142条)ことがあり、
考えてみると意外に
難しいことがわかると思います。
この機会に契約書を見直して
みてはいかがでしょうか。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年11月 8日 水曜日
平成29年11月8日第445号
1.近年の傾向
「LGBT」という言葉をご存じですか?
同性愛者のレズビアン(L)やゲイ(G)、
両性愛者のバイセクシャル(B)
心と体の性が一致しないトランスジェンダー(T)
の頭文字をとった総称です。
近年は国際人権法などの議論で
「SOGI」(ソジ)という呼称が使われ始めました。
日本では、「パートナーシップ証明」や
「パートナーシップ宣誓」、
「パートナーシップ登録」といった言葉が
ニュースにしばしば登場するようになりました。
2015年11月、同性カップルなどの
当事者の二人がパートナーであることを示す
パートナーシップ証明を渋谷区が発行するサービスを
開始したことは記憶に新しいと思います。
他に世田谷区、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、
沖縄県那覇市、北海道札幌市などの
自治体も証明を発行しています。
2.雇用におけるハラスメント対策
1985年に制定された男女雇用機会均等法は、
2007年の改正には女性に対する
セクシュアル・ハラスメントだけでなく
男性に対するセクシュアル・ハラスメントも
対象としました。
2016年に改正された厚生労働省
「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に
関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」
においては、
「職場におけるセクシュアル・ハラスメントには、
同性に対するものも含まれる。
また被害を受けた者の性的志向又は性自認に関わらず、
当該者に対する職場における
セクシュアル・ハラスメントも、
本指針の対象となるものである。」
ということが明言されています。
したがって、
事業主が性的言動によって
就業環境が害されることのないよう
講ずべき措置には性的少数者に
対するものも含まれると解されます。
3.企業対応
取り組みとしては、性的指向や自認を事由とする
解雇・いじめ、自認する性別の服装での出勤の可否、
社員旅行、トイレ利用等への相談窓口の設置、
福利厚生の見直し等、が考えられます。
また、取り組まないと、人格権侵害としての
損害賠償義務やその使用者責任、
また職場環境配慮義務違反という法的リスクや、
当事者、非当事者の生産性やモチベーションの低下、
職場への忠誠心の減少という悪影響をもたらします。
従業員に気持ちよく働いて、
職場で能力を十分に発揮してもらえるよう、
是非とも管理職や労務担当者だけでなく、
社員にもきっちりとした正しい
基礎知識を学ぶ機会を設けましょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年10月23日 月曜日
平成29年10月23日第444号
10月1日から7日まで
厚生労働省等の主催で全国衛生週間が設けられ、
「働き方改革で見直そう みんなが輝く 健康職場」をテーマに
安全衛生に関する行事が全国で開催されました。
安全な労働環境を作ることが
企業の発展には不可欠ですが、
勤務中に災害が発生した場合は
労災保険にて治療することになります。
労災保険の様式は
種類別に用意されていますが、
不完全に記入されると給付が
遅れますので注意が必要です。
労災保険の留意点
(1)
「療養補償給付たる療養の給付請求書」
の記入について
(ア)
労災保険で治療を受ける際に
病院経由で所轄の労働基準監督署へ
提出する書類です。
業務起因性と事業主の支配下にある
業務遂行性の2要件が求められます。
治療費、入院料、移送費等通常の
療養のために必要なものが対象ですが、
負傷者の判断で薬局で購入した
包帯や湿布薬は対象外です。
(イ)
様式の上部にある労働保険番号は
必ず記入します。
治療中に事業所の労働保険番号が
変更になった場合でも、
受傷時の番号を記入します。
氏名の下の職種の欄は
具体的に記入します。
例えば、
「薬品製造業の製品検査員」等
分かりやすく記入しましょう。
(ウ)
災害発生状況欄は、場所、作業内容、
作業状態と事故発生の因果関係を
具体的に記入します。
既往症が有る場合や、
従前からの負傷は対象外ですが、
審査で認められれば、
業務が原因で悪化した部分は
労災保険の対象になります。
しかし、左足を負傷し、
それをかばう行為で右足が
負傷した場合の右足は、
業務との因果関係がないため、
対象とされません。
(エ)
事業主の証明欄は、発生した災害が
業務による災害であると事業主が認めて社
印を押印する欄です。
(オ)
最下段の療養の給付を請求する、
住所、氏名の記入欄は労働者が記入します。
署名のみでなく必ず押印してください。
(カ)
派遣労働者の場合は、
事業主欄は派遣元であり、
派遣先の事業主は裏面
の証明欄に押印します。
(キ)
裏面にある削除・加筆の捨印欄は、
記入上に訂正した本人の印を使いますので、
事業主印、本人印等です。
(2)
労災保険に使用する各様式は、
厚生労働省のホームページから
ダウンロードできます。
事業所にあらかじめ揃えておくことをお勧めします。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年10月 8日 日曜日
平成29年10月8日第443号
『法定相続情報証明制度』について
5月29日から、
相続手続を簡素化する
『法定相続情報証明制度』が始まりました。
1. 制度の概要
(1)相続人が登記所に対し、
次の書類を始めとする必要書類を提出する。
(ア)被相続人が生まれてから
亡くなるまでの戸籍関係の書類等
(イ)上記の書類等の記載に基づく
法定相続情報一覧図
(被相続人の氏名・最後の住所・生年月日
及び死亡年月日並びに相続人の氏名、
生年月日、及び続柄/登記に
利用するものとは様式や内容が異なる。)
(2)登記官が内容を確認して、
認証文付きの法定相続情報の
一覧図の写しを交付する。
2. 手続の流れ
(1)申出(法定相続人又は代理人)
(ア)戸籍謄本・除籍謄本等を収集する。
(イ)法定相続情報一覧図を作成する。
※放棄や遺産分割協議は対象外とする。
※数次相続の場合は、1人の被相続人ごとに作成する。
(2)確認・交付(登記所)
(ア)登記官による確認と
法定相続情報一覧図を保管する。
(イ)認証文付き法定相続情報一覧図の
写しの交付を受ける。
3. その他
(1)不動産がない場合でも利用可能。
必要な範囲で複数通数発行可能。
(2)代理人となることが出来るのは、
法定代理人のほか、民法上の親族と資格者代理人。
(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・
税理士・社会保険労務士・弁理士などに限る。)
(3)登記所の管轄は次の通り。
郵送による申出も可能。
(登記官の交付手数料は無料。)
(ア)被相続人の本籍地
(イ)被相続人の最後の住所地
(ウ)申出人の住所地
(エ)被相続人名義の不動産の所在地
(4)5年間は再交付可能。
但し、当初の申出人に限る。
(5)被相続人や相続人が日本国籍を
有しないなど戸籍謄抄本がない場合は利用不可。
(6)死後認知や、制度利用後に
廃除があった場合等は再度、申出が出来る。
(7)登記申請と同時でない場合は、
出生からの証明が必要。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年9月23日 土曜日
平成29年9月23日第442号
平成29年1月1日に施行されました
育児・介護休業法がさらに改正され、
10月1日から施行されます。
以下改正のポイントをご紹介いたします。
1.保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得可能に
育児休業期間は、原則として子が1歳に達するまで、
保育所に入れない等の場合に、
例外的に子が1歳6ヵ月に達するまで延長できましたが、
子が1歳6ヵ月に達する時点で、
次のいずれにも該当する場合には、
子が1歳6ヵ月に達する日の翌日から
子が2歳に達する日までの期間について、
事業主に申し出ることにより、
育児休業をすることができるようになります。
(1)育児休業にかかる子が
1歳6ヵ月に達する日において、
労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
(2)保育所に入所できない等、
1歳6ヵ月を超えても休業が特に認められる場合
この2歳までの休業は、
1歳6ヵ月到達時点でさらに
休業が必要な場合に限って申出可能となり、
原則として子が1歳6ヵ月に達する日の翌日が
育児休業開始予定日となります。
1歳時点での延長は子が1歳6ヵ月に達する日までです。
ご注意ください。
育児休業給付金の給付期間も延長した場合は、
2歳までとなります。
2.子どもが生まれる予定の方などに
育児休業等の制度などをお知らせ
事業主は、労働者もしくはその配偶者が
妊娠・出産したことを知ったとき、
又は労働者が対象家族を
介護していることを知ったときに、
関連する両立支援制度について
個別に制度を周知するための措置を
講ずるよう努力しなければなりません。
この措置は、
労働者のプラバイシーを保護する観点から、
労働者が自発的に知らせることを
前提としたものである必要があります。
そのためには、
労働者が自発的に知らせやすい職場環境が重要であり、
相談窓口を設置する等の育児休業等に関する
ハラスメントの防止措置を事業主が講じている必要があります。
3.育児目的休暇の導入促進
事業主は、小学校就学までの子を
育てながら働く方が子育てしやすいよう、
育児に関する目的で利用できる休暇制度を
設ける努力義務が創設されます。
「育児に関する目的で利用できる休暇制度」とは、
配偶者出産休暇や、入園式、卒園式などの
行事参加も含めた育児にも利用できる
多目的休暇などが考えられますが、
失効年次有給休暇の積立による
休暇制度の一環として
「育児に関する目的で利用できる休暇」を
措置することも含まれます。
各企業の実情に応じた整備が望まれます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年9月 8日 金曜日
平成29年9月8日第441号
昨年、厚生労働省は、
約20年後の2035年頃を見据えて多様な働き方に向け、
有識者による懇談会を開催し、
「働き方の未来2035~一人ひとりが輝くために~」と
題した報告書をとりまとめました。
今回はその報告書の提言内容を簡略に紹介します。
1.技術革新は、大きなチャンスをもたらす
AI等の技術革新により働く場所や時間の制約を無くし、
充実感のある働き方を求め、
障害があってもすべての人が、
より自由で自律的である働き方を可能とします。
2.チャンスを生かすには、新しい労働政策の構築が不可欠
企業の変容スピードが速くなり
機動的に変化せざるを得なくなっています。
働くという活動に対して民法(民事ルール)も
根本に立ち返っての検討が必要です。
3.働き方の変化に伴うこれからのコミュニティのあり方
コミュニティにおいてもその担い手が
企業から居住地域へと変遷し、
働く人の意識も会社から職種へと変化します。
また、
SNSやAI、VRなどの技術革新も多様な働き方を
支援できるように進化していくことが求められます。
4.人材が動く社会と再挑戦可能な日本型セーフティネット
個人が望むより良い働き方ができるようにするための
セーフティネットを日本の実態に合わせて
充実させていくことが必要です。
人材が企業間を動いていくことを積極的に捉える視点と、
やり直しや再挑戦を可能とする仕組みを
政府は整えていく必要から、
職業教育や訓練を充実していくべきです。
5.働く人が適切な働き場所を選択できるための情報開示の仕組み
働き方の選択にあたっては、
必要な情報が比較可能な形で提供されるための
枠組みづくりが求められます。
企業は「どんな働き方を求めるか」を正確に提示し、
働く人が簡単にそれを入手し、
比較検討可能な情報プラットホームを
整備することが重要です。
6.これからの働き方と税と社会保障の一体改革
働き方に関する変化と多様性をできるだけ妨げないような、
税と社会保障のあり方を考えていく必要があります。
例えば、
男女が共に働くことが一般的となっていくことを考えると、
世帯主が配偶者を扶養することを
前提とした家族を単位とする社会保障制度を、
個人単位に置き換えることも重要になるでしょう。
7.早急に着実な実行を
こうした変化が、
働くすべての人に恩恵をもたらすためには、
新しい労働政策を考え、
構築していく必要があります。
しかし、
法律や制度の変更には、
かなりの時間を要することを考えると、
早急かつ着実に労働政策のあり方を
検討していく必要があります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年8月23日 水曜日
平成29年8月23日第440号
「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」
(以下、「障害者虐待防止法」という)
をご存知でしょうか。
障害者虐待防止法ができた背景には、
障害者のもつ特性に対する周囲の理解不足や、
本人の成長を願ってちょっとした
「注意」や「指導」が、
「暴言」や「無視」に発展したり、
心理的虐待や身体的虐待などにつながったりする
可能性があるという点があります。
1.虐待の定義(障害者虐待防止法第2条第8項第1号から5号)
(1)身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、
もしくは生じるおそれのある暴行を加え、
または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
(2)性的虐待
障害者にわいせつな行為をすることまたは
障害者をしてわいせつな行為をさせること
(3)心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な
対応または不当な差別的言動その他の障害者に
著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(4)放置等による虐待
障害者を衰弱させるような著しい減食または
長時間の放置、当該事業所に使用される他の
労働者による上記3つの虐待行為と同様の
行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと
(5)経済的虐待
障害者の財産を不当に処分すること
その他障害者から不当に財産上の利益を得ること
2.障害者虐待への対応の留意点
虐待をしている人、虐待を受ける人に
自覚があるとは限りません。
当事務所の顧問先様においても、
障害者と認識していない従業員から
市町村に障害者虐待があった旨を
通報したということがありました。
労働条件について苦情申入れをしてきた
従業員の方が激高されたので、
その方の顔の前に手を出して阻止しようとした、
現場主任の方の行為を指してのことです。
会社側は、その従業員の方が障害を
お持ちであったことも知らないし、
気づいてもいませんでした。
思いがけないことも起こりますからご注意ください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年8月 8日 火曜日
平成29年8月8日第439号
1.改正の概要
平成29年3月31日に
「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、
同日公布されました。
今回は、その中の職業安定法について
解説したいと思います。
内容は、ニュースなどで話題となっていた
「ブラック求人問題」に対処するものが
主になっています。
法律は成立しましたが、
まだ施行されていない内容ですので
施行前に是非知っておいていただきたいと思います。
2.職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化
(1)求人不受理
公共職業安定所及び職業紹介事業者は
求人の申し込みはすべて受理しなければならず、
例外は一部にすぎませんでした。
今回は、
求人を不受理とすることができる範囲を拡大し、
一定の労働関係法令違反の求人者による
求人及び暴力団員による求人のすべてを
受理しないことができるとされました。
(2)虚偽求人申し込みへの罰則の強化
虚偽の条件を提示して、
公共職業安定所又は職業紹介事業者に
求人の申し込みを行った場合、
6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の
罰金に処せられます。
申し込みをしただけで罰則の対象に
なることに注意が必要です。
(3)求人サイト、求人情報誌等への指導監督
職業安定所や職業紹介事業者を通じて
労働者を募集する場合に限らず、
求人サイト運営事業者や自社のサイトで
求人募集をする場合も指導監督が及ぶことになります。
これまで、
職業安定所に苦情が寄せられていた
民間の求人情報について対処することが
可能となりました。
(4)労働契約締結前の労働条件等の明示
事前に労働条件を明示しておきながら、
労働契約を結ぶ際に以前明示したものと変更がある場合は、
きちんとそのことを相手に伝えることが義務付けられました。
3.募集内容の見直し
2の(1)については公布から3年以内の施行、
(2)~(4)については
平成30年1月1日施行となっています。
今回の改正内容は、
職業安定所が労働市場の
需給調整機能重視から
監督規制強化へと舵を切ったと
みることができます。
求職者の目を引く求人情報とするあまり、
募集内容と実際の条件が異なっていて
法令違反に問われることのないよう
一度見直してみる必要がありそうです。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年7月23日 日曜日
平成29年7月23日第438号
1.これまでの経緯
低年金者の増加や、納付意欲低迷等の議論の中、
平成24年8月に、年金受給資格の「10年」への
短縮の法案が成立しました。
平成27年10月の消費税率引き上げと同時に
行うことになっていたところ大幅に延期され、
その後、平成28年11月「年金機能強化法改正法」が
可決・成立されました。
これにより期間短縮に係る施行期日が
平成29年8月1日となり、
平成29年9月分の年金から支給(支払いは10月)
されるようになります。
10年への短縮で、
老齢基礎年金の受給権者が約40万人、
特別支給の老齢厚生年金の受給権者は約24万人と、
合わせて64万人の方が
受給権を得ることができると言われていて、
日本年金機構は今年2月末から
7月にかけて対象者に年金請求書を送付しています。
2.受給資格者とは
では、実際に対象者となるとは、どういうことでしょうか。
まず、
ア)国民年金保険料送付済期間、
イ)国民年金保険料免除期間、
ウ)被用者年金加入記録
をあわせて10年から25年未満の方です。
また、前記のア)~ウ)の期間が10年ない場合、
合算対象機関(いわゆる「カラ期間。」
を探す必要がありますが、
なんとか120ヵ月分以上を確保したいところです。
なお、この合算対象期間は多岐にわたるため、
専門の社会保険労務士や、年金事務所、
「街角の年金センター」等に相談されるとよいでしょう。
3.後納や任意加入も活用しましょう
国民年金の毎月の保険料の納付期限は翌月末日ですが、
2年前まで遡って納付することができます。
さらに、平成27年10月から
平成30年9月までの3年間に限り、
過去5年分まで遡って
納めることができる後納制度があります。
また、年金受給期間10年を満たしていない方は
手続きを行うことによって最長70歳まで
国民年金に任意加入することができます。
振替加算や寡婦年金の対象に
なるかもしれないことについての
確認もしたいところです。
ただし、
10年加入の年金を受給していた人が
死亡した場合でも、
その遺族に遺族年金は支給されません。
あくまで今回の制度改正は、
老齢基礎年金などの老齢年金であり、
遺族年金、障害年金の受給要件に変更はありません。
企業の従業員の方から、質問があった場合、
適宜相談にのれるよう準備できればよいでしょうし、
また身近な専門家を活用してみては如何でしょうか。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年7月 8日 土曜日
平成29年7月8日第437号
1.1億総活躍社会の実現と労災保険特別加入
平成29年度、
1億総活躍社会の実現に向け、
政府は中小企業事業主の
労災保険加入を促進するとともに、
安全な作業環境の整備と公平な
競争を確保するため、
建築作業の一人親方の特別加入の
促進を掲げています。
労災保険は、
事業主に使用される労働者に対して
補償を行う制度ですから、
自営業者は補償の対象とはなりません。
しかし中小企業事業や個人事業主、
建築の一人親方等は、
勤務の実態が一般の労働者と大差なく、
労災保険法で保護すること必要がある場合があり、
これらの人々に労災保険への加入を
認めるのが特別加入制度です。
2.労災保険特別加入制度の種類と適用関係
労災保険は、
一般の労働者が対象となる部分と
特別加入部分とは補償内容の異なる部分があり、
保険制度の適用や実務処理も異なります。
(1)中小企業事業主の特別加入(第1種特別加入者)
常時300人、卸売サービス業は100人、
金融・不動産・小売業は50人以下の
労働者を使用する事業主であり、
労働者に係る保険関係が成立しており、
労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託する者です。
労働者を1人でも雇用する場合は対象となりますが、
年間を通じ延べ100日以上になることが必要です。
請負による建築事業の下請けを行う事業主の場合、
自らの直営工事は徴収法第7条の「有期一括」の
保険関係を成立させておき、
その関係に基づき事務組合に委託します。
これにより、元請工事の中に従事する場合と同じく、
自らの請負工事でも労働者と同様の
業務についても補償されるのです。
ただし、事業主としての業務は対象外です。
(2)一人親方等及び特定作業従事者(第2種特別加入者)
一人親方とは、
(ア)個人タクシー
(イ)建築業
(ウ)漁船
(エ)林業
(オ)医薬品配置
(カ)再生資源取扱業
(キ)船員の事業
などです。
いずれもアルバイト等を雇用する場合は、
延べ年間100日未満である必要があります。
製造業の一人社長は一人親方とはなりません。
特定作業従事者等とは、
(ア)比較的大規模の農業や大型機械を使用する農業
(イ)家内労働とその補助者で、プレス機を使用する作業等の従事者
(ウ)労働組合の常勤役員
(エ)家事使用人としての介護者等が該当しますが、
ボランティアは含まれません。
(3)海外派遣者(第3種特別加入者)
日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から
派遣されて海外支店等の事業に従事する労働者です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年6月23日 金曜日
平成29年6月23日第436号
日本に不動産を所有する海外居住の
外国人または外国企業が、
その不動産を売却する場合や、
海外で居住する日本人が、
その不動産を売却する場合の
不動産登記に必要な書類や、
その他の留意点についてまとめてみました。
1.海外居住の外国人または海外在住日本人が
日本の不動産を売却する際の登記の書類
(1)権利証書は、通常の不動産取引と
同じように必要となります。
(2)印鑑証明書は(印影を証明するということを
制度としている国や地域は限られていますので)
「サイン証明書」によることになりますが、
次の2通りの方法があります。
(ア)署名すべき書類に対して
サイン証明書を綴り合わせて割印をし、
一体の書類としたものに対して、
証明権者が奥書証明するもの(奥書証明方式)
(イ)申請者のサインを、単独で証明するもの
(単独証明方式)
(3)登記用委任状について、
奥書証明方式の場合は一体化していますが、
単独証明方式の場合は、
全く同一のサインであると登記官が認める必要があります。
(4)法人の場合、資格証明書が必要になりますが、
実務上では[宣誓供述書]を利用して
手続を進める方法が多く採用されています。
(5)固定資産評価証明書も、
通常の取引と同じように必要になります。
(6)外国人が登記名義人のときの住所や
氏名が変更されているときは、
その内容や原因を記載した「宣誓供述書」を
利用することになります。
2.サイン証明書について
(1)外国人の場合の証明書
(ア)当該外国の在日大使館・領事館における証明権者
(イ)当該外国の本国の公証人や弁護士等
(2)日本人の場合の証明書
(ア)在外日本大使館・領事館における証明権者
(イ)日本の公証人
3.買主の源泉徴収義務について
(1)源泉徴収義務は買主にありますが、
個人が自己または親族の居住用に取得した土地等で、
その対価が1億円以下の場合は、
源泉徴収義務が生じません。
(ア)買主が法人の場合、対価の額に関わらず、
源泉徴収義務が生じます。
(イ)買主が個人の場合でも居住用でない場合は、
源泉徴収義務が生じます。
(2)手付金や中間金でも、それぞれの支払時に
源泉徴収する義務があります。
(3)源泉徴収の税率は、
源泉所得税及び復興特別所得税の合計で
10.21%です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年6月 8日 木曜日
平成29年6月8日第435号
傷病等の治療のために労災保険から
給付を受けるべきところ、
健康保険から給付を受けてしまうことあります。
その際の調整規定が変更されました。
1.労災保険と健康保険の間で直接調整を行うことが可能に
労災保険から給付を受けるべきケガや病気で
健康保険から給付を受けた場合は、
従来、健康保険から労災保険に切替えの際、
従業員が健康保険から受けていた給付を
健保組合等に全額返還してから、
改めて労働基準監督署に対して
労災保険申請を行う必要がありました。
給付額が高額の場合は
従業員にとって大きな負担となっていました。
これに対し厚生労働省が発した
2017年2月の通達によると、
従業員が労働基準監督署に申し出ることで、
労災保険の支払先として健保組合等を
指定することを可能とし、
労働基準監督署から健保組合等に対して
直接支払いを行うことで、
労災保険から健康保険への切替えを
行うことができるようになりました。
2.新しい取扱いによる切替え手順
(1)被保険者が、労働基準監督署に、
いったん全額を自己負担することなく
労災保険を請求したい旨の申出を行い、
健保組合等から労働基準監督署に
レセプト等を提出することの同意書を提出
(2)労働基準監督署と健保組合等の調整
(3)被保険者が、支払先を健保組合等とした
「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を作成し、
健保組合等から送付された返還通知書と
労災保険給付の受領を健保組合等に
委任する旨の委任状を添付し労働基準監督署へ提出
(4)提出された請求書に基づき、
労災保険から被保険者と、健保組合等へ給付
3.従来の取扱いによる手続きは今後も可能
新しい取扱いが可能となりましたが、
今後も、いったん健保組合等に
費用の全額を返還したあとで労災保険から
給付を受ける従来の手続きも可能です。
新しい取扱いは、従業員の金銭的負担が大きく
軽減された一方、以下の理由から、
従来の取扱いよりも手続きが煩雑になったといえます。
・労災申請を行う前にあらかじめ労働基準監督署
への申出を行わなければならない。
・同意書や委任状を作成して提出する必要がある。
・健康保険から給付を受けている7割部分自己負担の
3割部分でそれぞれ労災保険請求書を作成しなければならない。
そのため、健康保険から受けた給付の金額が少額のときは、
従来の取扱いに基づいて労災保険への
切替えを行ったほうが都合がよい場合もあります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年5月23日 火曜日
平成29年5月23日第434号
平成18年度から運用を開始した電子申請ですが、
これまで思うように浸透していません。
そこで少しでも皆さんに知ってもらおうと、
今回は電子申請の簡単な紹介をさせていただきます。
1.電子申請とは
e-Gov電子申請システムとは、
様々な行政への申請・届出を
インターネットを使って行うものです。
電子申請を行う際には、事前準備として
電子証明書の取得が必要となります。
2.メリット
(1)これまで行政機関へ申請・届出の際は書類を
持ち込んだり郵送したりしていましたが、
電子申請は会社や自宅のパソコンから
24時間いつでも行うことができます。
(2)行政機関の窓口が閉まっている夜間でも
休日でも申請が可能です。
(3)年金事務所やハローワークへと
異なる場所へ提出しなければいけない場合でも、
パソコンの前に座ったまま
幾つもの行政機関へ提出することができます。
申請書を作る手間も簡易な機能があり、
更に作った書類の内容をチェックする機能も
付いていて精度の高い申請・届出になります。
(4)提出した後も審査過程の進捗を
確認することができます。
審査が終われば、メールで知らされ、
e-Govサイトから返戻資料を
取り出すことができます。
従来の紙ベースでの返戻資料を
希望される申請者へは、
郵送で送り返してくれます。
(5)申請後の手続書類はすべて
データ化されるのでペーパーレス化が促進されます。
(6)マイナンバーの漏洩のリスクヘッジができます。
3.デメリット
(1)e-Gov電子申請対応のソフトがないと
一括申請に対応できず、ひとつひとつ会社データや
添付ファイルを入力しないといけない点は手間がかかります。
(2)添付書類をPDFやJPEGなどの
電子ファイルをいちいち添付する必要があります。
以上、システム上の手間はありますが、
業務の効率は向上しますので是非ご活用ください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年5月 8日 月曜日
平成29年5月8日第433号
1.これから10年間が勝負
平成28年4月に
中小企業財務課が作成した資料によると、
以下の通りの記載があります。
・65歳以上の経営者が約4割を占め、
今後5年以内に、
いわゆる団塊世代を含む多くの経営者が
事業承継のタイミングを迎えるものと考えられる。
・一方、事業承継に向けた準備を行っている会社は
4割程度にとどまり、
経営者が60歳以上の会社のうち、
後継者が決まっている会社も4割に満たない。
・このような状況を踏まえ
~中略~
中小企業経営者、支援機関及び
行政機関の認識・取組の方向性を
共有することにより、
今後5~10年間の
事業承継支援策の強化に繋げる。
このようなことから、
今後10年間で約半数の経営者が
引退期にさしかかるため、
国としては、
事業承継問題を避けて通れない、
と考えています。
2.事業承継ガイドライン改訂の方向性
まずは、これまでの取り組みについて、
事業承継を取り巻く状況の
客観的な整理・分析を行う、
としています。
そして、見直すべき点を洗い出し、
(1)事業承継に向けた取組の重要性を
経営者が再認識すること、
(2)早期取組の重要性とその周知を徹底すること、
(3)支援体制の整理・改善を図ること、
(4)事業承継には事業価値の向上が
極めて重要であること等に
分類・整理して進めていく方向のようです。
3.事業承継の取り組みの重要性
弁護士として倒産案件に関わる中で、
実際に事業承継がうまくいかなかったことを
倒産の理由として挙げている企業もありました。
中小企業は日本の企業数の99%以上を占め、
地域経済・社会を支える存在として
日本の経済活動の基盤となっています。
各地方の中小企業が存続することで、
地域が賑わい、地域で働く場所も
確保されると思います。
公的機関で事業承継問題にも
関わらせて戴いているので、
「事業承継」が円滑にできなかった、
という理由での「廃業」を
出来るだけ防げるよう、
事業承継の取り組みの重要性など、
これからもお伝えしていきたいと思います。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年4月23日 日曜日
平成29年4月23日第432号
1.改正労働者派遣法
派遣労働者というとどんなイメージがありますか。
「非正規労働者」、「弱い立場」、「代替要員」、
「派遣切り」などネガティブなイメージが
先行しているのではないでしょうか。
実際にも「労働者の使い捨て」との批判を浴び、
平成27年9月30日に改正派遣法が施行されました。
そこでは、派遣労働者のスキルアップや
雇用の安定を図ることなど
派遣労働者の保護に重点が置かれ、
派遣業界を取り巻く環境が
以前と大きく変わることとなりました。
2.派遣労働者活用のメリット
最近、報道では人手不足が
深刻になったといわれています。
厚生労働省の発表によると、
2016年の平均の有効求人倍率は
1.36倍と7年連続で上昇、
1991年以来25年ぶりの高水準となっています。
新規求人倍率も2.04倍となっており、
人手不足の傾向は当分続きそうです。
このような環境の中で人材を確保するのに
多額の費用と時間がかかってしまい、
中小企業にとっては優秀な人材を
採用することは容易ではありません。
そこで、人手が足りない期間のみ、
必要なスキルを有している派遣労働者に
仕事を任せることは合理的だと言えます。
また、直接派遣労働者に指揮命令を
することができる点で業務委託の
場合と異なり、よりきめ細かな仕事を
してもらうことができます。
さらに、
その人材が優秀であれば
直接自社で雇用することで
組織力を上げることも可能となります。
他方、
優秀な人材を直接雇用するために
派遣労働者を受け入れる
「紹介予定派遣」という方法もあります。
6ヵ月以内の派遣契約の中で
それ以降直接雇用するかどうかを
判断することができます。
初めから正社員雇用をした場合の
解雇のリスクを回避することができますし、
ミスマッチによる離職を防ぐことが
できることからも検討に値する制度だと思います。
3.助成金の活用
派遣労働者を直接雇用する場合には、
厚生労働省の助成金を活用して
人材確保を容易にする方法があります。
「キャリアアップ助成金」では、
派遣労働者を正社員雇用することで、
通常よりも助成金額が多くなっています。
これまで採用に悩んでいた方は
一度検討してみてはいかがでしょうか。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年4月 8日 土曜日
平成29年4月8日第431号
1.制度概要
本助成金は、
労働時間等の設定の改善を図り、
過重労働の防止及び長時間労働の
抑制に向け勤務間インターバル
(休息時間数を問わず、
就業規則等において
終業から次の始業までの休息時間を確保
することを定めているもの)
の導入に取り組んだ際、
その実施に要した費用の一部を助成するものです。
2.支給要件
(1)支給対象事業主
次のアからウのいずれかに該当する
事業場を有する中小企業事業主であること
ア.勤務間インターバルを導入していない事業場
イ.すでに休息時間数が9時間以上の
勤務間インターバルを導入している
事業場であって対象となる労働者が
当該事業場に所属する労働者の
半数以下である事業場
ウ.すでに休息時間数が9時間未満の
勤務間インターバルを導入している事業場
※その他、「資本又は出資額」や
「常時雇用する労働者」
に関する要件があります。
3.成果目標と支給対象となる取組み
次の取組みのうち、
いずれか1つ以上を実施し、
成果目標として、
事業主が事業実施計画において
指定したすべての事業場において、
休息時間数が
「9時間以上11時間未満」または
「11時間以上」の勤務間インターバル
を導入すること
(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修
(3)外部専門家
(社会保険労務士、中小企業診断士など)
によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(時間外・休日労働に関する規定の整備等)
(5)労務管理ソフトウェアや
労務管理用機器の導入・更新 等
4.支給額
取組みの実施に要した経費のうち、
謝金、旅費、借損料、会議費、
雑役務費、印刷製本費、備品費、
機械装置等購入費及び委託費の
合計額に4分の3を乗じた額が
成果目標の達成状況に応じて支給されます。
・休息時間数9時間以上11時間未満:
上限40万円
・休息時間数11時間以上:
上限50万円
※申請受付:平成29年12月15日まで
※「新規導入」に該当する取組みがなく、
「適用範囲の拡大」または「時間延長」に
該当する取組みがある場合は
上記助成額の半額が支給されます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年3月23日 木曜日
平成29年3月23日第430号
1.退職金制度は見える化されていますか?
実は、会社にとって退職金制度の設置義務はありません。
しかし、就業規則等で会社が社員との間で
退職金の支払いをルール化すれば、
会社にとっては社員と契約した制度になるため、
支払いの責任が生じます。
では、何が問題かというと、
先代の決めた制度が未だに残っているケースです。
景気が良い時代に、急ごしらえで作った制度、
なんとなく同業者の社長から聞いて、
こんなもんだろと決めた制度であったならば、
この際制度改革に着手すべきです。
退職一時金制度の場合は、
支払い義務が生じてから減免を求めることもできず、
定年退職者、中途退職者が予想以上に多かった期は、
赤字転落などという事態は
絶対に避けなければなりません。
2.退職金・企業年金の4つの類型
退職給付制度はたくさんの制度や法律がありますが、
大きく4つの種類に分けて
整理すると理解しやすいです。
一つ目は「退職一時金制度」。
実際の支払いの段階で全額を損金算入出来ますが、
事前準備金に対しては税制上の
メリットはありません。
かつ、
退職給付会計
(実際積立額-将来支払う退職給付支払額=退職給付債務)が
適用され、会社にとって債務とされます。
これは二つ目の「確定給付企業年金」
にも言えることです。
ただ、この「確定給付企業年金」は
事業主掛金は全額損金算入できます。
これは三つ目の「共済型」
(たとえば中小企業退職金共済制度)も同じ。
また、四つ目の「確定拠出年金」も
事業主掛金は全額損金算入されます。
勿論税金面だけでなく、運用責任はだれが負うのか、
自己都合退職時に減額できるのか、
中途退職時に一時金支給が出来るのか、
年金支給開始年齢は何歳からか等、
金融機関からの制度提案を受けたり、
中退共本部への相談等により
退職金制度を固める必要がありますが、
何より、
従業員の方の納得を得られ、
会社への貢献や仕事へのインセンティブを
高めてもらうことが一番大事なことではないでしょうか。
3.労使交渉の開始
新制度の採用については基本的に
既得権の保障と期待権他についての
労使合意が必要になります。
社員説明会を行い、きちんとした情報公開と、
制度の目的と方針の説明、
旧制度との不公平感、
世代間の不公平感等に配慮し、
出来れば全従業員から同意書を
取り付けておくのが無難です。
社会保険労務士等の外部専門家を上手に使い、
客観的視点からの解説を加えるのも
有効ではないでしょうか?
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年3月 8日 水曜日
平成29年3月8日第429号
米国の大統領選挙後から、
今後の経済動向に関心が集まり、
各種の経済指標が話題になっています。
景気ウォッチャー、日銀短観等、
様々に解説されていますが、
それぞれの指標には特徴が有ります。
その特徴を踏まえ参考にすると、
これらの調査を興味深く見ることができます。
「経済指標」は、
景気に先行して動く指標が先行系列、
一致して動く指標が一致系列、
遅れて動く指標が遅行系列
と分類されています。
1.景気ウォッチャー調査
家計動向、企業動向雇用等各分野の動向を
観察できる業種(タクシー運転手等)から選定され、
その協力を得て地域ごとの景気動向判断の
基礎資料とすることを目的としています。
調査主体は内閣府であり、
全国ではなく地域ごとの先行きの
5段階評価の判断に点数を与え、
調査は、2・3ヵ月先の身の回りの
景気動向を質問するもので景気の先行きは
2・3ヵ月先を指したものです。
毎月末の調査結果は
原則翌月の第6営業日に発表されます。
2.日銀短観
全国企業短期経済観測調査です。
調査は、約1万社の企業を対象に、
3,6,9,12月に実施され、
速報性に重点が置かれています。
調査時点の判断と、3ヵ月先の判断を
調査するもので経営者の近い将来の
動向をどうみているかを知ることができます。
短観の中でも注目されているのが
「業況判断DI」です。
これは、「良い」と答えた企業から
「悪い」と答えた企業を減じたもので、
数値の変動を観察することが大切な指標です。
景気の天井が落ちた時、
景気の底を打ったときの
見極めに活用されています。
3.経済・物価情勢の展望(展望レポート)
日銀が担当しており、
毎年4・10月に公表されます。
政策委員会・金融政策決定会合で決定され、
実質成長率・国内企業物価・消費者物価の上昇見通し、
不安要因の分析等を行い公表します。
4.家計調査
総務省が担当し、全国で9千世帯を対象に、
家計収入・支出、貯蓄・負債等を
毎月調査し公表されます。
消費動向が判断でき、又、
過去1年間の収入・貯蓄・負債の状況等が調査され、
実額と共に名目増減率が公表されるので
物価変動を考慮した消費増減の動向も判断できます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年2月23日 木曜日
平成29年2月23日第428号
自筆証書遺言は、
筆記用具と紙と印鑑があれば
作成することができるため、
普通方式の遺言の中では
最も簡単に作成することができる遺言と
されています。
1.自筆証書遺言とは
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、
これに押印することによって成立する
遺言のことをいいます(民法第968条第1項)。
2.自筆証書遺言の長所と短所
(1)長所
・遺言の内容や存在の秘密性を保持できます。
・証人の立ち会いが不要です。
・作成費用が不要です。
(2)短所
・字の書けない人は利用できません。
・要件を備えないと無効になるおそれがあります。
・偽造・変造・紛失・隠匿・不発見のおそれがあります。
・家庭裁判所による検認の手続が必要になります。
3.自筆証書遺言の作成のポイント
(1)遺言者が全文を自書すること
(2)作成日付の記載、氏名の自書、押印があること
(3)加除訂正があるときは所定の方式に従っていること
4.家庭裁判所による検認手続
(1)遺言書の保管者や遺言書を発見した
相続人は相続の開始を知った後、
遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して
検認の請求が必要です。
(民法第1004条第1項)
なお、検認の申立書には
『申立人・相続人全員の戸籍謄本』及び
『遺言者の戸籍謄本
(全相続人を把握するため8才頃から死亡まで)』
を添付することを要します。
(2)検認手続を経ない自筆証書遺言に基づく
相続登記申請は受理されず、却下されます。
(平成7年12月4日民三第4344号民事局第三課長通知)
金融機関においても同様の取り扱いが
なされる場合がほとんどです。
(3)検認の性質は、後日における
偽造・変造・毀損を防ぐ一種の
検証手続・証拠保全手続とされており、
遺言の内容の真否を審査し、
その効力の有無を確定するものでは
ありませんので、後に遺言の効力を
争うことは可能です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年2月 8日 水曜日
平成29年2月8日第427号
平成29年1月1日以降の離職者から、
特定受給資格者の範囲が見直されました。
1.特定受給資格者とは
特定受給資格者とは、倒産や解雇等の理由で退職した
雇用保険加入者だった者のことであり、
この場合、労働者が再就職の準備をする時間的余裕もなく、
離職を余儀なくされたことから、失業給付の取扱いが
自己都合退職よりも有利な扱いになります。
また、失業給付受給に必要な雇用保険加入期間については、
通常は離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して
12ヵ月以上必要ですが、特定受給資格者の場合は、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して
6ヵ月以上ある場合でも可能となっています。
以下、今回から拡大された特定受給資格者の内容をご紹介します。
2.妊娠、出産、介護等を理由とする不利益な取扱いによる退職
(1)育児介護休業法の規定に基づき、
育児休業、介護休業、看護休暇、介護休暇の申出をしたが、
正当な理由なく拒まれたため、休業開始予定日までに
休業または休暇を取得できなかった場合
(2)妊娠・出産をしたこと、産前休業を請求し、
または産前産後休業をしたこと、並びに育児休業、
介護休業、看護休暇、介護休暇の申出または
取得したことを理由とする不利益な取扱いを受けた場合
(3)事業主が、育児・介護休業法、労働基準法、
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保等に関する法律の労働者保護法令に違反し、
または措置されなかった場合
3.賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった場合
(1)現実にその月(賃金月)中に
支払われた額(何月分であるかを問わない。)が
その者が本来その月(賃金月)中に支払を
受けるべき額の3分の2に満たない月が1ヵ月以上あった場合
(2)毎月決まって支払われるべき賃金の
全額が所定の賃金支払日より遅れて
支払われたという事実が1回以上あった場合
上記いずれかに離職した場合は特定受給資格者に該当します。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年1月23日 月曜日
平成29年1月23日第426号
去年12月20日に
「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」の
中間報告として
「同一労働同一賃金ガイドライン案」が公表された。
雇用における正規・非正規間の格差問題是正に
大きな期待が寄せられる。
中間報告の内容を見る限り、
実現には多くの問題が横たわっている。
諸外国と比較をしても、各国ごとの歴史の上に
成り立って構築されてきた労働市場の構造には、
同一労働同一賃金の実現のさせ方に大きな違いが
あるとのことである。
日本においては、
諸外国と比べ労働者の流動性が低く、
それ故か企業ごとに労働条件が定められることが多く、
欧州のように産業別労働協約により
同一労働同一賃金が保たれていない。
そうした状況を踏まえて検討会では、
下記3点を柱にして長期的に
改革を進めるとのことである。
(1)正規・非正規社員両方の
賃金決定ルール・基準の明確化、
(2)職務や能力等の賃金など
待遇水準との関係性の明確化
(3)能力開発機会の均等・均衡による
一人ひとりの生産性向上
また、ガイドラインでは、具体的な事例として
「問題とならない例」
「問題となる例」
を載せているので、その一例を掲載する。
基本給について、労働者の
職業経験・能力に応じて支給しようとする場合
(1)問題とならない例
基本給については社員の職業経験・能力に
応じて支給しているA社において、
ある職業能力の向上のための特殊な
キャリアコースを設定している。
正規社員であるXは、このキャリコースを選択し、
その結果としてその職業能力を習得した。
これに対し、非正規社員であるYは、
その職業能力を習得していない。A社は、
その職業能力に応じた支給をXには行い、
Yには行っていない。
(2)問題となる例
基本給について社員の職業経験・能力に応じて
支給しているE社において、
正規社員であるXが非正規社員であるYに比べ
多くの職業経験を有することを理由として、
Xに対して、Yよりも多額の支給をしているが、
Xのこれまでの職業経験はXの現在の業務に
関連性を持たない。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年1月 8日 日曜日
平成29年1月8日第425号
1.懲戒処分ができる場合(総論)
懲戒処分が有効となるのは、
(1)就業規則に根拠があり、
(2)その懲戒事由に該当し、
(3)懲戒処分が社会通念上相当なものである場合です。
就業規則を作成する際、懲戒事由毎に処分を定めていることが一般的です。
それでは、具体的類型毎に、どのような点に着目し、
どのような処分を下せば「相当」と言えるのでしょうか?
相当性の判断は、一般論として、
(1)行為の内容、
(2)結果の重大性、
(3)頻度や期間、
(4)業務内容、
(5)過去の処分歴、
(6)反省の有無などを総合して判断されるべきものといえます。
以下、具体的な2つの類型を見ていきましょう。
2.経歴詐称
経歴は、採用のためのみではなく、
採用後に基本的資料となるものです。
そのため、偽ったことが判明した場合には、
たとえ採用後の勤務に非難すべき点が
なかったとしても労働契約上の信義則違反として
懲戒事由となり得ます。
判例は「重要な経歴」を詐称した場合に限り、
懲戒処分としての相当性を認める傾向です。
重要な経歴とは、例えば、最終学歴・職歴、犯罪歴
(但し、賞罰歴における罰とは一般的には
確定した有罪判決をいいます。)
がこれに当たります。
(最判平成3年9月19日...炭研精工事件)
3.勤務懈怠
無断欠勤、出勤不良といった勤務懈怠は、
それ自体は単に労務提供という労働者側の
債務不履行であり(損害賠償請求できるかどうかの問題)、
それが職務規律に違反したり、企業秩序を乱したと
認められる場合に、初めて懲戒事由となるものといえます。
よって、欠勤の頻度や継続性、その理由、企業の注意・指導の
有無やそれに対する労働者の対応、業務に与えた影響、
従来の取扱いを考慮して、懲戒処分の有効性を
判断する傾向にあります。
勤務懈怠について企業が注意・指導をしない場合には、
これを許していたと判断されてしまう可能性も
あるので指導書のような形で、「書面」にて、
勤怠不良について改善をするよう
注意・指導しておく必要があるでしょう。
「指導書」には、欠勤の頻度・これによって、
どのように業務に支障があったのか、など、
できるだけ具体的な記載があることが望ましいです。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年12月23日 金曜日
平成28年12月23日第424号
1.満65歳以上の新規雇用者の加入義務
現在、満65歳以降に新たに職業に就いた労働者は、雇用保険の加入者になる
ことはできませんでしたが、雇用保険の適用上限年齢が撤廃され、平成29年1
月1日以降満65歳以上で加入要件(週20時間以上かつ、31日以上の雇用見
込みの方)に該当する人を雇い入れる場合、雇用保険被保険者資格取得届の提
出が必要になります。また、施行日前にすでに満65歳以上の方(加入要件該当
者)は、施行日付で加入手続きが発生する可能性があります。この場合の届出期
日は特例で平成29年3月31日までとなります。ただし、この期日に遅れても
時効にならない限り加入手続きは可能です。平成28年12月末日時点で高年齢
継続被保険者である場合は、既に資格取得手続きは行われているので、届出は
不要です。なお、現在の高年齢継続被保険者とあわせ、65歳以上の被保険者
名称は「高年齢被保険者」となります。また、現在4月1日時点で満64歳以
上の雇用保険料は、現在保険料免除になっていますが、新たに被保険者となる
65歳以上の人も、平成31年3月31日までは保険料は免除になります。あ
わせて、高年齢被保険者には、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給
付金の支給対象となり、離職後、高年齢受給資格者となった場合、常用就職支
度手当、移転費、求職活動支援費も支給対象になります。
2.適用拡大の背景
厚生労働省「雇用保険部会報告」では、我が国の生産年齢人口は、既に減少局面
にあり、潜在的に人手不足のなか、65歳以上の新規求職者数、就職件数の増加、
また65歳を超える就労希望者の増加や、老後の収入に対する不安等があるとい
う背景の中、改正をした旨の報告をしています。
3.課題
(1)離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月必要という一般被保険者
に比べ、「6ヶ月」で高年齢求職者給付金の対象となり、計画的に離職と就職を
繰り返す循環的離職者となり、不正受給につながる認識が必要です。
(2)平成32年4月1日からは、現在保険料が免除されている人に加え、すべ
ての被保険者分、事業主分共に保険料が徴収され、会社の人員構成によれば、
新たなコスト増になります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年12月 8日 木曜日
平成28年12月8日第423号
確定拠出年金法が本年6月に改正され、個人型確定拠出年金の対象が広がり、
来年1月からは公務員や主婦も対象になります。特徴は自己責任で運用するこ
と、転職後の持運びが可能なことです。法改正された個人型を中心に確認しま
しょう。
1.確定拠出年金の特徴
(1)いわゆる3階建て部分の年金。法改正に基き、平成29年から原則誰で
も加入可能
(2)自らの責任で運用し、運用結果に応じた年金額を将来に受け取れる。
(3)税制優遇のメリットは有るが、手数料が必要であり、原則60歳まで受
取り不可能
2.確定拠出年金の概要
(1)種類
企業型と個人型があり、企業型は厚生年金適用事業所の事業主が実施者と
なり、加入者は実施事業所に使用される被用者年金被保険者で、掛金拠出は事
業主だが加入者も可能。一方、個人型は国民年金基金が実施者となり、加入者
は原則誰でも可能となり、掛金は加入者が拠出する。
(2)運営者と記録管理者
ア 掛金運営者は、運営管理機関と呼ばれ、みずほ・三井住友・ゆうちょ
銀行等
イ 記録管理は、記録関連運営管理機関と呼ばれ、加入者への各種通知等
を行う。
(3)給付
老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3種類で、老齢給付は掛金10年以上
で60歳から受取可能、1ヵ月以上2年未満の加入期間では65歳から受取可
能となる。ただし、70歳までに自身で申請手続きが必要で、手続きしなかっ
た場合は一時金となる。
(4)掛金額と変更について
個人型は、国民年金の第1号被保険者と60歳未満の厚生年金被保険者で、掛
金は前者が毎年6万8千円、後者は2万3千円までが拠出限度額となり、全額
が所得控除の対象となる。掛金額は毎年4月から翌年3月の間で年1回変更で
き、個人が運用商品を選択する。
(5)実施方法と注意点
運用商品は株や債券の投資信託が中心、運用商品の変更は可能。施行は公布日
の平成28年6月3日から2年以内で、公布日から2年以内に、加入者に提示
する3以上の運用方法について「内1つ以上は元本確保」という制限はなくな
る。個人型は運営管理機関から必要書類を取寄せ、受付金融機関へ申し込むこ
とから始まる。加入には手数料と口座管理料、投資信託の場合は信託報酬が必
要。途中換金は原則不可能で、60歳以降に老齢年金として受取りとなる。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年11月23日 水曜日
平成28年11月23日第422号
法務省は7月5日、相続手続を簡素化する「法定相続情報証明制度(仮称)を来年
度に新設する。」と発表しました。一体、どのような制度なのでしょう?
1.新設の目的
法務省の発表によりますと「相続登記が未了のまま放置されることは、いわゆる所
有者不明の土地問題や空き家問題を生じさせる大きな要因の一つであるとされてい
ます。(中略)そこで、法務省民事局では相続登記を促進するための新たな制度と
して当該制度を新設することとしました。」と、されています。
2.現状と問題点
(1)相続人は、遺産に係る相続手続に際し、登記所や金融機関に対して、被相続
人が生まれてから亡くなるまでの戸籍及び相続人全員の戸籍等の関係書類等一式を
揃えて、同じ書類を管轄の異なる登記所や各金融機関にそれぞれ提出しなければな
らず、煩雑で手間がかかっています。
(2)金融機関等においては、そもそも戸籍関係書類等一式を読み解いて相続人を
特定することや、書類が足りない場合に追加書類の提出を相続人に求めることなど
に多くの手間がかかっており、しかもこれらは1人の被相続人に対して複数の金融
機関等で重複して行われているため、膨大な社会的コストが発生しています。
3.新制度のあらまし
(1)相続人が登記所に対し、次の書類を提出します。
(ア)被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係書類等
(イ)上記(ア)の記載に基づく法定相続情報(被相続人の氏名・本籍・住所・生
年月日・死亡年月日と相続人の氏名・本籍・住所・生年月日・続柄・法定相続分)
を記した関係図である申請書
(2)登記官が(1)の内容を確認し、証明文付きの法定相続情報の写しを交付し
ます。
(3)相続財産たる不動産に管轄登記所が異なるものがある場合、上記の写しを添
付すれば相続登記の申請が可能となります。
(4)被相続人名義の預金の払い戻し等、他の相続手続に使うことも可能とします。
4.今後の見通し
法務省の発表によれば「年内にパブリックコメント(意見公募)を実施して、詳細
を決めたうえ、来年5月の開始を目指す」ということです。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年11月 8日 火曜日
平成28年11月8日第421号
ハマキョウレックス事件は、一般貨物自動車運送事業Y社に勤務する契約社員
(配送ドライバー)のXが、XとY社との間には、期間の定めのない労働契約が
成立している、また、仮に成立していないとしても、正社員と契約社員たるXと
の労働条件を比較すると、不合理な相違があると主張した事案です。
1.争点
1)Xに期間の定めがない労働契約が成立しているか
第1審、控訴審においては、採用の面接時、Xに対して半年、あるいは1年
後には正社員に登用する可能性があることを示唆した事実が認定されましたが、
入社時の契約書にはその旨の合意はなく、XのY社の正社員としての労働契約の
合意の事実を否定しました。
2)労働契約法第20条(以下、「労契法」という)についての考え方
ⅰ)第1審の判断
正社員と契約社員の業務自体に大きな相違は認められないが、正社員は、業務の
必要性に応じて業務内容や就業場所の変更命令を甘受しなければならず、管理責
任者等のY社の中核を担う人材として登用される可能性がある一方、契約社員は、
業務内容、労働時間、休憩時間、休日等の労働条件の変更がありうるにとどまり、
管理責任者等Y社の中核を担う人材として登用される可能性がある者として育成
されるべき立場にあるとは言えないとして、労契法第20条違反とは判断しませ
んでした。
ⅱ)控訴審の判断
有期労働契約と無期労働契約との間の労働条件が単に相違するとういうだけで、
労契法第20条の適用があるものではなく、両者の労働条件の違いが「期間の定
めの有無に関連して生じたものであることを要する趣旨である」としました。
労契法第20条に照らして不合理と認められるかどうかは、
(1)「労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」、
(2)「当該職務の内容及び配置の変更の範囲」と
(3)「その他の事情」を考慮要素として、「個々の労働条件ごとに判断される
べきものであると解される」として、1つひとつの労働条件ごとに、労働条件の
相違と言えるかどうかを検討するとの考え方を示しました。
2.不合理性の判断
上記(1)~(3)は、一定の「要件」としてではなく、判断する「要素」と
して位置付けられており、これらに照らして総合的に判断するという手法をとっ
ており、「同一」か否かまで厳正な判断はしておらず、弾力的な判断ができる
ようにしています。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年10月23日 日曜日
平成28年10月23日420号
来年4月から、年金の受給資格期間が短縮され、これまで25年間の被保険者期
間が必要でしたが、無年金者を少なくする目的から10年で受給資格を得られる
ことになる予定です。
65歳以上の無年金者は現在90万人いると推計されます。国民年金に未加入の
人、加入していても保険料が払えずに免除されている人が、将来無年金者や低年
金者となる可能性が高いのです。今の推計では800万を超えると言われていま
す。
こうした制度を諸外国ではどうかと見ると
国名 年金支給開始年齢 受給資格期間
アメリカ 66歳 10年相当
イギリス 男65歳、女62歳5ヵ月 なし
ドイツ 65歳3ヵ月 5年
フランス 61歳2ヵ月 なし
他国と比べ日本の年金受給資格期間が随分長いことが分かります。これでは国民
皆年金制度そのものが崩れてしまいかねません。高齢化社会に向かって公的年金
を安定的に運用していくために、平成26年4月に施行された年金機能強化法の
下、以降これまで幾つもの施策が実施されてきました。
1.基礎年金の国庫負担を1/3から1/2に恒久化(平成26年4月施行)
2.産休期間中の社会保険料免除
3.遺族基礎年金を父子家庭へも支給
4.未支給年金を受け取る遺族の範囲を拡大
5.70歳に年金繰り下げた人が請求を遅れた場合でも、遡って年金の支給が可
能
6.国民年金の任意加入時の未納期間が受給資格期間に算入
7.所在不明の年金受給者について届出が必要
8.障害年金の額改訂請求が1年を待たずに請求可能
9.特別支給の老齢厚生年金の受給権を得たときに遡って障害者特例による支給
が可能
10.短時間労働者に対する社会保険の適用拡大(平成28年10月施行)
11.受給資格期間の短縮(平成29年4月施行予定)
これ以外にも、時効で納めることができなかった国民年金の未納保険料が平成
27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納める
ことができます。被保険者期間が不足して年金を受給できない人が受給資格を
得られる可能性が出てきます。
こうした施策の財源に、消費税を10%とする必要性が問われています。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年10月 8日 土曜日
平成28年10月8日419号
平成29年1月1日施行にて、育児・介護休業法の一部制度の改定があります。
併せて、男女雇用機会均等法にハラスメント防止措置(育児・介護休業法含む)
が追加されます。今回は、追加されるハラスメント防止措置について触れます。
男女雇用機会均等法第11条には、セクハラ防止対策義務規定が従前からあり
ます。今回新たに、第11条の2に「職場における妊娠、出産等に関する言動に
起因する問題に関する雇用管理上の措置」が定められ、同様に、育児・介護休業
法第25条に「職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇
用管理上の措置」が定められました(ハラスメント防止措置)。何れも、措置義
務で事業主は措置を講じる必要があります。
厚生労働省によると、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生
原因の背景には、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動(他の労働者
の妊娠、出産等の否定につながる言動や制度等の利用の否定につながる言動。
単なる自らの意思の表明を除き、本人に直接言わない言動を含む。)が頻繁に
行われるなど制度等の利用又は制度等の利用の請求等をしにくい職場風土があ
り、また、制度等の利用ができることの周知が不十分であること、等が挙げら
れています。
これらを解消していくことが、防止効果を高めるうえで重要であることを
留意し「講じなければならない措置」として挙げている措置内容は次のとお
りです。
1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備
3.職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントにかかる事後
の迅速かつ適切な対応
4.職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景
となる要因を解消するための措置
5.上記措置と併せて、プライバシー保護に対する必要な措置及び周知、不利
益取扱いを行わない定め及び周知
措置内容は、従前からあるセクハラ防止措置(1.2.3.5)とほぼ同じで
4の項目が新たに追加されました。全てのハラスメントの防止措置として一体
化することも可能です。指針の中では「その他のハラスメントの相談窓口と一
体的に相談窓口を設置し、相談も一元的に受け付ける体制が望ましい」として
います。ハラスメント行為者となるのは上司・同僚です。上司の場合1回の言
動でもハラスメントとなります。リスク対策のためにも措置を講じ対策を取る
必要があります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年9月23日 金曜日
平成28年9月23日418号
平成28年度の第二次補正予算案が8月下旬に閣議決定されました。
「最低賃金引上げの環境整備として、経営力強化・生産性向上に向けて、
中小企業・小規模事業者への支援措置を推進・拡充する」という国の方針
を踏まえ、予算案には業務改善助成金及びキャリアアップ助成金等につ
いて助成額等の拡充が盛り込まれています。
業務改善助成金及びキャリアアップ助成金の拡充内容(概要)は次の
とおりです。
1.業務改善助成金
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための
設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内
で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた場合に、
その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。
これまでは事業場内最低賃金が800円未満の事業場を対象としてい
たため、地域別最低賃金が800円以上の都道府県では利用できませ
んでした。今回の改正では、800円以上1,000円未満の事業場にも
対象が拡充されました。また、さらに大幅な事業場内最低賃金の引上
げ(90円以上)を行う事業場に対する助成措置が助成の上限額が増
額されたコースも新設されます。
なお、拡充後の本助成金の支給は、第二次補正予算の成立が条件と
なりますが、申請は予算成立前でも可能です。
2.キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定(処遇改善コース)」は、有期
契約労働者、短時間労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の
基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合に助成す
る制度です。
今回、中小企業が基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給
した場合、助成額が加算されることになりました。さらに申請があった
企業において、生産性の向上が認められる場合は加算額が増額さ
れます。
生産性の向上については、決算書類から算出した労働者1人当たり
の付加価値から判断されます。
なお、本助成金の加算措置は第二次補正予算の成立と厚生労働省
令の改正等が必要となるため、現時点ではあくまでも予定です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年9月 8日 木曜日
平成28年9月8日417号
1.原則は不利益変更には合意が必要
法律上、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、
労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」
ただし、「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、
A.変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、
B.就業規則の変更が、
(1)労働者の受ける不利益の程度、
(2)労働条件の変更の必要性、
(3)変更後の就業規則の内容の相当性、
(4)労働組合等との交渉の状況
(5)その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは」
変更が許されています(労働契約法第9条、第10条)。
つまり、A「周知」とB「合理性」をクリアした場合には、例外的に不利益変更の効
力が生じるとしているのです。
2.合理性が認められた事例
最高裁平成9年2月28日第二小法廷判決(第四銀行事件)では、実質的に
58歳定年制であったものを60歳に延長する措置に応じて、55歳以上の労働者
の賃金を引き下げることとした労働条件の不利益変更の合理性が認められました。
具体的には、
(1)就業規則変更による労働者の不利益は、従前の定年後在職制度の下で
得られると期待した金額を2年近くも長く働いてようやく得ることができるという
のであるから、不利益はかなり大きなもの、特に、高齢の行員にとっては相当
の不利益とみざるを得ないとする一方、
(2)定年延長の要請とこれに伴う55歳以上の賃金水準の見直しには高度の
必要性が認められること、
(3)変更後の55歳以上の労働者の労働条件内容は同業他社等ほぼ同様で
あり、賃金水準は社会一般の水準と比較してかなり高いこと、
(4)本件就業規則変更は、全行員の約90%(50歳以上の行員についても
約6割)で組織されている労働組合との交渉・合意を経て行われたものであ
るから変更後の就業規則の内容は労使間の利益調整がなされた結果とし
ての合理的なものであると一応推測できるといった事情から、「合理性」を
肯定しています。
3.合理性の基準
他方で、特定の高年層(55歳以上)の労働者に集中的に不利益になる
という変更後の労働条件の不相当性が重視され、「合理性」が認められなか
った事例もあります。就業規則の不利益変更は、使用者側の変更の「必要性」
の程度と、労働者側の受ける不利益の大きさに応じ、「相当性」があるか、
比較衡量して「合理性」を決めると言えます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年8月23日 火曜日
平成28年8月23日416号
1.事実確認及び証拠収集は正確に行う
注意・指導の際の前提条件。先入観、決めつけで指導を行わない。
2.指導のタイミングが適切か否か
指導・注意の対象行為と指導・注意までの期間が必要以上に長い場合には
効果は低い。また、そもそも指導・注意の必要がなかったのではないかと判断されることも。
3.指導場所は適切か
他の従業員の前での指導・注意はその者の部下がいないか、などの配慮が必要。
4.指導時間や時間帯は適切か
長時間にわたる注意・指導、遅い時間の注意・指導は避ける。
5.指導方法が適切か否か
(1)暴力行為は行わない。
(2)過度に大声は出さない。人格を否定する発言、名誉棄損、威圧的な発言も行
わない。
対象者の態度が悪くても冷静な対応が必要。対象者が録音をしていることも想定
しておく。
2名で行ったり、録音をしたりするのも対策の一つである。
(3)軽微なミスについて行き過ぎた注意・指導は行わない。嫌み、皮肉にも注意
する。
(4)メールでの指導は基本的に行わない。行うにしても他の従業員にCC等で送
らない。
長時間、起立させたままで、注意・指導を行わない。
(5)精神論のみで注意・指導は行わない。注意・指導は具体的に。
(6)特定の者に対して注意・指導を行うのではなく、同じミスをした他の従業員に
対しても平等に行う。
(7)対象者の様子、体調、健康状態への配慮を行う。特にメンタルヘルス不調者
への注意・指導には一層の配慮が必要。
6.指導後のフォローを行う
指導対象者であっても評価すべきところはしっかりと評価する。強い注意・指導を
行った場合は特にフォローを行う。指導後のフォローによりパワハラ問題の顕在化
リスクは低減する。
7.指導日時、指導場所、指導者、指導内容、本人の発言などを正確に記録する
正確、詳細な指導記録は今後の注意・指導につなげるために必要である。
特に別室において1対1で指導・注意を行うと、後に、言った言わないのトラブルに
なる可能性もある。特に厳しい指導の場合は2名で行うことや、場合によっては口
頭で録音することを告げて録音するといった対策も必要である。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年8月 8日 月曜日
平成28年8月8日第415号
1.「第三者行為」とは?
労災保険では事業主体を「保険者」といい、一方、給付を受ける者を「被保険者」
または「被災労働者」といいます。各々の保険制度では目的に照らして保険給付
を行いますが、その給付の原因が保険者、被保険者以外の不法行為であった
場合、加害者は損害賠償の義務を負います(民法第709条)。
この加害者のことを第三者といいます。たとえば、勤務中の鉄道駅職員を殴った
お客(加害者)等です。
2.届の提出の必要性
労災保険給付が第三者の行為が原因であった場合、給付を受けるべき受給権
者は、労災保険法施行規則第22条の規定によって第三者行為災害届を労働
基準監督署長に行わなければなりません。これは同法第12条の4に定める求償
あるいは控除の調整に必要な情報を報告させるためのもので、第12条の4は、
同一の災害原因で第三者から損害賠償が行われた場合の控除と、保険給付した
場合の求償を定めています。
3.届出書を作成するうえでの留意点
(1) 事業主等(労働者でない)で「特別加入」(制度)の承認を受けていない者が、
業務中の交通事故で相手のない自損事故で被災した場合は、第三者行為災害に
該当しませんが労災保険、健康保険共に適用を受けられないので注意を要します。
健康保険では事業主も被保険者になりますが、労災では事業主のため適用除外
です。健康保険は業務上の給付は対象外で、その結果健康保険、労災保険共に
給付から除外されることになります。ただし例外的に、被保険者が5人未満である
法人の代表者等で、一般の従業員と著しく異ならない労務に従事しているもの
が、業務に起因して負傷した場合、適用されることがあります。
(2) 業務上の災害で、同僚の運転する車両に同乗しているときの事故の場合、
相手方と同僚の運転者が第三者に該当し2人の共同不法行為に該当しますが、
この場合保険者(政府)は一方の第三者が同僚(事業主の支配下にある)である
ことから、法の趣旨に添いかねることにより、求償権の実行を差し控えることに
なります。
(3) 被災者が労災保険を適用して受診した場合でも、被災者が法律に定めら
れた給付制限の重過失に抵触する場合は、保険者から既に受けた給付額の返
還命令を受け、休業(補償)給付は給付の都度(制限期間なし)、障害(補償)給
付、傷害(補償)年金は療養開始後3年以内の給付につき、30%減額されます
ので注意が必要です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年7月25日 月曜日
平成28年7月25日第414号
我が国においては、国民皆保険制度によって国民は公的保険制度に加入し、
保険診療を一定限度の負担で受けることができます。また、保険適用が認め
られていない先進的医療については、安全性・有効性を確認した上で、
保険外併用診療制度として保険診療との併用が認められています。
今回は、保険外併用診療制度の中の次の制度をご案内します。
1.評価療養と選定療養
健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると保険が
適用される診療も含めて医療費の全額が自己負担になる。
ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める
「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認め
られており、保険外診療部分については全額自己負担だが、
通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の
費用は、一般の保険診療と同様に扱われる。
(1)評価療養:先進治療や医薬品等であり将来保険給付の
対象とするべきかの評価を行うものである。先進医療は
有効性・安全性が確認されれば保険適用となるが、
確認されなければ除外される。
(2)選定療養:差額ベッド代、時間外診療費や予約診療費等
2.患者申出療養
平成28年4月から、国内ではまだ承認されていない医薬品等の
使用等を迅速に使用できる仕組みとし、患者の治療の選択肢を
拡大するものとして導入されました。
患者が臨床中核病院(厚生労働省が承認した質の高い臨床
医療を行うことができる医療機関)に申し出ると、病院は
厚生労働大臣に申請を行い、同大臣は速やかにこれの
安全性・有効性を確認し、検討した上で承認・非承認を通知します。
承認されれば患者はその治療を受けることができます。
患者が申出を行うに当たっては、大臣告示に規定する申出書を
医療機関と相談しながら作成し、以下の書類と共に臨床中核
病院を経由して、厚生労働省保険局医療課に提出することが必要です。
(1)被保険者証写し
(2)臨床中核病院の意見書
(3)患者への説明時に用いた申出に関わる療養の内容及び費用にかかる
説明文書
(4)患者の同意書
(5)申出に係る相談を実施した場合の面談記録
(6)患者が申出に係る書類の確認を行ったことを証する書面
本制度により混合診療の範囲は広がるが、自由診療を推奨するものでは
ないこと、安全性が確認されない治療としての危険があることの理解は必要です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年7月 8日 金曜日
平成28年7月8日第413号
公正証書遺言とは、民法第969条及び第969条の2に基づき
公正証書による遺言のことをいいます。
平成17年に約70,000件でしたが、平成26年には
約105,000件になりました。
1.公正証書遺言の長所と短所
(1)長所
・自筆の必要がありません。
・原本を公証役場で保存するため、変造・隠匿・紛失・破棄の恐れがありません。
・家庭裁判所による検認手続が不要です。
(2)短所
・作成手続が煩雑で、費用がかかります。
・証人2名の立ち会いが必要になります。
2.公正証書遺言の作成方法
(1)証人2人以上の立会人を決めること
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
(3)公証人が口授を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧
させること
(4)遺言者と証人が、筆記が正確なことを承認の上、各自がこれに署名押印
すること
(5)公証人が適識な方式に従って作成した旨を付記してこれに署名押印
すること
※平成11年の民法改正で、聴覚・言語機能障害者に関する特則が設けられました。
3.公正証書遺言を作成する場所
原則として公証役場ですが、遺言者が外出困難な場合は公証人が出張して
くれます。
4.公正証書遺言の撤回・変更方法
(1)遺言の撤回・変更は、公正証書遺言はもとより、自筆証書遺言や秘密証書
遺言など、他の方式の遺言によっても可能です。
(2)遺言内容の変更において、遺言の前後で内容が異なる場合、その異なる
部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものと認められます。
5.公正証書等遺言登録検索システム
(1)東京の公証役場では昭和56年・他の全国の公証役場では平成元年以降に
作成された公正証書遺言・秘密証書遺言についてコンピュータで検索すること
が出来ます。
(2)生前は遺言者のみ、遺言者の死亡後は相続人などの利害関係人から利用できます。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年6月23日 木曜日
平成28年6月23日第412号
出生時両立支援助成金とは、平成28年度から新たに新設された、
育児休業を取得しやすい職場風土づくりを行い、男性労働者に
一定の育児休業を取得させた場合に受給できる助成金です。
今や男性の育児参加は様々なメディアで取り上げられていますが、
男性の育児休業制度は根づいていないのが実情です。
短い期間でも育児休業を取得し、普段の業務から離れることは、
企業にとっても多くのメリットが考えられます。業種によっては、
男性が子供や女性目線での商品開発やサービスに積極的になる
可能性や、仕事と子育て等の両立支援を手厚くサポートする
企業には、くるみん認定が取得できるなど、魅力的で優秀な
人材が集まる力となっていきます。
<受給条件>
1.男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続
14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得すること
2.過去3年以内に男性の育児休業取得者がいないこと
3.平成28年4月1日以後、育児休業開始前に男性労働者が
育児休業を取得職場風土作りの取組を行っていること
・男性労働者に対する育児休業制度取得促進のための資料等の周知
・管理職による子が出生した男性労働者に対する育児休業取得の推奨
・男性労働者の育児休業取得促進に関する管理者に対する研修 etc.
4.育児介護休業法に規定されている育児休業制度及び所定労働時間
短縮に関する制度について就業規則又は労働協約に明記していること
5.一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること
6.支給申請日以前1年間に育児介護休業法や次世代育成
支援推進法等について重大な違反をしていないこと
<支給額>
取組かつ育休1人目:30万円(中小企業60万円)
2人目以降:15万円 ※支給対象となるのは、1年度につき1人まで
男性職員が長期の育児休業を取得することは難しいところもあると
思いますが、大企業で14日、中小企業であれば5日以上を最初の
一歩として取り組んでみてはいかがでしょうか。
詳しくは、当事務所までお問合せください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年6月 8日 水曜日
平成28年6月8日第411号
去年9月30日から施行されている改正労働者派遣法については、すでに
当新聞(395号)で取り上げていますが、今回は、その改正の真髄である
派遣労働者のキャリア形成支援についてご案内いたします。
労働者派遣法第30条において、キャリア形成を念頭に置いた段階的な
教育訓練の実施が求められています。
現在のところ法律上では努力義務となっていますが、派遣業務の
許可・更新申請においては、そうした実施計画が必須となっています。
派遣事業者として、必然的に派遣労働者を雇用した段階から継続した
キャリアアップを目的とした教育訓練の対策をとらねばならなくなっています。
そのキャリア支援措置としては、次の内容となっています。
1.段階的かつ体系的な教育訓練の実施
第30条の2では、すべての派遣労働者に対し有給無償で年間8時間以上の
教育訓練を実施しなければならないとなっています。
また、実施する教育訓練は派遣労働者のキャリア形成に資する内容でなければなりません。
さらに、無期雇用の派遣労働者に対しては、実施する
教育訓練が長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容の
ものでなければなりません。
また、派遣労働者の採用時においても、入職時の教育訓練を
必要としています。
2.キャリア・コンサルティング窓口の設置
派遣元事業主は希望する派遣労働者に対して、労働者の
職業生活の設計に関する相談その他援助を行うための
キャリア・コンサルティングを可能とする窓口を
設けなければなりません。
以上、派遣事業を行う企業にとって、特に中小規模の会社に
おいては厳しい課題となるかもしれませんが、これによって
労働者に対し劣悪な条件で使い捨て同様な雇用環境で
あった会社が淘汰されていくものと思われます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年5月23日 月曜日
平成28年5月23日第410号
1.事例
労働基準法第65条には、産前6週間・産後8週間の「産前・産後休業」期間の
条文が設けられ、また、健康保険法第102条には出産した場合の保険給付
として「出産手当金」の定めがあります。今回は、上記法律の出産における
基準日について触れます。
今回モデルケースとして、出産予定日9月1日(産前休業開始日7月22日)
の女性が、体調不良で産前休業開始日の数週間前から休みを取り、早産と
なり7月1日出産した事例で解説します。
2.労働基準法
労働基準法では「産前6週間の期間は出産予定日を基準として計算し、産後
8週間は現実の出産日を基準として計算する(出産予定日は産前6週間に
含まれる)。6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に予定された
出産予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は、
産前休業期間に含まれる」とあり、産前休業の基準日は「出産予定日」として
います。よってモデルケースでは産前休業は出産日(7月1日)の
1日だけとなり、出産日の翌日の7月2日から産後休業期間となります。
3.健康保険法
一方健康保険法の出産手当金では「被保険者が出産したときは、
出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは、出産予定日)
以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの
間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、
標準報酬日額の3分の2相当額を支給」とされています。
産前休業の基準日が「出産の日」であるため5月21日から
産前休業が始まり産後休業が終了するのは8月26日となります。
4.まとめ
このように法律の条文により産前休業期間の考え方が変わります。
モデル例の女性が産前休業前の休みに労務に服していなければ
出産手当金が支給されます(切迫早産などの理由で傷病手当金の
支給を受けていた場合、出産手当金の内払となります)。
結果、平成26年4月から始まった産前産後期間中の保険料免除
申請も可能です。
*通常、産前休業に入る前まで労務に服し休業に入るため、
出産予定日より早く出産した場合は産前休業期間が短くなります。
産前休業に入る前、年休など利用し労務に服していない期間が
あれば(出産手当金額は年休収入により調整あり)、
モデルケースほど出産日が早くない場合であっても、
保険料免除制度等の手続きには注意が必要です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年5月 8日 日曜日
平成28年5月8日第409号
妊娠・出産・育児期や家族が介護の必要な時期に、男女ともが離職することなく
働き続けることができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し、
雇用環境の整備に向けた改正が施行されます。その中でも今回はアベノミクスの
第3の矢である「介護離職防止」に向けた「仕事と介護の両立支援制度の見直し」
について紹介します。
1.介護休業の分割取得
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業の分割取得が
可能となります。(現行は通算93日まで、原則1回が上限)
2.介護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化
半日単位(所定労働時間の2分の1)の取得を可能となります。(現行は原則1日
単位。努力義務では時間単位の取得が可能)
3.介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務)
介護休業とは別に、利用開始から3年間の間で2回以上の利用を可能とする
制度の導入が事業主の義務となります。事業主は次のいずれかの措置を
選択して講じなければなりません。
「所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)」「フレックスタイム制度」
「始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ」「労働者が利用する介護サービス
費用の助成その他これに準じる制度」
4.介護のための所定外労働の免除(新設)
介護終了までの期間について請求することのできる権利として新たに新設されます。
ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者等は労使協定で除外が
可能。1回の請求につき1ヵ月以上1年以内の期間で請求でき、事業の正常な
運営を妨げる場合には事業主は拒否できます。
5.有期契約労働者の介護休業の取得要件の緩和
「(1)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
(2)93日経過から6ヵ月を経過する日までの間に、その労働契約
(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了する
ことが明らかでない者」と取得要件が緩和されます。
(現行では(1)は同様、(2)が「1年以上」、介護休業開始予定日から
93日を経過する日以降の雇用継続見込みは削除されます。)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年4月23日 土曜日
平成28年4月23日第408号
1.運送会社において、労働者が交通事故を起こした場合
運送会社の従業員が、業務に関して、交通事故を起こし、第三者に損害を加えた
とき、会社は、使用者責任(民法第715条第1項)により責任を負うことになります。
しかし、会社の経営者としては、従業員のミスで交通事故となったのに、全て
会社が責任を負うのは、納得できない、という方も多いのではないでしょうか。
これについて判断した最高裁昭和51年7月8日判決をご紹介します。
2.事案の概要
石油等の運送・販売会社の従業員が、タンクローリーを運転していたところ、
追突事故を起こした。会社は、追突された車両所有者に車両修理費用等を
支払ったので、従業員に対して、求償・損害賠償請求をした事案。
<最高裁の判断>
「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接
損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を
被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の
業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは
損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、
損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、
被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと
解すべきである。」
3.報償責任の法理というもの
最高裁の判断の根底には、報償責任の法理(事業活動において利益を得ている
使用者は、その収益活動から生ずる損害については責任を負うのが公平)がある
とされます。これにより、使用者の労働者に対する損害賠償及び求償権の行使を
一定の割合で制限されることになります。
制限割合については、一律の判断基準はありません。判例に列挙されている
事情を総合的に見て判断されます。ちなみに、上記事案においては、会社が、
石油等の運送・販売という危険を伴う事業であること、会社が任意保険に加入
していないこと、労働者が特命により臨時的に加害車両を運転して業務中
発生した事故であり労働者の過失が重大なものでないこと、労働者の勤務成績が
普通以上であったことを考慮し、労働者に対し、求償ないし賠償請求できる
範囲は、信義則上損害額の4分の1が限度であるとした原審の判断を
相当として認めています。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年4月 8日 金曜日
平成28年4月8日第407号
人事担当者からこのような相談がありました
退職する従業員から過去の未払い残業代の請求をされています。残業はすべて
自己申告制となっており、本人からの申告に基づき適正に支払ってきました。
今回の従業員の言い分は「会社と上司からの売上アップ、経費削減の
プレッシャーが強く、とても実際働いていた時間を申告できなかった。」というものです。
会社としては適正な申告をすれば支払っているのにそれをしなかった従業員に
問題があると考えていますが、支払わなければなりませんか?
結論からいいますと、実際に残業をしていて未払い残業があった場合
「適正申告しない従業員が悪い」という考え方は通用しません。
申告しなかったことは「自己責任」であり、後日残業代を請求しても「会社側に
支払い義務はない」と考えてしまいそうですが、実際に時間外労働があって
残業代が未払いであるなら未払い残業代の請求権は発生します。
遡及できるのは最大過去2年分
労働基準法第115条には、賃金(退職手当を除く)の請求権は2年間と定められています。
従って、時間外労働賃金の時効は権利発生から2年となり、従業員側は
最大過去2年分の残業代遡及請求が可能です。この請求において
在職中か否かは問いません。
過去の労働時間の把握の仕方
ただ、過去の労働時間が正確に把握できていなければ実際に残業代の算出が困難です。
労働基準監督署でも客観的な記録がなければ支払命令などは出しようがありません。
このケースでは、日報として退社時刻近くに本社にメールを送っていました。
そこでこれを客観的な記録として労働時間を把握することが出来ました。
手書きの出勤簿では早く退社したことになっていたのですが、
実際残業していたということがこの記録から確認されたのです。
ほかにも百貨店などの入館退館記録、従業員本人による手帳への
記録なども労働時間の記録として認められることが多いようです。
自己申告制を採る企業の場合、手間はかかりますが日々の勤怠を適正に
把握していくことでトラブルを防止することができます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年3月23日 水曜日
平成28年3月23日第406号
1.個別労働関係紛争とは?
個別労働関係紛争とは、労働条件その他労働関係に関する事項についての
労働者と使用者間の争いです。具体的には、解雇、雇止め、配置転換・出向、
昇進・昇格、いじめ・嫌がらせといった事項についての労働者と使用者間の
争いで、使用者、労働者双方が、労働局での相談や、あっせん制度を
利用することができます。
2.労働局のあっせん制度
通常は、行政的解決の方法としては、都道府県労働局長による助言や
指導の後にあっせんに進む場合が多いのですが、最初からあっせんの
利用を求める労働者もいます。
手続きとしては、労働者が「あっせん申請書」を都道府県労働局長に提出し、
労働局で審査し、「紛争調整委員会」へあっせんを委任します。
その後「あっせん開始通知書」が労働局から送られてきます。ここで、
使用者は労働者と紛争状態になったことを意識するわけです。ただし、
あっせんに応じるかどうかは自由ですし、不参加でも不利益な取扱いが
なされるわけでもありません。
3.紛争調整委員会
「紛争調整委員会」とは、弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の
専門家で組織された委員会で、都道府県労働局ごとに設置されています。
この紛争調整委員会の委員の中から指名されるあっせん委員が、紛争解決に
向けてあっせんを実施します。
あっせん委員は中立な立場であっせん案を出してくれますし、あっせん案に
同意できなければあっせんを打ち切りにできます。
4.あっせん当日
あっせんは、申請人と被申請人が別々の部屋で行われ、各々があっせん委員を
前に主張を行います。あっせんに要する時間は、約2~3時間で、顧問の弁護士や
特定社会保険労務士は代理人になることができます。費用は無料です。
あっせん開始の通知から、2ヵ月以内にあっせんが行われ、開催は1回のみで、
この1回で合意できるか否かを当事者が判断し、当事者双方が合意した場合、
その場で合意文書が作成されます。
5.メリット・デメリット
1回のあっせんで妥結できるので問題を早く解決できる等のメリットがある反面、
あっせんでの合意は民法上の和解契約なので、相手が履行してくれなくても
強制執行できないこと等があげられます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年3月 8日 火曜日
平成28年3月8日第405号
本年2月、成年後見人利用促進法の提案を政府与党が了承しました。
かつては、判断能力が衰えたり、喪失した人の法的関係を保護するために、
禁治産及び準禁治産の制度が設けられていました。
禁治産制度では、判断能力の程度が心神喪失の状況にある者を対象に
禁治産・準禁治産宣告が行われ、保護機関として後見人が置かれていました。
しかし、この制度では、
(1)禁治産等の宣告が戸籍に記載されるので、本人・親族等関係者に
避けられることが多かった。
(2)財産保護に偏っており日常生活の補助がない。
(3)行政機関に申立権がなく、身寄りのない人は制度を利用できない。等様々な
問題が指摘され、平成12年4月に民法が改正されて、成年後見制度ができました。
1.現在の利用状況
平成12年の申立件数は約三千六百件でしたが、平成26年の申立件数は
約3万4584件、当初の約9.5倍、制度利用者は27万9千人となりました。
今後、高齢人口の増大と一人暮らしの高齢者の増加により、利用者は増加すると
判断されています。日本の認知症高齢者は約300万人、
知的・精神障害者は約378万人にのぼります。
欧米では、人口の1割程度が制度利用の標準となっており、
我が国の潜在需要は120万人前後と推計されますが、
制度の内容が十分知られていないのが実情です。
2.制度の概要
(1)判断能力喪失の程度により、補助、補佐、後見の3類型で法定後見制度
とした。
(2)戸籍への記載に代えて、登記することで登録して公示する制度とした。
(3)市町村長に対し、法定後見開始の審判申立権を付与した。
(4)複数の後見人、法人の後見人が選任できるようになった。
(5)将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に代理権を
与える契約を公正証書で作成する「任意後見人」制度が創設された。
(6)財産管理だけでなく、介護契約・施設入所等身の回りの契約が可能となった。
将来、認知症等で判断力が低下した場合、財産の管理・介護サービス契約・
施設への入所契約・財産分割協議などの処置が必要となります。
現在、成年後見人の専門職受任機関として、弁護士、司法書士、社会福祉士、
行政書士、税理士がそれぞれの専門的な立場から受任、社会保険労務士も
介護保険や年金の専門家としての特性を生かして後見人活動を行っています。
親族にまさかの事態が発生することを予想して、予め対応策を立てておくことは、
安心な将来設計のために必要な準備と思われます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年2月23日 火曜日
平成28年2月23日第404号
重要な場面で提出を求められることが多い戸籍・住民票・印鑑証明書等
(以下「公的証明書」という。)ですが、その有効期限というのは、
どのように定められているのでしょうか?
1.主な公的証明書
(1)戸籍 ...人の親族法上の身分関係を公証するためのもの。
(戸籍法)
(2)住民票 ...居住関係の公証、選挙人名簿登録等のためのもの。
(住民基本台帳)
(3)印鑑証明書
印影があらかじめ届け出てある印鑑と同一であることを証明する官庁・公署の書
面。会社・法人については、根拠が商業登記法にありますが、個人については市区
町村長が条例や古くからの慣例に従って交付しているとされています。
2.公的証明書の有効期限
(1)一般法として有効期間・期限を定めた法律はありません。
(2)有効期限が求められるのは、個別に有効期限を定めている法律や
各地方自治体の条例等が存在するからです。次に例を挙げます。
ア.不動産登記での印鑑証明書 ...3ヵ月以内
イ.パスポート申請での戸籍・住民票 ...6ヵ月以内
ウ.古物商取得での住民票 ...3ヵ月以内
エ.一部市役所等の婚姻届出の戸籍謄本 ...3ヵ月以内
3.ある証明書が「3ヵ月」と定められている場合の具体例
民法第140条では「期間が、日・週・月・年を単位とするときは、(中略)初日は算入しない。」
と定められています。
また、行政機関の休日に関する法律第2条では「国の行政庁に対する申請・届出その他の
行為が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもってその期限とみなす。」
と定められています。
(1)4月10日作成の場合 ...7月10日まで有効
(2)3月30日作成の場合 ...6月30日まで有効
(3)2月28日作成の場合
ア.うるう年でない場合 ...5月31日まで有効
イ.うるう年の場合 ...5月28日まで有効
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年2月 8日 月曜日
平成28年2月8日第403号
平成27年6月1日に道路交通法が改正となり、自転車運転の違反を3年以内に2回行なうと自転車運転者講習を受けなければならなくなりました。エコブームや健康志向から自転車を利用する人が急増し、自転車と歩行者の事故が増えてきていることが背景にあります。また、自転車による事故が起こった場合、自転車通勤を容認する企業では、企業の「使用者責任」を問われる可能性を想定しなければなりません。自転車通勤を管理していくポイントと、企業に求められる対応について説明します。
1.従業員が加害者となった場合
まず、従業員が加害者となった場合の損害賠償について考えましょう。損害賠償については、従業員がその責任を負うことになりますが、それが果たせない場合には、企業が責任を追及されることがあります。そのため、企業のリスク管理としては、従業員に民間保険への加入義務を課すなどの対策を講じておく必要があります。
2.自転車通勤途上の事故は、通勤災害と認められるか
従業員が自転車通勤をする際に、まず心配されるのが通勤途上の事故の問題です。通勤災害として認められるためには、通勤と災害との間に因果関係がなければ保険給付の対象とはなりません。しかし、自転車通勤の場合には自由度が高いため、合理的な経路を外れる頻度が高いと考えられます。例えば、会社に届けている通勤経路ではなくても、日常生活上必要な行為として、子供の送迎のために保育園等へ行くことは、合理的な経路として取り扱われることになりますが、自宅から直接取引先に行くような場合は、通勤災害とはならず業務災害として取り扱うことになります。自転車通勤者に対し、通勤災害に関する基本的なルールを説明し周知徹底することが重要です。
実際に自転車通勤を認めることになると、許可する際の手続などを明確に定めておく必要があります。併せて自転車通勤規程や許可申請書、誓約書の提出などのルールを定め、企業の実態に合わせた運用管理が望まれます。また、事故のリスクの高さから自転車通勤を認めないということも考えられます。認めない場合には、その旨を従業員に周知し、無断で自転車通勤をする者が出ないよう就業規則の服務規定の中に自転車による通勤をしてはならない旨を定めておくことが求められます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年1月23日 土曜日
平成28年1月23日第402号
先日、電話相談で「フレックス制度を使用しているが、従業員が就労日に欠勤をした。月間の総労働時間は満たしているが、欠勤として処理してよいか?ちなみにコアタイムは設けていない。」という質問を受けました。
労働基準監督官が回答に対して常に参考にする「コンメンタール」の解説によると、年次有給休暇の出勤率の計算についての説明の中に次のように記載されていました。
1.コアタイムが設けられている場合
コアタイムはすべて欠勤し、フレキシブルタイムに一部労働した場合であっても、出勤率は、労働日単位で見ることとされているので、当該日は出勤したものとして取り扱わなければならない。
2.コアタイムを設けていない場合
コアタイムを設けていない場合には、出勤日も労働者の自由に委ねることとされている。この場合の「労働日」「出勤日」は、次のとおりである。
(1)清算期間における総労働時間労働している場合
当該清算期間における「全労働日」は当該労働者が実際に労働した日数とし、その全日出勤したものとして計算する。
(2)清算期間における総労働時間労働していない場合
当該清算期間における「全労働日」は所定休日を除いた日とし、そのうち当該労働者が労働した日を出勤日として計算することになる。
つまり、コアタイムを設けている場合には、所定労働日が定められていますが、コアタイムを設けていない場合は、法定休日を確保するために所定休日を定めることはできても所定労働日を定めることはでないという、この違いが一般的には理解されず大きな誤解となるようです。よって、コアタイムを設けていない場合は、月間の総労働時間を満たしているのであれば、賃金上での欠勤処置はすべきでないが、従業員管理上での欠勤措置は必要の範囲内で行えばよいということになるのです。
また、フレックス制度における総労働時間の過不足の処置について付け足すと、実労働時間が総労働時間を超えた場合には、その全額を当月に清算しなければ、労基法第24条に反することになりますが、実労働時間に不足があった場合、当月の賃金は全額支払った上で、不足する労働時間を次月の基準労働時間に上乗せすることは可能です。要するに先払いした賃金分を翌月に労働させることは問題ないという意味になります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年1月 8日 金曜日
平成28年1月8日第401号
いよいよ今年10月からパートタイマー等短時間労働者の社会保険(厚生年金、健康保険)適用基準が拡大されます。現在の基準は、通常の労働者(正社員)の4分の3以上(週40時間勤務なら週30時間以上)勤務する者が社会保険加入対象ですが、新たな社会保険適用拡大の基準は、次のすべての基準を満たす必要があります。
(1)週20時間以上の勤務
(2)賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)
(3)契約期間1年以上
(4)現行の適用基準で適用となる被保険者が501人以上(学生は適用除外)
現在、ご存じの通り所得税で「103万円の壁」、社会保険で「130万円の壁」があります。「103万円の壁」を超えると所得税が発生し配偶者控除も受けられなくなり勤務先の制度によっては配偶者手当も打ち切られる可能性があります。そして、健康保険の被扶養者や国民年金第3号から外れ、自ら社会保険料を支払う必要が出てくる「130万円の壁」が「106万円の壁」に変わろうとしています。
労働者のメリットとしては、健康保険に加入することにより、子が生まれた場合「出産手当金」(産前・産後休業期間)、病気やケガで会社を休んだ場合「傷病手当金」(休業後4日目から1年6ヵ月を限度)が標準報酬日額の3分の2支給されます。また、厚生年金に加入することにより、老齢年金額が増加しますし、障害にあった時の障害年金、亡くなった時の遺族年金等受けられる保障が増えます。
企業側としては、法案が審議されていた当時からパート労働者の多い流通、外食、医療・福祉関係の事業団体を中心に、社会保険料負担(平成24年3月厚労省の試算では事業主負担計800億円増)の重さに対し反対意見が多く出されていました。
今後、働き手側からの選択肢としては、(1)従来以上多く働いて年収を増やす(正社員を目指す)(2)労働時間を減らす(3)500人以下の会社へ転職が考えられます。ただし、近いうち(施行3年後適用要件の見直し)に適用基準(4)の人数は大きく下がり、該当企業が拡大し、加入対象となるパート等は増えていくと思われます。企業側としては社会保険料負担をカバーすべく「より多く働きたい」質の良いパート労働者の確保に向け「短時間正社員制度」等の制度構築も検討する必要があると考えます。
一方政府は、平成28年4月から4年間、現行の「130万円の壁」対策として、パート等に対して大企業で2%、中小企業で3%以上賃上げ・週5時間以上の勤務時間を増やした企業に助成金を支給する制度を始めます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年12月23日 水曜日
平成27年12月23日第400号
1.ストレスチェック制度の義務化
労働安全衛生法の改正により、平成27年12月からストレスチェック制度が義務化されました。
この制度は、定期的に労働者のストレスについての検査を実施し、自らのストレス状況についての気付きを促すことで、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、改めて職場のストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることを目的としています。
2.ストレスチェック制度の内容
事業者は、年に1回、労働者に対して質問形式でストレスチェックを実施し、実施者(医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士)が、ストレス状況を評価し労働者に通知する必要があります。ストレスが高い労働者に対しては、本人からの申出があれば、医師による面接指導の実施が義務とされています。
ストレスチェック実施後、面接指導を実施した医師からの意見聴取をおこない、必要があれば労働時間の短縮などの必要な措置を実施することも重要です。
また、労働者が安心して受検できるようにプライバシー保護や、不利益取扱いの禁止規定も定められています。
制度の詳しい内容については、厚労省のホームページで確認できます。「5分でできる職場のストレスチェック」という簡易ツールも公開されていますので、一度受検されてみてはいかがでしょうか。
3.ストレスチェック制度を実施しないことによる法的な問題
新たな制度が始まると聞くと事業者は、身構えてしまいますが、対象となるのは、従業員数50人以上の事業場です。50人未満の事業場は、当分の間、努力義務となりますので、多くの中小企業では、努力義務にとどまることになるのではないでしょうか。しかし、労働者のメンタルヘルス不調が社会問題化し、今回の法改正があったことは、十分に考慮しておく必要がありそうです。労働者が病気となった場合に、ストレスに配慮していなかったことが労働管理上の過失といわれる場合もあり得ます。労働者と会社というのは、中小企業にとっては車の両輪のような関係です。労働者が元気で輝いている会社は、事業も発展していくものです。これを機に、メンタルヘルスを考える「きっかけ」にしてみてはいかがでしょうか。
(スマイルグループ 弁護士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年12月 8日 火曜日
平成27年12月8日第399号
来年も実施される可能性の高い補助金をピックアップしました。
今後の国・自治体の動きによって追加・変動があると思いますが、ご参照ください。
公募開始時期(2015年)
2月:小規模事業者持続化補助金(1次)
3月:創業補助金(1次) ・
:海外ビジネス戦略推進支援事業(1次)
4月:創業補助金(2次)
5月:小規模事業者持続化補助金(2次)
:海外ビジネス戦略推進支援事業(2次)
7月:小規模事業者持続化補助金(追加)
<概要>
1.「創業補助金」最大200万円(経済産業省)
募集開始:3、4月(2015年)
対 象:個人事業主、株式会社、有限会社、合同会社、NPO法人など
対象事業:賃料、人件費、コンサル料、改装費、備品代、
HP製作費、広告宣伝費、登記費用など
補助金額:補助対象費用の2/3(最大200万円まで)
2.「小規模事業者持続化補助金」最大50万円(中小企業庁)
募集開始:2、5、7月(2015年)
対 象:常時使用する従業員が20人以下
(卸売/小売/サービス業等は5人以下)
対象事業:コンサル料、改装費、HP制作費、広告宣伝費、展示会出展費など
補助金額:補助対象費用の2/3(最大50万円まで)
採 択 率:20~30%(非公開のため予想)
3.「海外ビジネス戦略推進支援事業」最大160万円(中小企業庁)
募集開始:3、5月(2015年)
対 象:海外拠点を検討している中小企業者
対象事業:市場調査費、翻訳・通訳費、旅費、Webサイト構築費用
補助金額:補助対象費用の2/3(最大160万円まで)
採 択 率:(非公開)
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年11月23日 月曜日
平成27年11月23日第398号
本件は、業務上疾病により休職中で労災保険給付(療養補償給付・休業補償給付)を受けている従業員(X 男性)に対し、勤務先(Y)が労働基準法81条に基づき平均賃金の1200日分相当額の打切補償を支払って行った解雇について、解雇は無効であるとして、労働契約上の地位確認請求が認容されたことについての反訴です。
1.東京地裁、東京高裁の判決
Xは平成14年ごろから首や腕に痛みが生じて頸肩腕症候群と診断され、平成19年に労災認定を受け休職した。Yは平成23年に打ち切り補償約1629万円を支払いXを解雇。X側が地位確認を求めて提訴した。一審(東京地裁)は「打ち切り補償の適用は、使用者による療養補償(労災給付ではない)を受けている場合に限られる」とし、解雇無効と判断。二審(東京高裁)も支持していた。
2.争点は?
労働基準法は業務上のケガや病気で療養中及びその後30日間の解雇を禁止しているが、使用者が療養費を負担し3年が過ぎても治らない場合、平均賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払って解雇できると規定している。
一、二審の判決の結論が維持されたまま確定すれば、使用者が労災保険料を負担して労災給付を行っても打切補償の規定を適用した解雇ができないことになることから、実務に大きな影響を及ぼすものと注目されていた。
3.最高裁判決
最高裁は、平成27年6月、「労災保険が給付されている場合、労働基準法が使用者の義務とする災害補償は実質的に行われているといえる」という拡張説を明らかにした。4人の裁判官の全員一致で「療養開始後3年が過ぎても治らない場合、打ち切り補償の支払いで解雇できる」という初判断を示し、高裁への差戻し判決が出た。
近年、メンタルへルス疾患により長期間休職を行う労働者が増加しています。
このたび打切補償を支払ってなす解雇有効判断がありましたが、一方、療養中なのに解雇されてしまう労働者の保護とどう調整するのか、今後の動向にも注目です。
詳細は、学校法人専修大学(地位確認等反訴請求控訴)事件をご一読ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年11月 8日 日曜日
平成27年11月8日第397号
「社会保障と税の一体改革大綱について」(平成27年2月17日に閣議決定)を踏まえ、平成27年10月1日「被用者年金一元化法」が施行されました。
民間サラリーマンに適用されていた厚生年金保険が、公務員及び私学教職員にも適用されます。今回の一元化のポイントは、かつての国鉄や電電公社の厚生年金への統合とは異なり、各共済年金機関が実施機関となることです。つまり、被保険者資格の管理、保険料の徴収、年金額の決定、年金支払い等は、種別ごとに各実施機関が行い、厚生年金法を改正し適用することにより一元化されました。
1.一元化後の被保険者の種別
(従来の被保険者ごとに種別名称がつけられました。)
(1)第1号厚生年金被保険者:従来の厚生年金被保険者
(実施機関:厚生労働大臣)
(2)第2号厚生年金被保険者:国家公務員共済組合の被保険者
(国家公務員共済)
(3)第3号厚生年金被保険者:地方公務員共済組合の被保険者
(地方公務員共済)
(4)第4号厚生年金被保険者:私学共済制度の加入者
(日本私学振興共済事業団)
2.共済年金と厚生年金の制度の相違点の解消
両制度の差異を解消するため、内容により共済年金と厚生年金制度のどちらか
の規定が適用されます。主な概略は次の通りです。
(1)共済年金の制度が、厚生年金にも適用されるもの
ア 被保険者期間の計算
厚生年金の資格を得喪し、同月内に国民年金の資格を取得した場合、従来
は両方の保険料の負担が必要でしたが、国民年金のみの負担となります。
イ 在職老齢年金の期間
在職老齢年金は、資格喪失の月まで被保険者でしたが、退職した月まで在
職老齢年金となり、月末退職の場合でも翌月から年金の支給停止が発生しな
くなりました。
ウ 資格喪失時の年金額改定
従来は資格喪失日から起算して1ヵ月を経過した日の属する月から年金額
が改訂されていましたが、退職した日から起算され月末退職時の遅れが解消
されます。
(2)厚生年金の制度が、共済年金にも適用されるもの
ア 未支給年金の支給範囲
厚生年金の支給範囲の他に相続人があった場合でも、厚生年金の規定とな
ります。
イ 在職老齢年金:激変緩和措置への配慮
退職共済年金受給者が厚生年金被保険者となった場合、従来は別制度のた
め、賃金+年金が47万円を超えた場合の支給停止でしたが、28万円超に
緩和されます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年11月 5日 木曜日
平成27年10月23日第396号
相続が開始する以前に推定相続人が死亡・欠格・廃除などによって相続権を失った場合に、その者の直系卑属がその者に代わって同一順位で相続人となることをいいます。これは、直系卑属の期待権を保護するのが公平という考えに基づくものとされています。
1.被代襲者
被代襲者は、被相続人の子及び兄弟姉妹で、被相続人の直系尊属及び配偶者は被代襲者とはなりません。
2.代襲相続人「子の代襲相続の場合」
(1)代襲相続人の限定
代襲相続人は「被代襲者である子」の直系卑属(被相続人の孫・ひ孫など)また
は「被代襲者である兄弟姉妹」の子(被相続人の甥・姪)に限ります。
(2)子についての代襲相続
代襲相続人は、相続権を失った者の子であるとともに、被相続人の直系卑属で
なければなりません。そのため、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続人
とはなりません。
(3)兄弟姉妹についての代襲相続
代襲相続人は、相続権を失った者の子であると同時に、被相続人の血族(傍系
卑属)であることを要します。養子の縁組前の子は養子を代襲して養親の他の
子の遺産を代襲相続することができません。
(4)その他
代襲相続人は、被代襲者が相続権を失ったときに存在している必要はなく、相
続開始時に存在していればよいとされています。
3.代襲原因
代襲原因は、被代襲者が相続開始以前に死亡(失踪宣告を受けた場合や同時死亡の推定の場合を含みます)しているとき・相続欠格・相続人の廃除の3つの場合とされており、相続放棄は代襲原因とはなりません。
4.代襲相続人の地位
代襲相続人は、被代襲者に予定されていたのと同一の順序で、被代襲者に相当する相続分を相続します。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年11月 5日 木曜日
平成27年10月8日第395号
派遣労働という働き方は、 臨時的なものであるという考え方のもと、常用代替を防止し、派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップを図るため、平成27年9月30日から労働者派遣法が改正施行されました。
1.派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇の推進
派遣先は、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、次の点で配慮義務が課され、具体的な行動を行う必要があります。
(1)派遣元事業主に対し派遣先の労働者に関する賃金水準の情報提供等を行う
こと
(2)業務に密接した教育訓練を実施する場合は、派遣労働者にも実施すること
(3)派遣先の労働者が利用する福利厚生施設利用の機会を派遣労働者にも与え
ること
2.期間制限のルールが変わります
現在の期間制限を見直し、施行日以後に締結・更新される労働者派遣契約は、全ての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。
(1)同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる期
間は原則3年が限度となります。
※派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を1ヵ月前までに聴く必要があります。
(2)同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位において 受
け入れることができる期間は、原則3年が限度となります。
3.労働契約申込みなし制度
平成27年10月1日から、労働契約申込みなし制度が施行されます。派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、派遣先は派遣労働者に対し派遣元と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。
(1)労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
(2)無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
(3)派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
(4)いわゆる偽装請負の場合
施行日時点ですでに締結されている労働者派遣契約については、その労働者派遣契約が終了するまで、改正前の法律の期間制限が適用されます。しかし、申込みなし制度適用のリスクを完全に排除するためには、専門26業務など、期間制限違反を主張されるおそれがある場合は、10月1日時点で新法適用に切り替え、また、継続している労働者派遣個別契約は、派遣会社と合意の上9月29日で終了し派遣期間を9月30日開始とする労働者派遣個別契約を締結し、申し込みなし制度の適用を受けないよう締結日は平成27年9月30日と記載する必要があります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年10月 1日 木曜日
平成27年9月23日第394号
昨今、定額残業手当にまつわるご相談が多くなっています。事業主は定額残業手当を支払っているが、労働者は時間外労働の賃金未払を訴えるケースです。
定額残業手当制度を採用する場合、事前に時間外の労働時間あるいは手当額がどの賃金項目にどれだけ含まれているかといった説明が必要であり、書面上(雇用契約書、労働条件通知書、周知された就業規則等)にも記載が必要です。
定額残業制度がきちっと運用され、計算も正確に行われていれば、表題のように当月余った定額残業時間を翌月以降に繰り越すことが可能でしょうか。
平成21年3月27日東京地裁『SFコーポレーション事件』では、「月8万円の管理手当は割増賃金の内払いと認められ、繰越分の翌月に繰り越す旨の規定により未払割増賃金は存在しない。」という判例があります。
また、フレックスタイム制における通達昭和63年の基発第1号では、「精算期間における実際の労働時間に不足があった場合に、総労働時間として定められた時間分の賃金は、その期間の賃金支払日に支払うが、それに達しない時間分を、次の精算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠の範囲である限り、その精算期間においては実際の労働時間に対する賃金よりも多くの賃金を支払い、次の精算期間でその分の賃金の過払いを精算するものと考えられ、法第24条に違反するものではないこと」とあります。例えば、当月実労働時間が規定労働時間に10時間不足した場合は、規定賃金を支払えば、次月規定労働時間に10時間を上乗せ可能となります。
これらの考え方からすれば、定額残業手当の過払い分を翌月以降の不足分に充当するという取扱いも同様に考えられることができるように思われます。
しかし、『SFコーポレーション事件』の判決は、あくまで地裁レベルの判決であり、確定的な判断ではないことや定額残業手当過払い分の繰越ができるかどうかが争点の裁判ではなかったこと、この判決を受けて国から通達やコメント等がなく、行政指導の方針が変わったことを確認できていません。また、フレックスタイム制の通達は法定労働時間の総枠の範囲内であることと限定されており、残業時間の繰越しができるとはされていません。そのため、残業手当は月単位で支給される賃金であり、毎月賃金請求権が発生するため、月を超えて平均化することはできない、つまり定額残業手当の差額繰越はできないとする従来の見解のまま、毎月精算する制度にしておくことが無難です。
また、定額残業手当制度であっても、時間外計算は毎月必要であり、繰越充当するのであれば、さらに繰越充当時間の管理も必要となってきます。このことを考えれば、企業における運転資金の資金繰りという点では平準化というメリットがありますが、事務の効率化という点では逆効果のようです。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年10月 1日 木曜日
平成27年9月8日第393号
行政の事業所調査の中で、今回は各都道府県労働局雇用均等室が行う3つの「報告聴取」調査について触れます。
雇用均等室で扱う主たる法律は3つで、「男女雇用機会均等法」(以下「均等法」)「パートタイム労働法」(以下「パート法」)「育児・介護休業法」(以下「育介法」)です。
均等法第29条、パート法第16条、育介法第56条其々の条文に「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる」と記載されています。労働局雇用均等室は、この条文を根拠に各事業所へ調査を行います。
聞き取り・調査内容は、「均等法」では、母性健康管理対策・セクハラ防止対策(セクハラ相談窓口の設置含む)の規定整備状況又は社内掲示物の確認をし、ポジティブ・アクション(男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための自主的かつ積極的な取り組み)の推奨等について説明をします。
パート法では、パート社員の職務内容・人材活用の仕組み・正社員との待遇の格差が不合理となっていないか等を調査。また、正社員転換推進措置の整備状況、労働条件通知書(昇給、賞与、退職手当、相談窓口等の明示事項)の交付状況、雇入れ時の説明義務(賃金制度、教育訓練、福利厚生施設の利用、正社員転換推進措置等)が果たされているか等を確認します。
育介法では、各制度(育児6制度、介護5制度)の利用実績を聞き取りながら、育児・介護休業規程の有無、及び規程内容が現行の法の内容と合致しているか。また、各制度が法に則して運用されているか確認をします。
各報告徴収の調査では、法律内容に即していない規定・運用があれば、その場で助言され、是正・改善(行政指導)が求められます。是正期日は各法律の是正内容で異なり、原則、短いもので1週間以内(均等法、パート法)、長いものでも1ヵ月以内(育介法)となっています。罰則としては、報告の求めに対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料(行政罰で、刑事罰の科料とは異なります)とあります。各調査に掛かる時間は、均等法・パート法で約30分、育介法で約1時間位。法に則しての調査の為、拒否することは出来ず、日程の変更は求められます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年10月 1日 木曜日
平成27年8月23日第392号
1.無期労働契約への転換
平成24年に「労働契約法」が改正され、パート、アルバイト、契約社員、嘱託、派遣社員など雇用期間の定めのある「有期労働契約」の社員を保護する取扱いが創設されました。有期労働契約が繰り返し更新された場合に、雇用期間が通算5年を超え、労働者側から無期契約を希望した場合には、無期労働契約(期間の定めのない契約)に転換されることになりました。この「労働契約法」の改正により「就業規則の見直し」が必要になる場合がありますので、その注意点についてご説明します。
2.定年を定める必要性
これまで、有期労働契約者は期間が満了すれば退職となり、「定年」を定めておく必要がありませんでした。しかし、今回の改正により、無期労働契約に転換した場合には、「定年」がない限り、原則として雇い続ける必要があります。つまり、「正社員就業規則(無期労働契約)」、「非常勤社員就業規則(有期労働契約)」など、別々の「就業規則」を作成している場合には、「非常勤社員就業規則」にも、無期労働契約に転換した場合に備えた「定年」の定めをしてください。
3.具体的な対策
具体的には、有期労働契約者の就業規則にも、「無期労働契約へ転換した社員の定年は、満60歳とし、定年の達した日の属する月の末日をもって退職とする」など「定年」の定めを明記をしてください。しかし、さらに、60歳以降も有期労働契約を続けていた方が、その後に無期労働契約への転換を希望された場合、終身雇用となってしまう可能性も考えられますので、「雇用契約は最長でも、65歳まで」など第2の「定年」を定め、かつ、定年後は無期転換申込権を行使できないとする無期転換ルールの特例を利用するなどの対策が効果的です。上記の無期転換ルールの特例を利用する場合、管轄都道府県労働局に計画認定・変更申請書の提出を要します。
その他、有期労働契約の労働者にも無期労働契約者となった場合には、有期労働契約者に対しては規定されていなかった職種変更や、配置転換および賞罰などの適用があることも周知する必要があります。
(スマイルグループ 弁護士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年8月10日 月曜日
平成27年8月8日第391号
平成13年に個別労働紛争解決促進法が制定され、個別労働紛争の簡易迅速な解決を促進するための行政上の制度(個別労働紛争解決促進制度)が整備され、運用されています。制度は次の3つあります。
1.総合労働相談コーナーによる情報提供・相談
各都道府県労働局では、局内や労働基準監督署庁舎内、主要都市における駅周辺のビル内などに総合労働相談コーナーを設け、労働関係等に関する事項につき情報提供や相談を実施しています。労働関係についての相談等を広く受け付け、労基法・職安法などの法令違反とみられる事案については、管轄する機関を紹介したりしており、労働関係上のトラブルを広く、相談の対象としています。
2.都道府県労働局長の助言・指導
行政機関が紛争の当事者に対して、紛争に係る事実関係を整理したうえで、法令や判例等に照らして問題点を指摘したり、解決の方向性を示たりすることにより助言・指導を行い、当事者による紛争の自主的解決を促進しようとするものです。例えば、解雇された労働者から申請があった場合、都道府県労働局長は、労契法16条(解雇権濫用法理)に照らし、当該解雇が解雇権濫用に当たるおそれが強いと判断されるときには、解雇を撤回したり再考したりするように事業主に助言・指導を行うことが考えられます。
3.紛争調整委員会によるあっせん
個別労働関係紛争(募集・採用に関するものを除きます)につき、当事者の双方または一方から申請があった場合において、都道府県労働局長が必要と認めたときには、紛争調整委員会があっせんを行います。あっせんとは、当事者間による紛争の円満な自主的解決を図るため、紛争調整委員会が指名するあっせん委員が当事者の間に立って、話し合いを促進することを目的とする手続です。
あっせん委員は、当事者双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決するように努めることとされており、事件の解決に必要なあっせん案を全員一致により作成し、当事者に提示することもできます。合意が成立した場合、その合意は、民法上の和解契約として取り扱われます。
あっせん委員は相手方があっせん手続に参加する意思がない旨を表明したり、あっせん案を当事者が受諾しないなど、紛争解決の見込みがない場合には、手続を打ち切ることができます。つまり、あっせんは相手方に参加を強制することはできません。
上記のいずれも費用はかかりません。簡易・迅速な労働紛争解決が実現されているといえます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年8月10日 月曜日
平成27年7月23日第390号
年金分割制度とは、離婚した場合、婚姻中の厚生年金保険(共済年金保険)記録を当事者間で分割することができる制度です。
厚生年金は、世帯単位で構成されていて、年金受給権取得後は保険料を支払った被用者に対して支払われ、それによって扶養等されている配偶者も生活する仕組みです。そのため、被用者は離婚後も従前とさほど異ならない額の年金を支給され続けるのに対し、元配偶者は基礎年金及び自己の厚生年金加入記録に対する厚生年金のみしかもらえなくなります。これでは、元配偶者が長年専業主婦等をしていた場合に不公平であるため、婚姻期間中に会社員の被用者を支えた元配偶者の貢献度を年金額に反映させる等の主旨から、離婚時年金分割の制度が平成19年、20年から施行されています。
1.「合意分割」制度
平成19年4月1日以降に離婚した場合で、当事者の婚姻期間を対象期間とし、それぞれの婚姻期間中に支払った保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)の合計額を分割する制度です。仮に合計額に対する支払比率が夫は80、妻は20なら、「按分割合」は20%を超え50%以下となります。この按分割合について、お互いに合意しなければなりません。当事者間で合意に至らなかった時は、家庭裁判所の家事調停等で決めることになります。
2.「3号分割」制度
平成20年4月1日から離婚まで婚姻期間のうち配偶者が第3号被保険者であった期間(特定期間)を対象とし、被用者の標準報酬総額の2分の1が元配偶者に按分される制度です。当事者間での合意は不要で、婚姻期間を明らかにできる戸籍謄本等、請求者の基礎年金番号、標準報酬改定請求書等で手続きができます。ただし、平成20年3月以前の婚姻期間も対象にする場合は、平成20年3月31日以前の分割については上記の「合意分割」を請求することになります。
両制度とも分割後の年金の支給を受けるには、必ず自己の記録で受給資格(原則25年)が必要です。事前に年金事務所に情報提供の請求ができ、また年金事務所への請求期間は離婚後2年以内です。
年金分割は民法の財産分与の考え方を採用しながらも、年金には老後の生活保障という重要な役目があるため、その機能を蔑ろにする分割は認められないという制約(按分は上限2分の1)があります。また、分割は厚生年金部分のみで、夫が自営業者だった場合、夫は厚生年金には加入していないため、この制度では自営業者の元配偶者は年金の分割をしてもらえません。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年7月 8日 水曜日
平成27年7月8日第389号
教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者が自ら費用を負担し厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合に、その教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。従業員のキャリアアップや能力向上が、企業の持続的な成長を支える重要な要素と考えられ平成26年10月からは、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てに拡充されました。
1.給付対象となる講座とは
給付の対象になるのは厚生労働大臣が指定する講座です。教育訓練給付金の指定講座は、近くのハローワーク又は、厚生労働省「教育訓練講座検索システム」でご覧になれます。
2.一般教育訓練給付金(従来のもの)
雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて受講する場合は1年以上)である者が指定講座を受講した場合は、受講費用の20%が支給され、上限は10万円で、4千円超えない場合は支給されません。基準日(教育訓練開始日)前3年以内に教育訓練給付金を受けたことがある場合も支給されません。
3.専門実践教育訓練給付金(新制度)
中長期的なキャリア形成のため専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する助産師、看護師、放射線技師、理学・作業療法士、自動車整備士等の教育訓練が対象です。受講費用の40%(年間上限32万円)が支給されます。また、資格等を取得し、被保険者として雇用された場合には、さらに20%が追加支給され、合計60%、年間上限48万円まで給付されます。受講に必要な被保険者期間は10年(初めて当該教育訓練を受講する場合は2年)です。ただし、過去に教育訓練給付金を受給している場合には、10年以上経過している必要があります。申請は6ヵ月毎で、支給期間は2年間(専門職大学院等は3年間)です。
4.教育訓練支援給付金(新制度)
専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満の離職者が、専門実践教育訓練を受講するなど一定の条件を満たす場合には、さらに「教育訓練支援給付金」が支給されます。平成31年3月31日までの時限措置で、その間の所得保障として訓練期間の失業の状態にある日について基本日額の50%が支給されます。(基本手当が支給される場合は基本手当の終了後に支給されます)
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年6月23日 火曜日
平成27年6月23日第388号
限定承認とは、相続財産のうち積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)の総額がプラスになるのかマイナスになるのかよくわからないときに「積極財産の範囲内で消極財産を相続します」という意思表示のことです。
1.限定承認の方式
(1)自己のために相続の開始したことを知ったときから3ヵ月以内に財産目録を調製して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨の申述をしなければなりません。(民法第924条)
(2)相続人が数人あるときは、共同相続人全員が共同してでなければ、限定承認をすることが出来ません。(民法第923条)
2.限定承認の効果
(1)債務は縮減されませんが、相続人の責任が相続によって取得した積極財産の限度に縮減されるということで、いわゆる物的有限責任を負うということになります。
(2)相続債権者や受遺者への公平な分配のため、相続財産と相続人の固有財産とは切り離され、相続財産について清算が行われることになります。よって、相続人が被相続人に対して有した権利義務は消滅しなかったものとみなされます。(民法第925条)
(3)家庭裁判所は、相続人が複数ある場合は相続財産管理人を選任しなければならず、また相続財産管理のため、相続財産管理人を選任することも出来ます。
(4)公告及び催告の後、換価を行い、定められた順序に従って弁済が行われます。売却を必要とする相続財産があるとき、原則としては競売によることになりますが、限定承認者は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、相続財産の全部または一部の価額を弁済して、その競売を止めることが出来ます。(民法第932条但書)これを「先買権行使による競売停止」といいます。
3.限定承認者の責任
限定承認者が公告及び催告の手続を怠ったり、公告期間内に弁済する等により、他の債権者もしくは受遺者に弁済をすることが出来なくなったときは、損害を賠償する責任を負います。(民法第934条)
4.限定承認と、みなし資産譲渡所得課税制度
限定承認によって相続した資産については「相続開始の時に、相続時の価額に相当する金額により譲渡がなされたものとみなして、譲渡所得税を納めなければならない」と、されています。(所得税法第59条)なお、この場合の価格は路線価ではなく時価評価となります。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年6月 8日 月曜日
平成27年6月8日第387号
キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)とは有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者のキャリアアップ等を促進するため、正規雇用への転換実施に対し、1人につき50万円(H28.03.31以降は40万円・年間15人まで)を事業主に助成する制度です。また、10万円の特別加算は平成28年3月31日までの転換が期限となっていますので、正社員(正規雇用)への転換等を予定されている事業所様におきましては、計画的にご活用いただき、従業員さまのキャリアアップと業績アップを図りましょう。
<受給条件>
1 有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取組みを計画的に行なうための「キャリアアップ計画」を都道府県労働局長に届出ていること
2 事業主に雇用される期間が通算して6ヵ月以上の有期契約労働者を正規雇用に転換すること
3 正規雇用又に転換後、6ヵ月以上継続雇用(通常の勤務日数が11日未満の月は除く)すること
4 転換するにあたり、面接試験や筆記試験など適切な手続、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦などの客観的に確認可能な要件・基準などをいう)及び、転換の実施時期を就業規則等に明示していること
<申請の流れ>
キャリアアップ計画申請 → 正社員転換 → 支給申請
※支給申請は、6ヵ月分の賃金を支払った日から2ヵ月以内です。
正規雇用等転換コース以外にも、多様な正社員コース(雇用する労働者を短時間正社員に転換又は短時間正社員を新規で雇入れた場合)や有期契約労働者等を対象にした健康管理コース(パートや有期契約労働者等を対象とした健康診断制度を導入し、述べ4人以上実施した場合)などがあります。
詳しくは、当事務所までお問合せください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年6月 3日 水曜日
平成27年5月23日第386号
労働基準監督署で労働相談をしていると日々いろいろなご相談を受けるのですが、その中でも年次有給休暇については頻繁にご相談があります。その大半は「年休を取らせてくれない・・・」といった内容のものですが、まれに即答しかねるような悩ましいご相談もあります。今回は実際にあった難しい年次有給休暇におけるご相談とその回答をご紹介いたします。
1.年次有給休暇の返還
(問)入社してまだ半年を過ぎない新入社員が、病気で会社を休むことになり、気の毒に思った事業主が、年次有給休暇として取り扱ったが、結局その新入社員は退職することになった。そこで、法定以上で与えた年次有給休暇の返還を新入社員に求めたいが、可能か。
(答)一旦与えた年休を返還させることは、賃金の返還を求めることであり、賃金の全額払いに反するように思う。しかし、むしろこうした事業主の求めは、新入社員の退職に対する足かせとなり、公序良俗に反するという観点から、返還を求めるのはよろしくないという結論にいたった。
2.再雇用従業員の年次有給休暇
(問)定年退職後、嘱託社員として再度雇用する予定の従業員が、1ヵ月ほど休養をしたいとのことだが、年次有給休暇をどう扱えばよいのか。
(答)一旦雇用が途切れるので、また新たな雇用として年次有給休暇を与えるという考え方もあるが、雇用の終了時に再雇用の約束等がなされていれば、ある意味雇用が継続されていると考え、それに伴い年次有給休暇も継続すべきと思われる。途切れた期間の長さで判断する具体的数値基準はないが、一般的には1ヵ月程度であれば前出の考え方も可能である。
3.月2回勤務の場合の年次有給休暇
(問)自治体からの委託で事業をしているNPO法人に所属する労働者について、業務を行うのは月に2回程度だが、年次有給休暇は発生するのか。また、その根拠は。
(答)週5日もしくは30時間以上の勤務に満たない場合は、年次有給休暇は比例付与にて与えられるが、その場合の付与日数の計算式は、「付与日数=標準付与日数×週所定労働日数÷5.2」となる。小数点以下の端数の扱いは、通達において切り捨てとなっているため、勤務日数が月に2回程度では、年次有給休暇は発生しない。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年5月15日 金曜日
平成27年5月8日第385号
平成26年10月23日最高裁判決(広島中央保険生活協同組合事件)において、妊娠中の女性労働者に対する軽易業務転換(労基法65条3項)が男女雇用機会均等法9条3項(事業主は、女性労働者が妊娠、出産、産前産後休業を請求し取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない)違反と判断されました。
厚生労働省の新たな解釈通達についてご紹介します。
1.原則
妊娠、出産、育児休業等を「契機として」不利益に取扱った場合、原則、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法違反と判断されます。
※「契機として」は基本的に時間的に近接しているか否かで判断されます。時間的に近接しているかは「原則として、妊娠・出産・育児等の事由終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合」で判断されます。ただし、1年超えの場合であっても、事由終了後の最初のタイミングまでの不利益取扱いは「契機として」判断されます。
2.例外(不利益取扱いの例外)
1)業務上の必要性から支障があり、当該不利益取扱いを行わざるを得ない場合に、その業務上の必要性の内容の程度が、法の規定の趣旨に実質的に反しないものと認められるほどに、当該不利益取扱いによる影響の内容や程度を上回ると認められる特段の事情が存在する場合
※「特段の事情」には次のようなことが問われます。
経営状況悪化時-債務超過などにより不利益取扱いせざるを得ない事情があるか
不利益取扱いを回避する真摯かつ合理的な努力がなされたか
能力不足時 -妊娠等の事由発生以前から能力不足を指摘していたか
改善の機会を与えたか
2)契機とした事由又は当該取扱いに有利な影響が存在し、かつ、当該労働者が当該取扱いに同意している場合において、有利な影響や内容の程度が当該取扱いによる不利な影響の内容や程度を上回り、事業主から適切な説明がなされる等、一般の労働者であれば同意するような合理的理由が客観的に存在する場合
※合理的客観的理由には次のようなことが求められます。
・不利益取扱いの間接的な影響である降格、減給についても説明されたか
・適切な説明がされ、労働者が十分に理解し同意をしたか
・自由な意思の決定を妨げるようなことがなかったか
妊娠・出産・育休等の労働者に対して、安易な労働条件等の変更対応は禁物です。トラブル回避の為にも、十分な検討をしましょう。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年5月15日 金曜日
平成27年4月23日第384号
弁護士は、紛争が起きたときに仕事を依頼されます。そのため、どんなことで「トラブル」になるかがわかっています。その中から、「契約書」でトラブルにならないように、注意すべきポイントを3つ、お伝えします。今回は建築の際の契約を例にあげ、ご紹介します。
1.「何を」(目的物)を特定する!
「カントリー風の家」(目的物)を作ってください、という表現はトラブルを招きます。これは、建築業者の思う「カントリー風の家」と皆さんが思うものが違うからです。
トラブルを防ぐには、できるだけ、相対的な表現を避け、だれが読んでも、「同じ物」とわかる絶対的な表現にしなければいけません。
素材は何か、何をどのように作るか、など言葉で表現することが難しい場合には、図面、写真をつけるなどして、「どんな家」を作ることを頼んだのか、頼まれたのか、お互いに確かめておくことがトラブルを防ぎます。
2.変更の場合も合意書作成!
家の建築をしていく途中で「やはり出窓にしてくれない?」と言われ、了解。建築業者は、出窓にしたことで、費用が増大したため、その分を「追加工事100万円」として費用請求したところ、「予算の範囲内でやってくれると思っていた」と言われるトラブルもよくあります。
トラブルを防ぐためには、「変更」も現場の口頭やりとり等ですまさず、建築業者とご依頼主との間で、「追加工事契約書」として、合意の内容をはっきりさせておく必要があります。
3.損害賠償額の定め(違約金)
建築の完成期限に、家が完成しなかった。そのために生じた損害を賠償請求したい、というご相談もよくあります。
しかし、この損害は立証がとても難しいです。精神的な苦痛に対するお金の換算、細かい損害金(マンションの家賃代、通勤費など)の算出などが必要となり、とても手間がかかります。
そこで、あらかじめ「この契約の第○条に違反した場合には、金××円を支払う」という「損害賠償額の定め」をしておくと、このような細かい損害金の立証が要らなくなるので、トラブルを少なくできます。
契約を結ぶ際は以上のことをふまえましょう。
(スマイルグループ 弁護士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年4月 3日 金曜日
平成27年4月8日第383号
会社経営者のほとんどが生命保険に加入しています。加入目的を明確にして適正な保険に入っている方もいるのですが、なんとなくお付き合いで内容もよくわからないまま入ってしまったという方も意外と多く見受けられます。
そもそも生命保険加入の目的とはいったいなんでしょうか。
(株)セールス手帖社保険FPS研究所「企業経営と生命保険に関する調査」によると、社長の生命保険加入目的(法人契約の場合)は「社長の死亡退職金・弔慰金の準備」がトップ、次いで「万一に備えた運転資金の確保」「社長の勇退退職金の準備」「税負担軽減対策」「事業承継資金の準備」・・と続きます。
会社の置かれた状況よって生命保険の加入目的はおのずと異なります。
今回は第一に準備しておきたい、経営者に万一があった時に会社を存続させていくための「企業防衛資金」についてご案内いたします。
企業防衛資金の必要額は借入や運転資金に応じて算出
(1) 借入金返済資金=(借入金)×(返済割合)
経営者に万一のことがあれば、会社債務の返済を迫られる場合も想定されるため、借入金(支払手形、買掛金等含む)相当額程度を準備しておくことが必要です。
(2)当面の運転資金=(月額人件費等の一般管理費+月額販売費)×必要月数
事業が滞らないよう、当面の固定費を準備します。必要月数は企業の状況によって異なります。後継者が経営者としての力量を備えるまでの期間を考え、6ヵ月から12ヵ月程度が目安となります。
(3)納税準備資金={(1)+(2)}×0.6※
法人が受けとった保険金は益金となりますので、法人税等の課税対象になります。生命保険で準備する場合には「納税準備資金」も考慮しておかなければなりません。(※保険金が全額益金計上され、実効税率36.5%の場合、約0.6を乗じて算出)
(1)、(2)、(3)の合計が企業防衛のために必要な金額です。この金額を確認しないまま生命保険に加入すると、いざという時に必要な額に満たず役に立たなかったり、逆に余分な保険料を支払い続ける結果になったりします。会社の状況は変わりますので、年に一度は必要保障額を確認しておくことをおすすめします。
(スマイルグループ 社会保険労務士・FP)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年4月 1日 水曜日
平成27年3月23日第382号
パートタイム労働者は近年益々増加傾向で、平成25年は約1,588万人と雇用者総数(5,399万人)の約3割を占めています。また、パートタイム労働者の半数以上が賃金や会社、仕事等に不満を持っている等の統計(厚生労働省)が出ています。
このようなことを背景として、平成26年4月公布の「改正パートタイム労働法」が平成27年4月1日から施行されます。大きな改正ポイントは次の3点です。
※「パートタイム労働法」の対象「短時間労働者」とは、「1週間の所定労働時間を比べて、同一の事業所に雇用される通常の労働者より短い労働者」です。
1.通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取り扱いの禁止
<改正前>
次の3点を全て満たすパートタイム労働者は、賃金の決定、教育訓練、福利厚生施設の利用その他の待遇についてパートタイム労働者であることを理由として差別的取扱いが禁止されていました。
(1)無期労働契約
(2)職務の内容
(3)人材活用の仕組みや運用が通常の労働者と同一と見込まれる場合
<改正後>
上記(2)、(3)が通常の労働者と同一であると見込まれた場合、通常の労働者との差別的取扱いが禁止されます。つまり、有期労働契約者について(2)、(3)が正社員と同様の場合は、正社員の各種手当の支給対象となります。
2.パートタイム労働者の納得性を高める措置
<改正前>
事業主は、短時間労働者から求めがあった場合には、待遇決定にあたって考慮した事項を説明する義務を負っていました。
<改正後>
「雇入れ時」(有期契約は更新の都度)に、次の項目等を速やかに説明する義務を負います。また、文書明示事項に「相談窓口(担当者名、役職又は担当部署)」が追加されます。
(1)どのような賃金制度になっているか
(2)教育訓練の実施
(3)福利厚生施設の利用
(4)通常の労働者への転換等雇用管理の改善等に関する措置
3.パートタイム労働法の実効性を高めるための新たな制度
(1)無報告や虚偽報告などをした事業主に対する過料(20万円以下)の新設
(2)厚生労働大臣の勧告(雇用管理の改善措置違反)に従わない事業主の公表制度
4月1日からの施行に伴い、労働条件通知書の整備や、パートタイム労働者の雇用管理体制の見直しをしましょう。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年3月13日 金曜日
平成27年3月8日第381号
労働政策審議会は2月13日、厚生労働大臣に建議すべきであるとして、今後の労働時間法制のあり方について報告書をまとめました。
主な骨子案は次のとおりです。平成28年4月の施行が予定されています。
1.年次有給休暇取得促進
年次有給休暇日数が10日以上付与される労働者に対し、そのうちの5日分に
ついて、毎年時季を指定して与えることが企業に義務付けられます。
ただし、労働者が取得する場合や計画的付与により取得された場合の日数につ
いては、時季の指定は要しないとされています。これは、休みたい日に休めるメ
リットや、すでに年次有給休暇の消化に取り組んでいる企業の負担が増えない
よう配慮されています。
※年次有給休暇日数が10日未満のパートタイマー等については、対象に含まれ
ません。
2.フレックスタイム制の拡充
フレックスタイム制の清算期間の上限を現行の1ヵ月から3ヵ月に延長します。
併せて、1ヵ月当たりの労働時間が過重にならないように、1週平均50時間を超
える労働時間については、当該月における割増賃金の対象となります。
3.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル労働制)の導入
職務の範囲が明確で、一定の年収(1千万以上)を満たす労働者が高度の専門
的知識等を必要とし、従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常より高
くないとして省令で認められた業務(アナリスト、研究開発等)に従事させる場合は
労働基準法で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金の規定を適用し
ないとものとします。
この制度の導入については、健康管理上の特別な措置を要すること、必要な休
日を確保すること等様々な制約があり、対象となる労働者は限定されるように思わ
れますが、この制度をきっかけとして、成果型の労働評価や賃金体系の取り入れ
が積極的になることが考えられます。
4.中小企業における月60時間超えの時間外労働割増賃金率の適用猶予廃止
月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%超え)について、中小
企業への猶予措置が廃止されます。こちらのみ平成31年4月1日施行予定です。
その他にも労働者の健康確保に向けた取組みや長時間労働の抑制、労働時間の設定改善等を促進する内容の改正が予定されています。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年3月13日 金曜日
平成27年2月23日第380号
不動産の権利に関する登記を申請する場合には、原則として「登記原因を証する情報」を提供しなければならない(不動産登記法第61条)と、なっています。これを「登記原因証明情報」といいますが、その要件や内容をみていきます。
1.登記原因証明情報の意義
(1)登記申請をするためには「原因」が存在します。その「原因」の存在を登記官
が確認・審査する情報の提供を求め、登記申請の真正を担保することが目的
です。
(2)平成17年に不動産登記法が改正されるまでは、住所移転や氏名変更に伴
う登記名義人表示変更登記、真正な登記名義の回復や相続を原因とする所
有権移転登記等の場合には、初めから登記原因証書が存在しないものとして
申請書副本を添付していました。今後はこのような場合でも登記原因証明情
報を提供することになります。
2.登記原因証明情報の要件
(1)登記原因証明情報は「登記の原因となる事実又は法律行為に該当する具
体的な事実」を内容とするものでなければならないとされています。
(2)要件を満たすものであれば、処分証書(売買契約書、抵当権設定契約書
等)でも登記申請のために作成した報告形式のものでも登記原因証明情報
とすることができます。
(3)登記原因証明情報は、単一の情報に限られず、複数の情報の組み合わせ
であっても、登記原因を証するといえるものであれば足りるとされています。
ア)遺贈の場合...遺言書と戸籍の組み合わせ
イ)売買の場合...売買契約書と領収書の組み合わせ
(4)単独申請による登記や、実体法上一定の権利変動について特定の書面等
を作成して行うことが要求されているものに係る登記については、登記原因証
明情報の内容が特定の情報に限定され、又は登記原因証明情報の一部とし
て特定の情報を含むとされています。
ア)確定判決による登記...執行力のある確定判決の判決書の正本
イ)住所又は氏名の変更登記...住民票や戸籍
ウ)相続による権利移転の登記...戸籍・遺言・遺産分割協議書等
3.登記原因証明情報に記載されるべき具体的な情報
(1)登記申請情報の要項
(2)登記の原因となる事実又は法律行為
(3)作成名義人の署名又は記名押印
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年2月12日 木曜日
平成27年2月8日第379号
社会保険料の徴収方法は原則翌月徴収ですが、当月徴収としている会社もあるようです。そこで今回は当月徴収と翌月徴収の違い、注意点をご案内いたします。
1.言葉の定義
社会保険料・・・健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料のこと。
保険料は1ヵ月単位で徴収され、原則各月の最終日に資格を有している場合、保険料がかかります。つまり、入社(資格取得)月は1日に入社しても、末日に入社しても保険料がかかり、退職月は末日付で退職しない限り保険料はかかりません。
※同一月に入退社した場合のみ、1ヵ月分の保険料がかかります。
当月徴収・・・その月の保険料をその月の給与支払分から徴収していること。
(例)1月分保険料を1月支払給与で徴収
翌月徴収・・・その月の保険料を翌月の給与支払分から徴収していること。
(例)1月分保険料を2月支払給与で徴収
2.当月徴収の注意点(5日締め、当月15日払の会社を例に挙げます)
1)入社時(社会保険資格取得月)
前月6日~前月末日の間の入社従業員は、初めの給与で2ヵ月分の保険料の
徴収が必要です。例えば、4/30に入社した場合、4月分から保険料はかかり
ます。1回目の給与(4/30~5/5分、5/15支払)では、4月分と5月分の
2ヵ月分の保険料の徴収が必要です。出勤日が少ない場合は保険料よりも給与
が下回ることもあり、その場合の取決めをしておく必要があります。
2)退社時
前月の末日以外の日に退社した場合は前月分保険料の返還が必要です。
例えば、4/29に退社した場合、4月分の社会保険料はかかりません。その
ため、4月支払給与(3/6~4/5分)で4月分の社会保険料を控除している場
合は、5月支払給与(4/6~4/29分)で社会保険料を返還しなければなりま
せん。
※年末調整後の年末前の退職は1年の保険料額が変更となるため、留意が必
要です。
3.翌月徴収の注意点
1)社会保険料率が変更される月(3月、9月)に賞与を支払する場合
賞与は支払月の保険料率を乗じて、保険料を算出するため、保険料率が新しく
なる月は、翌月控除の場合、給与と保険料率が異なります。給与支払日より賞
与支払日が早い場合は特に給与計算ソフトの設定に注意しましょう。
当月徴収か翌月徴収か、その違いまでしっかりと把握したうえで、社会保険料
の控除をしましょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年2月12日 木曜日
平成27年1月23日第378号
産業保健総合支援センターは、産業医、産業看護職、衛生管理者等の産業保健関係者を支援するとともに、事業主等に対し職場の健康管理への啓発を行うことを目的として、全国47の都道府県に設置されています。
産業保健総合支援センターの主な事業内容をご紹介します。特に小規模事業場の事業主や労働者にとっては大変心強い味方となりますので、ぜひご利用ください。
1.窓口相談・実地相談(事前予約が必要)
産業保健に関する様々な問題について、専門スタッフ(産業医、労働衛生工学、メンタルヘルス、労働衛生関係法令、カウンセリング、保健指導)が窓口又は電話でご相談に応じ、解決方法を助言します。また、必要に応じ専門スタッフが現地まで赴き、具体的方法を助言します。
2.研修
産業保健に関する専門的かつ実践的な研修を実施します。また、センター以外の団体が行う研修には、教育用教材の貸出、講師の紹介等の支援を行っています。
3.メンタルヘルス
専門スタッフによる相談窓口や事例検討会の実施を行います。またメンタルヘルス対策の普及促進のため個別訪問支援や管理者向けメンタルヘルス研修を行っています。
4.情報提供
産業保健に関する図書・教材等の閲覧・貸出、コピーサービスを行います。また、メールマガジンの配信でタイムリーな情報提供も行っています。
5.広報・啓発
職場における健康管理の重要性を事業主に正しく理解していただくため、事業主セミナーを開催する等の広報・啓発活動を行います。
6.50名未満の事業場に対する産業保健活動支援
脳・心臓疾患のリスクの高い労働者に対する健康相談・保健指導やメンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導を行います。また、健康診断実施結果に基づく医師の意見聴取・事後措置の実施支援や長時間労働者への医師による面接指導、更に個別訪問による産業保健指導等を行っています。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年1月15日 木曜日
平成27年1月8日第377号
平成25年4月8日、第335号で紹介したマイナンバー制度の続編です。
政府発表によるマイナンバーとは、住民票を有する全ての人に対して1人1番号として、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認されるため活用されるものとされています。
このマイナンバー制度が何故導入されるのか・・・政府発表によると、
(1)個人ごとの所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を
不当に逃れることや不正な給付防止をすることにより、公平・公正な社会を実現
する。
(2)国民の利便性の向上を図ることにより、行政手続が簡素化され、添付書類の
削減等により国民の負担を軽減。また、行政機関から様々なサービスのお知ら
せを受け取ることができる。
(3)行政の効率化により、行政機関や地方公共団体で作業が重複している事柄に
ついて無駄の削減により、時間・労力の大幅な削減ができる。
が主な目的とされています。
平成27年10月、マイナンバー(個人番号)が市区町村から、住民票住所宛にマイナンバーが記載された「通知カード」が送られる予定です(中長期滞在者や特別永住者等の外国人にも通知)。「通知カード」には、氏名、住所、生年月日、性別、12桁のマイナンバーが記載されています。
平成28年1月以降は、「個人番号カード」が各自の市区町村申請に基づき、交付が可能です。この「個人番号カード」は、本人の写真が表示されるとともにICチップが入り、身分証明証として利用できるほかe-Tax等の各種電子申請に利用できます。
また、平成28年1月からは、社会保障、税、災害手続でマイナンバーが必要となります。雇用保険・社会保険の資格取得、年金の資格取得や確認・給付、税務署に提出する確定申告書、届出書等が該当します。その為、其々の事業所は各従業員のマイナンバーの取得が必要となります。マイナンバーは銀行預金口座にも適用され、当初は任意で登録を呼びかけ、その後義務化の是非について検討される予定です。
マイナンバーは一生使用するもので、番号が漏洩し、不正に使われるおそれがある場合を除き変更されません。個人情報管理を含め適切な管理が必要となります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2015年1月15日 木曜日
平成26年12月23日第376号
1.原則は縛れない
退職後、元職員には、「職業選択の自由」が認められています。そのため、例えば、会社が時間をかけ、教え込んだ金型製造ノウハウ、技術を用いて、元職員が会社と同業の金型製造業(競業)を始めることも原則として自由です。しかし、元社員が、会社が開拓した顧客に営業をし、顧客を奪っていったとしたら、納得できるでしょうか?
2.競業避止義務に関する合意の有効要件
このようなことを防ぐためには、あらかじめ「競業避止義務」を定めた就業規則、合意をしておくことが大切です。但し、「職業選択の自由」との関係から、「合理的範囲」と言えなければ無効となってしまいます。
その際のポイントは、裁判例を検討すると、
(1)労働者の地位
(2)使用者の固有の秘密・ノウハウの保護を目的とすること
(3)競業制限の対象職種・期間・地域が不当な誓約にならないこと
(4)代償措置の有無に
あるとされます。
3.企業側の出来る対策とは
裁判例から2.のポイントをふまえて、具体的に競業避止義務の「合理性」の判断をしてみます。
(1)営業職の場合、内勤の職員に比べて、その「地位」から合理性が認められや
すいでしょう。技術系専門職の場合、長期間その専門技術を身につけたのに、
その専門を活かす仕事がまったく出来ないと、合理性が認められにくい方向に
働きます。
(2)顧客台帳、技術、ノウハウが「秘密」として、特定の職員にしかアクセスできな
いなど、保護、管理されている場合、「ノウハウ」の保護のため、競業避止義務
が認められやすいでしょう。
(3)期間については、1年以内、最長でも2年以内を目途にした方がいいでしょう。
地域、職種も限定しておかないと、合理性が否定されやすいです。
(4)競業避止義務を課すかわりに、金銭の支給があると認められやすい方向にな
ります。職業を縛ることになるので、労働の対価とされる「退職金」に加えて「秘
密保持手当」等の支給がある方が、よりよいでしょう。
大まかに言うと、希望する職業が出来ないことによる元職員の不利益があまりに大きく、それに対して、会社側の守るべき利益が少ない場合には、合理性が認められません。合理的かどうかを迷う場合には、社会保険労務士、弁護士などに相談しましょう。
(スマイルグループ 弁護士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年12月11日 木曜日
平成26年12月8日第375号
平成26年11月14日、第8次社会保険労務士法が改正され、「出廷陳述権」をはじめとする社会保険労務士の業務範囲の拡大等が行われました。
1.ADRにおける紛争の目的の価格の上限の変更
社会保険労務士が関与できる個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(ADR)における紛争の目的の価額の上限が現行の60万円から120万円に引き上げられることとなりました。今までは、60万円を超える仕事は、弁護士と共同して行わなければなりませんでしたが、社労士だけで120万円までの仕事ができるようになりました。これにより、ハラスメントや賃金不払いなどが問題化する中、労働関連法に精通する社労士の業務範囲、役割が広がったといえます。
なお、行政型ADR(都道府県労働局や道府県労働委員会のあっせんなど)における特定社労士の代理権には今まで通り価格の制限はありません。
2.裁判所において弁護士の補佐人として出廷し陳述できること
今までは、社労士があっせん等裁判外におけるADRで労働紛争の代理人として仕事をすることができていましたが、今回の改正によって地方裁判所以上の審級における社労士の出廷陳述権が新しく付与されるようになりました。非訴訟事件も対象となるので、労働審判の審判廷においても陳述権があります。ただし、弁護士が受任している側に立っての陳述に限られ、あくまで弁護士と共同して陳述権を述べる機会が与えられたという考えです。
裁判所で裁判長や労働審判委員会の許可が不要となったことから、今までのように個別に許可を得る必要がなくなり、社労士は権利として出廷し陳述することが可能となります。新しい業務が創設されることとなり、今後の社労士の活躍が期待されます。
※陳述権(出廷陳述権)とは、訴訟が提起された処分につき、裁判所の許可を得ずして当事者または訴訟代理人と共に裁判所に出廷して陳述する権利のことをいいます。社労士が、対象となる事件に対して、社労士として自ら意見を述べることができるということです。
3.社会保険労務士法人の設立方法の変更
今までは2人以上の社労士が必要だった社会保険労務士法人の設立が、社労士1人でも可能となりました。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年12月11日 木曜日
平成26年11月23日第374号
過労死や過労自殺の防止を「国の責務」とした「過労死等防止対策推進法」が平成26年11月1日、施行されました。厚生労働省によると、平成25年度にクモ膜下出血や心筋梗塞などの脳・心臓疾患で労災認定されたのは306人、そのうち死亡に至ったケースは133人に達し、うつ病などの精神疾患でも436人が認定され、未遂を含む自殺者は63人にものぼります。また、日本の「過労死」は国際社会でも問題化され、2013年国連から日本政府に対して、過労死防止対策を強化するよう勧告も出ています。これらを背景に、厚生労働省が過労死対策を本格化させました。
1.目的(概略)
近年、我が国においては過労死が多発し、大きな社会問題となっていること及び過労死が本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であり、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与する。
2.過労死等の定義
業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害。
事業主等の責務
平成12年、最高裁までいった「電通事件(過労自殺)」。大手広告代理店Y社に勤めていたA(大卒新入社員)が、長時間に及ぶ時間外労働を恒常的に行っていて、うつ病に罹患し、入社1年5ヵ月後に自殺。最高裁は「Aが恒常的に著しく長時間にわたり業務に従事していること及び健康状態が悪化していることを認識していながら軽減措置を採らなかった。」として、Y社に民法第715条の使用者責任を認め、最終的には、会社が約1億6,800万円を支払うとの内容で和解が成立しました。
また、平成22年の「日本海庄や事件」では、入社4ヵ月後にA(労働者)は急性心不全により死亡。Aの1ヵ月の最低支給額は、「月80時間の時間外労働をすることが前提となっている給与体系」で、会社に安全配慮義務違反を認めたことはもとより、会社の取締役にも「労働条件を改善することなく放置していた。」として不作為の責任を負わせています。
今回の法律により、職場において、過重労働になっていないか、時間外労働や、従業員の健康等に再度、チェックし、配慮をするように努めましょう。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年11月14日 金曜日
平成26年11月8日第373号
近年、非正規社員が増加しており、正規社員と比較して、賃金等労働条件が低く、雇用が不安定であり、能力開発の機会が乏しいことから、正社員としての雇用機会を希望するものも多くなっています。しかし、企業の人材活用の仕組みや働き方が異なるため、現状のままで非正規社員の正社員化をすすめることは、企業にとってだけでなく、非正規社員にとっても困難な場合が多いです。働き方の2極化を緩和し、ワークライフバランスと優秀な人材確保の為、職務、勤務地、又は労働時間を限定した「多様な正社員」の普及が厚生労働省により検討されています。
1.多様な正社員の効果的な活用が期待できるケース
(1)勤務地限定正社員
・育児や介護の事情で転勤が難しい者について就業機会の付与と継続
・改正労働契約法に基づく有期雇用から無期転換の受け皿として活用する。
・非正規雇用からの受け皿として活用する。
(2)職務限定正社員
・金融やIT等で特定の職務等、高度に専門的なキャリア形成が必要な職務に
おいて、プロフェショナルとしてキャリア展開していく働き方として活用する。
・資格が必要な職務、同一企業内で他の職務と明確に区別できる職務に活用
する。
・高度な専門性を伴わない職務に限定する場合、職務の範囲に一定の幅を持
たせ円滑に活用する。
(3)勤務時間限定正社員
・育児等の事情で長時間労働が難しい者に、就業機会の付与と継続可能とす
る。
・労働者がキャリアアップに必要な能力を習得する際に自己啓発のための時
間を確保できる働き方として活用できる。
・勤務時間限定の働き方の前提として、職場内の適切な業務配分、長時間労
働を前提としない職場づくりが必要である。
2.労働者に対する限定部分の明示とその効果
転勤、配置転換の際の紛争の未然防止のため、職務や勤務地に限定がある場合には、限定の内容について明示することが重要である。又、企業にとっては優秀な人材を柔軟に確保できる効果がある。
「限定された社員」の待遇及び社内体制の導入準備については、給与・昇任に関する取扱い等専門家を交えて、自社に応じた制度の設計をすることが必要となります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年11月14日 金曜日
平成26年10月23日第372号
法制審議会の民法(債権関係)部会が平成26年8月26日に開催され「民法(債権関係)の改正に関する要項仮案」が決定されました。来年2月に法務大臣に正式に答申し法務省は来年の通常国会に民法改正案を提出する方針です。債権法の抜本改正は、明治29年に民法が制定されて以来、初めてで、消費者保護に軸足を置いた見直しになっています。
1.改正の目的
(1)民法を社会・経済の変化(現在の取引事情)に対応させること
(2)国民一般に分かりやすいものにすること
・判例ルールの明文化
・不明確な条文の明確化
・書かれていない前提・原理・定義を補う
2.改正の主なポイント
(1)時効期間の統一・・・様々な時効期間を5年に統一。
(2)約款に関する規定を新設・・・契約成立後の一方的な内容変更を禁止など。
(3)意思能力の規定を新設・・・判断力が弱い人が結んだ契約を無効にできる。
(4)誤解していた契約は取り消し可能に。
(5)欠陥商品の修理・交換・減額などの請求・・・消費者の対処方法が広がる。
(6)敷金のルールの明確化・・・経年劣化の修繕は、借主に義務がない。
(7)連帯保証人の届出義務・・・個人が中小企業の連帯保証人になるためには公証人との面談が必要。但し、例外あり。
(8)殺傷事件などの損害賠償請求権を長期化・・・被害に遭ってから20年、損害賠償請求権を知ってから5年。
(9)法定利率を引き下げて変動制に・・・3%にして、3年に一度見直す。
(10)債権譲渡禁止特約の緩和・・・将来見込まれる収益を第三者に譲りやすくする。
3.身近なケースでは
(1)飲食店のツケ・・・時効1年→5年
(2)お金の貸し借り・・・時効10年→5年
(3)自動車保険料は値上げの可能性も・・・。
法定利率の引き下げに伴い、交通事故等で生きていれば得られた利益(逸失利益)から、将来得られるはずだった利益(中間利息)を控除します。このときの「除額は法定利率による」(平成17.6.14最高裁第三小法廷判決)とされていますので、結果として、加害者が支払うべき補償額が増加することになります。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年11月14日 金曜日
平成26年10月8日第371号
スマイル新聞第367号では「介護離職」回避のため、親の介護と仕事の両立支援の制度づくりについてご案内しました。今回は補足説明いたします。
1.自治体が実施する介護サービス
市区町村の介護保険制度や介護サービスについての相談先を知らせる各自治体の窓口を把握しましょう。
【窓口】
・各地域包括支援センター
・市区町村の介護や福祉関係の担当課
・社会福祉協議会
【サービス例】
・緊急一時入所サービス ・在宅訪問歯科保健診療 ・家事介護援助 ・電話訪問
・緊急通報器貸し出し ・給食の配達 ・日常生活用具購入補助 ・リフォーム補助
・徘徊検索 ・はり、きゅう、マッサージ券配布 ・紙おむつ支給 ・寝具消毒感想
・出張理美容 ・話し相手 ・成年後見制度利用支援 ・健康教室 ・賃貸支援
・家族介護慰労金支給 ・火災報知器設置支援 ・介護タクシー券配布
2.制度拡充を検討する際のポイント
企業が両立制度の拡充を検討するポイントとしては次のようなことがあります。
・勤務地限定の正社員制度を採用する。
・介護休業の分割取得を認める。
・時間単位の年次有給休暇を採り入れる。
・実家に週末帰省した従業員が月曜日の朝に実家から出社することができるように月曜日の始業時間を繰り下げられるようにする。
・1月当たりの上限を決めて半日単位での在宅勤務を可能にする。
3.将来の介護に備えて検討しておくべきこと
以下のようなことを各従業員が用意し、「介護しながら働き続ける環境を作るのは自分である」と意識啓発し、各々が認識しておくことも重要です。
・親が望む介護はどういうものか、兄弟姉妹や親戚も含め介護の役割分担を考える。
・地域包括支援センターに足を運んでどんなサービスがあるのか調べておく。
・親の変化に気づいたら、すぐに連絡が入るよう実家の近隣の人とつながっておく。
・宅配弁当や電気ポットなどの見守りサービスの利用を検討する。
・廊下や風呂場に手すりをつけるなど日常生活上の安全を確保する。
人財の損失をしないように制度の作成をしましょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年9月29日 月曜日
平成26年9月23日第370号
平成27年4月1日からパートタイム労働法が改正され、施行されます。その改正内容を簡単にご紹介します。
今やパートタイムで働いている人は、全労働者の25%を占め、日本の労働力に欠かせない存在となっています。しかし、その実態は、パートタイムというだけで正社員に比べ、劣った労働条件で働いているのが現状です。そうした状況を法によって守るべく今回の改正となりました。
1.パートタイム労働者の公正な待遇の確保
(1)差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
(法第9条)
正社員と差別的取扱いが禁止される労働者の対象範囲に、これまで外されて
いた有期契約労働者も含められます。
(2)短時間労働者の待遇の原則の新設(法第8条)
パートタイム労働者の待遇に関する考え方の原則規定が明文化されます。つ
まり、職務の内容・人材活用が同じならその待遇に不合理は認めないというこ
とです。
(3)距離、経費に無関係の一律通勤手当は均衡確保努力義務対象
(施行規則第3条)
「通勤手当」という名称であっても、距離や実際かかっている経費に関係なく
一律に金額を支払っているような職務の内容に密接に関連支払われている場合
正社員との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務内容、成果、意欲、能力、
経験等を勘案して決定するように努めなければなりません。
2.パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
(1)パートタイム労働者を雇入れたときの説明義務の新設(法第14条1項)
事業主は実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければなり
ません。
(2)説明を求めたことによる不利益扱いの禁止(指針第3の3の(2))
(3)パートタイム労働者からの相談対応の体制設備を義務化(法第16条)
(4)相談窓口の周知(施行規則第2条)
パートタイム労働者を雇入れの際の労働条件通知書等の文書に相談窓口
の明示が義務付けられます。
(5)親族の葬儀のため、勤務しなかったことを理由とする解雇などは不適当
(指針第3の3の(3))
3.パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
(1)厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設
(法第18条第2項)
(2)虚偽報告などをした事業主に対する過料(20万円以下)の新設
(法第30条)
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年9月11日 木曜日
平成26年9月8日第369号
育児介護休業法第11条では、「要介護状態にある家族を介護する従業員は、対象家族1人につき、通算93日間、1要介護状態ごとに1回」介護休業を取得することが出来るとされています。
1.行政通達上の定義
「介護」...歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること
「要介護状態」...負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
介護保険制度における「要介護状態」と必ずしも一致するものではありません。
また、介護認定とも関係ありません。
2.介護休業期間(通算93日間)の趣旨と介護休業取得の可否
実は、法律における介護休業期間は介護施設への入所準備、介護認定の申請等の準備期間とし、従業員本人が直接介護をすることを目的としていません。仕事と介護の両立を準備する期間とされています。
対象家族が特別養護老人施設に入所している場合、従業員による対象家族への歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与する必要がない期間と考えられますが、施設の方から家族の介護を求めているような場合、制度利用は可能と判断されます。
しかし、「精神的支え」や「看取り」の様なときで、歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜供与を伴わない純粋な要件の場合、介護休業の対象には当たりません。
3.「1要介護状態ごとに1回」とは
要介護状態が異なるという意味であり、要介護状態に該当した人がいったん要介護状態に該当しなくなり、その後再び要介護状態に該当した場合を指します。
要介護状態にあった対象家族が、別の病気を併発し、更に症状が重くなった場合は、いったん要介護状態に該当しなくなったとはいえないため、「1要介護状態ごとに1回」には該当せず、介護休業制度の利用ができません。
しかし、会社の裁量により制度利用を認めることは法の介護休業制度を上回ることであり問題ありません。但し、雇用保険介護休業給付金は支給されない可能性があります。
また、会社側から求める「異なる要介護状態」であることの証明は、介護休業申出の要件とはされていません。従って、異なる要介護状態かどうかは従業員本人からの申出に拠る場合で判断せざるを得ないかと考えます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年8月29日 金曜日
平成26年8月23日第368号
労働基準法38条の2第1項では、「事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」と定められており、会社の外で働く営業職や新聞記者のような、労働時間を正確に把握するのが難しい事業場外の仕事につく従業員について、実際の労働時間にかかわらず、決めた時間を労働時間としてみなす、みなし労働時間制を認めています。
しかし、みなし労働時間制が認められないケースもあります。
1.みなし労働時間制認められなかった事例
(1)阪急トラベルサポート事件
平成26年1月24日、最高裁判所は旅行添乗員の業務につき、労働基準法の
いう「労働時間を算定しがたいとき」にあたらないと判断しました。
つまり、みなし労働時間で賃金を計算することは認められないとの判決が出ま
した。
(2)この事件のポイント
この事案では、添乗員の業務は予め旅行日程が定められ、これに従って行動
するように管理されていること、変更の場合には会社に確認がいることなどから、
「労働時間を算定し難いとき」にあたるとはいえないとしています。
つまり、単に事業場外で業務に従事したということだけでは、みなし労働時間制
とは認められません。
営業職で、何時まで営業するのか、何件営業するのかを従業員に一切任せて
いるような「使用者の具体的な指揮監督が及ばないような場合」でなければ、
「労働時間を算定」できると裁判所は考えているということがポイントです。
2.企業側の対策
(1)事業場外で働く従業員に具体的指揮、監督をしているかを検討すること
細かな指示がある場合、みなし労働時間制は適用されないと考えましょう。
(2)みなし労働時間制の適用がない場合も考え、労働時間の把握をすること
労働時間を把握し、所定労働時間に対する賃金と時間外労働に対する
割増賃金とは明確に区別して賃金を支払いましょう。上記の判例でも、
日当に割増賃金部分が含まれていると企業側が主張しましたが、日当に
区別がないため認められていません。
(3)素早い対応・解決
従業員から割増賃金等の請求があった場合、速やかに社会保険労務士、
弁護士などの専門家に相談し、解決をはかりましょう。上記の裁判でも、
賃金と同額の「付加金」が請求され、認められました。その場合、賃金の2倍
の額を支払うことになってしまいます。
裁判での見込みを素早く知って,できれば裁判前に対処しましょう。
(スマイルグループ 弁護士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年8月 8日 金曜日
平成26年8月8日第367号
昨今、急激な少子高齢化とライフスタイルの変化により、
親の介護が原因で離職をする方も少なくありません。
このような「介護離職」により、優秀な人財を喪失しないために、
企業には仕事と介護の両立支援の制度づくりが求められています。
そこで、両立支援の制度づくりについてご案内します。
1.両立支援には「お互い様」の風土づくりが大事
親の介護をする従業員の年齢は一般的に40歳代後半以降です。
そのため、そう簡単には他の従業員に任せられない業務を担当している人も多く、
たとえ企業に両立支援制度が整えられていたとしても、
実際に利用することが難しい人もいるでしょう。
そこで必要とされるのは職場全体の意識を変えることです。
誰もがいつ、どのような状況で時間制約を持つかわからないと考え、
「お互い様」の風土を作ることが大事であり、
企業は支援する方針を明確にし、全従業員に表明することが重要です。
2.制度づくりの手順
(1)現在の介護支援制度と介護保険制度の概要の周知
介護休業、介護休暇、短時間勤務制度など
企業の介護支援制度の仕組みを周知するだけでなく、
市区町村の介護保険制度や介護サービスについての相談先を知らせると、
従業員にとって介護しながら、働く自分を具体的にイメージしやすくなります。
(2)介護をしている(していた)従業員に対するヒアリング
介護経験のある従業員に対するヒアリングや、
全従業員に対するアンケートの実施などにより、
その企業にあった介護支援の制度や取組みを検討することができます。
(3)現在の介護支援制度の拡充や運用面の工夫、その他意識啓発の取組の検討
(2)の結果を踏まえて、勤務地限定の正社員制度や
育児・介護中の転勤猶予制度などの制度の拡充や運用面での工夫を図ります。
また、実際に利用することができるように、
管理職研修やキャリアデザイン研修の実施や
仕事との両立に対応できる相談窓口を設置するなど
意識啓発の取組みについても検討します。
(4)両立支援の周知と意識啓発の実行
制度導入を従業員に積極的に周知することで意識啓発し、
職場風土を変えましょう。
また、「介護しながら働き続ける環境を作るのは自分自身でもある」
ということを意識啓発する必要があります。
そのためには、会社全体でワーク・ライフ・バランスを意識し、
業務や体制を見直し、社員間の良好なコミュニケーションを心掛けることです。
上記のように制度づくりを実施し、人財の損失を阻止しましょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年8月 1日 金曜日
平成26年7月23日第366号
化学物質による健康被害が問題となった胆管がん事案の発生や、職場から受けるストレスによる精神障害を原因とする労災給付の支給決定の件数の増加等、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、また、労働者の安全と健康の確保対策の一層の充実のため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が平成26年6月25日に公布されました。
改正は全部で7項目ありますが、なかでも改正の目玉であるストレスチェックについて記載します。労務管理や就業規則の見直し等が必要か、検討してみましょう。
「労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師又は保健師による検査(ストレスチェック)」について(施行日は公布日から1年6ヵ月以内、今後政令で規定)
(1)常時使用する労働者(厚生労働省は「基本的に健康診断の対象者と同様と
想定している」とコメント。)が50人以上の事業場は、年1回、従業員にストレス
チェックを実施することが義務付けられます。
(2)検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本
人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
(3)検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があれば医師による
面接指導を実施することが事業者の義務となります。
(4)面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を
講じることが事業主の義務となります。
また、(3)の申し出をした労働者に対し、不利益な取り扱いをしてはならず、
(4)に関しては、今後事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るた
めの指針が公表されます。
(5)検査や面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た
労働者の秘密を漏らしてはならず、これには、行為者も事業者にも罰則があり
ます。
しかし、医師の意見を聴いた上で、作業の転換、労働時間の短縮等の措置が必要となった場合、きちんと対応できるでしょうか?意図的とまでは言わなくとも特定の業務を忌避する労働者が出る可能性があったり、当該措置を実施した後に不調者の職場復帰プログラムを作成したりする必要があるかもしれません。また、ストレスチェックは無料ではないので、予算措置を行う必要も出てきます。
50人未満の事業場は当分の間、ストレスチェックの制度は「努力義務」ですが、きちんとした制度を考える良い機会かもしれません。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年8月 1日 金曜日
平成26年7月8日第365号
労働災害(以下「労災」と言う。)が発生すれば、労災保険から各種の補償給付がありますが、被災者本人の人生設計に支障が生じ、企業にも負担が生じます。
勿論、事後の補償給付は大切ですが、いかに予防するかの工夫が最も大切です。
過去の発生事例から予防方法を考えることができますので、参考にしましょう。
1.印刷会社オフセット印刷機に腕を巻き込まれた事案
印刷機の配紙ローラーの埃を取り除くため、労働者がローラーを回転させ、刷毛で清掃作業をしていたところ、着衣の袖がローラーに巻き込まれたもので、厚さ1ミリ以下の隙間に腕を引き込まれ、肩関節まで巻き込まれたところで機械が停止した。
<負傷程度> 右腕挫滅、頚椎骨折
<災害の原因> 作業着の長袖のボタンが外れていたため、袖から巻き込まれた
もの。
<予防方法> 安全管理規程において作業前の着衣点検の実施を定め、確実
に励行する。
2.ひき肉製造機(ミートチョッパー)に指を巻き込まれた事案
業務多忙で多量の原料肉を詰め込んだため、機械内部で詰まりが生じ、手を入れて詰まった肉を除去していたが、詰まりが除去できたところで機械が動いたため、刃に指を巻き込まれた。
<負傷程度> 右全指切創全治3ヵ月
<災害の原因> 電源を切らなかったため、機械内部の詰まった肉を取り除いた
時点で、刃が作動したため、指が巻き込まれたもの。
<予防方法> 詰まった肉の除去作業時は、電源を切ることを安全管理規定に
定めて徹底する。
10人未満の事業所では、就業規則を労働基準監督署へ届け出る必要はありませんが、労災を予防するためには、就業規則に加えて安全管理規定を定め、作業開始前の準備の点検及び作業方法について、手順を定め、励行の徹底を図ることが必要です。
就業規則は事業所と従業員を労災から守る大切な定めです。小さな規則が大きな安全を担保します。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年8月 1日 金曜日
平成26年6月23日第364号
相続が開始した場合の、主な相続財産の範囲についてまとめてみました。
民法では『相続人は...被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。』と、定められています。
1.親族法上・相続法上の権利義務
(1)親族法上の権利義務(離縁請求権・認知無効確認請求権など)は、原則とし
て対象となりません。但し、既に具体化している権利(内縁の不当破棄に基づく
慰謝料・財産分与請求権・遅滞に陥った過去の扶養料など)については、相続
の対象となります。
(2)相続法上の権利義務も、原則として相続の対象とはなりませんが、相続の
承認・放棄をする権利や遺留分減殺請求権などは相続の対象となります。
2.占有権
民法上、明文の規定はありませんが、学説及び判例は占有権の相続を認めています。
3.保証債務
(1)通常の保証債務は主に相続の対象となり相続財産に属します。
(2)身元保証債務・包括的信用保証債務については、相続の対象となりません。
4.生命侵害による損害賠償請求権保証債務
(1)財産的損害について、判例は損害賠償請求権の相続を肯定しています。
(2)精神的損害(慰謝料)についても、『これを放棄したものと解する特別の事情
がない限り』相続の対象となります。(最判.昭43.8.2)民法上、明文の規定は
ありませんが、学説及び判例は占有権の相続を認めています。
5.生命保険金請求権
(1)保険契約で、被相続人が自分を被保険者とし、かつ、自分を受取人としてい
る場合は相続人が受取人たる地位を相続します。
(2)保険契約で、被相続人が自分を被保険者として、受取人を別の特定人とし
ていた場合には、その特定人が固有の権利として原始取得します。
(3)保険契約で、被相続人が自分を被保険者とし、受取人を単に相続人として
いた場合、死亡時の相続人が固有の権利として相続します。
6.香典
香典は相続財産に属しません。遺族に対する慰謝と、葬儀費用の儀礼的分担を意味するものとされ、前者は遺族全員が、後者は葬祭の主催者が取得するものとされています。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年6月 5日 木曜日
平成26年6月8日第363号
労働災害は態様によりリスクの深刻さは異なりますが、死亡等の災害発生時は企業の社会的責任が厳しく追及されることもあります。そこで、今回は企業が負う責任とリスク低減対策をみていきましょう。
1.民事・刑事上の責任
(1)安全配慮義務
-使用者が従業員の安全や健康に配慮しなければならない義務
過労死や過労自殺を含む労働災害の場合、安全配慮義務違反があったとして、賠償損害額が高額になる傾向があります。
(2)使用者責任
-従業員が第三者に損害を与えた場合に使用者が負う責任
企業は人を使用して利益を得ているため、従業員使用により生じた損害についても企業に責任を負わせるという考えであり、企業側に過失がなくても責任を問われることもあります。
(3)労働安全衛生法を遵守する義務
労働災害における刑罰法規である労働安全衛生法では災害防止のため、多くの措置義務を課し、義務違反には罰則規定の適用があります。そのため、労働災害が起こっていない場合でも、法違反により刑事責任が問われることもあります。
(4)両罰規定による責任
労働安全衛生法違反の場合、違反した該当者だけでなく、法人等も罰せられます。
以上の責任以外にも、労働災害が発生時は機械設備や足場、建物等の使用停止命令などの行政処分を受けるリスクや労働者に対しての休業補償責任、社会的な信用や評価が失われる社会的リスクがあります。
2.労働災害の発生リスクを低減するためのポイント
(1)経営幹部がリスク感覚を持つ
自社の災害リスクを認識し、普段から対策を講じることが大切です。そのためにも、経営幹部がリスク感覚を養っていることが必要です。
(2)安全衛生管理規程の整備
緊急時に冷静に対応できるよう安全衛生管理規程で危機管理体制を定めましょう。
(3)非定常作業のリスク軽減対策
通常作業と異なる作業をされる際に労働災害が起こるリスクは非常に高く、非定常時においても所定の安全衛生管理体制の下、作業管理することが求められます。そのため、非定常作業は許可制や届出制にし、作業計画・作業手順をしっかりと把握し、リスクアセスメントを行なうことが大切です。
以上を踏まえ、安全な職場作り、労働災害のリスクヘッジをしていきましょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年6月 5日 木曜日
平成26年5月23日第362号
割増賃金を計算するとき、どの手当を計算に含めていますか?一般的には労働基準法第37条第5項で定められた7種類の賃金(家族手当、通勤手当、子女教育手当、別居手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金)以外の賃金を割増賃金の計算の基礎に含めているのではないでしょうか。しかし、それについては誤解しがちなケースもあります。
誤解1
労基法第37条第1項及び第4項では、割増賃金は「通常の労働時間の賃金」を基礎とすると規定されており、上記7種類の手当の名称以外は全て割増賃金の計算の基礎に含まなければならないわけではありません。例えば、会社によって「扶養手当」など、名称は異なるけれど、実質的には家族手当と同様の手当を支払っていることがあります。このような場合は、名称にとらわれず実質的に判断し、割増賃金の計算の基礎から除外することができます。
また、労基法で定められた7種類の賃金であっても、例えば
(1)扶養家族の有無やその人数に関わらず一律で支払われている家
族手当
(2)実際の通勤距離に関わらず1日○○円と決めて支払われている
通勤手当
(3)賃貸住居者には○万円、持ち家居住者には○万円と決めて支払
われている住宅手当
など、従業員に一律に支給されているものについては除外することはできません。
誤解2
深夜労働の場合、所定労働時間の労働であっても2割5部の割増賃金を支払わなければなりません。例えば賃金に「深夜労働手当」などという名目で深夜労働の割増分(2割5分)を支払っている場合、上記7種類の割増賃金から除外できる手当には当てはまらないので、時間外労働や休日労働の割増賃金の算定の基礎にこの割増賃金を含めて計算しなければならないと考えてしまいがちです。ですが、これはあくまでも深夜労働に対する割増賃金であり、労基法第37条に定める「通常の労働時間の賃金」には含みませんので、割増賃金の計算の基礎から除外することとなります。
間違いやすい話ですが、通常はAという作業をして賃金を支払われている労働者が、特殊作業手当が支払われるBという作業を時間外に行った場合、その時間外労働に対する割増賃金の計算の基礎は、作業に対する賃金となり特殊作業手当を含めた賃金が計算の基礎となりますので、ご注意ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年5月 8日 木曜日
平成26年5月8日第361号
労働相談における労働者側の事例として「会社から給与明細書が貰えない」と言う相談がよくあります。今回は給与明細書の法的根拠に触れてみたいと思います。
1.労基法上の根拠
労基法上には定めが無く、行政通達(平成10年9月10日基発530号)により『使用者は、口座振込などの対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払いに関する計算書を交付すること』とされています。
(1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2)源泉徴収税額、社会保険料額等の控除額
(3)口座振込等を行った金額
※この通達は、「口座振込における通達」ですが、多くの会社が給与を口座振込みによって支給していることから、現金支給の場合も準用されるものと思われます。
尚、通達は法律ではありません。
2.各労働・社会保険法上の根拠
労働・社会保険料の各制度をみると、次の各々の法の条文によりそれぞれ保険料を控除する際、明細書の発行が義務付けられています。
(1)雇用保険料の控除-労働保険の保険料に関する法律第31条第
1項
(2)健康保険料の控除-健康保険法第167条第3項
(3)厚生年金保険料の控除-厚生年金保険法第84条第3項
また、所得税法第231条では、給与を支払う者は支払いを受ける者に支払明細書を交付しなければならないと定められています。
以上のごとく、労基法上では法的な根拠がなく行政通達ですので、給与明細書の発行について労働基準監督署へ相談をしても、監督署は「助言」はできても法的に罰することはできません。しかし、各法制度の中で保険料等の控除額を記載した明細書の発行が義務付けられています。
民事上のトラブルがあった場合、困るのは使用者側であり、給与明細書を発行する方が無難なのは当然です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年4月25日 金曜日
平成26年4月23日第360号
1.日本ヒューレット・パッカード事件
平成24年4月27日、最高裁判所は従業員の欠勤を就業規則所定の懲戒事由である「正当な理由のない無断欠勤にあたる」としてされた諭旨退職の懲戒処分が無効であると判断しました。つまり、無断欠勤を理由にした懲戒処分は認められない、と判断した、ということです。
2.この事件のポイント
この事案では、従業員が同僚らを通じて嫌がらせの被害を受けているとして年次有給休暇を取得して出勤しなくなり、その後も約40日間欠勤を続けています。会社側は、調査するも、そのような被害事実は見受けられなかったため、就業規則所定の「正当な理由のない無断欠勤」として、諭旨退職の懲戒処分をしました。
しかし、裁判所は「使用者は、この場合精神科医による健康診断を実施するなどした上で休職等の処分を検討し、経過を見るべき」とし、このような対応をしなかった以上、「正当な理由のない無断欠勤にあたらない」としました。
本件では「嫌がらせ」は幻聴であることが伺われるので、形式的、客観的には欠勤の「正当な理由」にはならない、と思えます。しかし、裁判所は、使用者として適切な対応をしない限り懲戒処分を認めるべきではない、という判断をしたことがポイントです。
3.会社側に出来る対策は
第1は、欠勤の理由が精神的不調のためと見受けられる場合には、まず、精神科医等に受診させることです。しかし、使用者側から「受診を勧めても行ってくれなくて困る」という話も聞きます。無理に通院をさせることは難しいので、就業規則の中に「必要と認めるときには従業員に健康診断を行うことが出来る」などの規定が必要です。
第2に、段階的な処分を心がける、ということです。「退職」「解雇」などは、従業員の身分を奪う重い処分となるので、裁判所は簡単に認めません。まずは、戒告、減給、休職(停職)処分等を検討し、その上で、改善が無く、やむを得ない場合にとることになります。ただ、精神的な不調の場合、従業員ご本人の責任を追及することが難しいので、実際に取り得るのは休職処分となりそうです。
一度、就業規則、懲戒処分のありかたを見直してみるといいですね。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年4月10日 木曜日
平成26年4月8日第359号
厚生労働省が設けている中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助金(通称:業務改善助成金)が平成26年度から京都府地域においても導入されることになりました。上手く活用して事業場内の一層の業務改善を図りましょう。
<制度の概要>
労働者の地域別最低賃金を引き上げることにより、大きな影響を受ける中小事業主の支援を目的として、次の2点を実施した場合に、業務改善に要した経費の内、最大で1/2(企業規模30人以下の場合は3/4)が助成されるというものです。
(1)事業場で最も低い賃金を800円以上に引き上げる計画を策定し、かつ、1年あたりの時給が40円以上となる引き上げを実施すること
(2)賃金制度の整備、就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等(当事務所の研修も対象となります)といった業務改善をすること。
例えば、
・POSシステムを導入し、在庫管理の業務効率化を図る
・業務用食洗機を導入し、機械で洗浄することで、作業時間の短縮を図る
・新型工作機械を導入し、生産スピードの向上や不良品率の低下を図る
・賃金制度の整備、就業規則の作成・改正(事業場内最低賃金の明記が必要)
・板金加工用の大型の動力切断機を購入し、作業の効率化を図る。
・販売管理ソフトを購入し、仕入・売上などをデータ管理し作業能率を上げる
など、業務や作業の効率化にかかる費用に対して助成されます。
支給対象となるのは事業場内最低賃金が800円未満の労働者を使用している中小事業主で、賃金改善計画や業務改善計画を策定して交付申請書を提出し、交付決定を受けた事業主が対象です(税金や労働保険の未納等がある場合は支給申請できません)。
<申請の流れ>
助成金交付申請 →助成金交付決定 →計画実施(機器の購入など) →実績報告
助成金の交付決定通知書がおりる前に機器の購入などを行った場合、その購入費用について助成金は利用できませんので、申請の手順を間違えないように気をつけましょう。
詳細については、当事務所までお問い合わせください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年4月10日 木曜日
平成26年3月23日第358号
1.産休期間中の保険料免除
育児休業期間の社会保険料は、申し出ることで、本人も、事業主も免除されていましたが、それと同様に産前産後休業期間中(産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間のうち、被保険者が労務に従事しなかった期間)の社会保険料が免除されます。
また、産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬月額が低下した場合は、子が3歳未満の期間中は、復帰後の3ヵ月間の報酬日額を基に、標準報酬月額が改定され、本人の負担が少なくなります。更に、養育期間標準報酬月額特例申請書を提出すれば、将来の年金額は、産前産後休業前の標準報酬月額で計算されます。
2.遺族基礎年金の父子家庭への支給範囲拡大
一定の子がいる場合に支給される遺族基礎年金について、平成26年4月1日以後に死亡したことにより支給する遺族基礎年金からは、これまで支給対象が「子のある妻又は子」に限定されていたものが、「子のある夫」にも支給されるようになります。
3.70歳以後に繰り下げ請求をしても70歳からの年金を受給
70歳に達した後に繰下げ支給の申出を行った場合に、申し出のあった月の翌月分からしか支給されなかったものが、改正後は70歳到達月の翌月分から遡って申し出があったものとみなし、70歳到達月の翌月分から支給されます。
4.未支給年金の請求範囲の拡大
年金受給者が死亡した場合、死亡月分の年金については受取人がいないこととなり、その受給権者と生計を同じくする2親等以内の親族に限り、「未支給年金」として受給を請求することができていましたが、改正後は、その範囲が生計を同じくする3親等以内の親族にまで拡大されます。
5.付加保険料の納付期間の延長
国民年金の上乗せの年金であり、任意加入である付加年金の付加保険料については、納付期日(翌月末日)までに保険料を納付しなかった場合、加入を辞退したものとみなされていましたが、改正により、予め付加保険料を申出ていることを前提に、過去2年分まで遡って納付することができるようになります。
※平成26年度の老齢基礎年金は0.7%引下げられ、満額で772,800円、平成26年度国民年金保険料額は15,250円(月額)となります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年4月10日 木曜日
平成26年3月8日第357号
厚生労働省労働政策審議会の分科会が平成27年4月の施行を提言している労働者派遣制度の改正についての報告をまとめました。
1.労働者派遣における現状の問題点
(1)常用労働者の雇用確保に主眼がおかれ、派遣労働者の保護とのバランスが取れてないこと
(2)派遣労働者のキャリアアップを促進する仕組みの必要性があり、本人の希望に基づき正規雇用・無期雇用への転換やキャリア形成支援を行っていくことが重要であること
(3)労働者派遣制度が複雑で分かりにくいこと。特に派遣受け入れ可能期間の制限
2.派遣期間制限について
派遣労働を臨時的・一時的な働き方と位置付け、派遣労働者が常用労働者の代替とならないよう、派遣労働を臨時的・一時的な利用に限ることを原則とする。
26業務について、実際には派遣先の正規労働者が従事している業務が相当程度あり、26業務に該当するか否かで派遣期間の取り扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先に分かりやすい制度となるよう見直す必要がある。
※26業務とは秘書や通訳など派遣可能期間の制限を受けない業務
3.解決策としての改正
(1)製造業における派遣は経済活動や雇用に大きな影響が生じる可能性があるため、禁止しない。ただし、有期雇用派遣労働者に対する雇用安定処置等を講じること。
(2)26業務の区分及び業務単位での期間制限は廃止とする。
(3)特定・一般の区別を撤廃し、すべての労働者派遣事業を許可制とする。
(4)労働者派遣制度は派遣労働者個人単位と派遣先単位の2つの期間制限を軸とする。ただし、60歳以上の者、育児休業の代替要員等は例外とする。
※個人単位とは派遣先の同一組織単位における同一派遣労働者の継続した受け入れ
(5)同一組織単位において、3年を超えて継続して同一派遣労働者を受け入れてはならない。ただし、過半数の労働組合から意見を聴取した場合は、さらに3年間派遣を受け入れることができ、その後3年が経過した時も同様とする。
※組織単位とは業務のまとまりがあり、その長が指揮監督権を有する単位とて契約上明確にしたもの
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年4月10日 木曜日
平成26年2月23日第356号
4月1日から消費税及び地方消費税が5%から8%に変更となるにあたり、「賃貸借契約に基づく使用料を対価とする資産の譲渡等」に関する項目をご紹介します。
1.不動産の賃貸借契約に基づく使用料を対価とする資産の譲渡等について
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。
(1)当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月末日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を 平成26年3月○日に受領する場合
→平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものなので、4月末日における税率(8%)が適用されます。
(2)当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合
→平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である平成26年3月分の資産の貸付けの対価として受領するものなので、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率(5%)が適用されます。
消費税法基本通達では「賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。」となっており、今回公表された事例によると、例えば4月分の賃料支払いの場合、法人税や所得税における資産の譲渡等の時期が平成26年3月であっても消費税の適用税率は8%となるため、結果として資産の譲渡等の時期と適用税率が必ずしも一致しないこととなります。
2.ファイナンス・リース取引について
平成20年4月1日以後に契約を締結したファイナンス・リース取引は、「リース取引の目的となる資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があったもの」(法人税法第64条の2)として取り扱われます。したがって引渡し時点(借受日時点)の消費税率が適用されます。これにより、借受日が改正法施行日前(平成26年3月31日まで)の場合は旧税率(5%)、改正法施行後(平成26年4月1日以降)の場合は新税率(8%)が適用されることになります。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年4月10日 木曜日
平成26年2月8日第355号
会社は残業削減に向けて、様々な施策を講じていますが、なかなか狙い通りの成果を上げることが出来ず苦労しています。そこでムダな残業を見つけ、それらを排除することが重要となります。それではムダな残業とは一体どういうものなのか、大きく2つに分類し、さらにいくつかのタイプに分けて紹介します。
1.一見してムダだと分かる残業
・生活費を稼ぐために必要がない残業を行う「生活残業」
・成果を上げている人が遅くまで会社に残っているので帰りづらい「罰ゲーム残業」
・誰かが帰るまで会社に残ってしまう「付き合い残業」
・仕事の密度が薄く、ダラダラ仕事をしている「ダラダラ残業」
・計画性がなく締切前に遅くまで残業するのが当然になっている「成行任せ残業」
これらについては、まず、残業は、業務が所定労働時間以内に終わらないから発生するものであり、残業代を稼ぐためにするものではないということを認識させます。そして、会社に長くいる=成果が出せていないことの責任を取る風土の確立、成果と結びつかない行動であればやめさせ、改善する、などを行います。
また、上司は部下が残業して何をしているのかを把握し、残業を行なう場合にはどんな仕事をいつまでに行うかを事前に申請させ、上司がその内容を精査した上で残業を承認する仕組みを作ります。フォローの必要がなければ、上司が自ら早く帰ることも大事です。部下も締切間際に残業をしなくて済むように仕事のゴールや方向性、ポイントを押さえ、締切から逆算してスケジュールを立てていく必要があります。
2.むしろ一生懸命頑張っているように見えてしまう残業
・すべてを完璧に仕上げないと気が済まない「自己満足残業」
・思い込みで仕事をし、納期間際に当初の狙いからズレていることが分かり、やり直せざるを得ない「独りよがり残業」
・自分の立場が奪われるという強迫観念から他人に仕事を渡せない「抱え込み残業」
これらについては、仕事を請けた段階で仕事のゴールや方向性、押さえるべきポイントを発注者と擦り合わせた上で、どこに対して力を発揮すべきかを把握させる、ゴールまでの道筋、中間報告の日程を組み込んだ段取りも併せて描かせ、この道筋に沿って仕事に取り掛からせる、などを行います。
日頃から職場の中で仕事の「見える化」、「共有化」を図り、万が一の時のフォロー体制及び仕事の継承体制を構築していくことも重要です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年1月24日 金曜日
平成26年1月23日第354号
前号(第353号)に続いて、厚生労働省から発表がありました表題についてもう少し詳細な報告を行います。
厚生労働省は、去年9月に「若者の使い捨てが疑われる企業」への重点監督を実施しました。監督にあたっては、「時間外・休日労働が36協定の範囲か?」、「賃金未払残業(サービス残業)がないか?」、「長時間労働者について、医師による面接指導などの健康確保措置が講じられているか?」を重点確認事項とし、監督調査を行いました。
その結果、重点監督を実施した5,111社のうち、82%にあたる4,189社で、何らかの労働基準関連法令違反が見つかりました。各業種での比率を見ると、特に接客娯楽業(87.9%)、運輸・交通業(85.5%)、保健衛生業(83.6%)、商業(83.2%)が全体平均である82%を上回る結果となっています。
主な法令違反は、次の通りに分類されます。
(1)違法な時間外労働があった・・・2,241社、43.8%
特に運輸・交通業(56.8%)、接客娯楽業(52.0%)が全体平均を大きく上回る結果となっています。
(2)賃金未払残業があった・・・1,221社、23.9%
特に建設業(37.0%)、接客娯楽業(37.0%)、商業(32.5%)、金融・広告業(32.1%)が全体平均を大きく上回る結果となっています。
(3)過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかった・・・71社、1.4%
特に製造業(2.6%)、教育・研究業(2.0%)、その他の事業(1.9%)が全体平均を大きく上回る結果となっています。
厚生労働省は、違反事業場に対し是正勧告書を交付し、是正しない事業場に対しては、送検も視野に対応する方針です。
なお、重点監督時に把握したものとして、1ヵ月の時間外・休日労働時間では、80時間超が1,230事業場(24.1%)あり、うち730事業場(14.3%)で100時間超が明らかになりました。
厚生労働省は、今後も引き続き若者の使い捨てが疑われる企業等に対し、監督指導を行っていくこととしています。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年1月24日 金曜日
平成26年1月8日第353号
昨年9月、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施(いわゆるブラック企業の実態調査)が行われ、新聞紙上にも大きく取り上げられました。調査は全国5,111事業所で行われ4,189事業所で違法な時間外労働など労働基準関係法令違反がありました。
京都労働局管内(調査対象事業所119、内違反事業所90)では、労働基準法第37条(割増賃金の支払い)違反で、過去に遡り、労働者計163名に約1億7,800万円の割増賃金が支払われることとなった事例があります。これらの違反があった場合、労働基準監督署から是正勧告が行われ、改善がない場合、送検、社名が公表されます。
労働基準監督官は、行政指導に従わず繰り返し法違反を犯し、また労働災害の発生原因に労働関係法規違反があると、刑事訴訟法による「特別司法警察職員」の職務を行います。「特別司法警察職員」の職務とは、一般の警察官と同じです。違反が悪質な場合、書類送検・強制捜査取り調べ・逮捕・被疑者を身柄拘束のまま送検する権限が与えられています。
どの様な送検があるか、京都労働局の事例2つを紹介します。
(1)賃金不払いで書類送検・・・平成24年3月14日、最低賃金法違反被疑事件について、京都地方検察庁に書類送検。
被疑者Aは、洋菓子製造・販売業を営む者であり、パート労働者1名に対して、平成23年4月分から同年6月分までの賃金合計183,131円をそれぞれの所定支払日である毎月末日に支払わなかった疑い。
(2)労災隠しで書類送検・・・平成24年3月22日、労働安全衛生法違反被疑事件について、京都地方検察庁に書類送検。
A社は大阪府内で建築請負業を営む事業者であり、3次下請会社として京都市内の家電量販店新築工事現場においてシャッター等工事を請負っていたが、平成22年8月8日、同社の現場作業員が作業中にトラックの荷台から落下して、左踵骨(しょうこつ)骨折等の負傷をし、2ヵ月以上休業することとなったにもかかわらず、Bは2次下請会社C社元大阪支店長Dと共謀し、所轄労働基準監督署長へ労働者死傷病報告書を提出せず、労災隠しを図った疑い。
※「労災隠し」とは労災を隠すという意味ではなく、労働者死傷病報告書の未提出を指します。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2014年1月24日 金曜日
平成25年12月23日第352号
近年、仕事によるストレス(業務による心理的負荷)が関係した精神障害についての労災請求が増え、その認定を迅速に行うため厚生労働省では平成23年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を新たに定め、これに基づいて労災認定をしていますが、平成23年度の精神障害労災請求は1,272件(支給決定件数325件)と毎年増加傾向が止まりません。企業において、危機意識を持ったますますの労務管理、対応に配慮が必要です。
1.会社分割とは
会社分割とは、平成12年の商法改正で認められた制度で、会社の一部を切り離して、設立会社へ移転するか(新設分割)、または、他の企業(承継会社)に吸収させるか(吸収分割)の方法により分社化を認める制度で現在は会社法に規定があります(会社法第757条~第766条)。いずれにしても消滅するA社の権利義務関係は包括的に、新設会社(C社)、または存続会社(B社)に承継されます。
2.会社承継法
この会社分割に併せてその労働者はどのように取り扱われるのかが問題となります。労働契約も承継されるため、すなわち「承継強制の不利益」と「承継排除の不利益」が想定され、異議申し立ての制度が設けられています。
3.使用者の責任
分割会社(A社)から、B社またはC社に移行後、短期間にうつ病に罹患したのであれば労災請求手続きはB社、C社が承継するとしても、その労働者が損害賠償を請求するのはA社なのかB社、C社なのかという問題になります。
雇用されている企業が異なっていても業務自体は一貫して継続しているのであれば使用者側に、それぞれ管理不十分として連帯して損害賠償ができると思われます。
雇用されている企業が異なっていて、業務自体も一貫して継続していないとき、A社の業務でうつ病になったのか、B社またはC社の業務でうつ病になったのかは明確ではありません。理論的には、A社とB社またはC社に別々に損害賠償を請求することにならざるを得ませんが、うつ病という疾患上短期に罹患するとは考えにくく、やはり分割時には顕在化していなくても、分割会社にも大きく責任を問われることになるでしょう。
安全配慮義務違反の債務が当然に承継されることは分割の際の計画書(契約書)の記載の有無もありますが、記載に有ると無いとにかかわらず、分割会社にも企業として責任は問われてくることになると思われます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年12月16日 月曜日
平成25年12月8日第351号
1.振替加算とは
振替加算とは、サラリーマンの夫が老齢厚生年金の配偶者加給年金額を受給している時、妻(大正15年4月1日から昭和41年4月1日まで生まれ)が65歳に達して老齢基礎年金を受給する際に支給額が上乗せされる制度です。もちろん夫によって生計を維持されている必要があります。
夫に支給されている配偶者加給年金額は、妻が65歳になれば打ち切られますのでご注意ください。
2.振替加算の経緯と注意点
なぜ振替加算という制度ができたのでしょうか。
昭和61年4月1日に年金法の大改正までは、サラリーマン世帯は夫の年金で妻を扶養するという考えであったため、妻は国民年金への加入義務はありませんでした。もちろん任意で加入することはできたのですが、大半は加入せず、老後は夫の年金で生計を立てるというのが一般的でした。そのため、夫の年金には妻の分として加給年金額が加算され、独身の受給者よりも多めに年金が支給されていました。
しかし、年金法の大改正以後、サラリーマンの妻は第3号被保険者として国民年金への加入が義務付けられました。これにより妻自身も年金がもらえる様になったのですが、今まで任意加入をしてこなかったサラリーマンの妻は60歳までに国民年金を満額でもらえる期間(40年)を満たすことができないため、もらえる年金額が少なくなってしまいます。この制度の変更による不公平を補うために妻の老齢基礎年金に一定額の加算を行う制度(振替加算)ができたのです。
振替加算の額については夫に支給されている加給年金額に妻の生年月日に応じた一定の率を乗じて支給されます。例えば大正15年4月1日に生まれの妻は加給年金額に1を乗じるので、加給年金額の額がそのまま支給されますが、昭和41年4月1日生まれの妻は加給年金額に0.067を乗じた額となり、かなり少なくなります。
夫の加給年金額がそのまま妻に支給されていると勘違いしてしまう方も中にはいらっしゃいますが、加給年金額よりも減額されてしまうことがほとんどですので、その点には注意が必要です。
なお、わかりやすくサラリーマンの夫とその妻としておりますが、夫が主夫で妻が勤めている場合は、振替加算は夫に支給されます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年12月16日 月曜日
平成25年11月23日第350号
裁判といえば「簡単には終わらない」というイメージがあります。
しかし、訴額が60万円以下の金銭支払請求事件については、1回で結審してその場で判決できる裁判があります。
手続の特徴
(1)簡易裁判所が管轄となり、訴額は60万円以下、内容は金銭支払請
求に限る。
(2)口頭弁論期日は司法委員立会のもと、ラウンドテーブル法廷で開か
れ、その日に結審することが原則。被告からの反訴の提起は出来ない。
(3)証拠調べは、期日にその場で調べることが出来るものに制限される。
(4)判決に不服があっても地方裁判所に控訴することは出来ない。判決
をした裁判所に対しの異議申立は出来るが、言い渡される判決には
不服申立が出来ない。
(5)裁判所は、債務者の支払能力に応じて3年を超えない範囲内で支払
いを猶予したり、分割して支払うことを認める。また、提起後の遅延損
害金を免除する判決をすることがある。この条件に対して不服を申し
立てることは出来ない。
(6)相手方からの申出又は裁判所の職権によって通常訴訟へ移行する
ことがある。
(7)同一簡易裁判所に対しては、年に10回までという回数制限がある。
(8)請求を認める判決には必ず仮執行宣言がつくので、判決の確定を
待つことなく、強制執行をすることが出来る。
少額訴訟の利用状況(「司法統計」(H20年度~H24年度)より)
(1)利用件数 年間に約12,700件~約17,100件
(2)訴えの種類(多い順)
1)交通事故による損害賠償請求 2)売買代金請求 3)貸金返還請求
(3)弁護士等に頼まず、原告・被告の双方が当事者本人によってなされ
たもの88.8%~89.3%
少額訴訟を提起された場合の注意点としては、起こす訴訟や事件が複
雑でじっくりと事実認定をして欲しい場合は、通常訴訟への移行をすべき
とされています。また、訴訟を放置した場合等は、欠席のまま判決される
ことがありますので、注意が必要です。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年12月16日 月曜日
平成25年11月8日第349号
「メンタルヘルス」は文字どおり、心の健康のことですが、近年特に注目されるようになったのは、それだけ心の不調を訴える人が社会に急増しているからです。
平成20年から施行された労働契約法では、それまで事業者の努力義務であった「労働者の安全配慮」が明文化され、法的義務が課せられるようになり、メンタルヘルス対策は、すべての企業に必須となりました。
リスク軽減の意識も重要です。特に経営基盤が脆弱な中小企業は会社の存亡にかかわるリスクといっても良いでしょう。対策が不十分で労使紛争や訴訟などが発生すれば、企業のイメージ低下、信用の失墜などにより、大きな痛手を負う可能性は高く、賠償責任が発生すれば致命傷になりかねません。精神障害の労災申請件数・同認定件数とも、ここ10年間で約5倍に急増していることも認識しておくべきです。
単に体制を整備するにとどまらず、常に現状チェックを行ない、より高度な水準を目指す「メンタルヘルスマネジメント(心の健康管理)」の考え方が有効です。
企業のメンタルヘルス対策の主な実施項目として
(1)産業医の選任・推進審議機関(衛生委員会)の設定・運用
※産業医の選任は常時50人以上の事業場で義務づけられています。
(2)過重労働者への適切な対応
(3)不調者への適切な休職措置と復職支援
(4)相談窓口の設置
(5)教育・研修
(6)職場のハラスメントの予防・ルール化
(7)メンタルチェック
定期健康診断も徹底し、受診だけでなく診断結果を踏まえた事後処理まで徹底することです。月100時間超の時間外労働をした人、(過重労働者)への十分なケアも大切です。これらは不調者の予防に加え、万一の紛争時のリスク軽減にも有効です。
ラインの管理者の負担にも十分配慮しましょう。この層は部下のメンタルヘルスケアなど大切な役割を担いますが、もともと職務の負担が重く、管理者自身が不調に陥る恐れもあり、会社としての配慮が必要です。
また、事業所外の専門機関として「産業保健推進センター」や「メンタルヘルス対策支援センター」などの公的機関があります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年12月16日 月曜日
平成25年10月23日第348号
通勤手当は、法律で支給が定められているわけではありませんが、通勤手当の支給が労働条件として定められていれば、実費弁償的に算定される出張の旅費等とは異なり、労働の対償として支払われる労働基準法上の賃金となります。したがって、支給条件が定められた通勤手当を、会社が一方的に労働者の不利益となる条件に変更することは、原則として許されません。また、個人ごとの支給に当たっては、通勤しなかった日の取り扱いにも注意を要します。
労働契約法第8条には「労働者と使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することが出来る。」とあります。しかし、その一方、労働契約法第10条で定める例外を除いて、使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することは出来ないとされています。
労働契約法第10条で定める例外とは「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである」場合とされています。
労働者からの合意を得るには、通勤手当を減額する理由の真摯な説明が必要ですし、合意が得られず就業規則の変更による場合には「通勤手当を減額しなければ、経営が立ち行かなくなる」ような、高度な必要性に基づく合理性が必要となります。
通勤手当は、法的には賃金でも、実費弁償的な性格を有しています。そのため、出勤しない日に不支給にすることは合理性があるといえますが、適正な規定が備わっていることが前提となります。通勤手当が賃金である以上、その支給基準は、賃金の決定、計算の方法に当たり、就業規則の絶対的必要記載事項となるからです。
労働基準法附則第136条で、使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、「賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」とされていますが、年次有給休暇の取得によって、通勤手当が日割り等で減額されることを就業規則等に明記しておくことで、年次有給休暇の取得日について賃金を減額することは可能となります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年10月12日 土曜日
平成25年10月8日第347号
パートタイマー等の採用の際、正社員の採用と同様に試用期間を設ける会社があります。試用期間を設ける契約は、一般的に「解約権留保付契約」とされ、試用期間中に不適格事由があれば本採用を拒否し、解雇するという労働契約(通常の解雇より広い範囲で解雇の自由が認められる契約)と言われています。また、労基法第20条により、試用期間中採用後14日以内の解雇には解雇予告が必要ないとされています。その様な理由で、正社員と同様に試用期間を設けている会社が多いと想像できます。
しかし、労基法第20条の試用期間中採用後14日以内に解雇予告なしに解雇できるのは、期間の定めのないパートタイマー等であって、期間の定めのある雇用契約締結者(以下、有期雇用者)は無理があると考えます。
労働契約法第17条第1項に「使用者は、期間の定めのある労働契約について、『やむを得ない事由』がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」とされています。厚生労働省の「労働契約法のあらまし」には、『やむを得ない事由』であるか否かは、個別具体的事案により判断されるものであるが、契約期間は労働者及び使用者が合意により決定したものであり、遵守されるべきものであることから、『やむを得ない事由』があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と認められる場合よりも狭いと解される、とあります。
この『やむを得ない事由』は、契約期間満了を待つことなく直ちに雇用契約を終了させざるを得ない特別重大な事由が必要となります。従って、期間雇用者に試用期間を設けた場合も、その契約期間中に特別重大な事由がない限り、契約途中で解雇することは無理があります。
期間雇用者にも試用期間を設ける必要があるならば、短期の有期雇用契約を締結し、その期間を試用期間とし、期間終了時点で契約の更新を判断する採用方法が有効な手段と考えます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年10月 2日 水曜日
平成25年9月23日第346号
自民党政権に代わり9ヵ月が経とうとしています。アベノミクスと名付けられた経済政策が推し進められる中、いつになれば中小企業にまでその恩恵が回ってくるのか不明です。
万が一、従業員の労働条件を下げざるを得ないとき、どんな方法があるのでしょうか。
1.労働条件の変更
労働条件の変更は、労働契約法に基づき「労使間の合意により変更することができる」と規定され、合意があれば可能といえます。また労働者に不利益な変更をする際に合意のない場合は、就業規則を変えることでその変更が可能となり、(1)変更後の就業規則の周知(2)労働者の受ける不利益の程度(3)変更の必要性(4)内容の相当性(5)労働組合等との交渉の状況(6)その他変更に係る事情、といった要件に照らして合理的である場合は労働条件を変更することができると規定されています。
2.変更解約告知
変更解約告知とは、労働条件変更のために従来の労働契約の解消と新たな労働契約の締結の申し込みを同時に行うことや、労働条件変更を申し込みつつ、それが受け入れられないときは労働契約の解約を行うこと等を労働者に対し告知する行為をいいます。
これは、労働契約の解約自体を目的に行われるものであるのか、労働条件を変更する手段として行われるものであるのか意見が分かれるところですが、変更解約告知を認めた裁判例(スカンジナビア航空事件、東京高裁判決、1995・4・13)では、(1)労働条件変更の必要性(2)その必要性が労働者の受ける不利益を上回り、変更を伴う契約の申し込みに応じない労働者の解雇が止むを得ないこと(3)解雇回避努力が尽くされていること、の3点を変更解約告知が認められる要件としています。
また、変更解約告知を認めない裁判例(大阪労働衛生センター事件、大阪地裁判決、1996・8・31)では、「労働者が新しい労働条件に応じない限り解雇を余儀なくされるとなれば、二者択一を迫られ、労働者は非常に不利な立場におかれることになるとして、変更解約告知は認められない」としており、いずれにしても変更解約告知には慎重の上に慎重であることが求められます。
3.「留保付き承諾」という課題
ドイツでは変更解約告知に対し、労働者が変更した労働条件に合理性があるかどうかを法の判断を待ってから承認するとした上で、暫定的に変更後の労働条件に従って就労する「変更解約告知の留保付き承諾」の制度が導入されています。現在、日本では留保付き承諾は変更の申し出を拒否したものとみなされ、法的に認められていません。今後日本においても変更解約告知法理が労働条件変更法理へと成熟していくことが期待されます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年9月10日 火曜日
平成25年9月8日第345号
1.9月1日から特別加入給付基礎日額の上限が引き上げられます。
労災保険は、労働者の業務または通勤による死傷病に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも業務の実情、災害の発生などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる次の事業を営む事業主には特別に任意加入を認めています。これが「特別加入」です。
・中小企業の事業では、金融・不動産・保険・小売業で常時使用する労働者が
50人未満。卸売・サービス業で100人未満。それ以外では30人未満の事業。
・個人タクシー等の運送事業や個人の建設業、漁船の船長及び林業等
(一人親方)
・特定作業としての農業。
・海外派遣される者。
現在、特別加入制度加入者は、本人が給付基礎月額(3,500円~20,000円までの13区分)を任意で選択し、労働局長の認定を受け、所定の保険料率を掛けた額を労災保険料として支払っています。
特別加入者の給与の実態や本体給付との均衝を踏まえ、労働者災害補償保険法施行規則等が改正され、9月1日から施行されました。具体的には新たに22,000円と24,000円と25,000円の3区分が加えられ16区分となります。
すでに特別加入している方が給付日額の変更を希望する場合には、平成26年3月18日~3月31日、6月1日~7月10日に手続を行なってください。
2.10月1日から「1,2-ジクロロプロパン」が規制されます。
安全衛生法施行令が10月1日から改正され、がん事案の原因物質の1つと考えられる「1,2-ジクロロプロパン」について、労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、特定化学物質障害予防規則の措置対象物質に追加します。
洗浄や拭き取りの業務ではご注意ください。
労災保険や労働安全衛生法施行令で気になる場面がありましたら、社会保険労務士にご相談ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年9月10日 火曜日
平成25年8月23日第344号
「リフォーム空室1室あたり最大100万円の補助金」というものがありますので、ご紹介します。
正式名称は「住宅セーフティネット整備推進事業」といいます。既存の民間賃貸住宅の質の向上と、空家を有効に活用することにより住宅確保要配慮者※ の居住の安定確保を図るとともに、災害時には機動的な公的利用を可能とする環境を構築するため、住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空家のある民間住宅の改修工事に要する費用の一部を国が直接補助するものです。(※ 高齢者世帯等)
1.対象住宅の要件(次の全ての要件を満たす必要があります)
(1)民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの強化に取り組む地方公共団
体との連携が図られる区域内で、1戸以上の空家(改修工事着工時点で入居
者募集から3ヵ月以上人が居住していないもの)があること
(2)改修工事後に賃貸住宅として管理すること
(3)原則として空家の床面積が25平方メートル以上であること
(4)台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するものであること
2.改修工事の要件
空家部分又は共用部分における以下の工事のうち、少なくとも一つの工事を含む改修工事を実施することが必要です。
(1)耐震改修工事
(2)バリアフリー改修工事
(3)省エネルギー改修工事
3.補助額
改修工事費用の1/3
※補助上限額 空家戸数×100万円
4.申請手続
受付締切:平成25年12月27日(金)[必着]
※応募の状況によっては、申告期限以前に募集を締め切られる場合があります。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年8月23日 金曜日
平成25年8月8日号第343号
警察庁交通局による平成24年の交通事故件数は約66万件、死者数は4,411人で昭和45年のピーク時と比較すると(昭和45年=16,765人)3割以下に減少しています。しかし、その中で目を引くのは自転車が加害者となる事故です。平成13年と平成23年の事故件数を比較すると、自転車対歩行者の交通事故は1,807件から2,801件に急増しています。
道路交通法では、自転車は「軽車両」に分類され、自転車の運転者が事故を起こした場合は刑事責任を問われます。また、人に損害を負わせた場合は、賠償責任も負うことになります。下記は、実際に起こった自転車交通事故です。
1.損害賠償額6,779万円
男性がペットボトルを片手に自転車で減速せず下り坂を走行後、交差点に進入。横断歩道を横断中の女性(38)と衝突、女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。
2.死亡事故を誘発した有罪判決
加害者男性(96)は、国道交差点で、赤信号を横断していた、加害者男性が乗る自転車を避けようとしたトラックが道路脇の建物に衝突し、トラックの運転手が死亡。
裁判官は、「信号に従って通行するのは自転車運転者の義務」としたうえで、「赤信号を見落として自転車で横断し事故を起こしたのは重大な過失」と自転車の過失を認定し、禁固1年4ヵ月執行猶予3年の実刑判決を下した。
3.親に9,500万円賠償命令
小学校5年生の男子児童の自転車が神戸市北区の坂を時速20キロ~30キロで下った際、散歩途中の女性に衝突。女性が意識不明の状態になったとして、被害者の夫が男子児童の母親を相手取り、計1億500万円の損害賠償を求めて訴訟した。
判決では、「母親が十分な指導や注意をしていたとはいえない。」と認め、母親から被害者に3,500万円、被害者が加入していた保険会社に約6,000万の賠償金の支払いを命じた。
自転車事故では、車のように交通反則金制度はありません。従って罰金であっても、全て「前科」がつく刑事処分になり、刑事罰を受けると、医師、栄養士、調理師などの免許が与えられなくなることもあります。
あなたは、自転車事故を甘くみていませんか?近年、自転車が加害者になるケースが増え、会社としても対応が問題となっています。そんなときに備えて、「自転車通勤規程」を作成しましょう。詳細は当事務所までお問い合わせください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年8月23日 金曜日
平成25年7月23日第342号
休日は、労働基準法第35条第1項で「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定められています。
また、休日は、原則として暦日制で与えるものです。即ち、午前0時から午後12時までの24時間となっています。例え24時間勤務であっても、非番の継続24時間を休日とは認められません。ただし、業務上やむを得ないと認められる次の3つの場合について行政の解釈例規は例外を認めています。
1.8時間3交替制
シフト勤務制で1週間ごとに勤務帯が替わる場合、暦日制だと勤務帯によっては、2暦日にまたがる休日付与の必要があり、週休制をとった立法の趣旨に合致しないことになります。
そこで、シフトによる交替制が就業規則に記載されかつルールに則った勤務帯の交替となっている場合には、例外的に休日は継続24時間を与えることで成立するものとされています。
2.自動車運転者
自動車運転者業務の特殊性から暦日の24時間を休日とすることが困難であるため、休息時間と休日について特別な取扱がなされています。休息時間に24時間を加算して得た労働義務のない時間、通常勤務の場合には連続した労働義務のない32時間を、隔日勤務の場合には連続した労働義務のない44時間を休日として取扱います。また、休息時間を分割して付与する場合、2人乗務の場合及びフェリーに乗船する場合については、連続した30時間の労働義務のない時間を休日として取扱います。
3.旅館業
フロント係、調理係、中番及び客室係は、旅館業という特異性から1日の勤務帯は、顧客のチェックインからチェックアウトを基準として編成されます。従って、2暦日にまたがる時間帯となり、休日の付与や時間外の取扱が、一般業種と大きく異なります。旅館業においては、午前0時から午後12時を、正午から翌日の正午までの24時間と読み替えることが可能となり、その時間を含む継続30時間(当分の間、継続27時間)の休息期間が確保される場合、例外として認められています。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年7月 9日 火曜日
平成25年7月8日第341号
人が会社に雇用されて労働契約が結ばれる行為も民法における契約行為の一種ですが、その労働契約が終了する事由として「退職」と「解雇」があります。時に「退職」と「解雇」が混同して使用される場合がありますので、次に整理します。
退職...労働者側から使用者に対し一方的な意思表示によって労働契約を終了すること。
解雇...使用者側から労働者に対し一方的な意思表示によって労働契約を終了すること。
また、退職日を指定するのは、あくまでも労働者であり使用者ではありません。労働者・使用者双方が「退職日」等合意することによって労働契約が終了する場合は「合意解約」となります。
「解雇」をする場合、解雇予告(労基法20条)が必要です。「退職」する場合は、会社の規定にもよりますが2週間前の申出等(民法627条1項)が必要です。
では、労働者側からの退職の申出がされた場合、その申出は何時でも撤回することができるのでしょうか。
判例では、「退職の意思を撤回できるのは、退職の意思を承認する権限ある者が承諾するまでなら、退職の意思は撤回できる」とされています。
言い換えると、人事権のある人物が退職を承認すれば、労働者側の都合で、使用者側の同意なく退職の撤回はできなくなります。退職撤回を認めないとなれば、その退職の承認が何時であったかがポイントとなります。後日のトラブル回避の為には書面で退職の申出を受け、承認後は退職受理通知などを残すことが賢明です。
退職と解雇の取り扱いについて触れましたが、労使ともに通常は長期的な継続雇用を望むのが一般的です。「退職」「解雇」について現実的な問題点は多数ありますが、今後も会社の持続的な発展をするためには、労使の信頼関係を重視されることを望み、武田信玄の有名な言葉を引用します。
<人は城、人は石垣、人は堀、情は味方、仇は敵なり>
この言葉は「どれだけ城を強固にしても、人の心は離れてしまったら世は治めることができない。情けは人をつなぎとめ、結果として国を栄えさせるが、仇を増やせば国は亡びる。」という言葉を残しています。
つまり、「人材の重要性 = 組織は人間力」ということではないでしょうか。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年7月 9日 火曜日
平成25年6月23日第340号
平成25年6月12日、厚生労働省は国民年金保険料の「2年前納制度」の導入を報道発表しました。開始は平成26年4月で、試算によれば1年前納の割引率2.1%から倍近い4.0%になります。年金制度も少しずつ変わっていきます。
さて、御承知のように公的年金は、国民の老齢、障害、死亡時に生活を補償するものです。なかでも障害年金は、関係者の主観が入り、それが障害年金の請求をより困難に、複雑にしています。もらえるのに制度がわからなかったということのないようにしたいですね。一般的な流れは、次のようになります。
1.基本方針を立てましょう
この病気なら障害年金がもらえるというように、原因となる傷病名が限定されているわけではありません。「障害の等級・程度」は「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」という通知が厚生労働省から出されています。また、傷病の発生した時期や、初診の医療機関の連絡先を確認しましょう。
2.年金記録の確認
初診日で保険料納付要件(初診日の前日において前々月までの期間または直近1年間に未納がないかを問われます)を確認しましょう。初診日が20歳前の場合は問われません。
3.受診状況証明書等の取得
診断書作成医療機関と初診の医療機関が異なっている場合、初診の医療機関で作成していただく書類です。連絡や訪問をして作成を依頼しましょう。
4.診断書の取得
可能な限り医師と面談し診断書のポイントを伝えるようにしましょう。
5.病歴(就労状況)申立書の作成
「請求者本人」が「障害年金の審査担当者」に思っていることを伝える書類です。
6.戸籍などの添付書類を揃える
7.窓口に裁定請求書を提出する
以上簡略に書きましたが、やはり時間と粘り強さが必要です。また、書類の取得もなかなか難しいものがありますので、ぜひとも国家資格であり、年金の専門家である社会保険労務士にご相談ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年6月20日 木曜日
平成25年6月8日第339号
アベノミクスは、概ね良好な評価がされている様子で、日本の経済政策は、世界の注目を集め、今後の動向が注目されています。景気回復への期待から、株価は乱高下し、金利の状況は、先行き上昇の気配が濃厚です。しかしながら、中小企業庁発表の中小企業景況調査における、各企業の雇用状況に関する今後の見通しは厳しい見方のようです。
派遣や有期雇用による調整局面に関与する法改正について、この時期に再度取り上げました。
1.労働契約法
有期労働契約を反復更新している場合の雇用不安の解消と労働条件の是正を目的と
して改正されました。派遣労働者に関しても同様のスタンスで法改正がされています。
1)有期労働契約の更新拒否には、客観的で合理的な理由が必要とされ、更新を
拒否する事が相当と認められない場合には、従前と同一の条件で更新されま
す。
2)有期労働契約が反復更新され通算5年を超えるときは、労働者の申し込みによ
り、無期労働契約に転換されます。
2.労働者派遣法
名称が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」と変わり、派遣労働者の保護が前面に出ています。法改正の趣旨に注意しましょう。
1)均等待遇確保のため、正規雇用者との待遇格差について、派遣会社から正規
雇用者の賃金・福利厚生等の情報提供を要求さ れることが有ります。
2)派遣先の都合で派遣契約を解除する場合は、派遣労働者の新たな就業機会
の確保、休業手当等の支払いに要する費用の負担措置が派遣先の義務とな
りました。
派遣労働者を受け入れる場合は、正規労働者の賃金情報の流出や派遣契約解除に伴う新たな費用負担の発生等、当初に予想していなかった事態が発生することに、注意が必要です。
契約社員や派遣社員について、その人が必要な人材か調整すべき人材かを考えたとき、客観的な評価が有効です。回復基調の出発点での円滑な労務管理を目指して、人事・労務管理の専門家社会保険労務士にご相談ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年6月20日 木曜日
平成25年5月23日第338号
相続対策を実行する場合には、「相続税の軽減対策」「納税資金対策」「争族対策」の3つをバランスよく組み合わせて行うことが大切です。
1.相続税の軽減対策
次の世代へできるだけ多くの財産を承継させるためには、相続税の節税が欠かせません。
さらに、相続税が増税されてより一層の備えが求められます。
まず相続対策の基本として次のものを中心に行っていきます。
1)養子縁組の活用
2)生命保険契約の活用
3)贈与の実行
4)賃貸マンション等の建物の建築
毎年、贈与を繰返していくなど、一見地味に思えるかもしれませんが、小さなリスクで大きな効果をあげるためには、これらの基本の対策を積み重ねて行くことが最も重要です。
2.納税資金対策
例えば、生命保険契約を活用する方法があります。相続人が受け取った一定額までの生命保険金は、相続税が非課税となりそのまま相続税の納税資金に充当することができます。
また、相続税は、延納や物納といった納税方法も選択でき、相続財産に占める不動産の割合は全体の半分を占めています。特に、収益性が低く、処分が困難な不動産を物納すると、相続税評価額で収納してもらうことができ、不良資産の整理にも役立ちます。
3.争族対策
家庭裁判所における家事手続案内件数のうち相続関係は総数の約3割を占めており、件数も年間15万件を超えています。
相続が発生した場合、相続財産は共同相続人の共有財産と解されます。このことは、相続財産を管理・処分するのに、相続人全員の合意が必要となることを意味し、この共有状態を脱するためには、相続人全員の合意に基づく遺産分割協議が必要となります。
しかし、遺産分割協議が調わずそのまま放置しておくと、合意が必要な相続人の数が飛躍的に増えることにもなりかねません。
このような事態を避けるためには、財産所有者が自らの意思を「遺言書」という形で法的に明らかにしておく必要があります。相続対策は早く始めるほどコストとリスクを分散し、軽減することができるため効果的であるといえます。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年5月21日 火曜日
平成25年5月8日第337号
中小企業では、契約労働法が4月1日から改正されたことから、「契約社員」とは何か?の定義が問われているところです。「契約社員=期間の定めのある従業員」という定義にして、その多くが過去の採用における失敗からリスク管理として「契約社員採用」という行動に出ています。
「契約社員採用」で集まる応募者側の問題
応募者の視点で考えると、「契約更新時に交渉ができるほど実力に自信がある人」か「腰掛けで次の職場までのつなぎと考えている人」意外は、わざわざ契約社員を選んで就職したいとは思っていません。通常、契約社員の方は次回の更新に不安を感じていますし、結果として人生設計にも影響が出やすくなります。
「契約社員という立場」であっても、どうしても入りたいほどの魅力と特長のある会社であれば別ですが、企業は「契約社員でもいいからとにかく仕事に就きたい」という方々を集めてしまいかねません。
「契約社員採用」にまつわる企業側の問題
企業の多くが契約社員を採用するメリットまたは目的はいくつか挙げられます。
(1)契約更新時に満足な結果を出せていなければ、労基法の解雇に該当せずに雇用関係を終了させることができる(経営状態に合わせての人員整理が容易であり、試用期間のように試し雇いができる)
(2)退職金が不要
(3)一定年齢以上は更新しないことで平均年齢を保つ
(4)年俸制を適用し人件費の負担を抑えたい
など、若干不適切とも言える考えが見え隠れしていることがあります。
「契約更新というイベントがあるから常に緊張感をもって仕事をしてもらえる」など、経営者の詭弁を聞いたこともありますが、それはマネジメント能力の不足を社員に押し付けているだけです。正社員でも従業員満足度を上げれば、緊張感をもって仕事をしてもらえます。
中長期的な採用における「成功」を願うなら正社員採用を
正社員募集と契約社員募集には差がかなりあります。また、技術の流出、従業員満足度、人材の自転車操業、会社への帰属度、社員の生活や幸せなどからも、人材戦略として中長期的な視野をもっての正社員募集をお勧めします。
※契約社員を正社員にすることを前提にした、月15万円×最大2年という「若者チャレンジ奨励金」が生まれました。詳細は当事務所までおたずねください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年5月21日 火曜日
平成25年4月23日第336号
1.「労使間の慣習」は法的拘束力を持つのか?
民法第92条によれば、長年継続された「労使間の慣習」は、法的拘束力を持つことがあります。未然にトラブルを防ぐため、「労使間の慣習」が法的拘束力を持つのはどのような場合か把握しておきましょう。
2.「労使間の慣習」が法的拘束力を持つ要素とは
・同種の行為または事実が、一定の範囲において長期間反復継続され定着して
いる。
・当事者双方が、明示または黙示にこれによることを排除・排斥していない。
・当該労働条件について、内容の決定権や裁量権を有する者が規範意識を有し
ている。
等を要する必要があります。
判例でも、単に長年継続されているということだけではなく、当事者が「規範意識」を持っていることが重要となってきます。
さらには使用者(労働条件を決定し得る権限を有する者か、またはその取り扱いに一定の裁量権を有す者)が長年繰り返してきた内容であるならば、慣習に沿った内容に就業規則を変更することになります。
そのため、就業規則を変更できる権限を持った者が、その「労使間の慣習」の取り扱いに義務意識を持っていることが必要となり、労働者が「労使間の慣習」において権利を得るには、高いハードルがあります。
一方で、使用者においても権利の行使が「権利の濫用」として、黙認・放置されていた一定の規律違反行為に対して無効となることがあります。
3.「労使間の慣習」例
・就業規則などに定められていない場合の行為準則となる場合
(日本ダンボール研究所事件、三菱重工業事件等)
・就業規則など成文化されたルールを補足する場合
(石川島播磨重工業事件、京都新聞社事件等)
・就業規則など成文化されたルールに反する取り扱いをする場合
(大栄交通事件、日本大学事件等)
すでに「労使間の慣習」が存在している場合、その慣習を労使合意のうえ廃止できれば良いですが、今後当慣習が発生しうるものであれば、就業規則等に明記してルール化すべきです。ただ、このときは労働条件の不利益変更とならないよう注意が必要になります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年4月16日 火曜日
平成25年4月8日第335号
政府は、国民一人ひとりに番号を振り、年金や健康保険などの社会保障給付と納税を一つの個人番号で管理する「共通番号制度」について、平成28年から導入する関連法案を3月1日に閣議決定し、22日衆院で審議が始まりました。
共通番号は「マイナンバー」と呼ばれ、納税や年金の照会などから番号を使った手続きが可能になります。
「マイナンバー制度」の導入についてのメリット
住民、行政の過度な負担の軽減につながります。
・住民側...社会保障給付等の申請を行う際にまた、必要となる情報につき、申請者が添付書類等を付けることなく、申請を受けた行政機関等が、関係各機関に照会を行うことで取得することが可能となるため、申請者が窓口で提出するものは、請求書のみで足りる。
・行政側...行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が保有する個人情報が、同一人の情報であるということの確認を行うことができ、行政機関、地方公共団体等の間において当該個人情報の照会・提供を行うことが可能となる。
「マイナンバー制度」に関する懸念
過去の調査では個人情報の漏洩など、政府の情報管理体制への不安が次のように大きいことが分かります。
・個人情報漏洩によるプライバシー侵害(40.5%)
・個人情報の不正利用による被害 (32.2%)
・国により監視・監督される恐れ (13.0%)
「マイナンバー」法案のポイント
1)住民票コードから国民一人ひとりに番号を付ける
2)番号を本人に知らせたうえで、番号情報を入れた顔写真付きICカードを配る
3)納税や年金の給付申請等、当面は行政手続きに利用する
4)平成27年中に番号を通知、平成28年1月から利用開始予定
5)平成29年1月から国税庁や日本年金機構等の間で個人データーを交換する
6)平成29年7月から地方自治体も情報交換に参加する
等となっています。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年4月16日 火曜日
平成25年4月1日臨時号
この奨励金は、若年者の正社員化を目的に、35歳未満の非正規雇用(契約期間の定め有り)の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、職業訓練を実施する事業主の方に奨励金を国が支給するものです。
<若年チャレンジ訓練の対象者>・・・1年度に計画できる訓練は60人月が上限
・35歳未満の者・過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3
年以上雇用されたことがない者
・登録キャリア・コンサルタントにより、若年チャレンジ訓練へ参加することが適当
と判断され、ジョブ・カードの交付を受ける者
<対象となる訓練>・・・訓練期間は3ヵ月以上2年以下
・OJT(自社内での訓練)とOff-JT(座学)を組み合わせた訓練
・全体の訓練時間にOJTが占める割合が1割以上9割以下であること
・1ヵ月当たりに換算した訓練時間数が130時間以上であること
・訓練受講者の主要な労働条件(就業時間、賃金形態)が正社員と同じであるこ
と
<受給金額>
・訓練奨励金 ・・・訓練実施期間に訓練受講者1人1ヵ月当たり15万円
・正社員雇用奨励金 ・・・訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合
に、1人あたり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円
<受給までの流れ>
(1)訓練実施計画を作成し、1ヵ月前までに都道府県労働局(ハローワーク)へ
届出
(2)労働局(またはハローワーク)が訓練実施計画の内容を確認
(3)訓練受講者の選考・決定(ハローワーク・民間職業紹介機関への求人、
社内訓練生募集、ジョブ・カード交付)
(4)訓練実施計画に基づき訓練を実施
(5)訓練奨励金の支給申請
(6)正社員雇用奨励金の支給申請(正社員転換後、1年または2年経過時点)
※ジョブカードとは、履歴シート、職務経歴シート、キャリアシート、評価シートの4つからなるファイルです。ハローワークやジョブ・カードセンターで発行できます。
詳細については、当事務所までお問い合わせください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年4月16日 火曜日
平成25年3月23日第334号
平成25年4月1日から改正高年齢者雇用安定法(以下「高齢法」。)が施行されます。
平成18年4月1日から改正施行されていた高齢法では、定年の定めをしている事業主に対して、高齢者雇用確保措置が義務付けられていました。
具体的には(1)定年の引き上げ(2)継続雇用制度の導入(3)定年の定めの廃止。
3種類のうち(2)の継続雇用制度は「再雇用」制度と「勤務延長」制度に大別されました。今年の3月末までは労使協定により基準を定めた場合は、継続雇用制度の希望者全員を対象としない制度も可能であったものが、今改正で「希望者全員雇用」が原則となります。
一方、老齢厚生年金の支給開始年齢引上げにより、60歳定年に達しても1円の年金も貰えない無年金世代が登場するようになりました。今回の改正は、定年から年金受給までの期間をスムーズに連結するのが目的のため、受給開始年齢以上においては従来通り労使協定で対象者に係る基準を設けて良いとの「経過措置」が導入されました。
1.就業規則の変更
すでに就業規則で定年を65歳以上としている企業、定年制なしの企業、65歳まで希望者全員雇用の企業は今回の法改正に伴う見直しは必要ありません。しかし、労使協定により基準を設けて再雇用を制限している企業は希望者全員を継続雇用制度の対象とする必要があり、就業規則にもその点を変更して監督署への届出が必要になります。
年金受給開始年齢までは希望者全員を対象とし、それ以上の年齢は基準を設ける「経過措置」を導入するにしても、厚生労働大臣が新たに定めた「指針」では就業規則に定める解雇・退職事由に該当する場合以外継続雇用をしないことができません。
労使協定での人選ができなくなる分、継続雇用制度に労働者が申し込むことで労働者に雇用継続の合理的期待がありと判断され、継続雇用拒否には解雇に相当する客観的合理性・社会的相当性が求められることになります。 そのため、就業規則の解雇事由又は退職事由についても見直しておく必要があります。
2.再雇用後の労働条件
前述の雇用確保措置のうち、どの制度を選択しても、「賃金」に関しては特段制約がなく、年収が6~7割程度にダウンする傾向にあります。しかし、雇用形態の違う正社員と嘱託であったとしても賃金等の労働条件が大幅に低下させるには、合理性が必要になるケースがあります。また、裁判例でも、極めて過酷で、勤務する意思を削がせると認められるような労働条件を提示することは雇用継続を排除したと判断され、認められていません。労使間で十分に協議し、納得性の高いものになるよう心掛けてください。(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年3月15日 金曜日
平成25年3月1日臨時号
この奨励金は、健康・環境・農林漁業分野等の事業における正規雇用の労働者に対し、職業訓練(Off-JT)を行った場合に、訓練に要した経費を支援するものです。
訓練前に職業訓練計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
研修費用が全額支給(上限有り)される珍しい助成金です。該当事業主は、この機会を利用して、従業員の方に受講させ、売上アップ、職場活性化にお役立てください。
<対象となる事業主>
・医療・介護・福祉
・情報通信業、電気業
・運輸業、郵便業
・スポーツ・健康教授業、スポーツ施設提供業
・廃棄物処理業
・建設業のうち健康・環境・農林漁業分野に関する建築
・製造業のうち健康・環境・農林漁業分野に関する製品を製造、取引
・農業、林業、漁業
・学術、研究開発機関のうち健康・環境・農林漁業分野に関連する技術開発
・その他の事業のうち健康・環境・農林漁業分野に関連する事業を行っているもの
<対象となる職業訓練>・・・受講する労働者の数に制限はありません
(1)健康・環境・農林漁業等、業務に関するもの ・・・趣味・教養等は対象外
(2)1コースの訓練時間数が10時間以上であること
<受給金額>...1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円
(1)事業主負担の訓練費用を1訓練コースにつき対象者1人当たり20万円が上限
(2)事業社内訓練の場合、外部講師の謝金は1時間当たり3万円が上限
<受給までの流れ>・・・訓練コース追加・変更の場合は、前日までに、変更申請要
(1)受給資格認定申請・・・訓練開始1ヵ月前までに、職業訓練を作成し、申請
(2)職業訓練計画の認定
(3)職業訓練計画の開始・・・申請日から6ヵ月以内に訓練を開始
詳細については、当事務所までお問い合わせください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年3月15日 金曜日
平成25年3月8日第333号
社会保障関係NEWS
1.平成24年 厚生労働省「賃上げ等の実態に関する調査から」
平成24年中に、1人平均賃金を引上げた又は、引上げる予定の企業は、約75.3パーセントに上り、改定額は4,063円、改定率は1.4パーセントとなります。いずれも、前年の1.3パーセント、3,513円を上回り賃金等が上がります。
2.公的年金実受給者数は、3,867万人、前年度末に比べ71万人増加
平成23年度末現在、公的年金加入者数は、6,775万人となり、前年末に比べ51万人減少、しかし公的年金の受給権者数は、3,867万人で、前年末に比べ71万人増加しています。加入者が減っている一方で、受給者は増加しています。
(平成24年12月17日の公的年金実受給者数 厚生労働省集計)
3.巳年生まれは、1,020万人、新成人は122万人
平成25年1月1日現在の巳年生まれの人口は1,020万人で、総人口1億2,747万人に占める割合は約8パーセントと少なく、男女別では、女性が32万人多くなっています。今年の新成人は、昨年度と同数の122万人となりました。
もしも家族が倒れたら
年金受給者が増え、受給者を支える若者が減っている中で、今まで元気だった方が突然けがや病気で体調不良となり入院する場合があります。また、退院後は介護が必要な状態になったり、認知が発症して誰かが絶えず見守りが必要となることが、考えられます。そんなもしものとき、介護施設や費用の負担等突然の事態に直面することになります。
そんなとき、地域包括支援センターは、様々な相談に乗って支援してくれます。
地域包括支援センターでは、ケアマネージャー・保健士・社会福祉士等が配置され高齢者の相談業務を行っています。介護が必要になったとき、介護保険の申請手続をはじめ自治体独自のサービスを受ける準備もスムーズに進められます。
平成24年に介護保険法が改正され、高齢者が住み慣れた地域で生活ができる体制作りの整備が進んでいます。中学校区に1ヵ所あります。パンフレットだけでも取りに行かれては如何でしょうか。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年3月15日 金曜日
平成25年2月23日第332号
筆界特定制度は、隣地との境界がハッキリしないときに土地所有者の申請により、法務局が筆界の現地における位置を特定する制度です。
筆界とは、表題登記のされている一筆の土地とそれに隣接する土地との境であり、「公法上の境界」のことです。「私法上の境界」(所有権界)とは異なり、土地所有者間で決めたり変えたりすることができません。
しかし、長年に渡る土地の利用状況や売買、相続等で土地所有者、隣接地所有者が変わり「真正な筆界が一体どこなのか」がわからなくなる場合があります。
筆界特定制度はこのような場合、筆界の位置を特定することができない場合でも、土地所有者の申請により、その位置の範囲を特定できる制度です。平成18年1月20日から実施されています。
1.筆界特定制度の注意点
・申請手数料は土地の価格(固定資産評価額)に応じて納付
・測量が必要な場合の費用は申請人の負担
2.制度創設の理由
・短期間での解決
従来からの主流である裁判所に境界確定訴訟を起こす方法は、解決までにおおよそ2年の期間が費やされていました。筆界特定制度は比較的短期間に終了することを目的とし、解決までの期間は半年から1年を目指しています。
・費用負担の軽減
従来は訴訟を起こしていたため、費用も大きな負担となっていました。この制度の申請手数料は訴訟に比べ、大きな負担とならないように定められています。
3.手続きの流れ
(1)筆界特定の申請(申請手数料の納付)
(2)申請の受付(申請情報の審査、受理)
(3)公告・通知(公告と関係人宛の通知)
(4)筆界調査委員の指定
(5)測量費用の予納(予納告知)
(6)筆界特定調査(委員:土地家屋調査士による調査・測量)
(7)意見聴取(筆界登記官による意見聴取等)
(8)筆界特定委員の意見書の提出
(9)筆界特定の公告等 (申請人に通知・筆界特定をした旨を公告・関係人に通知)
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年2月15日 金曜日
平成25年2月8日第331号
遅刻・早退と残業との関係や給与支払形態について勘違いされている方が多々います。給与計算に大きく関わってくることです。そのため、賃金の基本であるノーワーク・ノーペイについて今一度確認しましょう。
1.ノーワーク・ノーペイとは
ノーワーク・ノーペイの原則とは「労働なければ賃金なし」ということです。つまり、出勤しない分について賃金は発生しないことが基本です。
従って、労働者が所定労働日に欠勤、遅刻、早退などをしたときは、それは労働者の都合による労働契約の不履行に該当しますから、欠勤の日はもちろん、各種休暇であっても原則として完全月給制でない限り賃金を控除します。
天災事変や交通ストライキで労働者の責任ではなく、出勤できない場合もその損失は労働者が負担しなければならず、控除の対象となります。
但し、例外もあります。
(1)年次有給休暇
(2)休業手当
・使用者都合(機械の検査、原料の不足等の「経営障害」による休業)の場合
...平均賃金の60%以上の手当
・不当解雇など使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合
...平均賃金の100%の手当
年次有給休暇と休業手当はノーワークであっても賃金を支払う義務が生じます。
2.給与の支払形態
月給制 ...通常、完全月給制をさします。もし欠勤や遅刻があった場合でも、
ノーワーク・ノーペイの原則に反し、欠勤分の給与を差引かない制
度
日給月給制...欠勤(年次有給休暇を除きます)があった場合、ノーワーク・ノーペ
イの原則が適用されて、欠勤分の給与は、月給額から差引く制度
3.遅刻・早退と残業時間の関係
労働時間についての基本的な考え方は実労働時間主義です。つまり、労働時間は実労働時間が1日8時間(変形労働時間制は平均して1週40時間)を超えないかぎり残業とは解釈されません。
但し、就業規則や賃金規程に「○○:○○以降に働いていた場合は割増賃金を支払う」等の旨を定めていれば、支払義務が発生します。これは実労働時間主義ではなく、定時制ということを就業規則や賃金規程で定めているからです。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年2月 5日 火曜日
平成25年1月23日第330号
大学3回生の採用活動が本格化する時期となりました。もうすでに、内定を出された企業もあるのではないでしょうか。 万が一、諸事情により内定を取消したい場合は次のことに注意しましょう。
1.内定は労働契約の成立
一般的に採用内定した場合、企業と内定者間で、入社日を始期とする「解約権留保付労働契約」が成立しているものとされています。つまり、採用内定通知書に記載されている取消事由が発生した場合、新卒内定者が大学等を卒業できなかった場合等限られた場合にだけ、労働契約を解約することができる条件が付されているに過ぎません。基本的に入社後の試用期間中の労働者と同じと思ってください。
そのため、合理的な理由もなく、内定取消をする場合は解雇権の濫用となり、内定取消が不当と判断されると、無効となります。
2.内定取消が認められる場合
では、経済事情や経営状況の悪化など、企業の一方的な理由でも、内定取消が認められるのはどのような場合でしょうか。
(1)内定取消が経営上の十分な必要性に基づくもので、やむを得ない措置である
こと
(2)内定取消を回避する努力を尽くしたこと
(3)内定取消対象者選定について、客観的・合理的基準を作成し、適正に運用し
たこと
(4)内定取消を行なうにあたり当該内定者と誠実かつ十分に協議したこと
といった整理解雇の要件と同様に社会通念上相当として認められることを要します。
3.金銭的補償
内定取消が認められたとしても、内定取消による深刻な打撃を受ける内定者に、金銭的補償(損害賠償)を求められることも多々あります。
補償額の基準は定められていませんが、最低でも1ヵ月分の給与は念頭においておきましょう。また、新卒内定者であった場合は、1年間就職時期が遅れることも考えられ、1年分の賃金程度の額となることもあります。
内定取消はよほどのことがない限りできないと認識し、法的紛争への発展や企業イメージのダウンなど大きな損害を被ることがないようにしましょう。そのためにも、内定取消者との真摯な話し合いが必要です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2013年1月11日 金曜日
平成25年1月8日第329号
健康保険加入者本人が業務外の事由で病気やケガのために仕事を休み、給与の支払いがない場合、加入健康保険制度から休業補償として「傷病手当金」が支給されます。支給要件は次の4要件をすべて満たす必要があります。
・ 業務以外の事由による病気やケガのため療養中であること
・ 療養のための労務不能であること
・ 連続3日間を含み4日以上仕事を休んでいること
・ 給与の支払いを受けていないこと
退職後の継続給付としての受給要件は、次の2点です。
(1) 退職までに被保険者期間が継続して1年以上あること
(2) 退職日の前日までに連続して3日以上休業し、退職日も休業していること
(1)の要件について、保険者が変わっても1日の空白もなく被保険者資格が継続していれば、加入期間が通算され要件を満たします。この要件でトラブルとなるケースでは、社会保険料を鑑みて(末退職すれば当月分と翌月分の2ヵ月分の保険料負担が発生)、又は勘違いにより、例えば月末の31日が日曜日の場合、退職日を30日の土曜日(資格喪失日は31日)とし退職月の保険料のみ支払った場合などにおいて、当該被保険者(本来の資格喪失日は翌月1日)が、1日の空白を伴って転職することとなり、その後1年以内に業務外の傷病で傷病手当金の支給申請をしたとき、要件を満たさず不支給となりトラブルとなります。
(2)の要件の注意点は、退職日(資格喪失日の前日)に残務整理や引き継ぎ業務で出勤しても、出勤日扱いとしないことです(給与が支払われれば労務に服していると判断され、受給権を失います)。
継続給付の注意点として他には、退職後1日でも労務に服すれば権利を失うことです。たった1日でもアルバイトをして賃金を受けると以後傷病手当金は支給されません。また、雇用保険の基本手当の支給申請をすれば、労務不能ではなくなったとして継続給付は打ち切られます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年12月26日 水曜日
平成24年12月23日第328号
例年なら、12月中旬には来年度の税制改正大綱がまとまるのですが、今年は総選挙のため税制改正も予算編成も年を越します。そこで、現段階の情報をお伝えします。
1.所得税関係
(1) 給与所得控除額
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額の上限が245万円となります。
(2)特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算
退職所得の金額の計算において、勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等に係る退職所得の2分の1課税が廃止されます。
(例)勤続年数4年の法人役員が退職金1,000万円を受け取った場合
従来は、(1,000万円-160万円※)×1/2=420万円が退職所得でしたが、平成25年1月1日以後は、勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等に係る退職所得の2分の1課税が廃止されるので、1,000万円-160万円=840万円
となります。※退職所得控除額 40万円×4年(勤続年数)=160万円
2.住民税関係
(1)特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算
住民税においても、上記1(2)と同様の扱いになります。
(2)退職所得に係る個人住民税の10%税額控除
退職所得に係る個人住民税について、従来その税額を10%減額する措置(10%税額控除)がなされていましたが、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等については、その10%税額控除が廃止されます。
3.消費税関係
事業者免税点制度
平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について、従来の基準期間(個人は、その前々年、法人は、前々事業年度)の課税売上高での判定に加えて、特定期間(原則として、個人は前年1月1日から6月30日、法人は前事業年度の前半の6ヵ月間)における課税売上高が1,000万円を超える場合には、事業者免税点制度が適用されなくなります。
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年12月10日 月曜日
平成24年12月8日第327号
平成24年8月10日、民主、自民、公明の3党の賛成多数により、社会保障と税の一体改革関連法案が参議院で可決され、それに伴い、年金に関しても大きな改正がありました。施行日等を確認しましょう。主な改正点は次のとおりです。
1.受給資格期間の短縮(施行日:平成27年10月1日)
納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えるため、老齢基礎年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮します。ただし、受給資格期間を満たせば、いくらの年金額が受け取れるのかという別の問題が浮上します。
2.基礎年金国庫負担1/2の恒久化(施行日:平成26年4月1日)
平成21年度以降、基礎年金の国庫負担割合は2分の1とされてきましたが、財源は綱渡り状態でした。この財源を平成26年度からの消費増税(8%)により安定的に確保し、恒久的に国庫負担割合2分の1を維持しようとするものです。
3.短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用拡大(施行日:平成28年10月1日)
社会保険における「格差」を是正するため、非正規労働者に社会保険を適用します。(1)週20時間以上(2)月額賃金88,000円以上(3)勤務期間1年以上(4)従業員501人以上の企業で適用されます。
当然に保険料は労使折半ですので、対象企業は運用面、費用等準備が必要です。
4.産休中の厚生年金保険・健康保険の保険料免除(施行日:平成26年8月21日までに施行)
次世代育成支援の観点から、産前産後休業期間中被保険者が労務に従事しなかった期間の厚生年金保険料を免除します。また、産前産後休業終了後に育児等で報酬が低下した場合、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額を改定します。
5.遺族基礎年金の父子家庭への支給(施行日:平成26年4月1日)
遺族基礎年金の受給権者を死亡当時生計維持関係にある「子のある妻」または「子」に対してのみから、「子のある夫」に対しても拡大しようとするものです。
ただし、1、2、5については消費税改革施行時期に合わせて施行されます。かつ、消費税増税法には景気条項が伴っており、今後政局を含め、ますます情勢への注目が必要です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年11月26日 月曜日
平成24年11月23日第326号
本年も終わりに近づいてきました。長引く不況等で売掛金や貸付金等の回収が滞っていませんか。金銭の支払を請求しても相手が応じてくれない、反応がないといった場合には、裁判所の力を借りて相手に支払をするように請求する方法があります。その中で手軽に行なえる『支払督促』をご紹介します。
1.支払督促とは
支払督促とは日本の民事司法制度の1つであり、一定の金銭などの支払いを求める場合に、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に申立てをする手続きのことをいいます。
2.支払い督促の条件
次の2つの条件を両方満たさなければならなりません。
1)金銭の支払いを目的とする請求であること
金銭の支払い以外では金銭の代替物又は有価証券に限られています。
2)債務者(=支払いを求められている者)に送達することができること
これは債務者が支払督促の存在を認知し、督促に対する異議申立ての機会を
十分に確保するとともに、支払督促の濫用を防ぐことが目的です。
3.支払い督促のメリット
1)安価
裁判を行なう場合に比べ、印紙代が半分程度の金額で済みます。費用は印紙
代、切手代を入れて、請求額にもよりますが、数 千円です。また、その費用は
支払督促の際に相手に請求することができます。但し、当事者が法人であれば、
その分の登記簿 謄本の取得代(1通1,000円)が別途必要です。
2)郵送で申立てることが可能
3)債権者(=支払いを求めている者)が裁判所に出頭不要
※但し、訴訟に移行した場合は裁判所に行かなければなりません。
4)書類審査のみ
裁判所は証拠調べをせずに支払い督促を実行するので、手続は簡単かつ迅速
に進みます。しかし、近年振込め詐欺に支払督 促が悪用されているという一面
もあります。
5)迅速
債務者が異議申立てをしなければ、早くて申立てから1ヵ月くらいで強制執行
ができることもあります。
金銭の回収にお困りの場合は、一度『支払督促』を検討してみてください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年11月 7日 水曜日
平成24年11月8日第325号
日本の住宅は従来まで20~30年で建て替えられてきました。 現在では60年程度を目安とし、長く住み続けられる性能の住宅が求められています。長く住み続けるためには、構造体の耐久性が重要です。これは耐震性や省エネ性とも関わりの深い事項です。
今回は構造体に使われる素材ごとの注意点を確認します。その概要を理解しておきましょう。
構造体ごとの耐久性についてのチェックポイント
1.木材:
水分や湿気に強い材料か、乾燥の度合い、防蟻処理が充分か
木材の強度や品質、精度は乾燥の度合いで異なります。従来、住宅用の木材は1年ほどの時間をかけて乾燥させていました。しかし、近年はコストの問題などがあり、専用の乾燥機を使って乾燥させることが多いです。お風呂の材料によく使われるヒノキなどの木材は湿度に強いですが、高額です。そのため、スギなどの木材が構造体に広く使用されています。そこで注意したいのが木材の乾燥状態です。
また、木材は種類によってシロアリの被害が異なります。その点にも注意が必要です。
2.鉄骨材:
防サビ加工が充分に行われているか
鉄骨材は木材と比べて品質や性能、精度を確保しやすい素材です。しかし、その耐久性を損なうのはサビの発生です。そのため、住宅の構造材として加工する際には、防サビの処理が大切になります。処理の種類は様々ですが、亜鉛メッキ処理を行なうのが一般的となっています。サビ止めの塗料を塗っている場合もあります。
3.コンクリート:
養生期間が充分とられているか、塩分が含まれている砂利(海砂利)が使われていないか、クラック(ひび割れ)が存在しないか
住宅の基礎を形づくるコンクリートの強度は、住宅の強度全体に影響を及ぼします。
コンクリートも腐食は避けられません。コンクリートはアルカリ性なので水分中の酸性物質と反応して中性化します。それによってもろくなった部分から、水分が内部に浸透し、内部の鉄筋がさび付きます。それが強度を低下させる原因の一つとなります。
防水や断熱施工も含め、しっかりと施工を行なってくれる信頼のおける依頼先を選びたいものです。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年10月24日 水曜日
平成24年10月23日第324号
平成24年10月1日から労働者派遣法改正法が施行されました。
派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため、派遣会社・派遣先には新たに義務が課されました。
新たに課された主な義務は次のとおりです。
派遣会社に課された義務
(1)雇用期間が30日以内の日雇派遣の原則禁止
但し、ソフトウェアの開発や財務処理などの政令で定める業務に派遣する場合、60歳以上の人、雇用保険の適用を受けない学生、副業として日雇派遣に従事する人※、主たる生計者でない人*のいずれかに該当する人を派遣する場合は例外として認められます。※生業収入500万以上 *世帯収入500万以上
(2)グループ企業内派遣を8割以下に規制
(3)マージン率や教育訓練に関する取組み状況、派遣料金の明示
雇入れ時、派遣開始時、派遣料金額の変更時には派遣労働者本人への派遣料金又はッ所属する事業所における派遣料金の平均額(1人当たり)の明示が求められます。
(4)待遇に関する事項などの説明
労働契約締結前に派遣労働者に対し、賃金の見込み額や待遇に関すること、派遣会社の事業運営に関すること、労働者派遣制度の概要の説明が義務化されました。
(5)有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
有期雇用の派遣労働者の希望に応じ、無期雇用への機会の提供、派遣先での直接雇用の推進、教育訓練の実施のいずれかの措置をとるよう努めなければなりません。
(6)派遣労働者が無期雇用労働者か否かを派遣先への通知事項に追加
派遣先に課された義務
(1)派遣先の都合で派遣契約解除時に講ずべき措置
新たな就業機会の提供、休業手当などの支払いに要する費用の負担などの措置です。
(2)労働契約申込みみなし制度の導入(平成27年10月1日施行)
派遣先が違法派遣であると知りながら、派遣労働者を受入れている場合、違法状態が発生した時点で派遣先が派遣労働者に直接雇用の申込をした者とみなす制度です。
派遣会社・派遣先の両方に課された義務
(1)離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止
直接雇用者を派遣労働者と置き換え、労働条件を切り下げることを防ぐためです。
(2)派遣先で同種の業務に従事する労働者との均衡待遇の確保
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年10月11日 木曜日
平成24年10月8日第323号
1.なんのために使った費用?
簿記を教えているときに「決算の結果は勝手に出るものではない、役員、社員皆の意思決定や活動(営業や製造など)の結果が反映されています。」と教えています。企業の経営成績である「業績」を良くしようとすれば、「皆さんの意思決定や活動を変えないと変わらない。」ということを何回も繰り返し話をしています。ところが、自分たちの取った活動の結果がどんな費用に計上されているのか、製造原価なのか、営業・管理費なのかをすべてごちゃまぜにして計算している企業が多いのです。月次の在庫も正確に把握せず(数量も原価も)すべてどんぶり勘定。これでは自分たちの企業の実態が分かりませんし、どう意思決定や活動を変えれば利益につながるのかがなかなか見えてきません。
2.製造コストは何故把握しないといけないのか?
高度成長時代(ずいぶん昔のこと)のように需要そのものが大きく伸びているときには何をしても、どんぶり勘定でも利益が出ました。バブルが崩壊して久しいですが、特にここ10年間で海外企業との品質価格競争にさらされ、得意先からはどんどん価格下げの要求が厳しくなってくると、どんぶり勘定をしてきた企業はその要求に応えられない体質になってしまっています。1単位あたり(個数、㎡、セット等の売買単位)のコストが分からなければ勝負になりません。だからこそ製造コストの計算が必要になってくるのです。
3.どうしたらいいのか?
まず、使った費用は製造原価と販売費・管理費に最低でも分ける必要があります。製造原価をさらに製品別等に配分し、適切な製品別コストを計算するにはやはり専門的な知識が必要です。担当されている税理士の先生方に相談され、計算の仕組みを考えてみるといいでしょう。それで、儲かっている製品、赤字を出し、足を引っ張っている製品、儲けさせてくれている得意先、要求だけきつくて儲けさせてくれていない得意先等の分析ができます。それを基にいろいろな戦略が取れるようになってきます。製造原価の計算ができるようになると、月次でも製品や材料の在庫の把握もできるようになります。それでしっかりと正確な実績を把握し、それを羅針盤として経営のかじ取りをしていくことが必要です。
あなたは、いつまでも過去の経験と「勘ピューター」に頼った経営をしますか?
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年10月11日 木曜日
平成24年9月23日第322号
平成24年9月1日から肢体不自由の障害年金について、認定基準が改正されました。肢体不自由の主な障害認定基準として、上肢の障害・下肢の障害・肢体の機能の障害の3つがあり、脳梗塞や脊髄損傷のような脳・神経系統の障害や、筋萎縮性側索硬化症・リウマチ・多発性筋炎のような多発性の障害に関しては、上肢の障害・下肢の障害の基準を適用せず、肢体の機能の障害によって認定するとされております。この肢体の機能の障害に該当した場合、上肢の障害や下肢の障害と比べて等級が低くなってしまうという不利益が存在しておりました。
例えば、事故などで神経を損傷し、右足だけ完全に麻痺をして筋力が喪失した場合ですと、「下肢の障害」であれば2級となるところ、「神経系統の障害による肢体の機能の障害」で認定され、一上肢・一下肢のみの障害の場合は3級とするとされていました。外見上、共に右足が日常生活に用をなさない状態ですが、かたや2級で、かたや3級になってしまうという不利益が発生しており、ずっと問題提起されておりました。 そのような不利益を解消するために、今回の改正では、肢体の機能の障害で認定しなければいけないと定められている障害においても、その障害が一上肢・一下肢にのみ障害が存在している場合は、それぞれ上肢の障害・下肢の障害の基準で認定すると変更になっております。
障害者雇用で採用された従業員さんや、脳梗塞を発症してしまった従業員さんがおられましたら、今回の改正によって障害年金の等級が変更される可能性があります。しかし、年金というのは申請主義となっており、患者さんから額改定請求という等級変更を求める申請をしない限り等級はそのままです。
また、すでに障害年金を受給されておられる方には、定期的(数年毎:障害のケースによって、2年・3年・5年・7年・永久認定)に更新の手続きがあるのですが、その更新の際に等級が上がることはめったにありません。自分から申し出ないと等級が上がりませんし、年金機構から受給者に改正の案内が行くこともありません。該当者がおられましたら、是非今回の改正の案内をしてください。
(スマイルグループ 社会保険労務士 )
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年9月19日 水曜日
平成24年9月8日第321号
労働基準法第39条(年次有給休暇)に「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。(以下省略)」と規定されています。
「労働日」とは、原則として暦日計算によるものとされています。したがって、通常の勤務が時間外労働によって翌日の午前2時までに及んだ場合、当該翌日が年次有給休暇(以下、年休)取得日であれば、歴日による1労働日とはならず、年休を与えたことにはなりません。同様に、年休取得日に年休取得者を会社へ一時的に仕事で呼びつけた場合も年休を与えたことにはなりません。
年休の不利益取扱いに関しては、労基法附則第136条に「使用者は、年休を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と規定が置かれています。精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際し、欠勤日等として取扱うことは、権利として認められている年休取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならないとしています。
では、年休取得時に皆勤手当を減額する措置は、上記の附則第136条に抵触し、必ず無効となるのでしょうか。
判例では、年次有給休暇取得時の皆勤手当減額については「法の趣旨からみた場合には必ずしも望ましいものではない。」としています。
しかし、「その趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、年休の取得に対する事実上の抑止力の強弱等の事情を総合的に判断した結果、年休取得を抑制し、かつ、その権利の保障を失わせるとまではいえない場合、年休取得時における皆勤手当の減額は有効」(沼津交通事件、最高裁二小、平5.6.25判決)とした裁判例もあります。
通常、年休取得時の皆勤手当減額を行う際、その減額の程度等を勘案し、年休取得を著しく抑制することのないよう取扱うことが必要となります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年9月19日 水曜日
平成24年8月23日第320号
東日本大震災からの復興の財源確保のため、復興特別所得税が創設されました。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に、給与や報酬などを支払う者は、その支払う給与等や報酬等について、所得税の源泉徴収に加えて復興特別所得税の源泉徴収及び納付が必要となります。
源泉徴収する復興特別所得税は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%となっています。
具体的な給与と報酬に係る源泉徴収は次のとおりです。
1.給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表(復興特別所得税額も含まれた税額表)に従って源泉徴収していきます。
また、給与ソフトなども平成25年1月1日以後に支払われる給与等については、給与ソフトの更新がされていれば、復興特別所得税が含まれた金額が自動計算されます。
2.報酬等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%です。そのため、源泉徴収すべき税率が報酬の10%の場合、所得税及び復興特別所得税の額は次のようになります。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
=支払金額等×10.21%(合計税率※1)
※1 合計税率(%)=所得税率10%×102.1%
<具体例>・・・52,500円(消費税等2,500円を含む)の報酬を支払う場合
●変更前(平成24年12月31日以前)
報酬の額 50,000円
消費税等の額 2,500円
源泉所得税※2 5,000円=50,000円×10%
差引支払額 47,500円=50,000円+2,500円-5,000円
※2 請求書等に報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、報酬の額の10%を源泉徴収することが可能です。
●変更後(平成25年1月1日~平成49年12月31日)
報酬の額 50,000円
消費税等の額 2,500円
所得税及び復興特別所得税 5,105円=50,000円×10.21%
差引支払額 47,395円=50,000円+2,500円-5,105円
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年8月17日 金曜日
平成24年8月8日第319号
平成24年8月3日、有期雇用で働く人が、契約を更新して通算5年を超えた場合、本人の申し込みによって期間の定めのない(無期)雇用となること等を義務付けた労働契約法の改正案が参議院本会議で可決、成立しました。
平成20年秋以降の経済情勢の悪化(リーマンショック)の際に、有期契約労働者の雇止めや契約期間途中での解雇が増加するなど、有期契約労働者の雇用の不安定さや、処遇格差が広く認識されるようになったことが、背景にあります。主な改正点を記載します。
●有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
(1)無期転換制度
有期労働契約期間が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みに
より、無期労働契約に転換させる仕組みを導入。
(2)無期転換後の労働条件
現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く)と同
一の労働条件(別段の定めがある部分を除く)とする。
(3)クーリング期間
原則として、当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が
満了した日と当該使用者との間で締結された次の有期労働契約との間に空白
期間があり、当該空白期間が6ヵ月(その他厚生労働省令で定める期間)以上
であるときは通算契約期間に算入しない。
●有期労働契約の更新等(いわゆる、雇止め法理の法定化)
有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には解雇権濫用法理を類推適用し、雇止めを制限する法理が規定された。
●期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めのあることにより無期契約労働者の労働条 件と相違する場合、その相違は、業務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合 理であってはならないものとする。
無期転換の直前の雇止めや、一定のクーリング期間をおけばいくらでも有期契約を反復更新することができるという点、無期転換後であっても待遇は相変わらず正社員との格差が出るなど、問題点と課題が多く、来春(一部新聞では平成25年4月1日)施行までに大いに検討が必要と思われます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年8月17日 金曜日
平成24年7月23日第318号
平成16年公表の「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために、事業者が講ずべき措置に関する指針」の改定に伴い、「雇用管理に関する個人情報の取扱いガイドライン」が再編されました。適用は平成24年7月1日からです。
ガイドラインの内容は次のとおりです。
1.ガイドラインの適用対象
・5,000人分を超える個人情報を事業活動に利用、かつ、労働者を使用する民
間事業者
・上記対象事業者の雇用管理情報の取扱い
2.情報取得・利用のルール ・雇用管理情報の利用目的をできる限り特定する。
・利用目的はあらかじめ公表するか、情報取得の際に本人に通知または公表す
る。
・利用目的範囲内で雇用管理情報を扱う。
・雇用管理情報は適正な方法で取得する。
3.個人データ管理・取扱いのルール
・個人データについては、正確かつ最新の内容に保つ。
・漏洩、滅失、毀損を防ぐための安全管理措置をとる。
・取扱う従業員や委託先を監督する。
・個人データを第三者に提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
4.本人からデータ開示などを求められたときの対応
・遅滞なく開示するなど、適切に対応する。
・雇用管理情報の取扱いに関する苦情に対して適切かつ迅速な対応をする。
・苦情受付窓口の設置などの体制整備に努める。
ここでいう個人情報とは顧客情報、従業員情報など、すべての種類の個人情
報であり、労働者等(採用応募者・退職者を含む)の氏名、連絡先、特定の労働
者を識別できる映像などの情報、家族関係に関する情報などを指します。
今回の再編は事業者に現在の法・指針・解説に基づく運用の変更を求めるも
のではありませんが、改めて、企業が取扱う個人情報や労働者等やその家族
状況等の機微に触れる情報を多く含む「雇用管理情報」の収集や管理方法等
について、適正に実施されることが求められています。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年8月17日 金曜日
平成24年7月8日第317号
長引く不況で家賃滞納も増えています。ここで法律の手順を、おさらいしてみます。
1.手紙・電話・訪問による家賃支払いの督促
単に『忘れていた』というような改善の余地がある場合もあります。 『支払う気が
ない』とか居留守を使ったり、約束を破るなど悪質な場合もあります。
2.内容証明郵便(配達証明付)で、条件付解除通知による督促
後日の証拠となります。ここまでの時点で話し合いが成立することもあります。
解決した場合でも再発防止のため、契約書や連帯保証人を見直す必要があり
ます。
3.契約解除
与えた猶予期間内に滞納賃料を支払わない場合は、契約解除となります。
4.訴訟提起
解除後は直ちに訴訟提起となります。第1回期日は1ヵ月以内です。 期日まで
に任意交渉が成立し、退去となることもあります。
5.明け渡しの判決又は和解
賃借人が分割払いや明け渡し期間の猶予等、和解を求めてくることがありま
す。 和解できない場合は、判決となります。賃借人に送達後、2週間で確定し
ます。
6.強制執行(催告)
執行官が建物に入り『約1ヵ月後に退去するよう』書面で警告します。
7.強制執行(断行)
任意の退去がない場合、荷物を出し、鍵を変えてしまいます。
8.目的外動産の保管
保管替えを行う動産類については、破損等ないように注意が必要になります。
保管場所を執行対象建物内とすることもあります。
9.目的外動産の処分
目的外動産の引き渡しや売却、あるいは廃棄処分を行います。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年6月21日 木曜日
平成24年6月23日第316号
社内メンター制度
1.メンター制度
近年、メンター制度をとりいれる企業が増加しています。メンター制度とは、会
社や配属部署における上司とは別に、指導・相談 役となる先輩社員(メンター)
が、仕事の経験が足りない新入社員や中途採用者(メンティ)をサポートする制
度のことをいいます。この制度を導入する目的は様々ですが、多くの会社では
新入社員の定着化を目的としています。新入社員は壁にぶつかったり、悩みを
抱え、誰かに相談したいと考えていたりしても、直属の上司にはなかなか相談
しにくいものです。そこで、本音を真摯に聞いてもらい、アドバイスを得ることが
できるメンター制度に注目が集まっています。
2.メンター制度の長所
メンター制度を取り入れる長所は次のとおりです。
1)新入社員等(メンティ)にとって
・会社の風土や独自の制度を学び、早く馴染むことができる。
・将来への不安の解決ができる。 ・早期での戦力化が望める。
・仕事への取組み方を学び、問題解決能力や仕事に対する意欲・自主性が
生まれる。
・自己洞察力・対人関係能力が高まり、コミュニケーション能力が向上す
る。
2)先輩社員(メンター)にとって
・後輩の指導・育成を通し、マネジメント技術が向上する。
・人間関係力が強化され、人を育てる意識が向上する。
・サポートを通じて、新たな学習の機会ができ、自己成長が望める。
3)会社にとって ・新入社員の定着率が向上する。
・先輩社員のノウハウや経験の継承ができる。
・社内コミュニケーションの向上及び人間関係トラブルの回避ができる。
三方よしのメンター制度ですが、せっかく制度を取り入れても、形骸化しては
意味がありません。そのためには、メンターがメンティに対し愛情をもって接する
ことやメンターとメンティの信頼関係の構築が欠かせません。 人の成長なくし
て、企業の成長は望めません。ぜひ、御社でも人の成長を加速させるメンター
制度を取り入れてみませんか。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年6月21日 木曜日
平成24年6月8日号第315号
吾唯知足、うん? 友人の陶芸家の個展に行くと、「口」を真ん中に「吾唯知足」こんな文字を四方 かたどった色紙が展示されていた。じっと眺めていて、やっと、「吾唯知足」と読めた。気に入ってすぐに購入してきた。どんな意味か?「吾れ、唯だ、足りるを知る」と読む。人間の欲(権力欲、金銭欲、食欲、性欲等)には際限が無い、その欲が人間の苦悩をもたらす、これは、仏教の教えである。かと言って、人間に欲が無ければ、向上心も生まれないし、努力もしなくなってしまう。その欲の過ぎるのを戒めた言葉が「知足」足りるを知るということ。
企業に当てはめるとどうであろうか
企業が、利益だけを追求して、何でも利益が出ればいいというような方針を出し事 業をしていけば、いずれ社会から制裁を受け、企業として成り立たなくなってしまう。 「CSR」( Corporate Social Responsibility)という企業の社会的責任が重要視されてきたのはこうした企業の利益だけを追求する行き過ぎを制限するためであろう。企業も「知足」が必要だということである。
ソーシャルビジネスは?
ソーシャルビジネスも流行りである。事業モデルとしては従来からあるものである。貧困、環境問題、失業問題等の社会的問題を企業という形態で解決していくというビジネスモデルである。日本の経済は、ここ20年の間に徐々に国際競争力を無くしてしまって、大手のメーカー企業は、賃金の安さを求め、台湾、韓国、タイから中国へ、中国からさらにインドネシア、ベトナム、インドへ、このまま続くと最後はアフリカなんていうことになりそう。こうした、製造業の空洞化の経済の穴を埋めるようにソーシャルビジネスが表面に出てきたように思う。ソーシャルビジネスとは言え、事業体として存続して行かなければ、所期の目的も達成できない。「社会性」という理念が先行してしまって、儲けなくて、ボランティアでいいなんて言っていると事業の継続が難しくなってしまう。「社会性」と「企業性」の狭間でソーシャルビジネスは苦労しているようである。
儲けても構わない、「唯、足りるを知」れば。そんなところに落とし所があるように思う。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年5月23日 水曜日
平成24年5月23日第314号
辞めた労働者等が一人で入れる労働組合に加入して、会社に団体交渉を申し込
んでくるケースが増えています。その場合、とりあえずどのように対処するべきか
をお伝えします。
FAX等で団体交渉を開始する通知が送られてきます。日時と場所を指定してき
ますが、殆どのケースで、御社の会議室等を指定してきます。そのような時には、
「あいにくその日時は都合がつかないので、日時と場所について後日通知します。
」と返事をしてください。無視をするのは違法行為になってしまう恐れがあります。
その上で、団体交渉を行う場所を手配します。ここでの注意点は、
・御社以外の施設を利用する。
・借りられる場所の閉館時間の1~2時間前から閉館までを抑える。
以上の点がなぜ重要かと申しますと、労働組合はより有利な条件を飲ませようと
心理的圧力をかけてきます。そのため、御社の会議室等を使用すると、他の従業
員に聞こえるように声を荒げたり、終了時間が来ても帰らず居座ったりし、早く解決
をして問題から逃れたたいと経営者側に思わせるようにしむけます。そうなると、早
く解決をしたいばかりに向こうの言い分を飲まされてしまいがちです。しかし、場所
を会社外にしますと、他の従業員への影響は抑えられますし、閉館時間が来れば
強制的に終了される事ができますので、労働組合が交渉を粘って帰らせてくれな
いという事態は防げます。この2点だけでも相手から受けるプレッシャーを相当軽
減できる効果があります。
次にICレコーダー等で録音するのはお勧めできません。話し合った内容を文章
に起こす作業が必要になった場合、相当な労力が必要となります。もし、労働組
合側がICレコーダーで録音するのであれば、正確性を確認するためにこちらも録
音する事をお勧めしますし、侮辱的発言をされるので名誉毀損で訴える場合も録
音は必要となりますが、それ以外は書記役がその場でまとめた方がスムーズに
進みます。労働組合側も依頼された労働者の手前高圧的な態度で臨んできます
が、決裂させてしまうと裁判するしかなくなり、労働組合に依頼した意味が無くなり
ますので、決定的な対立を望んでいるわけではありません。よって、こちらは余裕
を持って対処すればいいでしょう。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年5月16日 水曜日
平成24年5月8日第313号
「パワーハラスメント(略してパワハラ)」という言葉がよく使われ、社会問題と
なってマスコミにもよく取り上げられます。パワハラとは、和製英語であるpower
harassmentの略語で、権限を濫用して嫌がらせを行うことであり、セクシュアル
ハラスメントと異なり、法律上の定義もなく、その防止を直接義務付ける法律もな
いのが現状です。
その様な中で厚生労働省では、3月に「職場のパワーハラスメントの予防・解決
に向けた提言」を取りまとめ公表しました。「職場のパワーハラスメント」とは、同じ
職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の「優位性を背景(
上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間などの様々な優
位性を背景に行われるものも含む)」に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身
体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいい、次の6類型が挙げられ
ました。
1.身体的な攻撃(暴行・傷害)
2.精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間はずし・無視)
4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、
仕事の妨害)
5.過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低
い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
「職場のパワーハラスメント」は業務上の指導と線引きが難しく、1~3以外の
ケースでは「業務上の適正な範囲」であれば本人が不満に感じてもパワーハラ
スメントには当たらないと指摘されています。具体的判断については、各企業・
職場で認識をそろえ、その範囲を明確にすることが望ましいとしています。
特に今回の報告では、上下関係を示す職務上の地位だけでなく、人間関係や
専門知識等を背景にした嫌がらせによる同僚同士や部下から上司に対する行
為も「パワーハラスメント」とするよう提案をしています。
対応策としては、予防するために
1.トップのメッセージ 2.教育する 3.ルールを決める
4.周知する 5.実態を把握する。
解決するためには、
1.相談や解決の場を設置する 2.再発を防止する等が挙げられています。
企業の職場環境において、また、リスク回避の為にも対応が必要です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年5月15日 火曜日
平成24年4月23日第312号
本年度の税制改正で、主だったものは以下のような内容で、平成24年3月30日に成立し、同年4月1日から施行されています。
なお、社会保障と税の一体改革として、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」が平成24年3月30日に国会に提出されています。この中で、消費税法の税率の改正や、相続税の基礎控除の縮減等が改正案とされています。
1.個人所得税関係
・住宅ローン減税制度の拡充 (認定省エネ住宅の特例の創設)
・給与所得控除に上限を設定 (給与収入1,500万円超は一律245万円)
・特定支出控除の支出範囲の拡大及び適用判定基準の緩和 (給与所得控除
の総額→2分の1)
・勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止
2.相続税・贈与税関係
若年世代への資産の早期移転や省エネルギー性・耐震性備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長する。
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長(3年延長)
・山林に係る相続税の納税猶予制度の創設
3.法人税関係
国内での企業活動を活性化させ雇用の維持・拡充を図っていくこと、東日本大震災からの復興を着実に達成するために、企業の国際競争力の強化や経済成長につなげていくことが重要な課題となっているなかで中小企業の支援、研究開発、環境保護を図る観点から改正・措置を講じる。
・研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の延長(2年延長)
・環境関連投資促進税制の拡充(太陽光・風力発電設備に係る即時償却制度
の創設)
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年4月23日 月曜日
平成24年4月8日第311号
平成9年に制定、平成12年4月に施行された介護保険法も3年を1期として今年度4月から「第5期介護保険事業(支援)計画」が始まります。「第5期」は平成24年度から平成26年度の3年間です。昨年6月に成立した「介護保険法の一部改正」は、介護保険法ができてから2回目の大きな改定となりました。
すでに65歳以上の高齢者が人口の23%を占める「超高齢社会」が、世界のどの国も経験したことのない猛スピードでさらに加速しつつある日本。今回の改定は今から13年後の平成37年、すなわち団塊世代が75歳以上になり高齢化がピークを迎え、ニーズが増大する時季に照準をあわせた皮切りとされています。
今回の目玉はずばり「地域包括ケアシステム」です。現在7兆円の介護費用が、このままでは19~24兆円に増加予想、つまり、増え続ける介護費用を抑制するため地域や在宅でできることはやってください、ともとれる改正。介護保険給付をはずすため(?)の問題点も見えてきます。また、今回はあわせて老人福祉法、健康保険法、社会福祉士法及び介護福祉士法も改正されています。
政府の法律概要説明による、「改正」ポイントは次の6点です。
1.医療と介護の連携強
2.介護人材の確保とサービスの質の向上
3.高齢者の住まいの整備等
4.認知症対策の推進
5.保険者の主体的な取組の推進
6.保険料上昇の緩和
1.の中に「保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする」介護予防・日常生活支援総合事業が盛り込まれました。すなわち、総合事業を導入するかどうかは市町村の判断であり、また、導入した市町村・地域包括センターが予防給付(介護給付)で対応するのか、新たな総合事業(介護保険指定サービス外)を利用するのかも判断できると決めています。
「要支援」者は、改正前まで予防給付(介護給付)であったものが、予防給付(介護給付)か総合事業(介護保険指定サービス外)かを自分で決めることもできず、総合サービス(介護保険指定サービス外)に振替られる可能性がでてくることになります。
介護保険制度の限界を、「地域包括ケアシステム」の名の下、地域・市町村で取組でください、ともとれる改正です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年4月20日 金曜日
平成24年3月23日第310号
平成24年度厚生労働省予算案に基づき助成金の改正(改悪?)が多くあります。その一例をお知らせします。
平成24年4月1日から「労働移動支援助成金」が一部変更されます。
労働移動支援助成金
この助成金は、事業の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労働者に対して、再就職支援を行った事業主に支給されるものです。種類及び改正点は次のとおりです。
1.求職活動等支援給付金
求職活動等の付与した事業主が対象となり、1人につき休暇1日当たり4,000円(中小事業主の場合:7,000円)が給付される給付金です。
この給付金は平成24年4月1日に廃止されます。ただし、今年度3月31日までの離職者に対して休暇を与えた場合は申請できます。
2.再就職支援給付金
民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、再就職を実現させた中小企業事業主に対し、委託費用の2分の1(限度額:1人当たり40万円)が支給されます。
この給付金の改正点は次の2点です。
1)「求職活動などのための休暇を付与し、その休暇日に、通常支払う賃金の額
以上支払ったこと」が要件として追加されます。
※ただし、今年度3月31日までの離職者に対しては現行の取扱いで、この要
件は追加されません。
2)55歳以上の労働者の再就職支援については、助成率が2分の1から3分の2
に引上げられます。
※ただし、このことについても、今年度3月31日までの離職者には、4月以降も
現行の取扱いで、助成率も年齢にかかわらず2分の1のままです。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年4月20日 金曜日
平成24年3月8日第309号
「終身建物賃貸借制度」とは、高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年8月施行)により、単身及び夫婦の高齢者がお亡くなりになるまで住み続けることができる制度です。
1.制度のあらまし
(1)住宅の構造についてバリアフリー住宅であることなど一定の基準があり、
また、賃貸人について終身賃貸事業者であるという、知事・市長の認可を受け
ることが必要です。
(2)この契約を結ぶと賃借人が生きている限り契約は存続し、お亡くなりになった
時に終了します。建物賃借権は相続されません。
(3)賃借人の申出により、この契約を結ぶ前に、1年以内の定期建物賃貸借契
約による仮入居、いわばお試し入居をすることができます。
2.賃借人の資格
(1)自ら居住するための高齢者。(60歳以上)
(2)賃借人と同居できるのは、配偶者(60歳未満も可)又は60歳以上の親族。
(3)配偶者又は60歳以上の同居親族が希望する場合、賃借人の死亡後1か月
以内の申出によって、同様の契約を結び、引き続き賃借することができます。
3.賃貸借契約が解約される場合
(1)賃借人からの解約の申し入れ
①通常通り、6ヵ月前の通知によることができます。
②療養・老人ホームへの入所などにより居住が困難になった時や、親族と同居
するために居住の必要がなくなった時は1ヵ月の通知によることもできます。
(2)事業者からの解約申し入れ
建物老朽化や、賃借人の長期不在などで、かつ、知事・市長の承認を受けた
場合に限られています。
4.その他
(1)借家契約と終身賃貸借を組み合わせた「期限付死亡時終了賃貸借」という形
態も作られています。
例えば定期借家契約が10年とすれば、10年後か死亡かのどちらか早い時
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年4月20日 金曜日
平成24年2月23日第308号
私たちは、成長の過程でいろいろな人に関わっています。その関係が生み出したものが今の「私」であると言ってよいでしょう。褒められたこと、叱られたこと、注意されたこと、助けられたこと、突き放されたことなどが思い出されます。そのようなかかわり方の1つとして、しかも成長に強い影響を与えるものとして「フィードバック」があります。
フィードバックは成長の促進を援助するための1つの方法です。
1.個人の成長を促進する
個人の成長の促進を援助するための方法はいろいろあります。自分中心(援助
者)から相手中心(非援助者)にならべると、支持・命令、指導忠告、フィードバッ
クの順になるでしょう。自分で考え、行動する人への成長のために最も有効なの
は、 フィードバックだとされています。
2.関係の成長を促進する
深い関係、つまり信頼関係をつくっていくためには、相手に対する今の思いを、
ありのまま相手に返すことが大切です。
3.チームの成長を促進する
フィードバックは、チームの活性化を図るため有効な方法です。相互フィードバ
ックの過程がそのままチームの活性化につながっていくと言えるでしょう。
フィードバックは日常生活そのもの
フィードバックするときの留意点を述べます。
・できるだけ具体的に、描写的に述べる。データに基づくことで、根拠が必要。
・先ほどのあの場面はであなたはこうしていたという具合に、時と場面を明示する
とよい。
・良い、悪いは言わない。
・見えたことだけでなく、私に与えた影響、特に気持ちも伝える。
・相手が受け入れやすいように、評価は禁物。クッション言葉などを使おう。
・「私は・・・」メッセージで。
・自分の考えを相手に押し付けない。どうするかは相手に任せる。
・変化が可能なことに限られる。努力しても変えようがないことは言わない。
基本的なこととして、フィードバックは相手中心であること。相手の成長を願ってなされるものです。そのためには相手に耳を傾けること、相手の発言を相手の立場に立って聴くこと、相手をよく見て言葉ではないからだのサインを見逃さないことが重要です。フィードバックは「鏡になること」なのです。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年2月17日 金曜日
平成24年 2月8日 第307号
日本の経済情勢はどうなっているの?
大雑把にいって日本のGDP(国民総生産)は、500兆円、日本の国債地方債をあわせて1000兆円、支払い能力を示すプライマリーバランス(基礎的財政収支)は2倍を超えています。企業でいうと、債務超過の状態になっています。また、国有財産も道路、橋梁、国有林等を含んだ資産総額で計算しても債務超過です。さらに、昨年は、円高、原油高(震災の影響もあり)と製造業の空洞化のあおりを受けて貿易収支も赤字に転落し、今年以降もしばらくこの基調が続く見込みです。それに対して、商社は、海外での投資案件からの配当収入が入り、大幅な増益となりました。しかし、国内の雇用には結び付かず、60歳以下の働く人たちの層でも生活保護を受ける人たちが増え続けています。
分かり易く日本の財政を家計に例えてみると・・・
景気はパッとせずリーマンショック前は、510万円もあった年収(税収)が423万円へ減ってしまいました。さらに追い討ちをかけるように出費はかさむ一方です。
(1)おじいちゃんの医療に係る費用(社会保障費) 264万円
(2)地方の中小企業に勤める長男の給料が少ないので仕送り
(地方交付税) 166万円
(3)塾へ通いたいという次男へは予算が苦しいので据え置きそれでも授業料
(文教費・・・義務教育、国立大学への補助等) 100万円
(4)過去の住宅ローンや教育ローンの支払いは、元利合わせて
(国債元本償還資金、国債残高に対する利息) 219万円
(5)さらに、東日本大震災の被災した実家へ再建費用が新たに10年ローンを組んで何とか
支援した(震災による補正予算) 116万円
差引足らない資金は、長期ローン(新規国債発行額)を組んで補っています。その額は、なんと442万円にも及び年収423万円を上回ってしまっています。(毎日新聞記事から形を変えて)と言うことになるようです。こういった状況下で「一体改革」の名のもとに消費税の増税議論がなされています。一体とは社会保障費のあり方との一体です。これらの数字は、100万円を10兆円単位に読み替えると国家予算になります。
さて、私たちの未来の生活はどうなるのでしょうか?それでも、居酒屋は繁盛しています。いつも不思議に感じるのは私だけでしょうか?
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年1月23日 月曜日
平成24年1月23日第306号
乾燥した天候が続き、インフルエンザが各地で流行しています。皆様の事業所ではどのような対策をとられていますか?
最近では定年年齢を引き上げたり、定年そのものを廃止する事業所が増えています。また、国も年金支給年齢引き上げを画策しているため、定年延長を法律で義務化する方向になっています。そのため、事業所で働く労働者の中に、高齢の方の割合が増えてきました。そこで高齢の従業員の健康対策として、肺炎及びインフルエンザの予防接種を受けるよう推奨してください。
日本人の死亡率は平成17年の時点で、1位 がん:30% 2位 心疾患:16% 3位 脳卒中:12% 4位 肺炎:10% 5位 不慮の事故:4%です。肺炎で亡くなる確率は事故で亡くなる確率の倍以上となっています。事業所で重要なポジションにおられる方が、職場で流行したインフルエンザが原因で肺炎となり、亡くなるという事例もあります。その場合、会社にとって非常に大きな損失となり、業務に支障をきたす恐れもあります。そこで、会社としては、65歳以上の従業員と65歳未満でも糖尿病・肺疾患・心臓疾患等の既往症をお持ちの従業員に、積極的に予防接種を受けるよう勧めてください。
肺炎といいましても、原因となる起因菌は様々あります。一番の起因菌はマイコプラズマと呼ばれる病原体ですが、これは、幼児・若年成人が中心にかかるもので、年齢が上がると共に感染割合は下がります。70歳以上だと1番が肺炎球菌であり、インフルエンザウイルス、嫌気性細菌、緑濃菌と続きます。高齢者が一番肺炎になりやすい肺炎球菌のワクチンを接種すると高齢者の肺炎の80%を予防できるといわれています。さらに、2番目に多いインフルエンザワクチンも併せて接種することで非常に効果的となります。
肺炎球菌のワクチンに関して、重篤な副作用は3例報告されています。しかし、死亡した例はまだ無く、比較的安全なワクチンであり、そのリスクはインフルエンザワクチンと同程度とされています。効果も非常に高いことから、国も積極的な摂取を勧めています。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年1月23日 月曜日
平成24年1月8日第305号
昨年4月、業務委託契約を結ぶ個人事業主にも団交権を認める最高裁判決が2件(カスタマーエンジニアの「INAXメンテナンス事件」、オペラに出演する合唱団員の「財団法人新国立劇場運営財団事件」)続けてあり、両裁判とも下級審の判決を破棄し、労働組合法の労働者性を認める判決を下しました。
下級審である高裁控訴審での、「INAXメンテナンス事件」の判決は、法的な従属関係を基礎付ける要素として、業務依頼に対する諾否の自由、時間的・場所的拘束、業務遂行についての具体的指揮監督、報酬の業務対価性等の有無、程度等を総合考慮すべきとして、労働者性を否定。「財団法人新国立劇場運営財団事件」においても、業務提供に関する諾否の自由、指揮監督の有無、報酬の支払い関係等から、合唱団員について、労組法上の労働者性を否定しました。
一転、最高裁判決により、労組法上の労働者は、団体交渉の必要が認められる者を範囲とし、労働基準法の労働者の適用範囲より幅広い概念としています。
判決後の厚生労働省労使関係法研究会による労組法上の労働者性判断基準として、(1)事業組織への組込み状況、(2)業務依頼に対する諾否の自由、(3)契約内容の一方的決定、(4)労務供給の日時・場所の拘束、(5)指揮監督の状況、(6)報酬の労務対価性、(7)労務供給者の事業性、(8)労務供給者の専属性を挙げています。このうち、労働基準法の労働者性判断基準になっていない項目は(1)と(3)です。
今後、企業としては、労基法上の労働者だけでなく、労組法上の労働者対策も必要となってきます。業務委託契約・請負契約でありながら、管理が甘いと、突然、組合(ユニオン)からの団体交渉があって拒否できない場合もあります。組合からの団交等に備え、日頃からの注意が必要となります。
対策としては、適法な業務委託・個人請負として、その労務供給者が(1)自由裁量権等による独立した事業者性、(2)兼業の自由、(3)労働時間の自由・自己管理、(4)勤務管理・就業管理・服務規律等の不拘束、(5)業務の外形的独立、(6)使用従属的な業務命令がない、(7)契約は対等の立場において複数の中から自由に選択、(8)請負内容等が注文指図により独立遂行が明白、(9)事業者としての報酬(源泉徴収なし)、(10)材料費等を負担し、経理・経費上の独立性等を有していることが挙げられます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年1月23日 月曜日
平成23年12月23日第304号
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年(改正前は1年)に延長されました。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。
更正の請求の範囲の拡大
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。
※当初申告要件が廃止された措置(主なもの)
所得税関係
純損失の繰越控除(所得税法70)
雑損失の繰越控除(所得税法71)
外国税額控除 (所得税法95)
法人税関係
受取配当等の益金不算入 (法人税法23、81の 4)
外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法人税法23の2)
所得税額控除 (法人税法68、81の14)
外国税額控除 (法人税法69、81の15)
また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。
この措置の適用は次のとおりとなっております。
(所得税関係)平成23年12月2日の属する年分以後の所得税
(法人税関係)平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年1月23日 月曜日
平成23年12月8日第303号
会社の経営難等により行なう「雇用調整」の一手段として、「解雇」以外に希望退職や退職勧奨などの人員削減施策があります。人員削減を目標とする「整理解雇」を含む「解雇」には、経営者が一方的に雇用契約を解除できてしまうため、労働契約法は使用者の解雇を制限しています。退職勧奨は業績不振の社員や、勤務態度が著しく悪い社員などを対象とする場合もあります。
メリット・デメリット
退職勧奨は経営者が一方的に行なうものではなく、社員に辞めてもらうよう依頼するものです。社員が辞めたくないと思えば、退職する必要はありません。また、退職勧奨に関する規定が就業規則や雇用契約書にない場合でも、経営者は自由に退職勧奨を行なうことができます。
一般的に従業員には、退職金の上積みの提示、有給休暇の消化、退職後の社会保険、年金、税金、失業給付については退職理由が「会社都合」として扱われるため、特定受給資格者に該当し、7日間の待機後すぐに失業給付を受けることができる等の説明をします。
また、経営者は解雇予告が不要になる半面、失業給付については「会社都合」による解雇のため助成金を一定期間受け取れなくなる場合があります。
退職勧奨と不法行為
退職勧奨が執拗で、不当に強要である場合、不法行為と評価されうるというリスクがあります。(下関商業高校事件 最高裁昭和55年7月10日第一小法廷判決)
(1)「被勧奨者の意思が確定しているにもかかわらず、さらに勧奨を継続することは、不当に被勧奨者の決意の変更を強要するおそれがあり、・・・・・一旦勧奨を中断して時期をあらためるべき」こと
(2)「勧奨の回数及び期間についての限界は、千差万別であり・・・ことさらに多数回あるいは長期に勧奨が行なわれていることは、・・・不当に退職を強要する結果となる可能性が強く違法性の判断の重要な要素」であること
(3)「被勧奨者の名誉感情を害することのないよう十分な配慮がなされるべき」こと
以上のことを総合的に勘案して、被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であったか否かを勧奨行為の適法性の判断基準として、損害賠償請求が認められています。
行き過ぎた勧奨が行なわれると退職強要となり、トラブルになれば他の従業員のモチベーションも下がります。リスクを考え、早い段階で退職に関する合意書を交わすことも大切です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年12月 4日 日曜日
平成23年11月23日(第302号)
年金や消費税の改革が話題に上がっています。外国ではどうなっているのでしょうか。わが国では「国民皆健康保険・国民皆年金」が強調されています。一方、アメリカでは健康保険に入れず、医療の恩恵に浴せない人が多いと言われてきました。従って、年金も我が国の方が、高水準の年金を受け取っていると思っている人が多いと思います。しかし、本当にそうでしょうか。
1)アメリカの老齢・遺族・障害年金保険制度は、被用者や自営業者の大部分が加入する中心的な公的年金制度です。2009年において、約1億5,900万人が加入し、老齢年金の平均受給額は、月額1,159ドル、夫婦世帯で1,884ドルでした。
2)年金保険料は社会保障税として、給与から天引きが普通です。納付実績が延べ10年間に達すると受給資格を得ます。老齢年金の受給額は所得水準によって変わりますが、所得再分配機能が働くように設計されているため、低所得者に有利になっています。支給開始年齢は65歳でしたが、現在は67歳へ引き上げ途中です。
3)老齢年金受給者の平均的な給付水準は、加入期間中の平均所得の約40%です。給付水準はそれほど高くありませんが、65歳以上の世帯の89%が受給し、アメリカの高齢者の生活を支える重要な制度となっています。
4)財源の大半は、我が国の社会保険料に当たる社会保障税で賄われ、その税率は12.4%(被用者は6.2%)です。現役世代の社会保障税は退職世代の給付に充てられます。給付を上回る分は、高齢化による将来の支出増加に備えるため、社会保障信託基金に積み立てられています。しかし、現行制度では、この基金はあと25年で底をつくため、改善策が検討されています。
各国の年金制度を比較、評価したレポート(Melbourne Mercer Global Pension Index)によると、日本の年金システムはその制度を維持していくうえで心配があること、受給額の不足(国民年金についての評価と思われます)を指摘されており、総合評価は16ヵ国中13位、米国は10位でした。
一方、消費税の増税が討議されています。現在の5%という税率は諸外国と比べて、高い方ではありません。10%に上げてもまだ低い方です。しかし、先進国で生鮮食料品に10%の消費税を掛けている国はありません。ほとんどが0%です。消費税だけではなく、年金、生活保護を含めた総合国民福祉政策の確立と超党派の国民的審議が求められます。そして、国民も相応の負担を受け入れる覚悟が必要です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年12月 4日 日曜日
平成23年11月8日(第301号)
『不動産の価格』というものは、一物四価とも一物五価とも言われていて色々なものがあります。今回は代表的なものと、その調べ方についてまとめてみたいと思います。
1.実勢価格(時価)
(1)実際に不動産売買の契約が成立する時の価格で、時価又は取引価格ともいいます。
(2)国土交通省の『土地総合情報システム』(http://www.land.mlit.go.jp/webland/)で平成17年度後半からの実際の取引情報が検索することができます。
2.公示価格
(1)国土交通省の土地鑑定委員会が地域の標準的な地点を選定し、毎年1月1日時点の正常な価格を公表するもので、毎年3月下旬に公表されています。
(2)国土交通省の『土地総合情報システム』(上記参照)で昭和45年以降の検索が可能となっています。
3.基準地価
(1)都道府県知事が毎年7月1日時点の基準地の標準価格を判定するものをいいます。
(2)9月下旬に公表され、市役所等で閲覧可能ですが、国土交通省の『土地総合情報システム』(上記参照)でも検索可能です。
4.路線価
(1)国税庁が、市街地において主要道路に面した1㎡当たりの土地の評価額について、毎年1月1日現在を価格時点とし、毎年7月に公表されています。公示価格ベースの8割が目安です。
(2)国税庁では路線価図の冊子版は作成されなくなりましたが、
国税庁のHP(http://www.rosenka.nta.go.jp/)で検索可能です。
5.固定資産税路線価
(1)市区町村が、土地・建物にかかる税金(固定資産税・都市計画税)の課税のために算定するもので、土地の評価額は公示価格ベースの7割程度が目安とされ、原則3年に1度の評価替えをします。
(2)財団法人資産価値評価システム研究センターの「全国地価マップ」
(http://www.chikam.jp/)で固定資産税路線価・相続税路線価・公示価格・基準地価を検索することができます。
(3)証明書の種類としては、ア.評価証明書 イ.公課証明書 ウ.住宅用家屋証明書
エ.固定資産課税台帳(名寄帳)などがあります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年10月31日 月曜日
平成23年10月23日(第300号)...経営労務監査
経営労務監査は、(1)労務コンプライアンスのチェック(2)部門制の役割、配置等に関する人材ポートフォリオ(3)従業員一人ひとりの満足度等を表す意識調査等の監査を三本柱にして構成されています。
2.目的
企業活動を「資本」と「労働」の二要素に分解した場合、「会計検査」が経営を資本運動のマネジメントとして貨幣価値で量的に把握し監査する手法であれば「労務監査」は経営を組織労働のマネジメントとして質的に把握し監査する手法といえます。
経営労務監査は、企業目標の達成に向けた経営戦略と人材マネジメントとが効果的にリンクして適法、適切に運営されたか否かをチェックし、それに基づいた是正制限や改善提言を行ない、円滑な経営活動をサポートすることを目的としています。
3.労務コンプライアンス監査
「労務コンプライアンス監査」を行なうメリットは、人事労務書類や職場をとりまく労働法令を整備することで労使間トラブルを未に防止することにあります。
労働基準監督署の行政指導も強化され、
・経営権の行使による組織的残業払いの未払い、調査
・長時間労働・労務管理状況の監査・指導
・残業計算、残業許可、労働時間管理の実態調査等が行なわれています。
労働総合案内コーナーへの平成22年の相談件数は113万件を超えています!
4.労務に関する環境を整備する
中小企業の経営者においては、労働条件を取り巻く最新の環境の変化を「知らないまま放置してきた」として、結果的に「違法状態に陥ってしまった」という状況を生んでいるケースが多いことは否定できません。そういった最悪のパターンを回避するためにも人事労務書類や職場をとりまく労働法令を整備していきましょう。
自治体では、業務委託等で企業の社会的責任(CSR)について責任が問われるようになったことからも労働条件審査(労務コンプライアンス監査)は、重要視しています。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2011年10月31日 月曜日
平成23年10月8日(第299号)...選択と集中
ポートフォリオとは元々、資産をいくつかの金融商品に分散投資することを意味します。事業・製品ポートフォリオは同じように、どのような事業分野・どのような製品に、限られた経営資源を投資するかという意味です。
縦軸の成長性のかわりに「マーケットシェア」を取ることが多いのですが、ここでは成長性を取り上げています。
「花形商品」は利益率も、成長性も高い事業・製品です。いわば現在の主役です。「ドル箱商品」はすでに最盛期を過ぎた事業・製品ですが、利益率は高く、利益に貢献していて、まだ選択され、残される分野です。「負け犬商品」は衰退期に入った分野、又は成長することなくそのまま低迷してしまった分野です。この分野がまず選択の対象になり、切り捨てられます。「問題児商品」は成長の可能性を持った分野で、今後の展開で花形商品にも、負け犬商品にもなる可能性があります。この分野は将来に関する十分な分析と対策が必要です。分析結果次第では切り捨てられるか、より大きなマーケティングコストをかけて花形分野に育てていくかの分岐点にある分野です。
さて、あなたの会社では、花形商品がどのくらいの割合を占めますか。そして、会社を維持し、成長させていくための今後の対策は十分ですか。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2011年10月31日 月曜日
平成23年9月23日(第298号)...知的障害と発達障害の障害年金について
この9月から障害年金の精神障害について基準が改正されました。その中で、同じような障害である知的障害と発達障害の初診日について、取扱いの基準が示されました。
知的障害も発達障害も、共に先天的要因による障害※です。これらの初診日の取り扱いについて、昭和43年2月23日付けの通達において、「知的障害(精神遅滞)者は、医学的には先天性のものとされているので、初診日の如何を問わず20歳前の障害基礎年金として取扱うもの。」と示されていました。
しかし、発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害等)については、IQも高く、大学を卒業していているケースもあり、就職後の人間関係で症状が悪化して、初めて発達障害と判明する方もいます。このようなケースの場合、一見就職後に発病したかのように考えられます。このため、初診日の取扱いが担当者によって分かれていました。
もし、就職してからの初診日となると、障害厚生年金と障害基礎年金の両方が受給できる可能性もありますし、所得制限もなくなります。(20歳前の初診日となると、障害基礎年金しか受給できず、しかも所得制限があります。)しかし、先の通達により、窓口の担当者は知的障害も発達障害も同じと捉え、20歳前の障害としてしか受け付けない方も多くありました。ところが、厚生省の年金担当者は、先天的な要因があったとしても、その症状が陰性であり、就職後に悪化して初めて受診したのであれば、そこを初診として取扱ってよいケースと説明をしていました。
私が扱った例でも、初診日が20歳以降にあっても、保険料納付要件が満たない方は、20歳前と認定されるように書類を整えて、障害基礎年金を請求して受給できるように申請したり、厚生年金加入期間中(就職後)に初めて異常を感じて受診しているのなら、有利な障害厚生年金を請求して受給できるように申請をしておりました。(20歳前の初診日の場合は、保険料を支払う義務がなく、国民年金の保険料を納めていたかといった事が問われません。)しかし、初診日が20歳以降の厚生年金加入期間中にあっても、役所の窓口で20歳前障害として申請するように指導されていた為に、障害基礎年金しか受給できていない方がかなりいらっしゃいます。
今回の基準改訂により、知的障害は20歳前を初診日とし、発達障害は実際に初めて医師の診察を受けた日を初診日とするとなりましたので、今後このような不利益を被る人は少なくなるでしょう。
もし、周りの方やご家族の方で、発達障害と診断されている人がおられましたら、一度年金事務所等で障害年金の相談をしてみてください。
※:一部例外はあります。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2011年9月12日 月曜日
平成23年9月8日(第297号)...パートタイマーの兼業
本来、法律で兼業が禁止されているのは公務員であり、私企業の労働者は法律による兼業が禁止されていません。その兼業を禁止するには、就業規則などの具体的定めによることとなります。
まず一般的に労働者に対し兼業を禁止できるかどうかが問題となります。今日、多くの企業は、就業規則などで兼業を禁止し、その違反を懲戒事由として定めています。しかしながら、本来、労働者は「労働契約により勤務時間中のみ労務に服することを原則とし、勤務時間外は使用者の支配下を離れ、自由であるはず」として、兼業について争われることがあります。
裁判例では、兼業禁止について無制限に認めてはいません。就業規則で兼業を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、合理性に欠くとされています。しかしながら、「労働者が労働時間外に適度な休憩を取ることは、誠実な労務提供の為の基礎的条件であり、また、兼業の内容によっては、会社の経営秩序を害することもあり得るから、兼業禁止規定には合理性がある」(小川建設事件、東京地裁昭57.11.19)として一応合理性が認められています。
兼業禁止の就業規則が認められる合理性要件として
(1)その兼業職業が会社の職場秩序を妨害し、もしくは労務の提供に特別な支障を来
たすたぐいの兼業である場合
(2)会社の業務内容によっては、労働者の兼業により会社の対外的信用が傷つけられ
る場合
などが挙げられます。
例えば(1)について、労務提供になんら影響のない場合まで、兼業禁止違反を問うことは無理があることもあります。
勤務日数や勤務時間が少ないパートタイマーについて、一律に兼業を禁止する規定を適用することに合理的理由を求めることは、困難な場合が多いと思われます。
パートタイマーの兼業についても、兼業が、不正な競業に当たる、営業秘密の不正な使用・開示を伴う、労働者の働き過ぎにより生命・健康を害するおそれがある、その態様により使用者の社会的信用を傷つける、などの特別な事情がある場合を除き兼業禁止を命じることは困難となります。言い換えれば、前述に該当した場合、パートタイマーにも兼業を禁止することも可能です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2011年9月12日 月曜日
平成23年8月23日(第296号)...平成23年税制改革(消費税関係)
1.事業者免税点制度について(この改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用します。)
この規定は、個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間(個人事業者の場合は、2年前。法人の場合は原則として前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下である場合について、従来は、自ら課税事業者を選択していなければ、免税事業者となっていました。
しかしこの規定では、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、その後の課税売上高の推移に関わらず、その年又はその事業年度が免税事業者になってしまいます。
これは、その年の前年又は前事業年度の原則として初めの6ヵ月(特定期間と言います。)の課税売上高又はその6ヵ月間に支払った給与等の金額の総額が1,000万円を超えていれば、免税事業者に該当せず、課税事業者として扱うというものです。
例 「個人事業者が、平成25年分の消費税の課税事業者になるかどうかの判定」
前提 ・平成23年(基準期間:2年前)の課税売上高 ・・・・・800万円
・特定期間(前年の上半期)の課税売上高 ・・・・・・1,500万円
・特定期間(前年の上半期)の給与等の金額 ・・・・・1,100万円
(1)改正前と同じようにまず、平成23年(基準期間)の課税売上高で判断します。
800万円≦1,000万円
(2)特定期間の課税売上高又は特定期間の給与等の金額が1,000万円を超えているかどうかの判定を行います。
特定期間の課税売上高を用いて、 1,500万円>1,000万円
特定期間の給与等の金額を用いて、 1,100万円>1,000万円
どちらを選んでも1,000万円を超えているので、平成25年は課税事業者となります。
2.課税売上割合が95%以上場合における仕入税額控除について
(この規定は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用します。)
これは、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者には、課税売上割合が95%以上の場合でも課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除ことができなくなりました。
よって、課税売上割合が95%未満の場合と同じ方法での消費税の計算をすることになって、納税額が増えることになります。また、会計ソフト等への入力の仕方が変わることもありますので、該当しそうな法人は、その事業年度の開始前にあらかじめ対応を検討して、その事業年度の記帳をスタートされる必要があります。
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2011年7月 8日 金曜日
平成23年7月8日(第293号)...災害に強い土地についてのポイント
に強い土地 (地盤のよい土地)について再確認してみましょう。
軟弱地盤に注意
地盤の強弱については、大きく分けると、丘陵地(洪積層)、台地(洪積層上のローム層)、低地(沖積層)の3つに分けられます。このうち、低地の沖積層に比較的軟弱地盤が多いと言われています。その中でも最も軟弱な地盤である可能性があるのは、湾岸部の埋め立て地です。液状化や不同沈下が起こる可能性が高く、地震の揺れが伝わりやすいエリアです。
ただ、比較的地盤が強いといわれる台地や丘陵地であっても、例えば、斜面の場合、過去に人工的な地盤の変更が行われたケースもあり、その変更の仕方の質が問題となります。一般に切り土よりも盛り土の方がやや地盤が軟弱である可能性が高いです。さらに河川や沼、湖など砂や泥が堆積しやすい場所も、地盤が軟弱である可能性があります。
地名は土地の履歴書
科学的な手段に頼れない時代には、その土地の状況を考えて地名を付けたと言われています。つまり、地名はその土地の履歴を凝縮した標語のようなものなのです。
(1)水域にちなんだ地名:軟弱地盤の可能性が高い
水戸・清水・川口・川内・寝屋川・白河・河内・綾瀬・池袋・沼津・泉大津・湖西・海南・近江・浪速 → 水戸は水門、近江は大きな海の意味です。
(2)水辺にちなんだ地名:水域に隣接する海岸、河岸、半島や島を表す地名。
横浜・浜松・灘・磯子・高砂・横須賀・新潟・江戸・松江・住之江・浦和・浦安・三浦・川崎・茅ヶ崎・尼崎・長崎・岸和田 → 江は入り江、浦は比較的小さな湾のことです。ちなみに当社の事務所が所在している地名は「墨江」少し北側の地名は「粉浜」といい、昔はこのあたりまで海岸があったそうです。
(3)さんずい・谷・沢・田のつく地名
河・池・沼・海・沖・潮・汐・洗・浮・渋・清・渡・滝・湘南・流山・越谷・渋谷・刈谷・藤沢・米沢・金沢・荻窪・溝口・深谷・浅草・秋田・成田・野田・町田・下田・磐田・田辺・梅田
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年6月23日 木曜日
平成23年6月23日(第292号)...年金受給額ネットで試算
千葉県在住の主婦(44)は、ねんきんネットで、会社員時代や、専業主婦となってからの記録を全て確認した。「記録漏れ等がないと改めて確認でき安心した」と話す。
主婦がねんきんネットに接続する際に利用したのは、4月に届いたねんきん定期便だ。今年4月以降の定期便には、「アクセスキー」と呼ばれる17けたの数字が記載されている。ホームページ上でこの番号と基礎年金番号、メールアドレス等を入力すると、即座に IDが発行され、パスワードを設定すれば、年金記録が閲覧できる。ただし、このアクセスキーは到着後3ヶ月程度で使用できなくなる。定期便が届くまで待てない場合、ホームページ上で登録手続をすることで、5日ほどで、IDとパスワードが取得できる。アクセスキーが期限切れになった人も、同様の手続で利用できるようになる。
同機構は、年金をいくらもらえるかという見込み額の試算ができる機能をを、今秋をめどに追加する予定。また、60歳以降に働きながら年金を受け取る「在宅老齢年金」」の金額や、年金を早めに受け取る「繰上げ受給」の額等も試算可能にするという。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年6月 8日 水曜日
平成23年6月8日(第291号)...プロジェクトマネジメント
顧問先も含め、ベンチャー企業等たくさんの会社の支援をしていますが、儲かっていない会社が多いです。それは、何故でしょうか?
もの造りをしている企業やソフトウェアなどをつくっているほとんどの中小企業は個別の製品の原価を把握していないのが現状です。儲かった会社も、儲からなかった会社も勘ピューターでおよその感じだけで推定していることがほとんどです。製造原価と営業費用も区分されていないところが多いのです。「計算の仕方が分からない」「面倒臭い」というのがその理由です。
見積もり段階では儲かるつもりで受注します。しかし、結果を計算してみると大幅な赤字受注になっている、なんていうことがしばしば起こっていませんか。そんな企業は特に取り組んでいただきたい管理方法です。
2.プロジェクトマネジメントって何?
何やら難しそうに聞こえますが、簡単にいうと受注案件ごとに担当者を決め、納期に間に合うように工程を管理して、さらに案件ごとに儲かっているのか、損しているのかを分かるようにすることです。そうすることによって、今後の価格交渉やコストダウンに役立ち、「筋肉質」の強い企業になってきます。
3.中小企業でもできる、プロジェクトマネジメント
その気になりさえすれば中小企業でもプロジェクトマネジメントすることは可能です。まず、経営者ご自身が、従業員にそれぞれに案件ごとの担当者になってもらって、その案件が儲かっているか、損しているのかをつかむ意識を持たせるところからスタートします。簡単なエクセルシート1枚(プロジェクト管理様式)でスタートできます。
企業にとって、「利益と資金は車の両輪」です。儲からない企業はやがて資金にも不足し、経営が行き詰まってしまいます。転ばぬ先の杖、今からでも遅くありません。
利益の出ていない企業はもちろん、利益が出ている企業はさらに筋肉質の体質の会社にしてみませんか!
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年5月23日 月曜日
平成23年5月23日(第290号)...医療費の限度額適用認定書を利用しましょう
近年の医学の発展により、高度な手術や新薬が開発され、様々な医療行為が受けられるようになりました。しかし、医療費が高額になる傾向があり、心臓バイパス手術では、3割分の自己負担金が約160万円になります。また、新薬の関係でいうと、1年前に発売された血液難病の新薬は、毎月の注射代が3割負担でも約120万円になります。他にも処方される薬代が毎月数万円という薬も多くなってきております。
これら高額な医療費に関しましては、健康保険に高額療養費制度というものがあります。これは高額な医療費に月ごとの上限を設け、費用が問題で治療が受けられないという方を少なくするのが目的です。その上限額は次のように定められています。
(70歳未満の場合:1ヵ月の医療費の上限額)
・一般被保険者(標準報酬月額53万円未満)
→(医療費の総額-267,000円)×1%+80,100円=83,400円
(多数該当)
(この他に、上位所得者や低所得者の区分もあります。)
ここで言う多数該当とは直近の1年間に高額療養に該当した月が3ヵ月以上ある場合に適用されます。一般被保険者の方で心臓バイパス手術により1ヵ月入院したと仮定しますと、医療費の総額が約530万円になりますので、高額療養費は大体13万円程となります。
この高額療養費制度は、原則は医療費の3割を病院に支払って、その後、健康保険に差額返還の手続きをする流れとなります。ただ、一括で160万円も支払えないという方も多く、その場合は、「限度額適用認定書」を保険者からもらっておきますと、病院の支払いが高額療養費で計算された約13万円ですみます。大きな手術の予定が入っている方は、事前に「限度額適用認定書」を取得される事をお勧めします。
ただし、この「限度額適用認定書」は、現在は入院にしか使用できません。外来で高額な治療を受けている方は対象となっていませんので、高価な注射薬を使用されておられるのであれば、病院にお願いして、一泊入院で治療を受けてください。そうしますと、限度額認定され、月々用意する医療費の負担が少なくてすみます。
外来についても、来年の4月から「限度額適用認定書」が適用される通知が厚生労働大臣からありましたので、来年度からは外来でも利用できるようになります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年5月 8日 日曜日
平成23年5月8日(第289号)...介護休業の回数日数及び日数
「通算して93日」の日数の根拠は、従前の制度にあった「3ヵ月」の最低基準を最長の介護休業期間(介護休業開始日とされた日の翌日から起算して3ヵ月を経過する日まで)を日数換算すると、初日+31日×2+30日×1=93日(最大)となります。
育児休業期間は、子が1歳に達するまで(例外として、パパママ育休の1歳2ヵ月の間の1年、保育所に入所できない場合等1歳6ヵ月まで)と長期休業期間の取得が可能である一方、何故、介護休業期間は当初3ヵ月となったのでしょうか。
「3ヵ月」に定まった理由としては、次の4点があり、主たる要因は(1)(2)です。
(1)家族による介護がやむを得ない場合の緊急的な対応。
(2)家族が介護に際し、施設に入れるかどうかという長期的な方針を決める判断期間。その期間が通常3ヵ月程度必要。
(3)家族の介護をする労働者の雇用継続の必要性と、企業の労務管理負担とのバランスの考慮。
(4)当時の調査として、介護休業制度を導入している企業では、3ヵ月以内の設定が大方を占めていた。
回数は、従前については「同一の対象家族について1回」でしたが、現在では「一の要介護状態ごとに1回」と複数回取得可能となっています(日数は通算して93日間)。ただし、一の要介護状態に1回となっているため、同一の要介護状態が継続しているときなどは途中で中断した場合、再度の取得ができなくなります(一旦病状が回復し、異なる要介護状態となれば複数回93日の範囲で取得可能)。例えば、老親の介護のため、長期に亘り毎週1日若しくは2日の介護休業を取得し続けることは無理があります。昨年改正された介護休暇(1人の場合5日、2人以上の場合10日/年)は取得できますが、日数に制限があります。
今後の社会を考えると、介護における取得回数等について更なる改正が必要と考えられます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年4月23日 土曜日
平成23年4月23日(第288号)...消費税の非課税取引
消費税の非課税となる取引について説明いたします。
消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
具体的には以下のようなものが、非課税取引になります。
(1)土地(借地権などの土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け
ただし、1ヵ月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。
(2)有価証券等の譲渡
(3)支払手段の譲渡
(4)預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
(5)郵便事業株式会社、郵便局株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(6)商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7)国等が行う一定の事務に係る役務の提供
(8)外国為替業務に係る役務の提供
(9)社会保険医療の給付等
(10)介護保険サービスの提供
(11)社会福祉事業等によるサービスの提供
(12)助産
(13)火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14)一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
(15)学校教育
学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など
(16)教科用図書の譲渡
(17)住宅の貸付け
ただし、1ヵ月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年4月 8日 金曜日
平成23年4月8日(第287号)...東日本大震災関連情報
今回の大地震におきまして、多くの方が亡くなられたことに対しお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。
震災に加え福島第一原発事故で、資材調達のめどが立たず受注を見合わせたり、売り上げが落ち込む企業、一方で被災地での需要急増や、被災による操業停止、計画停電で東日本の工場の代替を担い、フル操業する工場など経済もまた混乱しています。
京都労働局は被災者や被災企業を対象に仕事を紹介したり、雇用保険や雇用調整助成金に関する相談窓口を府内のハローワークに設置、休業や未払い賃金の立て替え払いなど労働条件に関する相談窓口を同局監督課に設けています。(4月5日京都新聞朝刊)
以下、厚生労働省からの東日本大震災関連情報において「雇用・労働関係」について震災後公表されている対応について一部を掲載させて頂きます。
こまめに情報を集め、粘り強く明日を信じて、この有の震災を乗り越えましょう。
◆派遣労働者への配慮について要請しました(3月28日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016av1.html
◆雇用・労働関係の特例措置をまとめたリーフレット(3月29日)
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=162283
◆労働基準法等に関するQ&A(第2版)(3月31日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f2k.html
震災の影響を受けての対応について(若年者雇用対策)
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=162199
◆雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金リーフレット
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=162405
◆東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vy1.html
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年3月23日 水曜日
平成22年3月23日(第262号)...新年度からの労働法改正
また、労働基準法以外にも4月1日から改定施行される法律や通達があります。
労災法関係では、労働者死傷病報告の様式が変更
事故が3月31日以前であっても、届出が4月1日以降になるときは新しい様式で届けます。派遣労働者が労働災害によって死亡し、又は休業した場合には派遣元及び派遣先の事業所がそれぞれの所轄労働基準監督署に報告を提出しなければならないのは従来と変わりませんが、派遣先の事業所の郵便番号を記入する欄ができました。これは、派遣先会社の事業所が複数ある場合に、どの事業所で仕事に従事していたかが判るようにする為です。
安全衛生法関係では、定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直し
従来、胸部エックス線検査の対象者は、40歳以上は従来どおり全員に実施、40歳未満の従業員は、下記1)、2)、3)以外の方については医師が必要でないと認めた時は省略することができる、と変わりました。つまりは医師が必要でないと認めていなければ検査を受けなければなりません。検査漏れを防ぐ為に、下記1)、2)、3)に該当しない従業員(主として節目年齢以外の従業員)のリストを作って医師の認印をもらっておくのが良いでしょう。
1)5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の従業員
2)感染症法で結核に係る健康診断の対象とされている施設で働いている従業員
3)じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている従業員
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年3月23日 水曜日
平成23年3月23日(第286号)...再び第3号問題
平成22年12月15日に厚生労働省の課長通達で「運用3号」という取り扱いが公表され、平成23年1月1日から実施されました。これを下図に示します。
夫 第2号被保険者(厚生・共済) 第1号被保険者期間
退職
妻 第3号被保険者 届け忘れのため第3号登録されていた期間
変更届を出すべき時点
必要な変更の届出が行われなかったことが判明した期間
上のようになっていた妻は次のようになります。 2年
妻 第3号被保険者期間 「運用3号」期間 第1号被保険者期間
正しくは、第1号被保険者の届出をし、年
金受給の期間が不足しているなら、保険料
を追納し、まだ不足なら任意加入するべき
で、そのようにしている人もいる。
昭和61年4月に国民年金第3号被保険者制度ができました。上の図によると、厚生年金の被保険者の配偶者が第3号被保険者として登録された数ヵ月に、夫が退職すると厚生年金の被保険者でなくなります。妻も第3号被保険者ではなくなりますが、そのままに放置しておくと、その後20年以上も第3号被保険者で居続け、最後の2年間だけ保険料を支払えば、残りの期間は第3号被保険者として扱われ、年金はその期間に応じて払われる、ということがあり得るわけです。おかしいですね。
この「運用3号」についてはいろいろの批判があり、この取り扱いは23年1月末で保留になりましたが、この間に2,300人余りの人がこの手続きの申請をしたとされています。現在、「運用3号」に関わる資格の変更や年金裁定は保留されています。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年3月 8日 火曜日
平成23年3月8日(第285号)...固定資産税の縦覧・閲覧・審査について
例年4月1日から固定資産税の縦覧が始まりますが、固定資産税は市町村が価格を決定して課税を行う賦課課税方式を採用しているため、納税者のほとんどはその計算根拠を十分に確認することなく、課された税額をそのまま納付しているのではないでしょうか。
近年あらゆるところで情報開示が進んでいますが、この機会に適正な固定資産税の課税が行われているか、しっかり確認することが必要です。(都市計画税も含みます)
土地及び家屋の評価替え年度
土地及び家屋の固定資産税の価格は、3年に1度の基準年度において評価替えが行われ、原則としてその後2年間は価格が据え置かれることとなっています。土地の評価は我々不動産鑑定士の仕事であり、現在平成24年度の評価替えの作業をしているところです。
縦覧制度
市町村長は、毎年4月1日から、4月20日又は納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、固定資産課税台帳を縦覧に供します。
閲覧制度
市町村長は、納税義務者その他の者の求めに応じて、固定資産課税台帳のうち、その者に係る固定資産に関する部分等を閲覧に供します。これにより、納税義務者以外でも、借地人・借家人等が、借地・借家対象資産の固定資産税額を閲覧できるため、固定資産税等の下落を材料に賃料引下げ交渉に発展することが予想されます。
審査の申出制度
納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録した旨を市町村長が公示した日から、納税通知書受付後60日までの間に、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができることとされています。なお、審査の申出は、原則として評価替えの年でなければ申出ることができません。
不服申立て制度
納税者は、固定資産税の価格以外に関する事項について、不服がある場合については、市町村長に対し納税通知書の交付を受けた日後60日の間に不服申立てをすることができます。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年2月23日 水曜日
平成23年2月23日(第284号)...100年企業に学ぼう!
100年以上の歴史を持つ企業は、韓国には5社しかありません。5,000年の歴史を持つ中国においても1,000社しかありません。
確認できた我が国で最も古い企業は、大阪の寺社仏閣建築の会社で創業が西暦578年とされています。聖徳太子が四天王寺を建立するために百済(くだら)から招いた工匠が始祖とされ、業歴は1,400年を超えています。
2位は京都の生け花の振興・教授の会、3位は山梨の老舗旅館と続き、上位7位までが業歴1,000年を超えています。
100年企業の社風をまとめると、「おっとりしている」、「ロングレンジでものを考える」、「原点に回帰しながらも常に革新を継続する」、「とにかく人を大事にする」といったものが目立ちます。
都道府県別に見ると、東京都が 2,058社(9.3%)で最多。愛知県1,211社(5.5%)、大阪府1,080社(4.9%)と続きます。
業種別では、小売業が6,279社(28.3%)でトップ。次いで製造業の5,447社(24.5%)。卸売業の5,216社(4.9%)の順になっています。
このデータでは、東京都で小売業(できれば酒小売、呉服・服地小売などの伝統的な商売)を創業するのが、長寿企業になる近道と推測できます。現在の経済状況では、必ずしも現実的とはいえませんが、意外なヒントが隠されているかもしれません。
100年を超える企業は大手企業ばかりではありません。中小企業においても伝統的な技を活かしつつ、先端ハイテクを追求する優秀なカンパニーは、この日本には数多くあります。
古くて新しい町「京都」も100年企業の宝庫です。景気の先行きが不透明な今日、「100年企業」にヒントを学んでみてはいかがでしょうか。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年2月 8日 火曜日
平成23年2月8日(第283号)...やさしい損益分岐点(儲かっていないと感じる会社編)
みなさんは、損益分岐点という言葉を聞いたことがあると思います。そして、何となくその意味も分かっていると思っているのではないでしょうか?
では、自社の損益分岐点売上を計算してみたことはありますか?ここで、簡単な損益分岐点の説明をしてみましょう。
あなたは、晴れて大阪梅田のホワイティに5坪の電子辞書を販売するお店を開くことができました。家賃は、月20万円です。いろいろな電子辞書を販売していますが、どれも売値は5万円、仕入価格は3万円とします。さて、この電子辞書を何台売れば家賃を払うことができるのでしょうか?「そんなの簡単!10台だよ。」って答えが返ってきました。そう、それで正解です。
どうやって計算しましたか?「1台売ると2万円の儲けだろ、10台売れば20万円の儲けだからそれで家賃が払えるよ。」そうです!10台売って50万円の売上、これが損益分岐点売上です。
もう少し、分析してみましょう。1台の売上高5万円から仕入価格の3万円(変動費)を引いた2万円の利益をちょっと難しいですが、「限界利益」と呼びます。1台売ると2万円の限界利益があり、家賃20万円(固定費)のうち2万円が回収できました。順番に限界利益で家賃という固定費を回収していって、10台ですべての固定費が回収され、損益はとんとんになります。これが損益分岐点の基礎です。"固定費を限界利益で回収すると損益分岐点になる"。
また、限界利益を売上高で割ったもの、これを「限界利益率」と呼んでいます。
上で示した、損益分岐点の基礎から 固定費÷限界利益率=損益分岐点売上という算式ができます。上記の事例でみてみましょう。
限界利益率は、2万円÷5万円=40%
20万円(固定費)÷40%(限界利益率)=50万円 これが損益分岐点の正体です。
売上高と費用を変動費と固定費に分けることができればあなたの会社でも簡単に損益分岐点売上が計算できます。変動費は、商品を仕入れて売るのであれば仕入価格、メーカーであれば概ね材料費が該当し、固定費は人件費や販売するための広告宣伝費等の経費、管理費用など売上によって変動しない費用が該当します。
さぁ、あなたの会社、一度損益分岐点を計算してみませんか?いくら売れば損益分岐点を超えるか、それがあなたの会社のまず目標とする売上高です!
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年1月23日 日曜日
平成23年1月23日(第282号)...社員教育で普通救命講習を受けましょう
消防署等で行われている、「普通救命講習」をご存知でしょうか?心肺蘇生を中心とした応急手当を学ぶ講習で、火傷や怪我の簡単な手当ても学ぶことができ、上級編では怪我の手当ての他に、搬送方法等も学ぶことができます。
これを是非社員教育の一環として採用してください。会社で従業員等が倒れたときに、救急車を呼んでも到着までに10分前後のとき間がかかります。この間に応急手当をしているか、していないかで救命率が大きく変わります。心肺停止ですと、3分間放置するだけで死亡率が50%を超えてしまいます。救急車到着までの間に心臓マッサージをしているだけで、その人が助かる確率が大きくなります。
職場でそのようなことは起こらないだろうと考えておられる方も多いでしょうが、私の関与していたある会社では、1日に救急車を2回呼ぶことになったケースがございます。幸い命に関わることもなく、労災を疑われる病気でなかったので、問題はなかったのですが、こと業場内で転倒して頭を打った等の場合、確実に労災になり、死亡と救命されたのでは、会社に問われる責任も変わります。また、障害の重さによっても会社が負う責任は変わりますので、応急手当は非常に重要となってきます。労災こと故の場合で、従業員が死亡したか、救命されたのかでは、労働基準監督署からの指導内容や、従業員及びその家族へ対する保障という点で大きく異なってきます。応急手当をしているだけで、救命率も上りますし、後遺症も軽くなりますので、会社のリスクマネジメントとしても最適です。
この普通救命講習は無料で利用でき、しかも一定の人数が集まると出張して行ってくれます。従いまして、会社まで出向いて講習をしてもらえますし、受講終了後は応急処置技能検定講習を受講した証明書を発行してもらえます。これは公的資格の一つとなっております。
私がサラリーマンとき代には研修を担当し、毎年この講習会を開催しておりました。消防署の方とも親しくなれますし、行政受けがよかったことも覚えております。費用の一切かからない講習ですので、是非受講することを検討してみてください。
申し込み先は、最寄りの消防署です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年1月 8日 土曜日
平成23年1月8日(第281号)現代うつ
従来、うつ病になりやすいタイプと言えば、几帳面で真面目、他人に気を遣い相手に合わせようとする物事にこだわる「メランコリー親和型」で40歳代後半から50歳代に多くみられました。このタイプは、休養や薬物療法によりある程度改善していくと言われています。うつ病の症状も変化し、最近ではこのタイプは少数派になりつつあると言われています。
従来型と違い「現代型うつ病」の特徴は、(1)自責感や悲壮感が殆どなく、漫然とした抑うつ気分で倦怠感が目立ち、自己中心的な性格が強く、何かうまく行かないと他人のせいにし(2)自分の都合のよい出来事には気分が良くなり(会社にいるときはうつ症状)、休日やプライベートタイムなどはごく普通に過ごしている(3)人間関係への過敏性などが見られ、気分の浮き沈みが激しい、などがあげられます。
従来型うつと現代型うつでは、全く異なる症状にて同じ様な対応を取ることは難しいとされています。従来型では、真面目で責任感が強い人に症状がでることにより自責感が強いとされているのに対し、現代型では、「上司、同僚が悪い」「会社が悪い」などと考え、休職した場合でも復職への焦りや、仕事に対する切迫感もなく、悪いことばかり目が向く傾向にあります。
現代型では、本人には悪気がなく、また、周囲に迷惑を掛けている意識すらなく、自分自身典型的なうつ病と思い込んでることもあります。一方、落ち込んだり、気分が優れない、眠れないなどの症状も見られます。
対応としては、従来型と同様に、休息と投薬を中心とした治療方法を取り、治癒に要する時間をある程度覚悟ください。本人との話では誠実に傾聴し、同意できないことは無理に受け入れず、職場の基本的なルールを丁寧に説明することも必要です。従来型では「『頑張れ』は禁句」と言われていましたが、通用しないこともあり、庇護的、保護的な環境をつくることばかりが良いとは限らないとも言われています。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年12月23日 木曜日
平成22年12月23日(第280号)...平成23年税制改正大綱
主だったものは、次のとおりです。
1.法人税率
法人税率が、30%から25.5%に引下げられます。
資本金が1億円以下の中小法人の800万円以下の所得に適用される税率は、18%から15%に引き下げられます。(平成23年4月1日開始年度から適用)
2.繰越欠損金の控除年限
法人の欠損金の繰越控除年数が7年から9年になったものの、欠損金と相殺される所得が80%に圧縮されます(中小法人は除く)。
3.相続税
基礎控除額が、現行の5,000万円+法定相続人1人1,000万円から3,000万円+法定相続人1人600万円に減額されます。また、死亡保険金の相続人1人500万円の非課税枠は、被相続人と生計を一にしていた者等に限られます。税率も最高税率が50%から55%にアップします。(平成23年4月1日から適用)
4.給与所得控除
給与所得は給与収入から給与所得控除を引いて計算されます。今までは上限がなかったのですが、給与収入1,500万円を超えると245万円で頭打ちになります。
5.成年扶養控除
合計所得金額が400万円(給与収入568万円)超の所得者は、23歳から69歳までの成年扶養親族を扶養控除の対象とすることができなくなります。ただし、学生や65歳以上70歳未満の者、障害者などの成年扶養親族は除きます。(平成24年から適用)
6.退職所得課税
退職金は、退職金額から勤続年数に応じた退職所得控除を差し引いた額の2分の1が課税の対象になり優遇されています。勤続年数が5年以下の会社役員や議員・公務員に対する退職金については2分の1課税が廃止されます。(平成24年から適用)
※税法が改正されるにあたり、賃金規程上の家族手当や住宅手当等の扶養家族の定義の見直しが必要になるケースが出てきています。平成23年1月1日以降ご注意ください。
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年12月 8日 水曜日
平成22年12月8日(第279号)...高年齢者雇用安定法と「2013年問題」
平成18年の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下、「高齢法」)の改正から4年以上が経過しました。
1.改正高齢法の概要
平成18年の改正高齢法で、企業には65歳までの雇用確保措置が義務づけられ、現在はその途上で、現時点での雇用確保義務年齢は64歳ですが、平成25年度にはその年齢は65歳になります。
ご承知の通り雇用確保義務の内容は(1)定年制の廃止(2)継続雇用制度の導入(3)定年延長のいずれかを講じることにより、雇用を確保しなければならないということなのですが、現在60歳以後の雇用はほとんどの企業が再雇用制度((2)の継続雇用制度の一つで定年退職後再雇用して雇用を継続する制度)により対応し、再雇用後の賃金は「年金」と「高年齢雇用継続給付の受給」を前提として、大きく引き下げられるのが普通です。
背景には60歳前の給与水準を維持できないことと、逆に言えば、60歳からは「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」という2つの公的給付があるという前提で60歳以後の賃金の引き下げが可能になります。
賃金の手取額に両給付の受給額を加えた「総手取額」が、一定の範囲で最大となる賃金の額を「高齢者の最適賃金設計」などという言葉で表現されています。
2.平成25年度(2013年度)以降の影響
しかし、このような継続雇用の在り方は平成25年度以降修正を迫られることになると思われます。
現在60歳になる一般的なサラリーマンは、まだ60歳から「部分年金」と呼ばれる2階建て年金の2階部分だけの年金(「報酬比例部部分」ともいいます)が支給されますが、平成25年度に60歳になる男性(昭和28年4月2日から30年4月1日生:女性は5年遅れ)からは、この部分年金の支給開始年齢が1年ずつ引き上げられます。つまり、60歳から61歳になるまでの1年間は無年金者になるわけで、雇用による収入しかない年が段階的に長くなるわけです。
60歳から年金が支給されない世代が60歳になったらどうなるの?ということが「2013年問題」といわれています。
支給開始年齢の引き上げに合わせて、定年年齢を61歳、62歳と延長し65歳までの残りを再雇用制度でまかなうのか、60歳の再雇用時には軽い引き下げ、年金支給開始年齢時に本格的な賃金引き下げをするのか、年金支給開始年齢に関係なく60歳から大幅な賃下げをするのか、などが考えられますが、いずれにせよ3年後というと遠い話というわけにはいかないようです。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年11月23日 火曜日
平成22年11月23日(第278号)...残業は合法的に処理しましょう
年末が近づいてきました。不況と言っても年末ともなれば仕事量が増えて残業を命ずることが多くなるでしょう。御社では残業は合法的に行われていますか?"名ばかり管理職"を作っていませんか?ご点検をお願いします。
では、合法的であるためのチェックポイントを挙げてみましょう。
1.36協定はちゃんと締結されていますか?
監督署へ協定届だけは提出されていても、協定書の作成等その協定を決めた手続がちゃんと行われていなければなりません。
2.36協定の有効期間はまだ十分残っていますか?
36協定の期間は1年とするのが普通ですが、継ぎ目で空白ができないように注意が必要です。これまで、過去に36協定が有効でなかった時期があった、というだけで労使紛争になった例があります。1日も空白期間ができないように注意してください。
3.従業員代表の選出は適正に行われましたか?
事業主が署名人を指名しており、従業員によって選出されていない、とか、親睦団体の代表者が従業員代表として署名捺印している、などは違法です。
従業員の親睦団体である「○◇社友会」の代表を労働者代表として36協定を締結していたが、この人物は労働組合の代表者でもなく、労働者の過半数を代表する者でもないから、この人物と交わした36協定は無効であり、残業命令も無効であるという判決が出た例もあります。
では、従業員代表はどのように選出すればよいでしょうか。それは「厳格な選挙等を行う必要はない。」とされていますが、次のようなことを確実に実行することが必要です。
(1)朝礼時に挙手で決める。
(2)全社員に従業員代表候補者を周知し異議がある場合は申し出るよう全員に伝える。
(3)書面で個別に同意を取っておく。
これらの経緯を文書に残しておくことが、後のトラブルを防ぐために有効です。
ファーストフード店の店長が、「自分は管理職とされていたが、実は"名ばかり管理職"であるから超過勤務給を支払え。」と会社を訴えたM社の事件は有名になりましたが、類似の事件は後を絶っていないようです。
従業員の管理職への昇進に当たっては、仕事の質、責任と権限に見合う給与・待遇を与えないと"名ばかり管理職"を作ってしまうことになります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年11月 8日 月曜日
平成22年11月8日(第277号)...「めやす賃料」について
「めやす賃料」とは?
賃貸住宅の広告・契約時などにおいて、「実際にいくら支払えばよいのか?」が分かりにくいということがよく問題となっています。地域による慣習、賃貸人の違いなどにより毎月支払う賃料は同じでも実質的に支払う金額に差が出てしまうことが、半ば常識となっていました。これらを一定の基準で整理し、実際に支払う金額がどれだけなのかを分かりやすく表示する仕組みが、「めやす賃料表示」です。我々不動産鑑定士が従来より賃料の鑑定評価をする場合にも、やや中身が異なりますが「支払賃料」「実質賃料」という名称を使用して算定しています。
「めやす賃料表示」のガイドライン
(財)日本住宅管理協会が発表した「めやす賃料表示」のガイドラインは、次のとおりです。
「賃料、共益費・管理費、敷引金、礼金、更新料を含み、賃料等条件の改定が無いものと仮定して、平均的な入居期間とされる4年間賃借した場合(定期借家の場合は、契約期間)の1ヵ月当たりの金額」と定義されています。
つまり、4年間(48ヵ月)居住時の(賃料+共益費・管理費+敷引金+礼金+更新料)÷48ヵ月という事になります。
「めやす賃料」に含まれる項目、含まれない項目
(1)めやす賃料に含まれる項目
・賃料 ・共益費/管理費 ・敷引金(敷金・保証金の償却金) ・礼金 ・更新料
(2)めやす賃料に含まれない項目
・仲介手数料、更新事務手数料 ・町会費 ・鍵交換費用 ・原状回復特約費用
・定額の設備使用料 ・賃貸保証会社への保証委託料 ・家財保険等の保険料 等
これは、物件使用の対価のみを対象とした方が、賃料の比較が容易であるためです。また貸主毎により異なる「特約により発生する費用」は対象外としなければ市場での比較が困難となるからです。「めやす賃料表示」は賃貸住宅のみならず、事務所・店舗等の賃貸借においても考慮されるべきものです。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年10月23日 土曜日
平成21年10月23日(第252号)...リーダーシップが業績を決める
1.人材3分法
人材を分けると次の3つになると言われています。良きリーダーシップをとれるのはもちろん「人財」です。さて、経営者、管理者としてのあなたはどの人材になりますか?
(1)人罪= 努力も頑張りもしない人、昇進しない・できない人、組織の足を引っ張る
人、愚痴をこぼす人
(2)人在¬= 頑張る人、そこそこ昇進する人、指示・命令があれば動く人、指示待ち人
材
(3)人財= 工夫し努力する人、どんどん昇進する人、次の一歩を考えて行動する人
2.嫌われるタイプのリーダーシップ
こんな人は嫌われるタイプのリーダーで、他の社員から尊敬を得られず、仕事の成果も上げられません。
(1)ワンマンで人の話を聞かない、1時間でも2時間でも愚痴や精神論を振りかざし、
部下が発言すると欠点をみつけけなす人
(2)意見をまとめられない、優柔不断、結果責任も取らない人
(3)手柄は自分のもの、失敗は部下に押しつける人
(4)自分の出世だけを考えて、部下の幸せを考えていない人
(5)公正な判断ができない人、好き嫌いで物事を判断する人
(6)人材の育成ができない人
(7)先を読むための情報収集や分析をしない人
など、上げ始めればきりがありません。さて、あなたはどれかに当てはまっていませんか。
3.良きリーダーシップ
2.で上げた項目の反対をすればいいことになりますね。
まず、部下の話をよく聴くことです。現在はバブルのころと違って「売ってこい!」の精神論だけではなかなか売れません。情報を集め、当然部下からの現場の情報は重要な情報源です。分析し、一歩先を読んで対策を取っていく、こんなリーダーになりたいですね。
結果的に部下が仕事をして業績を上げてくれるのですから、部下を育て、仕事を任せ、結果をしっかり評価してやることです。もし、結果が悪くてもそれは自分の育て方が悪いんだと責任をとるくらいの懐の広さが欲しいですね。部下はいつもあなたを見ていますよ!
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年10月23日 土曜日
平成22年10月23日(第276号)...36協定の特別条項に記載する「労使の協議を経て」とは?
36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)に定める時間外労働の上限は、法定の時間外労働の限度基準(1ヵ月45時間・1年360時間等)を基本とします。しかし、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」が予想される場合には、一定の条件の下で限度時間を超える時間を延長時間とすることが可能です。こういった協定を「特別条項付協定」といいます。
昨今、この「特別条項」が盛り込まれた36協定を届出した事業所には労働基準監督署の調査がはいりやすくなっていります。また、一般の調査でもその運用について条項どおり手続きが行われているかが、厳しく問われるケースが増えてきているため、さらに注意が必要です。
特別条項に定める内容ついては、通達に定められており、手続については次のように記載されています。
「労使当事者間において定める「手続」については特に制約はないが、時間外労働協定の締結当事者間の手続として労使当事者が合意した協議、通告その他の手続であること。また、「手続」は、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに当該特別の事情が生じたときに必ず行なわなければならず、所定の手続を経ることなく、原則となる延長時間を超えて労働時間を延長した場合は法律違反となるものであること。なお、所定の手続がとられ、原則となる延長時間を超えて労働時間を延長する際には、その旨を届け出必要はないが、労使当事者間においてとられた所定の手続の時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があること。」(平成11年1月29日基発第45号)
36協定の特別条項に「労使の協議を経て」と記載した場合で、実際に特別の事情に該当する場合には、誰と誰がどのタイミングで協議を行うかのシステムを構築し、実際のやり取りをその都度、議事録等で明らかにしておく必要があります。
よって、従業員に時間外労働をさせる場合には労使協定を結び所轄の労働基準監督署に届け出なければならないのは当然ですが、それだけで終わらず、締結後にはその内容を遵守し、継続的に時間外労働の管理を行っていくことが義務となります。
※特別条項の運用には「通告」という方法もありますが、労使間トラブル回避のために「労使の協議を経て」とすることが原則とされています。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年10月 8日 金曜日
平成22年10月8日(第275号)...残業ゼロに挑戦する
<あなたの会社は残業を当たり前と思っていませんか>
残業の多い会社は、経営者または管理者が残業を「善」だと思っていることが非常
に多いです。残業が多いと、何となくよく仕事をしているように思われがちですが、本当に欲しいのはパフォーマンス(売上高、利益)のはずです。従って、残業は追加的なパフォーマンスが上がる場合だけが「善」です。この考え方を変えないと残業は減りません。
<残業の多い会社の特徴>
あなたの会社でこんな現象は起こっていないですか?
1.残業を前提としているようにのんびり仕事をしている。
2.見た目は忙しそうだが、ミスややり直しが多く、業務の進み方が悪い。
3.初めから達成が難しい計画に基づいて仕事のスケジュールが組まれている。
4.会議が多く、しかも長い。経営者による訓示、はっぱをかけるような精神論が
多い。
5.終業間際の時間帯になって上司から仕事に指示・命令がよくある。
6.得意先からの注文内容の突然の変更や見直しが多く、受注側として振り回され
ている。
7.上司がいつも残業しているため、部下も仕方なく付き合っている。
8.社員たちの多くは、不満を抱えているが、それを聴いて活かす場がない。
さて、あなたの会社ではいくつ当てはまりますか。
<残業ゼロへの挑戦 その1>
コミュニケーションをよくとること。上下、横(部門間、同僚同士)、顧客との間でもっとも基本的に行われるのは、「報・連・相 (報告・連絡・相談)」ですが、簡単なようで簡単ではありません。
「確認」という作業も非常に大事です。事前・事後、スパンの長いものはもちろん途中経過等しっかりコミュニケーションをとってください。大層な「報・連・相・確認」を少ない回数行なうよりも、日々のちょっとした声かけを頻繁に行なうことで日常のコミュニケーションがかなり良くなるはずです。
もう一度、原点に帰って考えてみてください。ご心配ならご相談ください。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年9月23日 木曜日
平成22年9月23日(第274)...医療費の高額療養費制度について
ケガや病気で大きな手術を受ける場合、非常に高額な医療費を支払うことになります。しかし、この医療費には1ヵ月の上限が定められおり、それを超える分は還付されるという仕組みがあります。これを高額療養費制度といいます。ここでは一般的な収入(標準報酬月額53万円未満)のケースで説明します。
高額療養費の計算式は、「(総医療費-267,000円)×1%+80,100円」です。それを、1ヵ月の総医療費が400万円のケースで解説致します。
<例:総医療費 400万円>
・窓口で支払う医療費 120万円(自己負担が3割の場合)
・高額療養費 (4,000,000円-267,000円)×1%+80,100円=117,430円
・還付される金額 1,200,000円-117,430円=1,082,570円
ご覧のように自己負担分の大半が戻ってきます。しかし、この高額療養費制度は申請をしないといけません。申請をしない限り戻ってくることはありません。親切な病院ですと、そういう制度があるというだけでなく、申請書の書き方まで教えてくれます。また、保険者からも、高額療養費に該当しているので申請するように通知してくれるケースもあります。しかし、代わりに申請をしてくれるわけではありません。忘れずに申請しましょう。
ここで、解説いたしました他に、高額所得者のケースや、世帯で医療費を計算した場合、高齢者、1年に複数月に該当した場合などは計算方法が異なります。そういった場合は病院にいるソーシャルワーカーか、社会保険労務士にお聞きください。
サラリーマンが加入している健康保険では、入院のみに関して事前に限度額認定を受けておきますと、最初から医療機関での窓口負担が高額療養費の金額で済むようにすることができます。心臓の手術など、事前に高額の医療費がかかることがわかっている場合には、ご活用ください。【高額療養費の現物給付化 限度額適用申請】
その他にも、還付金額の8割までを無利子で貸し付けてくれる制度もありますので、急な入院で限度額認定を受けられなかった場合はご活用ください。【高額療養費貸付制度】
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年9月 8日 水曜日
平成22年9月8日(第273号)...2010年度最低賃金、平均15円の上げ幅か?
8月5日中央最低賃金審議会において、2010年度地域別最低賃金額改定の目安について、最低賃金引き上げ幅の目安を全国平均で時給15円とすることが決定されました(前年度の引き上げ幅は10円)。全国の都道府県で10円以上引き上げることになります。結果、全国平均の時給は728円(前年713円)に上がる見通しが発表されました。
上げ幅を巡っての協議は労使の対立が続き、デフレを背景に、厳しい経営環境を余儀なくされている企業も多く、「最低賃金の引き上げは、特に中小・零細企業の経営への打撃が大きい」と企業から言われていました。一方、労働者側は「政府目標の800円でも手取りで月13万円程度、ぎりぎりの水準」と応酬。
その後、各都道府県地方審議会の答申にて、先に国が示した目安を上回る引き上げ幅にした地域が相次いでいます。
審議の中では、生活保護支給額との逆転解消も焦点のひとつとなっていました。2009年度で生活保護費が最低賃金より高かったのは12都道府県。この度、その生活保護支給額との差額の大きい12都道府県での上げ幅は、東京都/30円(821円〔新最低賃金 以下同じ〕)、神奈川県/29円(818円)、京都府/20円(749円)、大阪府/17円(779円)、千葉県16円(744円)、埼玉県/15円(750円)、北海道/13円(691円)、兵庫県/13円(734円)、秋田県/13円(645円)、青森県/12円(645円)、宮城県/12円(674円)広島県/12円(704円)となる答申がされました(各地域、10月から11月に改定額が発行される見通し)。
生活保護支給額の方が高い逆転現象が続けば就労意欲が損なわれる一方で、最低賃金が引き上がれば、デフレ下での企業の厳しい現状において、特に都市部より地方の経営者へ与える影響は大きいものがあると推察されます。
日本商工会議所の「最低賃金引き上げ」に関するアンケート調査の結果発表によると、最低賃金が現在より10円程度引き上げとなった場合に「経営に影響が出る」と回答した小規模企業は18%。また、3.8%が引き上げにより「従業員を減らす」と回答。
最低賃金について、現民主党政権は6月の新成長戦略の中で、2020年までに名目3%、実質2%を上回る経済成長を前提に、全国最低800円、平均1,000円に引き上げる目標を掲げています(2009年度現在、最低賃金の低額な地域は沖縄県を含む4県が629円、最も高い東京都が791円)。政府の景気好転への積極的な打開策が望まれます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年9月 8日 水曜日
平成22年9月8日(第273号)...2010年度最低賃金、平均15円の上げ幅か?
8月5日中央最低賃金審議会において、2010年度地域別最低賃金額改定の目安について、最低賃金引き上げ幅の目安を全国平均で時給15円とすることが決定されました(前年度の引き上げ幅は10円)。全国の都道府県で10円以上引き上げることになります。結果、全国平均の時給は728円(前年713円)に上がる見通しが発表されました。
上げ幅を巡っての協議は労使の対立が続き、デフレを背景に、厳しい経営環境を余儀なくされている企業も多く、「最低賃金の引き上げは、特に中小・零細企業の経営への打撃が大きい」と企業から言われていました。一方、労働者側は「政府目標の800円でも手取りで月13万円程度、ぎりぎりの水準」と応酬。
その後、各都道府県地方審議会の答申にて、先に国が示した目安を上回る引き上げ幅にした地域が相次いでいます。
審議の中では、生活保護支給額との逆転解消も焦点のひとつとなっていました。2009年度で生活保護費が最低賃金より高かったのは12都道府県。この度、その生活保護支給額との差額の大きい12都道府県での上げ幅は、東京都/30円(821円〔新最低賃金 以下同じ〕)、神奈川県/29円(818円)、京都府/20円(749円)、大阪府/17円(779円)、千葉県16円(744円)、埼玉県/15円(750円)、北海道/13円(691円)、兵庫県/13円(734円)、秋田県/13円(645円)、青森県/12円(645円)、宮城県/12円(674円)広島県/12円(704円)となる答申がされました(各地域、10月から11月に改定額が発行される見通し)。
生活保護支給額の方が高い逆転現象が続けば就労意欲が損なわれる一方で、最低賃金が引き上がれば、デフレ下での企業の厳しい現状において、特に都市部より地方の経営者へ与える影響は大きいものがあると推察されます。
日本商工会議所の「最低賃金引き上げ」に関するアンケート調査の結果発表によると、最低賃金が現在より10円程度引き上げとなった場合に「経営に影響が出る」と回答した小規模企業は18%。また、3.8%が引き上げにより「従業員を減らす」と回答。
最低賃金について、現民主党政権は6月の新成長戦略の中で、2020年までに名目3%、実質2%を上回る経済成長を前提に、全国最低800円、平均1,000円に引き上げる目標を掲げています(2009年度現在、最低賃金の低額な地域は沖縄県を含む4県が629円、最も高い東京都が791円)。政府の景気好転への積極的な打開策が望まれます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年8月23日 月曜日
平成22年8月23日(第272号)...財産評価について
相続や贈与により財産を取得した場合には、相続税や贈与税が課されますが、その財産の評価について、いくつか説明します。
上場株式
上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価します。課税時期とは、被相続人が死亡した日や贈与を受けた日のことです。
ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
1.課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
2.課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
3.課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
家屋
家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。
したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。
土地
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
1.路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
2.倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年8月 8日 日曜日
平成22年8月8日(第271号)...男性の育児休業取得率
平成21年度雇用均等基本調査
平成22年7月16日厚生労働省は「平成21年度雇用均等基本調査」の結果を発表しました。女性の育児休業取得率は20年度より5.0%ポイントも低下し85.6%となったものの、男性の育児休業取得率は20年度より0.49%ポイント上昇し1.72%と過去最高との結果です。
一方、同じく厚生労働省の20年度「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」では、男性で「育児休業制度を利用したい」と思う人の割合は31.8%。育児休業制度を利用したいとは思ってはいるものの、実際には利用できない男性が多いようです。女性の社会進出が当たり前になった昨今、厚生労働省は「男性の育児参加」や育児休業取得の促進等を目的とした「イクメンプロジェクト」を始動しています。
(http://www.ikumenn-puroject.jp/index.html)
夫婦そろって育児休業を
育児休業法第5条には、原則として、その子供が1歳になるまでの間、労働者は休業できると定められています。今年6月の育児・介護休業法の改正により、「労使協定を定めることで配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合、他方の親は産後8週間を除き育児休業を拒むことができるという制度」が除外され、父母ともに育児休業が取得可能になりました。また、その場合、休業期間を1歳2ヵ月になるまで延長できる特典(パパ・ママ育休プラス)も付いています(ただし育休期間は父母各々1年間が上限)。また、いったん、生後8週間以内に育児休業を取得したなら、職場復帰後の再取得も可能です。
今回の改正では、残業など所定外労働の免除を制度化したり(従業員100人以下は平成24年6月30日施行)、小学校就学前の子供を看病するための看護休暇を拡充するなどして、労働者の仕事と子育ての両立を支えています。
今年4月には、東京都の文京区長が2週間の育児休業を取得して話題となりました。妻が専業主婦であったり、育児休業を取っている場合、自分が育児休業を取ることについて周囲にその必要性を説明できないと感じる人も多いかもしれませんが、父親の育児休業取得の需要は高く、法改正を絵に描いた餅に終わらせないためにも父親も育児休業を取得できるよう、環境の整備や回りの理解を深める必要があります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年7月23日 金曜日
平成22年7月23日(第270号)...消えた年金問題(第3号被保険者)
「宙に浮いた年金が5000万件」に代表される年金記録問題がここ数年、大問題になっています。前政権時代から始まった「ねんきん特別便」、昨年から始まった「ねんきん定期便」によって自分の年金記録を点検できるようになり、多くの人が社会保険事務所(現在は年金事務所)を訪れ、それらの人々の申告に基づいて調査と訂正作業が行われ、現在も続いています。社会保険労務士も長年、年金の記録確認作業に携わってきましたが、その中でなかなか理解されていないものの一つに「国民年金の第3号被保険者期間」があります。
昭和61年4月1日以降、「配偶者が厚生年金または共済年金の被保険者であって、自身が厚生年金または共済年金の被保険者でない場合は、国民年金の第3号被保険者とする」ことになり、自身が保険料を支払う必要がなくなりました。しかし、この身分変更は自動的に行われるのではありません。届け出が必要です。
自分が会社勤めをしていて、厚生年金の被保険者であった人が結婚し、退職した場合は配偶者が厚生年金か共済年金の被保険者であった時は国民年金の第3号被保険者になりますが、本人からの届け出が必要でした。
ところが、届け出を忘れる人が多く、結果として年金保険料の納付月数が最低限度の300月に満たなくなる人が沢山できてしまいました。今でも相談窓口で、「この期間は第3号になっているのと違うのですか?」という苦情を何度も聞かされています。このように、国民年金の空白期間の発生が止まらないので、国民年金の孔を埋めるために平成7年4月から「特例届出」制度が2年間運用されて、申告に基づいて調査・確認の結果、復活された第3号期間を「特例納付」として年金記録に追加するようになりました。また、平成14年4月からは配偶者を雇用している事業主が届け出るように変更されました。しかし、未届けが続出したため、平成17年4月から再び特例届出が認められるようになりました。
年金の期間確認に来る相談者の年金記録を見ると、まだ第3号被保険者の期間が誤っている例が時々出てきます。ご自身も第3号被保険者がどのようなものであるのか解っていない場合も多いのです。
事業主の方は、従業員のみならず、その配偶者の身分についてもご配慮いただき、「失われた年金記録」がこれ以上発生しないよう、ご確認をお願いします。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年7月 8日 木曜日
平成22年7月8日(第269号)...平成20年分の相続税の申告事績について
国税庁から、平成20年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について相続税の申告事績が発表されました。
相続税の申告事績
相続が発生した被相続人のうち相続税の申告が必要であった被相続人の割合は、全体の4.2%で平成16年から5年連続で同じ数値となりました。また、被相続人1人当りの課税価格及び申告税額はいずれも前年に比べて減少しています。
平成19年分 平成20年分 対前年比
1.被相続人数(死亡者数) 1,108,334人 1,142,407人 103.1 %
2.相続税申告書の提出人数 46,820人 48,010人 102.5 %
3.課税割合(2./1.) 4.2 % 4.2% ±0.0ポイント
4.納税者である相続人数 118,563人 120,127人 101.3 %
5.課税価格 106,220億円 107,248億円 101.0 %
6.税額 12,635億円 12,504億円 99.0 %
7.被相続人の課税価格(5./2.) 22,687万円 22,339万円 98.5 %
8.被相続人の申告税額(6./2.) 2,699万円 2,604万円 96.5 %
相続財産の構成比
相続財産の構成比は、土地が49.6%、現金・預貯金が21.5%、有価証券13.3%の順となっています。土地の構成比は平成4年の75.9%をピークに減少しており、平成18年から3年連続で50%を下回りました。有価証券については、平成19年後半のサブプライム問題、及び平成20年9月以降のリーマンショックの影響を反映して構成比が減少しています。
(種 類) 平成19年分 平成20年分
・土地 47.8 % 49.6 %
・家屋 5.3 % 5.4 %
・有価証券 15.8 % 13.3 %
・現金・預貯金等 20.5 % 21.5 %
・その他 10.7 % 10.2 %
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年6月23日 水曜日
平成22年6月23日(第268号)...過重労働の訴訟で 和解金2億4000万円
過労死・過労障害損賠訴訟
過労による自殺で、企業に損害賠償貢任を認めた史上初の画期的判決として、電通事件があります。電通は元社員Aさんの自己申告の労働時間について過小申告を認識し、上司がAさんの健康状態の悪化に気づきながらも、業務量や労働時間の軽減を図るなどの配慮をせず、その結果、Aさんは心身共に疲労こんぱいした状態からうつ病にり患し、衝動的、突発的に自殺するに至ったものとして、最高裁は会社の損害賠償責任を認めました。会社側には長時間労働と健康状態の悪化を認識しながら負担軽減措置(安全配慮義務)を取らなかった過失があるとして、東京高裁に審理のやり直しを命じ、平成12年6月、東京高裁で合計1億6800万円を遺族に支払う和解が成立しました。
今年3月に、過労死・過労障害損賠訴訟の解決額の最高額が更新されました。外食産業企業の康正産業株式会社(鹿児島市)で、鹿屋市の元レストラン支配人が、過重な労働の結果、低酸素脳症で倒れ、寝たきりの状態になりました。鹿屋労働基準監督署は会社側の安全配慮義務違反を認めました。また従業員と両親が同社を相手取り提訴し、鹿児島地裁は、安全配慮義務違反があったことを認め、その後、同社が和解金およそ2億4000万円を支払うことで和解が成立しています。
法定労働時間は1ヵ月45時間以内に
企業は従業員の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務違反)として、民事上の損害賠償責任を負っています。労災保険法に基づく保険給付は、企業側の過失がなくても支給されるものの、補償の内容は被災者たる労働者が被った損害の一部に限られます。非財産上の損害に対する補償(慰謝料)は一切ありませんし、財産上の損害に対する補償も平均賃金(給付基礎日額)を基礎に算定された定率的な補償にとどまります。
その結果、労災保険法に基づく保険給付で補填されない損害部分(慰謝料と逸失利益)の補償を求めて、民事上の損害賠償請求訴訟が提起されます。過労死が1件発生したら約1億円の損害賠償責任が生じるものとして、企業は法定労働時間は1ヵ月45時間以内におさめるよう従業員の時間外労働の管理に改めて注意を払いましょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年6月 8日 火曜日
平成22年6月8日(第267号)...中 国 経 済
産業の空洞化
奈良県には奈良県立大学という公立の大学がある。この大学の県外からの就学率は、97%、そして、県外就職率も同じく97%ということである。奈良県には、それだけ雇用を吸収できる産業が少ない。アメリカについで日本も生産拠点を中国他の新興国へ移し、産業の空洞化が起こり、国内での雇用チャンスが少なくなってきている。
中国の様子
出張で、上海、蘇州、常州の3都市をよく訪問する機会がある。上海は、人口2,000万人、蘇州で350万人くらいか、常州でも200万人くらいの都市だと思う。経済が発展し工場団地が林立し、その規模も小さな工場でも3,000坪から1万坪規模、大きくなると数十万坪にも及ぶ大工場が個々の工場団地に並ぶ。産業が発展すれば、そこの雇用チャンスが生まれ、人が地方からどんどん集まってくる。そして、都市としても発展することになる。アパートがこれでもかと建築され、周辺には、スーパーマーケットができ、道路も整備される。地震が少ないこともあり、基礎工事が日本よりはるかに簡易であり、何よりも鉄骨を組まない。ほとんどのビルは鉄骨とセメントだけで組みあがっていくので、工期はとても短い。1年後に行くとどんどん高速道路や公共施設等のインフラが整備され、驚くほどのスピードで発展している。
今までは、外資企業(日本、韓国、台湾、EU圏、アメリカ等)が中心で発展してきたが、そこで、技術取得した人たちが、ローカル企業へ就職し、どんどん技術力を付けてきている。まだ、品質面で甘さがあるが、それを補ってあまるほどコストが安くできるようになっている。これから、日系企業も、外資系企業との価格競争ではなく、中国のローカル企業との価格競争にさらされることになる。
8年前に行ったときは、ワーカーと言われる、工場労働者の賃金は、月額1万円前後であった。人口14億人と言われる中国では、労働者の供給は無限にあると考えられていたが、やはり優秀な人材は、高い賃金で、より条件の良いところへ転職していく。そして、賃金もその時に比べると、倍近くまで上昇してきている。それでも、まだ、私の1ヵ月の通勤費にも満たない。
中国の今後
こうしてみてくると、日経新聞の予測記事にもうなずける。経済成長力は、徐々に落ちてくるとは思われるが、まだ、当分の間、国際競争力は勝るであろう。中国からの観光客が、Made in Japan の商品を買っていく、それほど、Made in China の品質に課題はあるが、これも、数年経てば解消されるであろう。中国の競争相手は、今後、ベトナム、インド、マレーシア等人口が多く、まだ、賃金水準の低い国々になるであろう。 (スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年5月23日 日曜日
平成22年5月23日(第266号)...障害年金の加算に対する法改正
障害年金には障害等級1級・2級に該当しますと、障害基礎年金には子供の加算が、
障害厚生年金には配偶者の加算があります。
・子供の加算 227,900円(第一子、第二子)
75,900円(第三子以降一人につき)
・配偶者の加算 227,900円(但し、その配偶者が年収850万円以下)
旧法について
子供の加算に関しましては、対象の子供が18歳の年度末まで支給されます。また、配偶者の加算は、その配偶者が障害年金を受給するか、老齢年金を受給するまで支給されます。しかし、加算対象となるのは、障害年金を受給するに至った時点でいた配偶者と子供とされています。そのため、障害年金受給後に結婚しても、配偶者の加算は支給されませんし、妊娠して出産しても子供の加算が支給されないという状況でした。
法改正にいたる経緯
これにより子供が欲しいと意欲のある障害者の方が、子供をあきらめるという要因になっている指摘を受け、少子化対策の為にも法改正をしようという動きがありました。実は何年も前から国会には改正法案として提出されていたのですが、法案の重要度から後回しになり、毎回国会の会期末までに採決されないため廃案になっておりました。
新法について
しかし、今回は4月13日に衆議院を全会一致で可決され、4月21日には参議院も全会一致で可決されました。これに伴い、来年の4月から、受給権発生以後に結婚された方や子供が生まれた方に加算支給されることになります。
現時点で加算対象でない配偶者や子供がおられる場合、来年の4月以降ご自身で申請に行く必要があります。従業員等身近で該当する方がおられましたらご案内ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年5月 8日 土曜日
平成22年5月8日(第265号)...過労死と労災認定
労災の「対象疾病」
脳血管疾患・・・・・脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症
虚血性心疾患等・・・心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤
上記疾病が「業務による明らかな過重負荷を受けたこと」により発症したこと
発症の有力な原因が仕事によることがはっきりしていることであって、医学的経験則に照らして、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ得ることが客観的に認められる負荷を受けたことをいいます。
認定要件
1.発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと
異常な出来事に遭遇とは、(1)業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与し、著しい精神的負荷を受けた場合(2)事故の発生に伴って、救助活動や事故処理に携わり、著しい身体的負荷を受けた場合(3)屋外作業中、極めて暑熱な作業環境下で水分補給が著しく阻害される状態や特に温度差のある場所への頻回な出入りがある、ことなどが挙げられます。
2.発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと
評価期間は発症前おおむね1週間。特に過重な業務には、労働時間のほか、不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、出張の多い業務、交替制勤務・深夜勤務、作業環境(温度差・騒音・時差)、精神的緊張を伴う業務などの負荷要因が検討されます。
3.発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと
発症前1ヵ月間におおむね100時間又は発症前2ヵ月ないし6ヵ月間にわたって、1ヵ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされています。
月間時間外労働が80時間を超えると労基署が労災認定をする事例が増えます。また、損害賠償請求でも長時間労働は精神障害を発症するリスクが高いとされています。会社はダラダラ残業・深夜残業等をいたずらに認めるのではなく、抑制することが必要です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年4月23日 金曜日
平成22年4月23日(第264号)...報酬に係る源泉所得税について
居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税を源泉徴収する必要があります。ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。またサラリーマンの方が報酬・料金等を支払われた場合、通常源泉徴収義務者になりません。
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
(1)報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
原稿料や講演料など。
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、1人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(2)報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
馬主である法人に支払う競馬の賞金
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年4月 8日 木曜日
平成22年4月8日(第263号)...平成22年4月からの年金額について
物価スライド特例水準の年金額
現在支給されている年金額は、過去、物価が下がったときに、年金額を据え置いているので、本来よりも高い水準で支払われています。平成12~14年度の3年度は、前年に比べて物価が下落しましたが、社会的な影響を考えて、年金額が据え置かれました。この年金額を「物価スライド特例水準の年金額」と言います。これは、物価が上昇しても据え置きとなり、物価が直近の年金額改定の基となる物価水準(平成17年度の物価水準)よりも下落した場合にはその分だけ引き下げとなります。
本来水準の年金額
平成16年度の年金法改正で、年金額の計算方法が改正されました。物価や賃金の上昇や下落に応じて、増額、減額されるしくみです。基礎年金では「改定率」、厚生年金では「再評価率」を毎年改定することにより、年金額を決定します。
また、平成16年度の年金制度改正により「マクロ経済スライド」(物価や賃金水準の変動以外の社会的な要因、具体的には平均寿命の伸びや被保険者数の増減を反映して年金額を改定する)が導入されていますが、このマクロ経済スライドはまだ発動されていません。
今後、物価や賃金の上昇により、本来水準の年金額が物価スライド特例水準の年金額を上回れば、本来水準の年金額が支給されます。平成22年度においては、依然として特例水準の年金額が上回っており、その差は2.2%です。
(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003zh7-img/2r98520000003zip.pdf)
そして・・
「年金暮らしだから苦しくて・・・」とおっしゃっている高齢者の方々は、インフレが進んでもしばらくの間、年金額の増額には期待できません。一方で、保険料は毎年確実にアップしていきます。これを考慮した生活設計が必要になってきます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年3月 8日 月曜日
平成22年3月8日(第261号)...平成22年度税制改正大綱について
1.相続人等が居住又は事業を継続しない宅地等についての軽減措置を廃止する
相続人が事業や居住を継続しない場合にも現行では200㎡まで50%減額の特例がありますが、事業用・居住用ともに、相続人が居住や事業を継続しない場合にはこの軽減措置は廃止するとされています。
2.一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定する
現行では、例えば、80%軽減の要件を満たす配偶者と満たさない子が一の宅地等を共同相続して共有した場合、居住をしない子にも80%軽減が適用されていますが、取得者ごとに適用要件を判定するとされています。
3.一棟の建物の敷地のうちに特定居住用宅地等とそれ以外の用途の宅地等がある場合には、用途ごとに按分計算する
宅地の上に存する一棟の建物のうちに、例えば、居住用と貸付用がある場合、現行では特定居住用宅地等があれば全体の敷地が80%減額となっていますが、これを用途ごとに按分して適用要件を判定するとされています。
4.特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限ることを明確化する
特定居住用宅地等を「主として居住の用に供している土地等」には限定されないと解釈、つまり限度面積以下なら複数の土地等でも適用が可能という判決が平成21年2月4日に福岡高等裁判所において出されました。これを受け、「被相続人等が居住の用に供していた宅地等」が複数存在する場合には、「被相続人等が主として居住の用に供していた一の宅地等」が本特例の適用対象であることを明確化するとされています。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年2月23日 火曜日
平成22年2月23日(第260号)...改正育児・介護休業法の概要
1.3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。 ※注意1,2
現行法では、3歳までの子を養育する労働者に対して(1)勤務時間の短縮(2)所定外労働の免除(3)フレックスタイム(4)始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ(5)託児施設の設置運営(6)(5)に準ずる便宜供与(7)育児休業に準ずる制度の(1)~(7)までのいずれかを講ずることが義務付けられていました。
施行後は3歳までの子を養育する労働者について事業主に対し(1)、(2)を義務化し(4)~(7)については小学校就学前の子を養育する労働者に対しての「努力義務」としました。
2.子の看護休暇の拡充 ※注意2
小学校就学前の子が、一人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日取得できるようになります。
3..(1)父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヵ月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ、ママ育休プラス)。
(2)父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。現行は、子が1歳未満の期間に労働者1人につき1回取得可能。
4.配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とする制度を廃止する。
現行法の規定では、配偶者が専業主婦(夫)の労働者の場合、労使協定に基づいて育児休業の対象外とすることが認められてきました。この規定が廃止されます。
5.介護のために1日単位の休暇制度を設ける。 ※注意1,2
労働者の申し出により、要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、年5日までの休暇を取得できるようになります。(対象者が2人以上であれば年10日)
※注意1 常時労働者100人以下の場合、平成24年6月30日施行予定。
注意2 労使協定による除外規定あり
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年2月 8日 月曜日
平成22年2月8日(第259号)...ビジネスコーチング
企業の中での、ストレスでもっとも大きな原因の一つは、人間関係といえます。コミュニケーションがうまくとれない、話を聞いてもらえない、成果を評価してくれない、ほめてくれなくて、けなされてばかりいる、パワハラにあっている、というような人間関係によるストレスによって、ノイローゼになったり、就業不能になったりしています。
2.ビジネスコーチングの基礎
リーダーシップの取り方によって、ずいぶんこうした人間関係のストレスは解消できます。その一つの方法として、ビジネスコーチングがあります。その基本は、部下を信じて、仕事や責任を任せてできれば評価し、ほめてやるということです。さらに、一定の結果が出るまで待ってやる、その間じっと見守り耐えることが大切です。大方のリーダーは、できないだろうなという部下に、仕事を与え、すぐ結果がでないと、やっぱりお前では無理かと仕事を取り上げ、自分でやってしまい、おまえはまだ能力不足だなとけなす。こんなことをしていたら人材は育ちませんね。これは、仕事を任せたのではなく、放任したということです。
3.教育と訓練
さて、とは言え、まったく能力のない部下に、仕事ですから最初から信じて任せることはできません。少しずつ与えて完了を見届ける、完了したら、その次のランクの仕事を与えていき、できる仕事の質と量を増やしていく、したがって、それには必要な教育と訓練がスパイラル的に必要になります。教育・訓練の結果をしっかり判定し、その上で信じて任せてやる、こうして好循環を作り出すことができます。
4.あなたがボトルネック?
あなたは、今、担当している仕事を部下に任せることができますか?あなたは、もっと付加価値の高い仕事が見えていますか?今の、自分の仕事にしがみつき、手放すことができない上司はリーダーの資格はないですよ。そう、そんなあなた自身が組織のボトルネックになっているのです。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年1月23日 土曜日
平成22年1月23日(第258号)...健康診断の結果は大切に保管しておきましょう
<ケース1>聴力の衰えを健診で指摘された女性で、結婚退職する予定があったため、退職して2日後に受診を開始した。いよいよ補聴器が必要な状態になり、障害年金を申請しようとしたところ、病院に残っている初診日は退職後2日目であり、障害基礎年金しか申請できない。健診の記録があれば障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給できたのに、健康診断の記録がないために、年金額が100万円近く少なくなってしまった。
<ケース2>健康診断で尿から淡白が出ていることを指摘されるも受診せず、その後退職してずっと国民年金を支払ってこなかった。退職後15年近くたって全身の倦怠感により初めて受診すると、即入院となり透析を受けないといけなくなった。本来なら障害基礎年金のみの申請だが、そもそも国民年金保険料も15年近く未納であったために、申請する権利すらなかった。しかし、会社員だった頃の健診の記録が出てきたので、この時点で尿に淡白が出ているからすでに腎臓に異常があったと主張でき、障害厚生年金と障害基礎年金の両方(年額約150万円)が支給された。
※日本の障害年金制度は初診日主義という形をとっており、すべての基準が初診日となっています。障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)の2種類があり、初診日が国民年金の期間であれば、障害基礎年金しか受給できませんが、初診日が厚生年金に加入している期間にあると、(2級以上に該当すれば、)障害基礎年金と障害厚生年金の2種類が受給できるようになります。また、障害基礎年金では受給できない軽度の障害でも障害厚生年金のみ受給できるケースがあります。(障害等級3級)
初診日とは、基本的に医療機関に受診された初日ですが、健康診断で異常を指摘されたのであれば、健康診断を受けた日を初診日として取り扱うことが可能です。
(1)初診日に加入していた年金によってもらえる年金が異なる。
(2)初診日に前日の時点で、一定の保険料を納付している必要がある。
(3)初診日までに支払った保険料で年金額が決定される。(障害基礎年金を除く)
このような影響がありますので、健診結果は大事に保管するようにしてください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年1月 8日 金曜日
平成22年1月8日(第257号)...平成22年度保険料等の変更点
1.医療・介護
(1)健康保険料率(協会けんぽ)
全国平均で標準報酬月額の8.2%から9.3%程度への引き上げ
(労使折半、4月納付分から)
(2)介護保険料率
標準報酬月額の1.19%から1.5%(労使折半、4月納付分から)
2.年 金
(1)国民年金保険料
月額14,660円から月額15,100円(4月分から)
(2)厚生年金保険料率
標準報酬月額の15.704%から16.058%(労使折半、10月納付分から)
3.雇用保険
(1)雇用保険料率(検討中)
年収の0.8%から1.2%(労使折半)
(2)雇用保険の加入要件、適用拡大(検討中)
非正規労働者の雇用見込み期間6ヵ月以上から31日以上
4.子育て・教育
(1)子ども手当
中学卒業までの子ども1人当たり月13,000円(6月から)、平成23年度から倍増予定
(所得税、住民税の15歳以下扶養控除の廃止、増税となるのは平成23年1月から)
(2)児童扶養手当
母子家庭と同様に父子家庭にも支給
(3)高校授業料の実質無償化
公立高校生の授業料(年約120,000円)は徴収しない
私立高校生は世帯の年収に応じ、年120,000円~240,000円を授業料から減額 ※高等専門学校、専修学校も対象
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年12月23日 水曜日
平成21年12月23日(第256号)...年金の課税関係について
個人が年金を受け取った場合や保険料や掛金を支払った場合には、その年金の種類に応じて税制上の取扱いが次のようになります。
1.公的年金等を受け取った場合(遺族が受け取る公的年金を除く。)
公的年金等とは、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金や過去の勤務により会社などから支払われる年金等をいいます。
これらの公的年金を受け取った場合には、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算し、所得税が課税されます。(雑所得)
2.遺族が受け取る公的年金等を受け取った場合
遺族が受け取る公的年金等には、所得税や相続税がかかりません。
3.個人年金を受け取った場合
個人年金保険などの保険形式の年金契約で、保険料を支払っていた保険契約者が受け取る年金は、公的年金等以外の雑所得となり、所得税が課税されます。
保険形式の年金契約で、保険料を支払っていた保険契約者が受け取っていた年金を遺族が継続して受け取る場合にも、公的年金等以外の雑所得として、所得税が課税されます。
4.年金に係る掛金や保険料を支払った場合
年金に係る掛金や保険料を支払った場合には、次のような所得控除を受けることができます。
(1)社会保険料控除
国民年金、厚生年金保険の保険料で被保険者として負担するものや国民年金基金、厚生年金基金の加入員として負担する掛金
(2)小規模企業共済等掛金控除
確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会に拠出する個人型年金加入者掛金
(3)生命保険料控除
生命保険会社等と契約した個人年金保険契約などのうち一定に係る保険料
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年12月 8日 火曜日
平成21年12月8日(第255号)...官公需情報ポータルサイト
「官公需情報ポータルサイト」が平成21年10月1日に開設(運用開始)され、11月1日から、独自に検索システムを有している府省等への対応システムを含む本格運用が始まっています。
1.「官公需情報ポータルサイト」とは
国や独立行政法人、地方公共団体などがインターネット上で提供している入札情報を、簡易に検索・閲覧できるサイトです。「物件・工事・役務」といった受注内容の別や、納品や工事場所などの「地域」別、「発注機関」別など、個別のニーズに応じて入札情報を検索することができます。利用料は無料です。
「経済危機対策(平成21年4月10日)」及び「平成21年度国等の契約の方針(平成21年6月12日)」に基づき開設されました。
2.検索対象となる情報
国(全府省)、独立行政法人等(192法人)、地方公共団体(都道府県、市町村)などがインターネット上で提供している入札情報が検索できます。
3.アドレス
官公需情報ポータルサイト http://kankouju.jp/
4.詳細・問い合わせ先
(1)中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.
go.jp/keiei/torihiki/2009/
090916GovInfoPortalSiteStartUP.htm
(2)中小企業庁 事業環境部 取引課
電話 03-3501-1511(内線5291~7)
03-3501-1669(直通)
(3)平成20年度の地方公共団体における官公需の契約実績や中小企業の受注機会増
大のための取り組み事例も紹介されています。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/
torihiki/2009/091002LocalGovernmentKankouju.htm
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年11月23日 月曜日
平成21年11月23日(第254号)...労働基準法の改正
先のスマイル新聞第236号(H21年2月)でもご案内しましたが、改正労働基準法が平成22年4月1日から施行されます。長時間にわたり労働する労働者の割合が高く水準で推移していること等に対応し、労働時間以外の生活のための時間を確保しながら働くこと(ライフワークバランス)が出来るようにするためです。ご準備は進んでいますか?改めて、改定の概要をご説明します。
1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ(大企業のみ)
1ヵ月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げられます。ただし、中小企業については、施行から3年経過後に改めて検討することとされていますので、3年間は25%を保つことができます。
事業場で労使協定を締結すれば、1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引き上げ分(25%)の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与することができます。
2.割増賃金引き上げなどの努力義務が労使に課されます(すべての企業)
時間外労働が月に45時間を超える事業所様は、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要があります。新たに、次の項目が追加されます。
(1)特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する
割増賃金率も定めること
(2)(1)の率は法定割増賃金率を超える率とするように努めること
(3)月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
が必要となります。
(限度基準告示は改正法の施行までに改正されます。)
※平成22年4月1日までに新しい労使協定を締結して届ければ、この改正は適用さ
れません。
3.年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります(すべての企業)
事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で休暇をとること
ができるようになります。パートタイム労働者にも適用されます。
年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択す
ることができます。
1日分の休暇が何時間分にあたるかは、改正法の施行までに厚生労働省令で定められます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年11月 8日 日曜日
平成21年11月8日(第253号)...住宅ローンの返済が困難になったら
昨今の不景気により、失業したり、収入が減って住宅ローンの返済が困難になっている方が増えているようです。住宅ローンの返済ができなくなると、金融機関は担保となっている住宅を強制的に売却し、その売却代金を住宅ローンの弁済として充当します。これを抵当権を実行するといいます。このような状態に陥ると、もちろんその住宅に住めなくなり、事態は最悪です。そうならないために、金融機関には相談窓口を設けているところもあり、返済条件を変更できる場合があります。例えば「フラット35」を取り扱う住宅金融支援機構の場合は次のようになっています。
1.生活状況の変化に対応する返済方法変更のメニュー
(1)会社の業績が悪化し、収入が減った場合
返済期間の延長で月々の負担を軽減できます。
(2)賞与の支給額が減り、賞与払い分の支払いが厳しい場合
賞与払いの返済額を減額又は取り止め、月々の返済額を増やすことにより対応します。
(3)子供の進学等で一時的に月々の支出が増え、今の返済額では厳しい場合
一定期間毎月の返済額を減額できます。
2.返済期間の延長などにより、返済額を減額する場合
収入基準の条件はありますが、返済期間は最長15年まで延長可能となります。さらに失業中の方、または収入が20%以上減少した方は、返済期間の延長に加えて、元金の支払いを一時休止し、利息のみの支払い期間を設定することも可能です。
3.一定期間、返済額を減額する場合
子供の進学による教育費、入院による医療費など一定期間支出の増加が見込まれる場合、一定期間内において、返済額を減らすことができます。ただし、減額期間が終了した後の返済額は元の返済額と比較して増加し、総返済額も増加することになります。返済期間を延長する場合も、その分の利息が増え、総返済額は増加します。そのため、返済方法の変更は本当に必要かどうかを良く考える必要があります。
また、延滞が一度でも起こると契約違反となり、返済方法の変更自体ができなくなる場合がありますので、早めに金融機関に相談に出向くことをお勧めします。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年10月 8日 木曜日
平成21年10月8日(第251号)...公的年金受給者の住民税特別徴収制度の開始
地方税法の改正により、今月の10月から個人住民税(市税・府県税)の公的年金からの特別徴収制度が始まります。
現在、公的年金を受給されており、個人住民税の納税義務のある方は、年4回、普通徴収されていますが、今回の制度導入により、老齢基礎年金等から引き落とし(特別徴収)されることとなります。
1.対象
この制度の対象となるのは、「平成21年4月1日現在65歳以上の公的年金受給者のうち、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。「介護保険料の特別徴収の対象とならない方」「当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える方」等は特別徴収(引き落とし)の対象とはなりません。
対象となる方には、平成21年度市民税・府県民税通知書により、引き落としされる税額が知らされています。
2.特別徴収の開始は平成21年10月支給分から
平成21年度の引き落としは10月支給分から開始されます。そのため、年度前半の6月と8月は、普通徴収の方法で納付していただくことになります。
3.新たな税負担が生じるものではありません
この制度は、年金所得に係る個人住民税の納税義務者(公的年金受給者)が支払うべき個人住民税を、社会保険庁等の「年金保険者」が市区町村に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
なお、年金所得以外の所得に係る個人住民税は従来どおり普通徴収又は給与からの引き落としです。給与所得と年金所得の両方を有する人が、給与所得に係る個人住民税を給与からの引き落としの方法で納付する場合でも、年金所得に係る個人住民税は公的年金からの引き落としとなります。(事業所での給与計算の実務上の変更はありません。)
詳しくは、お住まいの市区町村の市民税課(課税課)にお問合せください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年9月23日 水曜日
平成21年9月23日(第250号)...健康保険の改正について
1. 平成21年9月からの変更項目
昨年の10月から政府管掌健康保険は全国健康保険協会が運営していくことになり、各都道府県に支部を置き、その地域の実情に応じたサービスが展開されることとなりました。それに伴い、平成21年9月までに都道府県毎の保険料を決定すると健康保険法が改正され、今まで全国一律(8.2%)であった保険料が、この9月より地域によって変更されています。これに伴いお給料からの控除額が変わりますので注意ください。
9月分の保険料を当月のお給料から控除するのか、翌月のお給料から控除するのかで変更する時期が変わりますが、それは御社のルールを確認し、変更をお願いします。原則は翌月控除です。
次に近畿各県の保険料をお伝えします。
滋賀県 8.18% 京都府 8.19% 大阪府 8.22%
兵庫県 8.20% 奈良県 8.21% 和歌山 8.21%
2. 平成21年10月からの変更項目
この10月より、緊急少子化対策として出産育児一時金が4万円増額され、42万円になります。今までは出産育児一時金として35万円に産科医療補償責任保険料として3万円の合計38万円が支給されていました。それがこの10月から平成23年3月までの暫定措置として42万円の支給となります。ただし、子育て支援を、より前面に出している民主党が政権を取りましたので、期間が延長されるなり、給付額が増えるなどの措置が取られるかもしれません。
※産科医療補償責任保険制度とは、出産時の事故により重度の脳性まひになったケースに
支払われる保険料です。支給対象となる赤ちゃんは、妊娠33週以降に体重2,000g以上で誕生して脳性まひになった子とされています。従いまして、次のケースは補償の対象となりません。
(1)色体異常などの先天的な要因
(2)妊娠33週未満や体重2000g未満で誕生した子
(3)産科医療補償責任保険に加入していない施設で出産した子
(しかし、病院、診療所、助産院で加入していない施設は皆無です。)
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年9月 8日 火曜日
平成21年9月8日(第249号)...会社都合の休業と賃金請求権
最近の雇用環境状況下で、会社都合の休業に基づき「休業手当」の支払いが発生しているところが散見されます。労使間のトラブル回避のためにも、ここで通達・判例を紹介しながら問題点を解説いたします。
【労働基準法第26条(休業手当)】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当
該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
【民法第536条(債務者の危険負担)】
(1)前2条(第534条、第535条)に規定する場合を除き、当事者双方の責めに
帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、
債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
(2)債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったとき
は、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務
を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
1.労働基準法第26条、民法第536条、使用者の「責めに帰すべき事由」の関係
労基法第26条の「使用者の責に帰すべき事由(帰責事由)」とは、天災事変などの不可抗力に該当しない限り、帰責事由はあると解されています。したがって、雇用調整のための一時帰休や原材料の欠乏、流通機構の不円滑による資材入手難で休業した場合など、労基法第26条「休業手当」の支払いが必要となります。
ここで問題になるのは民法第536条第2項「債務者の危険負担」の規定により100%の保障をする必要があるのではないかということです。
通説的見解では、両条文の「使用者の責に帰すべき事由(帰責事由)」の範囲が違うことがあげられています(『民法の場合』=「故意・過失または信義則上これと同視すべき事由」とあり、『労基法の場合』=「民法より広い概念で、不可抗力以外の経営障害事由を含める」とあります)。
例えば、親会社の経営難から下請工場が資材資金を獲得できず休業した場合は、不可抗力とはいえず労基法の「休業手当」の支払い要件に該当しますが、資材資金の獲得ができず休業した理由が使用者側の原因に基づかない場合、民法の「危険負担」の要件である債権者の責めに帰すべき事由には該当しないといえます。
ここで注意すべきことは、不況を理由とした生産調整のための休業の多くは民法第536条第2項の債権者(使用者)の責めに帰すべき事由に該当する休業であると考えられることです。
通達(昭22.12.15 基発第502号)では、労基法第26条の休業手当は、民法の一般原則が労働者の最低生活保障について不十分である事実に鑑み、強行法規で平均賃金の100分の60まで保障せんとする趣旨の規定であって、民法第536条第2項の規定を排除するものでないとあります。
また判決のなかには、使用者の民事上の支払義務を減額する趣旨でないため、一時帰休の際の賃金保障につき、民法第536条第2項に基づき100%の賃金支払いを認めている事件(池貝事件、横浜地裁判決 平12.12.14 労判第802号)もあります。労働者側は、休業手当が支給されている場合、賃金全額との差額を請求できることになります。
回避する手段としては、民法第536条は任意規定と理解されているため、個別の特約(当事者間の合意)がある場合は、強行法規である休業手当分の保障で可能です。よって、休業手当のルールを、就業規則にあらかじめ定めていた場合だけでは弱く、労働協約、労働契約等で労基法に反しない形で定める必要があります。
2.一時帰休中、アルバイトで得た賃金控除
前述の通り、一時帰休を命じた場合、使用者の責に帰すべき事由に基づき「休業手当(平均賃金の100分の60以上)」の支払いが必要となります。
労働者が、休業手当の支給を受けながらこの一時帰休中にアルバイトをし、別途収入を得た場合は、賃金の二重取りとなります。このような場合は、既に協定等において、一時帰休期間中に他で働いて得た収入の取扱いについて、取り決めがあればそれによることになります。
協定等に特段の取り決めがない場合、民法第536条第2項後段の「自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない」となります。
この取り扱いについては、解雇事案ですが、駐留軍山田部隊事件(昭37.7.20最高裁第二小法廷判決)の判決のなかで、「労働者は労働日の全時間を通じ使用者に対する勤務に服すべき義務を負うものであるから、使用者の責に帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た時は、右の利益が副業的なものであって解雇がなくても当然取得できるなど特段の事情のない限り、民法第536条第2項但書に基づき、これを使用者に償還すべきものとするのを相当とする」としています。と同時に、その控除限度額は、「労基法第26条の趣旨に照らし、その減額は100分の40までを限度とする」とあります。
3.結論
(1)会社の一時帰休期間中に支払う休業手当が平均賃金の100分の60である場合、
控除することはできません。
(2)支払う休業手当が平均賃金の100分の60を超える場合、超えた額を控除するこ
とが可能です。その場合の限度は、100分の100支払っていた場合、100分の
40となります。
民法第536条第2項と違い労基法第26条は、休業手当(平均賃金の100分の60)の減額を認めていません。よって、(100分の60については)控除することは許されません。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年8月23日 日曜日
平成21年8月23日(第248号)...外国為替証拠金取引(FX取引)の課税について
外国為替証拠金取引(FX取引)で生じた利益については、雑所得となり所得税が課税されます。(以下、一般の個人を対象とした取扱いについてです。)
平成21年7月21日に、大阪証券取引所に外国為替証拠金取引市場(FX市場)が
開設され、東京金融取引所に続いて国内2ヵ所目のFX市場ができました。
以下に、FX取引の課税関係を説明します。
1.申告分離課税
FX取引を取引所※を通じて行ったものである場合には、その生じた利益には雑所得が分離課税で課税されます。(所得税15%、地方税5%)
※東京金融取引所・・・『くりっく365』
大阪証券取引所・・・『大証FX』
また、損失が生じた場合は、他の取引所の上場先物取引の利益と損益通算が可能で、なお損失が控除できない場合は、翌年以降3年間にわたって、『くりっく365』や『大証FX』、他の取引所上場先物取引で発生した利益から控除することが出来ます。
2.総合課税
仲介業者による店頭取引(店頭FX)の場合は、給与所得などの他の所得と合算した総合課税となり、最大50%の税率(所得税40%、住民税10%)がかかる累進課税が適用されます。
また、損失が生じた場合は、他の総合課税の雑所得の利益とは雑所得の区分の中で通算は可能ですが、他の給与所得などとの損益通算や他の取引所の上場先物取引との損益通算は不可となり、3年間の繰越控除もありません。
現行の税制上、一般的に所得が一定の額を超える投資家にとっては、『くりっく365』や『大証FX』などの取引所を通じた取引の方が有利と言えます。
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年8月 8日 土曜日
平成21年8月8日(第247号)...遅延利息権限法・年金遅延加算金法が成立
現在の厳しい経済情勢の中、景気悪化で資金繰りに苦しむ中小企業からの「保険料滞納時の利息が高すぎる」との訴えに配慮したかたちで、平成22年1月1日から「遅延利息軽減法」が施行される予定です。あわせて、社会保険庁による年金記録漏れで、年金が未払いになっていた人に対し、過去5年を超える未払い期間を対象に、物価上昇分を上乗せして支給する「年金遅延加算金法」も、来春システムが整い次第施行されます。
1.「遅延利息軽減法」
<概要> 事業主が厚生年金・健康保険料、労働保険料を滞納したとき、現行年14.6%の遅延利息を、納期限または納付期限の翌日から3ヵ月(労働保険は2ヵ月)までの間に限っては年7.3%とする軽減措置がとられます。
<対象となる保険料>
(1)厚生年金保険料並びに厚生年金基金の掛金 (2)児童手当法の規定による拠出金 (3)国民年金保険料及び国民年金基金の掛金 (4)健康保険の保険料
(5)労働保険料 (6)労災保険法に規定する特別保険料
(7)石綿救済法に規定する一般拠出金 (8)その他9つの法律による保険料・掛金
2.「年金遅延加算金法」
<概要> 社会保険庁のミスにより、年金が長期にわたり未払いになった場合(年金の時効(5年)より遡って未払い金のある人が対象)、物価の上昇分を考慮した「遅延特別加算金」を上乗せして支給することとされました。すべての加算金は、非課税です。
<遅延特別加算金の支給>
社会保険庁は、厚生年金保険・国民年金保険の受給権者または受給権者であった者(未支給年金の支給の請求権を有する者を含む)について、この法律の施行後に当該受給権に係る裁定が行われた場合において、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払うものとされる年金給付の5年の時効を経過した分全額を基礎として、受給権を取得した日に適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該年金給付等を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額を、当該年金給付等を支払うこととされる者に対し支給することとなります。
また、この法律の施行日前に裁定が行われた者については、当該者の請求により行われるので注意が必要です。 (スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年8月 1日 土曜日
平成21年8月1日(臨 時 号②)...雇用調整にまつわる支出の税務処理②
前回に引続き雇用調整に伴って支出した各種費用の税務処理について検討します。
1.解雇に伴う解雇予告手当の支払い
解雇予告手当について、税務上は、「労働基準法第20条の規定により、使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する」こととされており、退職所得として源泉徴収の対象となります。
2.解雇処分等に係る紛争解決一時金の支出
解雇無効の争いや過去の未払賃金の請求などに伴い、紛争解決金等の名目で金銭を支払った場合は、従業員であった者が受け取った金銭は実態により判断されます。
(1)過去の未払賃金分がある時や時間外労働手当を遡及して受給する場合は、それぞれの支給日の属する年分の給与所得として課税対象となります。
(2)紛争解決金の中に、その支払いが遅れたことに対する遅延損害金相当する部分がある場合には、その部分は雑所得として課税対象となります。
(3)不当解雇等に伴う精神的苦痛に対する慰謝料は、損害賠償金として非課税になります。
3.希望退職(勧奨退職)での優遇措置の扱い
希望退職の募集や退職勧奨に当たって、優遇措置として退職金の加算や再就職(転職)支援を設けることが多いでしょう。退職金の加算額も含めて、企業側では全額を損金の額に算入します。従業員側は、全額を退職所得として所得税の課税対象となります。
また、再就職(転職)支援のため人材紹介会社等への支出についても、全額を損金算入することになります。
4.休業手当の支給と雇用調整助成金の受給
会社都合により休業手当を支払う場合は、給与として扱います。休業に伴い中小企業緊急雇用安定助成金を受けると益金の額に算入され法人税等の課税対象になります。
勘定科目は雑収入として処理をします。助成金の収益計上は、原則として支給決定通知を受けた時点としてください。国または地方公共団体等から受け取る助成金等は、消費税の課税対象ではありません。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年8月 1日 土曜日
平成21年8月1日(臨 時 号①)...雇用調整にまつわる支出の税務処理①
雇用調整の動きが非正規労働者だけでなく正規労働者にも広がり、企業と従業員等とのトラブルも増えています。雇用調整に伴って支出した各種費用の税務処理について2回に渡って検討します。
1.雇用調整にまつわる費用処理の原則
雇用調整にまつわる費用について、企業側では、通常、全額が損金算入されます。
一方、従業員が何らかの金銭を受領した場合には、労働の対価としてであれば給与所得、退職によって受けるものであれば退職所得として、課税対象となり源泉徴収の対象となります。「損害賠償金で、心身に加えられた損害に基因して取得するもの」であれば、所得税は非課税となります。
2.内定取消しに伴う一時金(迷惑料)の支払い
一般的には、「高校や大学の卒業予定者と企業との間に、就労の始期を卒業後としてい
る場合には、解約権を留保した労働契約が成立したもの」と解され、採用内定を取り消しした企業が、慰謝料(迷惑料)として金銭を支払うと損金額に算入されます。受け取った側は、前項と同じく損害賠償金として、所得税は非課税となります。
3.「派遣切り」による損害賠償金の支払い
派遣契約期間中の解除を行う場合、派遣先は派遣元に対する損害賠償金の支払いの問題が生じる可能性があります。厚生労働省は、労働者派遣法に基づく「派遣先が講ずるべき措置に関する指針」(平成21年3月31日改正指針公布)において、
・派遣先の責に帰すべき事由により中途解約する場合は、休業等により生じた派遣元の損害賠償をしなければいけないこと
・派遣契約に損害賠償に関する事項を定めることを求めています。
派遣元と派遣先との力関係や、その後の業務への影響を考慮して、実際に損害賠償金が支払われることは少ないかもしれません。法人税法上の損金性は問題ありませんが、消費税では一般的に対価性がないので、課税仕入には該当しません。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年8月 1日 土曜日
平成21年8月1日(臨 時 号②)...雇用調整にまつわる支出の税務処理②
1.解雇に伴う解雇予告手当の支払い
解雇予告手当について、税務上は、「労働基準法第20条の規定により、使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する」こととされており、退職所得として源泉徴収の対象となります。
2.解雇処分等に係る紛争解決一時金の支出
解雇無効の争いや過去の未払賃金の請求などに伴い、紛争解決金等の名目で金銭を支払った場合は、従業員であった者が受け取った金銭は実態により判断されます。
(1)過去の未払賃金分がある時や時間外労働手当を遡及して受給する場合は、それぞれの支給日の属する年分の給与所得として課税対象となります。
(2)紛争解決金の中に、その支払いが遅れたことに対する遅延損害金相当する部分がある場合には、その部分は雑所得として課税対象となります。
(3)不当解雇等に伴う精神的苦痛に対する慰謝料は、損害賠償金として非課税になります。
3.希望退職(勧奨退職)での優遇措置の扱い
希望退職の募集や退職勧奨に当たって、優遇措置として退職金の加算や再就職(転職)支援を設けることが多いでしょう。退職金の加算額も含めて、企業側では全額を損金の額に算入します。従業員側は、全額を退職所得として所得税の課税対象となります。
また、再就職(転職)支援のため人材紹介会社等への支出についても、全額を損金算入することになります。
4.休業手当の支給と雇用調整助成金の受給
会社都合により休業手当を支払う場合は、給与として扱います。休業に伴い中小企業緊急雇用安定助成金を受けると益金の額に算入され法人税等の課税対象になります。
勘定科目は雑収入として処理をします。助成金の収益計上は、原則として支給決定通知を受けた時点としてください。国または地方公共団体等から受け取る助成金等は、消費税の課税対象ではありません。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年8月 1日 土曜日
平成21年8月1日(臨 時 号①)...雇用調整にまつわる支出の税務処理①
雇用調整の動きが非正規労働者だけでなく正規労働者にも広がり、企業と従業員等とのトラブルも増えています。雇用調整に伴って支出した各種費用の税務処理について2回に渡って検討します。
1.雇用調整にまつわる費用処理の原則
雇用調整にまつわる費用について、企業側では、通常、全額が損金算入されます。
一方、従業員が何らかの金銭を受領した場合には、労働の対価としてであれば給与所得、退職によって受けるものであれば退職所得として、課税対象となり源泉徴収の対象となります。「損害賠償金で、心身に加えられた損害に基因して取得するもの」であれば、所得税は非課税となります。
2.内定取消しに伴う一時金(迷惑料)の支払い
一般的には、「高校や大学の卒業予定者と企業との間に、就労の始期を卒業後としてい
る場合には、解約権を留保した労働契約が成立したもの」と解され、採用内定を取り消しした企業が、慰謝料(迷惑料)として金銭を支払うと損金額に算入されます。受け取った側は、前項と同じく損害賠償金として、所得税は非課税となります。
3.「派遣切り」による損害賠償金の支払い
派遣契約期間中の解除を行う場合、派遣先は派遣元に対する損害賠償金の支払いの問題が生じる可能性があります。厚生労働省は、労働者派遣法に基づく「派遣先が講ずるべき措置に関する指針」(平成21年3月31日改正指針公布)において、
・派遣先の責に帰すべき事由により中途解約する場合は、休業等により生じた派遣元の損害賠償をしなければいけないこと
・派遣契約に損害賠償に関する事項を定めることを求めています。
派遣元と派遣先との力関係や、その後の業務への影響を考慮して、実際に損害賠償金が支払われることは少ないかもしれません。法人税法上の損金性は問題ありませんが、消費税では一般的に対価性がないので、課税仕入には該当しません。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年7月23日 木曜日
平成21年7月23日(第246号)...熱中症の予防
夏も盛りになりました。夏には、毎年熱中症が新聞種になっています。職場で熱中症患者を出さないように、予防対策を進めましょう。
1.職場における熱中症の発生状況
平成20年には17名の労働者が熱中症で死亡しています。4日以上の休業者は300名以上になっています。平成18年~20年の3年間の実績では、仕事を始めてから発症・死亡までの期間はその仕事の初日と2日目で50%を超えています。また、月別では7、8月で全体の80%以上を占めています。業種別では建設業38%、製造業19%、運輸交通業10%、商業6%など、発生場所別では屋外60%、屋内34%などとなっています。
2.WBGT値(暑さ指数)の活用
WBGT値とは暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数で、専用の測定器があり、計器のレンタルもできます。簡単に言えば気温と湿度を考慮に入れた体感温度とでもいうものです。例えば気温28℃で湿度90%のときWBGT値は30度、気温30℃で湿度65%のときWBGT値は28度、気温32℃で湿度70%のときWBGT値は31度などとなっています。WBGT値25~28度は「警戒」、28~31度は「厳重警戒」31度以上は「危険」とされています。
3.作業管理
(1)作業時間の短縮
作業の休止時間及び休憩時間を確保し、高温多湿環境での連続作業時間を減らす。
(2)熱への順化
作業者には計画的に高温環境への順化期間を設けることが望ましい。高温作業を
中断すると、中断4日目から順化の喪失が始まります。
(3)水分及び塩分の摂取
自覚症状の有無に関わらず、作業前後及び作業中の定期的な水分、塩分の摂取を
指導してください。摂取確認のための表を作成し、作業中の巡視による確認など
により、摂取を徹底するようにしてください。特に高年齢者はのどの渇きに鈍感
になるとされていますので注意が必要です。
(4)服装
熱を吸収したり保熱しやすい服装を避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用さ
せてください。直射日光下では通気性の良い帽子等を着用させてください。
4.健康管理
糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全、精神・神経関係の疾患、広範囲の皮膚疾患など、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある病気の治療中の労働者には、産業医や主治医の意見を聴いて就業場所の変更、作業の転換などの適切な措置を講じてください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年7月 8日 水曜日
平成21年7月8日(第245号)...「長期優良住宅法」について -200年住宅―
(1)住宅ローン面では返済期間最長50年の「フラット50」が利用できるようになります。また、「フラット35S」の金利優遇期間は当初10年間から20年間に延長されます。
(2)税制面では「住宅ローン減税」による控除額が一般住宅と比較して大きくなります。また、住宅ローンを借入れしない場合でも、所得税額から控除される制度もあります。登録免許税や不動産取得税、固定資産税に関しても一般住宅より税額が低く設定されています。
「長期優良住宅」は着工前に都道府県や市区町村に申請し、認定を受ける必要があります。認定基準は次の通りです。(※国土交通省ホームページから)
(1)劣化対策:数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること(少なくとも100年程度)
(2)耐震性:極めて稀に発生する地震に対し、損傷のレベルの低減を図ること
(3)維持管理・更新の容易性:耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行えること
(4)可変性:居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能なこと
(5)バリアフリー性:将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要な
スペースが確保されていること
(6)省エネルギー性:必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
(7)居住環境:良好な景観の形成や地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
(8)住戸面積:良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
(9)維持保全計画:建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること(少なくとも10年ごとに点検を実施)
但し、上記の認定基準をクリアするためには、建築コストのアップは避けられません。「長期優良住宅」はマンションよりも一戸建ての方が馴染みやすい制度かもしれません。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年6月23日 火曜日
平成21年6月23日(第244号)...「パワーハラスメント」労災認定の判断基準に
権利や地位を利用した嫌がらせ(主に職場の上司によるもの)、「パワーハラスメント(パワハラ)」に関する相談が、全国の労働局にある総合労働相談コーナーに相次いで寄せられています。平成20年度の件数は32,242件で、その前年度より3,907件増、6年前の5倍に上りました。
専門家は、パワハラ相談の急増について「人員削減や職場のIT化で社員同士のかかわりが減ったことも背景にある」と分析しています。
(読売新聞 平成21年6月9日夕刊)
1.相談事例
厚生労働省によると、パワハラの相談事例としては「上司から強く叱責され、殴られそうになった」「仕事のトラブルをすべて自分のせいにされた」「人格を否定するような言葉を言われた」などが多いということです。
実際の事例を少しご紹介します。
(1)お客様からクレームがあった時に上司から強く叱責されたことを会社に報告すると、逆にこの上司から殴られそうになった。
(2)「仕事が向いていないから辞めろ」と言われたり、他の社員の前で体重の測定を強要されたりした。
(3)上司と2人で得意先を回っているのに、仕事上のトラブルをすべて自分の責任とされ、会社に報告された。
(4)業務について叱責する時に、「体臭がする」など人格を否定するような発言を受け続けた。
2.今年度から、「パワハラ」労災判断基準に
厚生労働省は、4月、パワハラによってうつ病などになった場合に労災認定を受けられやすくするよう判断基準を見直し、パワハラを含む「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目を新設しました。従来は「上司とトラブルがあった」という項目しかなく、労災が認められるのはまれでした。
今回の基準見直しを受けたパワハラによる労災認定のケースは、まだ、厚生労働省に報告されていません。しかし、今後、申請の増加が予想されています。
一方、「パワハラは仕事の延長線上で問題となることが多く、労災か否かの線引きは困難」という指摘もあります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年6月 8日 月曜日
平成21年6月8日(第243号)...経済危機対策における税制上の措置
この経済危機に対応して次のような税制上の措置が取られることになりました。
1.中小企業の交際費課税の軽減
従来、交際費等の損金不算入限度額の定額控除は、資本金1億円以下の法人では400万円でしたが、600万円に引き上げられることになりました。
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用することができます。
2.研究開発税制の拡充
平成21年、22年度において税額控除ができる限度額が、当期の法人税額の20%から「30%」に引き上げられました。また、税額控除限度額を超過した額の繰越期間が、1年から最長「3年」(平成24年まで)に延長されます。
なお、この結果、平成21年、22年において発生した税額控除で当年度で控除できなかった税額がある場合は、平成23年、24年にその控除超過額を繰り越して控除することができる措置ができました。
3.住宅取得のための贈与税の軽減
平成22年までの時限措置ですが、直系尊属から居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合に、500万円まで贈与税が課せられないことになりました。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に受ける贈与に適用されます。
この特例は、暦年課税(110万円)または相続時精算課税(住宅の場合:3,500万円)の従来の非課税枠と併用できます。
4.環境対応車(エコカー)への買い換え等普及促進(平成21年4月10日に遡及適用)
5.グリーン家電(テレビ・エアコン・冷蔵庫)の普及加速(「エコポイント」の活用等)
省エネ家電製品を購入した際、価格の5%相当を「エコポイント」として消費者に還元する制度です。
詳しくは、専門家にお問い合わせください。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年5月23日 土曜日
平成21年5月23日(第242号)...無断欠勤による懲戒解雇の注意点
Q)ある日突然出社しなくなり、その後行方不明で1ヵ月以上連絡がとれない従業員がいます。就業規則には「無断欠勤が14日以上に及んだ場合には懲戒解雇する」と定めていますが、注意すべき点はありますか?
1.懲戒解雇の意思表示は、あくまで本人に対して行う必要があります
当該従業員を懲戒解雇とすることは、就業規則の定めにもあり、可能と思われます。(不慮の事故や事件に巻き込まれた場合などの特殊なケースは除きます。)
次に従業員本人に解雇の意思表示を行うわけですが、本人と連絡がとれないことを理由として、家族等に解雇の意思表示を行ったとしても有効とは認められません。
この場合の意思表示としては、民法第97条の2の規定による「公示送達」の方法があります。
2.「公示送達」は手続きが面倒~公示送達の方法~
(1)本人の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てを行い、裁判所の掲示場に掲示します。
(2)この掲示について官報および新聞に少なくとも1回掲載します。
(3)この意思表示が本人に到達したとみなされるのは、最後に官報および新聞の掲載があった日から2週間を経過したときとされます。
(4)よって、実際に解雇が成立するのは、最後に官報および新聞の掲載があった日から2週間を経過し、意思表示が本人に到達したとみなされた日からさらに30日が経過した日ということになります。(解雇予告手当を支払う場合は除きます。)
3.「就業規則の退職事由への追加」で、このケースのような場合に備えましょう
実務上、私生活での金銭トラブル等の個人的理由で正式な退職手続を行わないまま出社しなくなるなど、このケースのような従業員は少なからず存在します。
よって、従業員が行方不明となったとき、会社として解雇の意思表示をしなくてもいいように、就業規則で別途定めておくことが賢明です。
具体的には、就業規則におきまして、懲戒解雇とせず、自然退職という定めにしておきましょう。「14日間無断欠勤を続けた場合は、その最終の日をもって自然退職したものとする。」等を追加しておけば、会社からの解雇の意思表示や本人の意思表示がなくても退職が有効に成立すると考えられます。
なお、雇用保険の喪失手続きにおいては「自己都合退職」として処理をしてもらえます。社会保険についても「健康保険被保険者証添付不能届」を資格喪失届に添付し、被保険者証を回収できない旨を記入して手続きをすることになります。
また、退職金規定には、「無断欠勤で自然退職になったものには退職金は支給しない」と定めておくこともおすすめします。こうすることで、懲戒解雇とおなじような効力を発生させる事ができます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年5月 8日 金曜日
平成21年5月8日(第241号)...平成21年度社会保障制度のポイント
(1)全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率が変更されます
≪現在全国一律8.2%(労使折半。介護保険料1.19%は含みません。)≫
○公的な医療保険制度である「協会けんぽ」が9月分(徴収は原則翌月控除のため10月)から都道府県別の保険料率を導入します。
○近畿各府県の保険料率は次の通りになります。
京都 8.19%、大阪 8.22%、兵庫 8.20%、
滋賀 8.18%、奈良 8.21%、和歌山 8.21%
○今後は、地域ごとの運営努力が保険料率に反映され、健康づくりなどに力を入れて医療費を抑制すれば、その都道府県の料率は低くなります。
(2)「出産育児一時金」が増額されます
○現在の「出産育児一時金」は原則38万円ですが、10月からは4万円アップし42万円となります(緊急少子化対策として2年間の暫定措置)。尚、10月以降は各保険制度から病院に直接一時金が支払われる方式になる予定です(今は加入者が病院に出産費を支払い、手続後、各保険制度から加入者に一時金が支払われます)。出産費用が42万円を超える場合、差額分だけ病院に払えば済みます。
2.年金
(1)「ねんきん定期便」が発送されます
○社会保険庁は今年4月から毎年、厚生年金・国民年金のすべての現役加入者に対し誕生日月に定期便の発送を開始します。今年度分は、厚生年金加入者の場合、勤務していた会社名やその期間、保険料額や将来の年金額を計算する際の基礎となる月給(標準報酬月額)、ボーナス額が記載されます。加入記録が抜け落ちたり、給料が不自然に下っていないか注意する必要があります。
(2)保険料が上がります
○国民年金は4月分から250円アップの14,660円/月。厚生年金は9月分(徴収は原則翌月控除のため10月)から保険料率が0.354%アップで15.704%(労使折半)となります。
3.雇用保険
(1)雇用保険料率(労使折半分)が引き下げられます
○平成21年度(4月から)に限り、0.4%引き下げ(一般の事業1.2%→0.8%)られます。
(2)「育児休業給付金」の見直しがありました
○休業中(育児休業基本給付金)と復帰後(育児休業者職場復帰給付金)に分けて支給している育児休業給付の暫定処置(40%→50%)が当分の間延長されます。
○平成22年4月1日から、休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額休業期間中に「育児休業基本給付金」として支給されます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年4月23日 木曜日
平成21年4月23日(第240号)...経済危機対策における税制上の措置
麻生内閣の経済危機対策として、政策のうち税制上の措置については、次のような
ものとなっております。
1.住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上の者が、その直系尊属である者から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。
この特例は、暦年贈与又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。
これにより、例えば、暦年贈与で、父親から子が610万円※の金銭の贈与を受けて、子が住宅を取得した場合、子が他に贈与を受けていない場合には、贈与税がかからないことになる。
※従来の暦年贈与の非課税枠 610万円=110万円+特例の非課税枠500万円
2.中小企業の交際費課税の軽減
交際費の損金不算入制度について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げる。
3.研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制について、次のように拡充する。
(1)平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度 税額控除の適用を受けることができる限度額を、その期の法人税額の20%から30%に引き上げる。
(2)(1)の期間に、その事業年度の法人税額から控除することができなかった金額については、その後の事業年度※で繰越控除を受けることができるようにし、その場合には繰越控除の適用を受けることができる限度額は、その期の法人税額の30%とする。
※平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度又は
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年4月 8日 水曜日
平成21年4月8日(第239号)...平成21年5月から裁判員制度が始まります
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)により「裁判員制度」がいよいよ平成21年5月21日から施行されます。
1.裁判員の選任方法
裁判員の選任方法については、まず、毎年9月、市町村の選挙管理委員会が、衆議院選挙の選挙人名簿から、「くじ」で裁判員候補予定者を選定して名簿をつくります。次に、地方裁判所が、その名簿をもとに裁判員候補者名簿をつくり、対象となる事件について第1回の公判期日が定まったとき、裁判所は、この名簿に記載された裁判員候補者の中から、「くじ」で呼び出しをする裁判員候補者を選定し、それに応じて出頭した裁判員候補者で所定の不選任の決定がなされなかった者の中から、裁判員を選任することとなっています。
最高裁判所からは1年当たり約5,000に1人程度が裁判員等として裁判員裁判に参加する試算が発表されています。 (「よくわかる!裁判員制度Q&A」最高裁判所発行)
2.従業員が裁判員に選ばれたら
(1)労基法7条本文では、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。」と規定しており、裁判員等としての職務は、この「公の職務」に当たります。したがって、会社としては、従業員が裁判員等に選任され、その職務を遂行するために必要な時間を請求された場合、使用者は、これを拒否することができません。
(2)「公の職務の執行」について、法律上、有給にするか無給にするかは会社の定めにより自由に決定することができますが、従業員の裁判員としての職責負担に配慮し、「裁判員休暇」の規定を定めた場合、これを有給とすることが望ましいとされています。最高裁のHPでも、各種経済団体や企業等に対して、特別な有給休暇制度を作成するよう要望する旨が記載されています。
具体的には、就業規則への「裁判員休暇規定」の新設、特別休暇としての付与等の方法と、さらに有給・無給の取り扱い、有給とする場合の支給額等を明確に定めておくことが重要です。
3.裁判員の日当
裁判員候補者には1日当たり8,000円以内、裁判員及び補充裁判員に選ばれると1日当たり1万円以内で時間に応じ日当が支払われます。これは「報酬」ではなく、諸雑費や一時保育料等の出費、収入の減少などの一部を補償するものであり、税務上、雑所得扱いになります。年金などの他の雑所得と合わせて20万円を超える場合は、従業員は確定
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年3月23日 月曜日
平成21年3月23日(第238号)...リスクアセスメント[6]
リスクアセスメント導入の検討
担当部署或いは担当者を決め、職場の安全衛生活動の問題点を明確にし、問題点をリスクアセスメントによってどのように解決するかを検討し、導入の必要性を自ら理解します。導入効果が期待できることを確認した後、リスクアセスメント導入提案書を作成します。
トップによる導入宣言
事業場のトップがリスクアセスメント導入を決定し、自ら導入を宣言します。トップの導入宣言に基づきリスクアセスメント導入計画書を作成します。芝居じみていると思われるかも知れませんが、お祭りも必要なのです。導入計画書には次のような項目を含みます。
1.導入の目的、目標
2.推進組織、責任体制
事務局、リスクアセスメント実施チーム、対策実施部署を明確にします。
それぞれ責任者を任命します。定例的な会議を設定します。議長は「会して議せず。議して決せず。」にならないようにしなければなりません。
3.導入対象
最初は職場を限定して導入し、試行錯誤と改善によって習熟し、その後実施
対象を拡大することが実際的です。
4.実施マニュアルの作成日程
5.実施マニュアルによる試行日程
6.教育訓練の実施計画
7.職場での試行日程
8.リスクアセスメントの正式導入日程
9.リスクアセスメント導入に必要な費用の見積り
費用の見積り額によっては、導入対象職場を少なくするなど、計画を縮小することも必要になるでしょう。最初から完璧を求めず、小さいところから育てていくことが必要です。
従業員数の少ない事業場では一人が幾つもの役をこなす場合が多く、リスクアセスメントを実施する場合も計画から実施までごく少数の人数で行う場合があると考えられますが、計画書や報告書は決めたとおりに作成し、他部門への連絡が滞ることのないように特に留意しなければなりません。
アセスメントを1回で終わることなく、PDCAのサイクルを回すことによって安全度は確実に向上していきます。思い立ったが吉日、早速始めてください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年3月 8日 日曜日
平成21年3月8日(第237号)...平成21年度税制改正大綱について
国土交通省はこのほど、「主要都市の高度利用地地価動向報告」を発表しました。各地域の不動産鑑定士が主要都市の高度利用地における四半期ごとの地価動向をまとめたもので、それによると、平成20年第4四半期(08年10月1日から09年1月1日)における主要都市150地区の高度利用地の地価は、ほぼ全ての地区(148地区(98.6%))で下落しました。三大都市圏では、全ての地区で下落し、東京圏及び大阪圏では、大半の地区で3%以上の下落となり、名古屋圏では、大半の地区で6%以上の下落となりました。同省は「景気の悪化、新規分譲マンションの販売不振、投資・融資等の資金調達環境の悪化等を背景として土地に対する需要が減退したことや、オフィスビル等における空室率の上昇、賃料の下落等により、収益力について一部で低下する傾向が見られたことが主な要因」と分析しています。平成21年度の税制改正大綱では需要喚起によって活性化を狙う措置として主に次のようなものがあります。
1. 住宅ローン減税の拡充
5年間延長されるとともに、最大控除額が160万円から500万円(長期優良住宅の場合は600万円)にアップしました。
2. 長期譲渡所得の特別控除制度の創設
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した土地等を5年超保有し、その後譲渡した場合には、最大で1,000万円を譲渡益から控除されます。
3. 土地の先行取得の課税の特例制度の創設
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに、棚卸資産以外の土地等の取得後10年以内に、他の保有土地等を譲渡した場合に他の保有土地等の譲渡益の80%(平成22年取得分は60%)を繰り延べる(圧縮記帳する)制度です。従来の繰り延べはある物件を譲渡した後であって、これは譲渡に先んじて取得しても適用されます。
4.その他の期限切れとなる各種特例措置の適用期限の延長
(1)不動産の譲渡に関する契約書に係る印紙税の税率の特例措置
(2)既存住宅に耐震改修をした場合の所得税の特別控除
(3)住宅用家屋・土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率の特例措置
(4)土地・住宅地域に係る不動産取得税の軽減税率の特例措置
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年2月23日 月曜日
平成21年2月23日(第236号)...改正労働基準法が平成22年4月から施行されます
長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していること等に対応し、労働以外の生活のための時間を確保しながら働くことができるようにするため、一定の時間を超える時間外労働について割増賃金の率を引上げるとともに、年次有給休暇について一定の範囲で時間を単位として取得できることとする等の理由により「労基法改正案」が平成20年12月5日に成立し、12日公布、平成22年4月1日から施行されます。
1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ
(1)1ヵ月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
※中小企業(資本金又は出資総額3億円、小売・サービス業5、000万円、卸売業1億円以下又は常時使用労働者数300人、小売業50人、サービス・卸売業100人以下)については、当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予されます。
(2)代償休暇制度の導入
労使協定を締結すれば、1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行なった労働者に対して、法改正による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。
(3)1ヵ月45時間を超える(60時間未満)時間外労働については25%を超える率に引き上げられます。(努力義務)
※特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
2.年次有給休暇の時間単位取得
現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
時間外労働が月に45時間を超える事業所様は、25%を超える割増賃金率を含め、1年後のために今から対策をたてていきましょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年2月 8日 日曜日
平成21年2月8日(第235号)...乗数効果ってどういうこと?
景気対策として、定額給付金が2兆円超の規模で決まりました。さて、この経済波及効果については賛否両論で新聞紙上でも喧々諤々の論調です。そのもとになる考え方が乗数理論です。
1.乗数理論
乗数理論とは何でしょうか?公共投資、例えば、道路工事、橋梁、箱ものと言われる各種の公共建物の建築等を考えてみましょう。まず、政府が道路工事を100億円すると、そこには、土木建設会社が請負、下請けに出したり、工事作業する人たちが雇用されたり、工事資材や建設工事のための建設機械が購入されたりして、2次所得が生まれます。
次に、工事資材の業者は、セメントや砂利、アスファルト等を購入することになり、3次所得が生まれます。こうして、最初の公共工事の発注が次から次と所得を生み出し、最終的に当初の100億円の公共投資に対してどのくらいの所得を生み出すかを計算します。その倍率を乗数と言います。所得の一部は、貯蓄に回されるので、2次所得以下は順次その効果は小さくなっていきます。
2.定額給付はどのくらいの乗数効果が見込めるのか?
ここが議論の分かれるところですね。企業へ公共投資等の形で投資されると波及効果も大きく、乗数は4倍から5倍くらいになるかもしれませんが、個人へ直接給付金として配分されてもローン返済や貯蓄に回され、企業向けの公共投資より、波及する範囲も限定されたものになり、その乗数効果は限定的だと予測されます。
3.乗数効果の大きな公共投資
しかし、従来型の公共投資も原資は国債等の国の借金であり、将来に負担を残すことになります。同じ公共投資でも、例えば、環境対策や緩和ケア向けの施設や教育投資をする等将来役に立つような公共投資をすればと思いますが、なかなか一筋縄では行きません。
将来の安定、安全のためにその保障金として備蓄した方が、はるかに国民は安心し、お金を消費に回すのではないかと思います。将来に不安があるからこそ、貯蓄する訳ですから、安心を持って生活してもらえるような公共投資をしてもらうのが乗数効果も大きくなり、私たちも安心してお金が使えるようになります。そしてその消費が大きな経済効果をもたらすのではないかと思います。皆さんはどんな意見をお持ちですか。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年1月23日 金曜日
平成21年1月23日(第234号)...中小企業緊急雇用安定助成金
米国発のサブプライムローンによる金融バブルの崩壊から始まった世界同時不況、また商品市場(原材料)の高騰を受け、企業経営はますます厳しくなってきています。それに伴い、派遣切り等の雇用調整に関するニュースをご覧になる機会が多いかと思います。派遣や契約社員は、期間の終了時に再度延長を申し込まなければある程度の人員調整が可能です。(※法的に争いのある部分ではあります。)しかし、正社員を簡単に雇用調整して解雇することは法的に非常に難しく、様々な条件をクリアーしていないと裁判等の争いで負けてしまいます。
中小企業においては、派遣や契約社員より正社員をたくさん雇用されていると思います。したがって、ニュース等を賑わせている派遣切り等の雇用調整は取れませんし、正社員を簡単に解雇するわけにもいきません。そこで選択肢にあがってくるのが、従業員を休業させ休業手当を支払うというものです。休業手当は平均賃金の6割以上支払う必要がありますが、従業員を職場で遊ばせておくよりは安くつきます。しかし売り上げもないのに休業手当ですら企業にとって負担であると思います。そこで従来から、一定の要件を満たしている企業には、休業手当に関する雇用調整助成金という雇用保険が原資の助成制度がありました。しかし、従来の助成金では急激な景気悪化の状況に対応しきれないため、緊急措置として平成20年12月から当面の間、中小企業緊急雇用安定助成金という助成金が支給される事となりました。これは従来の受給要件を緩和し、受給額を増額するというものです。もし、雇用調整等をお考えの企業経営者様がおられましたら、是非この助成金も選択肢の一つに加えて検討してみてください。
<主な受給要件>
1. (1)最近3ヵ月の生産量がその直近の3ヵ月又は前年同期に比べて減少している
(2)前期決算等経常利益が赤字である(生産量が5%以上減少している場合は不問)2.従業員の全一日の休業または事業所全員一斉短時間休業をおこなうこと
3.2.または3ヵ月以上1年以内の出向を行うこと
<受給額>
~休業等の場合~
・休業手当相当額の4/5(上限あり)
・支給限度日数は3年間で200日(最初の1年間は100日まで)
・教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6000円を加算
~出向の場合~
・出向元で負担した賃金の4/5
最寄のハローワークにお問い合わせください。 (スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2009年1月 8日 木曜日
平成21年1月8日(第233号)...募集・採用における個人情報の取扱い
個人情報保護法に基づく規制
1.個人情報保護法に基づき、使用者は、応募者(労働者)の個人情報を取り扱うに際して、その利用目的を特定しなければなりません。利用目的を特定するにあたっては、厚生労働省からの指針の一部は次の表現をご参考にしてください。
・雇用契約の締結の際にご記入いただいたご家族等の氏名、住所、電話番号は、ご本人が万一のことがあった際の緊急連絡先としてのみ使用させて頂きます。
・当適性検査の結果は、今後、社内における人員配置を検討する際の資料としてのみ利用させて頂きます。
・人事労務管理にかかわる諸手続(年金・労働保険等)を行う際に、当社人事課職員がその目的に限って使用いたします。
2.応募者(労働者)から個人情報を取得するにあたっては、使用者は利用目的の明示または通知もしくは公表を行わなければなりません。
3.個人情報保護法では、個人情報の取得手段についても、不正の手段により取得された個人情報は、本人の権利利益を侵害するおそれが高いことから、「偽りその他の不正の手段」を用いることが禁止されています。
中途採用に際しての元勤務先からの情報収集
募集・採用段階の情報収集において、元勤務先企業への照会は「第三者からの間接収集」に該当します。その照会自体について本人から事前同意を得る必要があります。
照会を受けた元勤務先企業は、応募者(元従業員)の情報を提供することは、個人情報保護法23条の「第三者への情報提供」に該当し、同16条の「利用目的による制限」に抵触することから、本人から事前同意を得ない限り、情報提供を行うことは許されません。よって、照会への回答に伴う元勤務先企業の法的責任を免れるためには、「第三者への情報提供」等についても、事前に同意を得ておく必要があるといえます。
不採用者の個人情報の取扱い
不採用者の個人情報の取扱いについては、個人情報保護法は具体的義務を課していません。職業安定法5条の4に関する指針に従って、原則として、法令上保管義務のある情報を除き、速やかに返却または破棄・削除を適切かつ確実に行うべきでしょう。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年12月23日 火曜日
平成20年12月23日(第232号)...平成21年度の自民党税制改正大綱
12月12日に平成21年度自民党税制改正大綱が決定されました。主だったものは、以下のものです。
1.住宅ローン控除の拡充
平成21年から25年までの間の居住分の住宅ローン控除を拡充する。
また、同期間について認定長期優良住宅の取得にかかる住宅ローンについては、優遇した住宅ローン控除とする。
2.認定長期優良住宅の取得した場合の特別控除の創設
住宅ローン控除との選択として、原則として取得費の10%を所得税から控除する。
3.中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
中小企業等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を現行の22%から18%に引下げる。
4.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
中小企業等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できる。
5.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税のうち、相続等により取得した株式等(その会社の発行済株式等の総数の3分の2に達するまでの部分に限る。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。
6.上場株式等の譲渡、配当の税金
上場株式等の譲渡の税金と配当の税金は、現在10%(所得税7%、住民税3%)の税率となっているが、この制度は来年も延長して適用される。
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年12月 8日 月曜日
平成20年12月8日(第231号)...衛生管理~事業所の作業環境
産業構造の変化、高齢化の進展等労働者を取り巻く環境が変化する中で、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合が増加しています。また、「過労死」や、メンタルヘルスが大きな社会的関心を集めています。さらに、ダイオキシン類等の化学物質や石綿等による健康への影響が問題となっています。
事業場における衛生管理を適切に進めていくためには、事業場の衛生管理スタッフが、衛生管理に関する十分な知識を有していることが不可欠です。今回は作業環境管理の中でも気積・換気・採光・照明・トイレ・食堂について、労働者を常時就業させる屋内作業場等において定められていることを、ご紹介します。
気積について
屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について、10㎥以上としなければならない。
換気について
換気が十分行われる性能を有する設備を設けたとき以外は、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放可能面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。屋内作業場の気温が10度以下の場合は、換気に際し、労働者を毎秒1m以上の気流にさらしてはならない。
作業面の照度について (作業の区分) (基準)
・精密な作業 300ルクス以上
・普通の作業 150ルクス以上
・粗な作業 70ルクス以上
採光および照明について
明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。また、労働者を常時就業させる場所の照明設備については、6ヵ月に1回以上定期的に、点検しなければならない。
トイレについて
(1)男性用と女性用に区別すること。
(2)男性用大便所の便房は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上
(3)男性用小便所の個所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上
(4)女性用便所の便房は、同時に就業する女性労働者数20人以内ごとに1個以上
食堂について
食堂の床面積は1人について1㎡以上とする。
単に最低基準を守るだけでなく、快適職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしましょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年11月23日 日曜日
平成20年11月23日(第230号)...リスクアセスメント[5]
幾つかのリスクが検討・評価され、リスク低減が必要と判断された場合、原則としては、全てのリスクに対し、それらが許容可能リスク以下になるように対策を実施します。
手順...(1)リスクの高いものから優先的に実施するように計画する。
(2)様々なリスク低減対策案を出し合い、その中から最適な方法を選択する。
(3)リスク対策案の実施前にその妥当性を確認する。
(4)手順(1)で決めた計画に従い、リスク低減対策を実行する。
リスクの程度によってどのような措置を取るか、その原則を決めておく必要があります。
リスクレベル 措 置
些細 措置不要。リスクアセスメント実施記録の保管も不要
許容可能 コスト効果の優れた解決策、またはコスト増加がない改善について検討する。管理を確実に維持するために、監視が必要。
中程度 リスク低減のための検討が必要。費用を十分検討し、実施期限を決め期限内に実行する。中程度のリスクが更に重大なリスクに関係している場合は、詳細なリスクアセスメントを行う。
大きい 大きなリスクが低減されるまで業務を開始することは望ましくない。リスク低減のために多くの経営資源を投入しなければならない場合がある。リスクに関係する作業について緊急的な措置を講じることが望ましい。
耐えられない リスクが低減されるまで、業務を開始することも継続することも望ましくない。多くの経営資源を割いてもリスクを低減する。不可能なら業務を禁止。
リスク低減効果は一般的に(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の順序に従い対策を検討します。
リスク低減策の種類 対策の内容 具 体 例
(イ)本質的に安全な設備、機械等とする。 機械設備の改善によりリスクを低減する。 危険なシャープ・エッジをなくす。
有害な材料を無害な材料へ変更する。
(ロ)安全防護対策を採用す
る。 保護柵を設置する。
光線式の安全防護装置を採用する。
(ハ)保護具、追加安全対策
を採用する。 事故発生時に災害のひどさ、可能性を低減する。 安全帽、保護めがね等の採用
非常停止装置を設置する。
(ニ)使用上の情報により、
作業で災害を防止する 作業上で災害を防止する。 危険状態の表示、警告をする。
作業手順書に重要点を書き、重点管理する。教育訓練を実施する。
「よく注意していれば、事故は防げるものだ。」と、事故の発生を従業員の不注意のせいにすることは、間違っています。人間は過ちを犯すものです。過ちを犯しても事故が発生しないようにするのが経営者、管理者の務めです。(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年11月 8日 土曜日
平成20年11月8日(第229号)...個人情報保護法について
個人情報保護法は、だれもが安心してIT社会の便益を享受するための制度的基盤として、平成15年5月に成立し公布され、17年4月に全面施行されました。この法律は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的として、民間事業者の皆様が、個人情報を取り扱う上でのルールを定めています。そこで情報セキュリティについて解説することとします。
情報流出(漏洩)の実情
(1)漏洩数:NPO法人日本ネットワークセキュリティ協会調査結果
平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
対象事業者数 366件 1032件 993件 864件
合計被害者数 10,435千人 8,815千人 22,237千人 30,531千人
1件あたり人数 31,057人 8,922人 23,432人 37,554人
(2)情報流出の原因等
1.技術的要因には、人為ミスとして、設定ミス、誤操作、管理ミス等、対策不足として、ワーム・ウイルス、バグ・セキュリティホール、不正アクセス等があります。
2.非技術的要因には、人為ミスとして、紛失・置き忘れ、目的外使用、犯罪として、内部犯罪・内部不正行為、不正な情報持ち出し、盗難等があります。
3.情報流出の経路としては、紙媒体経由が最も多く、パソコン本体、USB・FD等の可搬記録媒体、メール・Web経由等が続きます。
情報セキュリティを実践する上でのポイント
(1)組織的安全管理措置
安全管理について従業者の責任と権限を明確に定め、安全管理に対する規程や手順書を整備運用し、その実施状況を確認する。
(2)人的安全管理措置
従業者に対して業務上秘密と指定された個人データの非開示契約の締結や教育・訓練等を行う。
(3)物理的安全管理措置
入退室の管理、個人データの盗難の防止等の措置を行う。
(4)技術的安全管理措置
個人データ及びそれを取り扱う情報システムのアクセス制御、不正ソフトウエア対策、情報システムの監視等、個人データに対する技術的な安全管理措置を行う。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年10月23日 木曜日
平成20年10月23日(第228号)...通勤手当の不正受給について
通勤手当は、会社によって様々な制度があります。多くは通勤にかかる費用の全部または一部を会社が負担する制度になっています。
自宅住所によって通勤の交通費は違ってきますので、社員が虚偽の申告をして実際の交通費より多額の通勤手当の支給を受けるという例も時に発生します。
比較的よくある例に、遠隔地に自宅のあった社員が近くに転居したにもかかわらず、そのことを会社に申告せず、従前どおりの過大な通勤手当の支給を受け続けるといったものがあります。
刑法246条は「人を欺いて財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する」と定めています(刑事上の詐欺罪)。
民法709条は「故意又は過失によって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています(不正行為)。
詐欺によって他人に損害を与えることは不法行為に該当し、その損害を賠償しなければなりません。
通勤手当の不正受給の場合の損害額は、虚偽申請によって申請を受けた金額と、実際の住所を申告すれば支給を受けたであろう金額との差額になるでしょう。
どの会社にも懲戒処分の制度があります。金銭上の不正行為は、会社の信頼を裏切るものであり、また、表に出た不正以外にも隠れた不正(余罪)を強く疑わせるものです。金銭上の不正は、金額の大小にかかわらず、社員にあるまじき背信的な非違行為として重い処分をされてもやむを得ません。
それは、経理担当者が会社の金銭を横領するというケースに限らず、一般社員の通勤手当の不正受給についても同じことです。
通勤手当の不正受給は、原則として、刑事上は詐欺罪、民事上は不正行為に該当します。会社秩序維持のため、厳しい懲戒処分も可能です。ただし、具体的な事情、反省度や被害弁償などを考慮して、適切な対処をすべきでしょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年10月 8日 水曜日
平成20年10月8日(第227号)...ゴーイング・コンサーンってどんなこと?
最近、新聞紙上で「ゴーイング・コンサーン」って言葉を見かけますね。一体、どんな意味なんだろう?簡単に言うと「事業の継続性」ってことです。なんや、当り前のことやないか、ってことになりますが結構奥が深い言葉なんですよ。
1.経理処理の前提
経理処理は、この「ゴーイング・コンサーン」を前提として、行うことになっています。例えば、会社で売っている商品は、正常な状態で売るからその価格が成り立ちますが、「店じまい」なんて出ていると大幅に価格ダウンして売っているのと同じで、倒産!なんてなるとその会社の売る商品は相当価格ダウンしないと売れませんし、ましてや、使っていた機械等はそれこそスクラップ同然の二束三文になってしまいます。ですから、会計上の資産は、事業が今後も継続して運営されることを前提としてその評価の仕組みが成り立っているといえます。
2.上場企業のゴーイング・コンサーン
新聞紙上に取り上げられている事例は、株式を上場している企業の株主等への報告書のそのコメントが付いたときです。どんな場合にそのコメントが付けられるかというと、赤字決算が3年も4年も続き、お金の流れ(キャッシュ・フロー)もやっと銀行からの借り入れでまかなっているような会社で、もし、銀行が貸出をストップすると資金が回らなくなって倒産、すなわち、「ゴーイング・コンサーン」の会社でなくなってしまうような場合に付けられます。株主は、このコメントを見て株式を買うか、売るかの判断に役立てることになります。厳しいですね、自ら事業経営が成り立たなくなる可能性があることをコメントする訳ですから。
3.中小中堅企業も同じ
以前212号では、「車の両輪」というテーマで書きました。利益も資金も事業を継続していく(ゴーイング・コンサーン)ためにはどちらも欠かせないということをお知らせしました。株式公開企業だけでなく、中小中堅企業もこの「ゴーイング・コンサーン」ということはとても大切なことです。さて、あなたの会社は、しっかり事業計画を立てていますか?あなたの後継者は、喜んであなたの事業を継続してくれますか?
さあ、しっかり、利益と資金を確保できるように経営をしましょう。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年9月23日 火曜日
平成20年9月23日(第226号)...「名ばかり管理職」にご用心!
今年の初めに、マクドナルドの店長に関する裁判があり、店長を管理監督者として認めず、残業代を支払うよう会社側に命じる判決が出ました。あくまで地裁レベルの判決ですが、これにより労働基準監督署の動きが変わってきました。昨年まではサービス残業の問題を中心に監査をしていましたが、今年から「名ばかり管理職」の取締りを中心に監査していくことになったそうです。ある労働基準監督署の次長によると、「京都でもマクドナルドのような業態の会社を含めてどんどん監査します。」とのことでした。皆様の会社におかれましても、十分にご注意ください。また、その次長の話ですが、「最近の労働者さんは権利意識が強くなり、以前は是正勧告に入るだけで感謝されたのが、時効になっていない2年分の残業代を支払うように是正勧告しないと、苦情の電話がある。」とのことです。その流れを受けまして、「名ばかり管理職」と指摘された場合は、2年分の残業代の支払命令が出ます。景気が後退局面になっていますので、今後の資金繰りに影響をあたえかねません。今のうちに見直しをしておいてください。
次に、裁判長が管理職としてみなせるかどうかの判断をした基準を示します。ご活用ください。
(1)職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
(2)その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か
(3)給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か
これらは、以前から労働基準監督署が示していた基準と、ほぼ同じです。今後は、監督署としては、(3)を中心に判断することになる予測です。私の元勤務先でも見られたことですが、課長に昇格したので、年俸制に変わり残業代がつかなくなった結果、基本給等は上昇していても、年収が下がってしまうというケースがありました。監督署とすれば、こういったケースは(3)に違反しているので、すべて「名ばかり管理職」として判断することになります。このような指摘を受けないように、今のうちから対策をしておいてください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年9月 8日 月曜日
平成20年9月8日(第225号)...第三者行為災害について
自動車事故等における第三者行為災害の場合、被災労働者またはその遺族など労災保険の受給権者は、労災保険から各種給付を受けることができますが、同時に、受給権者は、その災害を発生させた加害者から、民法による損害賠償を受ける権利も有していることになります。
しかし、労災保険から給付を受け、さらに、加害者からも同一の損害について賠償を受けるとすると、一つの事故による同一の損害について、二重に補償を受けることになってしまいます。
そのため、労災保険法では、国が受給権者に保険給付を行った場合には、国は、国が行った給付と同一の部分に限り、その給付の範囲内で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得(代位取得)するとしています。
逆に、受給権者が、第三者から労災保険の保険給付と同一の事由について損害賠償を受けたときは、国はその価格の限度で保険給付は行わないとしています。
では、第三者と示談を行った場合どうなるのかというと・・・・・仮に、示談によって、労災保険の受給権者が加害者である第三者に対して有している損害賠償請求権をすべて放棄した場合、その後に国が保険給付を行ったとしても第三者に対する損害賠償請求権を代位取得することができなくなってしまいます。
そのため、労災保険では、第三者行為災害に関する示談の取り扱いについての基準を定めています。(1)示談が真正に成立していること。(2)示談の内容が労災保険の給付と同一の事由に基づく損害賠償請求権の全部の補填を目的としていること。この二つの条件を両方満たす場合には、労災保険から保険給付は行われないとしています。
したがって、全損害の補填を目的としていると認められない場合は、保険給付は行われます(労災保険と同一の事由による示談金は、保険給付から控除されます)。
示談する場合の注意点
・加害者の確認(損害賠償責任は加害者本人だけでなく、その使用者や車の所有者にもある場合があります。使用者や車の所有者の氏名、住所、電話番号等も確認すること)
・金品を受領するときは、見舞金、香典、治療費等名目及び金額を明確にしておくこと
・出費はメモし、領収書を保管しておくこと
・損害の項目ごとに交渉、後遺症についての交渉は慎重に行うこと
・示談書の作成には、内容をよく確認して判を押すこと(後から変更できなくなります)
・示談書の内容は明確に(特に自賠責保険、労災保険、社会保険等の給付を含むかどうか)
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年8月23日 土曜日
平成20年8月23日(第224号)...被相続人の死亡によって受ける弔慰金等について
相続税法上の取扱い
被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料等については、通常相続税の対象になりません。
相続税の対象となる場合
1.被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
2.上記1.部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金
額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。
(1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
相続財産とみなされる退職手当金等
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金、
その他これらに準ずる給与(「退職手当金等」)を遺族が受け取る場合で、被相続人の死
亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
この場合において、非課税限度額を超えるときの超える部分の金額及び遺贈により受け
取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。
※非課税限度額
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年8月 8日 金曜日
平成20年8月8日(第223号)...終業後の接待飲食や宴会は労働時間?!
企業社会では、接待の飲食等が行われ、飲食中に仕事の話が行われますが、終業時刻後の取引先などとの接待飲食や宴会等については、労働時間となり時間外労働になるでしょうか? 次による判断基準をご参考にしてください。
「 飲み食い」が主たる目的の場合は、労働時間にあたらない
【取引上の交渉等における飲食時間で、「付き合い」としての飲食懇談を目的とする場合】
飲食時間をもって労働基準法上の業務遂行時間とみることはできず、原則として労働時間にならないと考えることが適切です。
理由: いくら交渉行為を飲食中に行っても、飲食をしている時間と労働時間の区別を明確に把握することは困難なため。
【従業員同士で行う歓送迎会・忘年会等】
労働時間にならないと考えることが適切です。
理由: 業務関連性がなく、業務遂行時間とみることはできず、明確に把握することは困難なため。
業務関連性がないため、その帰り道での事故は原則として労災保険の通勤災害に該当
しません。
業務として労働時間に該当する場合は?(下記の要件を充たす必要があります。)
(1) 積極的な特命 (2) 業務上の緊要性
・時間を限定した新作・新商品発表会のようなセレモニーや取引先の社長就任披露パーティー
・進水式、業務命令による得意先の開店祝い、総務課従業員が業務命令によって出席する弔事
・飲食時間そのものと、交渉時間が分離できる場合の交渉時間(ホテルで交渉中に夕食時刻となり途中で夕食をとり、その後交渉を続けた場合、前後は労働時間となる。)
「労働時間の算定しがたい場合」となる場合
事業外における飲食を伴う取引交渉時間は、労基法の「労働時間が算定し難い場合」に該当するので「みなし労働」が適用されます。
したがって「所定労働時間労働したものとみなす」取り扱いを受ける場合となり、所定の終業時刻までの労働時間をもってその日の労働時間として算定することになるので、時間外労働とはならないと考えられます。 (スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年7月23日 水曜日
平成20年7月23日(第222号)...リスクアセスメント[4]
リスクの見積り
第214号で述べたチェックリストに従って危険源あるいは危険事象についてリスクの大小を見積ります。リスクは、起こることが予測される災害・健康障害の重大性と、災害・健康障害が発生する可能性の2つの面から見積ることができます。
リスク=F〔(災害・健康障害の重大性)・その障害の発生可能性〕
上の式のFは変数2個の関数であるという意味です。和にするのか積にするのかは確定していませんが、数値で評価してその和を取ることがよく行われています。また、発生可能性を「危険源に接近する頻度」と「危険源に接近したときに災害が発生する可能性」の二つに分ける方法も用いられています。後者の方法では次のように3個の点数で評価します。
危険源に接近した場合に
災害・健康障害の程度 危険源に接近する頻度 災害が発生する可能性
程度 点数 程度 点数 程度 点数
致命傷 10 頻度 4 確実である 6
重傷 6 時々 2 可能性が高い 4
軽傷 3 ほとんどない 1 可能性がある 2
些細 1 ほとんどない 1
上例の評価基準を、例えば次のように設定して、どこを改善すべきかを決めます。レベルⅣは即時改善実行、レベルⅢは即時に改善計画策定開始、3ヵ月以内に実行、などです。
リスクレベル リスクポイントの合計 判定結果
Ⅳ 14~20 受け入れられない
Ⅲ 11~13 重大な問題がある
Ⅱ 8~10 問題が多少ある
Ⅰ 1~7 許容可能
許容可能なリスク
どのような職場にも絶対安全はあり得ないし、絶対安全を求めることは現実的ではありません。許容可能リスクとは、職場にそのまま放置してもやむを得ないようなリスクですが、どの程度まで許容するかについて決めておくことが必要です。
ISOでは、「その時代の社会の価値観に基づいて、所定の状況の中で受け入れられるリスク」と定義しています。また、同時に、絶対安全の理想と、製品、工程またはサービスによって満たされるべき要求と、ユーザーの利益、目的適合性、費用効果の優秀性及び関係する社会の慣行との間のバランスの結果であると言っています。それぞれの会社の製品、サービス等について許容可能の限界はどこにあるのか、トップが決めておかねばならないことです。 (スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年7月 8日 火曜日
平成20年7月8日(第221号)...中小企業の経営承継円滑化法について
平成20年5月9日に民主党を含めた与野党賛成のうえ、参議院で可決され新たに創設されたこの法律は、1.民法の特例、2.金融支援、3.相続税の課税の特例の3つが柱となっています。 そこで、この法律の概要と留意点などについて、解説することとします。
1.民法の特例
一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続(経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可)を経ることを前提に、以下の民法の特例の適用を受けることができることとしました。
(1)生前贈与株式等を遺留分の算定基礎財産の対象から除外できる。
(2)生前贈与株式等の評価額をあらかじめ固定できる。
従来の遺留分放棄は当事者全員が個別に申立てを行う必要がありましたが、改正後は、後継者が単独で家庭裁判所に申立てができることになりました。 民法特例の後継者は、先代経営者の遺留分権利者、すなわち、基本的に配偶者や子供のみが対象となり、かつ、合意の時点で単独で株式の過半数を保有していることが必要となっています。
2.金融支援
経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援するため、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者及びその代表者に対して、以下の特例を設けることとしています。
(1)中小企業信用保険法の特例 (対象 中小企業者)
(2)株式会社日本政策金融公庫法の特例 (対象 中小企業者の代表者)
この金融支援は、親族外承継や個人事業主の事業承継を含め、次のような幅広い資金ニーズに対応します。
(1)相続に伴う株式・事業用資産の散逸を防ぐための取得資金
(2)後継者の信用低下による取引先からの取引条件悪化や金融機関からの借入条件悪化時の運転資金
(3)親族外後継者が親族より株式等を取得する資金
(4)多額の相続税負担が発生したときの資金などが挙げられます。
3.相続税の課税の特例
事業承継の際の大きな障害の一つである、後継者の自社株式にかかる相続税負担の問題を解決するため、平成21年度の税制改正において、経済産業大臣の認定を受けた非上場中小企業の株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税を納税猶予(雇用確保を始めとする5年間の事業継続が要件)する制度が創設される予定で、その適用については平成20年10月1日に遡って適用される予定です。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年6月 8日 日曜日
平成20年6月8日(第219号)...内部監査の効用について
最近、会計業界を賑わしている問題に「内部統制システム」があります。簡単に言ってしまえば、リスクマネジメントの仕組みを会社の中に作りましょうということになります。
その会社のリスクを大きく全社的なリスク、業務リスク、決算リスク及びITリスクに分けてそれぞれリスクをカバーしたり、軽減したりする仕組みを作って行きます。
三様監査とリスクマネジメント
リスクをコントロールしている仕組みがうまく機能しているかどうかを見るのが「監査」という制度になるわけですが、現在の株式会社には、監査役監査、内部監査及び外部の公認会計士による会計監査の三様の監査制度があります。監査役監査は、リスクマネジメントの中でも会社全体のリスクを取扱うコーポレートガバナンス(企業統治と訳されています)がうまく機能しているかどうかを監査します。最近だとコムスンや船場吉兆のように法令違反を犯したり、食品衛生上問題になるような行為をして、結果的に会社へ大きな損害をもたらしていないかどうかといったような大きな視点から取締役の意思決定や仕事の内容を監査します。内部監査は、社長に直属して、会社の中の各部署が会社の方針やルールに従って効率よく業務を行っているかどうかを監査します。外部の公認会計士監査は、こうした内部統制システムが有効に働いているということを確認しながら、会社が作成し株主、金融機関等へ報告する決算の内容が正しく表示されているかどうかについて監査することになります。
内部監査の効用
監査というとすぐ大きな会社を想定しがちですが、基本的な目的は業務処理が会社のルール(標準的な基準や手続)に従って効率よく行われているかどうかを見ることが目的ですから、中小企業や中堅企業でも十分役に立てることができます。その他に、内部監査の効果としては、資産が十分管理され、活用されているかどうかをみたり、不正や誤りを未然に防止したりする機能を持っていますので、優秀な人材を充てると大きな効果が期待できます。
内部監査で求められる知識・スキル
内部監査は、各部署が行っている業務処理の監査をするわけですから、仕事の流れについての知識が必要です。また、監査をするには、監査手続を実施しますのでチェックの方法に関する知識も必要になります。優秀な人材を充てれば充てるほど会社の中は、効率よく動くことが期待できます。 (スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年5月23日 金曜日
平成20年5月23日(第218号)...後期高齢者医療制度についての会社の対応について
新聞・テレビ等で話題になっております、後期高齢者医療制度が4月から開始されました。これに伴い、社会保険に加入されている事業所では、様々な手続が必要となります。それらの対応をまとめてみましたので、ご参考にしてください。
雇用している従業員本人が75歳に達した場合
・社会保険事務所から、資格喪失届が郵送されてきますので、該当する従業員さんの保険証を添付して、社会保険事務所に提出します。
雇用している従業員本人が75歳に達し、75歳未満の扶養家族がいた場合
・社会保険事務所から、資格喪失届が郵送されてきますので、該当する従業員さんの家族も含めた全員の保険証を添付して、社会保険事務所に提出します。
↓
・社会保険事務所に、扶養されていた家族さん分の健康保険資格喪失証明を発行してもらい、従業員さんに渡します。
↓
・その健康保険資格喪失証明書を持って、住所地の市役所等に行き、家族さん分の国民健康保険の加入手続をします。(これは会社の手続きではありませんので、従業員さんに行なってもらってください。)
雇用している従業員さんの健康保険扶養家族が75歳に達した時
・社会保険事務所から、健康保険扶養異動届が郵送されてきますので、該当する扶養家族の方の保険証を添付して、社会保険事務所に提出します。
以上が現在必要な手続となります。
また、社会保険庁は、高齢者に対する医療費を現役世代が負担していることを知らしめるために、給与明細において、4月分の健康保険料から、それら高齢者に対する負担分としての特定保険料と、基本保険料を分けて表示するように求めています。ただし、システムの変更が必要なために、分けて表示することは義務化されていません。また、政局が混迷しており、今後この制度が維持されるかどうかも不透明であるため、給与計算ソフトを作成しているメーカーでも、対応を未定としている所が多いようです。これに関しましては、急いで対応する必要はないと考えます。しばらくは現状のまま運用され、今後の動向に注意をされれば良いと思います。 (スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年5月 8日 木曜日
平成19年5月8日(第193号)...従業員さんの年金申請はお済みですか?
世間では「2007年問題」が話題になっていますが、皆様の職場ではどのような対策をなさっていますでしょうか?多くの事業所では、雇用延長や再雇用制度により65歳までの雇用の延長を実施されていることと思います。従業員さんの老齢年金の申請について、助言はなさっていますか?実は、最近、申請をされていない方が非常に多い現実があるようです。
老齢年金は原則65歳からの支給開始になっています。しかし、経過措置により一定条件を満たせば60歳から支給されます。(しかも65歳までの年金は請求しないと消えてしまいます!)それを知らずに申請をされていない方が非常に多いです。その要件とは、次の2点です。
・65歳になったら老齢年金を受給できる権利を獲得している。
・厚生年金保険に過去合算して1年以上加入している。
上述の2点を満たしている従業員の方がほとんどだと思いますので、60歳の誕生日をお迎えになる際には、一言年金を申請するようにお伝えください。
私ども社会保険労務士が、行政協力で年金窓口相談業務をしていた際にも、60歳から年金が受給できるのに、65歳になって初めて申請に来られる方が多くいらっしゃいます。年金センターの職員さんによると、60歳から受給できることを知らない方や、仕事をしているともらえないと思っている人が非常に多いとのことです。
次に年金申請に必要な一般的なものを記載します。
・ご夫婦2人分の年金手帳
・貯金通帳
・認印
・戸籍謄本(全部記載されているもので、誕生日の前日から6ヵ月以内のもの)
・住民票謄本(世帯全員が記載されているもので、誕生日の前日から6ヵ月以内のもの)
・配偶者の所得証明若しくは非課税証明
・雇用保険証(高年齢雇用継続給付の受給者は、高年齢雇用継続給付決定通知書)
・(公務員だった期間がある方は、年金加入期間確認通知書)
当事務所では、年金申請手続きだけでなく、60歳以上の方には年金を絡ませた賃金のシミュレーションをご提案させていただいています。60~65歳の年金は、賃金が高額だと支給停止になったり、また高年齢雇用継続給付を受けると併給調整がはいりますが、年金や給付を可能な限り引き出し、ご本人の手取り減少をなるべく少なくして人件費の削減効果も大きい案を検討させていただきます。詳細については、お気軽に当事務所にご相談ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年5月 8日 木曜日
平成20年5月8日(第217号)...労働基準監督官による臨検とは
臨検監督とは、労働基準監督官の事業場への立ち入り調査のことで、労働基準法第101条において、行政上の権限として認められているものです。
臨検には、各々その臨検の背景があり、(1)定期監督、(2)労働者の申告、(3)司法手続きとしての告訴のいずれによるものなのかなどを把握することが重要です。
原則として臨検は、事前に日時や必要な帳簿・書類などが知らされることが多いですが、書類の改ざんのおそれがあるときは抜き打ち臨検もあります。また、サービス残業の実態を把握するための夜間調査もあります。
具体的な調査方法としては、ビルの入出管理簿に記載されている入出時間と、タイムカードや自己申告書に記入された終業時刻との差異、パソコンに記載されているオン・オフの時間の履歴確認など具体的な労働時間管理、さらに時間外労働の賃金支払の有無、各種労使協定の作成・届出、社員の健康診断の実施など様々な内容の調査が行われます。
参考)「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措置に関する基準」
(基発339号 平成13年4月6日)
是正勧告書とは、労働基準監督官が、法違反に該当すると判断した事項を記入し、是正するよう勧告するために交付する文書です。これは命令書ではなく、勧告書ですから、事業主側は是正することを義
務付けられることはありません。しかし、強制力がないからといって勧告に応じなければ、労働基準監督署は、法違反として捜査のうえ警察庁に送検することがあります。これはあくまでも、法違反として送検するのであって、勧告に応じなかったことを理由として送検するのではありません。
<是正勧告の例>
1.労働条件の明示(労基法第15条)
新規採用者に対し、労働条件通知書等の労働条件を明示した書面を交付していない。2.健康診断(労働安全衛生法第66条、規則第44条)
常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行っていない。
3.時間外労働等の割増賃金(労基法第37条)
割増賃金の算定基礎となる賃金に役職手当、皆勤手当等を加算していない。
4.就業規則の作成・届出(労基法第89条)
常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出ていない。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年4月23日 水曜日
平成20年4月23日(第216号)...<リース税制について>
平成19年度の税制改正(平成20年4月1日以後に締結する契約について適用。)で所有権移転外ファイナンス・リース取引(注)については、以下のようになっております。
1.売買取引があったものとして法人税、所得税の計算を行います。
2.リース税額控除制度を廃止する。(取得に係る税額控除の適用。)
(注)ファイナンス・リース取引(資産の賃貸借で、賃貸借期間中における契約解除の禁止及び賃借人が当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担等の要件を満たすもの)のうち、リース期間の終了時にリース資産の所有権が賃借人に無償で移転するもの等以外のもの
<中小企業の会計にかかる指針とリース取引との関係>
中小企業の会計にかかる指針では、原則的に所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買処理に係る方法に準じて会計処理を行うこととされていますが、通常の賃貸借取引に準ずる方法(従来行ってきた処理方法)で会計処理を行うこともできることになっています。(注記が必要となる場合があります。)
→今までと同じ会計処理を行うことも可能です。
<リース取引と消費税の関係>
リース税制の改正にともなって、平成20年4月1日以後に締結する契約に関しては、リース取引の目的となる資産の引渡し時に売買取引があったものとして仕入税額控除の適用を受けることになります。
上記の取り扱いは、リース料を経費処理(賃貸借取引として処理)した場合についても同様です。この消費税の取り扱いについての変更については、注意が必要です。
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年4月 8日 火曜日
平成20年4月8日(第215号)...採用時トラブル回避実務Q&A
去る3月1日から労働契約法が施行されました。これを機に労働実務に対しよりコンプライアンス(法令遵守)の必要性が高まっています。今回は、採用時のQ&Aを記載しますので、是非、参考にしていただければ幸いです。
1.採用時の労働条件の明示方法はどのようにおこなうべきか?
労基法15条では、(1)労働契約の期間に関する事項、(2)就業の場所、従事する業務、(3)始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項、(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算・支払の方法、締切・支払の時期、昇給に関する事項、(5)退職に関する事項について、書面で明示することとされています。また、(1)、(2)、(3)のうち「所定労働時間を超える労働の有無」を除き、いずれも就業規則の絶対的必要記載事項として記載すべきものであり、就業規則が整備されている場合には、適用される事項を明確にして就業規則を周知させる必要があります。
2.採用内定取消しをした時の法的な責任とは?
新規学卒者のいわゆる採用内定取消しの問題については、事業主が採用内定通知書を発し、学生から入社誓約書又はこれに類するものを受領した時点で一般的には労働契約が成立したとみなされる場合が多いと考えられます。この場合に成立する労働契約は、卒業できないことその他一定の事由による解約権を留保している労働契約となりますが、解約権留保付労働契約であるとはいえ、他への就職の機会と可能性を放棄するのが通例ですから、就労の有無という違いはあるものの、採用内定者の地位は、一定の試用期間を付して雇用関係に入った者の試用期間中の地位と基本的に異なるところはないと見るべきであるとしています。(昭54・7・20 第ニ法廷小法廷判決 大日本印刷事件)
3.試みの使用期間中の者にも解雇予告又は解雇予告手当の支払の必要があるか?
試用期間とは、一般的に本採用決定前の期間であって、その間に労働者の勤務態度、能力、技能等をみて、事業主が正式に採用するかどうかを判断し、決定するための期間です。事業主が試用期間中の者に対する解雇予告又は解雇予告手当の支払については、試用期間が14日以内であれば必要はありませんが、14日を超える場合には30日以上前に解雇予告を行うか、解雇予告手当の支払が必要となります。(両者の併用は可能)
(労基法20条 昭24・5・14基収第1498号)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年3月23日 日曜日
平成20年3月23日(第214号)...リスクアセスメント[3]
危険源の特定
1.職場の危険源を特定します。
2.危険源に接する人間を特定します。
3.人間と危険源がどのような状態のときにどのような危険事象になるかを特定します。
ここで大切なことは、機械は故障するものであり、人間は間違いを起こすことを前提
に考えることです。合理的に予見可能な誤操作、誤動作についても考慮することが必
要です。
具体的な進め方
職場に存在する危険源を漏れなく洗い出すためのチェックリストを準備し、危険源特定を
します。危険源は次のように分類されます。
1.機械的危険源
はさまれ、巻き込まれ等の災害の可能性
2.作業方法と職場のレイアウトに関する危険源
鋭いエッジ、高所作業、無理な姿勢を必要とする作業等による災害の可能性
3.電気的危険源
電気、静電気への接触による災害の可能性
4.健康と安全に有害な物質または化学物質の危険源
健康に有害な物質による災害、健康障害の可能性、可燃性材料による火災爆発事故の可能性
5.理的物質の危険源
電磁放射線(熱、光、X線等)、騒音、振動等による災害、健康障害の可能性
6.物学的な物質の危険源
微生物等による健康障害の可能性
7.職場環境に関する危険源
不適切な照明、温度、湿度、換気等による災害、健康障害の可能性
8.職場とスタッフの関係等、人的要因に関する危険源
安全衛生情報伝達方法、スタッフの知識不備等による災害、健康障害の可能性
9.心理要因に関する危険源
作業のきつさ、単純作業等心理的要因による災害、健康障害の可能性
10.作業体制に関する危険源
作業(連続繰り返し作業、シフト作業等)による災害、健康障害の可能性
11.その他の危険源
リスクアセスメントは製造業だけのものではありません。
これを応用して企業の危険を防止しましょう。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年3月 8日 土曜日
平成20年3月8日(第213号)...相続税の課税方式が変わる?
自民党が発表した平成20年度税制改正大綱で、相続税の課税方式を「遺産取得課税方式」に改めることを検討すると発表がありました。この改正が実現すると、今後の相続対策に大きな影響を与えることになりそうです。
1.現行の課税方式と遺産取得課税方式の違い (出典:自民党税制調査会 資料)
課税方式 現行制度 (法定相続分課税方式) 遺産取得課税方式
概要 遺産取得課税方式を基本として、相続税の総額を法定相続人の数と法定相続分によって算出し、それを各人の取得財産額に応じ按分して課税する方式 相続等により遺産を取得した者を納税義務者として、その者が取得した遺産を課税物件として課税する方式
考え方 ①累進税率の緩和を企図した仮装分割への対応
②農業や中小企業の資産等分割が困難な資産の相
続への配慮
といった観点から、実際の遺産分割の状況により負担に大幅な差異が生じることを防止するという考え方 偶然の理由による富の増加に担税力を見出して相続人に課税することにより、富の集中の抑制を図るという考え方
留意点 ①自己が取得した財産だけでなく、他の相続人が取得したすべての財産を把握しなければ正確な税額の計算・申告ができない。相続人の一人の申告洩れにより他の共同相続人にも追徴税額が発生する。
②相続により取得した財産の額が同額であっても法定相続人の数によって税額が異なる。
③現行の居住や事業の継続に配慮した課税価格の減額措置により、居住等の継続に無関係な他の共同相続人の税負担まで緩和される。 ①自己が取得した財産だけで、正確な税額の計算・申告ができる。相続人の一人の申告漏れにより他の共同相続人に追徴税額が発生することはない。
②法定相続人の数に関係なく、同額の遺産を取得した者には、同額の税負担となる。(各々の担税力に応じた課税をすることができる。)
③課税価格の減額措置は、居住等を継続する者のみに減税効果が及び、他の相続人の税負担は、軽減されない。
2.なぜこのような改正が検討されているのか
これは、現行制度に基づいて納税猶予制度の適用を受けると、他の相続人の税額まで下がってしまうことが問題視されているためです。またこれとは別に、他の相続人が財産を隠蔽した場合に、そのことを知らなかった他の相続人の税額も自動的に増えてしまうことは、他の相続人の理解が得られにくいと、以前から指摘されていた問題もあります。
3.改正の影響
今までは被相続人の遺産の総額が問題でしたが、改正後は相続人がいくら相続したかだけで税額が決まることになります。今後は、相続人個人単位での対策が重要になり、今まで以上に遺産分割対策、納税資金対策が重要視されてくるでしょう。また、基礎控除も全体財産に対してではなく、相続人個人単位で設けられる可能性が高く、その額によっては相続税の課税対象者が飛躍的に増えることも予想され、影響は多大になると思われます。なお、この
改正は、早ければ平成20年10月以降の相続分から適用される可能性があります。 (スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年2月23日 土曜日
平成20年2月23日(第212号)...車の両輪
"借金を返すと利益(所得)が減ると思う方、手を挙げてください"と。勇気のある方は何人か手を挙げてくれます。しかし、ほとんどの方が首をひねっています。つまり、分からないのです。
企業を車に例えて、その両輪は利益とお金の流れです。上の問に対する答えは、借金を返しても利益には影響ないので、利益は減りません。逆に、銀行からお金を借りたら売上になって利益が増えますかって質問をしてみると良く分かりますね。銀行から借金をするたびに、利益が増えて税金を払うようなことになれば大変ですよね。借金の返済はこれと逆のことですから、利益は減らないということになります。また、よく、決算期になって質問されることもこれに関連していて、"先生は所得が出て、税金を払えって言われるけど税金を払う金なんて残ってないよ。どこに行ったの?"こんな経営者は、儲かったからといって車をきっとベンツに乗り換えているのでしょう。これも利益とお金の流れを混同しているいい例ですね。
さて、資金がなければ会社は簡単に潰れます。たとえ利益が出ていても。お金は企業の血液みたいなものですから循環している限り、企業は倒産しないで維持できます。
事例で見てみましょう。
1.利益が出ているが、資金を設備に過剰投資して、手元に資金が残っていないケース。この場合は、仕入れ代金や給料の支払にさえ困ることになり、仕入れもできなくなり、従業員も辞めていってしまい、経営が困難になります。
2.赤字経営だが、個人資産を担保に銀行からお金を借りて、仕入れ代金や給料の支払に充てられるケース。この場合は、会社は、個人からの借入金が増えますが、支払資金がありますので倒産はしません。もちろん、借入余力がなくなり借入できなくなればそのときには経営の維持はできなくなりますが。
企業には、このように利益とお金が必要であり、まさに経営という車の両輪になるというわけです。
あなたの会社の利益と資金は大丈夫ですか。しっかり舵取りしましょう。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年2月 8日 金曜日
平成20年2月8日(第211号)...住民税からの住宅ローン控除
平成19年から国(所得税)から地方(住民税)への「税源移譲」が実施されました。所得税が軽減されたことから住宅ローン控除額が引ききれない場合は、区役所等へ申告
することにより、平成20年度住民税から控除されます。是非とも申告ください。
1.対象となる住居の入居時期
平成11年1月1日から平成18年12月末日までに入居している。
2.平成20年度住民税から控除される要件
(1)所得税から住宅ローン控除額が引ききれないこと。
(2)「住宅借入金等特別税額控除申告書」を区役所・支所へ提出すること。
※ 平成19年分源泉徴収票の添付が必要です。
(3)所得税の確定申告をされる方は、所得税の確定申告とともに税務署へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を税務署へ提出すること。
3.住宅借入金等特別税額控除申告書の提出期限
平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在お住まいの区役所・支所または
住居地を管轄する税務署へ提出してください。(毎年申告が必要です。)
≪住宅ローン控除モデルケース≫
夫婦+子ども2人、給与年収700万円、住宅ローン控除可能額:27万円の場合
(子ども1人は特定扶養親族)
税源移譲前
税額 住宅ローン控除額 負担額
所得税 263,000 263,000 0
住民税 196,000 0 196,000
合 計 459,000 263,000 196,000
税源移譲後申告を行った場合
税額 住宅ローン控除額 負担額
所得税 165,500 165,500 0
住民税 293,500 97,500 196,000
合 計 459,000 263,000 196,000
住宅ローン控除額が減少しないよう、住民税(所得割)から控除します。
税源移譲後申告を行わなかった場合
税額 住宅ローン控除額 負担額
所得税 165,500 165,500 0
住民税 293,500 0 293,500
合 計 459,000 165,500 293,500
控除額が減少し、負担が増加します。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年2月 1日 金曜日
平成20年2月1日(臨時号)...住民税からの住宅ローン控除
平成19年から国(所得税)から地方(住民税)への「税源移譲」が実施され、所得税が軽減されたことから住宅ローン控除額が引ききれない場合があります。この場合は、区役所等へ申告することにより、平成20年度住民税から控除されます。概要は次のとおりです。
1.対象となる住居の入居時期
平成11年から平成18年末までに入居している。
2.平成20年度住民税から控除される要件
(1)所得税から住宅ローン控除額が引ききれないこと。
(2)「住宅借入金等特別税額控除申告書」を区役所・支所へ提出すること。
※ 平成19年分源泉徴収票の添付が必要です。
(3)所得税の確定申告をされる方は、所得税の確定申告とともに税務署へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を税務署へ提出すること。
3.住宅借入金等特別税額控除申告書の提出期限
平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在お住まいの区役所・支所または
住居地を管轄する税務署へ提出してください。(毎年申告が必要です。)
住宅ローン控除モデルケース
(夫婦+子ども2人 給与収入700万円(住宅ローン控除可能額:27万円)の場合)
※ 夫婦+子ども2人の場合で子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※ 一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年1月23日 水曜日
平成20年1月23日(第210号)...障害年金の障害認定日について
病気や怪我により、不幸にもお体に障害が残った場合、障害の程度及び初診日に加入していた年金の種類によって、それぞれ障害年金が支給されます。自営業者の方や厚生年金・共済年金に加入している方の扶養されている配偶者の方ですと「障害基礎年金」が、厚生年金にご加入されていますと、「障害厚生年金」だけか、「障害厚生年金と障害基礎年金」の両方が支給されます。さて、この障害年金ですが、申請することのできる時期というものがあります。原則は、
・ 初診日から1年6ヵ月を経過した日
・ それまでに治った日(症状固定日)
と規定されています。しかし、これには様々な例外がありまして、次にその一覧を記載いたします。
・ 四肢の切断は切断した日
・ 人工骨頭、人工関節の場合は挿入、置換した日
・ 心臓ペースメーカー、ICD、人工弁の場合は装着した日
・ 人工透析は透析開始から3ヵ月を経過した日
・ 人工肛門は造設した日
・ 新膀胱や尿路変更の場合は作った(手術を受けた)日
・ 脳梗塞の場合は1年6ヵ月を経過するまでに症状固定をした場合、初診日から6ヵ月を経過している日以降
脳梗塞の場合は少し注意が必要で、6ヵ月を過ぎて症状固定をしたのに申請を忘れていて1年6ヵ月を経過してしまった場合は、症状固定日に遡らず1年6ヵ月を経過した日でしか申請をできなくなってしまう都道府県があります。これを知らないと最大で1年分の年金が支給できなくなりますので、事例によっては百数十万円も損をされる方がおられます。皆さんはこのようなことがないようにご注意ください。
詳細については、お気軽に当事務所にご相談ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年1月 8日 火曜日
平成20年1月8日(第209号)...有期雇用契約について
厚生労働省は、雇用期間を定めて働く有期雇用労働者の解雇規制を今後強化する方針です。企業が3回以上契約を更新した場合、次に契約を更新しないときは契約終了の30日前までの予告を義務付けます。現在、雇用されて1年以内の有期雇用労働者に対しては、事前の予告は必要ありませんでした(労基法に基づく「有期労働契約の基準」を改正、3月から適用予定)。
有期雇用契約(期間の定めの有る雇用契約)の現行制度のポイントを以下に整理しました。
1.契約期間の上限
一定の事業の完了に必要な期間(土木工事、ダム建設工事等)を定めるもののほかは、契約期間の上限は3年です。例外として、専門知識等を有する労働者・満60歳以上の労働者との契約期間の上限は5年となります。
2.契約締結時の明示事項
(1)当該契約の更新の有無を明示することが必要。
(2)契約を更新する場合又は更新しない場合の判断基準を明示することが必要。
3.雇止めの予告及び雇止めの理由の明示
(1)契約期間が1年を超える場合や、更新して1年以上雇っている場合、次に契約を更新しないときは契約期間満了日の30日前までに予告をしなければなりません。
(2)雇止めの予告後(雇止めの後)、労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときは、遅滞なく交付しなければなりません。
4.使用者が講ずべき措置の基準について
行政官庁は、雇止めに関する基準に定める内容に反した使用者に対して、「必要な助言及び指導を行うことができる」ようになっています。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年12月23日 日曜日
平成19年12月23日(第208号)...<平成20年度の税制改正大綱>
12月13日に平成20年度税制改正大綱が決定されました。主だったものは、以下のものです。
1. 法人事業税の改正
地方税である法人事業税の税率を半分くらいに引き下げました。その代わり法人事業税額に税率を掛けて国税である地方法人特別税が新たに創設されました。国は、この地方法人特別税を都道府県へ地方法人特別贈与税として配分するのです。平成20年10月1日以後開始事業年度から適用されます。
2.試験研究費に対する優遇税制
試験研究費を支出した場合の税額控除制度が強化され、税額控除額が多くなりました。
3.エンジェル税制の拡充
一定の要件を満たす特定中小会社に出資した場合に、その出資額について1,000万円を限度として、寄付金控除を適用することになりました。現行のエンジェル税制では、出資者個人が、他に株式投資などをしていないとメリットがないケースがあったことによる改正です。
4.事業承継税制
実施時期は明確にされていませんが、中小企業の株式を相続した場合における相続税の納税が優遇されます。事業承継相続人(事業を承継する筆頭株主で、社長の子供などが該当)が相続した親の会社の株式(発行済議決権株式の3分の2にまで)にかかる相続税の80%相当額の納税を猶予するものです。事業承継相続人が死ぬまで自社の株式を所有した場合などは、納税自体が免除されます。
5.住宅の省エネ改修促進税制
住宅ローンを借りて断熱工事を行った場合に、住宅ローン控除と同様の税額控除制度が創設されました。
6.上場株式等の譲渡、配当の税金
上場株式等の譲渡の税金と配当の税金は、現在10%の税率となっていますが、来年も継続されます。平成21年、22年も一定の制限(譲渡の場合は500万円までの譲渡所得、それを超えると20%の税率)はありますが、10%の税率が特例で適用できます。
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年12月 8日 土曜日
平成19年12月8日(第207号)...リスクアセスメント[2]
リスクアセスメント実施の準備
(1)リスクアセスメント実施範囲の決定
1.対象職場:どの職場を対象とするか。
2.対象設備:どの設備・機械とその周辺を対象とするか。
3.対象作業:どの作業を対象とするか。
製造作業、検査作業、保全作業、部品補給作業、異常処理作業、修理作業等、原則としてその職場に関係する作業全てが対象。
(2)リスクアセスメント実施計画の作成(時期)
1.新たな設備の導入、人員の大幅な入れ替えがあったなど、大幅な工程変更後
2.年1回等、定期的な評価実施
◆計画は実施部署長の責任で、関連部署と調整して作成します。
◆計画書に記入すべき内容は、リスクアセスメントとリスク低減対策の具体的な内容を、
5W・1Hに基づき、抜けのないように記入します。
◆参加者は、実施部署のメンバー、リスクアセスメントの教育を受けたメンバーが必要人数参加するように計画します。また、責任者を明確にしておきます。
◆無理な計画を立てないこと(最初から欲張った計画としない)、計画をフォローするための推進組織を作っておくことが必要です。
(3)情報収集(事前に入手)
1.実施している作業の時間・頻度 8.機械類の製造者の指示書
2.作業場所 9.取り扱う材料の寸法・形状・重量
3.作業実施者 10.材料を手で動かす距離・高さ
4.影響を受ける第三者 11.関係法令・規制・規格
5.作業者が受けた教育訓練の内容 12.適正と考えられる管理手段
6.作業手順書の有無とその内容 13.過去の労働災害の内容
7.使用する設備・機械類に関する使用、性能 14.ヒヤリハット報告
上の情報を集めるためには、次のような情報源があります。
1.作業分析書 6.労働安全衛生の管轄当局からの情報
2.作業者との協議 7.労働災害と災害要因のデータ
3.機械メーカーのデータシート、マニュアル 8.現場のルール、マニュアル
4.エキスパートからの報告書 9.作業環境の測定記録
5.安全衛生関係の定期刊行物 10.標準化機関、業界団体の基準
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年11月23日 金曜日
平成19年11月23日(第206号)...減価償却資産の償却方法の選定と変更
平成19年度税制改正により、減価償却について大幅な改正がなされたことに伴い、償却方法の選定・変更の手続きについての一定の経過措置が設けられております。この経過措置により現在適用している償却方法を変更し、または新たに取得する資産についての償却方法を再検討してみてはいかがでしょうか。
1.償却方法の選定
【償却方法の選定】
平成19年4月1日以後に取得した資産については、それ以前に取得されたものと区分して、資産の種類等ごとに選定します。選定にあたっては確定申告書の提出期限までに「減価償却資産の償却方法の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。
【償却方法のみなし選定】
平成19年3月31日以前に取得された資産について償却方法を選定している場合、その選定している資産と同一区分のものを平成19年4月1日以後に取得し、上記の償却方法の選定をしていないときは、同様の選定をしたものとみなされ、償却方法を適用します。 ※ 償却方法の選定をしていない場合は、平成19年4月1日以降に取得された資産についても法定償却方法が適用されます。
2.償却方法の変更
【原則】
償却方法を変更しようとするときは、下記の区分に応じてそれぞれの日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出し、承認を受けなければなりません。
法人 ・・・ 新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日
個人 ・・・ 新たな償却方法を採用しようとする年の3月15日
【経過措置の取り扱い】
下記の対象期間の、それぞれに記載する提出期限までに変更の理由等を記載した届出書を提出すれば、償却方法の変更の承認があったものとみなされます。
対象期間 届出書の提出期限
法人 ・・・ 平成19年4月1日以後 その事業年度に係る
最初に終了する事業年度 確定申告書の提出期限
個人 ・・・ 平成19年分 平成19年分の所得税に係る確定申告期限
※ 償却方法の変更については、上記対象期間の翌事業年度(翌年度)以後においては原則に記載した日までに申請書を提出する必要があります。
なお、平成19年3月31日以前に取得した資産については旧定額法を引き続き適用し、同4月1日以後に取得した資産については定率法を適用することも可能となります。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年11月 8日 木曜日
平成19年11月8日(第205号)...定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)のご紹介
平成19年4月から新たに2種類で構成された「定年引上げ等奨励金」制度が始まりました。
急速な少子高齢化による労働力人口の減少が見込まれる中で、働く意欲を有する高年齢者の方々の知識と経験を活用することが、重要な課題となっております。昭和61年の年金法改正に伴い、昭和36年4月2日(女性は5年遅れ)以後生まれの方からは、年金支給開始年齢が65歳となることも考え、65歳以上、更には70歳まで働ける企業の実現をめざすことが必要とされています。
●中小企業定年引上げ等奨励金
平成19年4月1日以降、就業規則により65歳以上への定年の引上げ、又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主で、一定の要件を満たす中小企業に対して支給
実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに申請が必要(いずれも1回限りの支給)
企業規模 支 給 額
65歳以上への定年引上げ
又は定年の定めの廃止 70歳以上への定年引上げ
又は定年の定めの廃止
(上乗せ額を含む)
1人~9人 40万円 80万円
10人~99人 60万円 120万円
100人~300人 80万円 160万円
●雇用環境整備助成金
要件を満たす65歳以上への定年の引上げ、又は定年の定めの廃止を実施し、その雇用する55歳以上65歳未満の高年齢者に対して定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等、雇用機会の確保・職業生活の充実に資することを目的とした研修等を実施した中小企業事業主に対して助成
企業規模 概 略 支 給 額
1人~300人 定年引上げ・定年廃止をした後1年以内に要件を満たす研修等を実施した場合 要件に該当する研修費用等の1/2
上限額は、1人あたり 5万円
1社あたり250万円
助成金の具体的な受給要件等につきましては、別途お問い合せください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年10月23日 火曜日
平成19年10月23日(第204号)...損益分岐点って何?
損益分岐点という言葉を知らない人はいないと思います。ですが、本当にその内容を知って日常の事業の中で使っていますか?
今回は超簡単損益分岐点の話をします。
さて、あなたは念願がかなって、梅田のど真ん中に5坪の電子辞書専門の販売店を開くことができました。家賃は月額20万円、いろんな電子辞書を売っていますがどれも販売価格は1台5万円、仕入原価は3万円です。
さあ、何台売ったら家賃を払えるでしょう。また、そのときの売上高はHow much?
簡単ですね。1台売ると2万円稼げます。それで20万円の家賃のうち2万円分がまかなえました。こうやって順番に1台ずつ上乗せしていくと20万円の家賃をまかなうのに10台売ればいいことが分かりますね。これで解答です。10台売れば家賃が稼げます。その時の売上高はそう、50万円ですね。
試算してみましょう。
10台売って 売上高 50万円
原価 30万円
販売利益 20万円
家賃 20万円
利益 0万円
これで損益分岐点の売上が計算できたことになります。損益分岐点売上は50万円が正解です。
このケースでは売上に比例して発生する原価は仕入原価の1台3万円ですね。こうして売上に比例して増加する原価を変動費と呼びます。そして、売上高からこの変動費を差引いた残りを限界利益と呼んでいます。このケースから、簡単にこの限界利益で家賃という固定費をまかなうと損益分岐点に達するということが分かっていただけたと思います。
このことをもっと簡単に表現すると、限界利益を売上高で割った比率を限界利益率といいます。このケースでは2万円÷5万円=40%が限界利益率になります。損益分岐点は、この限界利益で固定費を回収すればいいわけですから、
固定費 20万円÷0.4=50万円 で損益分岐点が計算できることになります。
簡単でしょう。これであなたの会社の損益分岐点が計算できましたね。さあ、赤字の会社はいくら売れば利益が出せるようになるか、今すぐ計算してみましょう。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年10月 8日 月曜日
平成19年10月8日(第203号)...外国人雇用状況の届出が必要になりました
10月1日以降、外国人(特別永住者を除く。)の雇入れ・離職の際に、その氏名や在留資格等の公共職業安定所への届出が義務化されました。これまでは、従業員50人以上の規模の事業所のみを対象に外国人雇用状況を1年に1回報告する制度がありましたが、今月以降は従業員規模を問わず外国人1人以上を雇用する全事業所が報告対象となりました。
雇用保険の被保険者である外国人の場合は、雇用保険被保険者資格取得届または喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出なければなりません。届出期限は、雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内です。
雇用保険被保険者ではない外国人の場合は、所定の届出様式に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載の上、届出が必要です。届出期限は、雇入れ・離職の場合ともに翌月末日までとなります。
なお、今月1日時点で現に雇い入れている外国人の場合は、平成20年10月1日までに所定の届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を届け出る必要があります(それまでに離職する場合は上記の方法での届け出ることになります)。
募集・採用にかかる年齢制限禁止の義務化
10月1日から労働者の募集・採用時の年齢制限禁止の例外がさらにきびしくなり、次のとおり例外の範囲がより限定されました。求人票作成の際等ご注意ください。
例外が認められるのは、(1)法令の規定で年齢制限がある場合、(2)芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合、(3)60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限定)の対象者に限定して募集・採用する場合、(4)定年年齢未満の労働者、(長期勤続によるキャリア形成を図る観点から)若年者等、(技能・ノウハウの継承の観点から)特定の職種で労働者数が相当程度少ない年齢層を期間の定めのない契約で募集・採用する場合に限られます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年9月23日 日曜日
平成19年9月23日(第202号)...~従来型組織から成果を上げる組織へ~
常に変革の時代ですが、現場の声を吸い上げるための組織のあり方にも
変化が求められます
従来型組織→成果を上げる組織へ
・言う→聴くスタイルへ
・問いつめる→問いかける
・先輩が後輩に話しかけやすい雰囲気→後輩が先輩に話しかけやすい雰囲気
・不信→信頼
・上下関係→フラット
・押さえつけ→協働
・効率化→活性化・創造化
・マイナス採点→加点採点
・うわべで判断→本質判断(行動・言葉・本音・内容・・・)
根本を認識・・・結果から原因を考える
・集団への一律対応→個別対応
・なりゆき→目的志向・ビジョン作り(将来のあるべき姿をしっかり認識し共有)
・あいまいな指示→正確でわかりやすい指示
・協力の手段:報告・連絡・相談の回数は少ない
→メンバーに不安を与えない・報告・連絡・相談を徹底する
・モチベーションを下げる→グループに活力を与える
・主観的に対応する→客観的に対応する
・真似させる→創造させる
・できないと攻撃→できる手段を一緒に考え本人に問う
・システム作り→人作り
(スマイルグループ 接客販売インストラクター)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年9月 8日 土曜日
平成19年9月8日(第201号)...失業給付の受給要件が改正されます
10月1日以降に退職される方につきまして、失業給付の基本手当(いわゆる失業保険)の受給要件が変更されます。今までは半年間働けば受給できましたが、近年の離職率の高さ、特に若者がすぐに離職してしまう事から、原則として1年以上働かないと受給できないように改正されました。以下に改正前と、改正後の受給要件を記載します。
~平成19年9月30日までに退職される方~
<一般被保険者の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヵ月以上あること。
<短時間労働被保険者の場合>
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヵ月以上あること。
~平成19年10月1日以降に退職される方~
これまでの週所定労働時間による被保険者区分(一般被保険者・短時間労働者)により異なっていた雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。
<原則>
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヵ月以上あること。
<倒産、解雇等による離職の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヵ月以上あること。
これから退職される方、特に9月か10月に退職を考えておられる従業員の方がいらっしゃいましたら、上記の点を踏まえ説明をお願いします。9月中の退職なら、失業給付の受給がきるが、10月以降に退職した場合に受給できなくなる可能性がありますのでご注意ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年8月23日 木曜日
平成19年8月23日(第200号)...使用人賞与の損金算入時期
法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。(使用人兼務役員に対する使用人分賞与を含む。)
1.労働協約または就業規則において定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)・・・その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
2.次に掲げる要件のすべてを満たす賞与・・・使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
(1)その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(2)(1)の通知をした金額を通知したすべての使用人に対し、その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に支払っていること。
(3)その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
3.上記1及び2に掲げる賞与以外の賞与・・・その支払をした日の属する事業年度
決算賞与として支給する場合に、その決算賞与に係る事業年度の損金とするためには、2の全ての要件に該当する必要があります。また、この場合にその2の要件を満たす賞与に係る社会保険料の会社負担分については、賞与の損金算入時期と異なり、賞与を実際に支給した日の属する事業年度の損金になります。
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年8月22日 水曜日
平成19年8月22日(臨時号2)...パートタイム労働法の改正
平成20年4月1日施行予定の改正パートタイム労働法の概要は次のとおりです。
1.労働条件の文書交付・説明義務
労働条件を明示した文書の交付等を事業主に義務付ける(違反の場合は過料あり)など。
2.均衡のとれた待遇の確保の促進
(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
(1)通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いを禁止する。
次の3要件を全て満たす短時間労働者
[1]業務の内容と責任の程度(以下「職務の内容」)が通常の労働者と同じである。
[2]職務の内容及び配置が通常の労働者と同じ範囲で変更される見込みがある。
[3]雇用契約期間に定めがない労働契約を締結している(反復更新で期間に定めがな
い契約と同視することが社会通念上相当と認められる有期雇用契約も含む)。
(2)(1)以外の短時間労働者については、能力や経験などを勘案して賃金(通勤手当、退職手当を除く)を決定するよう努力義務を事業主に課す。
(3)通常の労働者が従事する職務遂行に必要な能力を与えるための教育訓練については、(1)[1]に該当する短時間労働者に対しても実施する義務を事業主に課す。上記以外の教育訓練についても、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、能力や経験などに応じて実施する努力義務を事業主に課す。
(4)通常の労働者に対して利用する機会を与える福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)を、短時間労働にも利用する機会を与えるよう配慮する義務を事業主に課す。
3.通常の労働者への転換の推進
以下のいずれかの措置を講じる義務を事業主に課す。
[1]通常の労働者の募集に関する情報を既に雇用している短時間労働者に提供する。
[2]通常の労働者を新たに配置する際に、応募の機会を短時間労働者にも与える。
[3]通常の労働者への転換のための制度(試験制度など)を設ける、など。
4.苦情処理・紛争解決援助
(1)事業主が上記1~3の措置事項、禁止事項に関する苦情の申出を受けた時は、自主的に解決するよう努力義務を課す。
(2)紛争が生じた際は、男女雇用機会均等法に規定する紛争解決援助(都道府県労働局長による紛争解決援助、機会均等調停会議の調停)と同様の仕組みにする。
5.事業主等支援の整備
短時間労働援助センター(現在、(財)21世紀職業財団が指定されている)の事業を見直す(事業主等に対する助成金支給業務に集中)。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年8月22日 水曜日
平成19年8月22日(臨時号)...産業カウンセラーの技法
二つの技法を職場の管理責任者研修に加えることを提案したいと思います。
(1)一つは、傾聴訓練の研修
カウンセリングの基礎理論と実習を実際に受ける(ロールプレイング)ことによって、最低限カウンセリング・マインドを身に付けていただくなら、職場のコミュニケーションの改善に役立つはずだからです。
(2)今一つは集団的討議に役立つはずのグループ・エンカウンターの研修。
エンカウンターは出会いの意。つまり、小グループ活動による「人間的出会い」を通じて参加者の変革を目指すものです。
(3)こうした研修は1日コースでも可能ですが、できれば1泊コースで実行できればよいと思います。そうすれば、(1)によって、相談をうけた場合の受け方に大きな効果を発揮するでしょう。ただ、それだけでは相談者と1対1の話し合いで終ってしまうので、組織的には直接に生かされにくいと思われます。そこで、相談にあった事例を中心にしてグループ・エンカウンターを職場でやってみる、あるいはテーマを決めず自由にいいたいことをいいあうことを通じて、職場の中に一体感が共有できることになるでしょう。
以上のような研修が社内に広がって行けば、職場が楽しくなり、コミュニケーションも豊かになるはずです。こうした研修を皆様の職場で行い協働していきたいと思います。
(スマイルグループ 産業カウンセラー)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年8月 8日 水曜日
平成19年8月8日(第199号)...リスクアセスメント
とにかく想定されたものより大きい地震が起こった、揺れの加速度は設計値の2倍以上に達したなどということは、最初の想定が間違っていたということになります。起こり得る事故を想定し、それによる被害状況を推定し、被害をゼロにするか少なくするような対策を考えて実施する一連の作業をリスクアセスメントと言います。
自社の事業場でどのような事故が起こる可能性があるのかを早速再検討しましょう。リスクアセスメントの実施手順は次のようになっています。これから何回かに分けて(連続ではありませんが、)それぞれの項目についてご説明します。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年7月23日 月曜日
平成19年7月23日(第198号)...住宅ローン減税と税源移譲の影響
住民税の税源移譲問題がクローズアップされています。税率改正により、ほとんどの方の場合、所得税が減税、住民税が増税となります。これに伴って従来から住宅ローン減税の適用を受けていた方のローン減税額が減ってしまうケースが生じるため、これに対応すべく、減額される部分の金額について、住民税から控除する仕組みが設けられました。
(1)所得税の住宅ローン減税額が減ってしまうケースとは?
住宅ローン減税の控除額は、借入金の年末残高×1%(又は0.5%)で計算されますが、控除されるのは、その方の所得税額が限度のため控除額が減ってしまう方が出てしまいます。
【例】課税所得180万円、住宅借入金残高1,500万円(控除率1%)である場合
<改正前> 所得税 18万円 - ローン控除15万円=税額 3万円
住民税 9万円 → 9万円
<改正後> 所得税 9万円 - ローン控除 9万円=税額 0万円
住民税 18万円 → 18万円
となって税率改正により、6万円が控除できなくなってしまいます。
(2)改正による不利益部分を住民税で控除を受けるための手続き
所得税の住宅ローン減税の適用を受けるためには、初年度は確定申告が必要で、2年目以降は給与所得者は年末調整で控除を受けることができます(それ以外の方は確定申告必要)。
では住民税で控除するケースはどうかというと、給与所得者であっても、改めて手続きが必要になります(年末調整時に自動精算はしてくれません)。具体的な方法はまだ明らかにされていませんが、確定申告期限(3月15日)までに市町村に申告をしなければいけないことになりそうです。この手続きは初年度だけでなく、毎年継続しなければなりません。
(3)平成19年以後に居住開始の場合の取り扱い
上記の経過措置は平成11年から平成18年までの間に居住を開始した場合に限って適用されます。平成19年以降に居住開始の場合には、この取り扱いはなく、次の通りとなります。
控除期間が原則の10年と特例の15年の2通りの方法が選択できますので、もし控除額が切り捨てになってしまうようでしたら、15年の方を選択すると良いでしょう。
年末残高限度額は、居住開始が平成19年は2,500万円、平成20年は2,000万円
原則 1年目~ 6年目 1% 7年目~10年目 0.5%
特例 1年目~10年目 0.6% 11年目~15年目 0.4%
※現行税制では、住宅ローン減税は平成20年までの時限措置となっています。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年7月23日 月曜日
平成19年7月8日(第197号)...3歳未満の子を養育する被保険者等への給付算定上の配慮措置
どんな措置なのか?
平成17年4月から実施されていますが、あまり知られていない、何度も提出を要するなど忘れやすい手続きで提出期限が2年以内であるため、あらためてご説明します。
3歳未満の子を養育する期間、勤務時間の短縮等により勤務継続する者について、子が生まれる前に比べ社会保険の標準報酬が下がった場合、被保険者本人からの申出により養育特例期間中は、支払う保険料は安いまま、将来の年金額の計算には、従前(こどもが生まれた月の前月時点)の標準報酬を下回る期間については、従前の標準報酬月額を標準報酬月額とみなします。
養育特例期間とは?
子の養育を開始した月から下記の終了要件のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までを給付算定上の標準報酬月額を配慮する期間とします。
・該当する子が3歳に到達 ・該当する子の死亡又は養育の終了
・厚生年金保険の被保険者資格を喪失 ・育児休業等の開始
・該当する子以外について養育特例期間の開始
従前標準報酬月額とは?
子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を従前標準報酬月額といいます。
ただし、子の養育開始月が厚生年金保険の被保険者でなかった場合は、開始前1年間に遡って被保険者であった直近の月の標準報酬月額を従前標準報酬月額とします。
みなし標準報酬月額とは?
標準報酬月額が従前標準報酬月額を下回る月について、従前標準報酬月額を給付算定上の標準報酬月額とみなします。
手続きは?
「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」という手続き用紙と、続柄がわかる(子との関係がわかる)戸籍抄本、世帯全部がわかる住民票等の添付書類とともに提出します。
こんなときも忘れずに!!
男性・女性を問いません。転職等により標準報酬月額が1等級でも低下した場合も該当します。ただし、本人からの申出によるものですので、会社に必ず申出してください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年6月23日 土曜日
平成19年6月23日(第196号)...何故、残業が減らないのか
多くの会社で残業しているのに利益が出ていない会社を見かける。何故だろう?残業をして、利益が出なければ給料も上がらず、もちろん従業員のモラールも下がってくる。その原因は、どうも次の3つに集約されそうです。
1.コミュニケーションの悪さ
クライアントと営業、営業と製造、製造の中でも工程間のコミュニケーションがうまくできていないために、ニーズが伝わっていない、指示が十分でない、思い込みで仕事をしている。そのため、後で、やった仕事のやり直しをしているなんてケースはありませんか。各部署が自分の部署の部分最適だけ考えて仕事をしていると、こんな現象が起こってくる。私はこれを「蛸壺理論」と勝手に呼んでいる。要は、自分の仕事しか見えてなく、全体最適に結びついていないからミスややり直し作業が発生するのである。それとコミュニケーションで大切なことは言葉の定義である。同じ言葉を使っても指示した側と受けた側でイメージしたものが違えば当然に結果は違ってくる。たった5分の出来上がりのイメージの確認でこうしたミスは防ぐことができる。
2.知識、スキル不足
次が知識、スキル不足である。知らないことはできない。当たり前のことである。「魚を3枚におろす」ということを例に出して説明してみよう。先ず、魚を3枚におろすってことを知らなければ手をつけられないし、知っていても出刃包丁を持って捌いたことがなければなかなかきれいに捌けない。このことは仕事全般について言える。ある会社で経理規程を作ってくださいといったら闇雲のいろんな規程集から寄せ集めて作ってくれたのは良いが、全く中身がごたごたで使いものにならなかった。少なくとも経理規程はどんな規程で何を織り込まないといけないかを十分事前に知識をもって取り掛かってくれればこんな無駄な作業はしなくても済んだはずである。
3.方針、ルールが明確でないか、あっても朝礼暮改
方針やルールが明確でないと、各自が自分の方針やルールを作って勝手に動きはじめる。下手をするとベクトルが反対向きになっていて、お互いの成果を引っ張りあって、マイナスに働くことだってある。そこまで行かなくても重複した作業や、必要な作業が漏れたりすることもよくあることである。また、よく方針を変更する会社、特に組織変更をよくする会社はそのたびに仕事の分掌が変わったり、今までやってきた仕事が無駄になるケースが多い。もっと簡単なケースを上げると、みんなが使うパンチやホッチキスを決まった場所におきましょうというルールだけでも結構探す手間が省けたり、余分なものを買わなくて済むことがある。大きな方針や小さなルールを決めて全員が守るようにすることで随分業務の効率はよくなるものである。
あなたの会社は全室禁煙でしょうか?その禁煙を経営者や管理者が自ら破っていませんか?こんな会社は要注意です。あなたが守らなくて誰が守るのですか!
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年6月 8日 金曜日
平成19年6月8日(第195号)...これからの法改正と就業規則
今春、国会は「労働法制国会」と言われるだけあって、先日成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律案」のほか、「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案」「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」「労働基準法の一部を改正する法律案」「最低賃金法の一部を改正する法律案」など、雇用や労働時間、賃金などに関連する法案が、厚生労働省より多数提出されています。
今後の動向が注目されている法案のひとつに、「労働契約法案」があります。同法案で最も問題視されているのが、就業規則の改定で労働条件の内容を変更できるとする新しいルールの法則化です。
労働契約法案に記載されている「労働契約の内容と変更(第8条から第11条までの関係)」では、「労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」と原則を述べています。そのうえで、変更後の就業規則を労働者に周知させていた場合で、労働条件の変更等が合理的であるとき(後述)は、「変更後の就業規則に定めるところによるものとする」とする、就業規則の不利益変更における例外規定を明記しています。
現行制度では、必要性に基づいた合理的なものに限って労働条件の変更を有効とする、就業規則の不利益変更法理が成立していましたから、労使それぞれに大きなインパクトを与える内容です。
「合理的」の判断基準
労働条件変更の要件について同法案10条では、次の4点を判断要素とする、としています。
(1)労働者の受ける不利益の程度
(2)労働条件の変更の必要性
(3)変更後の就業規則の内容の相当性
(4)労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情
就業規則は、いわば会社の憲法です。就業規則にも「改憲」ルールができるのかどうか、今後もしっかり注目していくべきでしょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年5月23日 水曜日
平成19年5月23日(第194号)...~社内全員で、お客様を温かく迎えましょう~
社内にお越しくださったお客様に、スタッフ全員でご挨拶をしましょう
【気をつけましょう】
・小さい暗い声での挨拶(挨拶をしているのかわかりにくい)
・お客様が来られているのに、全員で挨拶していない(一部の人しか挨拶していない)
・お客様が自分の机の前を通っているのに、知らぬ顔をして挨拶しない(無視)
自分の仕事に没頭しすぎて、作業しながらの挨拶、下を向いて声だけの挨拶
(作業の手を止めて挨拶していない・お客様を見て挨拶していない)
→「暗い会社だ」「お客様を大切にしていない会社だ」と思われる場合がある
【心得】
・お客様は、時間を割き、交通費を支払って、わざわざ御社に足を運んで下さっています。また、同業他社が多い中、御社を選んでお越し下さいました。常にお客様一人一人を大切にし、感謝の気持ちを忘れないようにしましょう
・日々、お客様に満足していただけるサービスが提供できるよう自分を磨いておきましょう
・社内全体を「清潔」にしておきましょう
・スタッフ全員で、お客様を温かく迎え入れるような雰囲気づくりに努めましょう
→お客様が来られたことに気づいたら、お客様を見て、社内全員で、
明るく元気にご挨拶をしましょう
【参考】他企業の取り組み
事例1.一人のスタッフがお客様が来られたことに気がついて
「いらっしゃいませ。」と明るく元気に笑顔で挨拶→他のスタッフもお客様を見て
「いらっしゃいませ。」と明るく元気で笑顔の挨拶が続く
事例2.お客様が来られたことに気づくと、事務職員が全員立って、お客様を見て、
笑顔で明るく挨拶をしている
お客様の心理:「 明るく元気な会社だな。」「社内が明るくて、気持ちいいな。」
→会社やスタッフのカラーを読む(関連:好感度)
(スマイルグループ 接客販売インストラクター)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年4月23日 月曜日
平成19年4月23日(第192号)...企業の子育て支援に係る特例
平成19年度の税制改正で、子育て・再チャレンジ支援税制の1つとして、「企業の子育て支援に係る特例」ができました。
適用対象の法人が、一定の方法によって事業所内託児施設を設置した場合には、その託児施
設の設備等に関して割増償却を認めて、税制面から子育てを支援するものです。
対象者:青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法の規定に基づき同法に規
定する一般事業主行動計画(託児施設の設置及び運営に関する事項が定められているも
のに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(同法の中小事業主以外の一般事業主
にあっては、一定の要件を満たすものに限る。)
適用要件:平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に当該一般事業主行動計
画に従って託児施設の取得等をし、かつ、適用事業年度終了の日において当該託児施設
が事業所内託児施設(注)に該当するものとして証明がされた場合には、当該託児施設
及びこれと同時に設置する遊戯具その他の一定の器具備品については、5年間、普通償
却限度額の100分の20(中小事業主については、100分の30)の割増償却がで
きることとする。
(注)事業所内託児施設の要件
定員が10人以上(中小企業にあっては、6人以上)で、託児施設の利用者の半数以上
が、託児施設設置企業の従業員の子であること。
子育て支援について事業主の方に支給される「育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・ベビーシッター費用等補助コース)」というのもあります。
労働者が育児・介護サービスを利用する際に、その費用の全部又は一部を補助する措置に関
する制度を設け、その制度に基づき費用を補助した事業主及び育児・介護サービスの提供を行う者と契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置を実施する事業主に対して支給されます。これにより、育児や介護を行う労働者の雇用継続を図ることを目的としています。
受給できる額: 中小企業の事業主が負担した額の2分の1に相当する額
中小企業事業主以外の事業主が負担した額の3分の1に相当する額
支給期間 : 当該措置の実施を開始した日から起算して5年が限度
また、一般事業主行動計画の策定・届出をした場合には初年度に30万~40万円が支給されます。
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年4月 8日 日曜日
平成19年4月8日(第191号)...裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)について
ADRとは?
ADR法の施行に伴い「かいけつサポート」という愛称とロゴマークが制定されました。トラブルの解決をサポートするサービスであることをわかりやすく表したとのことです。
「裁判外紛争解決手続き」はADR(Alternative Dispute Solution)とも呼ばれますが、仲裁、調停、あっせんなどの、裁判によらない紛争解決方法を広く指すものです。例えば、裁判所において行われている民事調停や家事調停もこれに含まれますし、行政機関(例えば労働局、建設工事紛争審査会、公害等調整委員会など)が行う仲裁、調停、あっせんの手続や、弁護士会、社団法人その他の民間団体が行うこれらの手続もすべて裁判外紛争解決手続に含まれます。
ADR機関はわが国でも交通事故、建築、個別労働関係などの個別の分野や、弁護士会が設立している仲裁センターなどがありましたが、今年4月1日から施行されたADR法によって、ADRの範囲を拡大して、利用しやすくするための制度が導入されました。
弁護士又は弁護士法人でなくても、法務大臣の認証を受けた「認証紛争解決事業者」は、報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができるようになりました。
認証紛争解決事業者とは?
認定司法書士、弁理士、特定社会保険労務士、土地家屋調査士には一定の範囲で、単独又は弁護士と共同で和解の仲介を行うことができるようになりましたので、個別或いは団体で法務大臣の認証を受けたADR機関が新しく誕生してくることになります。
認証紛争解決事業者は
(1)認証業務であることを独占して表示することができます。
(2)認証紛争解決事業者は弁護士又は弁護士法人でなくても、報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができます。
(3)認証紛争解決事業者の行う和解の仲介の手続における請求により、時効を中断させることができます。
(4)認証紛争解決事業者の行う和解の仲介の手続と訴訟が並行している場合に、裁判所の判断により訴訟手続を中止することができます。
一方、認証紛争解決事業者は、業務の内容や実施方法に関する一定の時効を事務所に掲示することや、利用者に対して実施者に関することは手続の進め方を書面で説明することなどが義務付けられます。
当事務所も特定社会保険労務士として、あっせん等のADRにかかわることができます。ぜひご利用ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年4月 1日 日曜日
平成19年4月1日(臨時号)...小売等役務商標制度のお知らせ
商標法の一部が改正され、小売業等も平成19年4月1日から役務商標登録が新たに認められました。4月1日から小売等役務に関する商標登録の出願の受付が開始されています。(平成19年4月1日~6月30日までは同時出願の特例があります。)
今回、導入された役務商標とは、小売業者等が使用する商標について、事業者の利便性向上や国際的制度調和のため、保護される制度です。
たとえば、店名を既に商標登録している場合でも、役務商標の分類でない場合は、役務商標も必ず登録しておく必要があります。
何故なら、店名が役務商標の分類で登録されていなくても商標登録さえされていれば他人は役務商標登録をできませんが、この場合店名は商標としては使用されていないこととなり、不使用取消請求され、その後その他人に商標及び役務商標を奪われてしまうからです。
ただ、商標の登録日付より先にこちらが使用している場合には、先使用権が認められ継続使用できますが、それはあくまでも登録日前の使用部分に限られ登録日以後の使用部分の拡大は商標権侵害となります。つまり、その商標を使っての新規出店や代理店の出店等拡大展開ができなくなります。
商標登録の防衛策
商標登録出願も不使用取消請求も特許庁に申請してみないことには分からない状況です。
何故なら商標登録出願が拒絶されても、拒絶理由を論破できれば登録されてしまうからです。そのためにも、商標は使用・不使用に関係なく登録できるので、現在は使用していなくても新規出店や商品名については、候補名をより多く登録しておくと安心でしょう。
なお、現在使用中のネーミング等について、商標権違反(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、法人の場合は1億5千万円以下の罰金)にならないように、同じ又は類似の登録商標を調査しておく必要があります。
商標登録等については、特許庁のホームページ(http://www.jpo.go.jp/)も参考としてください。
(スマイルグループ 企業存続担当者)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年3月23日 金曜日
平成19年3月23日(第190号)...平成19年度 不動産に関する税制改正のポイント
平成19年度の不動産に関する税制改正の概要をご紹介いたします。納税者にとって有利な改正項目については平成19年1月1日に遡って適用されるものもあります。
1.減価償却制度の見直し
【残存価額の廃止】
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産について、残存価額を廃止することとされました。この場合の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)の2.5倍した数とされます。
【償却可能限度額の廃止】
4月1日以後に取得をする減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとされました。なお、定率法を採用している場合には、一定期間を経過した段階で定額法に切り替えて減価償却費を計算し、耐用年数経過時点に1円まで償却できるよう調整を図ることとされています。
3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却ができることとされます。
2.住宅ローン控除制度の見直し
平成19年分より国税から地方税への税源移譲が行われることに伴い、中低所得者層において住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれない金額が生じることが想定されます。そのため、平成19・20年に居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例を創設することとし、現行制度との選択適用とすることとされました。この特例では、控除率を引き下げる代わりに控除年数を延ばす措置が講じられています。
具体的には、現行制度では平成19年に居住した場合は、1年目~6年目はローン残高の1.0%(適用ローン残高2,500万円まで、最高25万円)7年目~10年目はローン残高の0.5%(適用ローン残高2,500万円まで、最高12.5万円)を控除できたのが、新しく創設された措置では、1年目~10年目は0.6%(適用ローン残高2,500万円まで、最高15万円)11年目~15年目は0.4%(適用ローン残高、最高10万円)を控除できるようになりました。
同じように、平成20年に居住した場合にも、1年目~10年目は0.6%(適用ローン残高2,000万円まで、最高12万円)11年目~15年目は0.4%(適用ローン残高 2,000万円まで、最高8万円)を控除できるようになりました。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年3月 8日 木曜日
平成19年3月8日(第189号)...平成19年4月からの社会保険改正について
(1)健康保険の標準報酬月額の上限・下限額が変更
現在の保険料や保険給付額の算出の基礎となる健康保険の標準報酬月額の上限・下限が、平成19年4月から下記に変更されます。改正に伴い、平成19年4月1日時点で、追加された等級に該当する被保険者については、平成19年4月分保険料(5月末納付分)から変更されます。保険料変更となる被保険者については、4月に社会保険事務所から事業所へ通知される予定です。
改正前(全39等級) 98,000円 ~ 980,000円
改正後(全47等級) 58,000円 ~1,210,000円
※厚生年金保険は現行のまま、(全30等級) 98,000円から 620,000円です。
(2)健康保険の標準賞与額の上限の改正
賞与支給の際は、支給額の1,000円未満を切捨てた額に保険料率をかけて計算することになっており、標準賞与額の上限は1ヵ月あたり200万円でしたが、改正により平成19年4月以降は、年度の累計額540万円を上限額とすることになりました。
※厚生年金保険は現行のまま、標準賞与額の上限は、1ヵ月あたり150万円です。
(3)傷病手当金・出産手当金の支給額が改正
現行では、支給対象となる1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていますが、改正に伴い、「標準報酬日額の3分の2に相当する額」に引き上げられます。
(4)任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金、資格喪失後の出産手当金が廃止
退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合に支給される出産手当金が廃止されます。出産育児一時金は従来どおり支給されます。
(5)高額療養費の現物給付化の実施
70歳未満の者の一医療機関における入院に係る高額療養費を現物給付化し、窓口での支払を自己負担限度額にとどめることになりました。(社会保険事務所にて事前申請・認定が必要です。)
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年2月23日 金曜日
平成19年2月23日(第188号)...内部統制システムって何?
2001年12月と2002年6月と相次いで起きた、エンロン事件、ワールドコムの二大粉飾決算・倒産事件を契機にアメリカでSOX法(靴下の話ではありませんよ、サーベインス、オックスレーという2人の法案提案者の名前を取って呼ばれるようになりました)という法律ができ、内部統制システムを強化し、粉飾を防止しようということになりました。日本でもカネボウの粉飾事件やライブドアの粉飾事件は記憶に新しいところだと思います。
そのSOX法が、日本にも上陸し、会社法、日本版SOX法(金融商品取引法)の中で内部統制システムの強化を取り入れることになり、平成19年4月以降開始する事業年度から適用されることになりました。そのため、株式公開企業は、右往左往しているのが現状です。
では、そもそも『内部統制システムって何?』ということになるわけですが、簡単に言うとリスクマネジメントの仕組みだと考えていいと思います。特に粉飾防止(財務報告の信頼性の確保と言っています)のための仕組みとその仕組みの有効性のチェックをしなさいということです。業務のプロセスの中には、適切な承認がなされていない、データの網羅性が確保されていない、会計基準が守られない、法律が守られない(サービス残業はそもそも法律違反)、業務効率が悪いといったようなことが内在しています。こうした、さまざまなリスクをコントロールするために、何か対策をしなさいというのが内部統制システムの話です。そんなに簡単なものかということですが、専門的にいうと複雑になりますので、大雑把にこんなとらまえ方をしていただけるとわかりやすいと思います。
では、中小企業には関係ないのか、と言うとそうではありません。リスクなんて中小企業の方がもっと多いので、中小企業でも内部統制システムは必要ですね。早い話、金庫を預かっている人は、社長が一番信頼されている人ではないですか。これすなわち内部統制システムです。大会社は、法律で"つくりなさい"と強制されているので大変なだけです。特に、日本人が一番苦手な「文書化する」っていう作業が膨大になる。これが、大企業を悩ましている原因です。
今後内部統制システムを体系化していくことが急務になりますね。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年2月 8日 木曜日
平成19年2月8日(第187号)...パワハラ~職場における人格侵害行為
パワーハラスメントを略して「パワハラ」といいます。パワーハラスメントという言葉は造語で、「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること」と定義されています。ボスハラスメント(ボスハラ)ともいわれています。これらの言葉は、職場における人格的利益の侵害を捉えたものです(人格的利益=身体的自由、自己決定、名誉、プライバシーなど)。
職場において人格侵害行為がなされた場合、行為をした個人にとどまらず、企業が使用者として、また安全配慮を怠ったとして責任を追求される場合があります。
上司が「おまえは馬鹿か。馬鹿は馬鹿なりの仕事をしろ」「帰れ、橋の下でホームレスをやった方がいい」「おい、リストラ」と呼ぶ、従業員全員のいる朝礼で「仕事の遅い人が来ました」というなど屈辱的な取り扱いを続け、さらに暴力を振るって怪我を負わせた事案について上司と企業に損害賠償責任を認めた判例があります。
現在、具体的に問題化している企業はそう多くないかもしれません。しかし、最近は権利意識の高まりを背景に、心身にわたって深刻な被害が生じているケースが取り上げられ、当事者から問題を積極的に訴えることが増えています。いったん訴訟等になれば企業イメージが著しく低下することは避けられません。そもそもこのような行為が横行しているようでは、従業員の士気も上がらず、人材の定着も見込めません。効率性の点からいっても優先して対策を講じることが肝要です。
具体的にどのような対策を講じるかについては、(平成10年労働省告示第20号参照)
(1)企業の方針を明確にし、従業員に周知する。研修・講習を行う。
(2)相談・苦情処理制度を設ける。
(3)申出に対しては迅速に処理担当者が直接事実を確認する。
(4)侵害行為をした者に対しては配置転換や就業規則に基づく毅然とした対応を取る。
(5)申し出た者のプライバシーに配慮し、申し出たことを理由とする不利益取り扱いをしない。を主なポイントと考え、セクシュアルハラスメントに対する対策をヒントにすればよいでしょう。
パワハラという言葉からは、上司と部下の関係が想起されますが、同様の問題は同僚同士でも発生します(いじめ)。職場における人格侵害行為の問題について、幅広く検討しておくことが求められます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年1月23日 火曜日
平成19年1月23日(第186号)...チームワークを発揮しよう
◆チームワークを発揮するためには日常の人間関係が大切
1.理念・目的・目標を確認する
2.働く価値を共有し、役割分担と責任を明確にする
3.声かけ等コミュニケーションを密にとる
4.ルールを守りながら、お互いを気にかける
◆チームワークが悪化する原因
1.無関心
2.ルール・マナー違反
3.スタンドプレー
4.問題点抽出に対し、人を攻め、改善策を提案しない
◆「あなたと一緒に働きたい・・・」と思われる人になろう
1.自分から心を開き、相手を尊重する
2.人の悪口・陰口を言わない・腹を立てない
3.問題点があれば、解決策を提案する
4.嫌なムードを作らない
5.心を広く持つ
6.自分から笑顔で挨拶する
7.誠実に接する
8.ほめ上手になる
9.時間を守る
10.報告・連絡・相談をする
11.「熱意」「やる気」を持って本気で仕事に取り組む
(スマイルグループ 接客販売インストラクター)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年1月 8日 月曜日
平成19年1月8日(第185号)...売れるHPの秘密とは!(2)
広告・HP等すべてのことに言えますが、よく売れているセールスレターには、多くの場合共通点があります。それさえ知っていれば、ある程度のセールスレターは書けるようになります。そこで、誰でもある程度のセールスレターが、書けるようになるヒントをお伝えしたいと思います。
売れる文章を書く上で、一番参考にしていただきたいのが、テレビショッピングです。実は、テレビショッピングの構成をそのまま真似するだけで、ある程度のセールスレターが書けるようになります。その手順は次のとおりです。
(1)問題点の提示 (2)それに対する共感
(3)問題点の解決方法の提示 (4)お客様にとってもらいたい行動の提示
この(1)~(4)の手順で文章を構成すると、ある程度、反応率を上げることができます。
また、最近ヤフーの検索システムが変更され、HPでの集客が、思うようにできなくなったのをご存知ですか?HPから集客している場合、検索順位が下がってしまうだけで、問い合わせがいっきに減少し、売上にも大きな影響があります。
実は、私もHPだけで集客しておりまして、検索順位の変動は、まさに死活問題です。検索順位が3位以下になったため、売上が一気に半分以下になってしまったという事を経験しております。そのため、高いお金を払って、ヤフーのディレクトリー登録を申請したり、SEOの業者に外注したりしていました。それをすれば、上位に表示されるのですが、早くも1週間後に大きく順位が落ち込んでしまうことが、頻繁におこります。PC画面に向かって、「何故なんだー」と叫んでしまうこともしばしば・・・。皆さんも、このような経験をされた事があるのではないでしょうか?
しかし、ある事を利用するようになって、私はこの問題から開放されたのです。その方法を使えば、確実に一番初めの検索画面で、しかも一番上に表示されるようになります。その方法とは、キーワード広告です。
このキーワード広告とは、ワンクリックあたりの単価を設定し、そのキーワードに対する広告の入札を行うというものです。これを使えば、ヤフーの検索結果の上に、スポンサーサイトとして表示されます。つまり、狙っているキーワードの、検索順位1位のサイトより上に、表示されるようになるのです。ネットの世界では、上に表示されるほど、クリック率が上るというデータがあります。つまり、一定のお金を支払うだけで、確実に見込み客を集めてくることができるのです。これを利用することによりまして、おかげさまで、安定した売上を確保できるようになりました。これを知らないのは大きな損です。皆様にも、是非利用していただきたいと思います。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年12月23日 土曜日
平成18年12月23日(第184号)...平成19年度の税制改正大綱
12月15日に平成19年度税制改正大綱が決定されました。主なものは、次のとおりです。
1.減価償却制度の見直し
平成19年4月1日以降取得する減価償却資産について、一度に償却できる金額が上がります。例えば耐用年数5年の場合、定額法の償却率は0.18(0.9×0.2)、定率法の償却率は0.369ですが、改正後の定額法は0.2に、定率法は0.5になるため、減価償却費が従前より多く計算されます。
また償却可能限度額も今までは取得価額の5%までが上限でしたが、今後は1円まで償却することが可能となります。つまり、100万円のものなら今までは95万円までしか経費にならなかったのですが、改正後は999,999円までを経費とすることができます。
2.留保金課税制度の適用除外
多額の利益を出している会社が配当などをせずに内部留保していると上乗せで税金が取られてしまう留保金課税について、資本金1億円以下の会社は適用から除外されます。平成19年4月1日以降開始事業年度から適用されます。
3.特殊支配同族会社
特殊支配同族会社に係る役員給与損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を800万円から1,600万円に引き上げます。現行では主催役員給与控除前の会社利益が800万円という基準でしたが、改正後は倍の1,600万円となります。平成19年4月1日以降開始事業年度から適用されます。
4.ファイナンス・リース
賃貸借取引とされている所有権移転外ファイナンス・リース取引について、全て売買取引とされます。今まで支払時にリース料と経理するだけだったものを、リース開始時にリース物件を購入したものとして資産計上し、減価償却費を計算する必要があります。平成20年4月1日以降に締結するリース取引から適用されます。
5.相続時精算課税制度
中小オーナー経営者が自社株式を子供に贈与(一定の要件を満たす場合)する際の相続時精算課税制度につき、贈与者の年齢要件を60歳に引き下げ、非課税枠が3,000万円になります。 (スマイルグループ 税務担当)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年12月 8日 金曜日
平成18年12月8日(第183号)...安全配慮義務
事業者は労働者(公務員を含む)の生命、身体、健康の安全を保護すべき法的な義務がある、というのがいわゆる「安全配慮義務」です。メンタルヘルスの分野でも、電通の過労自殺裁判で明示されています。これに違反して労働者の生命、身体、健康の安全を損なえば損害賠償ということになります。しかも最高裁は「危険が予見可能である限りは、事業主は具体的な結果を回避する措置を講じなければならない義務」までも求めています。これは事故だけでなく病気もあてはまります。判例を見てみましょう。
大石塗装・鹿島建設事件(最高裁 昭和55年12月18日)
転炉工場の鉄骨塗装作業中に地上31メートルから墜落即死した作業員の親族が、作業員の属していた会社と、その会社に作業を下請けさせていた会社を債務不履行もしくは不法行為に基づく賠償を請求した事件です。会社が使用を命じていた命綱を、作業者が使用していなかった重大な落ち度があったとして、第1審では賠償が否定されました。しかし、控訴審では使用者側に5割の責任があるとされました。
最高裁では、下請け会社と、元請け会社の双方に安全配慮義務違反があったと認められ、5割の限度での賠償を命じる判決がありました。
電通事件(最高裁平成12年3月24日)
電通の社員が過重労働のために健康状態が次第に悪化し、平成3年8月、上司も気付く異常な言動を示して帰宅した後、翌朝自殺したという事件です。
平成8年3月の第1審では、「常軌を逸した長時間労働」による過度の心身の疲労状態と、うつ病及びうつ病と自殺との因果関係を肯定し、上司が労働者の状態を認識しつつも具体的措置をとらなかったことに安全配慮義務不履行の過失があるとして使用者責任を認め、約1億2600万円の支払いを命じました。
この裁判は、翌平成9年東京高裁で3割減額する判決が出ましたが、さらに平成12年最高裁でこの3割減額の判断が差し戻され、結局会社が1億6800万円を遺族に支払うことで和解が成立しています。当時、マスコミで大きく取り上げられたことを覚えておいでの方も多いでしょう。
およそ危険が予測可能な場合は、万全の措置を講じる「安全配慮義務」が事業者に求められるようになってきています。ケガ・病気だけではなく、過重労働等による精神的な事故にもご注意ください。 (スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年11月23日 木曜日
平成18年11月23日(第182号)...「事業承継3つの方法」のメリット・デメリット
このたび中小企業庁より「中小企業の円滑な事業承継のための手引き」が発行されましたのでご紹介いたします。下記をご確認のうえ、十分な検討を実施したいものです。
親族内承継(身内への承継)
メリット:1)一般的に、内外の関係者から心情的に受け入れられやすい。(従来は身内
への承継が一般的だったため)
2)後継者を早期に決定し、後継者教育等のための長期の準備期間を確保することも可能。
3)相続等により財産や株式を後継者に移転できるため、所有と経営の分離を回避できる可能性が高い。
デメリット:1)親族内に、経営の資質と意欲をあわせもつ後継者候補がいるとは限らない。(世襲にこだわると、結果として会社経営が濁ることもある。)
2)相続人が複数いる場合、後継者の決定や経営権の集中が難しい。(不公平感をともなう後継者以外の相続人への配慮が必要となる。)
従業員等への承継(社内人材への承継)
メリット:1)親族内だけでなく、会社の内外から広く候補者を求めることができるた
め次世代の経営に、ある程度の選択肢(選択の幅)を持つことができる。
2)特に社内で長期間勤務している従業員に承継する場合は、会社に対する愛着心などが存在するため、経営の一体性を保ちやすい。
デメリット:1)親族内承継の場合以上に、後継者候補が経営への強い意思を有していることが重要となるが、必ずしも適任者が存在するとはいえない。
2)後継者候補において、事業承継のための株式購入に必要な資金力がない場合が多い。
3)個人債務保証の引継ぎなどの問題が多い。
M&A(第三者への承継)
メリット:1)身近に後継者として適任な者がいない場合でも、広く候補者を外部に求
めることができる。
2)現経営者が会社売却の利益を獲得できる。
デメリット:1)希望の条件(従業員の雇用、価格など)を満たす買い手を見つけることが非常に困難である。
2)経営の一体性を保つことが困難である。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年11月 8日 水曜日
平成18年11月8日(第181号)...労働者の業務遂行上の過失と損害賠償請求
労働者が仕事を遂行している途中で、ミスを犯して会社に損害を与えたり、又は第三者に損害を与えて、会社が肩代わりして支払った賠償額を労働者に求償する場合があります。会社が労働者に対して取り得る措置としては、人事上の措置や損害賠償を請求する等が一般的に考えられます。
1.会社が取り得る人事上の措置
会社は、就業規則で定めた譴責、戒告、減給、出勤停止等の懲戒処分をしたり、降格や配置転換、解雇(場合によっては懲戒解雇)等の人事上の措置を取ることができます。
例えば、軽微な過失による事故に対し、解雇等の重大な処分をすることは問題がありますが、そのミスが労働者の能力や適格性の欠如による場合には、解雇や契約更新拒否等の措置も理由があると判断されます。ただし、解雇や契約更新拒否等は労働者に与える不利益が大きいので、労働者の犯したミスと不利益が均衡しているか、会社がミスを回避するための安全対策や教育訓練をどの程度講じたか等を考慮して、判断する必要があります。
2.損害賠償の請求又は求償
労働者が仕事を行っている時にミスを犯す等、労働契約上の債務不履行があった場合に、実際の損害発生の有無や損害額にかかわらず、一定の違約金を定めたり、賠償額をあらかじめ定めておくことは、労働基準法第16条で禁止されています。ただし、労働者のミスによって具体的に会社に損害を与えた場合に、会社がその損害額を労働者に請求することは禁止されていません。労働者に故意や過失があれば、債務不履行又は不法行為として、損害賠償責任が発生するのが原則です。
しかし、労働者が労働を遂行する過程で通常発生する事が予測されるミス(軽微な過失)の場合は「損害の公平な分担」という信義則上の基本理念から、損害賠償責任を認めることは難しいと言えます。この「損害の公平な分担」は、労働者の業務遂行は会社が決定しており、そこから発生することが通常予想されるリスクは、会社が負担することが公平であるという基本理念です。判例は、労働者に対する損害賠償を認めないものや労働者が第三者に与えた損害を会社が肩代わりして支払った場合に、会社の労働者に対する求償権の行使を認めないのが一般的と言えます。
ただし、労働者が故意や重大な過失で会社に損害を与えた場合は、上記の「損害の公平な分担」という基本理念を適用する余地はありませんので、会社は全ての損害について請求することができます。
3.確認しましょう
□就業規則に、懲戒処分に関する規定はありますか。
□その懲戒規定の内容は、犯したミスと処分内容の均衡がとれていますか。
□過度なノルマ、過重な労働等を課さないよう事故防止策を講じていますか。
□日頃から、機械の点検や安全対策への安全教育に力を入れていますか。
□任意保険等に加入するなど、リスクの分散をしていますか。
就業規則の策定・見直しに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年10月23日 月曜日
平成18年10月23日(第180号)...法人が行なうリース取引に関する取扱い
<原則的な取扱い>
法人が賃貸借(リース)取引により固定資産を賃借した場合には、その賃借料は、原則として、賃借期間の経過に応じて損金の額に算入されます。
<例外1>・・・売買として取扱う場合
ただし、その賃貸借取引が、法人税法上のリース取引(注1)に該当し、かつ、一定の要件に当てはまるものについては資産の売買があったものとして取り扱われることになる。(注2)よって、この場合減価償却を通じて、固定資産の取得価額が損金に算入されていくことになる。
(注1)法人税法上のリース取引とは次の要件のすべてを満たすものをいう。
1)リース期間中の中途解約が禁止されているものであること又は中途解約をした場合には、未経過期間に対応するリース料の合計額のおおむね全部を支払うこととされているものなどであること(ノンキャンセラブル、フルペイアウト)
2) 賃借人がリ-ス資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつリース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること
(注2)法人税法上のリース取引のうち次のいずれかに当たるものは、賃貸借ではなく、リース資産の引渡しのときに売買があったものとして取り扱われる。
1)リース期間の終了時又は中途において、リース資産を無償又は名目的な対価で譲り受けるもの
2)リース期間の終了時又は中途において、リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているもの
3)賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のように、リース資産がその賃借人のみによって使用されると見込まれるもの、又は建築用足場材のようにリース資産の識別ができないものを対象とするもの
4)リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べ相当の差異があるもので、賃貸人又は賃借人の法人税又は所得税の負担を著しく軽減すると認められるもの
<例外2>・・・金銭の貸付けとして取扱う場合
譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る)を条件に資産を売却した場合(いわゆるリースバック)において、その賃借に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その資産の譲渡はなかったものとし、かつ譲受人から譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして取扱う。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年10月 8日 日曜日
平成18年10月8日(第179号)...医療保険制度の改正
本年6月の国会で、健康保険法等の改正が行われ、医療保険制度のうち、次の各給付が平成18年10月から変更されることになりました。
1.高額療養費の本人負担額の引き上げ
今後の変更も、従来と同様、70歳未満、70歳以上、特定疾患者という三つの枠組のままで、そのうち所得のレベルに応じ限度額が定められるのも従来どおりです。
基本的には、低位所得者は従前と変更なく、上位所得者(標準報酬53万円以上)や一般所得者は上限が引き上げられています。
(例:70歳以上の一般の者の外来・入院自己負担限度額 従前40,200円→44,400円)
2.出産(本人及び被扶養者の出産)
育児一時金 一児につき35万円(従前30万円)
3.埋葬料(本人及び被扶養者)
一律5万円(従前本人標準報酬1ヵ月分又は10万円のいずれか高い方、被扶養者 10万円)
4.70歳以上の者の療養給付本人負担分の変更
これも、現役並み所得者とされる、標準報酬月額28万円以上、あるいは年間課税所得145万円以上レベルの者は3割負担(従前2割)に変更になり、その他の所得レベル者は現行の1割負担のままです。
最低賃金の引き上げ
地域別最低賃金が平成18年10月1日(一部9月30日)から改定されました。
都道府県名 改定後 改定前
京都府 686円 682円
大阪府 712円 708円
滋賀県 662円 657円
兵庫県 683円 679円
奈良県 656円 652円
使用者は、この金額より低い金額で労働者(パートタイマー、アルバイトを含む。適用除外許可者除く)を使用することはできません。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年9月23日 土曜日
平成18年9月23日(第178号)...「京都のおもてなし」について
今回は、京都の「おもてなし」をご紹介いたします。「おもてなし」の要素には、今も昔も共通点が多数あります。
京都のおもてなし 「はんなり」...華やかさ、上品さ
老舗の料理店、旅館、お茶屋、古典の遊び...美しく遊ぶお客様たちに、勉励の「心」を発見させる。
もう一人の自分を見つけたような思いをさせることが可能なステージ。
おもてなしの構成
例:料理、舞妓と芸者、会話、茶の湯・華道・香合わせ等の芸能...美学
京ことば、やさしい言葉でコミュニケーションをとる。
お客様はグループでお越しになる場合とお一人でお越しの場合がある。
常連のお客様もいらっしゃれば、新規のお客様もいらっしゃる。
いずれも、京文化にふれ、楽しみ、感動していただく。
京都の空間
「京町家」...京都らしい生活の空間や時間をイメージ。
「ゆったり」「くつろぎ」「隠れ家的」「私だけの店」の趣。
京都ブランド
落ち着いた街並み空間に、品質を大事にする店がある。
最高のサービスを提供することで、地元住民や京都の訪問者をもてなす。
(スマイルグループ 接客販売インストラクター)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年9月 8日 金曜日
平成18年9月8日(第177号)...売れるHPの秘密とは!(1)
社長:「HPに100万円もかけたのに、全然問い合わせがないじゃないか!」
部下:「しかし、すごくいいHPに仕上がってますよ。さすがプロって感じですが・・」
社長:「まったく問い合わせが増えないのであれば、意味がないだろう!」
部下:「もう少し様子を見ましょう。HP作成のプロに頼んだのですから。」
御社では、こんな会話が繰り返されているのではないでしょうか?私の知る限りでは、多くのお客さんが同じ悩みをかかえておられました。実は、この会話の中に、この会社が陥った問題点が隠されているのです。この原因が何だかお分かりになりますか?
それはずばり、HP作成のプロに頼んだということだと言えます。なぜそれが問題点なのでしょうか?実は、HP作成のプロは、「あくまできれいなHPを作成するプロで、営業のプロでない」ことが多いからです。そういうHP作成のプロの場合は、問い合わせが増えるようにと考えてHPを作成しません。あくまで、発注者が満足するように、大企業が出しているようなデザインのHPを作ってしまうのです。
大企業のHPは、そのほとんどが商品や会社のイメージを高める目的で作成されています。したがって、すぐに問い合わせが増えるようなことはまったく考えていないのです。その証拠に、フラッシュを多用して、連絡先がわかりにくくなっています。これは、意図的に問い合わせの電話や、メールが来ないように設計されているのです。そのHPをまねして作っても、一向に問い合わせは増えません。中小企業が、大企業と同じ戦略で勝負しても、勝つことは難しいのです。ランチェスター戦略でもあるように、中小企業は接近戦を挑まないといけないのです。そのためには、とりあえず問い合わせを頂かないといけません。
まず、最初に取り掛かる内容ですが、以下の3点です。
・TOP画面の一番上のタイトル(ヘッダー)は会社名ではなく、会社の特徴にする。
例:障害年金専門の社会保険労務士です。
無色透明で紫外線カット率99%のガラスコーティング。
・ヘッダー下に連絡先を大きく表示する。できればフリーダイヤルの番号を大きく表示。
・メニューは左側に持ってくる。
多くのHPがそうなっているので、訪問者は見慣れている。また、お気に入り一覧を表示されている訪問者の場合、右側のメニューだと、メニューが画面からはみ出してしまう。
ここを変えるだけでも、問い合わせは倍になります。まずはこれから手を付けて下さい。次回の担当のときはコンテンツについて記載いたします。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年8月23日 水曜日
平成18年8月23日(第176号)...法人の有する金銭債権についての貸倒れ処理について
法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の
額に算入されます。(法人税法基本通達9-6-1~3)
1.金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、商法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
2.金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力などからその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
3.一定期間取引停止後弁済がない場合など
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含まない)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
長期間回収ができていない債権について、上記の規定に当てはまるものがないか、
再度ご確認ください。
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年8月 8日 火曜日
平成18年8月8日(第175号)...社会保険労務士と労働争議
従来、社会保険労務士法第2条第1項第3号かっこ書き及び法第23条の規定により、社会保険労務士は労働争議に介入することを禁じられてきました。ところが、平成17年の法改正によって「労働争議に介入することになるものを除く」という、上記の条項が削除されました。
従来でも、労働協約の締結等のために団体交渉の場に当事者の一方の委任を受けて当事者の一方と共に出席し交渉することは、法第2条第1項第3号に規定する相談・指導の業務に含まれるものであり、労働争議に介入することとならない限り 許されるとされて来ました。
ところで、「労働争議に介入すること」とは
労働争議が行なわれている時、或いはまさに行われようとする時に、
①当事者の一方の行なう争議行為の対策の検討、決定に参与すること
②当事者の一方を代表して相手方との折衝に当たること
③当事者の間に立って交渉の妥結のためあっせん等の関与を為すこと
等に限られるとされていました。
平成18年3月1日付の「社会保険労務士法の一部を改定する法律について」の厚生労働省通達では、上記の①のみが記述され、②及び③については曖昧になっています。
これにより、今後、社会保険労務士は
労働協約の締結等における、或いは労働争議における団体交渉の場に、当事者の一方の委任を受けて当事者の一方と共に出席し交渉することができる。
しかし、当面、
(a)当事者の一方を代表して相手方との交渉に当たること
(b)当事者の間に立って交渉の妥結のためあっせん等の関与を為すこと
は、まだ認められていないことになります。
事業主の方々は社会保険労務士の仕事の範囲が広がっていることをご認識の上、効果的にご利用頂くようお考え下さい。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年7月23日 日曜日
平成18年7月23日(第174号)...耐震改修工事をした場合の減税措置について
平成18年度の税制改正により、一定の既存住宅に関して耐震改修工事を行った場合に、所得税及び固定資産税において減税措置を受けられる規定が創設されました。
所得税額の特別控除制度について
概要
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、
1.一定の区域内において 2.昭和56年5月31日以前に建築された
3.居住用家屋について行った 4.一定の耐震改修工事が
5.住宅耐震改修に適合する改修である旨の証明がされたもの
である場合には、その者のその年分の所得税額から、その住宅の耐震改修に要した
費用の10%相当額(最高20万円)を控除することができます。
手続き
この規定の適用を受けるためには、
1.控除を受ける金額に関する計算明細書 2. 耐震改修等証明書
3.住宅耐震改修費用の額を記載した書類 4.その他財務省令で定める書類
を添付して所得税の確定申告をすることが必要です。
固定資産税の減額措置について
概要
昭和57年1月1日以前に建設された住宅に、平成18年から平成27年の間に一定の耐震改修工事(その工事費用が30万円以上のもの)を行い、工事完了日から3ヵ月以内に、市町村にその旨を申告すると、その住宅(家屋のみ)の120㎡相当部分について、固定資産税額が2分の1に減額されます。なお、減額を受けることが出来る期間は耐震改修工事を実施した時期により異なり、早期に耐震改修工事を行うと、減額期間が長くなり、有利になるような仕組みになっています。
H18.1.1~H21.12.31までに改修 → 3年度分が減額
H22.1.1~H24.12.31までに改修 → 2年度分が減額
H25.1.1~H27.12.31までに改修 → 1年度分が減額
手続き
この規定の適用を受けるためには、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者が、1.地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関または指定確認検査機関が発行した
証明書
2.耐震改修工事の領収書
を添付して、その耐震基準適合住宅の耐震改修が完了した日から3ヵ月以内に、その市町村に対して耐震基準適合住宅(減額)申告書を提出した場合に限り適用されます。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年7月 8日 土曜日
平成18年7月8日(第173号)...マイカー通勤には、ご注意を!!
通勤の利便性から事業所がマイカー通勤を認めている、もしくは黙認している、私用車の業務利用を黙認している等で事故が発生した場合は、使用者責任および運行供用者責任に基づいて、会社の責任が問われることがあります。
■ 使用者責任(民法715条)と運行供用者責任(自賠法3条)
民法715条の使用者責任とは、使用する労働者が、職務遂行中に第三者に損害を与えた場合に、その使用者が負う損害賠償責任をいいます。運行供用責任とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」とあるように、所有者等がその車両に対し「運行支配」や「運行利益」を有することを根拠に、その車両で発生した事故の相手方に対する賠償責任を負うことを言います。事故を起こした車両に対し「運行支配」や「運行利益」があるかないかで区別していますが、簡単に区別や判断できるものではありませ ん。
「運行支配」とは、自動車の使用、運行につき指示、制御などの支配ないし管理可能性をもつことをいいます。
「運行利益」の帰属は、その自動車の運行による利益が、営業上・経済上の利益に限らず、慰安のような精神的なものでもよく、又、賃貸や取引上のサービス等の間接利益でもよいと解釈されています。
■ 会社が責任を問われないために
1.私用車は通勤にのみ使用し、社用には絶対使用しない、黙認もしないこと。
2.私用車(通勤車)と業務との関連性がないこと。直接的又は間接的にも何ら利益を得ていないこと。
3.ガソリン代・修理代等維持費の負担など、私用車の運転を助長するような事実がないこと。
4.就業規則で適正に規定しておくこと。
など、すべての要件をクリアする必要があります。
■ やむなくマイカー通勤を認める場合は?
1.承認申請書の提出により、損害保険の加入状況、車検期間(登録期間)の確認、運転免許証の確認等により、事業所が承認を行なうこととし、定期的に更新状況等を確認すること。また、加入損害保険に関しては、自賠責保険はもちろんのこと、十分は補償の任意保険の加入を義務付けること。
2.マイカー通勤についての誓約書をとること。
3.定期的に安全運転講習会や安全教育を行なうこと。
マイカー通勤、就業規則の整備に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年6月23日 金曜日
平成18年6月20日(第172号)... <特殊支配同族会社の役員給与損金不算入>
特殊支配同族会社に該当する法人が、業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されません。ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が800万円(一定の場合には3,000万円)以下である事業年度などについては、適用除外となります。
なお、法人が特殊支配同族会社に該当する場合は確定申告書に明細書を添付する必要があります。
この制度は平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
○ 業務主宰役員とは
法人の業務を主宰している役員です。この場合個人に限られています。
○ 特殊支配同族会社とは
次の(1)(2)を満たすものをいいます。
(1)以下の3つの基準いずれかに該当する同族会社
①株式数基準
発行済株式又は出資(自己株式を除く)の総数又は総額の90%以上を保有している場合
②議決権数基準
一定の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有する議決権を除く)の90%以上を保有している場合
③株主数基準
株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その同族会社が業務を執行する社員を定めた場合には業務を執行する社員)に限る)の総数の90%以上を占めている場合
(2)業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の半数を超えるもの
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年6月 8日 木曜日
平成18年6月8日(第171号)...新しい厚生労働省助成金(H18.4.1以降)
<子育てを支援する事業主を応援します!>
●中小企業子育て支援助成金
中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、平成18年4月1日以降に育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(常用労働者100人以下)に対して一定の要件(※)を満たす事業所に助成金が支給される制度が新設されました。
1人目 2人目
育児休業 100万円 60万円
短時間勤務 利用期間 6ヵ月以上1年以下
1年超 2年以下
2年超 60万円
80万円
100万円 20万円
40万円
60万円
※次世代育成支援対象推進法に基づく一般事業計画を届出すること等支給要件があります。
<メンタル等の相談を外部委託する事業主を支援します!>
●中小企業職業相談委託助成金
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、労働者の職場への定着を促進するために、職業(メンタルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に委託を実施した場合に、当該事業に、要した費用の一部を助成します。
1.支給対象者
雇用保険の適用事業主であって、職業(メンタルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に3ヵ月以上委託し、当該認定中小企業者等における常用労働者数が減少していないこと。
2.支給額
委託契約に要した費用の1/3又は、雇用する被保険者数の区分に応じて以下の上限額のいずれか低い額
10人未満 10万円
10人以上 50人未満 25万円
50人以上 100人未満 40万円
100人以上 100万円
(スマイルグループ 産業カウンセラー・社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年5月23日 火曜日
平成18年5月23日(第170号)...傾聴のポイント
「話し上手は、聞(聴)き上手」 今回は、傾聴のポイントをまとめました
●傾聴のポイント ~コミュニケーションは、相手を受け入れることから~
・「心で聴く」...相手を受け入れる善意・愛情を持つ
・相手の話に耳を傾けて意識して聴く・話やすい環境を作る
・あいづちをうったり、うなずいたりして聴く(安心感を与える)
あいづち...目・表情・態度・言葉でうつ
・相手の目的は何か、相手の言葉・表情・語調から本心をつかむ
・共感する・相手の意見をじっくり聴く・言葉に表れていない真意を読む
・話の内容と相手の気持ちを区別して聴く
・「それは、たいしたことでないですね」等 否定的なことを言わない
・相手の話を途中でさえぎらない
・一区切りついたら、要点をまとめる
・気づいたことを、タイミングよくほめる
・・・特に、相手が不安に思っていることや自信を失いかけていることに対して、褒めると自分を受け入れてもらったと感じて安心する
→相手: 「この方には、何を相談しても受け入れてくれる」
→ 「前向きな言葉をかけてくれる」
→ やる気になる・自信がつく
◆意識チェック
1 人に対して興味を持っていますか?
2 相手を受け入れる心を持ち、自分自身も心に余裕がありますか?
3 常に謙虚で、柔軟な発想ができますか?
4 相手の話を聴く努力をしていますか?
5 人の気持ちに共感できますか?
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年5月 8日 月曜日
平成18年5月8日(第169号)...<障害基礎年金と老齢厚生年金の併給ができるようになりました>
平成18年4月1日以後障害基礎年金と老齢厚生年金が併給できるようになりました。それまでは障害を支給事由とする年金と、老齢を支給事由とする年金は併給できませんでした。そのため障害を負ってから納付していた厚生年金保険料が無駄になってしまうケースが多くあり、その問題を解決し、障害者の就労意欲を高めるために始まった制度です。
しかし、制度の周知が徹底されておらず、申請漏れが非常に多く発生しております。仮に障害基礎年金と老齢厚生年金の併給ができる場合は、自ら社会保険事務所に赴いて申請をする必要があります。しかし、資格のある対象者の方に対して、社会保険事務所からの案内は未だに何もされておりません。今後は対象者に案内を出す予定はしているとのことでしたが、申請をしないことには年金額の改定が行われません。
さらに、申請をした翌月から年金額が増額されますが、申請を忘れていても過去に遡って年金額の増額が行われるわけではありません。よって、知らずに放置されている方は非常に大きな不利益を受けていることになります。
そこで、今回は請求に必要な書類と申請方法をご説明します。
~必要な書類等~
・年金受給選択申出書
・障害年金の年金証書
・老齢年金の年金証書
・印鑑(認印で可)
~提出場所~
・住所地を管轄している社会保険事務所
年金受給選択申出書についてですが、新制度に対応した様式は未だに用意されて
おりません。そのため旧制度の様式で申請する形になっており、年金証書の番号を記載する欄が正しく表示されておりません。非常にわかりにくくなっておりますので、社会保険労務士か社会保険事務所にご相談ください。
また、申請する社会保険事務所ですが、お勤めの方は勤務先を管轄する社会保険事務所に提出する形になっております。しかし、実務的にはどこの社会保険事務所に提出しても正しい管轄先に書類がまわる形になっておりますので、どこに提出して良いのかわからないときは、お近くの社会保険事務所に提出してください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年4月28日 金曜日
平成18年4月28日(第168号)...<同族会社の留保金課税>
平成18年4月1日以後開始事業年度から適用される改正です。
同族会社の留保金課税とは、同族会社が内部留保した金額に対して、追加的に
一定の税率(10%、15%、20%)によって課税される制度です。
○ 留保金課税の仕組み
所得等-(配当等+法人税等)-留保控除額=課税留保金額
課税留保金額×特別税率=留保金課税額
○ 対象法人⇒要件の緩和
<改正前>
同族関係者上位3グループで株式等50%超を保有する法人
<改正後>
同族関係者上位1グループで株式等50%超を保有する法人
○ 留保控除額⇒控除額の増加
<改正前>(1)から(3)の最も多い額
(1)所得基準 :所得等×35%
(2)定額基準 :1,500万円
(3)積立金基準:資本金×25%-利益積立金
<改正後>(1)から(4)の最も多い額
(1)所得基準 :所得等×40%(中小企業は50%)
(2)定額基準 :2,000万円
(3)積立金基準:資本金×25%-利益積立金
(4)自己資本比率基準(中小企業のみ)
自己資本比率が30%に達するまでの額
○ 不適用措置⇒不適用措置の引き締め
<改正前>
(1)設立後10年以内の中小企業者
(2)中小企業新事業活動促進法の経営革新計画承認企業
(3)自己資本比率が50%以下の中小企業
<改正後>
中小企業新事業活動促進法の経営革新計画承認企業
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年4月 8日 土曜日
平成18年4月8日(第167号)...労 働 審 判 制 度
つい先日、4月1日から発足した労働審判制度をご紹介しましょう。
1.労働審判制度の概要
裁判官と労使の専門家で構成する労働審判委員会が、個別労働関係の民事紛争について、
地方裁判所において、事実関係の審理をしつつ、調停で事件の解決を試みます。
解決しなければ、当事者間の権利関係を踏まえながら事件の実情に即した解決案を審判として提示します。出された調停案に両者が同意すれば確定し、異議があれば訴訟に移行することになります。審議は3回以内とされています。
2. 労審判制度の特色
(1)合議体に労使の専門家が参加します
2
(2)簡易迅速を旨とする
原則として3回以内で審理を終結します。書類は最初に提出し、裁判所での審理は口頭
で行ないます。1回の所要時間は30分から90分程度と想定されています。
申し立てから3~4ヵ月程度で審判が出されます。
(3)柔軟性
当事者間の権利義務関係を踏まえつつ、事案の実情に即した解決をするために必要な審
判がなされます。オール・オア・ナッシングではなく、労使のバランスを配慮した解決を図ることができます。
(4)実効性
調停機能だけでなく、司法判断としての労働審判という判定機能を併せ持っています。
確定すると、強制力を持つことになります。労働局の調停などにおいては、どちらが是か非かということは二の次になりますが、審判では是か非かが示されます。
(5)経済的
裁判よりもずっと安い費用で解決できます。
3.労働審判の対象
(1)個別労働関係紛争
募集・採用、集団的労使紛争などは対象外です。
(2)労働者と事業主の間の紛争
労働者個人間の紛争は対象外です。
(3)民事に関する紛争
公務員の任用、利益に関する紛争、行政訴訟などは対象外です。
今後、裁判外紛争解決手段(ADR)の一つとして、利用が多くなると予想されます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年3月23日 木曜日
平成18年3月23日(第166号)相続税の物納制度の改正内容(税制改正大綱)
平成18年度の税制改正法案が2月6日に財務省から公表されました。その中から、相続税の物納制度の改正内容について簡潔に解説します。
相続税の物納制度については、物納の許可基準が明確でない、手続に長期間を要するケースが見られる等の指摘があることを踏まえ、物納制度に対する信頼を確保するため、手続の明確化・迅速化等の観点から以下の項目について改正されます。
●物納不適格財産の明確化について
抵当権が設定されている不動産、境界が不明確な土地等の一定の財産を物納不適格財産(管理又は処分をするのに不適格な財産)として定め、「市街化調整区域内の土地、無道路地などの一定の財産を"物納劣後財産"(他に物納適格財産がない場合に限り物納を認める財産)」として、その範囲での明確化を図ることとする。
●物納手続の明確化について
物納財産を国が収納するために必要な書類として、物納財産の種類に応じ、登記事項証明書、測量図、境界確認書等一定の書類を定めるとともに、申請者は、これらの書類を物納申請時に提出する。など物納の手続きについて明確にする。
●物納申請の許可に係る審査期間の法定等について
税務署長は、物納申請の許可又は却下を物納申請期限から3ヵ月以内に行う。ただし、物納財産が多数となるなど調査等に相当の期間を要すると見込まれる場合には、6ヵ月以内(積雪など特別な事情によるものについては、9ヵ月以内)とすることができることとする。
●物納申請を却下された者の延納の申請について
物納の許可を申請した者について、延納による納付が可能であることから物納申請の全部又は一部が却下された場合には、20日以内に延納の申請を行うことができることとする。
●延納中の物納の選択について
相続税を延納中の者が、資力の状況の変化等により延納による納付が困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、延納税額からその納期限の到来した分納税額を控除した残額を限度として、物納を選択することができる制度を創設する。
●その他所要の措置について
金銭又は延納による納付困難要件について、その判定方法を明確化する。等々
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年2月23日 木曜日
平成18年2月23日(第165号)...国民年金保険料は口座振替割引制度がお得です!
■ 保険料を前納される方は口座振替にするとさらにお得です!
口座振替での前納は、1年度分または6ヵ月分(4月~9月分、10月~3月分)の前納をお申込みいただくことができます。
平成18年度分の口座振替での前納のお申込みは、平成18年3月31日必着(社会保険事務所
まで)となります。郵送または金融機関等でお申込みされる場合は、お早めにお申込みください。
※ すでに口座振替で前納されている方は、お申込みの必要はありません。前納の口座振替日は4月30日(今年は日曜日にあたるため5月1日)です。
■ 月々の保険料も口座振替による早割にするとお得です!
● 毎月、現金で納めている方、口座振替で納めている方 翌月末支払(引落し)となっています。
● 口座振替で早割にすると
早割制度を申し込みすると翌月末の初回の口座振替にて2ヵ月分の保険料(従前の保険料と50円割引された保険料)が引落しとなり、その後の毎月の保険料が50円割引となります。
口座振替による早割をご希望の方は、社会保険事務所または口座をお持ちの金融機関・郵便局へ申し込みをしていただく必要がございます。(すでに口座振替により納付されている方も、申し込みが必要です) 口座振替の申し込み用紙は、社会保険事務所に請求していただくか、ホームページからダウンロードすることもできます。
※ 保険料の半額免除の承認を受けている方の口座振替は、通常の口座振替のみとなります。
<その他 ご注意ください!!>
◆平成18年3月~ 政府管掌健康保険の介護保険料率が1.25%→1.23%に変わります。
◆平成18年7月~ 健康保険法・厚生年金法の報酬の支払基礎日数が17日以上に変わります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年2月23日 木曜日
平成18年2月23日(第164号)...過重労働・メンタルヘルス対策(H18.4.1改正予定)
過重労働による健康障害の防止のために、事業者が講ずべき措置等については、時間外労働が月100時間または2~6ヵ月の平均で月80時間を超えた場合に、産業医の面接による保健指導、産業医が必要と認める場合に臨時の健康診断を行なうこととされていました。これは、脳・心臓疾患の発生に影響を及ぼす最も重要な要因として、発症前1ヵ月~6ヵ月の間で上記時間外労働の関連性が強いと判断されているからです。
事業者は、厚生労働省令で定める一定時間(月100時間)を超える時間外労働等を行った労働者を対象として、医師による面接指導等を行うことが義務づけられました。
面接指導を行う労働者以外でも、健康への配慮が必要なものについては必要な措置を講ずるよう努めなければならない、ともされています。
なお、事業者は常時使用する労働者を雇い入れる時、以下の項目について健康診断を実施しなければなりません。
1.「雇い入れ時の健康診断」
(1)既往歴および業務歴の調査 (2)自覚症状および他覚症状の有無
(3)身長、体重、視力、聴力 (4)胸部エックス線検査 (5)血圧測定
(6)貧血検査 (7)肝機能検査 (8)血中脂質検査 (9)尿検査
(10)心電図検査
以上の項目のうち3ヵ月以内の受診で証明書の提出があれば省略できます。また、事業者は常時使用する労働者について毎年、定期に健康診断を実施しなければな
りません。
2.「定期健康診断」
検査項目は上記(1)~(10)に喀痰検査を加えたものです。なお、35歳未満の者、36~40歳の者で医師が必要でないと認めた者については、(6)~(8)(10)を省略することができます。
通勤災害保護制度の対象の拡大
通勤災害とは、労働者が住居と就業の場所を「合理的な経路および方法」で通勤する場合に、その途中で起きた災害(業務に起因するものを除く)のことを言います。もともと、労働者災害保障保険法は業務に起因する負傷、疾病に対する保険給付を担当しておりましたが、その後、「就業のための通勤」という考えに基づき、通勤上の負傷、疾病についても労災保険で保険給付が行なわれるようになりました。
さらに今回、複数就業者が事業場の間を移動する場合も通災の対象となる予定です。この際、保険関係の処理は「第2の事業場」(第1の事業場から向かった先)で行ないます。
また、単身赴任者の場合、帰省先住所と赴任先住所の間を移動する場合も、通災の対象となる見込みです。(月1回以上の反復継続性が必要です。)
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年2月 8日 水曜日
平成18年2月8日(第163号)...継続雇用定着促進助成金はお急ぎください!
年金の受給年齢の引き上げに伴い、4月から高齢者雇用安定法が改正されるのはご存知だと思います。事業主は平成18年4月1日から、何らかの形で段階的に65歳までの雇用を継続するよう義務化されることになりました。(絶対に定年の年齢を引き上げないといけないわけではありません。あくまで65歳まで雇用が確保されればいいだけです。)
それに伴いまして、表題の助成金である継続雇用制度奨励金が、(現在ですと、最大30万円から1500万円までの受給額がありますが、)4月以降に大幅に減額される事が確定しています。以下に記載しています受給要件に該当される事業主の方は、3月末日までに申請をすれば、返済不要の助成金が支給されます。もちろん、申請をしないことには支給される事はありませんので、ご注意ください。
「受給要件」
1.雇用保険の適用事業所
2.1年以上継続して55歳から64歳の一般被保険者が1人以上いること
(従業員100人以上規模の場合は、100人ごとに1人を加えた人数が必要)
3.就業規則を変更して雇用継続制度を設けること
「受給額」 (現在のものです。)
継続雇用期間 61歳~64歳の
定年延長等 65歳以上の
定年延長等 定年延長等以外の
雇用継続制度
企業規模 1~4年 1~5年 1~5年
1~9人 35万円×1~4年 45万円×1~5年 30万円×1~5年
10~99人 75万円×1~4年 90万円×1~5年 60万円×1~5年
100~299人 150万円×1~4年 180万円×1~5年 120万円×1~5年
300~499人 185万円×1~4年 220万円×1~5年 150万円×1~5年
500人以上 250万円×1~4年 300万円×1~5年 200万円×1~5年
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年1月23日 月曜日
平成18年1月23日(第162号)...お客様のタイプ別接客アドバイス
●無口・意思の表示がない・自分の好みや主張を言わない
ちょっとした相手の表情・動作・目線・会話などから何に関心があるかを見抜く。お客様が答えやすい質問をし、落ち着いてお客様が決断できるよう心を配る。
●明るく話好き・よく話す・冗談が好き・話が違う方向にそれる
話をさえぎると気分を悪くする。熱心に話を聞く。タイミングをみて本筋に戻す。
●内気であまり話をしない・少しのことで動揺される
お客様に恥をかかせない。静かにお客様にペースを合わせる。自信を持たせてあげる。
●優柔不断・自分で決断しにくい
お客様との会話から、商品を絞り、わかりやすく商品説明をする。お客様が商品を比較し、選択しやすいようにサポートする。購買の決定権は、お客様に譲る。
●疑い深い・信用するまで時間がかかる
お客様にいい加減な答えを言わない。お客様に質問をなげ、疑問点を分析し、納得いただけるように説明する。お客様から信頼していただけるよう商品知識を豊富に持つことが大切。
●いばって、えらそうにする・威圧的・商品について詳しい等知識の豊かさを自慢する
プライドが高いので傷つけないよう尊敬の意を示す。丁寧な言葉使いをする・ほめる。
●気が長い・じっくり型
決定を焦らせない。お客様の希望をしっかりと聞き、商品・サービスを勧める。
●勝気・指示されることを好まない
お客様の意見や考えを尊重する。お客様のアドバイスには、的確に答えることが必要。 (勝気なお客様ほど、しっかりした人を好む)
★ポイント:相手のカラー・雰囲気に、自分が合わせる
(スマイルグループ 接客販売インストラクター)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年1月 8日 日曜日
平成18年1月8日(第161号)...LLPってなに?
平成17年6月成立した新会社法でLLPってできたけど使い道があるの?
今回はこのLLP(「Limited Liability Partnership」有限責任事業組合)について触れてみましょう。
名の通り構成員が全員有限責任
組合の構成員は2名以上あればよく、全員が有限責任で、設立手続も株式会社に比べると簡単です。
会社の定款の代わりになるものが「組合契約書」で、全構成員がこれに署名捺印し、出資金の払い込みをして、設立登記をするだけです。設立総会も取締役会も財産調査も不要です。
どんな組織?
組合員が信頼関係に基づき、運営していくのを基本にしていますので、株主総会なし、取締役会なし、ついでに監査役もありません。各組合員が自分の特徴を出し合って効率的に運営していくことを主眼においた組織形態になっています。
また、組合員を中心とした内部自治を重視していますので、責任権限や利益分配ルールを「組合契約書」の中で決めておく方がよいでしょう。
儲かったときの税金は誰が払うの?
法人と違って、各組合員の個人課税になります。利益配分ルールに従って、組合員別に所得を計算し、組合員は他の所得と合算して、個人で申告することになります。
例えば、組合配分所得が赤字になれば、給与所得等のほかの所得とも通算できて、源泉所得税が還付になるケースも出てきます。
どんな業種に向く?
「士業」のように専門家の集まりや、Sales・Repのように一定の社会的な信用を得ながら自分の得意分野の販売代理をしていくような形態に合うと思います。
特に、何人かでこれから共同で事業を起こしていくようなベンチャー企業向けの組織であると思います。お互いに自立できれば株式会社へ移行すればいいのですから。
あなたも、チャレンジしてみませんか!?
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2005年12月23日 金曜日
平成17年12月23日 (第160号) 平成18年度の税制改正大綱
定率減税の廃止
平成19年に全廃されます。(平成18年から減税幅が半減されています。)
所得税率の見直し
平成19年から現在4段階(10%、20%、30%、37%)に設定されている所得税率が6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)に見直され、また住民税は現行の3段階(5%、10%、13%)から一律10%となります。
地震対策
平成19年から所得控除として地震保険料控除(最高5万円)を創設し、既存の損害保険料控除は平成18年末までに契約した長期損害保険契約を除き廃止されます。
また平成18年4月1日から平成20年12月31日までに、既存住宅に一定の要件を満たす耐震改修を行えば、その改修費用の10%(最高20万円)が所得税から控除され、地方税では一定期間内に耐震改修を行った住宅につき、固定資産税が1/2減額されます。
中小企業対策
1.同族会社の判定及び留保金課税の計算につき改正が行われます。
2.交際費の範囲から1人あたり5千円以下の一定の飲食費が除外されます。
3.30万円未満資産の即時償却につき、1事業年度につき総額300万円の上限を設けたうえ、適用期限が2年延長されます。
役員報酬
一定の要件を満たす同族会社の役員報酬につき、給与所得控除相当額が損金不算入とされます。また、一定の業績連動型報酬を損金算入できるようになります。
※業績連動型報酬のうち、非同族法人の役員に対するもので損金経理や有価証券報告書への記載等一定の要件を満たしたもの。
その他(主だったもの)
1.IT減税、留保金課税の不適用制度の廃止 2.寄付金控除適用下限額を5千円に引下げ 3.情報セキュリティー対策用資産を取得した場合の特別償却又は税額控除の創設(情報基盤強化税制) 4.研究開発税制
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年12月 8日 木曜日
平成17年12月8日(第159号) 試行雇用奨励金(トライアル雇用制度)
1.求職者の条件
公共職業安定所に求職申し込みをしていること
2.求人側の条件
(1)雇用保険の適用事業所であり、安定所でトライアル雇用併用求人手続を行うこと
(2)過去6ヵ月間雇用保険の被保険者を事業主の都合によって解雇していないこと
(3)過去3年間に不正行為により奨励金の不支給又は支給取消の処分を受けていないこと
3.期間
原則として3ヵ月。ただし事業主と求職者の合意により、1ヵ月又は2ヵ月とすることもできます。
4.労働時間
同一事業所で雇用される通常の労働者と同程度(30時間を下回らないこと)、障害者等については20時間を下回らないこと
5.求職者への通知
トライアル雇用であること、トライアル雇用の趣旨が説明されていること。
6.計画書の提出
奨励金の受給を希望する場合は、計画書を作成し、対象者の同意を得た上でトライアル雇用開始の日から2週間以内に安定所に提出します。
7.奨励金の支給額
トライアル雇用対象者1人当たりの奨励金支給額は月額5万円として、支給対象期間の各月支給額の合計額となります。1ヵ月に満たない雇用期間がある場合は日割り計算されます。
30歳未満の求職者についてのトライアル雇用制度については、制度ができてから平成15年末までの約2年間で、トライアル雇用を終了した者の約8割が当該事業所での常用雇用に移行したとされており、安定した就職の促進に役立っております。
求職者をいきなり常用労働者として雇い入れるのは、やはり不安があると考える事業主が多いと思います。試行雇用制度を活用すれば、人物・能力をしっかり見極めた上で採用することができ、助成金もついてくるというメリットがあります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年12月 1日 木曜日
平成17年12月1日(臨時号) 過重労働・メンタルヘルス対策
事業者は、厚生労働省令で定める一定時間(月100時間)を超える時間外労働等を行った労働者を対象として、医師による面接指導等を行うことが義務づけられました。
面接指導を行う労働者以外でも、健康への配慮が必要なものについては必要な措置を講ずるよう努めなければならない、ともされています。
なお、事業者は常時使用する労働者を雇い入れる時、以下の項目について健康診断を実施しなければなりません。
1.「雇い入れ時の健康診断」
(1)既往歴および業務歴の調査 (2)自覚症状および他覚症状の有無
(2)身長、体重、視力、聴力 (4)胸部エックス線検査 (5)血圧測定
(6)貧血検査 (7)肝機能検査 (8)血中脂質検査 (9)尿検査
(10)心電図検査
以上の項目のうち3ヵ月以内の受診で証明書の提出があれば省略できます。また、事業者は常時使用する労働者について毎年、定期に健康診断を実施しなければなりません。
2.「定期健康診断」
検査項目は上記(1)~(10)に喀痰検査を加えたものです。なお、35歳未満の者、36~40歳の者で医師が必要でないと認めた者については、(6)~(8)(10)を省略することができます。
通勤災害保護制度の対象の拡大
通勤災害とは、労働者が住居と就業の場所を「合理的な経路および方法」で通勤する場合に、その途中で起きた災害(業務に起因するものを除く)のことを言います。もともと、労働者災害保障保険法は業務に起因する負傷、疾病に対する保険給付を担当しておりましたが、その後、「就業のための通勤」という考えに基づき、通勤上の負傷、疾病についても労災保険で保険給付が行なわれるようになりました。
さらに今回、複数就業者が事業場の間を移動する場合も通災の対象となりました。この際、保険関係の処理は「第2の事業場」(第1の事業場から向かった先)で行ないます。
また、単身赴任者の場合、帰省先住所と赴任先住所の間を移動する場合も、通災の対象となります。(月1回以上の反復継続性が必要です)
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年11月23日 水曜日
平成17年11月23日(第158号)...~平成17年7月1日 都道府県地価調査の実施状況~
国土交通省はこのほど、全国の都道府県地価調査結果(基準地価)を発表しました。価格の判定は不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これに基づいて都道府県知事が正常価格の判定を行ったものです。全国の対前年平均変動率を用途別にみると、住宅地△ 3.8%、商業地△ 5.0%、準工業地△ 5.2%、工業地△ 5.7%となっています。全国平均で見ると地価は引き続き下落していますが、住宅地、商業地とも下落幅は縮小しており、利便性・収益性等の状況による地価の個別化傾向もみられます。大阪圏の概況については以下の通りです。
大阪圏の概況
大阪圏の対前年平均変動率を用途別にみると、住宅地△ 3.7%、商業地△ 3.3%、準工業地△ 4.4%、工業地△ 6.0%、となっています。
1.住宅地
都心部やこれに近接する地域では、需要側の値頃感等から、利便性の高さによりマンション需要の旺盛な地域、住環境に優れている伝統的な高級住宅地、都市再生の取組みや交通基盤整備に伴い利便性が高まった地域等で多くの上昇地点が見られます。郊外部では、利便性が高く住環境に優れた地域で上昇や横ばいに転じた地点が見られます。反面、通勤遠隔地では、交通利便性が劣ることにより下落幅が大きい地点が依然として見られますが、その数は減少しています。
2.商業地
利便性が高く、均整のとれた街並みであることに由来して旧来より高度に商業業務機能が集積し、繁華性の高い地区、都市再生の取組みや交通基盤整備、大型商業施設の進出等に伴い利便性や集客力の高まった地区等においては、多くの上昇地点が見られます。近隣の中核的大規模商業施設の撤退や郊外型量販店の進出等の影響で集客力が低下した地域の中心商業地や近隣商業地では、下落幅が大きい地点が依然として見られますが、その数は減少しています。
このように、今回の基準地価においては、平成17年地価公示(平成17年1月1日)で見られた地価動向の変化がより鮮明になりました。その背景として、景気が底堅く推移する中で、1)大都市の中心部にあっては、収益型不動産に対する投資の活発化や需要側の値頃感による都心回帰指向から、利便性や環境の優れた地域における店舗や事務所、マンション等の需要が増加したこと、2)大都市の中心部以外の地域にあっては、市街地整備や鉄道などの交通基盤整備等に伴い、利便性の向上や優れた住環境が顕著となった地域等において住宅の需要等が堅調であったこと、等が挙げられます。3)一方で、利便性・収益性の相違や個別の地点の置かれた状況による地価の個別化(二極化)傾向も見られます。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2005年11月 8日 火曜日
平成17年11月8日(第157号)...営業秘密の保護強化-不正競争防止法改正の概要-
営業秘密の侵害行為や模倣品・海賊版によるブランド価値等の侵害行為に対する措置を拡充し、適正な競争環境を維持するために不正競争防止法が改正されました。
◆改正のポイント:営業秘密の保護強化 平成17年改正 平成17年11月1日から施行
○営業秘密の国外使用・開示処罰の導入
日本国内で管理されている営業秘密について、日本国外で使用又は開示した者を処罰の対象
営業秘密が関係する民事訴訟における裁判所の秘密保持命令に日本国外で違反した者も処罰の対象
○退職者の処罰の導入
元役員・元従業員による媒体取得・複製を伴わない営業秘密の不正使用・開示について、在職中に申込や請託があるようなケースも処罰の対象
◆営業秘密とは?
不正競争防止法では、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」とされており、例えば、アクセス者を限定して保管されている設計図や顧客名簿、販売マニュアル等で一般的に入手できないものをいいます。
◆営業秘密として保護されるためには?
①秘密管理性②有用性③非公知性の3つの要件を満たさなければ、誰かが無断で利用しても不正競争行為として差し止めたり、損害賠償請求することはできません。
秘密管理性とは、アクセスできる者を制限したり、秘密情報である旨の表示(例えば、㊙と書類に表示する等)をしたりすることにより、情報が客観的に秘密として管理されていると認められている状態にあると言えますから、企業としては、個人情報保護と同様の物理的技術的管理・人的法的管理措置を講じる必要があります。
◆罰則の見直し・法人処罰の導入
不正競争防止法違反の罪について、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金から、原則として、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に引き上げるとともに、懲役刑と罰金刑の併科規定を導入
営業秘密にアクセスする権限がない者が行った営業秘密侵害罪の犯人の属する法人について、法人処罰(1億5,000万円以下の罰金)を導入。企業としては、管理体制を強化し注意義務を尽くす必要があります。したがって、中途採用者などを採用する企業は、十分注意が必要です。
営業秘密に関する物理的技術的管理・人的法的管理については、お気軽にお問い合わせください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2005年10月23日 日曜日
平成17年10月23日(第156号)...~従業員の福利厚生制度の充実~
会社にとっては、従業員から信頼され、気持ち良く働ける労働環境を整え、従業員が能力を充分に発揮できるように福利厚生制度の充実を図ることは欠かせません。福利厚生制度を充実させることで従業員の会社への貢献意欲を高めることができ、従業員の事故、残業による過労死等、いざという時の出来事にも対応できます。いざという時の備えとして、ここでは従業員の労働災害に対する備えについてご案内します。
<労働災害に対する備えの必要性>
従業員にとっては、労働基準法、最低賃金法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法などの制度で社会保障制度が充実しており、労働災害に対する備えは充分であるように思えます。しかし、そのような社会保障制度ではまかないきれない民事上の賠償責任が発生した場合、会社にとっても従業員にとっても大きな損害が生じます。そのようなリスクに備え、健全な企業経営のためにも社会保障制度を超えた賠償等に対する福利厚生制度は必要になります。
<民事上の賠償責任>
会社は労働者に対して、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する安全配慮義務があり、これを怠ると民法415条により会社側の債務不履行となり、損害賠償責任が生じます。その安全配慮義務に違反がなかったかを立証する責任は会社側にあり、多くの判例で会社の責任を認めています。社会保障制度では実際の損害についてはある程度まかなえますが、安全配慮義務違反に対する賠償責任には応じられないため、そのための備えが必要になります。
社会保障ではまかないきれない民事上の賠償に備える商品として、生命保険・損害保険・共済制度など様々な機関からたくさんの商品が提供されています。会社のリスクマネジメントの観点からも従業員の福利厚生についてもう一度考え直してみませんか。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2005年10月 8日 土曜日
平成17年10月8日(第155号)...~中小企業融資の個人保証制度が変わる~
1.改正の趣旨
中小企業が金融機関から借入れをする場合、ほとんどが代表者の個人保証を求められてきました。こうした無期限の「包括的根保証契約」によって、倒産してしまうと家財一切合財取られてしまって、事業の失敗者が人生の失敗者みたいになってしまっています。こうした個人保証人の過大な責任を緩和するために、保証人が負担する責任を予測ができる範囲内に限定するように、保証限度額や保証期間を定めるように民法が改正され、平成17年4月1日から施行されました。
2.主な改正点
●保証契約 改正前 ... 口頭でも成立していた。
改正後 ... 口頭での約束は無効。書面での契約が必要になった。
●根保証契約 改正前 ... 極度額の定めがなくても有効。
の極度額 改正後 ... 極度額の定めがないと無効。
●期間限定 改正前 ... 根保証人が無期限で保証する契約も有効。
改正後 ... 契約で定められた5年以内の期間(定めがないときは3年間)に発生した債務のみを保証すれば足りる。
3.今までの契約はどうなる?
今回の改正前に締結された貸金等根保証契約は、残念ながらそのまま有効です。
4.保証限度を超える借入れはできなくなる?
保証枠を超えた資金ニーズがある場合は、保証のない借入れを受けるか、保証の限度額を拡大する変更契約をするなど、金融機関との協議をしていくことになります。
5.ご提案
この際、事業をする上での借入れ限度額を定め、それを根保証限度額とし、無理な借入れをして将来の見込みが立たない事業継続については、見直してみてはいかがでしょうか。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2005年9月23日 金曜日
平成17年9月23日(第154号)...~ヒアリングとトークのポイント~
皆様は、商談時、どのような手順でお客様と話をしていらっしゃいますか?
◆お取引前、ヒアリング・トークのポイント
1.明るい挨拶
事前に、電話やメール等で、何らかのコミュニケーションがあった場合、そのお礼も申し上げる。
2.日常会話・雑談から
・急に商品の話や売り込みを始めない。まず、心を自分から開いて話をする。相手の心をほぐす。お客様がリラックスして、本音で話ができるような雰囲気を作る。
・お客様に、「今、お困りのことは、ございますか?」等、お困りのことや不便に感じていらっしゃることをお尋ねするモードに自然に切り替える。
3.なるべくお客様が話しやすいように、あいづちを打ちながら、質問を掘り下げて聴く
・自分が話すよりも、先にニーズを掴むために話の点をお客様に合わせ、お客様に思う存分話をしていただく...お客様は話を聴いてもらうだけでもストレス発散。
・聞き手の心得として、うなずきながら聞く。共感している様子を態度や言葉で示しながら聞く(腕を組んで聞かない=拒否的 足を組んで聞かない=失礼 目線を上から下に送るような感じで相手を見ない=見下げているように思われる)。
4.お客様のニーズや環境を理解して差し上げた後、自社の商品を勧める
・お客様が困っていらっしゃること不便なことが、自社商品によって解決する理由を述べ解決する手順等を、親切にわかりやすく(資料等を使って、五感に訴え、第三者の意見等も入れて)具体的に説明する。
・必要なものをピックアップして勧め、自分がどうしてお客様にその商品を勧めるのか、その理由も述べる。
・購入前・中・後の自社のフォーロ体制をお客様に伝え、信用・安心を先に売る。
(注意:必要以上に多くの商品を勧めない)
(スマイルグループ 接客販売インストラクター)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2005年9月 8日 木曜日
平成17年9月8日(第153号) ~着替えの時間は労働時間か?~
結論から言うと、その制服や作業着に着替えないと、労務を提供できない(仕事が始められない)場合、着替えに要する時間は労働時間となります。診療所等の看護士、レストランの接客係、工場の作業員等は着替えの時間も労働時間に当るということです。
ここで注意したいのが、着替えの時間が労働時間に該当するということは、すなわち着替えの時間について賃金が発生するということです。たとえば8時30分始業の会社の場合、8時30分までに着替えを済ませて、仕事を始められる状態にしていないと遅刻扱いにしてしまいがちです。しかし、着替えは労働時間に含まれるという考えに従うと、8時30分までに事業場に入っていれば遅刻とはならず、さらには8時30分から業務を始めるために、早目に出社して着替えた時間に対しては賃金が発生します。1日の労働時間を8時間と設定する事業所の場合であれば、時間外労働の割増賃金の対象となります。これは、業務終了後の着替えの時間にもあてはまります。「仕事をしていないのに賃金を支払わなければならないのか?」と事業主の皆様は考えられるかもしれませんが、着替えの時間も労働者を拘束している時間ですので、きっちり労働時間として管理してください。
また、労働時間の管理については、30分単位または15分単位で行っている場合が多いですが、労働基準法の解釈では厳密にいうと1分単位となっています。1日の時間外労働時間が5分以内であるという理由で切り捨ててしまうという運営は認められていません。つい先日も、大手ファーストフードチェーンが、このような管理を行っていたため労働基準監督署から指導を受けています。指導では、2年分の労働時間を遡り、1分単位で再計算し、賃金の清算をするよう命じています。労働時間の管理については、労働基準監督署も厳しくチェックをしています。皆様の事業所でもきっちりとした労働時間の管理と把握をお願いします。
※その月における時間外、休日または深夜の総労働時間に30分未満の端数がある場合はこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合にはこれを1時間に切り上げることは、事務簡便を目的として認められます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年8月23日 火曜日
平成17年8月23日(第152号) ~会計参与について~
〈会計参与とは〉
会計参与とは、株式会社における新たな機関をいいます。会計に関する専門的見識を有する者として、株式会社により選任される者が取締役・執行役と共同して計算書類を作成するとともに、当該計算書類を取締役・執行役とは別に保存し、株主・会社債権者に対して開示すること等をその職務とします。
〈会計参与の資格〉
会計参与は、公認会計士(監査法人を含む)または税理士(税理士法人を含む)でなければなりません。
〈会計参与の任期〉
原則2年。ただし、株式譲渡制限会社については、定款で任期を最長10年まで延長することができます。
〈会計参与の報酬〉
会計参与の報酬は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定められます。
〈計算書類の保存年数〉
会計参与は、会社とは別に5年間、会計参与が定めた場所において計算書類を保存しなければなりません。
〈会計参与辞任後の計算書類の保存、開示義務の有無〉
辞任した者は、計算書類の保存期間である5年間が経過する前であっても、保存、開示の義務は負いません。
〈会計参与に対する計算書類閲覧等の請求者が株主、債権者であることの確認方法〉
会計参与は、必要に応じて、請求者が株主、債権者であることを確認するため会社に対する照会等を行うことになります。
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年8月 8日 月曜日
平成17年8月8日(第151号) 安全配慮義務
安全配慮義務とは、広くは「職場環境において、生命・身体・健康を保護するよう配慮する義務」とされています。この義務は、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触関係に入った当事者間」において発生し、「法律関係の付随義務として信義則上負う義務」とされています。
なお、安全配慮義務は「労働契約」という契約形態によってのみ発生するものではなく、実態により判断される点で注意が必要です。例えば、「請負契約」という契約内容により下請企業の労働者が働く場合であっても、下請けの労働者を実際に指揮命令し、監督しているような場合は、「労働契約」が締結されていなくても、「労働契約」となんら変わることなく下請け労働者に対しても安全配慮義務という債務を負うことになります。
会社が労働者に、安全で健康に働けるよう配慮しているだけでは債務の本旨を履行したことにはなりません。安全配慮義務の内容に基づき、会社内での職場環境に応じた具体的な制度や措置を設け、それらが実際に活動や行動として行われていなければなりません。
冒頭に挙げた例では、安全ベルトを備えているだけでは足りず、危険作業では常にベルトを着用するよう指導・監督し、安全第一の気風を社内に作っておく必要があるのです。
(『企業の健康・安全配慮義務と労務管理』 森、 田隅 共著より)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年7月23日 土曜日
平成17年7月23日(第150号) いま、名古屋が元気印!
好調な名古屋圏
まず、名古屋圏の経済の好調が話題となっています。たしかに、各種データからもそれは裏付けられます。一例として、有効求人倍率を見てみますと、以前から全国平均を0.2~0.3ポイントほど上回って推移していましたが、ここへきてその差は0.7ポイント、絶対値では1.6ポイントまで拡大しています。また株式投資の世界では、「名古屋銘柄をねらえ」というキーワードも飛び交っています。
名古屋ではなく名古屋圏
ここで注意したいことは、好調なのは名古屋市に限定されているわけではないということです。自動車生産の中心地は豊田市、刈谷市であり、今年2月17日に開港した中部国際空港は常滑市、3月25日に開幕した2005年日本国際博覧会(愛・地球博)の会場は長久手町、豊田市および瀬戸市です。したがって、好調な地域は「名古屋市およびその周辺」とするほうが正確でしょう。
好調の理由
好調の理由として、まず、名古屋圏の人々の確実性が挙げられます。バブル期にも無茶な投資をしなかったため、当時は儲けそこなったのでしょうが、その後の落ち込みは少なく痛手を負いませんでした。このことは名古屋圏における地価の上昇率・下落率が東京、大阪に比べて低くおさえられたことに結びついています。
つぎに、製造業が強いということです。名古屋圏の企業は、急成長を続けるアジア各国に機器、設備を提供するかたちで活躍しています。幸いにも近年の円高は緩やかに推移しています。名古屋港からの輸出額7兆円は横浜・神戸を抑え全国トップとなっています。
このような製造業の活躍により雇用が増大し、1人当たりの県民所得は350万円となり(東京都に次ぎ全国2位)、消費の落ち込みを防いでいます。
そのうえ、歴史的にも大きな意味を持つ2大事業が加わりました。中部国際空港の開港および2005年日本国際博覧会の開催です。一昨年までの不況の時代、これらの2大事業が景気の下支えをしてきました。さらに今後も2兆円を越す経済効果が期待されています。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年7月 8日 金曜日
平成17年7月8日(第149号) ~気になる年金改正点~
◆厚生年金保険の保険料率の引き上げ
昨年の改正では厚生年金保険料率について、平成16年10月分(平成17年以降は毎年9月分)から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%に固定されることになっています。平成17年9月分より、厚生年金保険料率は下記のように改定されます。
(一般の被保険者)
保険料率 折半負担保険料率
平成16年10月~平成17年8月 139.34/1000 69.67/1000
平成17年 9月~平成18年8月 142.88/1000 71.44/1000
◆第3号被保険者の未届け期間の特例届出
(1)平成17年4月1日前の未届け期間について
ア.昭和61年4月に遡り、未届け期間について届出をすると、特例により2年を超える期間も国民
年金保険料納付済期間となります。
国民年金保険料納付済期間となります。
イ. 老齢基礎年金、老齢年金、通算老齢年金をすでに受けている場合は、届出日の翌月分から年金額
が改定されます。
イ.歳時点で受給権を有していなかった人が届出日以後、保険料納付済期間に算入されることにより
受給権を取得した場合、老齢基礎年金が支給されます。
(2)平成17年4月1日以降の未届け期間について
届出が遅れたことについてやむを得ない事由がある場合には、その期間について届出を行うことが
でき、保険料納付済期間に算入されます。
◆「年金分割」について
(1) 平成19年4月実施
平成19年4月1日以降に成立した離婚を対象として、離婚時の厚生年金の分割は、夫婦の合意
または家庭裁判所の決定により婚姻期間中の保険料納付記録を当事者間で分割でき、離婚して2年
以内であれば分割請求できます。ただし、分割された夫の加入期間は、妻の受給資格に反映されま
せん。
(2) 平成20年4月実施
平成20年4月以降の第3号被保険者期間について、離婚時、この期間に対応する相手(第2号被
保険者)の厚生年金加入期間を分割対象として、半額が請求可能となります。相手(第2号被保険
者)の同意がなくとも、また家庭裁判所の結果に関係なく、2分の1に分割される仕組みです。
くわしくは、お気軽に下記までお問い合わせください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年6月23日 木曜日
平成17年6月23日(第148号) ~高年齢者雇用安定法の改正に向けて~
〈高年齢者雇用安定法の改正にあたって取り組むべきこと〉
上記(1)(3)を選択するとリスクは大きくなるため、一般的には(2)継続雇用制度を選択することをお勧めします。継続雇用制度を導入することで会社は一定の基準に達したスキルを身につけた者だけ継続雇用することが可能になるため、対象者を限定できるようになります。会社側は継続雇用する者を限定するために評価シートを作成し、明確な基準を設け、基準に達した者だけ雇用するという仕組みや体制をつくる必要があります。
〈継続雇用制度を導入するメリット〉
(1)自己の人生設計を考えさせることができる(2)評価制度を理解させることができる(3)社員一人一人が自分の適正を考えることができる(4)優秀な社員の会社への定着率を高めることができる(5)やる気を高めることができる(6)会社に必要な人材を育てることできる
〈継続雇用制度の導入にあたって〉
1.個人別の評価シートをつくり、評価シートをオープンにする
2.上司が評価シートで部下を教育指導する
3.社員が評価シートで自己育成を図る
4.評価が組織的に確定している
5.評価が本人にフィードバックされる
以上のような仕組みをつくり、働く意思がある者がその基準を満たすように上司は指導します。人事制度を導入されている場合は、その制度の見直しにより対応することが可能です。評価シートで明確な基準をつくり、体制を整えることで平成18年4月施行の高年齢者雇用安定法の改正に向けて十分な準備ができます。各事業所で評価シートの導入を検討してみませんか。
人事制度(評価シート)の構築は、社員と会社を成長させる仕組みです。
評価シートの内容、作成方法等、詳細は下記へお問い合わせください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年6月 8日 水曜日
平成17年6月8日(第147号) NPO法人の税務
NPO法第5条において、NPO法人では本来の事業に支障のない限り、事業目的の遂行活動に必要な経費不足を補うため、収益事業を行うことができるとされています。NPO法人が法人税法上の収益事業を行った場合は、法人税が課税されることになります。法人税法上の収益事業とは、以下の33種類の事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。
(1)物品販売業 (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業
(4)物品貸付業 (5)不動産貸付業 (6)製造業
(7)通信業 (8)運輸業 (9)倉庫業
(10)請負業 (11)印刷業 (12)出版業
(13)写真業 (14)席貨業 (15)旅館業
(16)料理店その他の飲食業(17)周旋業 (18)代理業
(19)仲立業 (20)問屋業 (21)鉱業
(22)土砂採取業 (23)浴場業 (24)理容業
(25)美容業 (26)興行業 (27)遊技所業
(28)遊覧所業 (29)医療保健業 (30)技芸・学力教授業
(31)駐車場業 (32)信用保証業 (33)無体財産権の提供等
を行う事業
NPO法上の特定非営利活動に該当する事業でも、上記の33業種に当てはまれば、原則として法人税法上の収益事業となり、法人税の申告義務があります。
<消費税>
NPO法人は、消費税に関して消費税法別表第三に掲げる法人とみなすことがNPO法で規定されているため、公共法人や公益法人等と同じ扱いになります。
つまり、消費税の仕入税額控除に関して一般の事業者と異なり、補助金、会費、寄付金等の対価性のない収入(以下「特定収入」という)により賄われる課税仕入れ等の消費税額を仕入控除税額から控除する調整が必要となります。
<地方税>
NPO法人が収益事業を行っているかどうかにかかわらず、地方税の申告義務はあります。ただし、収益事業を行っていない場合には、住民税の均等割が免除されることが多くあります。(管轄都道府県、市町村の条例によって決まります。)
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年5月23日 月曜日
平成17年5月23日(第146号) ~売れる条件を重ねましょう~
今回は、小売店を例に挙げ、販売分析の一例をご紹介させていただきます。
〈チェック項目〉
※売上金額が高かったときのことを分析する
1.環境・社会背景と商品の関係は、どうであったか
2.集客手段・時期
3.どのようなイベント開催時に集客の効果があったか
4.お客様へのアプローチの方法と声かけはどうであったか
5.ニーズ・購買時のメリットと商品・価格帯はどうであったか
6.どのようなセリングポイント・セールストークを使ったか
7.どのような販売ツールを活用したか
8.販売している自分のフットワークは、どうであったか
9.客単価を上げるために、どのような工夫をしたか
10.次の機会の購買に結びつけるために、どのような工夫をしたか
〈アドバイス〉
1.その時期に必要とされている商品の売る時期を逃さない
2.CM・DM・ちらし・新聞・雑誌掲載等、様々な販促媒体が有る
3.お客様はどのようなメリットにより、自店に足を運んで下さったか
4.商品を売りつけようとせず先にニーズを訊く・読む・その後勧める
5.同じ商品でも近隣同業他社より、ほんの少しでも安いこと
6.お客様により多少異なるが、売れるトークは繰り返し使える
7.ターゲット層にマッチしたマスコミ・雑誌情報を上手に活用する
8.買う人と買わない人の見極めを迅速に五感で判断する 「時は金」
9.ニーズに合った商品を短時間で紹介する・購買商品との関連性
10.あればさらに生活が充実する商品を理由を加えて紹介する+自身の考えたPRを追加する
*自社商品・サービスの提供(前・中・後)に安心・安全・信頼を
*固い話ばかりせず、ユーモアで相手の心をほぐす・場を和ませる
(スマイルグループ 接客販売インストラクター)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年5月 8日 日曜日
平成17年5月8日(第145号) ~従業員の兼業について~
しかし、多くの会社では、兼業を禁止している就業規則が作成されていると思います。
しかも、それが懲戒(解雇)の用件になっています.一方で兼職・兼業は、就業時間外に、かつ、会社設備外で行われます。これはあくまで労働者の私生活に該当する行為ですから、使用者の労働契約上の権限が及ばない範囲といえます。
したがって、裁判上も兼業・兼職の禁止規定は有効としつつ、具体的な兼業・兼職の内容を判断して、職場秩序に悪影響を及ぼす場合や、労務の提供に支障を生じさせるような場合に限り懲戒(解雇)を認めるということになっています。
具体的にいいますと、兼業先での労働により遅刻欠勤が増えるような場合や、競業会社の取締役に就任したなどの場合であれば、懲戒(解雇)の対象になり得ますが、業務にまったく支障をきたさない毎朝2時間程度の新聞配達等は、懲戒(解雇)に該当する兼業には該当しないと判断されます。
従業員がこっそりアルバイトをしていたという理由をもって、直ちに懲戒(解雇)にするのは避けてください。
その他、注意すべき点として、他の職場による労働時間と御社での労働時間を合わせて、
1日8時間を超えるようであれば、割増賃金の対象になってくることが挙げられます。そのことを忘れてしまわれることが多いですので、ご注意ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年4月23日 土曜日
平成17年4月23日(第144号) 「人材投資促進税制」って何?
<内容>
当期教育訓練費を直近2期分の教育訓練費の平均額より増やした企業を対象として、その増加額の25%を法人税額から控除できる制度です。(法人税額の10%を限度)
<中小企業者の特例>
上記の内容に代えて、以下の内容で税額控除を受けることが出来ます。
教育訓練費の額に特別税額控除割合(注)を乗じて計算される金額が法人税額から控除できます。(法人税額の10%を限度)
(注)特別税額控除割合
教育訓練費増加割合(当期の教育訓練費が直近2期分の平均額を控除した金額をその過去2年間の平均額で割った割合)の2分の1(100分の20を限度)
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年4月 8日 金曜日
平成17年4月8日(第143号) 定年延長が義務化されます!!
1.必要な措置
定年を定めている事業主は、高年齢者の安定した雇用を確保するため、
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければなりません。雇用を終了する年齢は、年金定額部分の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせ、下記のように平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくものとします。
平成18年4月1日~平成19年3月31日 定年年齢62歳
平成19年4月1日~平成22年3月31日 定年年齢63歳
平成22年4月1日~平成25年3月31日 定年年齢64歳
平成25年4月1日~ 定年年齢65歳
2.継続雇用制度
現に雇用している高年齢者が希望する場合に、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。これには
(1) 定年年齢が設定されたまま、定年に到達した従業員を退職させることなく引き続
き雇用する『勤務延長制度』と、
(2) 定年に到達した従業員をいったん退職させた後、再び雇用する『再雇用制度』の
二つがあります。
再雇用あるいは勤務延長する従業員について、この制度を適用する基準を定めることができます。しかし、「会社が特に必要とする」など、実質的に基準がないような取り決めはできません。基準に該当するかどうかを労働者が予見でき、そのレベルに到達していない従業員に対して能力開発等を促すことができるような具体性を持つものでなければなりません。
3.助成金
定年の引き上げまたは65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を、新たに導入した事業主や、高年齢者事業所を設立し継続雇用制度を設けた事業主には、「継続雇用定着促進助成金」が支給される場合があります。詳細については下記までご相談ください。
法律の施行は現在より1年後ですが、必ず文書化することが求められています。就業規則の改訂や労使協定等の作成が必須であり、人事評価の見直しその他、関連するいろいろな作業が必要となりますので、早速着手しないと間に合わなくなります。お急ぎください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年4月 1日 金曜日
平成17年4月1日(臨時号)...平成17年4月から育児・介護休業法、年金制度等が変わります!!
1.育児介護休業法の改正(下記は主な改正事項)
(1)育児休業・介護休業の対象労働者が一定の範囲の期間雇用者まで拡大
(2)育児休業期間の延長
一定の場合には子が1歳6ヵ月に達するまで育児休業ができます。
(3)介護休業 取得回数制限の緩和
1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで介護休業ができます。
(4)子の看護休暇の創設
1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できます。
2. 次世代育成支援の拡充
(1)子が3歳に達するまで育児休業期間中の保険料を免除
育児休業等の間の厚生年金保険料免除措置が、最長で養育する子が3歳になるま
でに延長されます。
(2)育児休業等を終了したときに保険料を改定
育児休業等を終了して職場復帰したとき3歳未満の子を養育している場合、申出
を行うことにより、月額変更届による随時改定や、次の算定基礎届による定時決
定を待たなくても標準報酬月額を改定することができるようになります。
(3)勤務時間の短縮等の措置で勤務した場合の標準報酬の取扱い
子が3歳になるまで勤務時間の短縮等の措置を受けて勤務し、標準報酬が養育開
始前より下がった場合、申出を行うことによって、将来受ける年金額に不利が生
じないように老齢厚生年金の額の計算を行ううえでは養育開始前の報酬があると
みなして年金額を算定する制度が導入されます。なお、保険料は実際の標準報酬
に応じて徴収されます。
3.60歳台前半の在職老齢年金の「一律20%カット」の廃止
60歳から64歳までの方が厚生年金に加入し報酬と老齢厚生年金のどちらも受けている場合、報酬が低い場合でも年金額の20%が一律に支給停止されていました。平成17年4月からは一律20%の支給停止が廃止され、総報酬月額相当額と、老齢厚生年金の月額との合計が28万円を超えるときに調整を行うことになります。
4.平成17年3月以前の第3号被保険者の届出忘れの救済措置
平成17年4月からは、特例として届出を行うことによって国民年金第3号被保険者の未納期間を保険料納付済期間とすることができます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2005年3月23日 水曜日
平成17年3月23日(第142号) ~不動産登記法が改正されます~
105年ぶりとなった今回の改正は、インターネットを経由して登記申請をすることに
より、国民の負担の軽減・利便性の向上を図ることを目的としています。
〈改正事項と改正の流れ〉
1.平成17年3月7日から法務局での手続きが変更
(1)「権利証(登記済証)」がない場合の「保証書制度」を廃止し、より充実させたイ.「事前通知制度」とロ.「司法書士等の有資格者代理人による本人確認情報の提供制度」が新たに導入されました。イ.は売主等登記義務者に対して、本人限定郵便によって登記申請があった旨の通知が行われます。これに記名押印(実印)して法務局に申し出たときに初めて登記が実行されます。ロ.はイ.を省略して登記申請できる特則です。具体的には、申請代理人である司法書士がその責任においてその内容を本人確認情報として法務局に提供するものです。
(2)従来の「登記原因証書」がない場合の「申請書副本」添付による登記申請は廃止され、「登記原因証明情報」の提供が必要的となります。具体的には、「売買契約書・領収書」「抵当権設定契約書」等で、これらの書面には当事者の署名または記名押印が必要となります。従来の委任状への押印のみではできなくなりました。
2.その後、順次オンライン申請が可能な法務局として、法務大臣の指定を受けた法務
局(オンライン指定庁)ごとに次の点が変更
(1)オンライン申請をする場合 : すべての添付情報をオンラインを利用して電磁的記録により送信しなければなりませんので、それが可能であるのか、特に登記識別情報・電子署名・電子証明書が用意できるのかを確認する必要があります。
(2)書面申請する場合 : 書面による申請であれば、指定後もすべての法務局で可能です。ただし、指定後はオンライン申請が法務局の開庁時間外でも送信可能であることから、朝一番に書面による申請をしてもその日の1番の受付とは限りません。
3.「権利証」から「登記識別情報」への移行
これまでは登記が完了すると登記済証(権利証)が交付されていましたが、今後は買主等の登記名義人に「登記識別情報」が通知されることになります。それは法務局が無作為に選んだ12桁の英数字からなり、この番号を知っていることが当該不動産の権利者としての確認資料のひとつとなります。ただし、すでに発行されている「権利証」は書面にする登記申請の際に提出することが原則となります。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年3月 5日 土曜日
平成17年3月5日(第141号) 「高額医療費貸付制度」をご存知ですか?
この高額療養費の決定は病院等から提出されるレセプトの審査を経て行われるので、請求してから支給されるまでに約3ヵ月程度かかり、医療費が高額な場合は家計のやりくりが大変になります。
そこで、全国社会保険協会連合会では、その間の医療費の支払いにあてる資金を無利子で融資する「高額医療費等貸付事業」を各都道府県の社会保険協会と協力して行っています。
1.貸付を受けられる方
政府管掌健康保険及び船員保険の被保険者であって、本人又は家族についての高額療養費の支給が見込める方。
2.貸付を受けられる額及び所要日数
高額療養費支給見込額の8割相当額が、申し込み日から10日程度で貸付られます。
3.申込み方法
次の書類を各都道府県の社会保険協会に提出します。
(1)高額医療費貸付申込書及び借用書
(2)医療機関が発行した保険点数のわかる医療費請求書
(3)高額療養費の受領を全国社会保険協会連合会に委任する委任状
(4)健康保険被保険者証
4.貸付金の返済と精算
高額療養費が支給されましたら貸付金と精算し、2割相当の残額は本人に返金します。
提出先・お問い合わせ
社団法人全国社会保険協会連合会 貸付事業課
〒108‐8583 東京都港区高輪3丁目22番12号 TEL:03-3445-0823(ダイヤルイン)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年2月23日 水曜日
平成17年2月23日(第140号) ~介護保険料率が平成17年3月から変わります~
11.1/1000(会社負担・本人負担共に5.55/1000)
↓
12.5/1000(会社負担・本人負担共に6.25/1000)
となります。詳細は社会保険庁発行のリーフレット(事業主の皆様へ-介護保険料率が平成17年3月1日から変わります)をご覧ください。
~雇用保険料率が平成17年4月1日から変わります~
雇用保険料が平成17年4月から19.5/1000(会社負担11.5/1000・
本人負担8/1000)となります(一般事業の場合)。
※農林水産業や清酒製造業=21.5/1000(会社負担12.5/1000・本人負担9/1000)建築業= 22.5/1000(会社負担13.5/1000・本人負担9/1000)
~個人情報保護法が施行されます~
個人情報保護法が平成17年4月1日から民間の事業者にも施行されます。
個人情報取扱事業者となるのは、過去6ヵ月間に1回でも個人情報データの保有数が5千人分を超える事業者で、個人情報取扱いに関する諸規定の整備や従業員への教育および安全管理措置等が義務付けられます。しかしながら、個人情報取扱事業者でなくとも事業として個人情報を扱っている場合は、個人情報保護法の遵守は必要とされます。
※個人情報の洗い出しは、たとえば従業員のAさんの情報がパソコン上の給与計算ソフト内にある、紙ベース上の労働者名簿、履歴書、賃金台帳にあるとなると、それぞれ別々に洗い出し、管理を個別に行うようご注意ください。
個人情報保護規程の作成・従業員教育・プライバシーマーク取得コンサルのご用命は下記へお問い合わせください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年2月 5日 土曜日
平成17年2月5日(第139号) ~内定取り消しの注意点~
1.内定の法的性格
最高裁判所の判断によると、会社側が入社誓約書を受領した時点で、解約権留保付始期付雇用契約という一種の雇用契約が結ばれたとされています。
2.内定者の地位
「就労の有無という違いはあるが、採用内定者の地位は、一定の試用期間を付して雇用関係に入った者の試用期間中の地位と基本的には異なるところはない。」とされており、試用期間中の労働者と同じ扱いをするべきとの解釈がなされています。
3.内定取り消しの扱い
極度の経営状況の悪化、急激な経済状況の変化等々の正当な理由もなく、内定を取り消したり、本採用を拒否したりする事は出来ません。正当な理由もなく内定を取り消せば、損害賠償を請求されます。また、内定を取り消し、撤回あるいは内定期間を延長しようとするときは、あらかじめ公共職業安定所等に届けでる必要があります。(職業安定法施行規則第35条)
4.内定取り消しをしても問題のない場合
・ 提出書類や面接で虚偽の事実を申告していた。
・ 内定後に犯罪を犯し、信頼関係を著しく損ねた。
・ 就業に耐えがたい重度の病気になった。
・ 単位不足で卒業できなくなった。
配置転換の申し出等、内定取り消し回避の努力を行なっても、どうしても内定を取り消さないといけない場合は、解雇予告手当て相当の金額を支払う意思を伝えるなどの措置を講じて下さい。そうしないとトラブルに発展する可能性があります。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年1月23日 日曜日
平成17年1月23日(第138号) お客様とスタッフの声を聞くシステムを作りましょう
お客様のニーズ・ウォンツをしっかり捉え、自社の商品やサービスに反映させることは、言うまでもありませんが、スタッフ各自の思いやアイデアを訊き反映させることも、同様に大切なことです。スタッフは、自分なりの考えやアイデアを持っています。顧客満足度を高めることと同様、スタッフの職務満足度("やる気"や"やりがい")も高めましょう。両者は、繋がっていることが多いのです。
他企業スタッフの声
◆「いろいろな委員会を設置しているが、いつも対応しているのは一部の人間。これでは虚しすぎる。」(スタッフ人数 約400名の企業)
→提案例:スタッフに"知らない間に会社が動いている意識"を持たせない。スタッフ全員が会社の経営に携っている意識を持ち、参画できるシステムを作る。全員が何らかの委員会(サークル・勉強会等)に参加でき、その中で役職・雇用形態を問わずフラットに意見を言い合える環境を作っている企業や、時間がとりにくい場合、部門ごとにスタッフが週1回1時間早く出社して、会議を行なっている企業もある。小売店・病院等、シフトが交替制の場合は、常に店長(院長)にスタッフ各自から、気兼ねなく質問や提案のメ-ルを送れるシステムを作ったり、提案事項等を、メモに書いて投書できるシステムを作っているところもある(その場合は、スタッフからの一方通行でなく、店長(院長)側からの回答を内部の掲示板等に貼っている)。
...一方通行でなく相互でコミュニケーションをとることがポイント!
◆「現場(直行直帰が多い)で、いつもこれでいいのかと自分の行動に確信がもてないときがある。研修の時に、その行動がよかったのか悪かったのかがわかるが、日常、いろいろなことが起こるので、どうしたらよいのかと悩む時がある。」
→ 提案例:現場で困った時、いつでも他のメンバー全員にすぐ連絡できるシステムを作る(例:携帯のメール等通信システムを使いこなし、各自の現場が離れていても、すぐに悩みや問題が解決できる環境を作る)。問題は、解決しないでおいて置くと、時間の経過と共に、悪化する場合がある。 ...問題発生→解決に寸時対応できるシステムを作る
プラスα
企業にとって、販売方法等(「こうして、売上が伸びた」等スタッフの成功事例)は、
メンバ-全員で共有することが大切...商売は水物なので、売れる時期には、売れる条件を一度にできるだけに多く重ね、いかに集中的に売上を上げるかがポイント
今、消費者は、生活に様々な不安を抱えている。自社の商品・サービスは、どの分野で、
お客様の不安を解消し「安心」「安全」を提供できるか。消費者の不安項目に対する解決策と、自社商品・サービスの関連性を見出すこともテーマだと思われます。
(スマイルグループ 接客販売インストラクター)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年1月 8日 土曜日
平成17年1月8日(第137号) 新年明けましておめでとうございます。今年もご安全に!!
飛躍のためには、まず心身ともに健康であることが必要です。労働災害があっては個人も企業も健康状態とは言えません。今年はより一層健康に留意し、安全に仕事を進めましょう。
先日の大津波で十数万人の命が失われたとされていますが、その報道を見ていると、人々が津波に対して驚くほど無知であったことが分かります。海岸に住んでいて地震があったら、まず津波の危険を考えるのが日本人の常識ですが、インド洋沿岸にはこの知識がなかったとのことです。津波には最初に水位が下がる場合と、いきなり水位が上がる場合とがあるということが説明されていましたが、これを知っていたらプーケット島などの犠牲者の数は遥かに少なくなっていたでしょう。一方、遠く離れたスリランカの方では地震も感じず、水位が下がることなく、いきなり高い波が押し寄せたのですから、被災はやむを得なかったのでしょう。それでも、地震発生から数時間もたってからの津波襲来ですから、警報システムが機能していれば避難の方法は幾らでもあったに違いありません。わが国でも津波警報が出たのに避難指示を出さなかった自治体があって問題になっていましたので、大丈夫と安心していられる状態ではないようです。
労働安全でも同じことです。
安全教育
情報伝達
を軽視してはなりません。新しく採用した従業員には「雇入れ時の教育」を、作業内容が変更された場合には「作業内容変更時の教育」を行わねばなりません。特に厚生労働省令で定められた危険または有害な43業務については、安全または衛生のための特別な教育を行わなくてはなりません。安全については、何よりも企業トップの姿勢、言動が重要です。「安全については○○君に任せてある。」と、安全管理体制のタガを緩めている企業トップは是非考えを改めて頂きたいと思います。大きい事故はこのような企業でよく起こっています。社内の危険因子をヒヤリ・ハット報告などで汲み上げ、リスクアセスメントを行うなどによって危険を予知し、全社にその情報を流して大事故になる前に危険の芽を摘み取っていくことが必要です。
では、今年もご安全に!
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年1月 1日 土曜日
平成17年(臨時号)...労災上乗せ保障の準備はできていますか?
「労働者災害補償保険法」は、労働災害に対して法的に保護する法律です。しかし、使用者の安全配慮義務違反をはじめとした民事上の賠償責任については、前号でご案内したとおり網羅していません。
そこで、労災給付を超えた補償責任が生じた場合にも対応できるよう、「労災上乗せ保障」についてご案内します。今回はなかでも労災上乗せ保障に加入した場合のメリットについて、事業主側からお伝えします。
(※保険会社、共済等各機関により保障内容は異なります。以下に記したメリットはご
参考までとしてください。)
〈労災上乗せ保障とは〉
使用者は、労災保険給付の価額の限度を超える損害について、民事上の損害賠償責任
を免れることはできません。このような責任を果たすため、企業で生命・損害保険また
は共済制度を導入することにより、労災保険でカバーされない保障を行うのが「労災上
乗せ保障」です。
〈メリット1:事業主が保障を受け取れる〉
事業主を受取人とした場合、被災労働者休業期間中の代替要員確保にかかるコストを、
保険給付で賄うことができます。
〈メリット2:加入できる対象が労災保険より広範である〉
労災保険に加入していない、役員や一人親方まで加入できる保険商品もあります。
〈メリット3:労災発生後にすばやく対応できる〉
労災認定を待たずに、治療のために自己負担した費用や休業補償を簡単に受け取れる
保険商品もあります。
〈メリット4:掛金を損金計上できる〉
掛金を全額経費として損金処理できる場合が多くあり、税制面で優遇されます。
労災上乗せ保障を導入する場合、保障内容について災害保障規程等により定める必要が
あります。詳しくは下記までお問い合わせください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年12月23日 木曜日
平成16年12月23日(第136号)...~所得税関係の改正点~
<平成17年から適用される改正で、すでにきまっているもの>
1.老年者控除の廃止
納税者本人が65歳以上で、その年の合計所得金額が1000万円以下の場合に適用されていた控除(控除額50万円)です。これが廃止となります。
2. 公的年金等控除額の変更
公的年金等控除のうち、年齢65歳以上の者の上乗せ措置が廃止されました。また老年者特別加算として、年齢65歳以上の者の公的年金等控除の最低保障額が50万円加算され、120万円とする特別措置が講じられました。
3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の縮小
<平成17年度の税制改正大綱>
12月15日に平成17年度税制改正大綱が発表されました。主だったものは、以下のものです。
1. 定率減税の縮小(所得税は平成18年1月から、個人住民税は平成18年6月から)
所得税における定率減税とは、年間の個人所得課税の税額を一定の割合で一律に削減する減税方式を言い、現在所得税の20%相当額(上限25万円)が差し引かれていますが、改正により10%相当額(上限12.5万円)の控除となります。
個人住民税における定率減税は、現在個人住民税所得割額(上限4万円)の15%が差し引かれていますが、改正後は7.5%相当額(上限2万円)の控除となります。
2.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用される中古住宅の範囲の拡大(平成17年4月1日以後居住分から適用)
現在は新築されてから20年(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石、レンガ造等は25年)以内の住宅であることとされていますが、改正後は築年数に関係なく地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準または、これに準ずるものに適合する中古住宅についても控除されます。
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年12月 8日 水曜日
★第135号(12/8)民事施行法施行令の改正で差押え可能な給与の範囲が変更に★
民事施行法の差押えが禁止される金銭の額に関して、「標準的な世帯の2ヵ月の必要生計費を勘案して政令で定める額」とるする改正が今年度なされています。このがくについての政令は次の通りです。
1. 計算の根拠は「66万円」
総務省統計局による直近の統計資料によって掲げられた勤労者の世帯の一世帯当り消費支出額を参考に、標準的な2ヵ月の必要生計費が「66万円」とされました。これをもとに、差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額について、次のように定められています。
ア 支払期が毎月と定められている場合・・・33万円
イ 支払期が毎半月と定められている場合・・・16万5000円
ウ 支払期が毎旬と定められている場合・・・11万円
エ 支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合・・・33万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額
オ 支払期が毎日と定められている場合・・・1万1000円
カ 支払期がその他の期間をもって定められている場合・・・1万1000円に当該機関に係る日数を乗じて得た金額に相当する額
キ 賞与およびその性質を有する給与に係る債権に係る法第152条第1項の政令で定める額・・・33万円
2. 天引きできる額は減った
この政令は平成16年4月1日の改正法施行にあわせて施行されました。法改正で養育費の取立てなどでも強制執行が可能になっていますが、手取り40万円の社員についてこれまでは毎月19万円を差押えることが可能(21万円が差押え禁止)でした。今後は7万円しか差押えができなくなったということになり、注意が必要です。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2004年11月23日 火曜日
平成16年11月23日(第134号)...~証券仲介業さらなる分野で解禁~
証券会社に顧客の株式売買などを取り次ぐ証券仲介業が2004年4月1日から企業や個人事業者に解禁されましたが、12月からは銀行などの金融機関にも解禁されます。
1.証券仲介業とは
証券会社等(証券会社または登録金融機関)の委託を受けて、その証券会社等のために以下の行為を業として行うもので、内閣総理大臣の登録を受けて営むことができることとされています。
(1)有価証券の売買等の媒介
(2)有価証券の募集もしくは売出しの取扱い
証券仲介業者の業務内容は、取引の勧誘等の事実行為に限定され、所属証券会社等の代理権はなく、顧客口座は証券会社等が保有・管理することとなり、代金の受け渡しや有価証券の預託は契約した証券会社が行います。なお証券仲介業者は、役員、使用人のうち勧誘行為を行う者について、証券外務員登録を受けなければなりません。
2.証券仲介業参入のメリット
この制度により会計事務所や生命保険や損害保険の代理店、あるいはファイナンシャルプランナーなどが証券仲介業者となることが予想されています。実際に各証券会社はこの制度を利用して、株式などの販売網の拡大に乗り出す契約や意思を発表しています。さまざまな業種からの証券仲介業参入のメリットは、個人投資家にとって自分の好みの証券の相談窓口に出会う機会が増えることにあります。したがって従来のように敷居の高さを感じることなく証券市場に参加できるようになります。この制度は証券市場の構造改革の一環として実施されるものですが、これにより証券取引がより身近なものになり、国民に証券投資が広まると期待されています。
3.証券仲介業参入における注意点
一見便利そうに見えますが、一方で登録を受けていない業者が証券仲介業者と偽って、株式取引の勧誘を行うことも想定されます。証券仲介業者を利用しようとする投資家は、金融庁のホームページや財務局などで、利用しようとしている証券仲介業者が登録された業者であるかどうかを確認することが大切です。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年11月 8日 月曜日
★第133号(11/8)改正「高齢者雇用安定法」への対応★
高年齢者雇用確保措置
1. 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主
雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、(1)定年の引き上げ(2)継続雇用制度の導入
(高年齢者が希望するときは、定年後も引き続いて雇用する制度)(3)定年の定めの廃止のいずれかを講じなければなりません。
2. 書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めたとき
事業主が事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に
係る基準を定めたときは、継続雇用制度を導入したものとみなされます。(この場合希望者全員としなくても構いません)
高年齢者雇用確保措置に関する特例等
1.定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置に係る年齢
平成25年4月1日までに下記の通り段階的に65歳へ引き上げるものとされています。
平成18年4月1日~平成19年3月31日 定年年齢 62歳
平成19年4月1日~平成22年3月31日 定年年齢 63歳
平成22年4月1日~平成25年3月31日 定年年齢 64歳
平成25年4月1日~ 定年年齢 65歳
2. 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主
平成25年3月31日までの間、高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を図るための必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
3. 大企業、中小企業のすべてが対象
大企業は施行後3年間、中小企業は施行後5年間、上記2の労使協定締結のための協議が調わないときは、就業規則等で対象労働者に係る基準を定めることができます。しかし、この規定も時限措置なので、労使協定で継続雇用の基準を定める方向で検討しておいた方が良いでしょう。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2004年10月23日 土曜日
平成16年10月23日(第132号)...所得税の源泉徴収制度
会社や個人が、人を雇って給与等を支払ったり、弁護士、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度一定額の所得税を源泉徴収することになっています。
2.納付期限
源泉徴収した所得税は、原則として、源泉徴収した翌月の10日までに国に納めなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満である場合は、年2回納付の特例(注)があります。
(注)この特例の対象となるのは、給与、退職金及び弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士等に支払った報酬にかかる源泉所得税だけです。
3.源泉徴収義務者
この所得税を源泉徴収して、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではなく、給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1)二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている個人
(2)弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている個人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
4.不納不加算税
源泉所得税を納期限までに納めないと「不納付加算税」というペナルティーが課されます。自主的に納期限後に納めて税額の5%、税務署から言われて納めると、税額の10%もの不納付加算税が課せられてしまいます。
また、延滞税も法定納期限の翌日から納付までの日数により、課されます。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年10月 8日 金曜日
★第131号(10/8)平成16年10月分から厚生年金料率が改正されます★
厚生年金保険の保険料率が、将来の保険料水準を固定した上で、給付水準を自動的に調整する仕組みが導入されることに伴い、平成16年10月分から0.354%ずつ毎年引上げられ、平成29年9月以降18.3%で固定されます。
尚、健康保険料(介護保険料含む)については、現行どおりで変更ありません。
1 .一般の被保険料(介護保険料含む)については、現行どおりで変更ありません。
現行保険料 13.58%→平成16年10月分から 13.934%(11月納付期限分)
平成17年以降は、毎年9月に0.354%ずつ引上げられます。
平成29年9月以降は、18.3%で固定されます。
2. 上記に加えて、全被保険者の標準報酬月額の平均額の2倍を基準として標準報酬月額の等級や標準賞与額の上限が改定されることになります。
各都道府県の最低賃金が平成16年10月1日から改正されます。
京都府最低賃金 現行677円/1時間 改正 678円/1時間
大阪府最低賃金 現行703円/1時間 改正 704円/1時間
滋賀県最低賃金 現行651円/1時間 改正 652円/1時間
最低賃金の対象となる賃金は、次の賃金を除外したものになります。
(1) 精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2) 時間外・休日及び深夜手当
(3) 臨時に支払われる賃金
(4) 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2004年9月23日 木曜日
平成16年9月23日(第130号)...~従業員の心の病~
8月20日に発表された「産業人メンタルヘルス白書」によりますと、約6割の企業で、「心の病」にかかる従業員が増加傾向にあると回答しています。特に30代という働き盛りの年齢層が半数を占めている状況です。また、約7割の企業が1ヵ月以上休職をする従業員が存在していると回答しています。今後は従業員の心の健康にも気を配らないと、企業経営に影響を与えてしまう可能性があります。
では、企業としてどのような対策を取ればいいのでしょうか。まずは不調者を出さないという事に重点をおく必要があります。つまり、「不調者・病人の早期発見・早期治療」より「労災・事故等の発生防止」「疾病予防・健康の保持増進」に力を入れる必要があるのです。そうすることにより、不調者の増加・休職日数の増加を抑制する事になります。今後は安全衛生委員会等で、従業員の心のケアについても議論されることをお勧めします。
次に、長期休業している従業員の対策についてですが、多くの企業が就業規則等で「休職が長期におよび職場復帰の見込みがない者は退職とする」と定めていると思います。しかし、従業員が納得した退職に持っていくのは、実際にはなかなか難しいものです。そこで従業員の障害年金受給を積極的に支援することも考えましょう。あまり知られていないことですが、うつ病でも障害年金が支給されます。しかも、長期の休業をしているという事は、その旨の診断書を会社に提出しているはずです。労働に制限を加える、もしくは労働することが困難と証明されますと年金の支給対象になることがあります。そこで、会社としては年金の受給を支援したという誠意を示し、且つ、年金が支給されるという事は国が働けないと認定したという事実を持って、従業員に退職を促されると良いと思います。そうすることにより、労使紛争に発展する危険性を排除できると思われます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年9月 8日 水曜日
★第129号(9/8)厚生年金基金加入継続に警告!★
※注 代行制度:国の老齢厚生年金の給付のうち事前積立が可能な部分(報酬比例部分の一部)について、掛金の徴収、積立、給付を行う仕組み
ところが、この厚生年金基金制度は、加入員の減少や保険料収入の伸び悩みに加え、長引く低金利による年金資産の運用成績の悪化などにより、基金の維持、存続が困難になっています。基金の運用利回りは、昨年度はプラスとなったものの平成12年度からのマイナス連続の影響は簡単には消せません。今までなら、5年に一度の掛金率の見直しの時期である財政再計算時に掛金率引上げで対応できていました。5年の間には、運用利回りの悪い時期もあれば良い時期もあり、それらが打ち消しあって、そう極端なことにならずに済んでいたのです。このようなマイナス運用の連続は基金始まって以来のことであり、各基金とも対応に苦慮し、代行返上、保険料の引上げや年金受領額の抑制を考えざるを得なくなるなど、多くの問題が生じてきています。脱退や解散も続出しています。厚生年金基金に加入されている事業所は、保険料を滞りなく支払っている場合でも、別途積立不足金の
負担が必要となります。まず、基金の積み立て不足をご確認ください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2004年8月24日 火曜日
平成16年8月24日(臨時号)...運転中の携帯電話使用への罰則が新設されました
平成16年6月9日に成立した、運転中の携帯電話の使用に罰則を設けた改正道路交通法の施行を前に、平成16年8月24日、道路交通法施行令の改正が閣議決定され、違反した場合の反則金額が正式に決まりました。
1.運転中の携帯電話使用に罰則が適用
これまでは、通話や注視により「交通の危険を生じさせた場合」に限って罰則の対象としていましたが、携帯電話による事故の未然防止には十分とはいえませんでした。そこで、今年6月に成立した改正道交法では、運転中に携帯電話を手に持つなどして会話をしたり、メールの送受信などで画面を注視するだけで罰せられ、「5万円以下」と定められました。正式な反則金額は、大型車が7,000円、普通車と自動二輪車が6,000円、原付き自転車が5,000円で11月1日から施行されます。ただし、違反しても期限内に反則金を納付すれば、罰金を科す刑事手続きには進まないとしています。
※ カーナビゲーションの使用は、従来通り、危険を生じさせない限り違反にはなりません。
※ 運転中の携帯電話の使用により交通の危険を生じさせた場合には、従来通りの罰則が適用されます。
・ 罰則「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」
・ 違反点数2点反則金
(大型1万2千円、普通9千円、自動二輪7千円、原付6千円)
2.酒気帯び検査拒否への罰金を最高30万円に
厳しい罰則が設けられたことにより、飲酒運転による事故は減少傾向にありますが、その反面、飲酒運転取締りでの酒気帯びの呼気検査を拒否する運転者が増えてきています。そこで呼気検査拒否に対する罰金が、「5万円以下」から酒気帯び運転に対する罰金と同額の「30万円以下」に引上げられました。
いずれも平成16年11月1日に施行されます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年8月23日 月曜日
★第128号(8/23)職場内の人間関係Ⅰ(忠告・説得のしかたについて)★
◆忠告のしかたについて
忠告前に考慮すべきこと
忠告には相手の行動を改めさせる目的をもっています。相手の立場を傷つけず、愛情や相手を思いやる心をもって忠告しましょう。
・ポイント
(1)事実関係を調べ、原因を明確にし、どこまで忠告するかを予測する。
(2)忠告する時・場所を考える→他人の前での忠告は反発感情を引き起こすため控える。1対1が原則
(3)詫びる気持ちを持って一貫した基準を持って話す。
(4)他の人と比較、内容追加、すり替え、追い詰めの忠告をしない。
(5)励ます。
(6)忠告を受けた方には痛みを伴う。それを取り除くために、あとから、声をかけるなどして、痛みを癒す努力をする。
(7)失敗を取り返すだけのチャンスを与える。
◆説得のしかたについて
説得前に考慮すべきこと
説得は、相手側の拒否する立場を受け入れてもらうために話をすることです。相手は、その内容に対し、能力的(できるだろうか)、経済的(資金)、物理的(時間がかかる)、心理的(恐れ)不安が伴いますので、それらの不安を取り除くようにしましょう。
・ポイント
(1)相手の気持ちに余裕がある時のタイミングを掴む。
(2)相手と話をするチャンスを積極的に作る。
(3)先手を打つ。(期限を定める、選択制にするなど)
(4)補助力を利用する。(代理の方に話してもらう、食事等打ち解けた雰囲気で話す)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2004年8月 8日 日曜日
平成16年8月8日(第127号)...消費税の届出関係
ところで、消費税の適用を受けるための届出書等の提出に関して、提出間違いも多いので、提出期限に特に注意が必要な主だったものをまとめました。
(1)消費税簡易課税制度選択届出書
簡易課税制度を選択しようとするとき(注1)
・・選択しようとする課税期間の初日の前日まで(注2、3)
(2)消費税簡易課税制度選択不適用届出書
簡易課税制度の選択をやめようとするとき(注1)
・・選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで (注2)
(3)消費税課税事業者選択届出書
免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき(注1)
・・選択しようとする課税期間の初日の前日まで(注2、3)
(4)消費税課税事業者選択不適用届出書
課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき(注1)
・・選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注2)
(注1)消費税簡易課税制度選択届出書又は消費税課税事業者選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
(注2)提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
(注3)事業を開始した日の属する課税期間から消費税簡易課税制度選択届出書又は、消費税課税事業者選択届出書に係る制度を選択する場合には、これらの届出書は、その事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出すれば、その課税期間から選択することができます。 (スマイルグループ 税務担当)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年7月23日 金曜日
★第126号(7/23)単身赴任の「帰宅」が労災の適用対象になります★
実現は早ければ平成18年春の見通し。
現行の労働者災害補償保険法は、通勤災害の適用対象を自宅と就業場所との往復に限っており、例えば単身赴任者が単身赴任先の自宅から家族の住む家族宅に戻る途中に交通事故にあっても、一定条件以外は労災の対象外だった。しかし、持ち家や子供の進学の影響などで単身赴任は避けられないものであり、増加傾向にあると指摘。赴任先と家族宅の移動で生ずる危険も業務と関連するものとした。
・対象とする時期
単身赴任者の帰宅の場合 家族宅へ帰るとき→仕事を終えた当日か翌日
赴任先へ戻るとき→勤務日当日かその前日
※注 移動中に家族と一緒にレジャー施設に行くなど、業務と関係ない場合は対象から除外される。
一方、副業など2つ以上の仕事を持つ「二重就労者」についても、企業の副業禁止規定の見直しやワークシェアリングの広がりで、今後さらに殖える可能性があると指摘。「職場間の移動は次の職場で労務を提供するために不可欠な行為」とし、適用対象に加える必要があると判断した。厚生労働省は今月をメドに中間報告を取りまとめ、必要な制度改正につなげたい考え。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2004年7月 8日 木曜日
★第125号(7/8)CRMって何? その5★
前回「コールセンターの裏側」をお話すると予告しましたが、最近非常に沢山のニュースに出てくる個人情報保護につきましてお話をしたいと思います。
CRMの基本となる、顧客データベース(顧客台帳)は、個人情報の集まったものです。
個人情報保護法は、今年既に成立し、来年4月から施行されます。個人情報としては、氏名、住所、職業のみならず、個人の映像や,メールアドレスなども個人が特定できる場合、保護の対象となります。(経済産業省指針)
DMを送信するためには、メールアドレスが必要ですが、このアドレスもyamada-taro@yous.co.jp(ユーズ社の山田太郎さん)というような表記の場合、個人情報となります。
さて、この個人情報の取扱いについてのポイントをいくつかピックアップしますと、本人が会員登録した先が本人の同意無しに、別の業者に名簿を渡したりすることはもちろんのこと、本人が希望していない情報を送ることも出来ません。(目的外利用) さらに、登録した本人から、自分の個人情報の利用状況の開示を請求された場合、開示の義務や個人情報の漏洩を防ぐための社内システムの構築(これには、外注先のみならず、社員との雇用契約に厳しく盛り込む企業もでてきます。)なども必要になり、企業側の負担はかなり大きくなります。
この個人情報保護法は、5000人以上の個人情報を管理している事業者は全てを規制対象としており、病院、人材派遣、金融業などは、重点対策業種となっています。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2004年6月23日 水曜日
★第124号(6/23)出向先法人が支出する給与負担金の報酬と賞与の区分★
法人の使用人が他の法人に出向した場合に、この出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給しているため、出向先の法人が自己の負担すべき給与相当額を出向元の法人に給与負担金として支払っているときは、法人税法上、出向先の法人が出向者に給与を支払ったものとして取り扱われます。出向者が出向先の法人でも単なる使用人であれば、、この負担金が給与でも賞与でもいずれも損金となります。
ところが、出向者が出向先の法人で役員になっている場合には、役員賞与については損金に算入されませんので、給与負担金のうちどの部分が報酬でどの部分が賞与かを確定する必要があります。この給与負担金が、報酬にあたるか賞与にあたるかの区分については、次の2つの給与の支給形態に応じてそれぞれ次のようになります。
(1)出向元の法人が出向者に給与を支給するたびに、その支給額の範囲内で、給与負担金が支出される場合
この場合、出向元の法人が支給する給与が定期の給与か臨時の給与かの区別によって、報酬と賞与に区別します。
(2)給与負担金が一定の期間内に出向元の法人が出向者に支給する給与の合計額の範囲内で、毎月定額または、一括して支出される場合
この場合、その給与負担金のうち出向元の法人が定期の給与として支出した金額までは報酬となり、これを超える部分の金額は賞与になります。
なお、出向先の法人が、出向元の法人の支給する給与の額を超えて給与負担金を支出している場合には、その超えた部分は給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて特に合理的な理由がない場合は,出向元の法人に対する寄付金などとして取り扱われるkとおになりますので注意してください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2004年6月 8日 火曜日
平成16年6月8日(第123号)...これだけは知っておきたい年金の基礎知識
国民年金の加入者については、3種類の被保険者がありますが、会社を退職されて無職となった場合、また自営業者となった場合、被扶養配偶者となった場合などと、変更される場合があります。今回は、最近問題になっている被保険者の種類を変更する場合の典型的な数例について、お話いたします。
1.社会保険に加入していた会社を辞めて、無職となった場合、又は個人の自営業者となった場合
被保険者の種類 第2号被保険者 ⇒ 第1号被保険者
届 出 ア.第2号被保険者の資格喪失は、会社が管轄社会保険事務所で資格喪失手続を行います。
イ.会社で資格喪失証明書を交付してもらい、その証明書と年金手帳を持参して、住所地の市・区役所で第1号被保険者への変更手続きを行います。
保 険 料 保険料は月額13,300円(平成16年度)(半年分、一年分前納の場合は、割引あり。)
(1)失業等給付を受給していない、収入が無いため保険料が全額払えないという場合 ⇒ 申請免除
失業等給付を受給していない、世帯主又は配偶者の前年所得(1月~6月までは前々年)が政令で定める額以下(※1)で、しばらく収入を得られないことを証明できれば、保険料の申請免除を行うことができます。申請免除は、申請のあった日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料について行えます。ただし、免除申請の時期が遅くなれば、それだけ免除開始月が遅れます。
※1 政令で定める額 ア.扶養親族等の数に1を加えた数×35万円+扶養親族があるときは、24万円
イ.障害者、寡婦の場合は、125万円
(2)収入が少ないが、保険料は半額なら払えるという場合 ⇒ 半額免除
世帯主又は配偶者の前年所得(1月~6月までは前々年)が政令で定める額以下(※2)で、しばらく収入が少ないことを証明できれば、保険料の半額免除の申請を行うことができます。
申請免除は、申請のあった日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料について行えます。ただし、半額免除の申請時期が遅くなれば、それだけ免除開始月が遅れます。
※2 政令で定める額 ア.扶養親族等がない場合 68万円
イ.扶養親族等がある場合 扶養親族等の数×38万円+68万円
ウ.障害者、寡婦の場合は、125万円
2.結婚をして(社会保険に加入していた)会社を辞め、配偶者(社会保険に加入している勤務者)の扶養者となったとき
被保険者の種類: 第2号被保険者 ⇒ 第3号被保険者
届 出 : 第2号被保険者の資格喪失は、会社が管轄社会保険事務所で資格喪失手続を行います。
配偶者が厚生年金制度や共済組合加入の場合
年金手帳を配偶者の勤務先事業主(又は共済組合)へ提出し、「第3号被保険者の届出」をその勤務先事業主(又は共済組合)を通じて行ってもらいます。
※結婚して氏名や住所が変わる場合は、氏名や住所の変更届もいっしょに行ってもらいましょう。
保 険 料 : 保険料負担はありません。
年金に関するご質問・ご相談は、お気軽にお問合せください。 (スマイルグループ:社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年5月23日 日曜日
平成16年5月23日(第122号)...土壌汚染対策法について
土壌汚染とは
土壌汚染対策法は2003年2月に施行されましたが、土地が鉛や砒素(ひそ)などの重金属やエチレン(ドライクリーニングや金属製品の洗浄に使う。)などの揮発性有機化合物が土壌中に蓄積された状態をいいます。地中に埋った産業廃棄物によっても汚染されることがあります。土壌汚染が発覚した土地は浄化対策を行わない場合、土地の資産価値を著しく下落させる事態を招き、対策を行う場合でも費用が高額となるケースがあり、地価の低い地域によっては土地価格がマイナスになることもあります。
土壌汚染の心理的嫌悪(スティグマ)減価率は20~30%
某機関が某市の居住者を対象に実施した「土壌汚染に対する市民の意識調査」によると、過去に土壌汚染が存在したが、現在は浄化された土地(不動産)の購入について、回答者の65%が「汚染の事実がある以上購入しない」と答えており、22%が「いわゆるスティグマ分の減価があれば購入する」と回答、「何とも思わない」という回答は6%しかありませんでした。また、スティグマ分の減価率に関しては、20%と30%の回答が多く、次に50%で、このことは賃貸借の場合でもほぼ同様の結果となっています。2000年の出来事ですが、大阪府豊中市で某大手不動産会社が分譲中のマンション建設現場において発覚した土壌汚染が、予想以上に近隣住民からの反響が大きく、7割がた完成していたマンションを取り壊して更地に戻した事がありました。
所有不動産のリスク管理
リスク管理としては、 1.リスク分析に基づき、地下タンクや配管の更新計画などの土壌汚染防止計画を策定する。 2.汚染の早期発見により、地下タンクの内容量の在庫管理の徹底など汚染範囲の局所化を図る。 3.汚染発覚時の対応方法(危機管理プログラム)を策定する。 4.ボイラーの燃料タンク、ガソリンスタンド、運送業等の給油施設、タンクが地上で地下配管のケース等、特に注意が必要です。(工場を除く)
土壌汚染と鑑定評価
新不動産鑑定評価基準の改正点のひとつに土壌汚染が価格形成要因として追加されました。不動産鑑定士は公的資料調査、登記簿・見聞等による地歴調査を行い、土壌汚染の有無及びそれと不動産の価格との関連について検討、考察を行っております。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年5月 8日 土曜日
平成16年5月8日(第121号)...~エンジェル税制~
<制度の概要>
エンジェル税制とは、その対象となる特定中小会社の発行した株式(以下、特定株式)について、(1)投資時点、(2)株式公開前の期間、(3)株式公開後においての譲渡所得の課税の特例のことです。
(1)投資時点・・・投資金額の控除の特例
特定中小会社に払込による投資を行ったとき、投資した年度の他の株式譲渡益から投資額を控除できる規定です。
(2)株式公開前の期間
価値喪失株式の損失の金額の特例・・・特定中小会社の解散等により、特定株式の価値が喪失した場合、一定の要件のもとに、譲渡損失とみなして、他の株式譲渡益との損益通算や損失の繰越控除を受けられる特例です。
譲渡損失の繰越控除の特例・・・特定株式について生じた譲渡損失について、一定の要件のもとに3年間の繰越控除が受けられる特例です。
(3)株式公開後※・・・特定株式に係る譲渡所得等の課税の特例
一定の要件を満たす、特定株式の譲渡益については、その金額を1/2に圧縮できる特例です。※一定の場合は、未公開の段階でも可。
エンジェル税制については16年度税制改正においても、証券会社や投資ファンドを通じた場合、投資先企業に係る適用要件のうち、試験研究や事業化に係る費用を一定以上支出することや外部資本が1/6以上などの要件が免除されたこと、また、未公開段階でのM&Aなどによる株式譲渡益の圧縮特例の適用など、要件手続きが大幅に緩和されています。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年4月23日 金曜日
平成16年4月23日(第120号)...~次世代育成支援対策推進法~
平成15年7月16日に次世代育成支援対策推進法が公布・一部施行されました。
右の図に示した人口推計によれば、わが国の人口は2007年頃に最大となり、以後減り続けると推定されています。特に問題なのは15~64歳の生産人口が減少することです。
政府は平成11年の「少子化対策推進基本方針」の閣議決定以来、種々の対策を実施してきましたが、昨年、「次世代育成支援に関する当面の取組方針」を取りまとめるとともに、地方公共団体及び企業における10年間の集中的・計画的な取り組みを促進するための「次世代育成支援対策推進法」及び地域における子育て支援の強化を図るための「児童福祉法の一部を改正する法律」を国会に提出し、両法は平成15年7月16日に10年間の時限法として公布施行されました。
次世代育成支援対策とは、子供が健やかに生まれ、育成される環境の整備のための、国若しくは地方公共団体が講じる施策、又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取り組みをいいます。そのために、
(1)主務大臣は、基本理念にのっとり、市町村行動計画、都道府県行動計画、一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画の策定に関する指針を定めなければなりません。(この指針は平成15年8月22日に告示されており、30ページもありますが、次のURLでアクセスできます。http://mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/sisin.html)
(2)市町村、都道府県は上の指針に基づき、目標を定め、5年ごとに行動計画を策定しなければなりません。(平成17年4月1日施行)
(3)従業員の数が300人を超える事業主は、指針に即して行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出なければなりません。従業員が300人以下の事業主においては、行動計画の届け出は努力義務とされています。(平成17年4月1日施行)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年4月 8日 木曜日
★第119号(4/8)消費税について★
1.個人事業者の方
平成15年度の課税売上高が1千万円を超えていれば、平成17年度から課税事業者となります。この3月の確定申告で、課税売上高が1千万円を超えた方は、今年中に、「課税事業者選択届出書」の提出が必要となります。(この届出書を前年中に提出するのは、税務署からの申告書や納付書の送付をスムーズに行うためという意味合いがあるようです。)
2.法人の方
消費税改正は平成16年4月以後開始する課税期間から適用されますので、3月末決算の法人であれば、今事業年度から適用されます。
免除点を判定する「基準期間」は、前々事業年度となりますが、3月末決算の法人であれば、平成14年4月~平成15年3月の課税売上高が1千万円を超えていれば、今事業年度から課税事業者となります。(そのため、前年度中に「課税事業者選択届出書」の提出が必要となっています。)
◆課税売上高とは・・免税点の判定に使われる課税売上高は、以下のような算式で計算される売上高です。
国内で行った課税資産の譲渡等の税抜対価の合計額 - 売上に係わる税抜対価の返還等の合計額
※1 輸出取引等の免税売上高は課税売上高に含めます。
※2 課税資産の譲渡等に係わる貸倒れは、課税売上高から控除されません。
※3 基準期間において免税事業者であった場合のその基準期間中の課税売上高には消費税が課税されていませんから、基準期間の売上高を
計算するときに、税抜き処理を行う必要はありません。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2004年3月23日 火曜日
★第118号(3/23)「裁判員制度」が実施されたら★
「裁判員制度」とはどういうものか、従業員が裁判員に選出されたらどうしたらよいのかなどについて以下に述べてみます。
◆「裁判員制度」とは
「裁判員制度」とは、裁判官3名と裁判員6名による合議体で、重大事件の有罪・無罪および刑の量定に関して審理・裁判を行います。
対象となる事件は原則、次とされています。
(1)死刑、無期懲役、または禁錮にあたる罪にかかる事件(内乱罪を除く)
(2)法定合議事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪のもの
◆裁判員はくじで選ばれる
裁判員は20歳以上の有権者から選ばれます。選挙人名簿をもとに有権者から裁判員候補者名簿が作成され、くじで選定された「裁判員候補者」が召喚され、選任に支障がないかを確認する質問手続きを経て選出されます。裁判員の候補から除かれるのは、心身の故障のため職務遂行に支障がある者や、国会議員などの公職にある者、法律の専門家、被告人・被害者の関係者等です。また裁判員を辞退できる者は、70歳以上の者、会期中の地方議員、学生・生徒、過去5年以内に裁判員に選任されたことがあるもの、重い疾病や障害を持つなどやむを得ない事由がある者に限定されます。
すなわち、裁判員に選ばれれば公判期日の出頭が義務づけられ、たとえ「仕事が忙しい」という理由であっても、出頭を拒否することはできません。
出頭した場合は、旅費・日当・宿泊料が支給されますが、出頭しなければ過料が課されることもあります。今後、従業員が裁判員に選出された場合、出勤上の扱いをどうするか、対応が必要です。
◆裁判員には厳しい守秘義務が課せられる
裁判員は、評議の経過など職務上知り得た秘密を漏らすことを生涯禁止され、守秘義務違反には、懲役・罰金刑が課されます。また、万が一被告人の関係者から金銭を受け取ったら増収賄罪、裁判を批判したら刑事罰も適用される模様です。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2004年3月 8日 月曜日
平成16年3月8日(第117号)...~企業価値の分析手法~
近年、新聞等でM&Aに関する記事も多くなり、その買収金額も場合によっては数千億円から数兆円といった非常に高額にのぼる場合があり、興味をもって読まれることが多いのではないでしょうか。これらの買収額の決定にあたって用いられる価値算定方法(バリュエーション方法)には、現在複数の考え方があり、今回はその基本的な考え方について取り上げたいと思います。
◆一般的な株式の評価方法
<純資産法>
純資産法は、会社の有する資産より負債の額を控除した株主の持分としての純資産の価値によって株式価値を評価する方法です。
<DCF法 (Discounted Cash Flow Method)>
DCF法とは、会社が将来獲得すると期待される現金ベースの収益(キャッシュフロー)を現在価値に引きなおすことによって、企業価値を算定する方法です。
<乗数法>
乗数法とは、公開会社の中から業種、規模等の類似する比較対象会社を抽出し、それらの会社の財務数値と株価の関連性を考慮した乗数を選定の上、評価対象会社の当該財務数値に乗じることで企業価値を算定する方法です。
<類似業種比準法>
類似業種比準法は非公開会社の評価にあたり、評価対象会社と、業種・規模等が類似する公開会社と、利益・純資産・配当等の項目で比較して、非公開会社の株式価値を算定する方法です。相続税法上とられている評価方法で、財産基本通達において詳細な評価方法の記述があります。
<配当還元法>
配当還元法は、配当額を一定の割引率で割り引くことによって算定する方法です。
(スマイルブループ:公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年3月 1日 月曜日
平成16年3月1日(臨時号)...~時間外労働の「特別条項付き協定」が平成16年4月1日から変わります~
平成16年4月1日から、時間外労働の限度に関する基準において「特別条項付き
協定」を締結する場合の「特別の事情」は「臨時時なものに限る」ことを明確にする
改正が施行されます。そのポイントを以下にのべます。
なお、詳細は別紙「時間外労働の限度に関する基準」(厚生労働省パンフレット)を
ご覧ください。
◆限度時間を超えて時間外労働を行なわせなければならない特別の事情
できるだけ具体的に定めることが必要になります。
◆「特別の事情」
一時的又は突発的であること、全体として1年の半分を超えないことが見込まれ
るものを指します。
◆限度時間を超えることのできる回数
限度時間を超える期間が1年の半分以下となるような、回数の定め方が必要にな
ります。
~介護保険料率が平成16年3月1日から変わります~
政府管掌健康保険料率が、平成16年3月分(4月納付期限)から1.11%(従前は0.89%)になります。
なお、詳細は、社会保険庁発行のリーフレット(事業主の皆様へ-介護保険料率が平成16年3月1日から変わります。)をご覧ください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年2月23日 月曜日
平成16年2月23日(第116号)...不良債権処理就業支援特別奨励金
不良債権処理の加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所(雇用調整方針を策定した事業所)からの離職を余儀なくされた支援対象者を雇入れる事業主に対し、不良債権処理就業支援特別奨励金が支給されます。
●雇用調整方針 不良債権処理の加速に伴い、離職を余儀なくされる人に対する体系的な
再就職支援を行うために、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、雇用
調整の見通し、対象者等を盛り込んだ方針を作成し、都道府県労働局に
届け出ていただくもの
●支援対象者 雇用調整方針を提出した事業所を離職した方として、「雇用調整方針対
象者証明書」の交付を受けた30歳以上60歳未満の方
不良債権処理就業支援特別奨励金
1.常用雇用支援の奨励金
受給要件(1)雇用保険の適用事業所であること
(2)支援対象者を常用労働者として雇入れること
(3)雇入れの直前6ヵ月間から奨励金支給までの間に事業主都合の解雇が発生していないこと
(4)タイムカード(または出勤簿)、賃金台帳、労働者名簿を整備していること
受給金額 支援対象者1人当たり60万円(新規・成長分野は70万円)
申請時期 雇入れ日から起算して3ヵ月を経過した日から1ヵ月以内
2.トライアル雇用支援の奨励金
受給要件 常用雇用支援の奨励金の受給要件(1)(3)(4)に該当し、対象者
をハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介によりトライアル雇用として受け入れること
受給金額 トライアル雇用後、常用雇用に移行した場合
※支援対象者1人当たり45万円(新規・成長分野は55万円)
トライアル雇用後、常用雇用に移行しなかった場合
※支援対象者1人当たり月額5万円(上限3ヵ月)
申請時期 常用雇用に移行した日の3ヵ月後から1ヵ月以内
常用雇用に移行しなかった場合はトライアル雇用の終了した日から
1ヵ月以内
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年2月23日 月曜日
★第114号(2/23)不良債権処理就業支援特別奨励金★
◆雇用調整方針 不良債権処理の加速に伴い、離職を余儀なくされる人に対する体系的な再就職支援を行うために、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、雇用調整の見通し、対象者等を盛り込んだ方針を作成し、都道府県労働局に届けていただくもの
◆支援対象者 雇用調整方針を提出した事業所を離職した方として、「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた30歳以上60歳未満の方
不良債権処理就業支援特別奨励金
1.常用雇用支援の奨励金
受給要件 (1)雇用保険の適用事業所であること「
(2)支援対象者を常用労働者として雇入れること
(3)雇入れの直前6ヵ月間から奨励金支給までの間に事業主都合の解雇が発生していないこと
(4)タイムカード(または出勤簿)、賃金台帳、労働者名簿を整備していること
受給金額 支援対象者一人当たり60万円(新規・成長分野は70万円)
申請時期 雇入れ日から起算して3ヵ月を経過した日から1ヵ月以内
2.トライアル雇用支援の奨励金
受給要件 常用雇用支援の奨励金の受給要件(1)(3)(4)に該当し、対象者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介にによりトライアル雇用として受け入れること
受給金額 トライアル雇用後、常用雇用に移行した場合⇒支援対象者一人当たり45万円(新規・成長分野は55万円)
トライアル雇用後、常用雇用に移行しなかった場合⇒支援対象者一人当たり月額5万円(上限3ヵ月)
申請時期 常用雇用に移行した日の3ヵ月後から1ヵ月以内
常用雇用に移行しなかった場合はトライアル雇用の終了した日から1ヵ月以内
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2004年2月 8日 日曜日
平成16年2月8日(第115号)...平成16年度の税制改正大綱
昨年12月17日に平成16年度税制改正大綱が決定されました。主だったものは、
次のとおりです。(平成17年度から適用される改正を除きます。)
1.青色欠損金等の繰越控除期間の延長
青色欠損金等の繰越控除期間が、現行の5年から7年に延長されます。これは平成13年4月1日以降開始事業年度から生じた欠損金から適用されます。そのため実質的には平成19年度から負担軽減の影響が現れることとなります。またこれに伴い、欠損金額にかかる更正の期間制限が5年から7年へ、過少申告にかかる更正の期間制限が3年から5年へそれぞれ延長されます。
2.住宅ローン減税の延長
10年間に渡り年最大50万円を税額控除できる現行制度が、1年間延長されます。平成17年度以降は制度自体は残るものの段階的に縮小されます。
3.住宅売却時の譲渡損失繰越控除制度
5年超所有の住宅ローンのある住宅を売却した場合、その売却損(ローン残高-売却額)を売却した年の翌年以降3年間にわたり繰り越して控除することができます。ただし、合計所得金額が3,000万円以下の年分に限られます。
4.土地譲渡益課税の軽減
5年超保有の土地を譲渡する場合(長期譲渡所得)の税率が、26%(所得税20
%、住民税6%)から20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げられます。保有期間が5年以内の土地を譲渡(短期譲渡所得)する場合の税率も、52%(所得税
40%、住民税12%)から39%(所得税30%、住民税9%)に引き下げられます。
5.土地、建物等の譲渡に係る損失の損益通算不可
土地、建物等の長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越を認められません。
6.上場株式等以外の株式(非上場株)の譲渡益課税の軽減
非上場株式の譲渡益にかかる税率が、26%(所得税20%、住民税6%) から
20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げられます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年1月 8日 木曜日
★第113号(1/8)「CRM]って何? その4★
新年あけましておめでとうございます
さて、みなさんは、年賀状をどの位出されましたか?
前回(89号)、DMと顧客データベースのお話をしましたが、顧客データベースに当たるものが住所録です。本文の作成もさることながら、宛名書きの生産性アップには感動します。住所録を整備しておけばプリンタがドンドン勝手に印刷してくれます。また、受け取った年賀状は本文を読みながら「来年用」に住所録訂正作業を行い、いつも面倒で年末まで先送りしていた作業を同時に完了できるようになって、仕事、生活両面で非常に大きな時間節約となりました。
また、受け取った年賀状の本文には、家族構成、年齢などが書かれており、前回(89号)お話した顧客データベースと共通する情報が一杯掲載されています。
顧客一人一人の情報を把握し、それを分析、活用して顧客の好みにさらに合った商品を開発、販売し、ずっと良いお客様になって頂くことがCRMの目標です。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2004年1月 1日 木曜日
平成16年1月1日(臨時号)...改正労働基準法が今年1月からスタート
改正労働基準法が今月1月1日から施行されています。そのなかからいくつかポイントをみていきましょう。
◆労働条件の明示について
解雇ルール(解雇は、客観的に合法的な理由を欠き、社会通念上相当であるとないと認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする)が労基法に明記されたことに伴い、就業規則・雇い入れ時に使用者が明示すべき労働条件にも「解雇の事由」を含めることが必要になりました。
◆有期労働契約について
有期労働契約期間の上限が、原則3年に、一定の高度で専門的な知識を有する者・満 60歳以上の者については5年に延長されました。また、雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している場合には、更新しない旨を明示されている者を除いて、雇い止めの予告は契約期間満了日の30日前までに、また、雇い止めの理由について労働者から証明書の請求があれば、遅滞なくこれを交付しなければならないとされました。
◆裁量労働制の対象範囲拡大について
企画業務型裁量労働制の対象範囲が拡大されました。たとえば適用対象事業場の基準については、一定の要件のもとで本店・本社に限定しないこととされました。また、労使委員会の決議要件が、全員合意から「5分の4以上」に緩和され、労働者代表委員の信任手続が廃止されました。
◆時間外労働の限度基準の制限について (平成16年4月1日以降に締結・更新された協定から適用)
いわゆる「特別条項付き36協定」について、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情は、「臨時的なものに限る」こととされました。運用通達によると、特別延長のできる期間は1年のうち半分を超えてはならず、また、その事情も「業務の都合により」というような抽象的な理由は認められなくなります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2003年12月 8日 月曜日
★第111号(12/8)就業規則、36協定の本社一括届出について★
就業規則と36協定の届出について、本社と各事業場の内容が同一である場合は、本社を管轄している労働基準監督署に一括して届出することができるようになりました。
◆一括届出をすることができる就業規則、36協定とは?
・就業規則については、本社と各事業場の内容が同一のものに限られます。
・36協定については、協定事項のうち「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数」以外の事項が同一で
あるものに限られます。
◆就業規則について
書面による届出の場合
(1)本社を管轄する労働基準監督署に、本社を含む事業場の数に対応した必要部数の就業規則を届出します。
(2)各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署長名を届出事業場一覧表に附記する必要があります。
(3)本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則は同一の内容であることが必要なため、届出事業場一覧表の欄外等に「本社の就業
規則と同一の内容である」旨を、また、就業規則変更の届出の場合には、これに加えて「変更間円の就業規則の内容は本社の就業規則と 同一の内容である」旨を明記します。
(4)就業規則の届出に添える意見書の意見聴取の手続きは、一括届出を行う場合でも、各事業場ごとに行う必要がありますので、注意してください。 もちろん意見聴取した意見書は、各事業場ごとの就業規則に添付します。
◆36協定について
(1)本社を管轄する労働基準監督署に、本社を含む事業場の数に対応した必要部数の36協定を届出する必要があります。(事業の種類、事業の名称、 事業の所在地(電話番号)、労働者数以外は同一内容であること)
(2)一括届出に際しては、各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署長名を明確にする必要がありますので、届出事業場一覧表を添えてください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年11月23日 日曜日
★第110号(11/23)固定資産の減損会計の適用指針★
企業会計基準委員会はこのほど、2006年3月期から義務化される固定資産の減損会計の適用指針を正式に発表」しました。
工場や店舗などの固定資産で時価が薄価を5割以上下回る場合や、3期連続して営業赤字が見込まれる場合は損失処理の
候補にします。固定資産には有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が含まれます。
回収可能価額の算定
減損損失を認識すべきであると判定された資産または資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額)まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とします。
正味売却価額について
正味売却価額を算定する場合には、以下のようにして求められた資産または資産グループの時価から処分費用見込額を控除して行われることになります。
(1)市場価格が存在する場合には、原則として、市場価格に基づく価額を時価とします。
(2)市場価格が観察できない場合には、合理的に算定された価額が時価となりますが、不動産については原則として「不動産鑑定 評価基準」に基づいて算定します。
再評価を行った土地について
「土地の再評価に関する法律」により再評価を行った土地については、再評価後の帳簿価額に基づいて減損会計を適用します。この場合、減損処理を行った部分に係る土地の再評価差額金は取り崩すこととなると解されますが、法律の定めのjもとで1回限りの臨時的かつ例外的に行われた土地再評価差額金は、売却した場合と同様に、剰余金修正を通して未処分利益繰り入れます。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年11月 8日 土曜日
★第109号(11/8)決算公告★
決算公告は「株主総会終了後、遅滞なく」公開することが義務づけられているため、3月期決算企業の株主総会が集中する6月の下旬に決算公告も一斉に発表されます。決算公告は、法定の公告ですが、一方で、法の義務によらない決算情報の告知を知識する企業も増え始めています。例えば、商法では規定のない連結決算の情報を決算公告に併記し、投資家や債権者により詳しく透明性の高い情報を伝えようとする企業も増えています。また、平成13年の商法改正で、インターネットでの決算情報の公開も認められ、ホームページ等でも情報を公開する企業もあります。
公告を怠りまたは不正の公告をした場合には、行政罰として、「100万円以下の過料に処す」と定められています。(商法第498条第1項2号、商法特例
法第30条第1項第9号)しかし、中小企業のほとんどが公告をしていないというのが実態です。
決算公告の料金ですが、官報の場合ですと、全国一律で2枠分59126円、3枠分88689円です。日刊新聞紙の場合は、官報より高く幅はありますが、数十万円くらいです。ホームページ等での開示は、低コストでできます。
ホームページでの開示方法
1.ホームページのアドレスを登記する必要があります。
2.ホームページに自社の貸借対照表(要旨ではなく全文。注記を含む)を掲載します。
※注 資本金5億円または負債合計200億円以上の会社は損益計算書の公告も義務づけられています。
3.一度掲載した計算書類は、5年間継続して掲載する必要があります。
※注 新しく公告を行う会社は、初年度は直近の分だけで結構です。
4.掲載するホームページは、自社のホームページでなくても構いません。
決算公告を行っていない中小企業がほとんどですが、商法に違反していて、望ましい状況ではありません。ホームページ上での開示を含めて、決算公告を考えてみてください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年10月23日 木曜日
★第108号(10/23)労働の安全さ
わが国の平成14年度の労働災害統計を見ますと、
死亡者は 1,658人
4日以上休業した人は 約12万6千人
労災保険で治療を受けた人は 約55万人
この数は減少を続け、ここ30年間にそれぞれ約3分の1になりました。それでもまだまだ多いですね。「うちの会社は安全だ。」と思っていても、全国平均程度なのか、良いのか、それとも悪いのか?比較するには何らかの数値データが必要です。労働災害発生の程度を知るのに使われている基本的な指標が2つあります。度数率と強度率です。
2.度数率
百万延実労働時間当たりの休業労働災害の死傷者数を示したものが度数率です。同一人が複数回被災した場合にはその回数とします。
度数率=死傷者数÷延労働時間数×1,000,000
平成14年度の全産業の度数率は1.77でした。仮に一人の労働者が年間2,000時間働いたとすると、従業員数500人の企業では、1年に百万時間になりますから、この企業で1年に2名が休業するような労働災害を被ったとすると、平均より少し上ということです。50人の企業では5年に一人の休業災害という割合になります。
3.強度率
いわゆる赤チン災害は無視し、労働者が休業した災害だけを取り上げて、休業日数を累計し、延実労働1,000時間当たりの損失日数で災害の大きさの程度を示すのが強度率です。強度率では損失した日数を合計するわけですが、死亡した場合は、365日ではなく、7,500日が失われたとします。労働災害による身体障害に応じて1級から14級までの等級がありますが、それぞれに損失日数が決められています.
強度率=損失日数÷延労働時間×1,000
平成14年度の強度率の全国平均値は0.12でした。御社の安全さは如何でしたか。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年10月 8日 水曜日
★第107号(10/8)平成15年度の消費税改正にご注意★
(1)免税点の引き下げ
(2)簡易課税制度の改正
(3)中間申告制度の改正
(4)消費税の総額表示
中小企業、個人事業者にとっては、(1)(2)の改正はとても大きな影響を与えるものとなりました。
(1)免税点の引き下げについて
納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限(免税点)が、改正前は3,000万円でしたが、改正により1,000万円に引き下げられました。
(2)簡易課税制度の改正について
簡易課税制度をてきようすることができる基準期間における課税売上高の上限が、改正前は、2億円以下でしたが、改正により5,000万円に引き下げられました。
(1)(2)について留意すべき点は、「基準期間」というのはその年(課税期間)の前々年になるということです。改正消費税は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されますから、個人事業者であれば平成17年度の課税期間から適用され、「基準期間」は平成15年度ということになります。(法人で3月決算の会社であれば、16年3月期の課税期間から適用され「基準期間」は平成15年度3月期)。このため、今年の売上から、課税売上と非課税売上とを区分して帳面をつけておく必要があります。
もし、今年の課税売上が1,000万円を超えることになれば(かなりの事業者が該当することになるといわれています)、たとえ平成16年度の売上が1,000万円以下となっても平成17年度には、消費税の申告・納付が必要になります。また、今年の課税売上高が5,000万円を超えれば、自動的に本則課税制度が適用になるため、仕入税額控除を受けるために帳簿や証憑をきっちり記入するなどの準備を整えていく必要が出てきます。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年9月23日 火曜日
★第106号(9/23)職場におけるメンタルへルス対策★
このため厚生労働省では、授業場において事業者がメンタルヘルス対策を進める上で実施することが望ましい事項について示した「事業場における労働者の心の健康づくりのてめの指針」を策定し、その普及、定着を図っています。
◆うつ病を軽視するな!
多くの自殺の背景には、躁(そう)うつ病、精神分裂病、人格障害、アルコール依存症、薬物依存など何らかの精神疾患が関与している。特に重症のうつ病では
一般人口に比べ自殺の危険度が20倍高いといわれている。朝早くに目覚める等の不眠の症状は要注意だ。
◆うつ病の4症状
(1)抑うつ気分 気分が沈み、訳もなく涙ぐむ。自己評価が極端に落ち込み、自信を失い自分を責める。後悔ばかりして絶望感が強まる。
(2)精神運動制止 思考能力が低下し、通常なら難なくできることに非常に多くのエネルギーが必要になる。なかなか仕事にとりかかれない、人に会うのがおっくう、決断がつきにくい。
(3)不安焦燥感 落ち着かずイライラしている状態。ひどくなると、じっとしていたり横になっていることもできず、部屋中を歩き回ったり、髪をかきむしったりする。
(4)自律神経症状 不眠、食欲不振など、うつ病に表れる身体症状。患者も家族も心の病気とは思わず、うつ病の診断にまで結びつかないことが多い。
◆周囲の人がうつ病患者にどう対応するか
・うつ病を疑ったら精神科専門機関の受診を勧める。(説明のつかない身体症状に注意。体調悪いのに、検査で何も見つからない場合、精神科医に 相談した方がうつ病の早期発見につながる)
・徹底的に聞き役にまわり、心の支えになる。
・患者を非難したり、安易な励ましは禁物。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年9月 8日 月曜日
平成15年9月8日(第105号)...四半期連結開示
米国では既に1970年から四半期決算が義務付けられており、2000年からは公認会計士によるレビューが必要になりました。日本においても、既に一部の企業では投資家の要請に応えるため自主的に四半期業績の開示を行っており、それは年々増加しています。東京証券取引所はこうした動きに対応するため、2003年には「四半期業績の概況」を開示することを義務付け、さらに2004年からは「四半期財務・業績の概況」を求めることになりました。
開示のタイミングについても、投資家の要請に応えるために年々決算発表のタイミングが早まっています。例えば、大手電機メーカーでは2003年3月期決算でついにすべての企業が連結決算の開示を4月中に完了しました。これはまるで連結決算早期化競争とも言えるような状況です。
なぜこのような連結決算早期化が進んでいるのでしょうか。それは連結決算発表が遅いということは、決算発表に至るまでにいろんな無駄があって遅くなっているのだろうと投資家をはじめとする外部者から判断されてしまうということが一つです。さらに、その改善努力をしていないということは情報開示に消極的だと投資家から判断されるためというのがもう一つの理由です。実際、投資家によるこのような判断が結局、企業の株価形成にまで影響を与えているのです。
従って、連結決算開示のタイミングを早めるとともに、四半期連結決算の開示に対してもできるだけ積極的に取り組むことが、株主から経営を委託されている経営者にとっては死活的問題となってきています。 (スマイルグループ:公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2003年8月23日 土曜日
平成15年8月23日(第104号)...マーチャンダイジングと商品力について
■マーチャンダイジングとは
アメリカのマーケティング協会の定義には、「企業のマーケティング目標を実現するために、ある商品、または、サービスを、最も有効な場所、時期、価格、数量で市場に提供することに伴う計画と管理」とされています。
これは、小売業者にとっては、商品選定・仕入計画・販売計画などに、相当します。
今回は、上記に必要な商品力の構成について、分析します。
■商品力の構成
1.商品の品揃え力
主力商品を中心に、商圏内で、同業他社の展示アイテム数を比較
(対象商品選定→調査対象の店舗選定→調査→アイテム比較
→自社マーチャンダイジング設定)
2.商品構成力
売場に、売れ筋商品が確保できているかを、再確認
(予算別実績把握→売れ筋商品・個数チェック→動向把握→展示個数チェック)
3.価格競争力
主力商品を中心に、商圏内で、同業他社の売価を比較
(対象商品選定→調査対象の店舗選定→調査→価格競争力比較→売価設定)
4.価格訴求力
チラシ・売場、接客において、お買得感が、お客様に伝わっているかどうかの
チェックをします
5.価値提案力
チラシ・売場・接客での商品の価値が、お客様に伝わっているかをチェック
■商品力とは
量(商品)・数(アイテム)が豊富で、品質が優れており、売れ筋が充分にあり、適切な価格であることは、もちろんのこと、その品揃え計画と、同業他社との比較により、商品の魅力を、充分にお客様に伝えているか、その結果が、売上高として顕著に反映されます。優れている店舗は、上記のポイントを充分に把握しており、また、個々のお客様からいただいた商品等への要望も、現場から、聞き逃さず、その声を上手に生かして、品揃えしています。大切なことは、店の事情で品揃え等をするのでなく、お客様の声をお聞きして、ご要望にお答えすべく、店を適宜順応させていくことです。
(接客販売 インストラクター)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2003年8月 8日 金曜日
平成15年8月8日(第103号)...<平成15年度の税制改正項目(法人関連)>
以下のような項目について改正が加わっています。
1 究開発減税の創設、拡充 (スマイル新聞97号参照)
2 備投資減税の創設、拡充
・ IT投資促進税制の創設
一定のIT関連設備等を取得した場合には、取得価額の50%の特別償却又は取得価額の10%の税額控除を受けることができる制度です。
・ 開発研究用設備の特別償却制度の創設
開発研究用設備の取得をした場合には、取得価額の50%を特別償却できる制度です。
※これらに関しては平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に取得等をして事業等の用に供した場合について適用されます。
3 中小企業・ベンチャー企業税制の創設・拡充
・ 同族会社の留保金課税
自己資本比率が50%以下の中小法人については、留保金課税を適用しない制度です。
※この改正は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
・ 交際費等の損金不算入制度
以下のように、対象法人の拡大し、定額控除額までの金額の損金不算入割合が引下げられました。
※この改正は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度に支出した交際費等について適用されます。
・ 中小企業者について、30万円未満の少額減価償却資産を取得した事業年度又は年分に全額損金算入等できる特例制度が創設されました。
※これらに関しては平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得をして事業の用に供した場合について適用されます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2003年7月23日 水曜日
★第102号(7/23)助成金関連情報★
1.中小企業基盤人材確保助成金
創業・異業種進出・経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇入れた事業主に対して、一定額を助成するものです。
基盤人材の雇入れは5人を限度とし、基盤人材以外(一般労働者)の労働者を新たに雇入れる場合は、基盤人材雇入れ数と同数を限度とします。
経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)とは・・?
(1)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有するもの。または、部下を指揮・監督する業務に従事する係長職以上の者
(2)上記(1)のいずれかに該当し、かつ年収350万円以上の賃金で雇入れられる者
受給できる事業主とは・・?
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)着手日から6ヵ月以内に「改善計画認定申請書」を提出していること
(3)着手日以降、第1期支給申請書の提出日までに事業の用に供するための費用を300万円以上負担する事業主であること
(4)基盤人材を雇入れる事業主であること
2.中小企業雇用管理改善助成金
職場への労働者の定着を促進するために、労働者に対し職業に関する相談を行うため設備・施設の設置・整備(環境設備事業)、または労働者に対し職業に関する相談を行う者(職業相談者配置事業)の配置を実施し、併せて新しい労働者を雇入れた場合、要した費用の一部を助成するものです。
受給できる金額
環境設備事業 要した費用の1/2(最高100万円)
職業相談者配置事業 職業相談者の賃金の1/3(1年分)
雇用保険の基本手当日額の最高額である330日分を限度とする。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年7月 8日 火曜日
★第101号(7/8)CRMって何? その3★
前回に引き続き、顧客ID(お客様の名前にあたるもの)のお話です。
顧客データベース(顧客台帳)は、顧客ごとのID(識別コード)を元に作成していきます。例えば、メールDMを送信するためには、メールアドレスが必要ですが、このアドレスそのものがIDとしても使えます。このID(メールアドレス)を教えてもらう為に、各社とも知恵とお金を使っています。
例えば、鞄のエースバック社では、「Hプラグ」という携帯電話用差込具を使って、自動的にメールを打ってもらいます。エース社では、このように収集したアドレス宛に携帯電話メールによる入場券を発発送しています。(社内販売用の入場券DMの半分がメールに切り替わると数百万のコストダウンが実現できるそうです。)
また、グリコ社のポッキー友の会では、現在14万人の携帯電話メールアドレスが登録されていて、新製品アイデアの調査や案内に活用しています。こちらは、当初「モーニング娘情報」をプレゼントしますということで、アドレスを登録してもらったそうです。
また、来年6月より電子政府政策の一環として全国でインターネットによる所得税、法人税の「電子申告」がスタートしますが、この電子申告を行う為に、税務署用IDを取得することになります。つい先日も税務署から「消費税が変わります。」というDMが郵便で届きましたが,将来的には携帯電話やパソコンへメールで届くことになるでしょう。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年7月 1日 火曜日
平成15年7月1日(臨時号)...受動喫煙防止が義務化
他人のたばこの煙による受動喫煙の被害防止を、初めて法律で定めた「健康増進法」が平成15年5月1日から施行されています。学校、病院、飲食店といった大勢の人が集まる場所での受動喫煙防止は「サービス」ではなく、「義務」となり、注意が必要です。
健康増進法とは...
がんや心臓病、糖尿病といった生活習慣病を防ぎ、健康長寿を目指した国の健康づくり運動「健康日本21」の法的な基盤作りを主な目的に昨年、制定された。様々な内容を盛り込んだ法律で、健康の増進を「国民の責務」と定めるなど論議を呼んだ部分もある。第25条では、公共の場所の管理者に対し「受動喫煙の防止措置をとるよう努めなければならない」と定めた。
<受動喫煙防止の措置が必要な場所>
・第25条で明示...学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務
所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設
・第25条の「その他の施設」として厚労省通知で例示
...鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船
◆禁煙関連の情報サイト「インターネット禁煙マラソン」 www.kinen-marathon.org
高橋裕子医師が禁煙支援のために開設。全国の禁煙支援医療機関のほか、全面禁煙にした学校、医療機関、官庁の一覧もある。
◆言いづらかったら...「イエローカード」
兵庫県喫煙問題研究会が作成。黄色地の名刺大の紙にメッセージを記載しており、直接言いづらい場合に、アピールできるよう作成されたカード。
送り先の住所、名前を書いた返信用の長3封筒を同封し、次へ申し込みをする。
〒651-1321 神戸市北区有野台8の4神戸アドベンチスト病院内科、薗はじめ、あて。
代金(1枚10円、50枚単位)と送料は受領後に振り込む。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2003年6月23日 月曜日
★第100号(6/23)今後は消費税改正動議に目が離せない!★
◆免税事業者の対象となる課税売上高の引き下げ
平成16年4月1日以後開始する課税期間から、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が3千万円から1千万円に引き下げられます。
◆簡易課税制度適用事業者の対象となる課税売上高の引き下げ
平成16年4月1日以後開始する課税期間から、簡易課税制度を適用できる基準期間における課税売上高の上限が2億円から5千万円に引き下げられます。
◆総額表示の義務化
平成16年4月1日以後に行われる価格表示から義務づけられます。「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することをいいます。
※注 「総額表示」の義務付けは、消費者が商品を購入する場合に、最終的な支払い総額が値札や公告を見ただけでわかるようにするものであり、事業者間取引における価格表示を対象とするものではありません。
ポイント⇒支払総額さえ表示されていればよく、「消費税額」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年6月 8日 日曜日
★第99号(6/8)総報酬制導入後の賞与支払い実務の留意点★
1.総報酬制の導入と賞与の考え方
従来行われていた賞与に対する特別保険料の届出は、平成15年3月をもって廃止、厚生年金保険の給付に反映させるため賞与の支払いについては、「賞与支払届」によって被保険者ごとの標準賞与額を届出することになりました。
標準賞与額=毎回の賞与支払額から1,000円未満切捨て
※1ヵ月につき、下弦は1,000円、上限は健康保険200万円、厚生年金150万円、同月に複数回支払う場合は合計額で決定。
賞与とは・・?
名称のいかんにかかわらず、労働の対償として支払われるすべてのもので、年間を通じて4回以上支払われる通常の報酬以外のものを賞与といい、毎年7月1日前の1年間に3回以下の回数で支払われるものが対象です。
2.賞与の保険料
保険料額=標準賞与額×保険料率
毎月の賃金からみる標準報酬月額の保険料と同率となり、保険料負担も労使折半(児童手当拠出金は全額事業主負担)です。例えば、政府管掌の場合は、健康保険82/1000,介護保険8.9/1000、厚生年金135.8/1000
3.賞与支払届と納付
支給日から5日以内に届出。事前の情報により被保険者氏名などが印字された用紙が1ヵ月前に届きます。賞与月が実態にあった登録となっているか事前確認をしてください。保険料は、納入告知書に基づき、賞与を支給した月の翌月末日に支払います。
4.賞与支給時の注意点
(1)賞与支払月の資格喪失者は、賞与の保険料は徴収不要
(2)育児休業中の方の保険料については、標準報酬月額の保険料と同様に免除
(3)40歳到達者は、到達月以降に支払う場合は、賞与から介護保険料も徴収
(4)65歳到達者は、到達月以降に支払う場合は、賞与から介護保険料は不要
※到達月 1日生まれの方は、前月の末日に満年齢に達するためご注意ください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年5月23日 金曜日
★第98号(5/23)平成15年度 相続税・贈与税の改正について★
65歳以上の親から20歳以上の子(代襲相続人を含む)への贈与について、選択制により、贈与時には軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で清算する制度です。具体的には、贈与時の非課税枠が2500万円とされ、この非課税枠を越える部分について、一律20%の税率で贈与税が課税されます。この贈与税は、相続時に相続税の計算上で精算され、払い過ぎの贈与税があれば還付が受けられます。
1.適用の選択については、受贈者である子は、兄弟姉妹がそれぞれ別個に選択するかどうかを判断することができます。また、贈与者である親も父・母ごとに選択することが可能となります。
2.贈与財産の種類や金額、贈与の回数には制限が設けられていません。
3.この制度を選択した受贈者が、この制度に係る贈与者以外から贈与を受けた場合には、その贈与財産の価額の合計額から、贈与税の基礎控除110万円を控除した後の金額に贈与税の累進税率を乗じて贈与税額を計算することになります。
4.相続税の計算に際し、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与をした時の時価とされます。
5.住宅取得資金については、65歳未満の親から贈与についても自己居住用の一定の家屋の取得または一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合、さらに1000万円の上乗せがあり、3500万円までが贈与時には非課税となります。
どちらを選択するか・・
従来からの制度を利用して、基礎控除である110万円未満を長期的に贈与し続ければ、その財産については受贈者のものとなり、相続税を課税されることはありません。住宅取得資金についても、従来の特例(5分5乗方式:平成17年12月31日まで)を選択すれば550万円までは非課税、また1500万円までは税額軽減があり、むろん受贈した財産について相続発生時に相続税を課税されることもありません。一度この新制度を選択すると、通常の贈与制度には戻れませんので、慎重に検討してから実行しなければなりません。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年5月 5日 月曜日
平成15年5月5日(第97号)...試験研究費の税額控除
1.改正点
従来は、試験研究費の額が対前年比で増加した額に対して、15%の税額控除をするという規定でしたが、平成15年度の税制改正で次のように改正されました。
(1)試験研究費の総額に対する特別税額控除
ア.従来の「増加試験研究費税額控除制度」との選択が認められる。
イ.試験研究費割合(4年間の売上高に対する平均割合)により
(試験研究費割合)
10%以上 試験研究費の総額×10%〈12%〉
10%未満 試験研究費の総額×(8%〈10%〉+試験研究費割合×0.2)
(2)産学官連携共同研究・委託研究に伴う試験研究費の別枠税額控除
(1)の税額控除に合わせて当該試験研究費に対して12%〈15%〉の税額控除ができます。
ア.〈 〉書きは、いずれも3年間の時限措置
イ.(1)及び(2)の税額控除の限度額は、当期の法人税額の20%になっています。従って、赤字の会社で納付すべき法人税額がなければ税額控除の適用はありません。
ウ.(1)および(2)の税額控除に代えて中小企業技術基盤強化のための税額控除制度があり、(1)の試験研究費割合にかかわらず12%〈15%〉の税額控除が認められます。
2. 試験研究費の集計
試験研究費を集計するためには、試験研究に携わる人を決め(出来れば組織で明確にする)、個々の試験研究案件(目的、予算等)を明確にして、それにかかった原価を把握しておくことが必要です。また、試験研究費の額を決算書に表示することによって、「研究開発型企業」のイメージを強調することもできます。 (公認会計士・税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2003年4月23日 水曜日
★第96号(4/23)試用期間について★
事業主は従業員採用の自由を持っていますので、従業員として不適当と判断した場合にはその従業員を解雇できますが、試用期間中といえども労働契約を締結して働いているわけですから、みだりに解雇することはできません。少なくとも、上の場合には事業主は30日分の解雇予告手当を支払わなくてはなりません。解雇予告手当を支払わなくてもよいのは日雇労働者で連続して雇われたのが1ヵ月未満の場合と、試用期間を明示の上、14日までに不採用を通知する場合と、2ヵ月以内の短期間雇用した場合及び4ヶ月未満の季節的労働者の場合だけです。
期間の定めのない雇用の場合には、試用期間中といえども解雇通知すると、解雇無効を訴えて裁判を起こされることがあります。試用期間中の解雇については三菱樹脂事件ほか多数の裁判例があります。三菱樹脂事件は,大学在学中に学生運動をしていた労働者がその事実を身上書に書かず、面接試験にも学生運動をしていなかったと事実を隠していたことがわかり、試用期間満了の直前に解雇されたというものです。
この労働者は、労働契約に基づく権利の確認と賃金の支払いを求めて裁判を起こしました。東京高裁は、雇用契約上の権利を認め、賃金の支払いを命じましたが、最高裁はこの判決を破棄し、東京高裁に差し戻したのです。しかし、東京高裁での差戻審で和解が成立し、労働者は現職復帰しています。結局解雇は撤回されたわけです。
就業規則に「試用期間を3ヵ月にする」と書いてあっても、無条件に解雇が認められるわけではありません。その期間内は理由が明確であれば解雇できますが、試用開始14日以後では解雇予告手当が必要です。さらに安全を期す場合は、一旦2ヵ月以内の短期雇用契約を結び、その間に求職者の適否を見て、正社員としての採用がokなら長期雇用契約に切換えるのが良いでしょう。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年4月 8日 火曜日
平成15年4月8日(第95号)...3月商法決算における実務留意点
平成15年3月期に当たって商法改正があり、実務的に留意すべき事項が非常に多くあります。1.営業報告書関係、2.決算書関係、3.株主総会関係、の区分で簡単に整理します。
1.営業報告書関係
議決権基準への改正
「大株主の状況」には議決権の割合を記載することになりました。
自己株式の取得、処分等
営業年度中に取得、処分した自己株式についての内容を記載。
取締役の責任軽減
取締役に対する責任軽減に係る定款の定めをした場合に、取締役及び監査役に支払った報酬等の額を記載。
委員会等設置会社
取締役及び執行役が受ける報酬決定方針を記載。
新株予約権の有利発行
株主以外の者に有利条件で新株予約権を発行した場合の内容を記載。
2.決算書関係
商法規定の改正等に伴う開示の変更の主なものが以下の通りです。具体的な開示方法ついては、専門家にご相談ください。
・貸借対照表の資本の部の表示方法の変更
・利益処分案の記載方法の変更
・資本の欠損の注記、1株あたり当期利益の注記にかかる計算方法の変更 など
3.株主総会関係
定款変更事項
改正後の規定の適用を受けようとする場合に、定款変更が必要となる主なものとして以下があります。
・監査役の任期が4年
・総会特別決議の定足数緩和
・各種書類の電磁的記録を書面と見なす場合
・取締役に対する責任軽減を定める場合 など
株主総会招集手続簡略化、書面による株主総会の省略
全株主の同意により招集手続が省略できたり、全株主の賛成票により総会自体を物理的に開催する必要がなくなります。
ホームページによる計算書類の公開での留意事項
5年間掲載が必要なこと、貸借対照表そのものの掲載が必要なこと。(公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2003年3月23日 日曜日
平成15年3月23日(第94号)...最 近 の 助 成 金 関 連 情 報
今春は、社会保険、労働保険ともに法改正があり、労務管理上大幅な事務手続業務の見直しが行われます。助成金についても変更時期である4月が近づいてきました。昨年と比べいくつかの助成金の廃止や新設が予定されていますが、これは主に、現在の助成金制度の利用状況等により利用率の低い助成金の廃止、浮いた財源の他の助成金への配分など、給付内容にメリハリをつける方向で検討されています。廃止、拡充が予定されている助成金は下記のとおりです。詳細については、まだ決定していないものも多いです。
また、継続雇用制度定着促進助成金については、昨年4月(および5月)以降要件の変更がありましたが、昨年度4月前に継続雇用制度の導入を行った企業については、まもなく申請期限を迎えます。受給金額が大きい昨年度要件で申請することができる企業は早めの申請手続きが必要です。
<廃止> <拡充予定>
中小企業雇用創出人材確保助成金 → 中小企業基盤人材確保助成金(仮称)
中小企業高度人材確保助成金 → に統合
中小企業雇用創出雇用管理助成金 → 中小企業雇用管理改善助成金
中小企業雇用環境整備奨励金 労働移動支援助成金
介護雇用環境整備奨励金 建設業労働移動支援助成金
地域雇用促進環境整備奨励金 在職者求職活動支援助成金
再就職促進講習給付金
継続雇用制度奨励金(3種)
情報関連人材育成事業派遣奨励金
能力再開発適応講習受講給付金
地域職業訓練推進事業助成金
派遣労働者雇用管理研修助成金
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2003年3月 8日 土曜日
平成15年3月8日(第93号)...相続税・贈与税の一体化措置について
平成15年度税制改正法案(3月4日衆院通過)では、相続税・贈与税の一体化措置(相続時精算課税制度の創設)が盛り込まれています。
この制度は現行の制度との選択制となっており、いずれか有利な方を選択することとなりますが、現行の制度を使った相続税対策との比較を行ってみましょう。
どちらが有利?
新制度では、生前贈与財産を贈与時の価額で評価するため、財産評価が将来値上がりしていく場合には、新制度にメリットがあります。例えば、業績が好調の自社株が考えられるでしょう。また、収益物件である建物も、家賃収入が子に移転され、他方、建物の評価は比較的低いため、メリットを享受できるケースといえます。 (公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2003年3月 3日 月曜日
平成15年3月3日(臨時号)...中小企業挑戦支援法について
中小企業挑戦支援法が2月1日から施行されました。
この法案の目玉としては、商法の最低資本金規制に係る特例を設け、新たに創業する者について、株式会社の場合は1,000万円、有限会社の場合は300万円という最低資本金規制の適用を受けない会社設立を認めるとともに、設立後5年間は当該規制を適用しないというものです。つまり、資本金が1円でも株式会社や有限会社が設立できるようになるということです。
また、払込取扱機関の保管証明を受ける義務等を免除するとともに、債権者保護の観点から、開示義務、配当制限等が課されます。
<ポイント>
1.最低資本金の特例は、新事業創出促進法第2条第2項第3号の「創業者」(事業を営んでいない個人であって、2ヵ月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者)であることについて経済産業大臣の確認を受けた者が設立する、株式会社及び有限会社について認められます。(以下確認株式会社及び確認有限会社という)
2.確認株式会社は経済産業大臣に、会社設立後直ちに商号等を記載した書面を、毎事業年度終了後3ヵ月以内に貸借対照表や損益計算書等の決算書類を提出し、経済産業大臣は、これらの書面を公衆の縦覧に供すること。
3.確認株式会社では5年以内に資本金を1,000万円まで増資するか、組織変更により有限会社(この場合は資本金300万円が必要)または合名会社や合資会社に変更しなければ、解散させられます。また、有限会社では資本金を300万円まで増資するか、組織変更により合名会社や合資会社に変更しなければ、解散させられます。
<消費税上のメリット>
確認株式会社は、資本金が1,000万円未満で設立されるため、通常の有限会社と同様に設立から2事業年度の間は消費税の納付義務がない免税事業者となります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2003年2月23日 日曜日
平成15年2月23日(第92号)...販売促進による売上アップの基本要素について
■プロモーションの検討
商品をお客様に伝える上で、自店ができていること、できていないことを、下記の基本項目で整理してみましょう。また必要に応じて、チェック項目を増やしていきましょう。注意する項目があればそれに対して、社内全員一丸となり、改善に取り組む必要があります。実は、店舗の売上アップは、このような現場の工夫から生まれるものが多いのです。
■基本要素
1.基本集客力...看板・駐車場・駐輪場等、集客の仕組みの構築や設備の充実度をチェック
店舗の告知は、できているか?(例:看板の場合、自転車と、自動車で来られる方では
走るスピ-ドが異なり、看板の見える距離・角度・高さも異なる)
駐車場は、入りやすいか? (例:自転車・バイク・自動車)
物理的に、入りやすいか? (例:入口について、前の道路に無駄な駐車がないか等)
2.基本売場力...店舗の環境整備、売場の基本設定力のチェック
入口付近は、快適か? (入りやすさ・清潔感・店の全体のイメージを見られる)
店舗のレイアウトは、適切か?(顧客の主道路〈顧客の8割が歩く通路〉の利用・一等
地〈何を置いても売りやすい場所 例:主道路沿い・什器のエンド等〉の活用)
3.基本接客力...お客様への礼儀・精算対応・待機等のチェック
基本態度は、充分備わっているか? (礼儀正しい態度)
精算対応は、万全か? (お客様を待たせないことは、接客の基本)
待機の仕方は、万全か? (店の場合、販売員はお客様が入りやすい動的待機を徹底)
4.商品集客力...商品を伝える要因のチェック
商品の告知は、適切な手段を用いているか? (マスコミ・チラシ・DM等)
外観での呼び込みは、できているか? (商品の外観にも魅力はあるか)
5.商品売場力...商品を売り場で伝えるための陳列やPOP活用のチェック
POPのつけ方・内容は、適切か? (わかりやすく、お買得をPRする)
品揃えは、充実しているか? (顧客は、商品を選ぶことを楽しまれる。新製品好き)
6.商品接客力...商品説明などを人を通してお客様に伝える能力のチェック
販売する者は、的確な商品知識を持っているか?(顧客の信用に繋がる)
顧客に対する接客の対応は、優れているか? (親切な対応を心がける)
固定客化に繋がっているか? (客単価を出す。低ければ、対応策を練る)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2003年2月 8日 土曜日
★第91号(2/8)平成15年度税制改正予定項目(所得税関係)の概要★
通常国会に改正案が提出され、3月末に成立する見込みの改正です。
1.配偶者特別控除の廃止
配偶者特別控除のうち控除対象配偶者(その年分の合計所得金額が38万円以下の配偶者)について配偶者控除に上乗せして適用される部分の配偶者特別控除が廃止されます。適用は、平成16年分以後の所得税についてです。住民税については、平成17年分以後について適用。
※注 合計所得金額が38万円以下・・給与所得のみの場合は年間収入が103万円以下
2.この改正で影響を受ける人
平成15年までは、パートの収入が70万円未満までは、その配偶者は、配偶者控除38万円と配偶者特別控除38万円の合計76万円の控除が受けられれていましたが、平成16年以降に関しては配偶者控除38万円のみになります。影響を受ける人は、配偶者が専業主婦の方や配偶者のパート収入が103万円未満の方となります。
3.モデルケース(夫:サラリーマン、妻:パート)
(1)パート収入金額が103万円未満の場合
改正前 妻:所得税はかかりません。
夫:配偶者控除(38万円)、配偶者特別控除(最高38万円)
改正後 妻:所得税はかかりません。
夫:配偶者控除(38万円)のみ
(2)パート収入金額が103万円を超えて141万円未満の場合(今回の改正で影響無し)
妻:所得税がかかります。
夫:配偶者特別控除(最高38万円)のみ
(3)収入金額が141万円以上の場合(今回の改正で影響無し)
妻:所得税がかかります。
夫:控除なし
※住民税に関しては,配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための要件は、所得税と同様ですが、所得控除額が所得税と異なるためには、パート収入が100万円を超えると住民税が(所得割)かかります。ただし、パート収入にかかる税金に関しては,その他の控除の金額があるため、上記の額は、所得控除が何もない場合の金額です。
このパート収入金額に関しては、配偶者が受ける所得控除の問題だけでなく、社会保険との関係や家族手当等の条件も異なりますので、個別の事例については、専門家にお問い合わせください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年1月23日 木曜日
★第90号(1/23)時間外・休日を適用除外できる管理監督者とは?★
最近、時間外手当を支給したくない理由で従業員を「課長職」にする事業所が見られます。労働基準法第41条第2号では、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)を「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」と定め、労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないことにしています。具体的な判断に当たっては、次の考え方によります。
(1)企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。
(2)職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動する職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として適用除外が認められること。
(3)管理監督者の範囲の決定に当たっては、資格、職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があること。
(4)管理監督者であるかの判定に当たっては、賃金等の待遇面についても無視し得ず、基本給、役付手当等においても、その地位にふさわしい待遇が
なされているか否か。
(5)いわゆるスタッフ職は企業内における処遇の程度によっては、管理監督者と同様に取扱い、法の規制外においても、これらの者の地位からして、特に労働者の保護に欠けるおそれがない者と考えられ、かつ、法が監督者のほかに、管理者も含めていることに着目して一定範囲の者については、管理監督者に含めて取扱うことが妥当であると考えられること。
管理監督者の範囲について、具体的な事例に対して判断を示したものとして、金融機関に関して解釈例規があります。一般業種では課長職も時間管理の必要があります。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年1月 5日 日曜日
★第89号(1/5)CRMって何? その2★
CRMを実現するための重要な情報(データベース)の1つに顧客データベース(顧客台帳)があります。この顧客台帳の中でも最も基本的な情報が、顧客ID(お客様の名前)であることはご存知だと思います。顧客台帳の活用方法をしては、郵便によるDM(ダイレクトメール)がありますが、郵便でDMを届けるためには名前と住所が必要です。
現在でも高価な値段で売られている名簿の多くはDMの発送用にりようされていますが、この名簿の顧客データからもお客様の様々な情報(特徴)を得ることができます。例えば、高校の卒業生名簿からはどの地域に住んでいるか(地域特性、地域属性)、男女比率、年齢比率、勤め先、婚姻率などの情報が容易に得られます。さらに、進学した大学や学部、就職先などから、ある程度の年収も推定可能です。結婚式関連のビジネス(式場、貸衣装、マンション販売他)であれば、適齢期にあたる卒業年度から既婚者を除いた卒業生をDM発送対象とすれば、レスポンス率(返信などの反応)が高くなります。
最近では、顧客IDから購買履歴(どのお客様がいつどこの店で何を買ったか)をデータベースに蓄積して、次の販売促進に活用するシステムがドンドン出来ています。コンビに、デパートなどのクレジットカードは、POSレジと組み合わせて顧客ごとの購買履歴情報の蓄積用にも使用されています。
顧客一人一人の情報を細かく把握し、それを分析、活用して顧客の好みにさらに合った商品を開発、販売し、ずっと良いお客様になった頂くことがCRMの目標です。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2002年12月23日 月曜日
★第88号(12/23)またまた外形標準課税です★
自民党内でも従来の党税調がいわば独裁的に決定する税改正に反対し、外形課税への反対を主たる目的として、税制議連が発足するなど予断を許さない状況がしばらく続きました。
数年越しの議論も政治的な決着を見せ,詳細については来年度中に詰めていくことになります。
この秋に大阪府議会議員勉強会及び商工会議所でセミナーをおこないましたが、聴講者の感想としては一様に今後の負担について不安を覚えておられました。今回の方針で中小人はひとまず安心といったところでしょうが、大法人は減税になる法人もあれば、赤字にもかかわらず納税しなければならない法人もあり、まさに悲喜こもごもといった様相です。
下記に一応の決着方針を記します。
【対 象】 資本金1億円超の大法人の法人事業税
【新制度】所得×7.2%+付加価値額×0.48%+資本等の金額×0.2%
付加価値額=収益配分額±単年度損益
資本等の金額=資本の金額または出資金+資本積立金額(段階的軽減あり)
収益配分額=報酬給与額+純支払利子+純支払賃貸料(人件費7割超非課税)
前回ご紹介した案(平成13年度総務省発表案)と比べて、制度設計上の外形部分はさらに半分の1/4となっており、何とか外形部分をいれました、という感じになっています。しかしながら、外形課税の取っ掛かりができたということで、片山総務相は非常にご満悦であったという記事も流れていました。
該当する法人の経理の皆様には,今後の詳細、特に付加価値額の大部分を占める人件費の定義について注視していく必要があろうと思われます。また、課税の安定性を指向する自治体の趣旨からすると、中小企業にとっても数年後に導入論議再燃の可能性は以前否めないところだと思われます。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2002年12月 5日 木曜日
★第87号(12/5)短時間労働者の人事労務管理★
全労働者に占める割合は、パート労働者が22.1%、パート等労働者が26.1%になっています。
そこで、パートタイマーのような短時間労働者については、パート労働法に基づいて、パート労働指針が定められており、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働者保護法令を遵守するとともに、その就業の実態や正社員等の通常労働者との均衡を考慮して労働条件を定めるべきです。
以下のような点に気をつけて適切な措置を講ずるように致しましょう。
1.雇入れ通知書の交付 6.賃金(賞与および退職金の有無)
2.就業規則の整備 7.健康診断の実施
3.労働時間 8.教育訓練、福利厚生
4.年次有給休暇 9.雇用保険、社会保険の適用の有無
5.労働契約期間 10.育児休業、介護休業に関する制度
雇入れ通知書は、賃金、労働契約期間、就業場所、従事すべき業務、始業・終業時刻、労働時間、時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換に関する事項、退職に関する事項、その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書を交付しましょう。(就業規則を交付することにより明らかにされている場合は、必要ありません。)また、正社員用の就業規則しかない場合は、短時間労働者もこれを準用することになってしまいます。短時間労働者を含め常時10人以上の従業員を使用する場合は、
短時間労働者に適用される就業規則を作成しましょう。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2002年11月23日 土曜日
平成14年11月23日(第86号)
伊藤副金融担当相は、この度日本公認会計士協会の奥山会長とDCF方式の導入について会談しました。大手銀行の貸出債権に対する引当金の算定に、企業の将来収益を反映させる「割引現在価値」(ディスカウント・キャッシュフロー、DCF)方式等を導入するため、同協会で具体的検討を行うよう要請しました。
DCFの導入は10月30日決定の不良債権処理の加速策「金融再生プログラム」に盛り込まれたもので、同協会は特別チームを設置して年内に導入のガイドラインの原案をまとめ、来年3月期決算に反映させる考えです。
DCF価格とは
DCF価格は、その不動産が生み出すキャッシュフローに着目して、それを割引率で現在価値に割り引いて求めます。この評価手法をDCF法と言います。割引率は、一般的な金利水準と個別のリスクから構成されます。DCF評価では、利回り(リターン)とリスクの査定なしには価格が成立しないので、投資家にとっては、それらを判断基準としてほかの金融商品との比較が可能となります。また、種々のリスクを盛り込めるので、欧米でもリスクに適応した評価手法として認識されています。
収益還元法は、その基本的な算定方法(式)の面から、大きく直接還元法(広義)とDCF法とに分けられます。直接還元法(広義)は、ひとつの純収益を還元利回りで割って一度の操作で価格を求める手法であり、DCF法は、一定期間の収益をキャッシュフロー表を用いて詳細に分析して、復帰価格と併せて価格を求める手法です。
このように、DCF法は、一定期間の将来予測を明示的に行って価格を求める手法ですが、あくまでも予測に基づく手法であるので、割引率等の査定とともに、予測の内容、精度等によって求められた価格の信頼性は左右されます。不動産投資や開発事業においては、将来予測は不可欠なものであり、不動産鑑定評価に当たっては、このような市場参加者の将来予測や価値判断手法を採り入れていく必要があります。(不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2002年11月 5日 火曜日
平成14年11月5日(第85号)...日本の経済どうなる?
1.中国
今年に入って、2回上海に行く機会があった。いま、上海はものすごい勢いで世界の経済にキャッチアップしてきている。中国には14億人の人口(統計上の人口で実際にはもっと多いといわれている。)がいてワーカーの賃金は月8,000円から12,000円である。これは、私が大学を卒業した昭和45年当時の高卒の給与水準と同じである。一方で技術および機械設備については日本を始めとする産業先進国から最新の技術や機械が導入され生産能力、品質等については急速に追いついてきている。これでは日本は勝ちようがないというのが実感である。こうした状況から見て日本の産業は2極化してしまうと予想されている。
2.産業の2極化現象
ミドル技術である家電、車、IT産業の一部、鉄鋼、繊維等々はコストの低さを求めて中国へ移転してしまうであろう。その結果、日本に残るのは、ナノテク、バイオ、高度なIT技術またはそれらの融合した技術と地域の中で循環または消費される産業のみが残ることになる。前者は、大学および民間、公的研究機関が蓄積している技術がその担い手になることが期待されるが、すでにバイオ技術の一部については上海でバイオフェアーが開催されるなど追いつきつつある。後者の地域循環型産業には、健康、教育、環境、ケア(福祉、介護等)及び観光の5つのKのつく産業と外食産業をはじめとするサービス産業が残ることになる。正に、消費経済になってしまい、大量の雇用を生み出すには力不足であろう。
「地域創造」これが今後のキーワードとなるであろう。もう一度、地域の持っている産業資源を見直し、組織化し産業としてマーケットを創造していことが重要になってくる。
3.中国の課題
中国にも課題がある。最大のものは沿岸部と奥地の所得格差である。産業化に向けて急速に先進国にキャッチアップしているとはいえ、まだまだ農業国であり、都市部の一部の所得の高い層に比較して所得水準は低く、さらに、都市部への人口の集中はいずれ環境等の社会問題を起こす可能性がある。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2002年10月23日 水曜日
平成14年10月23日(第84号)...就業規則の意見聴取をする者は、 どのように選んだらよいのでしょうか?
就業規則を作成、変更する場合には、意見聴取、行政官庁に届出、労働者への周知という、三つの手続きが必要です。
このうちの、意見聴取は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合には、事業場の労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことになります。
「過半数代表者」となる者
まず、労働者であることが必要です。
一般労働者はもちろん、パートタイマーやアルバイト、契約社員(嘱託社員)のほか、管理監督者や出向中の者、さらに休職中の者まで、その事業場に雇用されるすべての労働者が含まれます。
「過半数代表者」にはなれない者
事業場全体の労働時間などの労働条件の計画や管理に関する権限をもつ工場長や労務部長などの管理監督者や出向中の者は、過半数代表者となることはできません。
また、派遣会社から派遣された者も含まれません。
事業場に過半数労働者で組織された労働組合がない場合には、民主的な方法で過半数代表者を選出しなければなりませんが、その場合、会社が指名した者や、会社の意向にそって選任された労働者に意見を聴いても、意見を聴いたことにならない点に注意してください。
※民主的な方法とは、投票、挙手など、その事業場の過半数の労働者が
支持していることがはっきりわかるような方法で選ぶことが必要です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2002年10月 8日 火曜日
★第83号(10/8)雇用保険その他が変わります★
各業種一律に2/1000値上げされました。事業主負担分、被保険者ともに1/1000ずつの値上げです。
5月の年度更正の時には、15年3月分まで旧保険料率で計算し、納付していますので、10月分以降の6ヵ月分について不足が生じます。
各事業主には、12月中旬に納付書が郵送され、その金額を15円1月31日までに納付してi頂くことになっています。
被保険者の負担分は、10月分の給与から新しい保険料額表によることになりますので、注意が必要です。
翌月払いとしている事業所では、11月に支給する10月分の給与から保険料率が変わることになります。
2.10月1日から医療保険制度も変わりました。
・一部負担金限度額の引上げ(4回目以降の限度額も変更されました。)
上位所得者 139.800円+(医療費-699,000)×0.01(標準報酬月額56万円以上)
一般被保険者 72.300円+(医療費-361.500)×0.01
低所得者 変更なし
・3歳未満の被扶養者の一部負担金割合(外来)の引下げ
従来は外来3割、入院2割でしたが、外来、入院ともに2割になります。
・被扶養者の出産育児一時金を拡大 家族出産育児一時金従来出産一時金は配偶者にかぎられていましたが、例えば長女が出産した場合など、その人が健康保険の被扶養者であれば、対象になります。
・老人保険の変更
昭和7年9月30日以前に生まれた人は、引き続き老人保険が適用されますが、昭和7年10月1日以後に生まれた人は75歳から老人保険の対象になります。平成14年10月1日以降は、老人保険の対象者負担率は・・
一定以上の所得者 定率2割負担
一般及び低所得者 定率1割負担
となり、上限値も変わります。負担率は保険者から各保険者に通知されています。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2002年10月 1日 火曜日
平成14年10月1日(臨時号)...~総報酬制の実務・社会保険事務はどう変わるか~
平成15年4月1日、厚生年金保険法の総報酬制が施行されます。いよいよ施行まで
半年となり、緊急の研究課題となってきました。また平成15年4月の施行予定で健保
法の総報酬制も国会に提起されており、平成15年からの社会保険はまさに総報酬制を
土台として展開されようとしています。
1.総報酬制とは
総報酬制という新しいシステムは、一言でいえば、賞与も広義の「報酬」ととらえ年金
計算や保険料徴収の要素にするという仕組みです。
2.標準報酬月額と標準賞与額
月額給与と賞与は、支払われた金額そのままの数値が直接計算に使われず、それぞれ「標
準報酬月額」「標準賞与額」ととらえ直して年金や保険料の計算に使われます。
1)標準報酬月額
月額給与から標準報酬月額を定めるという考え方は、現行と変わりません。
2)標準賞与額
賞与が支払われた月に、被保険者ごとに標準賞与額を決定し(賞与額はその時支
払われた額の1,000円未満を切り捨て)1回の標準賞与額は150万円が上限です。
健康保険の上限は200万円の予定です。
3.保険料
総報酬制では、標準報酬月額と標準賞与額のそれぞれに同率の1,000分の135,8を掛けて、保険料が算出されます。健康保険料率は1,000分の82の予定です。
4.手続き業務
1)定時決定
4.5.6月の3ヵ月になり、時期が1ヵ月前倒しされます。
2)標準賞与額の届出
賞与支払いのたびに、被保険者ごとの標準賞与額を届出なければなりません。届出
された標準賞与額は、各被保険者の年金額の計算や在職老齢年金の計算の要素とな
ります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2002年9月23日 月曜日
★第82号(9/23)中小会社の会計基準の明確化に向けた動き
今年6月、「中小会社の会計のあり方に関する研究報告(経過報告)」が日本公認会計士協会から出され、(今秋には最終報告書が出される予定)、この調査研究報告によって中小会社での会計処理にあたっての統一指針が示されることになりました。
◆背景
商法では、中小会社にも決算公告を義務付けていましたが、官報や日刊紙に掲載するにはあまりにも手間と費用がかかるために、多くの中小会社はこの公告を行ってきませんでした。しかし、商法改正により平成14年4月1日から、インターネットのホームページを利用した計算書類の公告が商法上の開示として認められることとなり、今後は中小会社においても計算書類の開示を積極的に行うことが期待されています。
現状では、中小会社が会計処理を行おうとする場合、税法基準に従ったり、あるいは税法限度額以内の任意の金額による処理を行って計算書類を作成するなど、多種多様の実務が混在していて、会計処理方法が必ずしも統一されていません。このため、中小会社の会計基準のあり方を明確にして、作成される計算書類をより適正なものとする必要性が意識されるようになりました。
◆内容は・・
「研究報告」によると、会計基準は会社の規模に関係なく(中小会社、大会社に関係なく)あくまでも1つであるべきであるという前提に立ちながら、事務負担力等の中小会社の特性を考慮して、その適用方法に簡便法等をみとめるという基本的な考え方を明確にしています。会計ビックバンといわれる会計基準の諸々の整備によって、日本の会計基準も国際的水準に達することとなりましたが、これをそのまま中小会社に適用するにはあまりにも費用対効果のバランスを欠くものとなります。このため、「研究報告」の
各会計処理についての説明では、大会社に厳格に適用することが求められる会計基準を基礎に置きながら、簡便法や税法基準を随所に認める内容となっています。
このような中小会社の会計基準の明確化は、インターネットによる方法化社会の進展を背景とした、重要なひとつの基盤整備といえますが、それ以上に、資金の調達等の局面で中小会社の経理実務に対し、より具体的なインパクトをもたらすものとなるかどうか今後注目されます。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2002年8月23日 金曜日
★第80号(8/23)CRMって何?★
売り手は、ひとり一人のお客様をよく知ることから初めて、少しでもお客様の好みに合ったモノを好みに合った方法で提供しないと買ってもらえません。このように、顧客側の購買行動や心理を想定して、気持ちよく買い続けてもらえるよう商売を組み立てて行うというのがCRM(Customer Relationship Management)です。(顧客関係管理や顧客志向経営、顧客志向マーケティングなどと訳されています。)
顧客情報に基づいて商売を行う工夫は、古くは「越中富山の薬売り」の顧客台帳などにも見られますが、コンピュータのなかった時代には、ひとり一人の顧客台帳を作るだけでも大変な手間がかかり、実際に活用するのは大変でした。
情報技術(コンピュータ)や通信技術(電話など)の発達により、顧客情報の収集、管理、分析等の活用が機械化、自動化できるようになり、企業もそれらを活用した売り方を工夫するようになって来ました。さらにここ数年、インターネットや携帯電話の急速な普及により、企業と顧客が直接対話(コミュニケーション)を行い、顧客ごとの情報を入手し易くなりました。
顧客ひとり一人の情報を細かく把握し、それを分析、活用して顧客の好みにさらに合った商品を開発、販売し、ずっと良いお客様になって頂く事がCRMの目標です。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2002年8月12日 月曜日
平成14年8月12日(臨時号)...社員が一致団結して小さな削減を積み重ねる
地域密着型のミニスーパーを営むI社の月商は1,000万円、従業員は7名(パート含む)です。最近は、売上単価が下がる一方で経費は増加し、黒字確保に汲々という状況にあります。
すでに考えられる限りの経費削減策を実行し、これ以上は減らしようがないと考えていましたが、今期は売上・利益とも一層の落ち込みが予想されるため、さらなる対策の検討・実施を図りました。
・毎週月曜日の開店前に20分程度の打合せを行ない、削減に役立つと思ったことは、どんな小さなことでも提起する
・削減案は全員が提起し、毎週2件以上の削減策を決める
・準備が必要ないものは、その日からすぐに実行する
・特に貢献が著しい提案者には褒賞を与える
全員で知恵を出し合った結果、多くの節減策が出てきました。
・冷凍品陳列の効率化による空調費の削減
・陳列の工夫(売りたい商品を強調)による廃棄ロスの削減
・ダンボールなど廃棄物のリサイクル業者への売却 など
経費削減に特効薬はなく、小さな積み重ねが大きな成果を生みます。I社では、新たな対策によりすでに経費を約3%削減しましたが、さらなる削減が見込まれています。
なお、対策実行に当たっては5S(整理、整頓、清掃、清潔、躾)の考え方も参考にしました。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2002年8月12日 月曜日
平成14年8月12日(臨時号)...成果主義報酬による人件費の削減
サービス業のH社(従業員18名)では、中途採用の営業社員の賞与に成果主義を採り入れました。
基本給は低く抑え、代わりに年2回、成果報酬(賞与)を支払います。報酬額は、本人が営業で獲得した契約金額に応じて決まります。たとえば獲得額が2,000万円なら、その10%の200万円を成果報酬として支払います。
この方式だと、営業成績にかかわらず高い固定給を支払う場合と比べて、人件費を削減できるケースがでてきます。獲得した仕事(金額)が大きければ報酬(費用)も増えますが、そのぶんは利益への貢献度で十分カバーされます。
H社では、今後採用する従業員に対しては、新卒を除きこの方式を続けて採用する予定です。なお、希望者がいれば、現在在籍する従業員への適用も検討しています。
<実施上の留意点>
1.基準の明確化
「稼いだ金額」をどう査定し、報酬をいくら払うのか、基準を明確にする。自分一人の力か、共同作業なのかによっても金額は異なる。「何%払うか」も根拠を定義して本人の合意・納得を得る。人や仕事の質・内容によって変わることも考えられる。
2.管理体制の充実
成果主義が行き過ぎて不正を働いたり、独走して組織を乱さないよう注意する。また、成果報酬の対象者か否かにかかわらず、全社的な理解を得ておく。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2002年8月12日 月曜日
平成14年8月12日(臨時号)...成果主義報酬による人件費の削減
サービス業のH社(従業員18名)では、中途採用の営業社員の賞与に成果主義を採り入れました。
基本給は低く抑え、代わりに年2回、成果報酬(賞与)を支払います。報酬額は、本人が営業で獲得した契約金額に応じて決まります。たとえば獲得額が2,000万円なら、その10%の200万円を成果報酬として支払います。
この方式だと、営業成績にかかわらず高い固定給を支払う場合と比べて、人件費を削減できるケースがでてきます。獲得した仕事(金額)が大きければ報酬(費用)も増えますが、そのぶんは利益への貢献度で十分カバーされます。
H社では、今後採用する従業員に対しては、新卒を除きこの方式を続けて採用する予定です。なお、希望者がいれば、現在在籍する従業員への適用も検討しています。
<実施上の留意点>
1.基準の明確化
「稼いだ金額」をどう査定し、報酬をいくら払うのか、基準を明確にする。自分一人の力か、共同作業なのかによっても金額は異なる。「何%払うか」も根拠を定義して本人の合意・納得を得る。人や仕事の質・内容によって変わることも考えられる。
2.管理体制の充実
成果主義が行き過ぎて不正を働いたり、独走して組織を乱さないよう注意する。また、成果報酬の対象者か否かにかかわらず、全社的な理解を得ておく。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2002年8月12日 月曜日
平成14年8月12日(臨時号)...変形労働時間制で残業代を大幅に圧縮
D社(従業員30名)は繊維資材の卸売業を営んでいます。
各部署・従業員の業務分析をしたところ、経理や総務などの事務部門は月末・月初に仕事が集中し、月中は比較的暇な時間があることがわかりました。忙しい月は1人平均15時間ほどの残業があり、残業代も計25万円ほどになります。
そこで、D社では変形労働時間制を導入し、月末月初は週50時間労働、月中の2週間は30時間労働とすることにしました。4週の労働時間は160時間(50時間×2週+30時間×2週)で、平均すれば1週40時間の法定労働時間内に収まります。
変形労働時間制を採用しなければ、50時間働いた月末・月初の週は10時間の残業が発生しますが、変形労働時間制ならゼロになります。月に同じ160時間働くにしても、工夫次第でこれだけの違いが出てきます。
7名の従業員がこの制度の適用に応じており、7名合わせた残業代は多い月でも10万円程度で済んでいます。現在、他部署にも適用を拡大できないか検討を進めています。
<実施上の留意点>
1.労基法上の手続き
変形労働時間制を採用する場合は、従業員の合意を得たうえで就業規則(または労使協定)に定め、監督官庁に届け出る。
2.適用対象者
変形労働時間制は会社全体はもちろん、特定の部署や個人を対象としても適用できる。ただし、営業など仕事の性格上、変形労働時間制になじまない部署もある。
3.従業員の説得
「残業代が減るのは困る」という理由で、導入に反対する従業員が出るかもしれない。その場合には、私生活の充実や余暇の有効利用など、収入以外でのメリットを強調して説得する。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2002年8月 8日 木曜日
平成14年8月8日(第79号)...固定資産税の負担軽減問題
平成15年度が課税の基準になる評価額の三年に一度の改定年にあたるため、国土交通省や経済界は税制改正の柱として商業地を中心とした負担の軽減を要望する方針ですが、総務省は財政難の市町村の税収が減ることを警戒して負担減に消極的です。
固定資産税の評価替えでは、税負担に地価の変動を反映させるため、不動産鑑定士の鑑定評価額を基に三年に一度全国の土地すべてを評価し直します。
評価額は鑑定評価額(公示価格ベース)の約7割で、さらにその60~70%(負担水準という)、つまり公示地価の42~49%を実際に課税する際の課税標準額となっています。
国土交通省は固定資産税の負担の重さが不動産市況の悪化の一因になっているとして課税標準額の算出基準の見直しを要望する方向で調整しています。また、日本経団連も負担水準を50%台に引き下げるよう求めることを検討しています。
一方、総務省はこれからは地価の下落に伴って税負担も下がり、また固定資産税など土地の保有コストを軽くしないことが不動産の有効活用につながるとしています。
上場453社が土地再評価を実施
賃貸ビルや工場などの事業用土地を時価にし直す土地再評価を実施した企業が01年度だけで280社に上り、累計で上場企業の二割の453社に達しました。土地再評価は02年3月末までの時限措置で、特定の土地だけを選別的に再評価の対象にすることはできず、保有するすべての事業用土地が対象となるため、土地の含み損の一掃によって財務内容の透明性が格段に高まるとともに従来から含み益に頼ってきた経営もできなくなり、収益力がガラス張りになります。
再評価が急増したのは、固定資産の減損会計が06年3月期に導入されることが確実となったためで、減損会計では、値下がりした固定資産だけを対象に簿価と時価の差額を損失として計上する必要があるのに対して、土地再評価は含み損と含み益を相殺できるだけでなく、差額を期間利益に反映させる必要がないため、企業にとっては収益に影響がでない利点もあります。 (担当 スマイルグループ不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2002年7月23日 火曜日
★第78号(7/23)外形標準課税★
【現行制度(法人事業税)】 所得×9.6%
【新制度(案)】 所得×4.8%+付加価値額×0.66%+資本等の金額×0.48%
付加価値額=収益配分額±単年度損益
資本等の金額=資本の金額または出資金+資本積立金額
収益配分額=報酬給与額+純支払利子+純支払賃貸料
したがって、現行制度では、最終所得が赤字の場合には課税されないのに対して,新制度では赤字であっても資本金に応じた
一定税額が課されますし、経常利益が黒字であったりした場合には、付加価値額も黒字となって当該付加価値額に応じた課税が
生じるケースも考えられます。当該制度の導入にあたっては、地方税の歳入低減に悩む自治体と、中小、ベンチャー企業保護を
訴える商工会議所をはじめとする諸団体との駆け引きがまだまだ今後も続くことが予想されますが、年内には一応の決着を
見せることと思われます。各企業経理の皆様には、税額がどのように変わるかを試算しておくことも必要であろうと思います。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2002年7月 8日 月曜日
平成14年7月8日(第77号)...マーケティングリサーチの基本手順
■マーケティングリサーチとは・・
マーケティングリサーチとは、的確な戦略・戦術を考えるための基準材料を、正しく、必要なタイミングで収集することです。企業・消費者・顧客を繋ぐための重要な作業であるといえます。企業として確実な判断が求められる時、また、新たな発想で事業展開していく時、正しい市場の実態を把握するためには、必要不可欠な作業といえます。
リサーチを効果的に実施するには、適切な手順を踏んで作業を進めることが必要です。
■基本手順
1.目的・期限・費用を確認する...リサーチの目的やテーマを明確にする。リサーチに
要する時間・見積もりの上限を設定し、その範囲内で実行する。
2.基本情報を収集する...最初は、一次情報(簡単かつ安価で入手できる情報...例:官
庁統計・書籍・新聞・ホームページ・会社内部の売上・顧客・生産デ-ター等)か
ら、広く収集する。仮説立案に充分でなければ、二次情報(入手するためにコスト
と時間がかかる情報...例:企業独自の企画・調査等)により、ターゲットの顧客か
ら、直接収集する。
3.仮説を立案する...上記2で収集した情報に基づき、その地点での仮説を立てる。
その時には、現象の背景となる要因を深く掘り下げる。
4.裏付けのデーターを収集する...仮説を裏づけるために必要なデーターを収集する。
一つの仮説に対して、多く偏りのない情報から、複数のファクトを分析する。
(結論を導くための調査)
5.仮説の検証・修正をする...仮説の検証と修正を行い、必要に応じて、補足的に情報
収集を行う。
■情報収集時の注意点
一次情報と二次情報のバランスを考えて、活用する。一次情報と二次情報は、両者を相互に使いこなすことによって、各事実を客観的に検証することができる。また、その相互検証がリサーチ全体の信頼性を向上させる。
ただ、二次情報は、外部のリソースにより作成されたものであるので、利用時、適切性(情報のニーズにマッチしているか)正確性(信頼性)、最新性(本当に最新版か)、客観性(内容に偏りがないか)を、充分検証する必要がある。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2002年6月23日 日曜日
★第76号(6/23)緊急雇用創出特別奨励金★
平成17年3月31日までの暫定措置です。)
◆支給対象となる事業主
1.雇用保険の適用事業の事業主であること
2.労使の合意により、所定労働時間の短縮とそれに伴う賃金の減額を行うこと
3.事前に「緊急対応型ワークシェアリング導入計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けていること
計画認定の要件 ・最近3ヵ月間の生産量が前年同期に比べて10%以上減少していること
・最近6ヵ月で事業主都合による解雇を行っていないこと
・労使の合意により所定労働時間の短縮と賃金削減等のワークシェアリングを実施すること
4.計画認定後6ヵ月間に、45歳以上60歳未満の非自発的失業者等を雇入れること
5.ワークシェアリング導入後において所定外労働時間が増加していないこと
◆支給額
1.計画認定後の最初の1人の雇入れに際し、事業所の労働者数に応じて
300人以下の事業所→30万円 301人以上の事業所→100万円
2.雇入れた労働者1人につき区分に応じて
短時間被保険者→15万円 一般被保険者→30万円
◆申請時期
対象労働者を雇入れた日の3ヵ月後から起算して1ヵ月以内
このワークシェアリングの実施は所定労働時間の短縮ですから、その対応する賃金の減額は不可避です。現在多くの会社の就業規則条文では、「会社の居かなく在籍のまま他の会社または団体等の業務に従事してはならない」として、副業が懲戒事由の
事項となっています。しかし、会社として正規に副業または兼業をワークシェアリングの一環として認めていくためには、制限付の
解禁が必須条件になります。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2002年6月 8日 土曜日
★第75号(6/8)所得税・住民税負担の国際比較★
話題にのぼっています。
では、いったい日本人の所得税・住民税の負担は諸外国と比較して、どう違うのでしょう。
夫婦と子供2人の給与所得者の世帯(従来からの標準モデル。子供は1人が16歳以上22歳未満、専業主婦/専業主夫)を例に
とって考えてみましょう。
所得税の課税最低限は382万2000円といわれています。これは、収入金額(382万2000円)から給与所得控除(約130万円)が控除され、そこから社会保険料控除(約37万円)、配偶者控除・配偶者特別控除計76万円、扶養控除(38万円と63万円)、それに本人の基礎控除が38万円がひかれ、課税所得金額がゼロになるということです。
諸外国の所得税の課税最低限については次のようになっています。
イギリス 69万7000円 アメリカ 243万3000円
フランス 262万円 ドイツ 327万円8000円
日本の給与所得者の所得税・住民税の合計額は上記の標準モデルの場合、500万の収入で約11万円、1000万円で約86万円、2000万円で約440万円となり、いずれの場合にも諸外国と比較して低くなっています。
法人の実効税率の引下げの問題、消費税の税率の引上げの問題を含めて、国債や地方債の問題等、税制の改革に注目が必要になるのではないでしょうか。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2002年5月23日 木曜日
★第74号(5/23)企業に助成し未就職卒業者緊急支援 若年者トライアル雇用★
「学校は出たけれど・・」失業率が過去最悪の5%で推移する中、高校や大学、短大、高等専門学校などの卒業生も就職難に直面し、行政側も卒業後の「事後対策」に踏み出すことになりました。国が本腰をあげ、更正労働省が発表した「未就職卒業者緊急支援事業」で企業に1人当たり月額5万円の助成を行います。
1.特長
・ハローワークが推薦・紹介する30歳未満の未就職若年者を3ヵ月までの短期間、試行的に雇い、その間の実務能力向上をはかる。
・一定の奨励金を支給することで企業における初期の費用負担の軽減を図る。
・トライアル子幼虫に業務遂行能力を見極めた上で、本採用するかどうかを決定できる。(どうしても能力等において無理な場合はトライアル雇用だけで終了してもかまいません。)
2.奨励金の支給
・トライアル雇用実施する雇用主に、実施対象者1人につき1ヵ月あたり5万円が支給される。ただし、トライアル雇用期間中の賃金が10万円未満の場合は、月額給与の1/2の支給となります。
・トライアル雇用中に教育訓練等を行った場合は、外部の教育機関・講師に支払った費用、教材購入に要した費用が上限6万円まで支給される。
3.計画書の作成
トライアル雇用開始後、トライアル雇用中の措置について、「トライアル雇用活用計画書」を提出します。計画書には、実施する措置の内容(どのような指導・訓練を実施するのか)と本採用のための用件(どの程度の業務遂行能力が必要とされるか)を記入し、若年者の同意を得た上でハローワークへ提出します。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2002年5月 8日 水曜日
平成14年5月8日(第73号)...安全衛生管理体制
業種
項目 建設業など
屋外産業的業種 製造業等
工業的業種 商品卸小売業等
サービス産業的業種 その他の業種
(証券・金融業等)
総括安全衛生管理者 100人以上 300人以上 300人以上 1,000人以上
安全管理者 50人以上 50人以上 50人以上 選任不要
衛生管理者 50人以上
産業医 50人以上
安全衛生推進者 10~49人 10~49人 10~49人 選任不要
衛生推進者 選任不要 10~49人
作業主任者 危険有害な作業について選任義務あり(作業名は安衛施行令第6条に規定)
統括安全衛生責任者 建設業の元請が選任*1 ――― ――― ―――
元方安全衛生管理者 建設業の元請が選任 ――― ――― ―――
安全衛生責任者 建設業の下請業者が
選任 ――― ――― ―――
店社安全衛生管理者 建設業の本社、支店等で選任 ――― ――― ―――
安全委員会 100人以上 *2 100人以上 100人以上 設置不要
衛生委員会 50人以上
安全衛生委員会 安全委員会および衛生委員会の設置義務のある事業場は
安全衛生委員会に一本化してもよい。
(安全、衛生或いは安全衛生委員会は毎月1回開催)
注*1 元請、下請、関係請負人の合計労働者数が50人以上の時に選任。ただし、ずい道、橋梁の建設、圧気
工事の時は30人以上で選任。
*2 災害の多い林業、金属製品製造業、自動車整備業等13業種では50人以上。
労災事故が発生した事業場では、安全衛生委員会が定期的に開かれていなかったとか、経営幹部が安全に対して無関心であったということが報告されています。
事故発生を反省して、経営幹部が積極的に安全衛生管理に取り組み始めたところ、社内全体が明るくなり、活気が出てきた、という実例があります。御社も安全重視を再確認下さい。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2002年4月23日 火曜日
★第72号(4/23)連結納税制度 2 ★
1.2%の付加税率の意味
連結納税制度を適用しようという会社は,従来の税率に加えて2%の付加税率が上乗せされ、24%の税率(資本金1億円以下の
中小企業年800万円以下の所得)が適用されることになります。何故か?企業グループ間(連結納税上は100%子会社になりますが)の取引で売買があり、それが連結グループ間で在庫として残っていると、未実現の利益として控除できるようになっていて、
従来の単体ベースの課税所得より少なくなってしまうからです。
もう一つ大きな問題は、例えば連結子会社で赤字(ただし、連結納税制度が導入される前の税務上の繰越欠損金及び連結グループ加入前の欠損金は除外されます)を出していると、親会社または他の連結子会社の黒字と所得が相殺されて課税所得が
減ってしまうからです。課税の所得の減少は、即ち、税収の減少となりますので、政府はこの税収減収を防ぐために2%の付加税率を経過的につけることにしています。しかし、これでは連結納税制度を導入した意味がありませんので民間企業側からはかなりの反論があり、ひょっとすると連結納税精度を適用する会社は意外と少ないかもしれません。
2.いつから適用?
平成14年4月1日以降に開始する事業年度からてきようできますが、適用を受けようとする事業年度の開始日の前日(普通は前期の決算期末)から遡って6ヵ月前の前日までに適用の届出を国税庁長官(実際の手続きは税務署)にしなければならないことになっています。
といっても今年の4月は過ぎてしまっていますので今年の9月末までに届出ればいいことになっています。クライアントの試算をしてみますか?
3.連結決算が要る?
連結決算は面倒くさいです。だからというわけではありませんが、連結納税する各会社が個別に税務申告書を作成し、合算して、未実現損益等の控除等の調整をいた上でグループ全体の納税額を計算し、それを各グループ会社の所得金額等を基準に配分することになります。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2002年4月 8日 月曜日
★第71号(4/8)育児・介護休業法が4月から改正★
◆就業規則への記載
育児休業は労働基準法上の「休暇」に該当するため、就業規則等への記載、労働基準監督署への届出が必要です。
常時10人未満(パートタイマーを含めて数えてください)の労働者を使用する事業所では,就業規則の作成義務はありませんが、育児・介護休業法自体は適用されますので、育児・介護休業に関する労働条件を定めておくべきです。
1.どんな事業所でも休業の申し出は拒めません
ただし、労使協定を結べば、勤続1年未満等の従業員を省くことができます。
2.書式の用意が必要です
育児・介護休業の申出・撤回、休業中の取扱い通知は、すべて書面によって行います。「育児休業申出書」「育児休業取扱通知書(労働者に交付)」「育児休業撤回届」「育児休業期間変更申出書」等を用意しておくことが必要です。
今回の法改正の主なものは、以下です。
「義務」として・・
・勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢を3歳未満まで延長
・転勤に際して育児や介護の状況に配慮すること
・育児または介護を行う労働者の時間外労働の制限が1ヵ月24時間、1年150時間以内
「努力義務」として・・
・勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢を3歳未満まで延長
・子の看護のための休暇の措置
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2002年3月23日 土曜日
平成14年3月23日(第70号)...ナレッジマネジメント
一頃「ナレッジマネジメント」という言葉をよく目にしましたが、具体的にはどういうことでしょうか?また、業務にどんなメリットがあるのでしょうか?
(1)ナレッジマネジメントとは?
ナレッジマネジメントとは直訳すれば、『ナレッジ・・・知識、知恵』、 『マネジメント・・・管理』ですから、『知識や知恵の管理』ということになります。
もう少し含蓄をこめて言えば『企業内に目に見えない形で存在する、各人に溜まっている知識、ノウハウ、知恵を有効活用できる管理の仕組みを構築することによって、知的競争力を高めていく手法』ということになります。
(2)導入ツール
ナレッジマネジメントを達成するためには、知識、ノウハウ等を社内的にオープンにすることが必要になりますが、そのためには、社内LAN等の情報インフラが有効だといわれています。ソフトとして最も有名なのが、Lotus社のNotesですが、それに限らずとも、通常の共有サーバーへのデータ蓄積でも構いません。多くの場合、最も重要なことは、情報共有者がスムーズにデータにアクセスできる環境、すなわちパソコンを所有していることとなります。
(3)業務のメリット
知識やノウハウの一部は、情報インフラの活用で共有することができます。これによって、リサーチ業務やルーチン業務等について余分な労力を費やさずにすみます。
但しノウハウの一部や知恵については、情報インフラ等でうまく表現・伝達しきれないものがあるため、限界があることも知っておく必要があります。
(4)業務への影響
ナレッジマネジメントを実施する場合、情報インフラの導入は通常不可欠ですが、それだけではうまく機能しません。
知識やノウハウは、まず人に帰属する性質をもつ(属人的)ため、1)いかに情報収集に参加させるか、2)いかに収集した情報を有効活用するか、3)いかに収集した情報を管理するかを考えて仕組みつくりをする必要がありますが、ここでは3)のナレッジの管理業務について述べます。これには情報の収集・公開・維持業務があります。
・収集業務:あらかじめ企業が収集する情報のルールを決めて、社員に周知させておく
・公開業務:収集された情報がルールに準じていることを確認し、共有するに足らない価値の低い情報や共有すべきでない情報を取捨選択
・ 維持業務:新たに共有すべき情報や共有が不要となった情報を取捨選択
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2002年3月 8日 金曜日
平成14年3月8日(臨時号)...~3月、4月から変わる社会保険制度~
1.介護保険料率の変更
健康保険の介護保険料率変更が2月15日付で下記の通り告示されました。
(現行)10.9/1000 ⇒ (H14/3/1から)10.7/1000
料率変更は平成14年3月1日より適用されます。当月控除の事業所様はご注意ください。
2.厚生年金保険の被保険者資格延長
現在、厚生年金保険の被保険者は、65歳未満の人とされていますが、平成14年4月1日からは65歳以上70歳未満の人も厚生年金保険の被保険者となります。
したがって、これらの人の厚生年金保険の被保険者資格取得届を提出するとともに、保険料の徴収が必要となります。
<65歳以上70歳未満の人の在職老齢年金>
65歳以上70歳未満の人が老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険の被保険者となるときは、賃金に応じて老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止される場合があります。
(1)老齢基礎年金は支給停止せず、全額支給されます。
(2)賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額の合計額が37万に達するまでは、満額支給されます。
(3)賃金と老齢厚生年金の月額の合計額が37万円を超える場合は、超過部分の1/2の額
の老齢厚生年金が支給停止されます。
なお、平成14年4月1日時点で65歳(昭和12年4月1日以前生まれ)に到達しており、老齢厚生年金の受給権を有している人については、上記の支給停止は行なわれません。
3.第3号被保険者の届出方法の変更
国民年金の第3号被保険者(厚生年金や共済年金組合に加入している人に扶養される配偶者)の届出は、本人が市町村に行なうことになっていましたが、4月以降は健康保険の被扶養者(異動)届と一緒に事業主を通じて社会保険事務所に提出することになります。
組合健保の場合は、組合の対応ごとに違う方法になりますので、ご確認ください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2002年3月 8日 金曜日
★第69号(3/8)教育訓練 導入編Ⅰ★
社員各人が互いに仕事のパートナーとして認知し、自分の役割・指名を明示、確認することによって、一定の成果が期待されることでしょう。これから行われる教育訓練は、上記内容をふまえ、一時期だけでなく長期的なビジョンで柔軟に活用しましょう。
教育訓練は,大きく分けると次の4種類になります。
1.OJT(各部内の職場内プログラム)
2.OFF-JT(人事部門主催の集合研修プログラム)
3.自己啓発プログラム(オープンカレッジ、語学講座、資格検定取得等)
4.人事ロケーション(自己申告制度等、面談制度を含めて実施)
今日は、上記4項目、人事ロケーションの大手企業の教育訓練制度をご紹介いたしますので、どうぞご参考になさってください。
◆大手企業の教育訓練制度の例
目標管理制度
1.社員自身が、会社から一方的に与えるのではなく、1年間の仕事の目標や課題を作り、キャリアプランを立てて実効する
2.定期的に上司と面談し、評価を受ける
3.次の目標を立てていく
企業の目的:社員ひとり一人を"個"として評価すること
結果を人事考課や人事異動に反映させること
企業人事担当者の声:「目標管理制度の中で、自分にとって仕事の存在を明確にし、意思表示をして、実績を作ってほしい」(花王)
「本人の興味や持ち味を生かして仕事をして欲しいので、目標管理を導入している」(エトワール)
「企業として、どういう人材が必要なのか、どういう人材がコアとして残っていけるのか、社員の1人として、
自分に対する課題でもある」(オリックス)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2002年2月23日 土曜日
平成14年2月23日(第68号)...防火管理者の選任・届出
一定規模以上の事業所には安全管理者・防火管理者などの設置義務があります。
職場における社員の安全と健康を確保することは、会社に課せられた当然の義務といえます。そのため、労働安全衛生法では、事業場における安全衛生管理体制の設置を求め、業種・規模ごとに安全や衛生についての管理者の選任を義務づけています。
3月1日から始まる春の全国火災予防運動を前に、消防法による防火管理者の選任・届出の方法をご紹介します。
◆防火管理者
防火管理者とは、消防の設備や書き設備等の点検、整備のできる、管理または監督的な地位に
ある人で、法令に定められた講習を受講した人をいいます。
その職務は、消防計画の作成や避難訓練の実施など防火管理上必要な業務をすべて含みます。
【選任が必要な事業所】
店舗・病院・飲食店では算定人員が30名以上、一般の事業所・事務所・学校などでは算定人員が50名以上の防火対象物には、防火管理者を選任しなければなりません。
【資格要件】
防火管理者の資格を取得するためには、各地の消防署で行なわれる1~2日間の講習に参加しなくてはなりません。講習が終わると終了証が手渡され、防火管理者として登録できます。
講習の申込みは、事業所を管轄する消防署に準備してある申請書で行ないます。有料の教材を用いますが、講習自体は無料です。
【選任・届出の実務】
防火管理者を選任・解任する事由が発生したときは、遅滞なく最寄りの消防署に「防火管理者選任(解任)届出書」を提出しなければなりません。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2002年2月 8日 金曜日
★第67号(2/8)所得税の確定申告★
今年の確定申告では、申告書の書類をこれまでの6種類から、申告書Aと申告書Bの2種類に統合するとともに、従前の分離課税用申告書、損失申告書及び修正申告書は、申告書Bとともにしようする別表となりました。また、申告書の用紙サイズを扱いやすいA4判に改め、2枚にすることにより裏面から表面に転記する方式が廃止されました。文字サイズ等も大きくなり書きやすくなりました。
申告書Aは申告する所得が給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの方で予定納税額のない方が使います。
申告書Bは申告書Aに該当しない方が使います。また、一定の場合には分離用(第3表)や損失表(第4表)を併用することになります。
還付申告について簡単に説明します。
◆還付申告について・・
以下に当てはまる方で、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が収めすぎになっている方は、還付を受けるための申告
(還付申告)をすることができます。
(1)平成13年分の給与所得が一定額以下の方で、総合課税の配当所得や原稿料などがある方
(2)給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金(所得)等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けることができる方
(3)平成13年の中途で退職した後就職しなかった方で、年末調整を受けなかった方
(4)退職所得がある方で、その所得を含めて申告することにより源泉徴収された所得税について定率減税の適用を受けることができる方
(5)予定納税をしている方で、確定申告の必要がなくなった方
・給与所得者で過年度の還付申告をしていなかった場合
還付申告は所得のあった都市の年の翌年の1月1日から5年間できますので、過去に申告をしていない方は、今年であれば平成9年分までについて申告することができます。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2002年1月23日 水曜日
★第66号(1/23)高額療養費と医療費控除★
被保険者が、同じ月内に、同じ医療機関(入・通院別、診療料、診療所ごと)で治療を受け,保険適用自己負担額(薬剤一部負担金を含む)が、一定額を超えた場合は高額医療費の支給が受けられます。
平成13年1月より健康保険の場合は、上位所得者(健康保険では標準報酬月額が56万円以上の人、国民健康保険では住民税の基礎控除後の所得を合計した額が670万円を超える人)は、121,800円、一般の人は63,600円を超えた場合はさらに患者負担が1%増加する制度が施行されました。
・一般の自己負担限度額 63.600円+(かかった医療費-318.000円)×1%
・上位所得者の自己負担限度額 121.800円+(かかった医療費-609.000円)×1%
・住民税非課税世帯 35.400円(改正なし)
同じ月内に、3万円(住民税非課税世帯21,000円)以上の自己負担が2回以上あった場合は、その額を合算し計算します。同じ世帯で、一年間に4回以上の高額療養費の支給を受けた場合は、4回目以降からの支給額は月37.200円(住民税非課税世帯24.600円、上位所得者は70.800円)を超えた額となります。
2.医療費控除とは・・
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差引くもので控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
◆医療費控除の対象となる医療費の要件
納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までに支払ったものであること。
◆医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額 最高200万円
(実際に支払った医療費の合計額)-保険金などで補填される金額*-10万円*
※保険金などで補填される金額→生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、出産育児一時金など
※10万円→その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2002年1月 8日 火曜日
★第65号(1/8)労働安全衛生マネジメントシステム 6★
1.労働者の意見の反映
前回スマイル新聞第61号で、危険な有害要因を特定し、安全衛生目標を設定し、安全衛生計画を作成するところまで述べました。これを実行に移すためには、労働者に計画を知らせなければなりません。また一方的に「これをやれ!」というだけでは実のある効果は得られません。
予め定めた手順に従って、労働者の意見によく耳を傾けて計画を作成し、実施運営に当たっても労働者の意見を反映し、みんながやる気になるようにすることが大切です。
2.安税衛生計画の実施及び運用等
労働安全衛生マネジメントシステムは、一度やったらそれで終わりといったものでなく、継続的に繰り返しおこなってレベルを上げて行こうとするものですから、適切且つ継続的に実施する手順を定めておいて、例えば1年ごとに計画を見直し、更新していくことが必要です。
作業に必要な機械、設備、資材等の譲渡または提供を受ける場合には、これらのものが危険または有害要因になるのかどうかを定めるのに
役立つような書面を入手するように努めなければなりません。また、これらのうち必要な事項を労働者や関係事業者に周知させる手順を定め、これに従って関係者に周知させなければなりません。
3.作業所において必要な基本的事項に関する手順の作成等
以上述べてきたことは会社全体についてのことなのですが、建設業ではそれぞれの工事現場が離れている場合が多いので、それぞれの作業所
(工事現場)について計画を作成し、
(1)関係請負人の安全衛生管理能力の評価
(2)日常的な点検及び改善
(3)労働災害、自己等の原因調査ならびに問題点の把握及び改善
(4)文書化、記録及び報告
等の手順を定めておく必要があります。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2001年12月23日 日曜日
平成13年12月23日(第64号)
1.連結納税制度とは
今までは、親会社や子会社があっても個々の会社単位で法人税の申告をしていたよね。この連結納税制度は、親会社と子会社を申告するときに合算して申告することが出来るようになるってこと。"な~んだそうか。結果いっしょじゃないか"ということになりそうですが、違いを次の簡単な例で仕組みを見てみましょう。
(例) 親会社の所得 500万円
子会社の損失 100万円
とすると、従来だと親会社の税金は、
500万円×40%(住民税も含めて概ね)=200万円
となります。子会社は赤字ですから税金はありません。結果として、グループ全体では
200万円の納税額となります。これが、連結納税になると、
親会社の所得と子会社の損失とを合算して、合計所得は、400万円になり、課税はこの400万円に対してかかることになるので、
400万円×40%=160万円
となり、従来の個別会社ごとの納税額に比べて、40万円の減少になり、結果お得です。
2.なぜ、こんな制度ができたのか
もう、ほとんど先進国が連結納税制度を採用しており、日本も国際化を進めるためこれに追いつこうというのが最大の理由ですが、これ以外にも大きな理由があります。大きな企業が特定の事業部門を分割して子会社にするとき、仮にこの子会社が赤字を出したときに、税金面で損をするため、なかなか、こうしたダイナミックな経営戦略が取りにくかったのですが、この連結納税制度が導入されるとこうした税金上の損が解消されるため経営の意思決定がしやすくなったというのがもう1つの大きな理由です。
3.中小企業への影響は?
先ず、中小企業にもこの制度が使えます(選択性)から、既に、子会社を持っている会社は、うまく使えば節税になります。もう一つは、株式投資をしていると、投資先企業が、どんなことを考えて、分社しているか、また、この制度が導入されると業績にどんな影響があるのか見るときに役に立ちます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2001年12月 8日 土曜日
平成13年12月8日(第63号)
年末年始には故郷に帰省する人が多いと思います。
未成年勤労者の帰郷旅費を一部援助する「勤労青少年旅客運賃割引制度」があるのをご存知ですか?
この制度は、20歳未満の勤労青少年が、鉄道や航路、バスで帰郷する場合に、原則として年2回を限度にその旅客運賃を20%割り引く制度です。
この制度の対象者は、労働基準法が適用される事業所等に雇用される15歳以上20歳未満の者で、就職に際して住居を移転した者となっています。利用方法は、事業主が対象者である勤労青少年に「勤労青少年証明書」を発行し、年度ごとに作成した勤労青少年証明書発行台帳に記入するとともに、所轄の労働基準監督署に申請して「勤労青少年旅客運賃割引証」を発行してもらいます。そして、勤労青少年が乗車券を購入するときに、「勤労青少年証明書」「勤労青少年旅客運賃割引証」を提示すれば割り引いてもらえる仕組みとなっています。
最近では、利用者が減少しているようですが、20歳未満の労働者を雇用している事業所では、福利向上のためにも利用したいものですね。
詳細につきましては、所轄の労働基準監督署にお尋ねください。
<炭疽菌感染の恐れをふまえた郵便物の留意>
差出人として調味料や化粧品などの白い粉を郵便物で出すことがある場合には、ポストには投函せず、郵便局の窓口に差し出し中身を申告するようにしましょう。
郵便局では、差出人の了解を得たうえで、「危険物ではない」という申告のもと引き受けた旨の表示と通信日付印を押した付箋を、郵便物に付けて届ける取り扱いをしています。
海外取引のある会社では、特に文書取扱担当者に注意を促しておきたいものです。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2001年11月23日 金曜日
平成13年11月23日(第62号)
この10月にあたらしい助成金制度が誕生しました。「キャリア形成促進助成金」は、企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成するものです。
1.訓練給付金 4.職業能力評価推進給付金
2. 能力開発休暇給付金 5.キャリア・コンサルティング推進給付金
3. 教育訓練休暇制度導入奨励金
の5種類があります。
また、訓練給付金及び職業能力開発休暇給付金の特例として、中小企業労働力確保法に基づく認定組合等の構成中小企業者又は認定中小企業者には中小企業雇用創出等能力開発助成金が、地域雇用開発促進法に基づく「同意能力開発就職促進地域」の事業主又は「同意高度技能活用雇用安定地域」内の事業主団体傘下の構成事業主に対しては地域人材高度化能力開発助成金がそれぞれ支給されます。
『受給できる事業主』は、次のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業の事業主
2.事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、雇用労働
者に周知しているものであること
3. 能力開発推進者を選任し、都道府県能力開発協会に選任届を提出していること
4.労働保険料を過去2年間以上滞納していないこと及び過去3年間に助成金の不正受給を行ったことがないこと
詳細につきましては、社会保険労務士にお尋ねください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2001年11月 8日 木曜日
平成13年11月8日(第61号)
1.危険又は有害要因の特定及び実施すべき事項の特定
前回で述べた有害要因を決定したら、有害要因を除去するために何をなすべきかを決めていきます。一方、労働安全衛生法、事業場安全衛生規程等に基づき、これらを満足するために実施すべき事項を決めます。
例えば、防止すべき重点事項として「クレーン作業での荷物落下事故防止」を指定した場合、玉掛け技能講習受講者の増員、ワイヤーの点検、交換などが実施すべき事項になるでしょう。
2.安全衛生目標の設定
安全衛生方針に基づき、特定した危険または有害要因を除くために、これから行なっていく安全衛生活動の具体的な目標を定めます。ここではできるだけ具体的に目標を設定することが必要です。
上の例では、「玉掛け作業技能講習受講者を10名増加する。」「今期中にワイヤーの点検を100%完了し、交換必要と認められるワイヤーを全数新品にする。」などが目標となるでしょう。このように、数値を挙げて達成度を見易くすることが望ましいとされています。
上の場合、「玉掛け技能講習を実施し、受講者を増加する。」といった数字のない目標はよくありません。
3.安全衛生計画の作成
安全衛生目標を達成していくための具体的な方策を示す実施計画を作ります。これは安全衛生方針とか、安全衛生目標とどこが違うのでしょうか?
安全衛生計画には、前期の目標達成度合い、予算と費用実績の比較、発生した労働災害などを考慮して、どの部署が何を担当するか(責任と権限)、計画実施に必要な費用は幾らか、日程はどうするか、などを盛り込みます。
計画の期間は1年程度とし、3ヵ月程度ごとに定期的に見直して、遅れているものがあれば対応策を検討し、遅れを取り戻さなければなりません。また、新しい機械、設備等を導入した時は見直す必要があります。
安全はタダではありませんが、最も利率のよい投資であることをお忘れなく。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2001年10月23日 火曜日
平成13年10月23日(第60号)
賃金台帳についての記載は、労働基準法第108条にあり、次のように書かれています。
「使用者は、各事業所ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額
その他命令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」
つまり、使用者は次の事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならないことに
なっています。給与明細も同様と考えてください。
(1)氏名
(2)性別
(3)賃金計算期間
(4)労働日数
(5)労働時間数
(6)時間外労働時間数・休日労働時間数・深夜労働時間数
(7)基本給・手当その他賃金の種類毎にその額
(8)賃金の一部を控除した場合には、その額
※日々雇入れられる者(1ヵ月を超えて引き続き使用される者を除く)については、(3)
の「賃金計算期間」は記入不要となっています。
※年次有給休暇の日数及び時間は、実際に労働したとみなして合計を(4)(5)に記入し
ますが、括弧で囲んで別掲するのが望ましいとされています。
※労働時間等に関する規定の適用除外者(監督・管理の地位にある者など)については、
(5)(6)の記入を要しません。しかし、「深夜労働時間」については割増賃金を支払う必要があるので、「深夜労働時間数」も記入するようにしてください。
割増賃金は、法定時間外労働0.25増、法定休日労働0.35増、深夜労働0.25
増が最低基準です。最低賃金法にも注意して賃金額を決めましょう。
日常業務としてはもちろん、労働基準監督署の調査の際にも、上記に留意しましょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2001年10月 8日 月曜日
平成13年10月8日(第59号)
確定拠出年金とは、毎月一定の掛け金を積み立て、その運用成績に応じて将来受け取る年金額が変動する仕組みの年金制度です。アメリカの401(k)プランを参考につくられているために、日本版401(k)プランと呼ばれることもあります。
拠出された掛け金が個人ごとに明確に区分され、掛け金とその運用収益の合計額をもとに60歳以降の給付額が決定される年金で、企業が掛け金を拠出する「企業型」と従業員等が任意に積み立てる「個人型」の2種類があります。
大きな特徴は、加入者(従業員)が自己責任において、年金資産の運用指図を行う点にあります。事業主は、加入者が自ら判断できるよう、資産運用に関する基礎的資料の提供や必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定められています。
<ポータビリティ>
従来の退職年金制度では、例外を除き、企業を退職した時点で精算する必要がありました。確定拠出年金では転職時に年金資産を持って会社を変わることができます。転職先が確定拠出年金を実施していればその制度に、実施していなければ個人型の確定拠出年金課税されることなく資産を移管できるので、転職をしても退職金や退職金税制の面で不利にならずにすみます。
<給付>
給付には老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金の4種類があります。老齢給付金を60歳から受給するには加入期間が10年以上必要で、それより加入期間が短い場合は8年以上61歳から、6年以上62歳からというように、段階的に受給開始可能年齢が上がります。原則年金ですが、一部を一時金にすることも可能です。
<税法上の取扱い>
税制面については、各段階において以下の取扱いがなされます。
1.拠出時
・ 加入者拠出は所得控除
・ 企業拠出は損金参入
2.運用時
・ 年金に対して特別法人税を課税(平成14年度まで凍結予定)
3.給付時
・ 年金は公的年金等控除の対象
・ 一時金は退職所得課税を適用
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2001年9月23日 日曜日
平成13年9月23日(第58号)
<出産費貸付事業創設>
出産時には、医療保険より出産費用等の経済的負担の軽減を図るために出産育児一時金(配偶者の出産の場合は、配偶者出産育児一時金)を支給しています。現在は、一子につき30万円ですが、これらの給付は請求してはじめて行われるものであり、実際には出産後に請求が行われてから、2,3週間後に支給されています。
このため、被保険者等は、一時的に出産費用を工面する必要が生じており、こういった問題に対して、総合的な少子化対策の一環として、医療保険の保険者(政府管掌健康保険、船員保険、国民健康保険)が、被保険者または被扶養配偶者の出産に関して、無利子の資金を貸し付けることができるようになりました。
<貸付けを受けられる人>
1. 政府管掌健康保険または船員保険の被保険者(被保険者であった者を含む)で、出産育児一時金の支給を受ける見込みのある方
2. 出産予定日まで1ヵ月以内の者または1ヵ月以内の被扶養配偶者を有する者
3. 妊娠4ヵ月以上の者で医療機関に一時的な支払が必要となった者または被扶養配偶者
なお、会社等を辞められて任意継続被保険者(疾病任意継続被保険者)となった方、日雇特例被保険者も貸付を受けられます。
<貸付け額>
1万円を単位として現在24万円までが限度額として貸し付けを受けられます。なお、貸付には、利子はつきません。後ほど支給される出産育児一時金が、貸付け金の返済にあてられますが、差額は貸付申込者の金融機関の口座に振り込まれます。
<貸付け手続き>
出産費貸付金申込書に所定事項を記載し、以下の書類を添付し、社会保険協会に申し込みをします。
1. 全社連会長に受領を委任した出産育児一時金の請求書
2. 出産費貸付金借用書
3. 被保険者証
4. 母子健康手帳の写し
5. 医療機関が発行した出産費用のわかる請求書等
詳細は、社会保険労務士にお問い合わせください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2001年9月 8日 土曜日
平成13年9月8日(第57号)
「ポジティブアクション」という言葉をお聞きになったことがありますか?
個々の事業所において、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、男女労働者の間に格差が生じていることが多いのですが、法(例えば、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働基準法など)を遵守するだけでは格差はなかなか解消されません。
「ポジティブアクション」とは、このような男女間格差の解消をめざして個々の事業所が進める自主的かつ積極的な取組みのことです。次の1~5のような手順で取組みます。
1.現状の分析と問題点の発見(男女労働者の雇用状況にアンバランスがある場合にその原因を考える)
2.具体的取組計画の作成(「○年間で女性管理職○%増加」など目安となる期間の設定と目標達成のための研修等フォローアップ計画)
3.具体的取組の実施
4.具体的取組の成果の点検と見直し
5.積極的取組を行うための体制の整備とコンセンサスづくり
また、「ポジティブアクション」の具体的な目標は次の5つが挙げられています。
『女性の採用拡大』・『女性の職域拡大』・『女性管理職の増加』・『女性の勤続年数の伸張』(職業生活と家庭生活との両立)・『職場環境や風土の改善』(男女の役割分担意識に基づく慣行の見直しやセクシュアルハラスメントの防止など)
現実には、完全失業率も5%を超え、近畿地方はその全国平均を上回る失業率が続いています。最近実施されたアンケートでも、男女間格差の改善に取組めない理由として「日常業務が忙しく、対応する余裕がない」「コスト上昇につながる」というものもありました。また、男性の理解がなかなか得られないのも事実です。しかし、快適な職場環境づくりとは外見だけの美しさではなく、だれもが働く意欲のわく職場ではないかと考えています。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2001年8月23日 木曜日
平成13年8月23日(第56号)
1.安全衛生方針の表明
このシステムは事業者の安全衛生方針の表明でスタートすることになっています。では、社長さんは方針の中に何を書けばよいのでしょうか。方針には次の3点を書いて下さい。
(1) 労働者の協力の下に、安全衛生活動を実施すること
(2) 労働安全衛生関係法令及び事業場において定めた安全衛生に関する規程を遵守すること
(3) 労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施し、運用すること
2.危険又は有害要因の特定
適切な安全対策を立てるためには、何が危険であるかを認識する必要があります。先ず、工程のフローチャートを作成して下さい。次に各工程での危険個所、或いはどのような危険事態が発生する可能性があるか、をヒヤリハット報告を参照するなど、現場労働者の意見を汲み上げて列挙します。
次に危険の程度を予測して段階をつけ、表にまとめます。例えば次のような具合です。
1 2
設備又は作業項目 粉砕作業 原材料の搬送
作業内容 粉砕機による粉砕 金属塊を移動する
(噛み合せ部の点検作業)
危険源(危険要素) カバーのない回転部 積荷の崩壊
リスクの内容 指を挟まれる 積荷の下敷きになる
発生の可能性(a) 2 2
重大性(b) 2 3
評価(a×b) 4 6
取るべき対策 特になし 専用運搬車を導入
対策後発生の可能性 1
重大性 3
評価 3
稀な作業 休業災害事例あり
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2001年8月 8日 水曜日
★第55号(8/8)希望退職制度の運用にあたって事前に留意すべき点★
希望退職とは、経営をとりまく厳しい状況を社員によく説明をしたうえで、人員削減のために自主的に退職を求めるものです。
したがって、社員の理解と協力が必要不可欠です。
社員の理解と協力がなければ、希望退職は成功しないし、過剰雇用も解消しません。
希望退職は、本人の意思に基づくものとはいえ、「退職」を伴うものです。退職は、社員の人生と生活にとって重大なできごとです。
経営者の一つの責任は、社員の雇用を守ることであり、その責任を、経営環境の悪化を理由として簡単に放棄することは許されません。
今回は、希望退職制度を運用するにあたっての事前に留意すべき点をご紹介します。
1.経営責任の明確化
社員の理解と協力を得るためには、経営が不振に陥ったことについて、経営者の責任を明確にする必要があります。経営者自らの責任を明らかにすることなく、「人員が過剰になったから退職してくれないか」 「経営収支が良くないから辞めてほしい」と呼びかけても、自発的に退職届を提出して会社を去る社員はあらわれないでしょう。
2.危機意識の醸成
希望退職を成功させる条件の一つは、「社員の危機意識」です。すなわち、「経営を取り巻く環境はきわめて厳しい」「安易な方法では厳しい状況を克服できない」「仕事の量に比較して人員が過剰になっている。人員過剰を解消しなければ会社の将来はない」という意識を社員に持ってもらうことが必要です。
3.希望退職に先立つ雇用調整
希望退職を実施するまえに、退職を伴わない雇用調整策を積極的、総合的に講じるべきです。退職行為を伴わない主な雇用調整には以下のようなものがあります。
(1)時間外労働の削減・抑制
(2)休日の増加
(3)パートの再雇用停止・削減・解雇
(4)臨時社員、契約社員等の再契約停止・削減・解雇
(5)中途採用の削減・停止
(6)新卒採用の削減・停止
(7)退職者の補充見送り
(8)定年制の実施・見直し
(9)定年退職者に対する再雇用・勤務延長制の適用停止
(10)賃金調整(定期昇給の抑制・停止、ベースアップの抑制・停止、手当の減額・
不支給、賞与の抑制・不支給、基本給のカットなど)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2001年7月23日 月曜日
★第54号(7/23)解雇予告、解雇予告手当について★
「解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮することが出来ます。」 (労働基準法第20条第2項)
この不況時には、この条文はとても有名なものになっていますから、事業主は注意深く運用する必要があります。
今回は、運用するに当たっての注意点を幾つか列記します。
<解雇自体に正当な理由があるかどうか>
「解雇予告をすれば」または「解雇予告手当を支払えば」解雇がOKだと思っていませんか?
これは間違いです。労働基準法では良くても解雇理由に正当性がない場合は解雇自体が認められません。この点を勘違いしている場合が多いのです。
<日数の計算方法について>
「少なくとも30日前に予告」となっていますが、いつの日から計算していくのでしょう。
それは、予告した日の翌日からです。(民法第140条「初日不算入」)そして、30日は、労働日ではなく単純に暦日でカウントします。
ですから、例えば8月31日に解雇したいのであれば、8月1日以前には予告しなければなりません。
<解雇予告手当について>
1.支払時期・・・解雇予告手当の支払は、解雇と同時に行う必要があります。ただし、予告日数を短縮する為に予告手当を支払う場合は、予告と同時に支払う必要はなく、予告の際に予告日数と予告手当を支払う日数が明示されている限り、現実の支払は解雇の日までに行われたら良いとされています。
2.支払方法・・・予告手当の支払については、直接払い、通貨払いを行うよう指導されています。また、小切手による支払を認めない判例も有ります。ですから、事業所で直接現金で支払ってください。
<行方不明の者への予告>
解雇の意思表示は、相手方に到達しないとその効力は発生しません。しかし、行方不明の者に意思表示は出来ません。そうなると、行方不明の者はいつまで経っても解雇できません。それはとても不合理ですよね。ですから、そのような場合は、簡易裁判所に公示送達の申立を行います。そうすれば、相手がいなくても効力を発生させることが出来ます。しかし、実務上は内容証明郵便かもっと簡便な配達証明を行方不明の者の住所へ送付します。受取りがなく返却されてきても、保存しておけば意思表示を相手に到達させようとした努力はある程度証明できるからです。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2001年7月 8日 日曜日
★第53号(7/8)健康保険・厚生年金保険の保険料★
今回は健保・厚年の保険料についての話です。(なお、ここでいう「従業員」とは、健保・厚年の被保険者のことです)
<原則>当月分の保険料を、翌月分の給与から控除し、翌月末日までに納付する
(例)4月1日に採用した従業員の4月分の保険料は、5月末日までに納付
なお、保険料は月単位で計算されるので、入社した月に1日しか加入期間が無く
ても1か月分を納付する。逆に月半ばの退職は、当月分の納付義務は無い
(例)4月30日に採用した従業員の4月分の保険料は、5月末日までに納付
(例)5月30日に退職した従業員の5月分の保険料は、事業主に納付義務なし
<例外>
(イ)次の場合は、当月分の保険料を、当月分の給与から控除する
1.被保険者の資格取得をした月と同一の月に資格を喪失した場合
(例)4月1日に採用し、4月20日に辞めた従業員の4月分の保険料は、
4月分の給与から控除する
2.月末で退職した場合
(例)4月30日で退職した従業員の4月分の保険料は、4月分の給与から
控除する
(ロ)賞与等(年3回以下)を支給した場合は、毎月の保険料とは別に納付する(いわゆる「特別保険料」のこと)
(ハ)育児休業を取得した場合は、その間の保険料の納付が事業主・従業員とも免除される。特別保険料も同様に免除される
(ただし、免除されるためには申請が必要。また産後休暇中は免除されない)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2001年6月23日 土曜日
★第52号(6/23)児童手当の支給要件が緩和★
今年、6月からの所得制限限度額は、301万円(現行170万円)に扶養親族等および児童1人につき38万円(当該扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は1人につき44万円)を加算した額とされます。
ただし、手当支給率を国民年金加入者と同程度に揃えるという意味合いから、厚生年金加入者、共済年金加入者などの場合には、特例給付が適用されており、この限度額も上がっています。
<平成13年6月以降の児童手当の所得制限の限度額>
扶養家族等の人数 所得制限額 特例給付の場合
0人 301万円 460万円
1人 339万円 498万円
2人 377万円 536万円
3人 415万円 574万円
4人 453万円 612万円
5人 491万円 650万円
6人 529万円 688万円
なお、昨年度以前に所得制限により受給できなかった方でも、所得の変動などのため、再度請求していただくことにより受給できる場合があります。
詳しくは、従業員の方がお住まいの市役所、区役所等におたずねください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2001年6月 8日 金曜日
平成13年6月8日(第51号)
この給付金は、事業内職業能力開発計画書に基づいて、従業員に体系的かつ段階的に職業訓練等を行う事業主に対して助成するもので、労働者の職業能力の開発向上を図るこことを目的としています。そして、生涯能力開発給付金には、次の2種類があります。
講師謝金・手当等
1.能力開発給付金 企業内で実施 運営費 施設・設備の借上費
教材費
受講期間中の賃金
受講奨励金等(55歳以上)
入学料・受講料・教材費
外部の教育訓練施設に派遣 受講期間中の賃金
受講奨励金等(55歳以上)
有給教育訓練休暇の付与 入学料・受講料・交通費等の援助
2.自己啓発助成給付金 休暇期間中の賃金
有給教育訓練休暇の付与以外 入学料・受講料・交通費等の援助
※ ただし、初年度は25歳以上が対象(中小企業のみ)です。
【受給要件】 次のすべてに該当する雇用保険の適用事業主であること
・事業内職業能力開発計画届を提出(4/1~6/30)していること
・上記計画書に基づき、従業員(雇用保険の被保険者)に教育訓練を受けさせ、費用全額を
事業主が負担していること
・実際の訓練時間が10時間以上あること
・給付金の支給申請に係る証拠書類を整備し、提出できること
給付内容は、運営費・受講費等50,000円(55歳以上は70,000円)を限度としてかかった費用の1/2~1/8、訓練中の賃金は、年齢により1日につき3,000円から5,000円、バランスよく計画書を作成、訓練実施し導入奨励金の対象となった場合は、300,000円(1事業所1回限り)等です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2001年5月23日 水曜日
★第50号(5/23)国民年金の「学生納付特例制度』をご存知ですか?★
(弊紙でも昨年この制度をご紹介いたしました)
申請し承認を受ければ、毎月13,300円の保険料支払いを先延ばしできますが、申請者は該当者の約6割にとどまっているそうです。
1.対象者は?
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設(各種学校その他の教育施設については、個別に定められている)に在学する学生等(それぞれ夜間、通信教育の課程を除く)。
学生本人の前年の所得が68万円以下(扶養親族等がない学生の場合は、約133万円までの年収)であることが条件です。(親世帯の所得は不問です)
2.届出の時期と方法は?
20歳になった月の翌月の月末までに、「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入の上、住所地の市区町村の国民年金担当窓口に提出します。「申請書」は国民年金担当窓口に備え付けてあります。手続きには次のものを持参します。
イ.学生証(コピー可)
ロ.年金手帳
ハ.みとめ印
※ なお、届出は前年の所得を確認する必要があることから、毎年度必要となります。
3.学生納付特例の承認を受けるとどうなるか?
(1) 学生納付特例期間中に、万が一の事故や病気で障害が残った場合、受給資格があれば満額の障害基礎年金が支給されます。いわゆる「無年金障害者」にならずにすみます。
(2) 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。年金の額には反映されませんが、10年以内であれば、保険料を追納することができます。追納は、一括・分割どちらでも可です。(2年を過ぎて追納する場合は、当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます)
※学生納付特例制度は申請のあった月の前月から承認することとなっています。つまり、承認される前の期間は、保険料を納めなければ未納期間となりますのでご注意ください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2001年5月 8日 火曜日
★第49号(5/8)労働安全衛生マネジメントシステム(3)★
「4.1.1 安全衛生方針の表明」に続いて、次のようにステップを進めます。
4.1.2 危険又は有害要因の特定及び実施すべき事項の特定
ただ注意せよといっても精神論に終わってしまいますから、当該工事に伴う危険にはどんなものがあるか、健康に有害なものとしてはどのようなものあるかを具体的に列挙します。
次に、これらの危険又は有害要因を除去あるいは低減するために何をすべきかを決めます。
決定に当たっては、労働安全衛生法等の法令、自社の安全衛生規程を参考にします。
4.1.3 安全衛生目標の設定
4.1.2で特定された危険又は有害要因等を踏まえ、4.1.1の安全衛生方針に基づき、安全衛生目標を設定します。
4.1.4 安全衛生計画の作成
安全衛生目標を達成するため、4.1.2で特定された実施すべき事項、安全衛生に関する行事等の日常的な安全衛生活動に係る事項、作業所の指導及び支援に関する事項等を容とする安全衛生計画を作成します。
4.1.5 労働者の意見の反映
安全衛生目標の設定及び安全衛生計画の作成に当たり、安全衛生委員会の活用等労働者の意見を反映する手順を定め、この手順に基づいて労働者の意見を反映させるようにします。
安全衛生計画の実施及び運用に当たっても労働者の意見を反映する手順を定め、この手順に基づいて労働者の意見を反映するようにします。
このシステムは図のように、[計画]→[実施]→[評価]→[改善]、すなわち Plan, Do, Check,Act のサイクルを繰り返すことによって、より高いレベルに到達することを目指しています。
上に述べたことは、会社全体としての[計画]段階になります。個々の作業場での計画については後で述べることとし、次回は実施段階へ進みます。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2001年4月23日 月曜日
★第48号(4/23)労災保険の中小事業主等の特別加入制度をご存知ですか?★
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
1.特別加入できる中小事業主およびその者が行う事業に従事する者
「中小事業主」とは、常時300人(金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業にあっては50人、卸売業にあっては100人)以下の労働者を使用する事業の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)をいいます。
「中小事業主が行う事業に従事する者」とは、労働者以外の者で当該事業に従事する者をいいます。すなわち、特別加入を行うことのできる事業主の家族従事者や中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員などが対象となります。
2.特別加入を行うための条件
(1)雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
(2)労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
3.給付基礎日額
労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。最高1日2万円(年間730万円)
4.保険料について
保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日)×それぞれの事業に定められた保険料率
例えば、給付基礎日額を1万円とした場合の年間保険料は、小売業では約2万円、建設業(既設建築物設備工事業)では、約5万5千円となります。また、労働保険事務組合に加入する必要かありますので、別途会費等が必要です。
中小企業事業主と同様に、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者についても、特別加入の制度が設けられています。また、今年4月からは、介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練または看護に係る作業に従事する者を対象とした労災保険の特別加入制度が新設されました。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2001年4月 8日 日曜日
★第47号(4/8)組織構造について★
分業によって細分化された作業をグループ化することをすることを部門化といい、部門化するための基準となるのが、生産、販売、研究開発、人事、財務などの職能および製品、サービス、地理、顧客などの目的です。そしてその部門化するための基準により、通常、組織図として示される組織構造は2つあります。
それは、(a)職能別組織と(b)事業部制組織です。
(a)職能別組織
職能別組織とは、上記に記載したとおり生産、販売、研究開発、人事等の職能別の部門化
による組織であり、少数事業の経営に向く集権的な組織です。
<メリット>
・専門化による知識や経験の高度利用
・経営資源の共通利用による経済性・経営資源の統一的管理
<デメリット>
・部門間の対立やセクショナリズムの発生
・ゼネラリストの育成が困難(人事政策で幾分解消可能)
・部門間の調整機能がトップに集中し、意思決定が遅延する
(b)事業部制組織
事業部制組織とは、製品、サービス、地理、顧客などの目的別に部門化した組織です。
各事業部は、それぞれが目的遂行に当たって必要な職能を全て備えていることから自己完結的組織ともいわれ、分権的な構造です。
<メリット>
・ゼネラリストが育成できる。
・分権化により意思決定が迅速化し、事業部ごとの柔軟な対応や革新が可能になる。
・事業部ごとに業績評価が可能であるため資源の配分を合理化できる。
<デメリット>
・企業全体の利益よりも事業部の利益が優先する・経営資源の重複が生ずる。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2001年3月23日 金曜日
平成13年3月23日(第46号)
平成13年4月1日以降の離職に関しては、下記のとおりの給付となります。
①一般の離職者(定年退職者や自己の意思で離職した者)
被保険者区分
(全年齢共通) 被保険者であった期間
5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
一般被保険者 90日 120日 150日 180日
短時間労働被保険者 90日 90日 120日 150日
②倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満 5年以上
10年未満 10年以上
20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ―
30歳以上45歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
※ 網掛けの部分は、一般の離職者よりも給付日数が手厚い層を表します。
※ 短時間労働被保険者の場合は日数が異なります。
※ 倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされたものとして手厚い給付日数が給付されることとなる方(特定受給資格者)とは、具体的には、下記の類型に該当する方をいいます。
(「倒産」等により離職した者)
①倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止)に伴い離職した者
②事業所の縮小又は廃止に伴い離職した者
③事業所の移転により通勤困難となったことにより離職した者
(「解雇」等により離職した者)
①解雇(重責解雇を除く)により退職したもの
②実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していたことにより退職した者
③継続して2ヶ月以上にわたり、賃金の一定割合以上が支払われなかったことにより退職した者
④賃金が、その者に支払われていた賃金に比べ一定程度未満に低下したため退職した者
(低下の事実が予見困難なものに限る。定年後の賃金低下などは対象外)
⑤離職の直前3ヶ月間に、労働基準法に基づき定める基準を超えて残業が行われたため、又は生命・
身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政機関から指摘を受けたにもかかわらず、事業所
において改善が行われなかったため退職した者
⑥事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っ
ていないため、雇用契約の終了を余儀なくされた者
⑦期間の定めのある雇用契約が反復された場合であって、当該雇用契約が更新されないことが予期
できない事態と同視しうる状態(一定期間以上、反復された雇用契約が継続した場合)で、雇用契
約が更新されないことにより、退職した者
⑧上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した者
⑨事業主から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより退職した者(従来から設け
られている「早期退職優遇制度」等に応募して退職した場合は、これに該当しない。)
⑩全日休業により3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当が支給されたことにより退職した者
⑪事業主の事業内容自体が法令に違反するに至ったため退職した者
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2001年3月 8日 木曜日
★第45号(3/8)行政が行った処分に不満があるときどうしますか?★
労働社会保険諸法令に基づいてなされた処分に不服がある場合は不服申立という制度を活用しましょう。
不服申立は、行政不服審査法、各法律に特別の定めがある場合その法律に基づいて行われます。
では、今回は労働法分野ではどのような手続の流れになるのか説明していきましょう。
1. 労働法分野
労働法の中で代表的な法律で皆さんと深い関わりがある労災保険、雇用保険について説明していきます。
<労災保険>
不服申立は、2段階の請求が行えます。1段階目が各都道府県労働局にいる労働者災害補償保険審査官に行う審査請求、2段階目が東京にある労働保険審査会に対して行う再審査請求です。また、この段階を踏まないと裁判を起こすことができませんので注意が必要です。
※審査請求・・・労働基準監督署長が行った処分に不服がある場合(例えば、労働災害だと思って治療費や休業時の休業補償を請求したにも関わらず、支給しないとの決定がありそれに不満があるとき)に、処分がわかった日(配達証明付郵便を受け取った日)の翌日から60日以内に手続をします。
※再審査請求・・・審査請求が棄却された(労働基準監督署長が行った処分を支持した場合)ことを知った日の翌日から60日以内に手続をします。
<雇用保険>
この不服申立も2段階の請求が行えます。1段階目が各都道府県労働局にいる雇用保険審査官に行う審査請求、2段階目が東京にある労働保険審査会に対して行う再審査請求です。
また、この段階を踏まないと裁判を起こすことができませんので注意が必要です。
※審査請求・・・職業安定所長が行った処分に不服がある場合(例えば、失業給付を請求したにも関わらず、支給しないとの決定がありそれに不満があるとき)に、処分がわかった日の翌日から60日以内に手続をします。
※再審査請求・・・審査請求が棄却された(職業安定所長が行った処分を支持した場合)ことを知った日の翌日から60日以内に手続をします。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2001年2月23日 金曜日
★第44号(2/23)年次有給休暇Q&A★
1 年休の買い上げ
Q. 当事業所では、退職時に使い切れなかった年休を買い上げていますが、これは法律的に問題はないですか?
A. 年休を買い上げること(買い取りの予約など)は、年休を与えないということになるので、原則的には法律違反です。しかし、い上げが禁止されているのは、法律に基づいて付与される年休に限られ、退職によって効力がなくなる年休については、法律の及ところではありません。したがって、退職者の年休の買い上げは特に問題ありません。また、年度内に使い切れなかった分の年休を、結果的に買い上げることも差し支えあ
りません。
2 退職時のまとめ取り
Q. 当事業所では、退職時に年休をまとめ取りして1日も出勤せず、給与のみ受け取って退職していくというケースが慣例化し、業務の引継ぎが十分できません。時季変更権を行使できますか?
A. 労働基準法は、業務の正常な運営を妨げる場合には、年休請求日を他の日に変更させることができる、と規定しています。これが、時季変更権と言われるものです。しかし、時季変更権を行使できるのは、他に変更できる日がある場合に限られます。上記のケースでは、退職者は年休を使い切ってしまった日に退職するわけですから、他に変更できる日はないということになります。このため、時季変更権を行使することはできません。法律面で年休のまとめ取りを防ぐ有効な手立てはない、ということになります。年休に入る前に、業務の引継ぎを完全に行なうよう指示する以外にありません。
※ 欠勤をゼロにするために、年休の振り替えをする場合、従業員本人からの申出に基づいて行なうのであれば、特に問題はありません。(「年休を付与しなかった」ということにはなりません)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2001年2月 8日 木曜日
★第43号(2/8)労働安全衛生マネジメントシステム(2)★
建設業の経営者が、労働者の協力の下に「計画-実施-評価-改善」の一連の過程を定めて継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進することにより、建設事業場における労働災害の潜在的危険性を低減し、労働者の健康増進、快適職場の形成を促進し、もって建設事業場における安全衛生水準を高めることを目的とします。
2.適 用 等
このガイドラインは、危険又は有害要因等を考慮しながら、建設業労働安全衛生マネジメントシステムを確立しようとする建設事業者に適用でき、すべての規模の建設事業場を対象とします。また、これは労働安全衛生法に基づいて事業者が行うべき具体的な措置を細かく定めるものではありません。
「うちの会社は小さいからこんなことは考えなくてもいいよ。」ではなく、
「あなたの会社に最も適した方法をみんなで考えて実行しましょう。」と
いうわけです。具体的なことはそれぞれの事業者が、自社に最もシッ
クリ合うように定めることが求められています。
3.用語と定義(省略)
4.システムを確立するために必要な基本的事項
4.1.1 安全衛生方針の表明 (項目番号を原文に合わせていますので、飛び飛びになっています。)
1)事業者は、建設事業場における安全衛生方針を表明し、労働者に周知させます。
2)安全衛生方針には次の事項を含めます。
(1)労働者の協力の下に、安全衛生活動を実施すること
(2)労働安全衛生関係法令及び建設事業場において定めた 安全衛生に関する
規定等を遵守すること
(3)計画-実施-評価-改善のサイクルを適切に実施し、運用すること
3)安全衛生方針を必要に応じて関係する事業者に周知させることが推奨されます。
事業者は、経営の責任の一つとして、まず、自らの方針を掲げることが求められています。そして、それを従業員すべてに知らせ、従業員の協力の下に安全衛生活動を進めていくのがよいというわけです。「知らしむべからず、依らしむべし」とか、一方的な上意下達だけでは人は動きません。人を動かすためには、人をその気にさせなければならないのです。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2001年1月23日 火曜日
平成13年1月23日(第42号)
1.目 的
職を失い深刻な状況に直面している中高年齢者を一定期間試行的に雇用する事業主に対して、奨励金を支給する等の支援を行うことで、中高年齢者の雇用を増加させるきっかけを作るための事業が創設されました。
2.高年齢者緊急就業開発事業の概要
対象事業主 雇用保険の適用事業主
対象労働者 公共職業安定所に求職申込をしている45歳以上の求職者
支給要件 1. 公共職業安定所に求職申込をしている45歳以上の労働者を公共職業安定所の紹介により試行就業させること。
2. 過去6ヵ月以内に事業主都合で解雇をしていないこと。
3. 過去3年以内に同一の事業所を離職した者でないこと。
実施方法 1. 公共職業安定所に試行就業に係る求人の申し込みを行う。
2. 公共職業安定所の紹介により、面接等を行い採否を決定する。
3. 雇い入れから2週間以内に、常用労働者への移行に向けて中高年齢者試行就業実施計画書を作成し公共職業安定所に届出る。
4. 試行就業終了後、2週間以内に、所定の様式により、試行就業の実施結果の報告書を公共職業安定所に提出する。
試行就業期間 原則として3ヵ月
試行就業中の労働条件 1.関係法令を遵守し、1週間の所定労働時間は、同じ事業所で雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度とする。
2.対象労働者が65歳未満であれば、雇用保険の被保険者とする。
支給額 対象労働者1名に対して1ヶ月当たり10万円(上限)、最高3ヶ月
支給時期 試行就業期間終了後、2ヶ月以内に申請
留意点 試行就業終了後は、常用雇用に移行し、引き続き雇用するよう努力すること。
3.申請窓口
各都道府県の高齢者雇用開発協会が、支給申請受付等の事務をおこないます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2001年1月 8日 月曜日
平成13年1月8日(第41号)
<健康保険制度の主な改正内容>
改定項目 改正前 改正後
高額療養費の
自己負担限度額 1ヵ月 63,600円 1ヵ月 63,600円 +
(医療費-318,000円)×1%
入院のときの
食事負担 1日 760円 1日 780円
標準報酬月額 92,000~980,000円 98,000~980,000円
介護保険料率 1000分の6 1000分の10.8
育児休業期間中の保険料 被保険者本人負担分のみ免除 事業主負担分+賞与などにかかる
特別保険料も免除
<老人保健制度の主な改正内容>
改正項目 改正前 改正後
外来のとき 一部負担金
1日 530円
(月4回まで) ・ 医療機関で院外処方せん
を交付されなかった方は
医療機関で3,000円
・医療機関で院外処方せん
を交付された方は
医療機関で1,500円
薬局で 1,500円
入院のとき 一部負担金
1日 1,200円 医療費の1割
食事負担 1日 760円 食事負担 1日 780円
訪問看護を受けたときの基本利用料 1日 250円 老人保健の訪問看護
に要する費用の1割
老人高額医療費
支給制度
(新規に創設) 1ヵ月 30,000円以上の一部負担金を支払った老人の方が、同一世帯に複数いるときなどは、合算して、37,200円を超える額が払い戻されます。
※ 1月には健康保険証の更新も行なわれます。ご注意ください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2000年12月23日 土曜日
★第40号(12/23)雇用保険の適用が拡大されます★
以下の適用基準が廃止されます。
・年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)
・1ヶ月あたりの所定労働日に関する要件(1ヶ月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)
新しい適用基準
次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する場合に被保険者となります。
(イ)次の①又は②に該当する場合
①同じ派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
②派遣元事業主との雇用契約が1年をこえないものや派遣先が異なる場合であっても、
同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれるとき。
(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.パートタイム労働者の雇用保険の適用基準が緩和
以下の適用基準が廃止されます。
・年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)
新しい適用基準
次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する場合に被保険者となります。
(イ)1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が1年である場合
・3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合で、その事業所の過去の就労実績等からみて、
契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれる場合
(ロ)1週間の労働時間が20時間以上であること
※すでに雇用されている登録型派遣労働者・パートタイム労働者で、今までの基準では適用されなかった労働者も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年12月 8日 金曜日
平成12年12月8日(第39号)
平成13年1月から引き上げられます~
○育児休業給付とは‥
雇用保険の一般被保険者が1歳未満の子を養育する為に育児休業を取得して賃金が一定水準を下回った場合に、その被保険者に対し次の2つの給付金が支給される制度です。
<育児休業基本給付金>育児休業の期間中に支払われた賃金が‥
50%以下 → 休業開始時賃金月額×30%
50%超80%未満 → 休業開始時賃金月額×80%-賃金
80%以上 → 支給されません
<育児休業者職場復帰給付金>
育児休業終了後、引き続き6ヵ月間雇用された場合に一時金として‥
休業開始時賃金月額×10%が支給されます。
○介護休業給付とは‥
雇用保険の一般被保険者が要介護状態にある対象家族を介護する為に介護休業(支給対象となる一人の家族につき1回の介護休業期間に限る。ただし、最長3ヵ月間)を取得し賃金が一定水準を下回った場合に次の給付金が支給される制度です。
<介護休業給付金>介護休業の期間中に支払われた賃金が‥
40%以下 → 休業開始時賃金月額×40%
40%超80%未満 → 休業開始時賃金月額×80%-賃金
80%以上 → 支給されません
※改正後の給付率の適用は、支給単位期間の初日が平成13年1月1日以降にある支給対
象期間に限ります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2000年11月23日 木曜日
平成12年11月23日(第38号)
1.使用者が労働者に支払うもの
× 旅館・飲食店などにおいて客が従業員に手渡すチップ
○ 無償・低廉な価格で食事の供与を受け、または当該旅館等に宿泊を許される場合の実物給与・利益
○ レストラン・バーなどで一旦事業主に支払われ(サービス料)、当日の労働をした労
働者に機械的に分配される場合
2.労働の対償
(イ)任意的恩恵的給付・・・これに該当するものは、労働の対償とはいえない
1)慶弔禍福の給付 ただし、労働協約・就業規則・労働契約などにあらかじめ支
2)家族手当 給条件が明確にされており、それに従い使用者に支払義務が
3)退職手当 あるものは、労働の対価と認められ、賃金となる。
4)一時金(賞与)
5)社外積立の退職金
6)貨幣以外の物または利益の支給
(ロ)福利厚生給付・・・労働の対償としてでなく、福利厚生のためのものは賃金ではない
1)資金貸付・住宅貸与・共同利用施設
2)食事の供与 就業規則に規程していない
食事代が賃金から差し引かれない この3点を満たす場合は賃金
豪華な食事では無い では無い
3)企業の負担する生命保険料
×税金・社会保険の労働者負担分~労働者がそれによって法令上の義務を
免れるので賃金となる
(ハ)企業設備・業務費・・・業務上必要なものであるため賃金ではない
1)作業服・作業用品代
2)出張旅費・交際費
×通勤手当~本来労働者自身が負担すべきものなので、賃金となる。
3.労基法上の諸手当・・・賃金と解さないものもある
(イ)休業手当
(ロ)解雇予告手当
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2000年11月 8日 水曜日
★第37号(11/8)労働安全衛生マネジメントシステム(1)★
これまでは、法律の規制によって災害をなくしていこうというのが基本的な考え方でしたが、今後は企業オーナーや経営者並びに従業員の自主的な活動によって災害を減らしていくべきであるという方向にあります。
ISO 9000 とか ISO 14000などの国際標準の認証を取って製品の品質を高めている
ことが企業のPRによく利用されています。労働安全衛生についても同じような動きがあ
り、ここ数年議論が続いてきました。
しかし、企業における安全衛生管理は製品の品質管理とは性質が違い、第三者機関の認証を取得するといった性質のものではなく、それぞれの企業の自主活動によるべきものであるという考えが主流になってきています。
そのため、ISOではなく、ILOが国際的な取りまとめをすることになりました。
一方、会社の労働安全に対する取り組みを、第三者の機関に監査してもらい、認証を得たいという企業もあります。そのために使われているのが OHSAS 18001という規格です。
この規格は ISO 14001とそっくりに作られており、既に ISO 14001の認証を取得した企業にとっては比較的容易に認証が得られると言われています。
しかし、認証手続きやその後の維持にはかなりの金額が必要とされています。
我が国では平成11年に労働省から「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」が発表され、その後幾つかの業界団体がそれぞれの業界に特有の事情を踏まえて成文化した安全衛生管理指針(マネジメントシステム)を発表しています。
建設業界は労働災害の発生が多いため、新しい考え方に立つ労働安全衛生マネジメントシステムの普及に熱心で、「建設業労働災害防止協会」が「建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」と、その解説書を配布して普及に努めています。
労働安全衛生シリーズは次回から、その要約とキーポイントを解説していく予定です。建設業に限らず、きっと皆様のお役に立つと思います。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年10月23日 月曜日
★第36号(10/23)労働条件明示の義務★
そこで、労働基準法では、使用者に対し、労働契約を締結する際に、労働者に労働条件を明示する義務を課しています。
<明示すべき労働条件の範囲>
1. 労働契約の期間に関する事項
2. 就業の場所・従事する業務の内容に関する事項
3. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替
制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
4. 賃金の決定、計算・支払いの方法,賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項
5. 退職に関する事項
6. 昇給に関する事項
7. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定,計算・支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
8. 臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金に関する事項
9. 労働者に負担させる食費、作業用品代その他に関する事項
10. 安全・衛生に関する事項
11. 職業訓練に関する事項
12. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
13. 表彰、制裁に関する事項
14. 休職に関する事項
※上記のうち1から5については、書面で明示する必要があります。
労働者を採用するときは、後々のトラブルを避けるためにも十分な説明と話し合いを行い、書面で労働契約書の締結を行いましょう。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年10月 8日 日曜日
★第35号(10/8)賃金の引き下げについて★
1.基本的な方法
賃金の引き下げ等の労働条件の不利益変更を実施するにあたっては、
①従業員と協議する方法、
②就業規則を変更する方法
の2通りの方法が考えられます。
2.従業員と協議する方法
労働契約も契約ですから、その内容についても、労働基準法等の労働法規に反しない限り当事者の合意により変更することが出来るのは当然のことです。
したがって、当事者である使用者と従業員との間で協議をし、その結果合意の上で変更するのであれば、たとえ従業員の不利になる変更であれ、労働基準法等の労働法規に反しない限り変更することは可能です。
ただし、当事者間の協議において従業員に提示された条件を飲まなければより条件の悪い処遇や解雇があるような言動を取ることは、厳に慎まなければなりません。
また、合意結果は文書にして当事者の署名捺印し、保存することは当然です。
3.就業規則(賃金規程等)を変更する方法
就業規則(賃金規程等)を変更する方法は、使用者による一方的な変更です。なぜなら、就業規則の変更には従業員代表による意見書の添付が必要なだけで、同意までを求めている訳ではないからです。
しかし、不利益変更の場合は恣意的且つ一方的な変更では争いが生じた場合非常に不利になります。
ですから、判例が示す以下の一方的不利益変更の合理性の判断基準に沿って変更することになります。
①変更の必要性と変更後の制度内容のそれぞれについての合理性が問題とされること
②不利益の判断にあたっては、その緩和策、代償措置が講じられているかが考慮されていること
③同業他社の状況その他世間水準も制度内容の合理性判断の参考となること
④多数従業員との話し合いの状況やその反応も制度内容の合理性判断の参考となること
⑤賃金・退職金といったものの不利益変更については特に高度の合理性が要求されること
※ 自分が不利益を被る立場であれば、どの程度で折り合いが付けられるかを考えながら変更をおこなわなければなりません。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年9月23日 土曜日
★第34号(9/23)時間外労働Q&A★
Q.当事業所では、1日2時間、1ヶ月30時間という時間外労働協定を結んでいます。仕事がとても忙しいときに、従業員自身が同意すれば、1日3時間や1ヶ月35時間の時間外労働を命令できますか?
A.たとえ従業員が個人的に同意しても、協定の時間数を超える時間外労働は労働基準法違反となります。
2 役職者との協定
Q.当事業所には労働組合がないため、役職者を従業員代表に指名し、その者と時間外協定を結んでいますが、問題はありませんか?
A.従業員代表は、従業員が投票や挙手などの方法で自主的に選任すべきでものです。事業所が一方的に役職者を従業員代表に指名するのは適切ではありません。従業員代表として適格性を有しない者が締結した協定は、適法な時間外労働協定とはいえず、これに基づいて時間外労働を行なわせることは労働基準法違反となります。
3 割増率の低い残業手当
Q.ある従業員が「少しでもたくさん収入を得たいので、割増率は20%でもいいから残業をやらせてほしい」と申し出ました。割増率が低ければ事業所としても都合がいいのですが、その申出を受け入れてもよいのですか?
A.労働基準法は残業の賃金割増率を25%以上としていますので、25%を下回るのは法違反です。たとえ従業員自身の申出であっても、法違反であることに変わりありません。
4 法定労働時間内の残業
Q.当事業所は所定労働時間を7時間としています。1時間の残業を命令した場合、残業分の手当はどのように取り扱えばいいですか?
A.1日8時間以内の労働は、労働基準法上残業扱いとしないで差し支えありません。したがって、通常の賃金を支払えばそれで足ります。
5 遅刻者の取扱い
Q.当事業所では勤務時間を「午前9時~午後6時」としていますが、1時間遅刻した従業員に対しても、午後6時以降の労働を時間外扱いとし、割増賃金を支払わなければならないのですか?
A.労働基準法が割増賃金の支払を義務付けているのは「1日8時間を超える労働」に対してです。1時間遅刻した従業員は、午後7時以降に8時間を超えることになります。
したがって、午後7時までの労働に対しては割増賃金を支払う必要はありません。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年9月 8日 金曜日
★第33号(9/8)厚生年金保険の標準報酬月額の上下減額が改定されます★
<現 行>
報酬月額 標準報酬
1級 95,000円未満 92,000円
2級 95,000円以上101,000円未満 98,000円
<改定 後>
報酬月額 標準報酬
1級 101,000円未満 98,000円
<現 行>
報酬月額 標準報酬
30級 575,000円以上 590,000円
<改定 後>
報酬月額 標準報酬
29級 575,000円以上605,000円未満 590,000円
30級 620,000円以上 620,000円
※なお、改定は厚生年金保険に関しての報酬月額だけですので、健康保険に関しましては従来とおりの標準報酬月額をあてはめます。
※保険料の引き落としは原則「翌月控除」です。よって今回の算定基礎で改定された保険料は意図的に「当月控除」を採用していない限り11月分給与から控除します。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年8月23日 水曜日
★第32号(8/23)賃金の口座振込みについては、本人の同意が必要です★
◎口座払いについて労働基準法施行規則は、次のように規定しています。
「使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができる」
つまり、事業所の方で一方的に口座振込みを行なうことは認められていません。
◎口座振込みについて、労働省では次のような通達を出しています。
1.口座振込みは、書面による個々の労働者の申出又は同意により開始し、その書面には次に掲げる事項を記載すること
ア.口座振込みを希望する賃金の範囲およびその金額
イ.指定する金融機関店舗ならびに預貯金の種類および口座番号
ウ.開始希望時期
2.労働組合又は従業員代表と次に掲げる事項を協定すること
ア.口座振込みの対象となる労働者の範囲
イ.口座振込みの対象となる賃金の範囲およびその金額
ウ.取扱金融機関の範囲
エ.口座振込みの実施開始時期
3.口座振込みの対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること
ア.基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
イ.源泉徴収額、労働者が負担すべき社会保険料額等、賃金から控除した金額
ウ.振込んだ金額
4.振込まれた賃金は、所定の賃金支払日の午前10時ごろまでに払出しが可能になっていること
5.取扱金融機関は、一行に限定せず複数とするなど、労働者の便宜に十分配慮して定めること
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年8月 8日 火曜日
平成12年8月8日(第31号)
1.労働災害の数
業務上の傷病、いわゆる労災はどのくらい発生しているのでしょうか?
日本全国では1年間に
この数は、ここ25年の間にそれぞれ約半減しているのですが、それでもまだまだ多いですね。「うちは大丈夫。」と気を緩めていると、事故が起こって青くなるということになりかねません。では何が原因で事故が起こっているのでしょうか。
2.労働災害の原因
労働災害死亡事故の原因 重大災害の原因(平成10年)
死亡者数 1,844人(平成10年) (1件3人以上死亡)
上の図に見られるように、最も多いのが交通事故です。建設業では墜落・転落 と
物の飛来・落下が多く、製造業では挟まれ・巻き込まれ が多くなっています。これら4つの原因に対して十分な対策ができれば、死亡数は半分以下になるのは確実です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2000年7月23日 日曜日
★第30号(7/23)社会保険の手続きモレはありませんか?★
1.昇給等があった時には・・・
4月は多くの会社で昇給等が行われる時期です。昇給等で固定的賃金に変動があった時には、標準報酬の随時改定が行われることがありますので、注意が必要です。
※「随時改定」とは報酬が大幅に変わった場合、通常の決定時期を待たずに標準報酬の改定が行われ保険料が変わることです。
以下の3つの要件すべてに該当する人について行われます。
(1)昇給などで固定的賃金に変動があったとき
(2)固定的賃金の変動月以後引き続く3ヶ月間に受けた報酬の平均月額と現在の
標準報酬月額の等級との間に2等級以上の差が生じたとき
(3)対象となる3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が20日以上あるとき
該当した場合には「被保険者報酬月額変更届」により変動月から3ヶ月間の報酬を届出ます。報酬月額を算出する際には、残業手当などの非固定的賃金も含めます。
ただし、昇給で基本給が上がったが残業が少なくて結果として総額が下がったような場合には、随時改定は行われません。
2.賞与が支払われた時には・・・
年3回まで支払われる賞与に対しては、事業主は被保険者に支払った賞与額の1000分の8(被保険者負担1000分の3、事業主負担1000分の5)を健康保険に、1000分の10(被保険者、事業主折半負担)を厚生年金に、特別保険料として納めなくてはなりません。
賞与の支払いがあったときには、事業主は「賞与等支払届」を作成し、社会保険事務所に被保険者全員の賞与の支払総額を届出ます。
この届出に基づいて特別保険料が計算され、一般の保険料に合算されて、翌月の納入通知書で請求されます。一般の保険料と
一緒に翌月末日までに納入することとなります。
随時改定に該当した場合には変動月から4ヶ月目に(4月昇給であれば7月分から)等級が改定されます。賞与の支払いがあったときには、忘れずに「賞与支払届」を提出しましょう。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年7月 8日 土曜日
平成12年7月8日(第29号)
平成12年4月から、学生本人が一定所得以下であれば、在学期間中の保険料を「後払い」できるようになりました。(「10年間」の支払猶予制度=「学生納付特例制度」)
4. 対象者
大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、専修学校および各種学校等(具体的には個別に定めてあります。)に在学する学生等(それぞれ夜間、通信教育の課程を除く)であって、学生本人の(親の所得は関係なく)前年の所得が68万円以下(扶養親族などがいない場合であれば、収入が133万円以下)である人です。
5. 届出方法
住所地の市区町村の「国民年金の窓口」に申請書および下記の添付書類を提出します。
①年金手帳
②学生であることを証明するもの
③前年所得のある場合は所得証明書など
6. いつから適用になるのか?
届出(申請)のあった月の前月から承認することになっています。
ただし、平成12年に限り、7月末日までに申請すれば、平成12年4月から承認されます。
7. どのような効果が発生するのか?
(1)学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の「障害基礎
年金」又は「遺族基礎年金」が保障されます。
(2)特例期間はこれまでの学生の申請免除と違い、「老齢基礎年金」の受給資格要
件には算入されますが、年金額には反映されません。
(3)各月から10年以内であれば保険料を追納することができ、追納があった期間
のみ年金額に反映されます。
8. 従前の制度はどうなったのか?
20歳以上の学生の国民年金強制適用に伴い設けられていた、これまでの「学生の申請免除」は、平成12年3月で廃止されました。ただし、「法定免除」(1、2級の障害年金受給者、生活保護需給者などが対象)は、今後も学生に適用されます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2000年6月23日 金曜日
★第28号(6/23)最低賃金Q&A★
A. 最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を求め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
Q2.最低賃金はすべての人に適用されるのですか?
A. 最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働基準局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められて
います。
<最低賃金の適用除外を受けられる労働者は>
①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
②試用期間中の者
③職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
④ イ 所定労働時間の特に短い者
ロ 軽易な業務に従事する者
ハ 断続的労働に従事する者
となっています。
適用除外許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書3通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働基準局長に提出してください。
Q3.最低賃金にはどのようなものがありますか?
A. 最低賃金には下図のように地域別最低賃金(各都道府県内すべての労働者とその使用者に適用)と産業別最低賃金(各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者に適用)の2種類があります。
なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年6月 8日 木曜日
★第27号(6/8)私傷病で欠勤中の社員の給料や社会保険料の取り扱い★
「ノーワーク・ノーペイの原則」
会社を欠勤している原因が私傷病の場合には、「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されます。
したがって欠勤した日数に応じて給料を控除しても法的に何ら問題はありません。
また、欠勤中の社会保険料や住民税については、給料が支払われているか否かに係らず、社員が会社に在籍している限り、本人から徴収することになります。給料が支払われていない場合の社会保険料等の徴収の方法は、前もって預かるか、会社が一旦立て替えておいて社員が出社してから返してもらうなどの方法があります。
※無給とする場合に社会保険料や住民税を本人から徴収せずに、会社が支払うと、その場合は所得税法上賃金とみなされ、課税対象となりますので、注意して下さい。
「傷病手当金」
休業日について給料を支払わなかった場合には、療養のため労務不能となった日について、標準報酬日額の60%に相当する額が、療養のため労務に服することができず、連続して3日休業した場合(待期期間といいます)健康保険から傷病手当金として4日目から最長1年6ヵ月間支給されます。
ただし、「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されるとは言え、就業規則に、私傷病による欠勤の場合であっても給料を支払う旨の定めがある場合には、もちろんその定めによって、給料を支払わなければなりません。
その場合、標準報酬日額の60%以上の給料を支払った日については、傷病手当金は支給されず、支払われた給料が標準報酬日額の60%未満の場合には、その差額が傷病手当金として支給されます。
(例えば、支払われた給料が40%の場合は、差額20%の傷病手当金が支給されます)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年5月23日 火曜日
平成12年5月23日(第26号)
保険料率の引き上げや離職理由によって失業給付に差をつけることなどを盛り込んだ改正雇用保険法が4月28日に可決・成立しました。失業者の急増による雇用保険財政の破たんを防ぎ、雇用のセーフティーネットを再編成するのが狙いです。
1.求職者給付の所定給付日数の再編 平成13年4月施行
今回の改正では、リストラ等会社都合の退職者と、自己都合退職者に対する受給について、所定給付日数に違いが出ることになりました。
① 定年、自己都合等による離職の場合 ③就職困難者の場合
被保険者で
あった期間 5年 未 満 5 年 以 上
10年 未 満 10年以上
20年未満 20年 以 上 被保険者で
あった期間 1 年 未 満 1 年 以 上
90日
(90日) 120日
(90日) 150日
(120日) 180日
(150日) 45歳未満 150日 300日
65歳未満 150日 360日
②倒産、リストラなどによる解雇の場合
1 年 未 満 1 年 以 上
5 年 未 満 5 年 以 上 10年 未 満 10年 以 上
20年 未 満 20年 以 上
30 歳 未 満 90日
(90日) 90日
(90日) 120日
(90日) 180日
(150日) 210日
(180日)
30 歳 以 上 45 歳 未 満 90日
(90日) 90日
(90日) 180日
(150日) 210日
(180日) 240日
(210日)
45 歳 以 上 60 歳 未 満 90日
(90日) 180日
(150日) 240日
(210日) 270日
(240日) 330日
(300日)
60 歳 以 上 65 歳 未 満 90日
(90日) 150日
(150日) 180日
(150日) 210日
(180日) 240日
(210日)
2.育児休業給付と介護休業給付の支給額の充実 平成13年1月施行
現行賃金月額の25%相当額の支給 → 賃金月額の40%相当額に引上げ
3.教育訓練給付金の上限の引上げ 平成13年1月施行
現行給付金の上限20万円 → 支給限度額を30万円に引上げ
4.パートタイマーの加入要件の緩和 平成13年4月施行
年収90万円以上が見込まれること、の要件が廃止されます。
5.雇用保険の保険料引上げ 平成13年4月施行
事業主負担分と被保険者(従業員)負担分がともに引上げられることになります。
一般の事業 1000分の11.5 → 1000分15.5 労使各々 1000分の2負担増
建設の事業 1000分の14.5 → 1000分18.5 労使各々 1000分の2負担増
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2000年5月 8日 月曜日
★第25号(5/8)休暇について★
休日と休暇の違いについてご存知ですか?
休日も休暇も「休みの日」という事実は同じですが、法的性格は異なります。
「休日」とは、労働契約上予めその日は労働の義務のない日とされている日であり、「休暇」とは、労働の義務のある日について一定事由の発生等の根拠に基づき一定の手続を経る事により、その義務が免除される事となる日である。
2.休暇の種類について
休暇については、法令又は就業規則等により定められている以下のものが一般的です。
◎年次有給休暇 (必ず有給)
◎育児休業 (有給・無給は労使の取り決め)
◎介護休業 (有給・無給は労使の取り決め)
◎生理休暇 (有給・無給は労使の取り決め)
◎産前産後休業 (有給・無給は労使の取り決め)
◎慶弔休暇 (有給・無給は労使の取り決め)
◎母性健康管理のための休暇 (有給・無給は労使の取り決め)
3.年次有給休暇とその他の休暇との関係について
本人の意思で各休暇(産後の休業は除く)を取らず、年次有給休暇を利用する事が可能です。
例えば、年次有給休暇の取得残日数が多くあるので無給の休暇を取得せず、年次有給休暇を取るような場合です。
但し、産後の休業については原則この様な事は出来ません。
なぜなら、産後の休業は、これを利用するか否かの判断が労働者本人に委ねられているのではなく、労働基準法により就業させる事が出来ないからです。
つまり、産後の休業の期間は労働の義務のある日ではないということです。
労働義務のない日に年次有給休暇を取得する事は出来ません。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年4月23日 日曜日
★第24号(4/23)介護雇用創出助成金の創設について★
改正介護労働者法に基づき、介護分野における良好な雇用機会の創出等を支援するため、平成12年4月1日から、介護雇用創設助成金がスタートします。
~介護人材確保助成金~
受給できる事業主:次のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業主であること
2.以下の介護サービスの提供を業として行う事業主(以下、「介護関連事業主」といいます。)であること(他の事業と兼業していてもかまわない。)
イ.訪問介護
ロ.訪問入浴介護
ハ.通所介護、短期入所生活介護
ニ.福祉用具貸与・販売
ホ.移送
ヘ.要介護者への食事の提供
ト.介護老人福祉施設で行われる介護サービス
チ.訪問介護
リ.短期入所療養介護
ヌ.介護老人保健施設、介護療養施設で行われる介護サービス
ル.訪問リハビリテーション
ヲ.通所リハビリテーション
ワ.居宅介護支援
カ.その他の福祉サービスまたは保健医療サービス
3.以下に伴い、新たに雇用保険の被保険者となるような労働者を雇入れること
イ.介護分野における新規創業
ロ.異業種から介護分野への進出
ハ.従来から実施していた介護サービスとは別のサービスの提供
ニ.支店の増設による営業エリアの拡大
受給できる額...対象労働者の雇入れの日から起算して1年間に、認定事業主が当該対象労働者に支払った賃金の額の1/2(当該雇入れに係る労働者が短時間労働被保険者である場合は、当該対象労働者に支払った賃金の額の1/3)です。
介護人材確保助成金以外にも、介護能力開発給付金・介護雇用管理助成金・介護雇用環境整備奨励金などがあります。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年4月 8日 土曜日
平成12年4月8日(第23号)
人材開発,労務管理等についてのモデル的な取り組みをバックアップ
新たな雇用の創出に向けて平成12年度中に人材開発や労務管理の取り組み
(モデル計画)を実施する中小企業を応援する制度です。
中小企業地域雇用創出特別奨励金
発動要件 支給を受ける前提として、中小企業労働力確保法の「改善計画(創業、異業種進出に係るものに限る」を提出し,都道府県知事の認定を受けている必要があります。
モデル計画の作成 1.計画実施期間の設定(平成12年12月末まで)
2.雇入れ労働者数の設定
雇用保険の一般被保険者である労働者が4人以上が条件となります。
3.人材開発、雇用管理への取り組みについての計画策定
※ 人材開発の取り組み方針と今後の人材開発計画の野概要、人材開発機材の設置・整備に関する計画
※雇用管理の取組方針と、今後の雇用管理改善計画、及び外部コンサルタントによる指導に関する計画
モデル計画の実施 認定を受けたモデル計画に基づく取り組みを実施
人材開発機材の導入及び専門家のアドバイスによる雇用管理の取り組みの完了終期は平成12年12月31日です。
支給対象
となる
関係費用 支給対象事業の終了後、完了届と申請書を提出。
※人材開発用の機材を確保する為の経費
※労務管理に関する、外部コンサルタントによる専門的な指導を受ける為
の経費
支 給 額 雇入労働者数 4~9人 10~19人 20人以上
奨励金の額 750万円 1,150万円 1,500万円
※ 雇入れ労働者とは雇用保険の一般被保険者に該当する労働者で3人以下の場合は奨励金は支給されません。
※ 関係費用の合計額がその奨励金の額に満たない場合は、関係費用の合計額が支給額となります。
※ 関係費用の合計額が300万円を下回る場合は該当しませんのでご注意ください。
☆詳細は当事務所までお尋ねください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2000年3月23日 木曜日
★第22号(3/23)産前産後に関する法律(保存版)★
◆危険有害業務の就業制限(法第64条)
使用者は、妊産婦を妊娠、出産、保育等に有害な業務に就かせてはなりません。
◆産前産後休業(法第65条)
産前休業期間は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)産後休業期間は8週間が認められています。
ただし、本人の請求により、産後6週間経過後に医師が認めた業務については、就業させることができます。
※産後は最低1ヶ月は床上げせずに静養することが必要です。理解しましょう。
◆軽易業務への転換請求(法第65条)
妊産婦が請求すれば、他の軽易な業務に転換できます。
◆時間外・休日労働及び深夜業の制限(法第66条)
使用者は、妊産婦が請求した場合、時間外・休日労働及び深夜業をさせてはなりません。
◆妊娠中の解雇制限(法第19条)
出産休暇中、その後の30日の解雇は禁止されています。
2.男女雇用機会均等法
◆妊娠、出産等を理由とする解雇制限(法第11条)
女子労働者の婚姻、妊娠、出産、産前産後休業をとったことを理由とする解雇は禁止されています。
◆保健指導を受けるための時間の配慮(法第26条)
事業主は、女子労働者が、保健指導や健康検査を受けるための時間を確保できるよう配慮するよう努めることが求められます。
◆指導事項を守るための措置(法第27条)
事業主は、女子労働者が、健康診査などで医師から与えられた注意事項を守れるよう必要な措置を講じるよう努めることが求められます。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年3月 8日 水曜日
★第21号(3/8)妊娠中の労働環境における留意点★
使用者は、休み時間には心身ともゆったりした環境を与え、体調が不良の場合は仕事を中断させるなど、妊娠について充分な理解を示しましょう。
1.妊娠・分娩への影響を有する就労条件とは
◆1日の労働時間が8時間以上
低体重児出産、妊娠中毒症
◆深夜勤務
流産、早産、低体重児出産
◆高温環境
強いつわり、妊娠中毒症、低体重児出産、子宮復古不全
◆低温環境
妊娠中毒症、流産、早産、低体重児出産
◆反復作業
早産、低体重児出産
◆階段昇降・重量物運搬・振動
切迫早産、切迫流産
◆産前休暇日数が少ない
妊娠中毒症、流産、早産、低体重児出産
◆途中に階段の多い通勤
流産、早産、低体重児出産
2.避けるべき動作とは?
◆過激な運動
◆下腹部に力が入る動作(重いものを持ち上げる、背負う等)
◆振動を与える動作
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年2月23日 水曜日
★第20号(2/23)高額療養費と医療費控除★
被保険者が、同じ月内に、同じ医療機関(入・通院別、診療科ごと)で治療を受け、保険適用自己負担額(薬剤一部負担金を含む)が、一定額を超えた場合は高額医療費の支給が受けられます。
被保険者本人の保険適用自己負担額が63,600円(住民税非課税世帯35,400円)を超えた分が、同じ世帯で、同じ月内に、30,000円(住民税非課税世帯21,000円)以上の自己負担が2回以上あった場合は、その額を合算し、63,600円(住民税非課税世帯35,400円)を超えた分が支給されます。同じ世帯で、一年間に4回以上の高額療養費の支給を受けた場合は、4回目以降からの支給額は月37,200円(住民税非課税世帯24,600円)を超えた分の額となります。
2. 医療費控除とは
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
<医療費控除の対象となる医療費の要件>
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までに支払ったものであること。
くわしくは、高額療養費は、最寄の社会保険事務所又は市町村の健康保険の窓口でご相談を。
医療費控除は、最寄の税務署で確定申告の手続きが必要です。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年2月 8日 火曜日
平成12年2月8日(第19号)
1.会社が支出する休業手当、賃金、職業訓練費などの経費を補填するために支給されたもの
↓
その給付の原因となった休業、就業、職業訓練などの事実があった日の属する事業年度に収益計上します。年度末までに支給される金額が確定しない場合には見積計上する必要が有ります。
具体例
中小企業雇用創出人材確保助成金 雇用調整助成金
中小企業雇用創出雇用管理助成金 認定訓練派遣等給付金
中小企業雇用創出等能力開発給付金 長期教育訓練休暇制度導入奨励金
能力開発給付金 地域高度技術人材確保助成金
自己啓発助成給付金 障害者雇用継続助成金
中小企業高度人材確保助成金 中高年労働移動支援特別助成金
パートタイム助成金 地域雇用奨励金
特定求職者雇用開発助成金 育児・介護費用助成金
2.会社が、定年の延長、高齢者や障害者の雇用、労働環境の改善など、一定の基準を満たせば支給されるもの ↓
その支給決定のあった日の属する事業年度に収益計上します。
具体例
受給資格者創業特別助成金 受講環境整備奨励金
中小企業雇用環境整備奨励金 高年齢者雇用環境整備奨励金
継続雇用制度奨励金 地域雇用特別奨励金
多数継続雇用助成金 地域雇用環境整備助成金
特例事業場労働時関短縮奨励金
助成金・給付金によっては、両方のタイプを含む場合がありますので注意して下さい。
詳細は、管轄の税務署でお尋ね下さい。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2000年1月23日 日曜日
★第18号(1/23)介護保険制度について★
①介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村(特別区)です。
②対象者は40歳以上のすべての国民で、各住所地の保険者への個人単位での強制加入となります。
@65歳以上の国民は第1号被保険者と呼ばれ、住民票のある市町村で自動的に加入となります。
@40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者と呼ばれ、それぞれの医療保険(健保、国保、共済等)の保険者を通じての加入となります。
2.介護保険被保険者証
①要介護認定の申請を行う場合には、申請書に被保険者証を添て市町村に申請することになるので、個人単位で被保険者証が交付されます。
@第1号被保険者は、原則特別な届出は不要で全員に発行されます。
@第2号被保険者は、必要になったとき(要介護・要支援認定を受けた者・交付申請した者)に住所地の市町村へ申請することにより発行されます。
3.介護保険料
①第1号被保険者の場合
@保険料は、保険者である市町村ごとに異なります。
@徴収方法は、年額18万円以上の老齢・退職年金を受けている者は、年金から天引き、それ以外の者は、市町村へ個別に支払います。
②第2号被保険者の場合
@健康保険に加入している者は、各自の報酬月額に介護保険料率を乗じた額が保険料(半額は事業主負担)となり、給与から天引きとなります。
※被扶養者は、直接保険料を負担することはありません。
@国民健康保険に加入している者は、保険料は所得や資産額によって異なり、市町村へ世帯主がまとめて支払います。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年1月 8日 土曜日
平成12年1月8日(第17号)
中小企業に対する基本的な施策や方針を定めている中小企業基本法を改正する法律が、12月3日公布され即日施行されています。
●中小企業の範囲が拡大された
中小企業の定義、つまりどの程度の規模の会社を中小企業というかについては、73年以来改正されておらず、物価上昇等を勘案し、改正されました。
範囲が拡大されたことによって、これまでボーダーラインをわずかに超えていたために、中小企業に対する政府系金融機関の低利融資を受けられなかったり、優遇税制の適用もされなかった企業にとっては朗報です。
なお、この中小企業の範囲の拡大に併せて、中小企業に対する施策を個別に規定している他の法律も改正されています。
●創業や経営革新を促進・支援
従来の中小企業基本法は「大企業との格差是正」といった、いわば中小企業から脱却することを目的としていました。これに対し、改正法では、中小企業の多様で活力ある成長発展こそが、日本経済の強化につながるとし、積極的に評価しています。この改正法の特徴は、ベンチャー企業や創業者、さらには自助努力する者に対する支援を明確にしていることです。
「新しい中小企業の定義」( )内は改正前の数値
●製造業・建設業・その他の業種
資本金 3億円(1億円)以下 従業員数 300人以下
●卸売業
資本金 1億円(3,000万円)以下 従業員数 100人以下
●小売業
資本金 5,000万円(1,000万円)以下 従業員数 50人以下
●サービス業
資本金 5,000万円(1,000万円)以下 従業員数 100人(50人)以下
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
1999年12月23日 木曜日
★第16号(12/23)適切な帳簿書類の保存を心掛けましょう!!★
帳簿書類の保存期間は、次のようになっています。
◎労働者名簿、賃金台帳、その他雇入、解雇、災害補償、賃金等の労働関係に関する
重要書類 ⇒ 3年
◎健康診断個人票 ⇒ 5年
◎現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、経費帳等 ⇒ 7年
◎損益計算書、貸借対照表、棚卸表等 ⇒ 7年
◎領収書、小切手帳控、預金通帳、借用書等 ⇒ 7年
◎有価証券受渡計算書、社債申込書等 ⇒ 7年
◎契約書、請求書、見積書等 ⇒ 中小5年、大7年
◎納品書、送り状、貨物受領証、出入庫報告書、検収書等 ⇒ 5年
※「中小法人等」とは、普通法人等のうち事業年度終了時の資本金が1億円以下であるもの等をいいます。
2.ファイリングの基本
ファイリングシステムとは、「書類を有効に活用するために、一定の約束のもとに分類・整理して、保管・保存し、廃棄にいたるまでの一連の管理制度」のことです。
書類には、保管→保存→廃棄というライフサイクルがあります。書類の使用頻度に応じて、的確に保管から保存・廃棄へと流れる仕組みを作り、管理します。
3.整理よければ、すべてよし
書類探しをラクにするためにまず必要なのは、書類サイズの統一や書類戻しの実行です。
書類のサイズがまちまちであれば、同じ場所にファイルしたくても、うまくまとめきれません。
また、たいていの人は書類の検索には全力を尽くしますが、用が済むと適当なところに戻してしまいがちです。
これでは再び同じ書類を検索する際、余計な時間と手間がかかってしまいますし、他のスタッフにも迷惑がかかります。
「書類探しを1日に10分減らすだけでなんと1億円の経費が浮く!?」と言うのは、極端な例えですが、これはオフィスに千人の人間が働いて、それぞれが10分間書類探しをしたと仮定しての試算結果です。書類の整理整頓を、日頃から心掛けたいものです。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
1999年12月 8日 水曜日
平成11年12月 8日(第15号)
1.退職願と退職届の違いについて
一般的に退職願と退職届との間にそれほど厳密な区別を設けないでそれらの言葉を
使っていますが、厳密に言えば一応次のような区別がなされています。
◎ 退職願は、従業員側から企業に対してなされる労働契約の合意解約の申し入れです。
ですから従業員の「やめたい」という意思表示に対して、使用者が「わかった」と
意思表示することで初めて退職できるのです。
◎ 退職届は、従業員側からなされる労働契約解除の一方的な意思表示であるとされています。
つまり、従業員が退職届に記載した退職日と届出日の間が原則14日間以上あれば、法的には使用者はこれを拒めないのです。(根拠:民法627条)
2.退職願(届)の撤回について
使用者側の同意を得ない、つまり従業員の一方的な撤回(退職するのはや~めた)
が認められるかどうか?(退職の意思表示において無効・取消原因がある場合はこ
の限りではない。)
◎ 退職願の場合は、合意解約の申し入れとしての退職の意思表示ですから使用者の承諾があるまでの間は撤回が可能であるが、使用者の承諾の意思表示があった以降は撤回が出来ない。
◎ 退職届の場合は、使用者の同意を要件としない単独の意思表示(退職する旨の一方的な意思表示)であるので、これが使用者に到達した以後においては撤回することができないのが原則です。
3.真意によらない退職願(心理留保)について
退職の申出が、本人の真意によらないものであり、そのことを使用者が知っている
場合や知りうる状況にあった場合は、その意思表示は無効です。
しかし、懲戒解雇を免れるためには自発的な退職しかないと説得されたような場合
では、本心は退職したくないという事であっても、懲戒解雇か退職かを選択の結果
退職の意思表示をしたのであれば、心理留保による無効とはなりません。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
1999年11月23日 火曜日
平成11年11月23日(第14号)
1.所得税今年の改正点(年末調整にかかわる部分)
○平成11年分以降の所得税について、所得税額の一定割合が減税(定率減税)され
ることになりました。
定率減税額 控除率20%(上限25万円)
○扶養控除額が次の扶養親族の区分に応じて引き下げられました。
扶養親族の区分 改正前 改正後
年少扶養親族
/ S59.1.2以降生 38万円 48万円
特定扶養親族
/ S52.1.2~
S59.1.1生 58万円 63万円
2.年末調整の準備資料
○本人に記入させて、回収するもの
①扶養控除等(異動)申告書→平成12年分
②配偶者特別控除申告書
③保険料控除申告書 →平成11年分 →税務署にあります。
○本人から回収するもの
④住宅取得等特別控除申告書→対象者には、直接税務署から送付されます。
⑤生命保険料控除証明書
⑥損害保険料控除証明書 →対象者には、直接保険会社から送付されます。
⑦前勤務先の源泉徴収票 →平成11年に転職して来た方。
○本人に確認すること
⑧個人で負担している社会保険(国民年金・国民健康保険等)の年間納付額
※年末調整事務をスムーズに進めるためには、書類・データは早めに回収・確認して
おかれることをお勧めします。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
1999年11月 8日 月曜日
平成11年11月8日(第13号)
平成11年10月31日から変わりました。
1.被保険者区分の変更が生じた場合の届出
従来は、短時間労働被保険者以外の被保険者が短時間労働被保険者となった場合、又は短時間労働被保険者が短時間労働被保険者以外の被保険者となった場合には、その被保険者を雇用する事業主の事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に区分変更届-1及び区分変更届-2を提出することが必要でしたが、平成11年10月31日以降は、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)への区分変更届の提出のみになります。
平成11年10月31日以降に、雇用する被保険者の区分変更に係る手続を行なう際には、「雇用保険被保険者区分変更届」を使用してください。
2.事業所間で転勤した場合の届出
従来は、転勤前事業所より転勤前事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に転出届を提出したうえで、転勤後事業所より転勤後事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に転入届を提出することが必要でしたが、平成11年10月31日以降は、転勤後事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)への転勤届の提出のみになります。
平成11年10月31日以降に、雇用する被保険者の転勤に係る手続を行なう際には、「雇用保険被保険者転勤届」を使用してください。
3.届出様式の変更等
転勤届、区分変更届の提出の際には、雇用保険被保険者証及び「雇用保険被保険者資格喪失届・転出届・氏名変更届・区分変更届-1」(雇用保険被保険者資格取得届又は変更届を提出された際にお渡しする書類)を必ず一緒に提出してください。
平成11年10月31日以降、「雇用保険被保険者転出届」「雇用保険被保険者区分変更届-1及び2」については新様式を使用してください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
1999年10月23日 土曜日
★第12号(10/23)精神障害・過労自殺...労災認定に新基準★
7月に同省の専門検討会がまとめた基準に基づき精神障害の対象を世界保健機関(WHO)の提唱する新たな分類を使い、労災対象をすべての精神障害に拡大したのが特徴です。
過労自殺については、業務が原因で正常な認識や抑制力が阻害された状態での自殺を対象にしました。
これまで精神障害などの認定作業はすべて労働省本省が進めてきたが、指針にはストレスの度合いを測る「ストレス評価表」や効率的に判断ができるフローチャートを付け、監督署独自に調査、判定ができるようにしました。
1.業務上と認定する要件
・対象疾病に該当する精神障害を発病している
・発病前の六カ月間に仕事により強いストレスがあった
・業務以外のストレスや既往症、アルコールヘの依存などがなかったこと
その上で、ストレス後の極端な長時間労働などを考慮、総合的に判断するよう求めています。
2.企業の健康配慮義務
精神障害・過労自殺の認定基準の通達によって、認定の判断作業は末端の労働基準監督署にゆだねられ、認定までの時間短縮とともに認定件数も増加、遺族などへの救済が図られるものと期待されます。
最近の過労自殺では遺族が労災請求をすると同時に損害賠償を求め企業を相手取って提訴する事例が増えています。
労働安全衛生法では、企業は労働者の健康に配慮する義務を負います。過労自殺の認定は、企業の配慮が欠けていたことを国が認めたことにもなり、企業が自らの配慮を立証できない限り損害賠償訴訟で企業側に不利に働きます。
このため、メンタルヘルス面で、しっかりとした対応をしない限り多大なリスクを負う、ということを企業は認識する必要があります。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
1999年10月 8日 金曜日
★第11号(10/8)平成11年10月からの労働基準法改正!!★
平成11年9月末日まで、労働基準法では、時間外労働等の割増計算をする基準賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われる賃金、1ヵ月を超えるごとに支払われる賃金を除き、それ以外は全て加算することとなっていました。
ところが、平成11年10月1日からは法改正により「住宅手当」を除外できるようになりました。
ただし、住宅手当であれば、全て除外されるわけではなく、「住宅に要する費用に応じて算定される手当」(通達)により、下記の一定の条件が必要となります。
2.除外できる住宅手当の詳細とは
①費用に定率を乗じた額の例として、賃借住宅居住者には家賃の一定割合。
持ち家居住者には、ローン月額の一定割合を支給する場合。
②費用を段階的に区分して費用が増えるに従って割合を多くする。
たとえば、家賃月額5~10万円の者には2万円。家賃月額10万円を超える者には3
万円を支給する場合。
3.除外できない住宅手当とは
①賃貸住宅居住者には、2万円。持ち家居住者には1万円を支給する、というように住宅の形態ごとに一律定額としている場合。
②扶養家族がある者には2万円。扶養家族がない者には、1万円を支給する、というように直接住宅手当に関係ない扶養家族の有無で、その額が決定されている場合。
しかし、10月1日より基準賃金から通達に該当する住宅手当を「除外しなくてはならない」わけではなく、自動的に住宅手当が「除外されるわけではない」わけでもありません。
従来住宅手当を実施していた企業が基準賃金から住宅手当を除外しようとする場合には、就業規則、賃金規程の変更が必要です。
また、残業の単価が低くなるということは、「就業規則の不利益変更」の問題も考えられますので、合理性のあるようご留意ください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
1999年9月23日 木曜日
平成11年9月23日(第10号)
1.被保険者の種類と保険料
第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳~64歳の医療保険加入者
(被扶養者含む)
給付の
対象者 ○寝たきり・痴呆などで入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について常に介護が必要な人
○家事や身支度などの日常生活に支援が必要な人 初老期痴呆、脳血管障害など、老化にともなう病気によって介護等が必要となった人
保険料 所得段階に応じ市町村ごとに設定
(平成12年度全国平均
1人あたり月額2,500円程度) 加入している医療保険の算定方法に基づいて設定
保険料の
支払方法 ○年金額が年間18万円以上の場合は、年金から天引き
○上記以外の場合は、市町村に個別に支払い 医療保険料と一括して納付
2.サービス内容・・・市町村に要介護認定を申請し、要介護・要支援状態にあるか否か
を判定してもらいます。(平成11年10月頃から申請受付)
在宅サービス 施設サービス
要介護者 ○訪問介護(ホームヘルプ)
○訪問入浴
○訪問看護
○訪問リハビリテーション
○日帰りリハビリテーション
○居宅療養管理指導
○日帰り介護(デイサービス)
○短期入所生活介護(ショートステイ)
○短期入所療養介護(ショートステイ)
○痴呆対応型共同生活介護
(痴呆性老人のグループホーム)
○有料老人ホーム等における介護
○福祉用具の貸与・購入費の支給
○住宅改修費の支給
(手すり、段差の解消など) ○介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
○介護老人保健施設
(老人保健施設)
○介護療養型医療施設
・療養型病床群
・老人性痴呆疾患療養病棟
・介護力強化病院(施行後3年間)
要支援者 ○同上(痴呆性老人のグループホーム除く) ○施設入所はできない
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
1999年9月 8日 水曜日
平成11年9月8日(第9号)
1. 目的
雇用失業情勢が更に悪化した場合に備え、中高年の非自発的失業者に必要な雇用機会を提供できるような仕組みを作る為この奨励金が創設されました。
2. 緊急雇用創出特別奨励金の概要
緊急雇用創出特別奨励金
発動要件 ① 全国において、連続する3ヵ月の各月における完全失業率が5.2%を超える場合
② 地域ブロックにおいて、連続する2・四半期の完全失業率の平均が5.4%を超える場合
③ 沖縄県において、連続する2・四半期の完全失業率の平均が8.1%を超える場合
対象者 雇入れ計画に基づき、45歳以上60歳未満の非自発的失業者を公共職業安定所の紹介により常用労働者として雇い入れる事業主
支給額 雇入れ労働者1名に対し30万円
支給時期 雇入れ1ヶ月後に支給
支給要件 ① 雇用保険適用事業主
② 雇入れ計画を前倒しして雇用
③ 45歳以上60歳未満の非自発的失業者を公共職業安定所の紹介により常用労働者として雇用
④ 雇入れの1ヶ月後と雇入れ前とを比較し常用労働者が増加
⑤ 雇入れ計画提出日の6ヵ月前から支給までの間に事業主都合で解雇していない
実施期間 労働力調査結果の公表日の翌日を初日とし、当該月から起算して3ヵ月経過後の月に係る労働力調査結果の公表日を末日とする
(近畿ブロックは、平成11年7月31日より3ヵ月)
併給 ①特定求職者雇用開発助成金に上乗せして支給
②新規・成長分野雇用創出特別奨励金の支給を受ける場合は、支給しない
3.申請窓口
各都道府県の高齢者雇用開発協会が、支給申請受付等の事務をおこないます。
4.近畿ブロックの完全失業率
近畿ブロックの完全失業率は、平成11年1月~3月(5.4%)、4月~6月(6.1%)であり、この連続する2・四半期の完全失業率の平均は5.75%となっております。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
1999年8月23日 月曜日
★第8号(8/23)助成金・納付金を上手に活用していただくために★
助成金や給付金の多くは、雇用保険から拠出されています。そのため、大半のものは雇用保険に加入していないと、受給することはできません。
2.書類の整備はできていますか?
労働基準法・労災保険法・雇用保険法などに基づき、事務処理が行われていることが前提です。
普段から、出勤簿・賃金台帳・就業規則などの整備が必要となります。
3.あらかじめ手続きが必要なものもあります。
労働者の雇入れや施設の設置・整備の前にあらかじめ「計画」「受給資格」の認定や届出が必要なものがあります。これらの手続きを忘れると、受給できなくなりますので、十分にご注意下さい。
4.専門家を活用しましょう。
労働保険・社会保険の専門家として、社会保険労務士がいます。雇用保険を初めとする労働保険・社会保険の手続きのプロであり、助成金・給付金や人事労務の制度、就業規則作成についても知識をもっています。
5.先ずは、お気軽にご相談を!
当所では、助成金診断アンケートを実施し、貴社にあった助成金をご提案させて頂くサービスを実施しています。まずは、お気軽にご相談下さい。
助成金は、丸々純利益です。例えば、御社の粗利益率が、20%であるとしたら、100万円の助成金は、500万円の売上と同じ価値を持ちます。
手続きをすれば、受給できた助成金はあったかもしれません。
常に情報のアンテナは張っておきたいものです。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
1999年8月 8日 日曜日
★第7号(8/8)就業規則の制定及び正しい運用の必要性★
就業規則とは、事業場における労働条件や服務規律等が統一的、具体的に定めてある規則集のことであり、その事業場にとって最も重要で基本的な事柄が定めてあるものです。
単に事業場内で通用する内規ではなく、労働基準法その他関係法令に規制され、何かトラブルがあれば司法及び行政によって正しく作成及び運用がなされているか判断される、ある種公的な規則なのです。
2.なぜ就業規則の制定及び正しい運用が必要なのか?
労使間でトラブルとなっている主なものは、懲戒、退職、賃金・退職金の不払いに関するものです。そしてそれらのトラブルについて使用者側が負ける場合が多々見受けられるのです。それはどうしてか?それは
①就業規則自体がない
②就業規則に不備がある
③就業規則があっても正しく運用されていない
の3点が考えられます。
例えば「懲戒」においては、使用者が企業秩序違反行為を理由として労働者に対し制裁罰である懲戒を課す権利(懲戒権)の行使は、就業規則に定められた規定(内容的に合理性が有ると認められるもの)に基づいてのみ有効であるとされています。
さらに、同じ規律に違反した場合は同程度の処分が行われること、就業規則所定の懲戒手続に違反する処分は許されないこと、就業規則の懲戒規定は制定前の行為には適用されないこと等のルールもあります。
つまり、「懲戒」は懲戒規定が就業規則に正しく制定されており、そして正しく公正な手続が行われて初めて有効となるのです。
3.就業規則制定の薦め
使用者が行った行為が否定され、場合によっては損害賠償を行わなければならないという事態を回避するため、就業規則の制定及び正しい運用というリスクマネジメントは大変重要です。
この機会に、就業規則の制定をお薦めします。
そして、正しい運用については、ぜひ労働法の専門家、社会保険労務士にご相談ください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
1999年7月23日 金曜日
平成11年7月23日(第6号)
健康保険・ 厚生年金保険では、保険料や保険給付、将来受給する年金額の計算の基礎になるものとして、実際に事業主から受けている報酬月額(給与)をいくつかの等級に区分しています。これを、「標準報酬」といい、毎年1回は必ず金額の見直しをすることになっています。それが「算定基礎届」です。
1.算定の対象者
8月1日現在に在職する被保険者。ただし、下記のものは除く。
①7月1日~8月1日の間に新たに被保険者資格を取得した者
②8月~10月の間に、その直前3ヶ月の平均報酬額に2等級以上の差が出たため、
月額変更届を提出した者
2.計算方法
5月・6月・7月の3ヶ月分の報酬月額の平均値を出す。ただし、実際にその月に支
払った給与が対象となる。
例1)20日締め、25日支払いの場合 →5/25、6/25、7/25支払分
=5・6・7月分給与が算定対象となる。
例2)月末締め、翌月5日支払いの場合 →5/5、6/5、7/5支払分
=4・5・6月分給与が算定対象となる。
3.提出期限
平成11年8月2日(月)~10日(火)
(管轄の社会保険事務所によって別の期日を指定されることもあります。)
4.適用時期
平成11年10月1日~平成12年9月30日まで
現物給与がある場合・支払基礎日数20日未満の日がある場合、昇給差額が出た場合など、ケースによって算定方法が複雑になる事があります。間違いのない算定のために当事務所へご依頼ください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
1999年7月 8日 木曜日
平成11年7月8日(第5号)
非課税になる通勤手当とは、通勤にかかる運賃、時間、距離などの事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路および方法による運賃、または料金の額のことです。
●勤務が1ヵ月に満たない場合
中途採用者の入社当月分の通勤手当、またアルバイトなどの勤務が1ヵ月に満たない場合などでも、限度額については1ヵ月分が適用されます。
●交通用具の使用距離が片道15km以上の場合
ここでいう交通用具とは、自転車やマイカーなどのことです。このケースでは、その社員が利用できる交通機関を使った場合の運賃等の額で計算します。
● 交通用具の使用距離が片道2km以上15km未満の場合
非課税額は距離に応じて4,100円または6,500円となっています。交通機関を利用した場合の合理的な運賃等の額という扱いではありません。
● 交通用具の使用距離が片道2km未満の場合
全額が課税対象となります。なお、非課税の対象になる通勤手当とは、通常の給与に加算して支給するものに限られます。
●通勤手当の非課税限度額
通勤の方法等 非課税額(1ヵ月)
①交通機関または有料道路を利用する場合 10万円を限度に合理的な運賃等の額
②交通用具(自転車、バイク、車など)を利用する場合
※ 距離は片道。
※ なお10km以上の場合で合理的な運賃等の額が右の限度額を超える場合は、10万円を限度に、その超える額 35km以上 20,900円
25km以上35km未満 16,100円
15km以上25km未満 11,300円
10km以上15km未満 6,500円
2km以上10km未満 4,100円
2km未満 全 額 課 税
③交通機関の通勤定期券を現物支給する場合 10万円を限度に合理的な運賃等の額
④交通機関と交通用具を併用する場合 合理的な運賃の額と②の金額との合計額
(10万円が限度)
● 経費節減の工夫
不況で業績が低迷するなか、経費を節減する企業も多いことでしょう。通勤定期に関してはまず、通勤定期代の計算を1ヵ月単位から6ヵ月単位に変更するなどがあげられます。
また、マイカー通勤に対して公共交通機関を利用した場合の定期代相当額を支給している企業では、距離に応じてガソリン代を支給する方が手当額を圧縮できるケースも多いようです。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
1999年6月23日 水曜日
平成11年6月23日(第4号)
特例事業場(現在週46時間労働制の事業場)の事業主が、平成13年3月31日までに、省力化投資の措置、雇入措置、コンサルタント活用措置を行い、就業規則等を変更し、週所定労働時間を1時間以上短縮して44時間以下とした場合に、一定の助成を行う制度です。
1. 奨励金の対象となる事業主(①~⑤の要件を全て満たしていること)
①労働者災害補償保険の適用事業主であること。
②特例事業場(下表に該当する業種及び規模の事業場)の事業主であること。
業 種 常時使用する労働者の数
商 業 1~9人
映画・演劇業 1~9人
保健衛生業 1~9人
接客娯楽業 1~9人
③次に掲げる労働時間等に関する事項を就業規則等において定めている事業主であること。
イ 始業及び終業の時刻
ロ 休憩時間
ハ 休日
ニ 休暇
ホ 2交代制就業の場合においては就業時転換
④平成11年3月31日までに就業規則等を変更し、週所定労働時間を1時間以上短縮して44時
間以下とした事業主であること。
⑤週所定労働時間の短縮のために、平成11年4月1日以後、次のいずれかの措置を完了した事業
主であること。
措置の内容 支給額
A:150万円以上の省力化投資〈リース可、但し3年間の所要額〉 50万円
B:新たに1人以上の常用労働者の雇入れ(6カ月間雇用維持し、常用者が増加) 50万円
C:労働時間制度改善について社労士、診断士の助言・技術的援助を受けること かかった費用の額(上限10万円)
2.支給額
上記の表に記載されている額
※社会保険労務士に依頼した場合は,上記のA+CまたはB+Cというセットで助成の申請が可能です。
つまり、最大60万円が受給可能!!
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
1999年6月 8日 火曜日
平成11年6月8日(第3号)
「生涯能力給付金」とは、事業主が従業員の職業能力を高めるための教育訓練の実施、事業所外の研修・セミナーへの派遣等に要する経費の一部を助成する制度です。
2. 給付金の対象となる事業主
① 雇用保険の適用事業主であること。
② 事業内職業能力開発計画届を提出していること。
③ 計画に基づき、従業員(雇用保険の被保険者)に対し教育訓練を受けさせていること。
2.生涯能力開発給付金には次の2種類があります。
能力開発給付金 業務命令により労働者に対して教育訓練を実施する場合に支給されます。
① 事業所内で実施(社内集合訓練) ②外部の教育訓練へ派遣(事業外派遣訓練)
自己啓発助成給付金 労働者の自主的な申出により、事業主が教育訓練受講のための休暇又は経
済的援助を与える場合に支給されます。
①有給教育訓練休暇の付与 ②事業外の教育訓練受講の援助
3.対象となる訓練
例えば、専門的知識、技能の習得のための教育訓練、技術革新に対応するための教育訓練など実際
の訓練時間が10時間以上あり、対象者の年齢が一定の場合対象となります。
4.給付内容の概要(限度額あり) 例えば、中小企業の場合
① 企業内集合訓練の実施講師謝金、教材費 → 運営費の1/3(45歳以上は2/3)
② 企業外の教育研修施設への入学金、受講料 → 受講料等の1/3(45歳以上は3/4)
③ 訓練受講中の賃金 → 25歳~44歳4,000円(25歳未満3,000円、45歳以上は7,000円)
5.導入奨励金 一律300,000円、1事業所1回限り
新規に、生涯能力開発体系の導入・定着を図った中小事業主で、一定の要件を満たした場合
平成11年度の計画届の提出期限は、6月末日となっております。「企業は人なり」と言われるように、人材から人財へ。企業の体力を強化するためにも、是非ご検討のうえ活用して頂きたい制度です。制度の詳細については、当事務所へご相談ください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
1999年5月23日 日曜日
★第2号(5/23)パートタイム労働指針が変わりました★
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)に基づく「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善のための措置に関する指針」(パートタイム労働指針)が改正されました。(4月1日施行)
ポイントは、以下の通りです。
1.労働条件は、文書で明示してください。
(モデル様式がありますので、必要な場合は別途お知らせ下さい)
2.就業規則を作成・変更するときは、パートタイム労働者の過半数を代表するものの意見を聴いてください。
3.パートタイム労働者にも、年次有給休暇を与えなければなりません。
4.パートタイム労働者にも、解雇するときは予告をしなければなりません。
5.パートタイム労働者が退職時に請求したときは証明書を交付しなければなりません。
6.パートタイム労働者にも、健康診断を実施しなければなりません。
7.妊娠中・出産後のパートタイム労働者には、特別な措置が必要です。
産前産後の休業・通院時間の確保・医師等の指導事項を守れる用意するための勤務時間の短縮、勤務の軽減等をはじめ、必要な措置を講じなければなりません。
8.パートタイム労働者にも、育児休業・介護休業の制度等を講じなければなりません。
9.パートタイム労働者には、通常の労働者への応募に関する情報をあらかじめ周知してください。
通常の労働者募集の際は、その旨や内容についてパートタイマーに周知させ、現に雇用するパートタイマーに優先的に応募の機会を与えるよう努めなければなりません。
10.短時間雇用管理者を選任し、その氏名を周知してください。
常時10人以上のパートタイマー労働者を雇用する事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任するよう努めなければなりません。
これらにより、パートタイム労働者の「適正な労働条件の確保」・「雇用管理の改善」に関して事業主が講ずべき措置が、より一層明確になったといえるでしょう。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
1999年5月 8日 土曜日
★第1号(5/8)改正「中小企業退職金制度」がスタート★
1.退職金額
退職金額予定運用利率が年4.5%から年3%に引き下げられます。
もし、今までの退職金額を維持するのであれば、掛金月額を増額する必要があります。
2.特定退職金共済制度との通算
転職などをしたとき新たな就職先が中退共に加入していれば退職金を通算することが可能です。今後はさらに商工会議所や商工会などが行う特定退職金共済制度との間の移動の場合も通算受給が可能となりました。
3.分割受給制度の改善
これまでは60歳以上で退職する場合、一定の要件のもと、5年若しくは10年の分割で受け取ることができました。
今後はそれに加えて、一部(20万円以上)を一時金として受給し、残りを分割受給できるようになります。
4.申込金の廃止
これまで加入申込手続には1ヵ月分の掛金を申込金として添えることになっていました。今後はこの申込金が廃止となり、申込手続が簡素化されます。
<制度活用のメリット>
昨年度の税制改正で、退職給与引当金の繰入限度額が経過措置を設けて引き下げられました。金中退共の掛金は損金、必要経費となるので前もって費用化できます。
また、掛金については国の助成制度もあります。退職金負担が高まるなか、要検討の制度といえるでしょう。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL